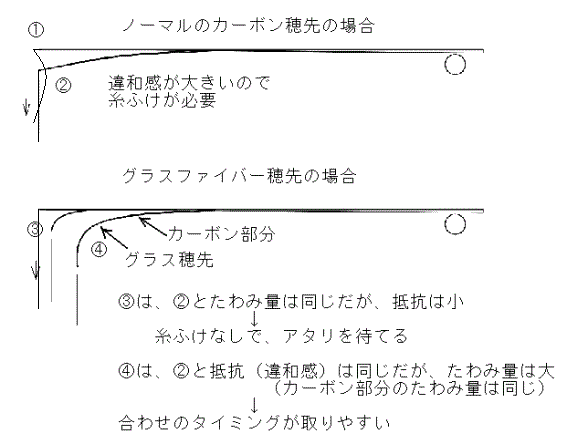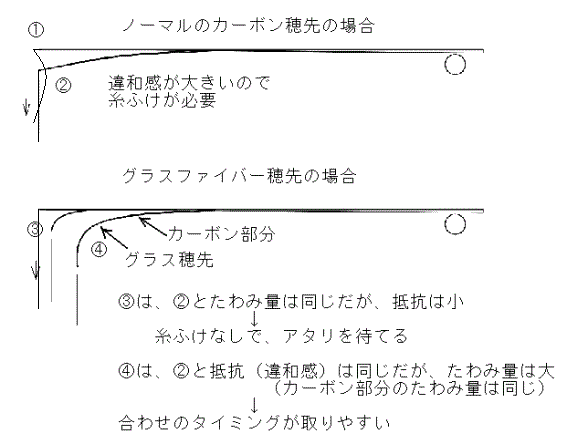トップへ
極軟穂先
チヌは、警戒心が強い魚と言われています。実際、穂先にアタリがあっても、抵抗があると、エサをすぐに吐き出してしまいます。くやしいのが、一気に引き込む大きいアタリでの素バリです。こういのは時々あるのですが、あっと思ったときには、「時すでに遅し」で、吐き出した後というのがほとんどでした。チヌの反射神経の方が人間の反射神経を大きく上回っているのだと思います。そこで、思いついたのが、極軟穂先です。穂先が柔らかければ、チヌがエサをくわえてから違和感を感じて吐き出すまでの間の時間をかせげる(距離をかせげる)ので、アタリを感じてから吐き出すまでの間に合わせをいれられるのではないかと考えたのです。
前打ち用や落とし込み用の竿の穂先は普通のチヌ竿よりもかなり細くできていますが、それでもカーボンロッドなので、そこそこの硬さはあります。子どもの頃に、よく父についてヘラブナ釣りに行ったのですが、記憶にあったヘラ竿の穂先は、もっと柔らかかった様な気がしました。そこで、釣具屋にへら竿用の替えの穂先を買おうと出かけました。すると、チヌの筏釣り用の穂先を自作するための素材だと思われるグラスファイバー製のソリッドの穂先が、数種類売られていました。その中でも、一番細いものを買って帰り、自分で加工し、穂先を取り替えて使い始めました。
使ってみると、本来の目的であった一気に引き込む大きいアタリに対しても、予想通り効果はありました。しかし、それ以上に別のメリットがあることが徐々に分かってきました。元々、アタリが有っても、すぐに吐き出されてしまうので、吐き出されないようにと考えただけだったのですが、穂先が柔らかくなったおかげで、アタリが確実にとれるようになったのです。と言うのは、今までは、チヌに違和感を与えないように、糸ふけを作り、糸ふけの変化でアタリをとろうとしていました。しかし、、殆どのアタリは非常に小さいため、私にはアタリが分からずに、エサだけよく取られていました。糸ふけを作らない場合は、餌を口にしても、チヌは違和感を感じ、すぐに吐き出してしまうケースが多かったように思います。コツンとアタリがあっても、それっきりとケースです。また、頻繁に、聞き合わせて、重みを感じたら合わそうとしていましたが、重みを感じた瞬間に、エサを吐き出されてしまい、素バリを引いてしまうこともよくありました。
しかし、改造の極軟穂先を使用した場合は、魚が引っ張った時の抵抗が非常に小さいので、糸ふけをあえて作る必要がなくなりました。これは、凄いことで、今までとれなかったアタリがとれる様になったのです。雑誌なんかでは、よく「糸ふけでアタリをとるんだ。」と言っておられる方がいますが、名人ならともかく私のような凡人には無理でした。しかし、極軟穂先では、嘘のようにアタリがとれ、アタリ開始から合わすまでの間にチヌにエサを吐き出されてしまうことが極端に少なくなったのです。要するに、チヌが当たっている時間が長くなったので、反射神経の劣る人間にでも「合わせたり「送り込んだり」といった行為を余裕を持って出来るようになったのです。
TV番組で、筏釣りが時々放映されていますが、そのとき、糸と同じ直線のライン上に小さく引き込まれる極軟穂先のアタリをご覧になられた方も多いと思います。まさしく、その様なアタリが、前打ちで出る様になったのです。
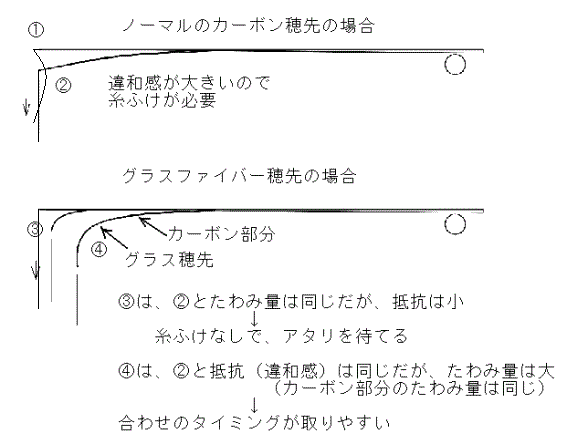 図.穂先の違い比較
図.穂先の違い比較
また、聞き合わせをしても、チヌが餌を離してしまうケースが減りました。居食いを合わせられるようになったのも、釣果UPに繋がりました。
極軟穂先を使った時に懸念されるのが、「合わせが効くのか」とか「折れないのか」とか「誘いがかけにくいのでは」とかいったことだと思いますが、全くそんな心配は全くいりません。合わせについては、穂先の次の2本目以降の胴の調子で決まるので、穂先は殆ど関係ありません。折れないのかについては、魚がかかった場合、胴の部分が曲線を描き、穂先部分は、ほぼ直線上になるので、魚がかかって折れる事はありません。誘いがかけにくいのではについては、カニが底にしがみついている時は少し剥がし難いですが、そんな時にはバカをくれると(一旦糸をゆるめ不意をついて剥がす)いとも簡単に、剥がせます。また、誘い方の一つの方法として、穂先をゆっくりと持ち上げ、カニがこらえきれずに剥がれてしまい、穂先が弾性ではね上がった分だけカニを浮かせるといったことをよくやります。この誘いでは、穂先が跳ね上がっている途中にゴツゴツと言ったアタリがでます。
いずれにしろ、穂先が柔らかすぎといったことに関わる弊害は、普通の釣り場では、まず無いと考えます。騙されたと思って、一度試して見てください。ポイントは、糸ふけを作らないことです。釣果倍増、間違いありません。
この秘策は、あまり広めたくはなかったのですが、このHPを観ている方は、そんなに多くはなさそうなので、公開しました。穂先の作り方は、気が向けば、後日紹介したいと思います。