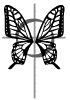 194.「憑神」
194.「憑神」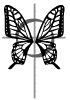 194.「憑神」
194.「憑神」
| 主なキャスト:中村橋之助・鈴木杏・葛山信吾・升毅・コング桑田・デビット伊東・藤谷美紀・秋本奈緒美・野川由美子 原作:浅田次郎 脚本・演出:G2 舞台監督:青木義博 公演記録:2007.10.1〜25@大阪松竹座(大阪) |
| あらすじ>>激動の幕末、慶応三年夏の江戸。下級武士である御徒士の次男別所彦四郎は、学問に秀でるだけでなく、剣は直心影流男谷道場の免許皆伝の腕前。小十人組の組頭井上家に養子に入り、妻八重との間に市太郎という男の子をもうけた。ところが、些細なことで養父軍兵衛に勘当されて別所家に戻り、兄左兵衛の妻にも邪魔者扱いされて肩身の狭い毎日。同じ御徒士出身で幼馴染の榎本釜次郎が、今や軍艦役にまで出世したのとは大きな違いである。酒に酔って小名木川の土手にやってきた彦四郎は土手から足をすべらせ、土手の下へと転げ落ちる。と、目の前にあらわれたのは“三巡稲荷”と書かれた破れ傾いた祠。彦四郎は何気なしに祠に手を合わせる。 家に戻った彦四郎が母に“三巡稲荷”の話をすると、母は顔色を変える。実は、彦四郎が拝んだのは“憑神”だったのだ。まずは、貧乏神が両替商伊勢屋となってあらわれる。貧乏神のせいで別所家は米を差し押さえられ、彦四郎の兄左兵衛は御徒士の株を売ることを考え始める。別所家の先祖は、大坂夏の陣の際、徳川家康の影武者となって討死した由緒ある家柄。紅葉山御蔵内の武具の手入れの役目を受け継いできた別所家の株を売ってはならないと、彦四郎は井上軍兵衛に借金を頼むが、冷たくあしらわれる。軍兵衛の屋敷を後にした彦四郎に声をかけたのは、元部下の小文吾。小文吾は、彦四郎が離縁される原因となった事件は、軍兵衛が仕組んだ芝居だったことを告げる。さらに修験道に通じる小文吾は伊勢屋に祈祷を唱え、困った伊勢屋は、貧乏神を別の人間に振る“宿替え”を提案する。恨み骨髄の井上軍兵衛への宿替えを頼む彦四郎。 彦四郎は街中で何度も騒ぎを起こしていた娘つやを助けて家に連れ帰り、そのままつやは別所家で暮らし始める。一方、貧乏神の宿替えの効果はてき面で、軍兵衛の屋敷が火事で焼けてしまう。彦四郎は放火の疑いをかけられるが、伊勢屋が彦四郎の無実を証言。伊勢屋は役目を終え、続いて疫病神があらわれることを告げて姿を消す。 慶応三年十月。洪水で小名木川があふれたため両国の力士が助っ人に駆けつけ、彦四郎も必死に川の水を防ぐ。弟とは対照的に、兄左兵衛は妻を連れて逃げ出す体たらく。兄弟の落差に組頭は憤慨し、兄の御役替えを言い出す。別所家とりつぶしの危機に、なんと次の憑神、力士の九頭龍為五郎実は疫病神がとり憑く。別所家を守るため、彦四郎が“宿替え”を振った相手は、ぐうたら者の兄左兵衛。九頭龍は宿替えを承知するが、驚くべきことを口にする。貧乏神、疫病神のあと、“三巡”すなわち三番目にやってくるのは、死神というではないか! 慶応三年十一月。別所家では、左兵衛が布団のなかで臥せっている。病気の真の原因は、彦四郎から宿替えした疫病神の九頭龍為五郎。左兵衛の布団の上には九頭龍が座っているのだが、彦四郎以外にはその姿は見えない。兄の病により、御徒士の役目は彦四郎が引き継ぐことになる。病に苦しむ左兵衛は御徒士の誇りである羽織を弟に手渡し、別所家累代の紅葉山御影鎧番の役目の大切さを話して聞かせる。話を聞き終えた彦四郎は、兄の差料である別所家に伝わる初代康継の刀を譲ってくれるよう頼む。突然、布団の中にもぐりこむ兄左兵衛。何か差料について疾しいことでもあるのだろうか?強引に刀を手にして彦四郎が抜くと、何と刀は錆びが浮くどころか真っ黒に腐っている。彦四郎は憤慨するが、兄はこんな世の中で鎧や刀の手入れをすることのほうがよっぽどの馬鹿だと自嘲気味に語る。年が明けて慶応四年。薩長中心の西国諸藩は「錦の御旗」を掲げるが、榎本釜次郎の乗る開陽丸は、淡路島沖で薩摩藩の春日丸と一戦を交える。薩摩へ早く戻るよう命令されていた春日丸は戦場から離脱し、海上を制覇した榎本が意気揚々と大坂城に赴くと、そこは最早もぬけの殻。徳川慶喜は江戸に逃げ帰ってしまったのだ。やむなく江戸に戻った榎本が彦四郎と戦況を語り合っているとき、刀屋の喜仙堂があらわれる。喜仙堂の話では、研ぎに出した別所家に伝わる康継の刀は贋作とのこと。ひょっとすると、彦四郎の先祖が影武者として大坂夏の陣で戦死したという伝承も作り話なのか、と悩みはじめる彦四郎。
|
| チケット代も高いし(1等席12600円、2等席7350円、3等席4200円)どうしよっかなー?って感じだったんですが。(苦笑)G2サイト先行もいちおあるんだけど…そこまでどうしてもっ!行きたいって感じでもないしなーと思いつつ。(爆)したらば近鉄百貨店の友の会(ママリンが家族も合わせて3口入ってるもので。苦笑)の案内で1等席12600円が12000円で観れるとかで定員各日10名(1日と14日だったかなー?)だし多かったら抽選になるかもなんだけどとりあえずそれで申し込んでみたりとか。で当たっちゃったのん。(おい)つか知らなかったんですけど1日って言えば初日じゃーんっ!(爆)思いっきり平日(月曜日)とかだったからそんなに応募もないだろ?って感じでほいほいと申し込んじゃったんですけれど。(苦笑)引き換えも当選はがきが届いてから1ヵ月後ぐらいだったので「忘れるYOっ!」と思ってたんですけど何とか用事のついでに(おい)引き換えて来たらば9列 22番っつー普通にいい感じの席が。(苦笑)ま、花道とは反対の通路側の席だったからちょっとね。(何が?)あ。でも冒頭の大坂城が攻め入られるシーンでは敵方の方が客席から登場だったので花道でない方の通路も使っててちょこっと見れたけど。(苦笑)まぁでも主役メインで観に行くわけじゃなし(おい)楽しめればそれでよしってわけで。そう言えば最近G2さんと言えば原作モノだと映画も一緒に公開されてたりで(「魔界転生」もそうでしたよねぇ?おぶおぶ)これもちょうど映画「憑神」は舞台版に行くかも?と思ってたので観てたのでちた。(笑)映画版は主演が妻夫木(聡)くんだったしちょっと若い設定過ぎるんじゃね?って感じだったんですけど(お兄ちゃんは佐々木蔵之介さんだった)舞台版は中村橋之助さんだしちょうどいいやも。原作は読んでないんですが(爆)映画版の方を観てたので判り難いところもなくすんなり観れてよかったんではないかと。ただ結構移動が多いのでどうするのかなー?と思ってたんですけど廻り舞台が2つあって彦四郎(中村橋之助さんの役どころ)の家と井上家が同時に廻って来たりしてたのでかなりスムーズだったんではないかなー、と。同時に2シーンずつ行き来出来るし。その辺りは「東京タワー」(観劇日記No.186参照)も似た感じで移動が多いところをスムーズに見せてたのでそれが生かされてる感じ?(偉そう)あ。「東京タワー」も映画とお芝居と同じような時期に公開でしたよね。(笑)でまず登場してくるのが貧乏神なわけですが。映画版は西田敏行さんが演じておられてかなり福々しい格好なのに貧乏神っつーギャップがおかしかったりしたんですけど舞台版は升毅さん。升さん、久しぶりだー。(喜)升さんだと見た目が細くてらっさるのでとても福々しいとは言えなかったりするんですけど(おい)その分上品さみたいな恰幅のよさより育ちのよさで勝負みたいな?(だからって西田さんが品がなさげって言うわけじゃないでつ)確か最初は貧乏神っていう存在に気づかせないやうに彦四郎と毎晩どんちゃん騒ぎで遊び歩いてたりしたと思うんですけどそこは舞台版ではカットされてて(当たり前だ。そこまでシーン増やしたらややこしくなる…)結構最初の方で手の内を明かしてたかな。お兄ちゃんの左兵衛が何とも情けなさ全開なんですけどそれがまたデビット伊東さんがぴったりで舞台で観るのは初めてだと思うんですけどよかったでつ。映画版のくらりん(おい)も「ま、いいじゃないかー」ってな感じでだらけっぷりが板についてたんですけどどうしても真面目な雰囲気のくらりんが堕落し切ってるのがいめいじじゃなくて何だかなー?ってとこもあったりしたので舞台版の方が好きかも。(おい)兄嫁は秋本奈緒美さんでらしたんですけどこっちもすごい合ってたし。確か映画版は鈴木砂羽さんでもっとこう彦四郎に対して邪魔邪魔オーラを終始醸し出してた(お役目を替わりに弟に譲るってのもすんげぇ嫌そうーな感じだったりしたし…)と思うんですけど舞台版はそこまででもなかったかなー?どっちかっつーと情けなさっぷり全開の左兵衛に対してのイライラの方が強そうな感じで。つかもう夫婦漫才のやうな掛け合いっぷりになってたとことかもあったし。(苦笑)映画版の兄嫁の方が「何であたしばっかりこんな目に合ってっ!」ってぎりぎりしてる感じが強かったけど舞台版はそれよりもちょっと天然っぽかったかなー?(え?)疫病神に宿替えされて取り憑かれて大変なことになってるのに「臥せってた方が何かとみんなが心配していろいろ気遣ってくれるからその方がラクでいい」とか言っちゃうぐらいに左兵衛ものんびりしてたし。(苦笑)ま、それだから最終的に死なずに済んでたりするんだろうけど。あ。でも疫病神だから死なせるまでの力ってのもないのか。死神なわけじゃないんだし。でそんな疫病神はコング桑田さん。映画版では赤井英和さんでしたけれどもこれはどっちもお相撲さんなわけだから体型とかは似たり寄ったりな。(は?)ただコングさんの疫病神の方が涙もろくて情に流されやすくて弱っちかった。(苦笑)赤井さんは「そんな相談乗れません」って宿替えのことも最初はすげなく断ったりしてたのに。で映画版と違うのが貧乏神&疫病神の戦闘状況の実況中継シーン。(は?)大阪初日だったからかそんなに遊びはなかったと思うんですけど「釜次郎、地団駄を踏んだ」は面白かったー。あれは舞台ならではの迫力とかもあって楽しかったれす。 で最後に取り憑かれるのが死神なわけですが。原作も映画版も確かちっちゃい女の子っていう設定になってる(原作は読んでないから知らないんだけど映画版でそうなってるってパンフに書いてた気がするー)ところを今回は普通の女の子ってわけで鈴木杏ちゃんが死神。ま、いきなり子役に死神役を舞台で演じさせるのは長丁場だし無理があるってのでそれなりに演技も上手くてそつなくこなせそうな杏ちゃんになったのかな、と。(おい)映画版は満を持してのホントに最後の最後に登場だったんですけど舞台版はもう最初から存在感ありまくりで。つやって名前から気が付けよっ!(死神だけにお通夜だしな。苦笑)って感じだったりするんですけどそれがもう全然気が付かず…。(黙)にしても「宿替えしちゃえばいいじゃん」とかオススメしたりしててかなり自己主張も強そうな死神っぷり。(は?)こうホントに先祖が徳川家康の影武者で死んだのか?(刀が贋物だったりしたから)とか疑っちゃったりし始める彦四郎だったりするんですがこのつやがむかーし取り憑いて死に至らしめたのが彦四郎の先祖の影武者で死んじゃったお爺さんだったってのが分かって有り難がったり映画版ではなかったエピソードもあったりとか。映画版より年齢が上がってる(おい)だけ彦四郎をなかなか殺せないのも彦四郎のことを秘かに好きになっちゃったからだとか貧乏神と疫病神のおじ様たちから冷やかされたりしつつ。(苦笑)映画版はさすがにそういうのはなかったなー。5歳ぐらい?とかの女の子だったしね。まぁでも宿替えも「取り憑いた本人(この場合彦四郎)の顔見知りでないと無理」だとかそういう説明はなかったのでとりあえず出て来る人の誰かに宿替え出来るみたいな成り行きっぽい感じになってたりはしたけど。最後の死神も映画版は途中偶然出会ってしまった慶喜に宿替えしてっちゃったり(勝手に。苦笑)してたけど舞台版はそういうのもなかったし。ホントに最後の最後も彦四郎が慶喜の不甲斐なさを憂いて自分が勝手に影武者になって出陣して行って死んじゃうとこまで映画版は描かれてたけど舞台版は曖昧なままで死んだかどうだか分からない感じ(たぶん死んだんだろうけど…)で終わってたりとかしたし。映画版にあった死神が彦四郎と一体化して取り憑くってのもなかったしなー。ま、そこは同時に舞台に存在することが出来なくなっちゃうから無理だろうけど。でも映画版にはなかったけど憑神3人衆の楽器演奏シーン(鳴り物演奏で合戦を盛り立てるっつー)は楽しそうでよかったでつ。とまぁ映画版と比べつつ観ちゃったわけですけれども。(苦笑)榎本釜次郎(葛山信吾さんの役どころ)も映画版よりはかなり出番あったんじゃないかなー?映画版だと話題に上るだけでなかなか本人登場するとこはなかったと思うんだけど舞台版は何かと彦四郎と比較するためにか出番多かったですねい。あ。あと小文吾が確か井上家の使用人っぽかったと思う(映画版ではね)んだけど舞台版はただ単に彦四郎の元部下っていう扱いになってたかと。つか(福田)転球さんの役どころだったんだけど転球さんそのままだったよ…。(苦笑)映画版は彦四郎が妻夫木くんだったから小文吾も年齢を合わせるためにか佐藤隆太くんだったけど舞台版はその分年齢も上がってたかな。(おい)転球さんだからなのか(は?)かなりの慌て者っつかパニックになるとしどろもどろで何言ってるのか分からなくなっちゃうキャラっていう設定でホントもう転球さんにあてがきしたとしか思えません。(爆)まぁでもなにげに神通力っつか修験道の修行もしてたりで山伏の格好してたりで(これは映画版と同じ)ちゃんとお経を読めば貧乏神も疫病神もほうほうの体になるぐらい強かったりするんだけど見た目は弱っちそうな。(おい)でも転球さんはホント出て来るたびに面白かったでつ。(え?)あと観たかったのが関秀人さん。でもホント蕎麦屋でちらっと出て来るだけであんまり出番も少なかったので「関さんだー」とは思ったけどそれだけで…寂しい。とほ。うーん…でももったいなかったのは映画版では上野の山に自分たちも参上したいつって市太郎と左兵衛の息子が2人して家を出ようとするのに彦四郎がそんな無駄に命を散らせてはいけないみたいに諭して自分たち大人が何とかするから死に急ぐな!みたいにして言い聞かせるシーンとかがあってそれがこう彦四郎が最後どうして慶喜の身代わりになってまで死のうと思ったのか?武士としての生き様っつか死に様みたいなのがクローズアップされていかにして生きて死ぬか?みたいなのが強いめっせいじとして残ったと思うんですけど舞台版はそういうのがちょっとなくて残念だったかなー、と。なんとなーくすんなり見れちゃった感じがするっつか。だったら最後ちゃんと彦四郎が死に行く様を見せて終わった方が受け入れやすかったかも。彦四郎が死ぬことで何かが変わったわけじゃない。言わば半分は自己満足みたいなものかもしれない。だけど死んで後世に名を残すとかそういうことじゃなくて自分なりの落とし前のつけ方っつか自分なりの生きた証みたいなのが残せる人ってどれだけいるんだろ?って思うには思うけどどうにも「こんな彦四郎みたいないい人が死んじゃって残念ー」みたいなだけで終わっちゃったって感じでもったいない。もうちょっとコメディの先にあるものを見たかったかな、と。(え?)あ。初日ってのを全然知らないままだったんですけど(苦笑)終わった後客席ロビーにG2さんが出ておられたりとか。(客席のあるフロアと物販のあるフロアが松竹座は別になってるので)関係者さんな方々と歓談しておられたりしたので声は掛けたり出来なかったんですけどちゃんと来ておられるんですねい。(初日だからか?←爆)G2さんロビーとかで見るのって…3回目ぐらい?なんか珍しい気がしますです、ハイ。カテコも2回ぐらいだったかなー?結構さらっと終わっちゃいましたねい。つか月曜日だったんで全席埋まってなかったやうなー。(おぶおぶ)次AGAPEだっけ?今回から大王脚本じゃないんですよねぇ…。とか言いながら(片桐)仁さん出てるから行ってそうだけど。(苦笑)ま、2月なんでゆっくり考えますー。(おい) |