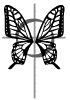 122.「歌わせたい男たち」
122.「歌わせたい男たち」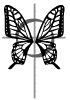 122.「歌わせたい男たち」
122.「歌わせたい男たち」
| 主なキャスト:戸田恵子・大谷亮介・近藤芳正・小山萌子・中上雅巳 作・演出:永井愛 舞台監督:菅野将機 公演記録:2005.11.23@シアター・ドラマシティ(大阪) |
| なんだか最近憲法9条の改正だとか「日の丸・君が代」周辺のことだとか首相の靖国参拝のことだとかそういう諸々のことがどばばばばぁーっと起こってたりしますが。なのでタイムリーな話題でありながら社会派ーっぽくなく「だからこうなんだー」っていう声高な主張でもなく重たい話題なはずなのに笑いもあったりしてこういうきっかけで考えるようになるってのも悪くないのではないのかなー?なんて。実際問題あたしは「日の丸・君が代」ってものに対してそんなに嫌悪感だとか罪悪感だとかそういうのは感じない方なのではないのかなー?と思います。でもそれは戦争の時代の後に生まれて育って来たからでやっぱりあの頃何か間違ってるんじゃないか?なんてふっと考えながらも突き進んで行くしかなかった戦争の時代を生きた人たちにはいい思い出とばっかり繋がってるものじゃないし戦後っていう時代に生まれた人の中でもそういう気持ちに共感して嫌悪感だとかを示す人がいてもおかしくないんじゃないかなー?と思うんですよね。でもそんなの人間だからみんながみんな同じ思いを抱けなんて絶対無理な話だし100人いたら100通りの考え方があるように君が代を歌いたい人と歌いたくない人がいても構わないと思うんですよね。でもそれを強制して歌わせる(そもそも入学式や卒業式に日の丸・君が代とセットだったことが小学校ぐらいしかなかったので(中・高と私学だったのであんまりそんな記憶がないんですよね。苦笑)こんなに大変なことになってるだなんて思いもしなかったってのもあるんですけど)っていうのはちょっと違うんじゃないのかなー?と。それにその歌わないことで解雇されたりとか転勤になったりだとかそういうのは果たして適切な処分と呼んでもいいのかな?と。確かに教員は国家公務員・地方公務員(公立であれば)なので労働基準法の適用除外(そういう勉強をちょっとばかししてるもので。苦笑)なので公務員法でどうなってるのかは正直分からないんですけどそれと内心の自由うんぬんの問題はまたちょっと違っててそこで持ち出すのはかなりずれた物の見方ではないのかなー?と思うんですけれど。でも生徒に対しても「歌う」にしろ「歌わない」にしろ「何故歌うのか?」もしくは「何故歌わないのか?」っていう説明がちゃんと出来る先生は果たして何人いるんでしょうか?歴史だとか日本史にしても受験対策上のことはやるけどそういう現代史?っていうのかなー?そういうのをちゃんと時間を割いて教えてもらった記憶がないんですよね。さーっと流して「とりあえずこういうことがありました」的な一般常識みたいなのは押さえておいてそれがどれだけテスト(つか受験?)に出るか?ってことだけでだから日本は今どういう立場に立たされてるんだとか日本の役割だとかそういうことを教えてもらったことがないって人が大半なんじゃないでしょうか?あたしも歴代首相の名前だとかは語呂合わせで覚えさせられたこととかは覚えてるんですけど(苦笑)戦争っていうことの位置づけみたいなものについてあんまり考えたことがないかもしれません。ただ漠然とそういう戦争だとかは起こらない方がいいし起こったらただ普通にひっそりと死ぬなんてことは望めないだろうしそうすると嫌だなっていうものすごーく戦争とは遠いところでしか考えられてない気がします。でもやっぱりみんなが一斉に日の丸の方を向いて起立して君が代を歌わなくちゃいけない、仕事だから心の中で何を考えてようとそれだけは守らなくちゃいけないってのはやっぱりなんだかおかしいと思うんですよねー。立ってなくても歌ってなくても心の中でひっそりと尊敬してるってこともあるかもしれないじゃないですか?そういうのもありでしょう?無理矢理何かをさせるっていう権利は誰にもないんじゃないですかねい?しかもそういうことを取り決めるってのは絶対違うと思います。それで戦争の時に国家に共産主義者だとかそういう取調べを受けて制裁を受けた人たちのことを連想したとしてもおかしくはないでしょう。卒業式だとか入学式だとか結局誰の物なんですか?学校のそういう儀式を受ける対象の人たちがメインなわけでしょう?そのー教育委員会だとかのお偉いさんたちのために見せる式じゃないじゃないですか。学校のいいところを見せる場なわけでもないでしょう?そりゃぁ卒業生だとか入学生だとかが「歌いたい」っていう気持ちに溢れてる人たちばっかりだったら歌えばいいんじゃないですか?オリンピックだとかW杯だとかで日本が勝った時に日の丸が掲揚されて君が代が流れるっていうのは晴れがましいし誇らしい気持ちにもなるし国旗とか国歌がなかったらなかったでそれはすごく寂しいなとも思うし。たぶんそれが新しくデザインが変わって国歌も詩が変わって違う歌になったとしたら最初はちょっと違和感があって変だなーと思うかもしれないけど少し時間が経てばなんとなーく慣れてくるんだろうしそれが初めからあったみたいな感じにいつかなるんだろうしそれももしホントに真剣に取り組んで国民投票みたいに応募みたいなのがあったとしたらその流れに乗るんだろうなーとも思うし。だから結局どっちつかずなんだろうなーと思います、あたしは。(苦笑)「歌え」って言われたら「そんなもんかなー?」って思って歌うだろうし「こうだから歌うな」って言われればそれに共感出来れば「そうかー。歌わないのもアリだなー」って思うし。むうーん。 と。舞台の5人も5者5様と言いますか。(苦笑)校長先生(大谷亮介さんの役どころ)は昔は「卒業式は誰のためのもの?」ってことを真剣に考えて日の丸・君が代に対しても割とフリーな考え方と言いますかいろんな考え方の人がいて当たり前っていう立場だったのに校長っていう役職になった途端に学校の対面だとか自分の立場だとかそういう諸々のしがらみで「歌って当然」っていう風になっちゃった人っていうか。若い先生たちはあんまりそんなことには関心がないと言うか歌わない先生がいることで研修時間を割かなくちゃいけなかったりそういう面倒事に巻き込まれるぐらいなら事なかれ主義っつかいろいろあってもみんな同じでいいんじゃない?みたいな?社会の先生(近藤芳正さんの役どころ)はただ1人反対派で。でもビラ配りをして積極的に活動するわけじゃないしとりあえず1人だけ自分の考え方を押し通すみたいな静かな憤りって言うか。まぁでも一番まともな考え方の人ですよね。音楽の先生(戸田恵子さんの役どころ)は中立派かなー。つか割と流されやすい人って感じな。この状況に対して特に何も考えてないしそれがおかしなことだってことにも気が付いてないし「こうだからおかしいんだよ」って言われれば「あーそうなのかー。おかしいのかー」って思ってそっちにも付いちゃうんだけどでもそうすると職自体なくなっちゃうからそれはダメだしだったら嫌々でもいいから歌った方がいいよーなお人よしさんですよね。あたしはここな感じがする。(え?)現場にいたらきっと面倒は勘弁な方に付いちゃうと思うんですけど。(爆)でも問題意識とかそういうのが薄い人の方が多いと思いますよねー。「え?なんかおかしい?」って思わない人の方が多いっつか。「おかしい」って思ってたらもっと主張するだろうしもうちょっと流れが変わるんじゃないかなー?と思うんですけれど。社会の先生が言う「このことをおかしいと思わない方がおかしいんだよ」ってちゃんと説明するシーンはずもーんと来ましたね。そういう感覚が麻痺しちゃいけないよな、と。でも1人で闘わなくてもよかったんじゃないのかな?とは思ったりとか。だからちゃんと説明して「こうだからこうなんだよ」って教えてあげればよかったんじゃないかな、と。その基準って言うのかな?判断基準が曖昧なとこで「歌う」「歌わない」っていう議論がされちゃってて土台なんか全然ないに等しいですよね。「歌う」にしろ「歌わない」にしろ明確な判断基準って言うんでしょうか?強制されて仕方なくじゃなくて「自分はこう思う」っていう芯のところがあればいいんじゃないかなーと思います。ま、それを全然与えて来なかった、与えられて来なかった、教えてもらおうとしなかったっていうのも問題あるんですけどね。と今回は4列 37番となかなかのかぶりつきな席で。もっとなんて言うのかなー?「歌わせたい男たち」っていうタイトルから連想して戸田さんが卒業式をボイコットする役なのかなー?なんて思ってたんですけれど。こう当日になって「やっぱり歌えない」ってことになって保健室に立てこもるーみたいな?(は?)でみんなが入れ替わり立ち代わり説得工作に来るみたいなお話になるのかと勝手に思ってたんですが。(おい)ま、でもそんなに遠くじゃないですか。(え?)でもこうじわじわと息苦しい国になって来てる感じがして怖いですよね、やっぱり。自由っていうのはやりたい放題とは全然違うけど今あるこれとは違うなーと。大体卒業式に警察が大挙してやって来るだなんて事態はよくないですよねー。なんか後味も悪いし思い出としてもいい思い出とは思えないし。なんか絶対思い出したくないことって言うか卒業式なのにそれはどうなの?ってのもありますね。先生も大変だけど生徒も大変だなー、と。こんな日本でも生きてかなくちゃいけないし選んだのはみんななんだし責任の一端は誰にでもあるんですよね。仕方ないけど。何か画期的に変わるなーんてことがあればいいんですけどねー。(遠い目)まぁでも他の国から見たとしても国歌のこととか国旗のこととかでもめてる国って言うのは滑稽っていうか恥ずかしい感じもするんですけど。(苦笑)まだまだ12月地方公演もあるようですしもし観る機会があれば観てほしいと思いますです。 |