Weblog of HK
���X�̋L�^��G�����C�̌����܂܂ɋL�q���Ă����܂��B ���͉Ȋw�����҂����Ƃ���40�N�]���߂����Ă��܂����B�����͐V�K�łȂ���Ȃ�Ȃ��� �ŁA�o���邾�����̐l�ƈقȂ������_�����Ƃ��Ƃ��A�Ǘ��������ꂸ�����̐M���铹�� �i�ނ��Ƃ�M���Ƃ��Ă��܂����B���̒��N�̐����K���ŁA���Ƃ��ĕϐl�ƂȂ�A�Љ�� �ł͏�Q�ƂȂ肩�˂܂���B���������āA�����ɋL�����Ƃ��A�Ƃ�悪��̂��Ƃ����X ����Ǝv���܂����A��l�̐l�Ԃ̓ƒf�ƕΌ��Ƃ��āA���ᔻ�E�����]���������K���ł��B2021.12.29
�䂪�Ƃ̑��z�����d
�����̌������̂��_�@�ɉ䂪�Ƃł͑��z�����d���u�������B�ݒu���Ă���5�N�Ԃ̃f�[�^�� 2016.5.19�̃u���O�ɋL�ڂ����B���̐��\�ɖ��������̂ŁA�䂪�ƂŎg���d�͂̑S�Ăz�����d�� �܂��Ȃ����ƁA2016�N9���ɑ��z�����d���u�݂����B2017, 2018, 2019, 2020,2021�N�̌��ʃf�[�^�� �L�ڂ���(��:12���͑O�N�̂���)�B���ʑ��z�����d�ʂ�}1�ɁA���ʓd�͏���ʂ�}2�Ɏ����B���̂P�N�Ԃ�
�����z�����d�ʂ�6372kWh(2020�N��6279kWh,2019�N��6434kWh,2018�N��6795kWh,2017�N��6455kWh)�ł������B
���d�͏���ʂ�7499kWh(2020�N��8151kWh,2019�N��7620kWh,2018�N��7900kWh,2017�N��7133kWh)�ł������B
�䂪�Ƃ̓I�[���d���ŁA��g�[�E�����E���C�E�Ɠd�E�Ɩ��S�ēd�C�ł���B"�S�d�͏���ʂz�����d�� �܂��Ȃ�"�Ƃ����ړI�͒B�����Ă��Ȃ����A�܂��܂��ł���B
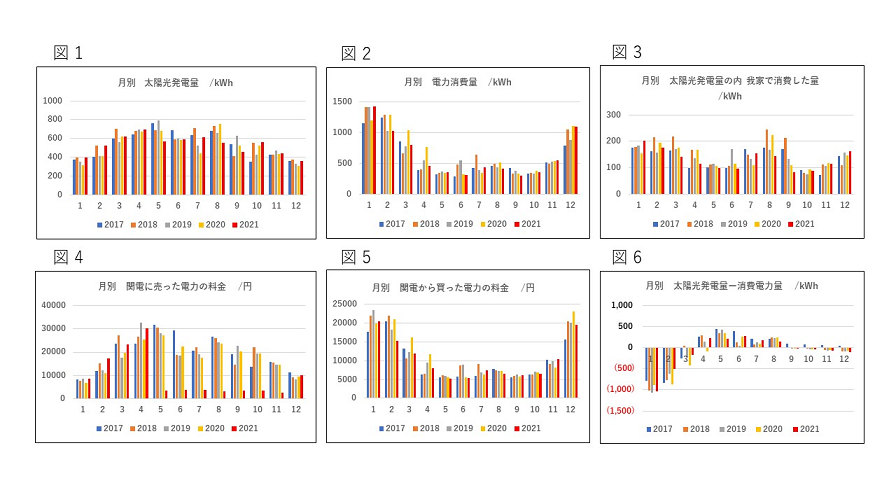
���z�����d�ʂ̓��A���d���ɉ䂪�Ƃŏ����d�͂͑��z�����d�̓d�͂��g�p����B���̗ʂ�}3�Ɏ����B �c����֓d�ɔ���B���ʂ̊֓d�ɔ������d�̗͂�����}4�Ɏ����B���d���ł�����Ȃ������Ɣ��d�̖������� �g�p�d�͂͊֓d���甃���B���ʂ̊֓d�Ɏx������������}5�Ɏ����B
�֓d�ɔ������d�̗͂�����: 2021�N��112,712�~(2020�N��217,296�~,2019�N��226,272�~�C20018�N��235,296�~�C2017�N��235,728�~)
�֓d���甃�����d�̗͂���: 2021�N��123,043�~(2020�N��137,840�~,2019�N��135,800�~�C20018�N��134,368�~�C2017�N��120,812�~)�ł������B
�Œ艿�i���搧�x�̌_���10�N�Ԃł���̂ŁA2021�N5���Ō_����Ԃ͏I�������B���d���i��1kWh������2021�N5���܂ł�44�~�A���̌��8�~�ł���B �����������̉������80%�ʂ��낤�B�ł�
���������ł́A10�N�����Ă��u���q�F�̊O�ɂ���R���v�[������A�g�p�ς݊j�R�������o�����ĂȂ��B ���q�F�����̏��u�͌��ʂ��������Ă��Ȃ��v�B�댯�ȏ�Ԃ����������Ă��܂��B
�����̌������̂̒���ɁA�䂪�Ƃ̑��z�����d�V�X�e����ݒu�����B�ݒu����10�N���߂��Ă�"���d���\�̒ቺ���قƂ�ǂȂ�"���Ƃ͋����ł���B ���z�����d���u���D����̂ł��邱�Ƃ��������邱�Ƃ��ł����B
�u�댯�Ȍ��q�͔��d����߂āA�Đ��\�Ȏ��R�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ɐ�ւ���v�ׂ����ƍl���܂��B
2021.12.17
 ���s�A���A�ޗǂɏZ��"���w����������N�̉�"�̌������o�[3�l�ŁA��N�Ɉ�x�قlj���Ă������A
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s�������āA��N�͉���Ƃ��ł��Ȃ������B���s�ɏZ��I�N����u��18�s����
�ʐ^��ƓW�ɏo�W��������I�����B������@��ɏW�܂�܂���?�v�ƗU��ꂽ�B���ɏZ��K�N�Ǝ���
16��11���ɉ��̋��s���������ق֍s�����BI�N�̈ē��Ɖ�����Ȃ���A��200�_�̍�i���Ϗ܂����B
���s�A���A�ޗǂɏZ��"���w����������N�̉�"�̌������o�[3�l�ŁA��N�Ɉ�x�قlj���Ă������A
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s�������āA��N�͉���Ƃ��ł��Ȃ������B���s�ɏZ��I�N����u��18�s����
�ʐ^��ƓW�ɏo�W��������I�����B������@��ɏW�܂�܂���?�v�ƗU��ꂽ�B���ɏZ��K�N�Ǝ���
16��11���ɉ��̋��s���������ق֍s�����BI�N�̈ē��Ɖ�����Ȃ���A��200�_�̍�i���Ϗ܂����B���s���������ق̎���́A�����Ƃ̑�R�c��ꏊ�Ȃ̂ŁA�ӏ܌�A�O�l�ŎU���B���͖�30�N�Ԃ�̖K��� "�Â�����ǂ��ۑ�����Ă���Ȃ�"�Ɗ��S���A�U����y���ނ��Ƃ��o�����B�܊p�Ȃ̂Łu��ۓ��ł����������v �ƌ����A�O�l�ŕ����čs�����B�X�̍\�����g�����A�̂Ə������ς���Ă��Ȃ������B
���̌�A�^�N�V�[�œ�T����O�Ɉړ���"������ǂ��ӃR�[�X"�����\�����B�뉀�����h��(�E�̎ʐ^�͂����ł̃X�i�b�v)�A �A���h�I�V(�ʖ�:�ꗼ)���������Ԃ������R�t���Ă��܂����B�痼�A�������A���Ă����āA�ǂ����"�痼�����L��ʂ�" �Ɵ����Ă�l�ł��B
�H��A��T���������U���B���͑�w��N���̎��ɁA��N�ԓ�T�������ɉ��h���Ă����̂ŁA�ƂĂ��������������B "�R��"�w����n���S�ɏ��A�r���œ�l�ɕʂ�������A16:30�ޗǂ̎���ɒ������B�ʂ�ۂ�K�N�� �u�M������Ԓ��������邾�낤����A��낵�����肢���܂��v�ƌ�������AK�N�́u�l�͍Ȃɑ厖�ɂ���Ă��邩��ʖځB �������炢�����x�ŁA����������v�Ƃ�����������B
2021.12.1

�j�I�C�X�~��
�t��ɍ炭�j�I�C�X�~�����Ԃ���ւ����t���Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B�@���Ԃɋ߂Â���Ɨǂ����������܂��B ���̉Ԃ̓��[���b�p���玝�����܂ꂽ���̂ŁA�i���̈���v�����̃V���{���Ƃ���A����}���A�̐������� �ے�����ԂŁA�Ւd��ɂ͂��̃X�~���F�A�Ԃ��������܂�Ă��܂��B���͍��N�A�X�~���ɂ��ĐF�X�w�т܂����B�B3��2���Ƀm�W�X�~����m��A3��3���Ƀj�I�C�X�~��������ƁA 3��9���ɃR�X�~���A3��10���Ƀ^�`�c�{�X�~���A3��16���Ƀq�S�X�~���A3��23���Ƀq���X�~���A3��27���ɃA���A�P�X�~���A 4��1���X�~���A4��9���V�n�C�X�~���A4��13���j���C�X�~��(�c�{�X�~��)�A5��4���t���g�X�~���A5��8���j�I�C�^�`�c�{�X�~���A 6��8���A�M�X�~�������܂����B
����Facebook��"��̉Ԃɖ������"�̃O���[�v�ɂ���Ă��������āA�ʐ^�𓊍e���A���X�����Ă��������܂����B
2021.11.16

��䉷��
���N��"�I�̃V�[�Y��"�ɂȂ����B�E�E�E�ŁA����"��䉷��"�֍s�����Ƃɂ����B��N��GO TO �L�����y�[���� �����āA��䉮�̗\�Ȃ��Ȃ��Ƃ�Ȃ��������A���N�͋Ă���11��15���̗\�����邱�Ƃ��o�����B15��9:00�ɎԂʼnƂ��o���B12:30�ɒ���s�ɂ��铹�̉w"�k����������͂�"�ɒ������B���H�Ƃ���"���˂��ǂ�"�� ���ׁA�_�Y����������"�����`�A�M���i���A���J�S�A���X"�����B���搼IC�ň�ʓ��H�ɏo�āA�ΎR�r(����܂����A �D���ŁA�u�r�v�ƕt���Ώ��̒��ł͓��{�ő�)�̐������֍s�����B�������U����A�ΎR�r�i�`�������K�[�f�� �֍s�����B���̃K�[�f���͎��R���ɋ߂���ԂŎ�X�̐A�����A�����Ă��āA���͍�N�K��ċC�ɓ���A���N�� �K��Ă��B15:30�K�[�f�����o���A���IC�ň�ʓ��H�ɏo�āA16:00��䉮�ɒ������B
��䉮�͂Ȃ�Ƃ����Ă����ǂ��B���D�̉��ɕ~�������̉����猹�N���o���Ă���B��������ł���B ���a�̕��͋C�A���M�̍�肪���͍D���ł���B�������������A18:00����I�Â����R�[�X�𖡂�����B�܂��ɐ�i �ł������B�ł�"���������ʏ��Ȃ������ǂ�"�Ǝv�����B���̗l�ɔN������"���������H�ׂ�����"�Ǝv���ʂ̗ʂ� �ǂ��̂��B�H��A�ēx����ɂ�������A21:30�A���B
16��7:00�N���B����ɂ�������A8:00���H�B9:30�`�F�b�N�A�E�g�B���ق̒��ԏ�ɎԂ�u���āA1km���̏��ɂ��� �䓒�_��(�݂䂶��A�n��811�N�̌Î�)�Ƃ��̋߂��ɂ�����p�����ӎ���(���ӎ��͔��P���ɑn���A�O�d���� �S�b���c���Ă���)�֍s�����B11:00��䉷����o���A12:00�A�n�����A�����ɒ������B�������U�A�낤�Ƃ�����A �J���~��o�����B13:30�A�n�����A�������o���A�_�˂ɋ߂Â��ƉJ�͎~�B16:30�ޗǂ̎���ɋA�������B
2021.11.11

�M�q�W����
���N���̂肽�Ă̗M�q���R�����������̂ŗM�q�W������������B������2020.11.10�̃u���O�ɋL�ڂ����B 3kg�̗M�q����E�̎ʐ^�Ɏ����������̃W�������o�����B����ň�N�Ԗ����g�[�X�g�ɕt���ĐH�ׂ邱�Ƃ��o����B ���ӁE���ӁI���̍D���ȉ�
�M�Z�Ȃ�@��Ȃ̐�́@��������@�N�����݂Ă@�ʂƏE�͂�
�M�Z�ޗ� �m��\�͔��\ ���˗�v�� ���V�z���V�k ��������C�g��
���t�W�@14�� 3400�@��ҕs��(���̂̑�����)
2021.10.25
�q���b�g�����
���͂���܂�80�˂܂Ő���������ƍl���Ă������A���ۂ�80�˂ɂȂ��Ă݂�ƁA����Ⴀ�q���b�g����� "90�˂܂Ő����邩�������"�Ǝv���������B�����l���v�ɂ��čl���Ȃ����˂Ȃ�Ȃ��B���N��Ԃ��ǂ��ω����邩�ɍ��E����邩��Ջ@���ςɑΉ����Ă��������Ȃ����E�E�E�B
�E�p�\�R���͍��̂����ɔ����ւ��āA�V�����i���Ɋ���Ă����������ǂ���?
�E���Ɨp�Ԃ͔����ւ����ق����ǂ���?
�E�����l���ɁA���̃X�e�b�v�ւ̕ω����K�v��?
���X�E�E�E
�܂��A�y�V�I�ɁA�V���v���ɁE�E�E�����Ă������B
2021.10.2

�����R
���͍����R(�W��1248m)�ɑ�w���̎����߂ēo�����B���̎��́A�������̊w�F�Ɠ�l�ő喔�܂Ńo�X�ōs�������R�ɓo��A �����`���ɕ����A�r���Ńe���g���Ĉꔑ���A�������������o�č����R�ɓo��A���J�܂ʼn��R���ăo�X�ɏ�����B ���̎������60�N�o�����B�����A����100���D�ɒ����鍂���R�o�R�����Ă����B���̂���č�����ł����������A ���ł̓u�i�̖������B����Ȃɓx�X�o�����̂́A������(�W��899m)���炾�Ɩ�ꎞ�Ԃœo���o����Ƃ�����y ���ƁA�Ɨ���Ōi�F���ǂ����R�i�ł��邱�Ƃł��낤�B�ł��邪�E�E�E�A����80�˂ɂȂ����B�o��̗͂����邩�c�s���ɂȂ����B�悵�A���̍ہA"80�˂ō����R�ɓo�����Ƃ��� �L�^���c���Ă�����"�Ǝv���������B�ł��A�����s���ł���B����ŁA����O�ɁA�_��R(�W��618m)�ɓo�����B�o�R���� �W����480���A���s����4.1km�A���s����2���Ԕ������s�����B���̌��ʁE�E�E���v�Ǝv�����B
10��2���A7:00�N���A8:00�ԂʼnƂ��o���B�r���A�p�c��̃A�O���[�}�[�g�Œ��H���A10:00�������ɓ����B�o�R�C�𗚂��A �X�e�b�L�������ēo�R���J�n�B��l�o�R������Ԃ̎ʐ^���B��Ȃ���A�������������o�����B�r���̓W�]���ɒ�������A ��҂��傫�ȎO�r�ƃr�f�I�J�����������č����Ă����B�u�T�V�o�ώ@�ł���?�v�Ɛu�˂���u�����ł��v�Ƃ̕Ԏ��ł������B ���������R�ɍs�������R�̈�́A���̎����ɂ�"�T�V�o�̓n��"���ς��邩��ł���B���͑o�ዾ�������b�N�T�b�N���� ���o���Ċώ@�ɉ�������B�b���ϑ��������T�V�o�͊ς��Ȃ������B�ŁA���͒���Ŋώ@���悤�ƌ��߂āA�ʂ���������B
12:00�ɒ���ɒ������B�A���̎ʐ^���B��Ȃ���A�������o�����̂ŁA���C�ł������B���ォ��ς��x�m�R�����̎ʐ^���E �Ɏ����B�����ŕx�m�R�������邩�ƒT�������A�����C�̔����ɂ̌������ŁA�c�O�Ȃ��猩���Ȃ��B20���قǓo�R�҂�����ɋ����B ���͒��ォ�班���~�肽�W�]�̗ǂ���̏�ŁA���H��ۂ�Ȃ���T�V�o���ϑ������B���̓W�]���ʼn������҂��o���ė����̂� �ꏏ�ɃT�V�o�ώ@�������B20�H�قǂ̃T�V�o���n���čs�����B13:00��҂ɕʂ���������R���J�n�����B14:00�������ɋA���A 16:00�ޗǂ̎���ɖ����A�������B����Ȃ�A�����R�R���ɂ܂��s�����Ƃ��o����̂ł͂Ȃ����E�E�E???
10��3���e�j�X�X�N�[���ɍs�����B�����������ؓ��ɁB����ς�N���ˁI
2021.9.21

���H�̖���
�����͒��H�̖������Ƃ����̂ŁA������O��"�����c�q"�����ƁA11�����a�َq������֍s�����B �ޗǂł͌����c�q�Ƃ����ƁA�c�q���Q�q���܂��Ă���B�����~�����̂�"�P���Ȕ����c�q"�ł���B ������Ă���a�َq�������m���Ă���̂ŁA�����܂ŏo�����čs�����B�K���������Ƃ��ł����B���̂����b�ɂȂ��Ă���e�j�X�X�N�[���͌����V�c�˂̉��ɂ���A����͎G�ؗтł���B�X�N�[�����I���Ă���A �X�X�L�ƃN�Y�̉Ԏ}���̂��Ă����B�Ƃ̒�ɂ́A�n�M�A�I�~�i�G�V�A�t�W�o�J�}�A�L�L���E���������̂ŁA���Ă����B �i�f�V�R�͒�ɂ���̂����ǁA�c�O�Ȃ���ԋG�͏I����Ă����B�����𓌑厛�啧�a�̌Íނ��������Δ��� �]�p�����Ԋ�ɐ������B���̉Ԃƒc�q�������ɏ���(�E�̎ʐ^)�A"���H�̖���"��҂����B21�����߂��āA�Q���_�̒����� �ۂ������l���ς���悤�ɂȂ����B
���̉ԁ@���ԁ@���ԁ@�Ȃł����̉ԁ@���݂Ȃ����@�܂����с@����̉ԁ@�@�R�㉯�ǁ@���t�W�@��8-1538
2021.9.15
��Ȉ�@
���͈�T�ԂقǑO�ɁA�E��ɃS�~���������l��"�ٕ���"���������B����ŁA����ɍs���čR���ǐ����z���̖ږ�� �����Ă��ē_�Ⴕ���B����͗ǂ������āA"�ٕ���"�͐����Ԍ�ɖ����Ȃ����B�Ƃ��낪�A����A�Ԃ��^�]���Ă��� �E�Ⴊ"�������������l�Ɍ�����"���ƂɋC�t�����B�����"��Ȉ�@�Őf�Ē����������ǂ�"�Ǝv���A�O�N�قǑO��"�������p" ������Ȉ�@�֍s�����B��t�͐f�@���āu�㔭������(�������p��A�l�H�����Y�̌��̖������ԂƋ��ɑ����Ă���)�ł��B ���[�U�[�����ő������鎡��(��X�؊J��p)�����܂��B�ɂ݂͂���܂���B�����ł����܂��B�v�ƌ���ꂽ�B "�㔭�������p���ӏ�"�ɏ�������ƁA���[�U�[�����Ǝ˂ɂ�鎡�Â��n�܂�A1-2���ŏI���A�ɂ݂��S���Ȃ������B
��p��6,310�~�B��ǂœ_���������������B����O��B��T�ԑ����邱�ƁB��t����́u���E���J���_�����g�p�������� �����Ԃ͎Ԃ̉^�]�͂��Ȃ��ł��������B�v�ƌ���ꂽ�B���āA���̊�́A���[�U�[�����Ǝ˂ɂ�鎡�Ò���͂ڂ₯�ăX�}�z�� �������ǂ߂Ȃ������B���X�Ɍ�����悤�ɂȂ������A�O�ɏo���ῂ����ėǂ������Ȃ��B�u�����Ԃ͎Ԃ̉^�]�͂��Ȃ��ł��������v �ƌ���ꂽ�̂ŁA�Ԃ̒��ŋx���B�ꎞ�Ԃقǂ����Ƃ���ŃT���O���X���������"�܂��A���v"�B�T�d�ɉ^�]���ċA����B
2021.9.4
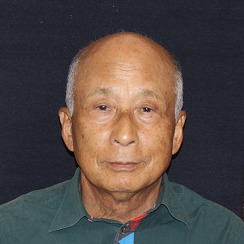
��80�˂̒a����
�����A���͖�80�˂ɂȂ�܂����B�E�̎ʐ^��2021�N9��2���Ɏ��B�肵�����̂ł��B"�N����̊炾�Ȃ�"�� �����ł��v���܂��B7��15���ɓ��茒�N�f���E�咰���f�����̂�9��2���ɕa�@�֍s���āA���ʂ�u���Ă��܂����B �u���̊ȒP�Ȍ����ł͖�肠��܂��A�܂��l�ԃh�b�N��f���Ă��������v�ƌ���ꂽ�B ���o�Ǐ�ł͍��̂Ƃ���ɂ��Ƃ�����Ȃ��B����ł������Ȃ��B�T2,3��̃e�j�X���y���ނ��Ƃ��o���Ă���B "���肪��������"�Ɗ��ӁE���ӂł���B�ł�"�̗͂͗����Ă��Ă���"�Ǝv���B�����������Ȃ��B"���������Ă͂����Ȃ�" �Ǝv���B
���̔N��ɂȂ�ƁA���h���E�����������X���w�Ǒ��E����Ă���B�₵������ł���B������������������y�E���y�� �����Â����Ă����B"�ǂ����F�����C��"�Ɗ肤�B���͍K�^�҂ŁA����܂ŏ[�������y�����l�����߂������Ă��������܂����B ������A�����̐搶���A�F�l�E�m�l�A��y�E�����E��y�A�Ƒ��A���̑������̐l�X�̂��A�ŁA�L����ӂ��Ă��܂��B ����"����������ł��ǂ�"�Ǝv���Ă��܂��B�ł��A"��������̂��l���̈ꕔ"�ŁA"������Ƃ���܂ł������Ē�����"�� �v���Ă��܂��B"�ǂ̗l�ȏI�����}�����邩�͓V���I"�@��킭�Έ��炩�Ȃ��Ƃ��I
�R���i�ЂŁA���������l�Ɖ���Ƃ��܂܂Ȃ炸�A���s�E��H���邱�Ƃ��܂܂Ȃ炸�E�E�E�̓��X�ł����A �g�̓I�ɂ����_�I�ɂ����N�ɕۂ悤�H�v���Đ������Ă����܂��傤�B
2021.8.29

�c��
���N�̉Ă�6���ɏ������������āA�ǂ�Ȃɏ����ĂɂȂ邩�ƐS�z�������A8�����{�ɉJ�̓��������ė������ĂƂȂ����B ���������͍ō��C��35���ł����A���ӂ�25���ȉ��ʼn߂����₷���Ȃ��Ă��܂����B�V�C�\��ɂ���9���ɂȂ�ƁA����� �������Ȃ�悤�ŁA����"���N�̉Ă������߂�����"�ƁA�����z�b�Ƃ��Ă���B�ł��A�R���i�Ђ́A�V�K�����Ґ���5��ڂ̃s�[�N���}���Ă���B���̐��͑��債��Õ��N�����Ă���B�M���łĂ� ����҂���ɐf�Ă��炤���Ƃ��o���Ȃ��B�g�̂̎ア�l�͂ǂ������炢���̂�? �R���i�Ђő����o���Ă����N���ɂ��Ȃ�̂ŁA�ً}���Ԑ錾���o���Ă����ʂ��������Ă���B �����e�j�X�X�N�[���ɍs������A���w�Z1,2�N�����e�j�X�̎��������Ă����B�q�����ϋq(�������e)�̕��� �l�������������B�������������}�X�N�𒅗p�����e�j�X�������B
"�����̂��Ƃ͎����Ŏ��I"�Ƃ����B�����A���������������B�������ɂ������ɏo�����A���V���Ńe�j�X�������B ���A�l�ŁA�i���g�J�����ɂ��̉Ă��߂������B�ł��A���̌��C�����̂��������Ȃ�B��҂����S���ĕ�点��Љ� �łȂ���Ȃ�Ȃ��B���C�Ȃ��̂͂����łȂ��l�������Ȃ���͂Ȃ�Ȃ��B
�E�̎ʐ^�͏H�C���B
2021.8.15
���~
�V�^�R���i�E�C���X(Covid-19 infections)�̊����Ґ����}�����Ă���̂ŁA���N�Ɠ��l���N���̋��� �A���ĕ�Q���鎖����߂��B���Z�s�̏]��Ɗ֎s�̒�ɓd�b�������đ��k������A�������ł������҂� ���債�Ă��邩��"�Ђ����������ǂ�"�Ƃ������_�ɂȂ����B��Q�����肢���āE�E�E�B12,13,14,15���ƘA���J�ŁA���J�ЊQ���A������Ă���B�ޗǂ̉�Ƃ̗��͍��ې�ŁA�������Ă��邪 �댯�͊����Ȃ��B���̉J�ŁA��̑��͂������茳�C�ɂȂ����B�C�����������ĉ߂����₷���Ȃ����B ����"���̗������ԂɁA�����ɂ���������������"�Ɗ肤�B
���̒ʂ��Ă���e�j�X�X�N�[����8��12-18���̊ԋx�݂ł���B���܂�������Ƃ��o�����A�e�j�X���o�����A �������֏o�����邱�Ƃ��o�����A�g�̂��a���Ă��܂��B��d��������Ɖ�ɂ��܂��B����������āA �����V���c�𒅂āA�J�ɔG��āE�E�E��ςł���B
2021.8.2
�s�A�m�̔��\��
�����s�A�m���K���Ă���J���C���y�����ޗǎ�������Â̑�59�\���܂ƌS�R��z�[���ŊJ�Â��ꂽ�B ����7��31��18:00�J���̑�ܕ���"���̎]��"��e�����B�������痈�K���������̒������A7��29�ɗ\�肵�Ă��� �R���i���N�`���̓��ڐڎ��8���Q���ɉ������āA���̔��\��ɗ��Ă��ꂽ�B���Ȃ��u���ꂶ�Ⴀ�ꏏ�ɔq�����悤�v �Ƃ���ė����B�ȑO�ɒ����̒������s�A�m�̔��\��ɗ��Ă��ꂽ�ۂɂͤ�y����Y��āA���t�r���ŁA�ۏ����e�����Ƃ���Œf�O���� ���܂����B����́A�y���͖Y��Ȃ������B���̉��t�́A�r���������������Ȃ������A�܂��܂��E�E�E�B���͂�� ��肭�e���邱�Ƃ͂Ȃ��B�I�����s�b�N�œS�_�̓����q���I��ł����s���邱�Ƃ�����̂��E�E�E�B �u�̑��I��̂悤�ɋْ������v�ƌ�������A�����̒����́u�Ō�܂Œe�����Ƃ��o���ėǂ������v�Ƃق߂Ă��ꂽ�B
�����̒�����8��2���A�����w�̑�K�͐ڎ���ŃR���i���N�`���̓��ڐڎ����ƌ����ċA���čs�����B ���́A�����̒������u���̕����͗�[�������Ă��������v�ƌ����Ă��������Œ��Q�������B"�Ȃ�قlj��K"�ł������B
2021.7.29

�ɐ��R
�����̒������u������x�o�R���������v�ƌ������B�荠�ȎR�Ƃ��Ĉɐ��R��I�B7��29��9:00�ɎԂʼnƂ��o�āA 12:00�X�J�C�e���X���ԏ�(�W��1260m)�ɒ������B�Ă����B���o�R������o�肾�����B�������ɐ��R�A���R�A�� �͑����B�h���̊O�͎����Q��Ă��āA���R�A���͎��̐H�ׂȂ��킵���c���Ă��Ȃ��̂��ڂɕt�����B200m���o�� ����A�i���g�I���c�ɁI�n�ʂ��@��N������A���R�A�����Ռ`���Ȃ��Ȃ��Ă���I�H���r�炳��Ă���I�߂������i ��ڂɂ����I�h�����C���Ă����l�A�ꂪ�����B�q�˂�ƕČ��s�̐E���Ƃ̂��Ƃł������B�h���͂��Ⴟ�ȃv���X�`�b�N�� �x���ɖԂ������e���Ȃ��̂ł������B���͍������������A����ł������肵���h�������ׂ����Ǝv�����B �������������Ă��邱�Ƃ����ʼn��Ƃ����Ȃ�������Ȃ��ƒɊ������B
�h�삪���܂������Ă��鏊�ł́A�V���c�P�\�E�A���^�J���R�E�A�~���}�R�A�U�~���̔��������Ԕ����������B �ȑO�A�n�N�T���t�E���A�C�u�L�t�E������R�������Ƃ���͍r�炳��Đ�ŏ�Ԃł������B�R���̏����߂��Œ��H���� �܂����B�����̎�l�����R�A���̕ۑS�ɔM�S�ŁA�C�u�L�W���R�E�\�E�Ȃǂ͑����Ă����B�C�u�L�t�E���������Ă����B �E�̎ʐ^�͈ɐ��R�R��(�W��1377m)�ŁB
���o�R��(�����p)���������B�L���o�C�\�E�A�~���}�R�A�U�~�̌Q�����������B15:30���ԏ���o���A18:00�ޗǂ̎��� �ɋA�������B
2021.7.26

���P��
�����̒������u�o�R���������v�ƌ������B7��25���ɓo�R�C���A26��9:00�ɎԂʼnƂ��o�āA�r���ŐH�Ƃ��A 12:30���P�����ԏ�(�W��1574m)�ɒ������B�ċG�ɂ͒ʏ햞�t�̒��ԏ�̓K���ł������B�ō������o���x(�W��1695m) ��ڎw���ĕ����������B�R�}�h���̖����������Ă����B�ߔN�R�}�h���̐��������Ă���Ƃ����Ă������A����Ȃ���v�H �r���̐���Œ��H(�`�̗t���i�A�R�؊��A�ӉZ�ƃg�}�g)��ۂ����B14:00���o���x�R���ɒ�����(�E�̎ʐ^)�B�u�����������������v�ƌ����̂ŁA�������A���h�҂��o�Ē��ԏ�ɖ߂����B15:30���ԏ���o���A18:30�ޗǂ̎���ɋA�������B
2021.7.25
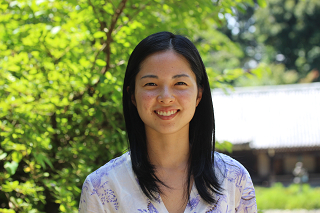
�����̒����̗��K
�����ɏZ�ޒ����̒������ޗǂ̉䂪�Ƃɂ���ė����B�ޏ��͕č��̃��V���g���B����w�Ŋw��ł������A�č��ŐV�^ �R���i�E�C���X�̊������g�債�͂��߂���N3���ɋA�����A�I�����C���Ŏ�u�����Ƃ����B���͏A���� ���Ă��āA�������ɓޗǂ֗V�тɗ��Ă��ꂽ�Ǝv���B�u���������A��\�肩?�v�Ɛq�˂���A�u7��29���Ƀ��N�`���̓��ڂ̐ڎ킪�\��o���Ă���̂�7��29���ɋA��v �ƌ������B���́u7��31���Ƀs�A�m�̔��\�����̂����ǁE�E�E����͎c�O!�v�ƌ������B���N�O�A�s�A�m�̔��\��� �ޏ������Ă��ꂽ���A���͊y����Y��ēr���Œe���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̃��x���W�̋@��Ǝv���Ă����̂��B
�E�E�E�Ƃ��낪�A�ޏ����u���N�`���̓��ڂ̐ڎ�̓���8��2���ɕς��Ă��炦���B8��2���ɓ����ɋA��̂ŁA �s�A�m�̔��\��ɍs����B�v�ƌ������B������ρI���x�͎��s����킯�ɂ͂����Ȃ��I�ْ�����Ȃ��I
�E�̎ʐ^�͏�ڗ����ŁB
2021.7.15

���N�f��
�����A�s�������猒�N�f���E���f�̎�M�[���X������Ă����B���͒�N�ސE��A���N4���ɐl�ԃh�b�N(����)����f ���Ă����̂ŁA���̌��N�f���E���f�������Ƃ͖��������B��N�ƍ��N�̓R���i�ЂŁA���͐l�ԃh�b�N����f���� �������B���낻��l�ԃh�b�N����f���悤���ȂƎv���Ă���Ƃ���ɁA���N�f���E���f�̎�M�[���X������Ă����B���͍l�����B���͂���9����80�˂ɂȂ�B�\���������������Ē������B�ȒP�Ȍ��N�f���E���f���邾���ŏ\���ł͂Ȃ����ƁB �ŁA�����A�a�@���N�f���E���f���ɍs�����B���̕a�@�A���܂Ől�ԃh�b�N����M���Ă����a�@�ł��邪�A���N3���A ���@���ҁE�a�@�X�^�b�t40���قǂ��V�^�R���i�E�C���X(Covid-19 infections)�Ɋ��������B���͓d�b���ċ��鋰�錟�f�ɍs�����B ���o�C�Ɗ�������A�낤�Ǝv���čs�����̂����A�������O�ꂵ�Ă���l�������̂ŁA���f�����B
�a�@�͈ӊO�ɁA�͂���Ă����B�X�^�b�t��100�l����Ǝv�����A���������Ɠ����Ă���ꂽ�B�����z�b�Ƃ����B ���t�����Ƒ咰���f�̌��ʂ�10����ɕ����邩��E�E�E�ƌ���ꂽ�B��t�������^�����ɓ��Ă����Ă���̂����� �u�S���t�ł���?�v�Ƃ�����������B�u�e�j�X�ł��v�Ƃ����Ɓu�ŋ߁A���˕a�ŋ~�}�Ԃʼn^��Ă���l�������ł����� �C��t���Ă��������v�ƌ���ꂽ�B
�E�̎ʐ^�́A�䂪�Ƃ̒�̘@�B���n�X�Ƒ����@�������ł���B

�u���[�x���[
�䂪�Ƃ̒�ɁA�u���[�x���[����������B���͎���̋G�߂ŁA������R�Ȃ��āA�}�����̏d�݂Ő��ꉺ�����Ă���B �n�������������Ă��āA���W���A�X�Y���A�q���h���A�C�\�q���h���������X�Ƃ���Ă���B�n�ʂɂ͑�R�̎����� ���Ă���B�~�J�̐���Ԃ����p���āA�����u���[�x���[�̎��n�����邱�Ƃɂ����B���̎��n��Ƃ͑�ςł���B �������A��Ɏh�����B���X�A�����������Ȃ̂����̒��ɕ��荞��ł��Ȃ��Ɛg�̂��������Ƃ������Ȃ��B �����̎��n��1kg�](�E�̎ʐ^)�B���ŐH�ׂ�̂�"���璼�ڂ����������Ƃɂ���"�A����ŃW��������邱�Ƃɂ����B �����ɋ��Ȃ�����Ă���"��������!��������!"�ƐH�ׂ��B�������|�낵��!"�����"�Ƃ����A��ɐA�����L���E���̎����傫���Ȃ���"�������n"�ƍs����"�J���X�ɐH�ׂ�ꂽ��" �Ƃ������Ƃ������B�J���X�̐H�Ƃ��s�����Ă���̂�? ���N�͎U�X�ł���B�����̓J���X�ɂƂ�ꂽ�B "�Ȃ�Ƃ��d�Ԃ������Ă�肽���̂����E�E�E"�ƍl����̂͗ǂ��Ȃ����H
2021.6.17

�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ����
6��16��20���ɓޗǎs�����ŐV�^�R���i�E�C���X���N�`���̓��ڐڎ�����B���ڂ͈��ڂ�� ����p���o��m���������Ƃ������Ƃł��������A���̏ꍇ�͉������������B"�N�����Ɣ������݂��Ȃ�A ���N�`���̌��ʂ����Ȃ�"�Ƃ������Ŋ��ŗǂ��킯�ł͂Ȃ����������A�܂������ɏI���܂����B�E�̎ʐ^�̓q������(�P�S��)
�Ă̖�́@�ɂ݂ɍ炯��@�P�S���́@�m�炦�ʗ��́@�ꂵ�����̂�
�唺���Y��(���t�W�@��8-1500)
2021.6.8
�~
�䂪�Ƃ̒�ɔ~�̑������B��N�͏\�������̂�Ȃ��������A���N�͑�L���30kg�]�̔~�� ���n���邱�Ƃ��o�����B�ł��A�ɓo������A�r���ɓo�����肵�Ď��n����̂ŁA�ɂ߂Ċ댯�� ����B��������Ȃ���̍�Ƃł���B����������A���ꂪ�Ōォ?�Ǝv���Ȃ���A�i���g�J���� �ɏI�������B���n�����~�͑唼�A�F�l�A�ߏ��̐l�ɂ�����Ă��������A�䂪�Ƃł́A2kg�� �~�W���[�X�A6kg��~�����A2kg��~�W���������̂Ɏg�p�����B�~���̍�����2012.8.22�̃u���O�ɋL�����B������Ę^����B
�����~���̍���
1) �V�N�Ȋ��n�~2kg�𐅂ŗǂ��A�w�^�����A�z�ЂŐ���@�����B���A�ňꒋ�� �����E�E�E�~���������F�ɕω�����B�ɂƂ���̂���~�͎�菜���B
2) 50cc�̃z���C�g���J�[���ǂ�Ԃ�ɓ���A�~������z���C�g���J�[�ɐZ������A�M�� ���ł����Е��e��ɓ����B��ʂɂ�������~������A�e����U�肩����B�~�E���E�~�E ���E�E�E�ƑS���Ђ���B�~2kg�ɑ��e��200g���g���B���͏�ɂȂ�قǑ��ڂɂ��A�Ō�Ɏc�� ������~�̏ォ���܂��B
3) �z���C�g���J�[200cc��Е��e��̒[���痬�����ށB
4) �d��(2kg)�Əd��(1kg)�����ĊW�����A���̓�����Ȃ����ʂ��̗ǂ��ꏊ�ŕ��u�B2,3������ �ƒЂ��`���オ���Ă��āA�~���S�ĒЂ��`�ɐZ����悤�ɂȂ�����A�d��(1kg)�����ɂ���B �Ђ��`��~�|�ƌĂԁB�������ĂP�T���قǕ��u������A���h��������B
5)�@�\�����Ɏ��g�F�ŏk�ꂪ�ׂ����V�N�Ȏ��h����ɓ����B�t������E�ݎ��A�����Ղ�� ���Ő����A���J�ɍ�������E�E�E����͂ƂĂ��d�v�B
6) ��������h(500g)�̐��C���Ƃ�A�e��50g���ӂ肩�����㋭�����ށB���݂��ނƃA�N�`���� �Ă���B���h���i���ăA�N�`���̂Ă���A����ɑe��50g���ӂ肩�����㋭������ŃA�N���o���B �A�N�͍i���Ď̂Ă�B�A�N����菜�����Ƃɂ��A�N�₩�ȍg�F�̔~����������B
7) ����ŃA�N����菜�������h��4)�ŏo�����~�|���������h���ق�������A4)�̔~�̏�ɉ����A �e����20g���ォ���T���B�d��(1kg)�����Ĕ~�E���h���S�Ĕ~�|�ɐZ����悤�ɂ���B�~�E ���h���S�Ĕ~�|�ɐZ�����Ă��邩����J�r�͐����Ȃ��B
8) �W�����A���̓�����Ȃ����ʂ��̗ǂ��ꏊ�ŕ��u�B�y�p�̓V�C�̗ǂ����ɔ~�����o�� ���Ɋ����B1-2����A�Е��e��̒�̂ق��ɂ������F�t���̈����~���A�Е��e��ɖ߂��A�~�|�E ���h�ɂ܂Ԃ��Đ����Ђ���(���̂Ƃ��͏d�͂���Ȃ�)�B�ēx�A�V�C�̗ǂ����ɔ~�����o���� �Ɋ����B
9) ���������āA�قǂ悭�����Ƃ�Ɗ��������~���ƂȂ�����A�Y��ȗe��ɓ���W�����ĕۑ�����B
10) ���h�͊������č��߂ӂ肩���ƂȂ�B�~�|�̓L���E���̉����݂ȂǂɓY�������� ���X���p�ł���B�܂��A�~�|�E���h��V���I�̔~�|�Ђ��Ɋ��p���邱�Ƃ��o����B
���́A�~�|�傳����t��500cc�̐��ɉ����A�X�|�[�c�h�����N�Ƃ��Ĉ������Ă��܂��B
2021.5.26

�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ����
5��26��20���ɓޗǎs�����ŐV�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ�\�o���Ă����̂ŁA���͗\�Ԃ�30���O�ɎԂʼnƂ��o�āA 20���O�ɐڎ���ɒ������B�T���ő҂���1���ŁA�\�f�[���o���\�f�����B�����ŁA�ڎ�ׂ̈ɕ��B�ڎ�̈�t�� 5�l�ł������B��1���Őڎ�̏��Ԃ������B���͔����|���V���c�ōs�����B����グ�āA���Ƙr�̋��E��������A���R�[������ ���Ē��ˁB�����Ƃ����ԂɏI�����B�ɂ��Ǝv���Ԃ��Ȃ�����(���ہA�������ɂ��Ȃ�����)�B���̌�A�o�ߊώ@��15���ԁA�o�� �ώ@���̎w��Ȃō����Ă����B���̊ԂɁA���ڐڎ�̗\��E���ӎ����`�B���������B�@���Ȃ�ُ�������A20��15���Ԃ� �^�]���Ď���ɋA�������B���̃V�X�e���A�ƂĂ��ǂ��ł��Ă���Ǝv�����B����Ȃ�A�J�ƈ�ł���Ă��炤���������ǂ��Ǝv���܂����B
�E�̎ʐ^�̓|�s�[�B�C�M���X�ł�5��8����VE Day(����E��탈�[���b�p�폟�L�O��)�ɁA�����̐l���|�s�[�̉Ԃ����ɏ����� ���܂����B
2021.5.19
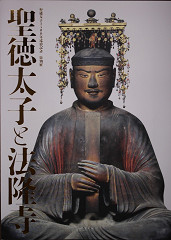
���ʓW�u�������q�Ɩ@�����v
�ޗǍ��������قŐ������q��1400�N�������L�O���āA���ʓW�u�������q�Ɩ@�����v���J�Â���Ă���B�J�͗l�ł������̂ŁA �O�͕����Â炢�������ق͂����Ă��邾�낤�Ɨ\�z���ďo�����čs�����B���O�\�D�恄�ł��������A�������œ��ق��� ���Ƃ��o�����B�悸�A���_���炢���Ɓu�\�z���Ă����ȏ�ɗǂ������v�B���͖@�����͑�D���ʼn��x���K��Ă��邵�A�@�����F�̉�̉���� ������B�R��ɁA�ƂĂ��ǂ������B �W���̎d�����ǂ��āA�Ⴆ�A�����͖@���������𐳖ʂ���q�ς��Ă���̂����ǁA�܂�œ��w�ɓ���Ă������������̗l�ɁA ��t�@�������A�l�V������?�����V�E�L�ړV�A�lj�(�͖{)��q���邱�Ƃ��o�����B���ɁA��t�@�������́A���̂���܂ł̈�ۂƂ� ��ψقȂ��Ă��āu���ɐl�ԓI�Őe���݈Ղ��v�������̂ɂ͋����܂����B���̑�����A�����O�����`�łĂ��Ă���A�g�߂� �q�ς��邱�Ƃ��o���܂����B
�����͕a�Ŕq����Z�ω����Z�̂��X�ɓW�����Ă����āA�O�㍶�E����Ԃ��ɔq�ς��邱�Ƃ��o���܂����B
�d���ɂ���Y�����X�ɓW�����Ă���g�߂ɔq�ς��邱�Ƃ��o���܂����B
"�������q��1400�N�������L�O����"�̂��ƂŁA����@�Ɉ��u����Ă��ĕ��i�͔q�ς��邱�Ƃ̏o���Ȃ��������q���⎘�ґ����� �q�Ϗo�����B�����Ė@�������@�G�a�̓��ǂ������Ă��āA���͓������������ُ����ł���A10�ʂ���Ȃ錻���ŌÂ̐������q�� �`�L�G���q���邱�Ƃ��o�����B
�����ɏq�ׂ��̂͂����ꕔ�ł��B�f���炵���W����ł��B�ޗǍ��������قł�6��20���܂ŁA�������������ق�7��13������9��5���܂� �J�Â����悤�ł��B���́A�ޗǍ��������قōēx�ϗ������Ă��������܂��B(�E�̎ʐ^�͐}�^�̕\��)
2021.5.17

�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ�
�V�^�R���i�E�C���X(Covid-19 infections)�͐��E�I�ȑ嗬�s�ɂ��r��Ȕ�Q���y�ڂ��Ă���B�������������ɂ� �A���j�I�Ȋ����Ǎ����̌o������킩��悤�ɁA�D�ꂽ���N�`���̊J���E�ڎ킪�K�{�ł���Ǝv���܂��B�č��̑哝�� �ƂȂ����o�C�f������́A���������č����Ƀ��N�`���̐ڎ������ʂ������Ă�����l���B�䂪���̎� "���N�`���̐ڎ�"�̏d�v���������ł����l�ł���B�ޗǂł�75�ˈȏ�̌������҂ɑ���"���N�`���̐ڎ�"���n�܂����B5��10���ɐڎ�\�J�n���ꂽ��10�����ŗ\�萔 ���I�[�o�[���Ă��܂��A���͗\��ł��Ȃ������B���̌�A���N�`���m�ۂ��ł����̂��A����5��17���ɐڎ�\�ĊJ���ꂽ�B ����́A�e�ʂ���R�����āA�����\�邱�Ƃ��ł����B5��26��20���ɓޗǎs�����Őڎ킪���邱�ƂɂȂ����B
�E�̎ʐ^�́A�I�i�K�A�Q�n�B�I�_�}�L�̖����z���Ă���B�ŋ߁A�䂪�Ƃ̒�ɗ��āA�D��ɔ��Ă��Ă���B
2021.5.3

���@�L�O��
5��3���͌��@�L�O���ł���B���́u���݂̓��{�����@��厖�ɂ����炵�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v �ƍl���܂��B���A�N����Ɖ����ł������B���́u�����͋v���Ԃ�ɍ����R�ɓo��v�Ɛ錾�����B4������Ɏ���80�˂ɂȂ�B ���Ȃ�̗͂������āu�W��1248m�̍����R�̎R���܂ōs����v�A�u���̂����ɓo���Ă������v�Ƃ����킯�ł���B 9:20���A���ȂɁu���ꂩ�獂���R�ɍs���Ă���B�Ƃ���ŁA���O���s�����H�v�Ɛ����������B�\�z�ɔ����� �u�����s���v�ƌ������B�ŋ߂̗̑͂����Ă����"�ƂĂ�����"�Ǝv���Ă����̂ɁE�E�E�B�u�܂��������B �����������āA������Ƃ��܂ōs���Ĉ����Ԃ����v�Ǝv�����B���Ȃ̏����Ɏ�Ԏ���āA10:00�ɎԂʼnƂ��o���B �r���̓p�c��̃A�O���[�}�[�g�ŁA���H�p�Ɋ`�̗t���i�Ƒ��݂����B12:00������(�W��804m)�̒��ԏ�� �������B�o�R�C�𗚂��A��������A�H�ƁE�����E�\���̈ߗ����ꂽ�����b�N�T�b�N��S���ŁA�o�R���J�n�����B 12:25�ɓr���̓W�]��(�W��1030m)�ɒ������B����"�W�]���܂ōs���Ώ�o��"�Ǝv���Ă����̂ɁA���Ȃ́u�܂��o��v �ƌ������B�i���g!�A13:30�����R�̎R���ɒ������B��C������ł��Ē��]�ǍD��"�x�m�R����ԎR��������"�Ǝv���� (�E�̎ʐ^)�B�����ɒT��������������Ō����Ȃ������B�߂��ɂ����o�R�҂��u�~�̑����Ȃ猩���邱�Ƃ�����܂��v �Ƃ��̏ꏊ�������ĉ�������(�E�̎ʐ^�̒��ɂ���܂�)�B���������Ă��Ċ����̂ŁA���H��ۂ�����A14:00�������R�� �͂��߂��B�����A���̉��R����ςł������B���Ȃ̓o�����X�����ɂ����l��"�������A�T�d��!"�Ɖ��R�����B 15:30�������̒��ԏ�ɖ����������B
�������X�~�����R���邱�Ƃ��o�����B����"�t���g�X�~��"�́A���ɂƂ��ď����Ŋ����������B
17:00�ޗǂ̎���ɖ����A���B����ɂ��Ă�"���Ȃ��ǂ�������"�̂ɂ͋V�����B
2021.4.28

�ᑐ�R
�ޗnj����V�^�R���i(Covid-19 infections)�̊����҂������Ă���A�R��ɓޗnj��m���́A���A���ɁA���s�̗l�� �ً}���Ԑ錾�����Ȃ��B�ޗǎs���͐l�o�������Ă���B�ł��A�ƂɈ����������Ă��Ă͐g�̂��݂�B����Ȏ��A���� �o���邾���l�̍s���Ȃ��Ƃ���s���āA�̂������Ƃɂ��Ă���B4��26���͉����ŋ�C������ł����B"�����A�ǂ����傤��"�ƁA�O�ɏo�Ďᑐ�R�߂��"�R��ɐl�e������"�E�E�E �ŁA���͎ᑐ�R�ɓo�邱�Ƃɂ����B���Ȃ�U������u��l�łǂ����v�ƁB���Ȃ��ŋߖڗ����đ̗͂������Ă����B �o���邾���������悤�Ƃ���̂����ǁE�E�E�B
14:00�ɉƂ��o�āA�啧�a���A���A����R�_�Ђ��o�āA�ᑐ�R�o�R����150�~�����ē��R�B�ᑐ�R�͎O�̃s�[�N ����Ȃ��Ă��āA���ꂼ���d�A��d�A�O�d�̃s�[�N�ƌĂ�ł���B��d�̃s�[�N�ɂ͎��̑��ɂ͈�l�����A ��d�̃s�[�N�ɂ͎��̑��ɂ͎O�l�����A�O�d�̃s�[�N�ɂ͎��̑��ɂ͏\�l���x�ł������B15:10�������ˌÕ��ɒ������B �W��342m�B�䂪�Ƃ̕W����80m������A���悢�^���ɂȂ�B
���̓��͋�C������ł��ēW�]���������B���A���A�����A����A���A����A�Z�b�A�����A��b�̎R�X���ς邱�Ƃ� �o�����B���ォ��ς�"�啧�a�����̌i�F"�̎ʐ^�������B�����̎R������R�ŁA���̉E�����Z�b�R�ł��B
���̌�́A���R�V�����A�������A�ᑐ�R�o�R�����A����R�_�ЁA���A�啧�a�����o��17:00�A����B����15,148�B
�Γ�Ԃ̉Ԃ��ς邱�Ƃɂ͑������ȁE�E�E�Ǝv���čs�����̂����ǁA�J�Ԃ��n�܂��Ă���(�E�̎ʐ^)�B �ƂĂ��F�������ǂ��A�V�ƃ}�b�`���Ĕ������A���\�����Ă����������B�����c�O�������̂́A�ȑO�A�������� �������������\��ʊω���F����(���� ��������O��)�Ǝ߉ޔ@������(���� ��������O��)���V�݂��ꂽ�a�� �ڂ���Ă��āA���� �߉ޔ@������(���� ��������O��), ��t�@�������E�����F����(�d�v������ ��������), �\��_������(6�� �d�v������ ���q����)�����ɂȂ��Ă����B
���̌�A������q�ςɍs�����B�����̋߂��ɃC���J�K�~�������Ă������o���Ă��āA�߂��Œ��߂邱�Ƃ͏o���Ȃ������B �Ō�ɁA���������_�ЂɎQ�q���ċA�H�ɂ��A17:15�ޗǂ̎���ɋA�������B
2021.4.3
�@�̐A�ւ�
�@�̐A�ւ��������B1. �Â��@�̔����Ђ�����Ԃ��A�@����V���ɂ߂Ȃ��悤��20cm�Ő藎�Ƃ����B��̔����琔�{�̂��B
2. ����A��������̖���������t�A���������엿��E�܂݂��ɓ���A���̏�ɓc�y��5cm������B
3. �o���邾��������20cm�̘@�����{�A�V���ɂ߂Ȃ��悤���ׂ�B
4. �@���̎���ɓc�y�A2�N�O�̗p�y(����ɂ��Ă͌�q����)��u���A10cm������B
5. ���ɂ������Ɛ��𒍂��B���t�ɂȂ�����ォ��ԋʓy���p���p���ƎT���A�c�y�̕\�ʂ������Ȃ�����B
��������ł�����A���_�J������B���̑w��10cm���͂ق����B
2�N�O�̗p�y�̍���
�@�������o������A�Â��y�����o���B����ɍ�������̖�����K���ʍ�������A�܋l�߂ɂ��� ��N�ԕۑ��B
�����炿��@���̂��������́@���ނ���Ł@����ɂ����ʁ@�䂫���ӂ肯��
�I�єV (�E��a�̏W)
2021.3.30

�R���i�Б�l�g
���ł̓R���i�Б�l�g���J�n�������ł���B���̉Ƃ���1km���̏��ɂ���a�@�ŃN���X�^�[(�W�c����)���������A �����̐V���ɂ��A28���������A�ʂ̕a�C�œ��@���Ă�������2�����R���i�Ɋ������Ď��S�����Ƃ̂��Ƃł���B ������80%�����N�`���̐ڎ�������A�R���i�Ђ͒��ÂɌ������Ƃ̂��Ƃł���B�������N�`���̐ڎ���J�n���� �ق����Ǝ��͑Җ]���Ă���B�ޗǂ͊w�Z���x�݂ɂȂ����e����?�ό��q�����債�Ă��Ă���B���͓ޗǍx�O�ɍs���̂��ǂ��ƁA����͎������� ��쎛�֍s�����B�}����������J�ł��������A��쎛�����͐��l�̔q�ώ҂ŁA�ՎU�Ƃ��Ă����B �������A ���ŗL���ȓޗnj��̖^���ŁA���l���u�����̏�ł�����A���̌����͂��������������v�ƊŔ𗧂Ă��� ������l�ł��B �����S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���������́@���ق݂�тƂ́@���Ƃ܂����@�����炩�����ā@���ӂ����炵��
�R�ӐԐl (�V�Í��a�̏W)
2021.3.15

���萁��
�ޗǓ��厛���̂����������������s�B���厛�啧�a��������֍s���������ɗ��h�Ȃ������������܂��B ���̖����萁���Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B�V�������ł��ˁB�͂邭��@�������Ȃ��Ɂ@�܂�ӂ��Ƃ́@���������T��Ɂ@���ɂ��邩��
�I�єV(�Í��a�̏W)
2021.3.1

����R
�V�C���ǂ��g�������̂ŁA���H��A�v���Ԃ��"����R�ɓo�낤"�Əo�����čs�����B�ޗǂ̉䂪�Ƃ��獁��R�܂� �ԂŖ�ꎞ�Ԃł���B14:00����R�������ԏ�ɒ������B�@ ����R�͕W����152m�B�V����R�Ƃ��Ă�邱�̎R�́h�_���V�~��R�h�Ƃ���A�w�Î��L�x�ɂ܂��ÎЂ� �������������܂��B�����b�N�T�b�N�ɐ����ƃJ���������č���R�̕��֕����čs�����B�R��ւ̓o����� ���t�̔肪�����Ă����B���̈���S�l���ł��m����u�t�߂��ā@�ė���炵�@�����ւ́@�ߊ�������@�V�̍���R�v �i�����V�c�@���t�W���P�@�Q�W�j�B
��������o�炸�A�E���ւ̎U���H��i��ŁA���̓V��ː_�Ђ֍s�����B�_�a���Ȃ��A�ʊ_���ɗ��h�Ȓ|�������Ă��āA ���̒��ɋ��S����Ȃ�⌊������"�V�Ƒ�_����������ɂȂ������"�Ƃ̂��ƂŁA�⌊����_�̂Ƃ��� �V�Ƒ�_���J���Ă������B
����ɉE���i�݁A����R�R��ւ̓o�R��������čs�����B�R���ɂ͏�m��O(�C�U�i�L���J��)�A���m��O(�C�U�i�~���J��)�� �������B�R���ɂ͓V�n�̍����_���J�鍑�헧�i���ɂƂ������j�_�Ђ��������B���ォ��ς����T�R�����̎ʐ^���E�Ɏ����B
����ɕ����āA���̗�(����3.7m�A����1.4m�A��1.9m�̎��R�ŁA�����ɕ�40cm�̗��ڂ���)�܂Ői�݁A�����߂��Ėk�i���A �V���v�R�̖k���̓V���R�_��(�_�a�w��ɂ���ԛ���̋��₪������)�ɎQ�q�����B����ɉE���ɐi�ނƁA�ŏ��ɂ݂� ���t�̔�̏��ɖ߂����B
16:00����R�������ԏ���o���A17:00�ޗǂ̎���ɒ������B����9989�B
��a�ɂ͌Q�R����� �Ƃ���ӓV�̍���R�o�藧�� �����������
�����͉��������� �C���͉��������� ���܂�������x����a�̍���
���t�W�@��1-2 �����V�c
2021.2.25

�������~��
���N�K��Ă��錎�����~�т֍s�����B���̉Ƃ���ԂŖ�40���ōs����B13:00�u�ΔȂ̗��������v�ɓ����A ���c�H���ł��˂��ǂ��H�ׂ��B�H��A�߂��̔�������n��A�O�c�Ή��n���U��B�~�͌ܕ��炫�B ���̌�u���}���g�s�A�������v�֍s�����B��N���Ɗٓ��̘F�[�ŁA���݂�ő����Ă��ĐH�ׂ���̂����ǁA ���N�̓R���i�ЂŒ��~�B�يO�̉Δ��ŖH�݂��Ă��ĐH�ׂ��B���̌�A�V�_�~�сA���Y�~�сA��ڔ��i�A�^���� �Ƃ����ϔ~�R�[�X���U���B�~��3-5���炫�A�ϔ~�҂͗�N�̖�30%�ł������B���݂Ȃ�Ł@����ɂ��݂��ށ@�ނ߂̂͂ȁ@��������������@����ЂƂ�����
�I�F�� (�Í��a�̏W)
2021.2.21

�t�̖K��
�������������Ȃ��Ă��āA�ޗǂ̍����̍ō��C����20���ł����B�����A�䂪�Ƃ̒�ɗ�����̓z�[�z�P�L���� �����K�����Ă��܂����B�䂪�Ƃ̒�ł́A���E�o�C�A�ցA�T���V���E���炢�Ă��܂��B�Z�c�u���\�E�̉Ԃ� �U�����A�Z���o�I�E�����A������(�E�̎ʐ^)���Ԑ���ŁA��X�̉Ԃ��߂���������܂��B����A�ޗǂ̍x�O�̓c�ɓ�������Ă�����A���t�̉ԁA�I�I�C�k�m�t�O���A�n�R�ׁA�^�l�c�P�o�i�ɉ����āA �^���|�|�A�X�~���A�J���X�m�G���h�E���X�̉Ԃ��ς邱�Ƃ��o���܂����B�쑐�̎ʐ^���B���āA���̖��O�ׂ� ����ƁA���\�y�����B�쓹������y���݂������܂��B
���������A�{�i�I�ȏt�ɂȂ�܂��ˁB�R���i�ЂŒ��݂����ȋC�������ꐰ��Ƃ��Ă��܂��B
�͂邽�Ɓ@���ӂ���ɂ�@�݂悵�̂́@��܂������݂ā@���ӂ݂͂���
�@�p������ (�E��a�̏W�@�����@�t)
�@
2021.2.12

����(�Ƃ���)
���H��A���������͉�������������Ȃƍl�����B����͓��A����R�_�ЁA�t����A�ۑ��~���A�V�_�ЁA ��_�ЁA�������ƕ������B�����͎s�O�ցB�Ԃ�15���قǁB�����̊�D���ɒ������B���ԏ�ɎԂ��߁A ��D���֔q�ςɍs�����B�{���ɓ����Ď����}�X�N�𒅗p�����̂����āA�Z�E������}�X�N�𒅗p�� �u�R���i�ЂŁA�q�ώ҂��w�ǖ�����������܂��̂ɁA�悭���Q�肭�������܂����v�ƌ����Ă���A ����l�ׂ̈ɁA�Ƃ��Ƃ��Ɛ������ĉ��������B�{������ɔ@�������A���̎���Ɏ����V(��)�A�����V(��)�A �L�ړV(��)�A�����V(�k)�����A�w��ɎO�d�����ڂ����Ƃ���������F�R�ۑ������J�肵�Ă������B ���������ƁA�뉀�����U����A�����̎R�ɂ���L����܂ōs�����B��R�邪��]�ł����B �E�̎ʐ^�́A���q���㌚���̏\�O�d�Γ��B�������������ƃp���t���b�g"�����̐Ε�"����ɁA�쓹�E�R�����U����A���ԏ�ɖ߂����B���̊ԁA �N�ɂ����Ȃ������B
���ɂ����Ɂ@�Ƃ��邱�ق�́@�Ђ܂��ƂɁ@�������Â�Ȃ݂�@�͂�̂͂͂�
������ (��)
2021.2.1

�ߕ�
�������A�����͐ߕ��ł��ˁB124�N�Ԃ��2��2�����ߕ����ƁE�E�E�B��̃Z�c�u���\�E(�ߕ����@�E�̎ʐ^)�� ����A�J�Ԃ��܂����B���N�A�ߕ��ɂ͉����Ԃ��炩���Ă���܂��B���a1-2cm�̏����ȉԂŁA�F���n���ŁA�悭 ���Ȃ��ƋC���t���܂��A���݂��ݒ��߂�ƋC�i����������Ԃł��B���Ăɂ͎p�������A��s���n���Ɏc��A 1���Ɋ���o���܂��B�͂邽�Ɓ@���ӂ���ɂ�@�݂悵�̂́@��܂������݂ā@�����݂͂���
�@�p������ (�E��a�̏W�@�����@�t)�@
2021.1.23

���N�`��
�č��ł̓o�C�f�����߂ł����哝�̂ɏA�C�Ȃ����܂����B�V�^�R���i��Ƃ��āA���N�`���̐ڎ� �ɗ͂𒍂��ł����܂��B�����A�V�^�R���i������������ɂ́A�D�ꂽ���N�`���̊J���E�ڎ킵�������� �v���܂��B�Ȋw�I�ɍl���āu���N�`���̐ڎ킪�����̓��v���Ǝv���܂��B���́u�v���ȑΉ��v������� ���܂��B���{�ł��u���N�`���̊J���̐��������Ə[��������v�K�v������Ǝv���܂��B���̗l�Ȗ��� �����A�V���ɋN���蓾��̂ł�����E�E�E�B�U���Łu�ۑ��~���v��ʂ�����A���~���炢�Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B���̖ɂ́A�؎D�u�ޗNjC�ۑ�ώ@ ���v���t���Ă��܂����B
�킪�����Ɂ@�݂��ނƂ����Ђ��@�ނ߂̂͂ȁ@����Ƃ��݂����@�䂫�̂ӂ���
�R���Ԑl (���t�W�@��8��1426)
2021.1.12

�ޗǂɐ�
�����A�N������Ⴊ�~���Ă����B���H���ς܂��ƁA�J��������ɁA���C�𗚂��ďo�����čs�����B ���厛�Ă�����A�啧�r�֍s�����B�J��������ɂ�����q�����l�������������B�啧�a�� ������̕��i��ōs�����B�啧�a�ł̓njo���I�����m���A���V�A����̂ɏo������B �C���h�ւ��ꏏ�ɗ��������Ē������m�ŁA�ʐ^���B�点�Ă����������B���ɎQ�q���āA�Βi ������Ƃ��A�낤���]�|���������B��邵���͊���₷���B�R���N���[�g�̓���I��ŁA �啧�a���ʂ̕��֍~��čs�����B�啧�a�O�̋��r�������啧�a���ς��ʐ^���E�Ɏ����B ���r�ɕX���͂��ĐႪ�ς����Ă����B���̌�A���傩���Ζ�A�ۑ��~�����畂�䓰�ւƐi��� �s�����B���䓰����̓��ɎԂ��߂Ďʐ^���B���Ă���l����R�������������B�����x�@���� ����Ă��āA���X�Ɓu���Ԉᔽ�v�̐ؕ����Ă����B�����ŁA���������牎��r�֍s�����B ���̌�}�X�N�����āA���X�X���A����ɋA�����B����10587�B2021.1.9

����
�g�����v�č��哝�̂��A�ߌ��h������č���c�����ɗ���������ȂNj��l�̐U�镑�������āA���E�����������ꂳ���� ���܂��B�悭���č��l�̉ߔ����o�C�f������������哝�̂ɑI�Ǝv���܂��B�č��Љ�̉��P�E�i�������҂������� �v���܂��B���āA���{�ł��B�V�^�R���i(Covid-19 infections)�̊����҂��}�����Ă��܂��ˁB���N�`���̊J���E�ڎ킪�Ԃɍ���Ȃ� ��������܂���ˁB�l�Ƃ��Ă�"�������X�N���o���邾���������"�l�ɂ��邵������܂���B�ł��A���C�Ȃ�A�Ƃł��� �Ƃ��Ă���킯�ɂ������܂���B���́A�o���邾���l��������������ăE�I�[�L���O�B���O�ł̃e�j�X�B�c�ɓ��̎U��B �E�E�E�ŏ��肽���ƍl���Ă���̂ł����E�E�E�B
�������ޗǂ��C����������A���~��Ԃ̊����ƂȂ��Ă��܂��B����Ȏ��A���N������A��ɏo�ăV���o�V��(�V�\�Ȃ̑��N���ŁA �͂ꂽ�s�̓��ǂɐ����z���グ���A�X�_���ɂȂ�ƌs���瑚�����o����)���ςɂ����܂��B�����͌����ŁA�����ȑ��� (����)���o���Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B
2021.1.3
����
1��2���@�s�A�m�̒e���n�߂̌�A�����߂ɔʎ�S�o���������B��N�̂Ɣ�ׂđ債���i���͂Ȃ��E�E�E���܂��������B �������ɎU���B�啧�a��������A�t�����n���o�āA�ۑ��~���ցB���~�̑����̂��`���z���炢�Ă����B�Љ��A������ ���o�āA���������X�X���o�ċA��B8181���B1��3���@�����̐�����������A�C���^�[�l�b�g��"�`�̖̙�����@"������ׂ��B���H��A�`�̖̙���������B ���̌�A�H�p�����ɍs�����B���w�̐l�B�����Ȃ��Ƃ͂����A���\�����B�R���i�������x�������A�܂�����ق� �[���ɂ͎v���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B
����ɂ��Ă��A���{�̃R���i���N�`���̊J���͉����܂Ői��ł���̂��낤���B�D�ꂽ���N�`���̊J�����ً}�̉ۑ�ŁA �W�҂͑S�͂Ŏ��g��ł�����Ǝv�����E�E�E�B"���Ƃ̑��͂������Ď��g�ނׂ��ۑ�"�Ǝv���B���̓��N�`���� ���؎����ɎQ�����Ă��ǂ��Ǝv���Ă��܂��B
2021.1.1

2021�N���U
�V�N���߂łƂ��������܂��B�F�l�̂����K�����F��\���グ�܂��B���N����낵�����肢���܂��B�V�^�R���i(Covid-19 infections)�̊����҂��A���{�ł܂����債����܂��B���͂��̐����͎��l���A �P��̏��w���A���n:���ւ̋A�Ȃ����� Stay at home �ɓO����\��ł��B���ȂƎ��̓�l�����ŁA ���G��(�卪�E���������Đ����������X�`�ɏĂ��݂�����)�����������܂����B
�E�̎ʐ^�͍P��̉䂪�Ƃ̏��̊ԁB�Ԋ�͓��厛�̌ÍށB�Ԃ�HK���B�|�����͉��t���쐽���搶�̍�i: �@�@��l�M�ɂ��"�얳����ɕ�"�����搶���T���X�N���b�g�����E�o�T�ŕ����яオ��l�ɏ����ꂽ�B
���͌���79.3�˂ł��B�����Ă���A����9����80�˂ɂȂ�܂��B��N�̓R���i�������x�����āA�l�ԃh�b�N ��f���܂���ł������A���A�l�ŁA���݂Ȃ�̖�����ނ��Ƃ������A���C�ɉ߂������Ă��������Ă���܂��B �Ƃ��Ă�����ȃs�A�m�Ə�������B���Ȃ��K�����y����ł��܂��B�̗͂��Α����ɘV�����Ă��܂����A ���������ƂɁA�܂��e�j�X�����邱�Ƃ��o���A�T2�E3��e�j�X���y����ł��܂��B���N�ێ��ׂ̈ɂP��8000�� �̃E�I�[�L���O��S�����Ă��܂��B�����A������A���_���ɂȂ邩������܂��A���̍K���̏�Ԃ����� ���Ƃ��F�O���Ă��܂��B
2020.12.29

�N��
���N�����Ɠ�������ƂȂ����B�R���i�ЂŎ��l�����ł���B�����͐Â��ɉƂ��Ă�A�����ɂ��s���Ȃ� �\��ł���B����ŁA�����p�̔��������قڊ����������A�Ƃ̑|���E���@���������A���ւ̔��Ɋ`�a ��h�������Ƃ��I�����B�����p�̉Ԃ����������A��������t�����B���N�͑��ڂɁA���������͏o�����B���āA�S�Ċ��������牽�����邩�B�e�j�X�X�N�[����1��5�����炾�B�g�̂����K�v������B�l���݂�����āA ���������Ȃ��B���̐��̒J��o���čs�����B�N�����Ȃ�����o���Ă����Ɓu���{�����w����j��Y:���ޗǎs �����{�݁v�Ƃ����̂ɏo������B���߂ēޗǎs���ɔz���������������̎{�݂炵���B����ɓo���Ă����Ɓu �E�͎ᑐ�R�E���͎O�}���v�ɏo���B���͍��i�B�h���C�u�E�F�C�ɏo���B�u���s�֎~�v�ł���B ���͖������ĉ����čs�����B�b������Ɓu�ޗǎs���W�]���v�ɏo���B�X�}�z�����o���Ďʐ^���B����(�E�̎ʐ^)�B �啧�a�E�������̌d���E�����ɂ͓��R�E����R�E�����R���������B��������R���ɓ����Đi�ނƑ啧�a���ɏo���B
2020.12.19
�䂪�Ƃ̑��z�����d
�����̌������̂��_�@�ɉ䂪�Ƃł͑��z�����d���u�������B�ݒu���Ă���5�N�Ԃ̃f�[�^�� 2016.5.19�̃u���O�ɋL�ڂ����B���̐��\�ɖ��������̂ŁA�䂪�ƂŎg���d�͂̑S�Ăz�����d�� �܂��Ȃ����ƁA2016�N9���ɑ��z�����d���u�݂����B2017, 2018, 2019, 2020�N�̌��ʃf�[�^�� �L�ڂ���(��:12���͑O�N�̂���)�B���ʑ��z�����d�ʂ�}1�ɁA���ʓd�͏���ʂ�}2�Ɏ����B���̂P�N�Ԃ�
�����z�����d�ʂ�6279kWh(2019�N��6434kWh,2018�N��6795kWh,2017�N��6455kWh)�ł������B
���d�͏���ʂ�8151kWh(2019�N��7620kWh,2018�N��7900kWh,2017�N��7133kWh)�ł������B
�䂪�Ƃ̓I�[���d���ŁA��g�[�E�����E���C�E�Ɠd�E�Ɩ��S�ēd�C�ł���B"�S�d�͏���ʂz�����d�� �܂��Ȃ�"�Ƃ����ړI�͒B�����Ă��Ȃ����A�܂��܂��ł���B
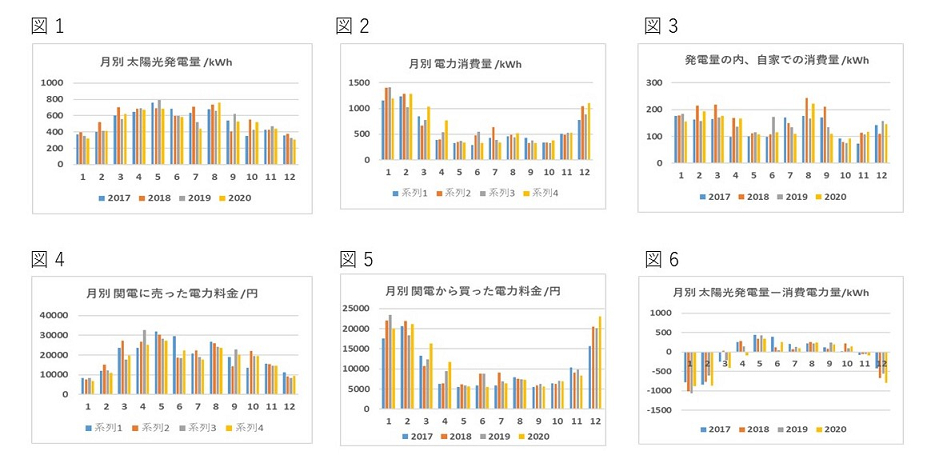
���z�����d�ʂ̓��A���d���ɉ䂪�Ƃŏ����d�͂͑��z�����d�̓d�͂��g�p����B���̗ʂ�}3�Ɏ����B �c����֓d�ɔ���B���ʂ̊֓d�ɔ������d�̗͂�����}4�Ɏ����B���d���ł�����Ȃ������Ɣ��d�̖������� �g�p�d�͂͊֓d���甃���B���ʂ̊֓d�Ɏx������������}5�Ɏ����B
�֓d�ɔ������d�̗͂�����: 2020�N��217,296�~(2019�N��226,272�~�C20018�N��235,296�~�C2017�N��235,728�~)
�֓d���甃�����d�̗͂���: 2020�N��137,840�~(2019�N��135,800�~�C20018�N��134,368�~�C2017�N��120,812�~)�ł������B
�Œ艿�i���搧�x�̌_���10�N�Ԃł���̂ŁA2021�N5���Ō_����Ԃ��I������B���̌�͔��d���i�������Ȃ�̂ŁA �����������̉������80%�ʂ��낤�B�ł�"���d���\�̒ቺ���قƂ�ǂȂ�"���Ƃ͋����ł���B
���������ł́A10�N�����Ă��u���q�F�̊O�ɂ���R���v�[������A�g�p�ς݊j�R�������o�����ĂȂ��B ���q�F�����̏��u�͌��ʂ��������Ă��Ȃ��v�B�댯�ȏ�Ԃ����������Ă��܂��B
�����̌������̂̒���ɁA�䂪�Ƃ̑��z�����d�V�X�e����ݒu�����B���̌��ʁA���z�����d���u���D����̂ł��� ���Ƃ��������邱�Ƃ��ł����B�u�댯�Ȍ��q�͔��d����߂āA�Đ��\�Ȏ��R�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ɐ�ւ���v �ׂ����ƍl���܂��B
2020.12.10

��䉷��
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��V�K�����Ґ����܂������Ă��܂��ˁB����Ȏ��ɕs�ސT�ł͂��邪�A�P�����ȏ�O�ɗ\�� �����̂ŁA�o�����čs�����B9��10:15�ɎԂʼnƂ��o���B�r���A���掩���ԓ������̓��̉w"������������͂�"�Łu�R������v�Ɓu�����`�v�� �����A�x���`�ŐH�ׂ��B
14:15����s�̌ΎR�r�����ɒ������B�ΎR�r�͒r�Ƃ������Ɗ����ŁA�L��ł������B �L���N���n�W���A�q�h���K���A�z�V�n�W���A�E�E�E�̃J���ނ���R�����B�~�T�S(����߂��)���O�H������ł����B ����"���Ԕ��]�[��"���U���B�u���R���Ή������v�Ƃ��Đv�A�ێ�����Ă���l�ŁA���̑f���炵���ɖ������ꂽ�B
16:30��䉷���䉮�ɒ������B����9��ڂ̏h���ł���B�����A����ɓ������B��䉮�̉����͌Õ��ŏ������A ����"���C�ɓ���"�ł���B��������ł���B
18:00����[�H"�J�j�Â���"�B�u�ǂ����̂�K�ʂɁE�E�E�v�ŁA������"�J�j�Â���"�͐�i�ł���B
20:30 ����ɓ�������A�A���B
10�������̌�A8:00���H�B9:20�`�F�b�N�A�E�g�BGoTo�L�����y�[���ƒn��N�[�|���ŗ����͔��z�B����ɁAGoTo�n��N�[�|���� ��12,000�~�B����Ȃ��ƂɁA�ŋ����g�����Ƃɔ������u�������̂͂�����Ƃ��v�ƁB�A�蓹�́u���̉w�v�ŁA GoTo�n��N�[�|�������g�������B14:00�ޗǂ̎���ɋA�������B�����A�b���͋ސT�B
2020.12.4
�r���͂���
�����A12���ł���B�ŋ߁A�r���͂����������B���N�O�܂ł́u���ꂪ���E�v�̒m�点�������������A ���̔N��ɂȂ�ƁA���������搶���͑唼�����E����Ă��āA������̗F�l�₻�̔������]�� �͂��悤�ɂȂ����B�O�������搶���̑��E��"��܂��ƖڕW��������"�l�ȑr�������傫���B ��y��F�l�̑��E��"���ɐ����������A�e�������������Ԃ�������"�₵�����傫���B�ŋ߂����A���̌O�������搶�A�����������e�����������F�l�Ɩ��̒��ŏo��B
���������Ɂ@�͂��肪�˂��@������Ȃ�@�������܂Â����@�����Ă����
�I�F���@(�Í��a�̏W)
2020.11.30

�R���i�Ђł̓��X
"�R���i�Ђ̑�O�g������"�ƕ��Ă���B�ł��A�ޗnj����ɂ͌��\�A�ό��q�����āA�t�̗l�ȋْ����� ���܂芴�����Ȃ��B���́A�����O�ɐ_�˂֍s���Ĉȗ��A�d�Ԃɏ���Ă��Ȃ��B�T2,3��e�j�X�X�N�[���ɍs���A�e�j�X�̖������� �U���ɂł����A���8000���̕��s�������낪���Ă���B�y���E�x���͓ޗǂ͐l�������̂ŁA�ԂœޗǍx�O�֍s���A �Ԃ��߂āA��R������B����A��̎R(�W��600m)�ɁA�����b�N�T�b�N��"�F�����̗�"��t���A��l������� �o�������A�r���ŒN�ɂ����Ȃ������B�E�̎ʐ^�͈�̎R�̒���ŁA�������Ă��āA�W�]�͂Ȃ������B�����A �֍��̏�ɖ��s�҂̑����J���Ă������B
���͂���܂ŁA���܂�}�X�N�𒅗p���Ă��Ȃ������B�X�[�p�[�}�[�P�b�g��d�Ԃ̒��Œ��p������x�ł������B �������A�ŋ߂́APEE����99%(N95�Ή�)�}�X�N�p���@�\�t�B���^�[���}�X�N�ɑ������A"�l��������"�Ɗ������� �}�X�N�𒅗p����悤�ɂȂ����B
2020.11.17

����R
�I�̃V�[�Y���ɂȂ�A���ȂɁu��䉷��ɍs�����v�ƌ�������A���Ȃ��u�x�ɑ�����R�ɍs�������v�ƌ������B ���͋��ȂɑË������B�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ���A11��15,16�����Ă��āAGo To �g���x���L�����y�[���� �Ώۂɂ��Ȃ��Ă����̂ŁA15����"���t�I�O���v����"�A16����"�g�Y���C�K�j�t�H�̖��o�v����"��\���B15��9:00�ɎԂʼnƂ��o��13:30�x�ɑ�"����R"�ɒ������B�`�F�b�N�C����15:00����\�Ƃ̂��ƂŁA"����R"�̗��ɂ����� �ۂ��Q���ׂ��Ă���l�Ɍ�����?"�ێR(�W��1085m)"�ɓo�邱�Ƃɂ����B�z�e���̕W����900m�Ȃ̂Ŏ荠�ł���B �u�i�E�~�Y�i���̐X���A�W��1000m���邱���葐�n�ƂȂ�A�c�������h�E�A�����h�E�A�}�c���V�\�E�̏I���� ������ꂽ�B�C���J�K�~����R����A�t�ɖK�ꂽ����������낤�Ǝv�����B�E�̎ʐ^�͏ێR�R���܂ōs�����؋��ʐ^�B 16:00�`�F�b�N�C���B������A17:30���"���t�I�O��"�A�I�͖{���Ŕ������������B
16��10:00��"����R"���o��"�ؒJ��k��"���U��A���̌�A��͌��A�܂��݂��������o�āA12:30��R�����ԏꒅ�B �Q����o���āA�V��@�ʊi�{�R"��R��"�{���ɎQ�q������A��_�R�_�Љ��{�ɎQ�q�����B��_�R�Ƃ͑�R�̂��ƂŁA ��Ր_�͑卑��_�B16:00����R�W�]���B������k����̑�R�̗Y�p���ς����Ă����������B16:30"����R"�ɋA���B 17:30���"�g�Y���C�K�j�t�H�̖��o"�������������B䥂ōg�Y���C�K�j�͗�߂Ă��Ďc�O�ł������B
17��9:45�`�F�b�N�A�E�g�B�߂��̋��������R�w�K�������U����A10:30"����R"���o���A14:30�ޗǂ̎���ɋA�������B �O���ԑS�ĉ����ŁA"��R"�����\�����Ă����������B�x�ɑ�����R�̕��C�͉���łȂ������E�E�E���ꂾ�������_�B
2020.11.10

�M�q�W����
���N�����_��E���b�N�X�����̗M�q�������������̂ő����W������������B5.0kg�̗M�q���� ���a8cm����10cm�̚�4�A���a8cm����8cm�̚�11���t�̗M�q�W�������ł���(�E�̎ʐ^)�B �_���E�ꖡ�E�Ö����قǗǂ��A�Ƃ��Ă����������B�g�[�X�g�ɕt���ĐH�ׂ�B��N�͂P�P���� �P�ނƂ������A�����ɂ͖����Ȃ��Ă��܂��Ă����̂ŁA���N�͗ʂ𑝂₵���B����łP�N�� �����y���ނ��Ƃ��o����B���C���̂Ƃ��ɂ́A����ɗn�����ăn�`�~�c�������Ĉ��ށB �̂����܂�A�����⋭�E���{�����ɂ��Ȃ�B������2011.11.15�̃u���O�Ɍf�ڂ������A��̉����������̂ł����ɋL���B
�M�q�W�����̍���
1. �M�q(5kg)�����킵��p���Čy�������A�z�ЂŐ@������A�w�^����菜���B
2. �M�q���㉺�����ɐ��āA�ʌ`�̃������i���ŃS���S���Ƃ��A�`���i��o���B
3. �`���i��o�����M�q�̊O��ɓ����Ă������w�ʼn����o���B
4. �i�����`���U���ō����B�����`���X�e�����X���̓�(7.5���b�g��)�ɓ����B
5. �U���Ɏc������A3.�łƂ肾��������{�E���ɓ����B
6. ��̓������{�E���ɃJ�b�v�P�̐��������A����������B�悭�~����������U���ō����A �����`�̓X�e�����X���̓�ɓ����B
7. �U���Ɏc��������{�E���ɓ���A�J�b�v�P�̐��������A�悭�~����������U���ō����A �����`�̓X�e�����X���̓�ɓ����B
8. �ēx7.�Ɠ�������������A��͎̂Ă�B�E�E�E��̎���̔S�X�����̂̓W�����̌ʼn��Ɋ�^����B
9. �M�q�̊O��(���܂̈ꕔ���t���Ă���)���ׂ������ɂ���B����1mm���x�ɐS�����߂č��݁A �X�e�����X���̓�ɓ����B
10. �O���j���E��(2kg)���X�e�����X���̓�ɓ����B
11. �S�Ă̍ޗ����������X�e�����X���̓�𒆉�(IH�ڐ���:7)�ŔM���A�׃��ő~��������B ��u����Ƃ�����~�߂Ȃ��B�E�E�E����d�v�B
12. �O�c�O�c�ϗ����Ă�����A���(IH�ڐ���:6)�ɂ��A�~�������Ȃ���30�����x�ς߂�B �M�q�̐�肪���F���甼�����Ȃ�������~�߂�B
13. �M�������ɁA���S�ٕt�̊W�̂���r�ɂ߂�B�ŏ��ɏ��ʓ���A�r���g�܂��� �����班�ʓ���E�E�E�ƒi�K�I�ɓ����Εr�͔j�����Ȃ��B�ޓ��̋�C���o���邾�����Ȃ� ���邽�߂ɃW�����t�ɂ��ĊW����������߂�B����Ŏ����ň�N�ԕۑ��ł���B
14. �W�������ς���ɂQ�J�b�v�̐�������ĔM���Ȃ���ƁA���������M�q���ƂȂ�B �ܑ̖����̂ŔO�̂��߁E�E�E����Y��ɂȂ�B
(��) ���S�ٕt�̊W�̂���r�Ƃ́A�W�̐^�Ƀy�R�|�R�Ɠ��������������āA�M���W�����t�� ���ĊW��߂Ă����ƁA��߂��Ƃ��ɂւ��݂܂��B�����W��������������A���y����̂Ŗc��݂܂��B �ւ���ł���Έ��S���ĐH�ׂ��܂��B�J����ۂɂ́A�}�C�i�X�h���C�o�[���ŁA�W�������J���� �悤�ɂ��ċ�C�����Ȃ��ƊJ�����܂���B
2020.11.8

�A�����J�̑哝�̑I��
�A�����J�̑哝�̑I���̌��ʁAJoe Biden�����I�m���ɂȂ����B���̓z�b�Ƃ����B���E�ōł��͂����� �A�����J�̑哝�̂͏d�v�ł���B���E�e���Ƙb�����������A�Ë��E���ӂ�T��p���͏d�v�ł���BDonald Trump ����ł́A���܂�ɂ��e��ŁE�i���������B����ł��A�č��l�̔������x�����Ă��邱�Ƃ͖Y��Ă͂����Ȃ��B �ł��A�ł��ADonald Trump������đI���Ȃ������č��l�͐����Ǝv���B����Joe Biden����̏����錾�̎������p��BBC News�Ŋς��B�u���f�łȂ�������ǂ����߂�v�A�u�č��𐢊E ���瑸�h����鍑�ɂ���v�Ƃ̔����͊������BJoe Biden�����łȂ��A���哝�̂ɂȂ�Kamala Harris����� �������ǂ������B�����̍l����\�������̔\�́E���̊��ɂȂ�l�i�̊m���̑����Ɋ������B
���"�[�f��"(�m�R���M�N�̉��|��)��E��ł��āA�l���c����������"�L"�ɑ}����(�E�̎ʐ^)�B
�Ђ������́@�����̂��ւɂā@�݂邫���́@���܂ق��Ƃ��@����܂��ꂯ��
�����q�s (�Í��a�̏W)
2020.10.27

�쓹����
�C������K�ɂȂ��Ă��܂����B�ŋ߂͏T3��e�j�X�����Ă���B����ɏ�B���Ȃ����A����"���N�Ŋy���߂�Ηǂ�" �Ǝv���Ă���̂ő�c�ł���B10�N�]�e�j�X�X�N�[���ŁA�ꏏ�Ƀe�j�X�����Ă�������҂��u�R���i�Ђ̃X�g ���X�������āA����ǂ��Ȃ����v�ƌ����āA�x��͂������ꂽ�B���͈�@�����ɍs�������ʖڂ������B�Ȃ� �₵���B�V�C���ǂ������̂ŁA���H��"�쓹������A�H�̑��Ԃ��y������"�ƁA�����ƃJ�����������b�N�T�b�N�ɓ���A �Ԃ�30����ōs����ޗǎs���J���֍s�����B���̂�����͔������c��ڂƏ��R�E���R�т̔��������Ŏ��̂��C�ɓ��� �̏ꏊ�ł���B���H�킫�ɎԂ��~�߁A�����b�N�T�b�N�ɌF�悯�̗��t���A�X�e�b�L��Ў�ɕ����������BYAMAP (�R�ƌk�J�Ђ��o���Ă���5������1�̒n�}�ɁA���ݒn�E���s�L�^���L�ڂ����)�͂ƂĂ��֗��ŁA�X�}�z�ł������ �Ȃ���������B���x�A��肪�I�����Ƃ���ŁA�_�Ƃ̕��͑���������Ă���ꂽ�B�m�R���M�N�A�q���h���o�i�A �q���A�U�~�A�c���K�l�j���W��������R�������B�R���̖��琂�ꉺ�������m�T�T�Q���A���ɐ�����Ă���E���� �Ɨh��Ă����B���F�̓��ʂ͂ƂĂ������������B���̓J�����ł��̎p���B�����B
�n�}�������ɂ�����Ă�����A�y�g���b�N�Œʂ肩�������_�Ƃ̕����A�Ԃ��~�߂āu�����֍s�����Ƃ��Ă����?�v�ƁB ���́u"���̐X"�֍s�������̂ł����E�E�E�v�ƌ�������A�u���̓��͖����Ȃ����B�q���̍��ɂ͍s�������A���̓_�����ˁB "���̐X"�֍s���Ȃ�Ԃœ����܂ŘA��čs���Ă���v�ƁB����"���̐X"�֍s���̂��ړI�ł͂Ȃ��̂ŁA���d�ɂ��f������A ���̕ӂ���Ԃ���āA�������������Ԃ����B�E��̎ʐ^�̓c�������h�E�B�ƂĂ����K��"�쓹����"�ł������B
2020.10.15

�����S�W����
�s�����̔��S������ɍs������A�����������ȍg�ʃ����S���������B���K�̕������^���Ԃł����B ���̓����S�W��������낤�ƌ��߁A18�̍g�ʃ����S�����B4kg�̍g�ʃ����S�A3�̃������A1.4kg�̃O���j���[������o���������S�W�������E�̎ʐ^�ł���B
���S������̓X������Ǝ��͒��ǂ��ŁA���������������A���W�ܑ�͖����ł���B���̎������Ȃɘb������ �A���Ȃ͓{��o�����B���̓{��̂��q�˂���u�����s������L�����B�����M���̍Ȃƒm���Ă���̂ɁE�E�E�v�ƁB �����u����Ȃ̓�����O���B�l�͖����̗l�ɔ������ɍs���B���܂ɍs�����O�܂Ŗ����ɂ����瑼�̂��q����܂� �����ɂ��Ȃ����Ⴂ���Ȃ��v�ƌ����Ă��[�����Ȃ��B�u���A����Ȃ��Ǝ������Ɍ����M�����s�������v�ƁB ���́A���S������̎�l�Ƃ��X������Ƃ����ǂ��Ȃ̂��B
����͂ށ@���Ƃ��ɂ������@�����͂��Ɂ@����ʂ�����@������䂩��
�ɐ� (�E��a�̏W)
2020.10.5
�_�C�G�b�g
�C���K�ɂȂ��Ă��āA����̏H�A�I�A�C�`�W�N�A�u�h�E�A���Ԑ����X�������������o����Ă���B����������ƁA �c�C�c�C�肪�o�āA�H�ׂ܂����Ă����B�Ƃ��낪�A�̏d��������ċ������B62kg�A���̓K���̏d��60kg���I�B�����E�R ���i�Ђł̉^���s�����d�Ȃ��āA���̎n���B�����A�H�������ƂP��8000���ȏ�̃E�I�[�L���O���n�߂��B���͂���܂Łu�x�����ۃ��N�`��(�j���[���o�b�N�XRNP)�v�̐ڎ�������Ƃ��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�ŋ߂̃R���i�� �ɂ��Ɣx���ɂȂ�₷���l���E�E�E�ŁA�e�j�X���Ԃ̂���҂���֍s���āA���̗\�h�ڎ�����Ē������B������7000�~�B ���̐ڎ��5�N�ȏ�L�����������B���Ⴀ�A���͎��ʂ܂ōĐڎ�͕K�v�Ȃ��B
���̂���҂���ɁA�u�C���t���G���U�\�h�ڎ�v�͉���������ǂ����q�˂���"2�T�Ԍ�ɗ��Ȃ���"�ƌ���ꂽ�B ���́u����҃C���t���G���U�\�h�ڎ�v�����Ē������B������1700�~�B
2020.10.1

���H�̖���
������10��1���B�C������K�ł���B���͒��N����Ƃ����A�钅�A�V�[�c�A���J�o�[���̐�������A�Ă̖��� �������B�����āA�H�p�̖钅�E�����o�����B�����āA������"���H�̖���"�A�V�C���ǂ������Ϗ܂ł������ł������B�����ŁA���͐悸�\������������p �̒c�q���ɍs�����B�s�o���Ă������A���̓}�X�N�𒅗p���ĂȂ�B�����c�q10��700�~�� �������B�ƂɋA���āA��ʼnԂ�E��ŁA�����p�̉Ԃ����B�n�M�A�X�X�L�A�I�~�i�G�V�A�t�W�o�J�}�A�L�L���E �Ƒ������B�i�f�V�R�͍炫�I����Ă���̂ő���Ƀ������R�E�B�N�Y�͖������H�̎����̑唼�͑������B
 ��R�̉ԂȂ̂ŁA���厛�啧�a��L�̌Íނ��������Δ���]�p���ĉԊ�Ƃ����B�䗬�ő�_�ɐ��������ɒu�����B
�����āA�c�q�����̉��ɒu�����B
��R�̉ԂȂ̂ŁA���厛�啧�a��L�̌Íނ��������Δ���]�p���ĉԊ�Ƃ����B�䗬�ő�_�ɐ��������ɒu�����B
�����āA�c�q�����̉��ɒu�����B�����A�������o����ƌ��̏o���҂��������B18��20���A�t�����R(��W�R�̉�)�̎R�̒[���猎���łĂ����B �_��Ȃ������ŁA������ῂ����B
�������I����ƁA�����c�q�������āA���ȕ��ɂ܂Ԃ��Ă����������B
�݂Â̂����Ɂ@�Ă���Ȃ݂��@�����ӂ�@����Ђ������́@���Ȃ��Ȃ肯��
�� ���@(�E��a�̏W)
���܂̂͂�@�ӂ肳���݂�@�������Ȃ�@�݂����̂�܂Ɂ@���ł�������
���{���� (�Í��a�̏W)
2020.9.25

�㍂�n
10�����O�A�V���L���ŁuGOTO�g���x���@�z�e�����35%�⏕�v�̍L�������āA�㍂�n�鍑�z�e���ɓd�b������A �u23��,24���Ȃ�Ă��܂��v�Ƃ̂��ƂŁA�}篁A2�A���̏㍂�n�s�������肵���B�\�������́A�V�C �\����ǂ��������A�O���ɂ͑䕗�̐ڋ߂�����A�u23���͌ߌォ��J�A24���͑S���J�A25���͌ߑO�͐���v �̓V�C�\��ɂȂ����B23��8:30�ޗǂ̎�����Ԃŏo���B13:30���������Ȓ��ԏ�ɓ����B13:50�����Ȓ��ԏꔭ�̃o�X�ɏ�� 14:20�鍑�z�e���O�ʼn��ԁB�u�䕗�͓����̐i�H�ɂȂ����v�Ƃ̂��Ƃ�"����"�B�`�F�b�N�C����A�����ɊO�֏o���B ���s�̋��Ȃ��u�����͊ς�Ȃ���������Ȃ�����A�͓����֍s���ĕ䍂�A��̎ʐ^���B�肽���v�Ƃ����̂ŁA�悸�� �͓����֍s�����B�_��������"�䍂�A����o�b�`��"�Ƃ͂����Ȃ��������A���܂�A����A�O��A����̒��オ�������B �ʐ^���B���āA���Ȃ́u�����A�����A�J�ł��ǂ��v�ƌ������B���̌�A���쉈���̗V����������ēc�㋴�ցA ����Ɏ��R�����H��i��œc�㎼���E�c��r�֍s�����B�U��Ԃ��"�_���オ���ĕ䍂�A�S�Č�����(�E�̎ʐ^)"�B ���b�L�[�E���b�L�[�I�@����ɐi��ŁA�吳�r�ցB�[�����B���Ċx�Ƒ吳�r���ӏ܂�����A�z�e���A�����B����10,601�B 17:30���[�H�B���̓��͘a�H�B�X���b�p�𗚂��ĐH���ɍs��"�p���������v��"�������B
24��7:30���H�B�u�䕗�͂���ɓ����ɐi�v�Ƃ̂��ƂŁA�܂�B8:30�J��E�P�������A�z�e�����o���B���썶�݂̗V������ �����āA�͓������o�Ė��_���ցB���_�ق�"���ǂ�Ƃ��Ă�"�Œ��H�B���_�r�E�䍂�_�ЂɎQ�q������A����E�݂̗V������ �����ĉ͓����ցB����Ɉ���E�݂�����ăE�F�X�g�������[�t�E�c�㋴���o��15:00�z�e���ɋA�������B�J���~�炸�A�U��� ���̂��ނ��Ƃ��ł����B����19,748�B17:30���[�H�B���̓��͗m�H�B�o�R�C�𗚂��ĐH���֍s�����B
25��8:00���H�B�y���~��̉J�B9:10�z�e���O�Ńo�X�ɏ��9:40�����Ȓ��ԏꒅ�B���ԏꒅ�ɒ�߂Ă������Ԃɏ��A �y���~��̒��𑖂�A16:00�ޗǂ̎���ɋA�������B
�㍂�n�鍑�z�e���͉��K�ȃz�e���ŁA�]�ƈ��̑Ή����ǂ��A�������������������B�����A�������̂��c�O�ł������B �㍂�n�����\���邱�Ƃ��o�����B�ēx�s���Ȃ�A7���H
2020.9.15

�}�X�N
���͂��܂�}�X�N�𒅗p���Ȃ������(�����Ă��}�X�N�𒅗p���Ă��Ȃ��̂́A�N���̊�Ŏ҂�����)�A �o�X�E�d�Ԃ̎ԓ��A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�ɓ���ۂɂ́A������G�`�P�b�g�ɂȂ����Ǝv�����p���Ă���B �����������K�Ŋi�D�����̂��~�����Ȃ��āA���������ȟ��������X�ɍs�����B�X������Ɋ��߂��āA �I�[�K�j�b�N�R�b�g��100%�̗��̃K�[�[�}�X�N�����B�l�i�������āA��Ŏg���̂Ă̒������s���z �}�X�N50���������������B�X�ɁA�ƂɋA���Đ�������ǂ�ŋ������B�Ȃ�Ɓu�{�i�͊����E���o��K�X�� ��h���ړI�ɂ͎g�p�ł��܂���v�Ə����Ă������B�R���i�E�C���X���Ւf����ړI�Ȃ�uNIOSH(�č����J�����S�q��������)��N95�K�i�EEU��FFP2�K�i�ȏ�� �������}�X�N���g�p���Ȃ���Ȃ�܂���v�E�E�E�Ƃ������Ƃ����ɂȂ��Ēm�����B
�E�̎ʐ^�̓V���c�P�\�E�B
���Â�Ȃ��@���͂�ׂ̂̂́@�����͂����@�����ӂЂƂƂ��@�݂邯�ӂ���
�O�㍑�l�@(�V�E��a�̏W)
2020.9.4

79�˂ɂȂ�܂���
����9��4���A��79�˂̒a�������}���܂����B���A�l�ŁA���̂Ƃ���̒��͗ǂ��A�����Ƃ����Ĉ������������A ������ނ��Ƃ������A�g�̂ɒɂނƂ���������A���C�ɉ߂������Ē����Ă��܂��B�R���i�ЂŁA���N4���� �s���Ă���"�l�ԃh�b�N��f"�ɂ͍s���܂���ł����B��N�̌��t������"�X�����̋��ꂪ����"����Ə��߂� �ꂽ���������͎܂���ł������A���̂Ƃ��뉽�̎��o�Ǐ���������C�ɉ߂������Ă������Ă���܂��B���́A�T2,3��e�j�X���y���݁A�Ƃ��Ă�����ȃs�A�m�ƏK�����y����ł��܂��B�ǂ����Ă���Ȃɉ���ł� �ʔ����낤�Ǝ����ł��s�v�c�ł��B����������K���J�n�����̂�"���̎]��":���E�����p�̕ҋȂ�I��ŁA ���̔��\��ʼn��t��ڎw���܂��B���\��͏�肭�Ȃ邽�߂̃��`�x�[�V�����ł��B
�E�̎ʐ^�͏H�̎���(�R�㉯�ǂɂ��� ���A���A���A���q�A���Y�ԁA���сA�j�[)�̈��: ���Y��(�I�~�i�G�V)
���̉Ԃ�������ɐA�������A���͖S���`�ꂪ�u���͏��Y�Ԃ͏L�����猙����v�Ƃ�����������B���͂��̎��A ���̂������ł��Ȃ������B�b��������A���̈Ӗ������������B��Ԃɂ��Ďb�������"�������������悤��" �L�����A�����ɖ����Ă����B����ŏ��Y�Ԃ̊������[�Ă�ꂽ�̂ł��낤��?
���݂Ȃւ��@�݂�ɂ�����́@�Ȃ����܂Ł@���Ƃǂނ����́@������������
�������� (�V�Í��a�̏W)
�������ʂƁ@�߂ɂ͂��₩�Ɂ@�݂��˂ǂ��@�����̂��Ƃɂ��@���ǂ납��ʂ�
�����q�s (�Í��a�̏W)
2020.8.30

�ɐ��R
9:45�ɉƂ��o�āA12:15�ɐ��R�X�J�C�e���X���ԏ�(�W��1260m)�ɒ������B�r���A�C�k���V���B�e���悤�� ���h�Ȗ]�������Y���\�����l�B�����S�l�����̂ɂ͋������B���ԏ�͂قږ��t�ŁA�R���i�Ђ̉e���͂Ȃ��A �ʏ�̓��킢�ł������B���͍��R�A���̎ʐ^���B�낤�ƒ���ւƑ����V����������čs�����B���Q��h�����߂̃t�F���X�����ʂ������̂��A�܂��r���ł͂��邪�A�����̍��R�A�����ς邱�Ƃ��o�����B �V�����ɓ��������Ńn�N�T���t�E���ɏo������B�T���V�i�V���E�}�̉Ԑ���(�E�̎ʐ^)�B�����g���m�A�C�u�L�g���J�u�g�A �V�I�K�}�L�N�A�A�L�m�L�����\�E�A�V���c�P�\�E�E�E�E�Ɗy���܂��Ă��������܂����B����(�W��1377m)��PA�Ŕ������I�j�M���� �T���h�C�b�`��H�ׂ��B�_�������Ȃ�ƌ��\���������������B15:00�X�J�C�e���X���ԏ���o����17:30�ޗǂ̎���ɋA�������B
2020.8.27

�R�͉z����
�������������Ă��܂���37�����z����l�ȓ��͂Ȃ��Ȃ�܂����B����8��18,19,25���̃e�j�X�X�N�[���͋x�݂܂����B �̗͂��������Ďc���ɔ�����"�N���̒m�b"�ł��B8��26���v���Ԃ�Ƀe�j�X�X�N�[���ɍs���Ă��܂����B���̓��� �ō��C����35���ł������A�i���g�J�����Ƀe�j�X���y���ނ��Ƃ��o���܂����B�����"���N�̉Ă͏��z����ꂽ�E�E�E" �ƁA�v���܂����B�����v���Ē�߂�ƁA�����Ԃ�"�H�̋C�z"���������܂��ˁB�E�̎ʐ^�̓c���K�l�j���W���B
���݂��ĂɁ@�܂����邠���́@�����Ȃ�@�Ȃт��ʂ������@���炵�Ƃ�������
�����@(�E��a�̏W)
2020.8.17

�ҏ��̉߂�����
�ޗǂ͘A�����V�Ėҏ��������Ă���B�����̍ō��C����37���ł���B���Ԃ͗�[�̌����Ă��镔�����Ă��Ă���B �������Ă��Ă��Ă��A���܂茩���Ƃ��Ȃ������͗ǂ��Ȃ��Ǝ����Ɍ����������Ă���B����A���Ȃ��]��ɂ������Ƃ� �Ȃ����D�����Ă���̂ŁA�����������p���Ă��鎆��(�ʋC���E������̗ǂ��A�������ɂ����K)�ŏo�����p���c ���v���[���g�����B�u����͉��K�B������~�����v�ƌ������B�ŁA�V�����̂��ė^���A������Ƃ����B�������Ă��ĉ������Ă��邩�Ƃ����ƁA�Ǐ��A�s�A�m�A�p�\�R���B���������������Ȃ�����(���ɂ͐�����) �������Ɖ߂����Ă���B
�[���A�������������Ȃ�����A�U���ɂł����A�����������ċA��B���̍��̕��ϕ�����5000���B�������Ȃ����A��� ���т������B�V�����[�̌�A�����̃p���c�E�V���c�ł��낮�B�[�H��A���y���Ȃ���"�K��":��������B���Ȃ��� �s�v�c�Ɩʔ����B
�E��̎ʐ^�̓g���G�\�E(�b��:�g���G�Ƃ͙̗l�ȉQ���͗l�A�ܕىԂł����ɉQ�����Ă���)�B
���܂̂��́@���ӂ��̂����Ɂ@�����͂�ā@���炷�݂킽��@���������̂͂�
��������@(�E��a�̏W)
2020.8.13
���~�x��
�ޗǂ�8��11���̍ō��C����37���ł������B�e�j�X�X�N�[����12�������T�Ԃ��x�݂ł���B����13:30-15:00�� �e�j�X�X�N�[���֍s�����B���Ԃ̊J�ƈ�͌��Ȃł������B����Ⴤ�o�C�Ǝv�������A�̒��������Ȃ����璆�~�� �邱�Ƃɂ��ăe�j�X�������B�����A�_���Ȃ��J���J���Ƃ�ł������B�i���g�J�����I�������B���N�̂��~�͌̋�:���֎s�ւ̕�Q��𒆎~�����̂ŁA�����Ɠޗǂɑ��Ăł���B��[�̌������������Ă��� ����Ɖ��K�����A�g�̂��݂�̂ŁA12���[��16:30����U���ɏo���B�܂������̂ɁA���厛�啧�a�O�̎Q���ɂ́A �ό��q�����l�������Ă����B�O�����b���ό��q�����Ȃ肢�āA���̓r�b�N�������B
8��13�������͈����"�Ƃ��Ă낤"�Ǝv���Ă�����A���z�̋���11:00�ɋ��Ȃ��u���͔M���ǂ��B���~�̔��������Ă��āI ���}���c�q�͔����邩�炷���s���āI���������X�g�͂���I�@�M���͉��V���Ńe�j�X�����Ă���̂�������v�I�v �ƁA�̂��܂�����B�d�����Ȃ����甃�����ɍs���A�A������V�����[�𗁂тāA�Ȍ�A��[�̌������������Ă����B ��������������A�e���Ŕ����Ă����\������l�ŐH�ׂ��B
�Ȃ�܂́@�݂˂̂������́@��������@����ɂ����݂́@�������������
�r�ݐl�m�炸 (���a�̏W)
2020.8.10

�R�̓�
�����́u�R�̓��v���Ƃ����̂ŁA��y�ɓo���"���P���E���o�P�x"�֍s�����Ƃɂ����B�}篎v�������̂ŁA 10:20�ɉƂ��o���B�r���A��F�ɔ_�Y���������Ńg�}�g�ƃL���E�����A��ꒃ���Ŋ`�̗t���i(�R�Z�b�g)�� �����A���P���̒��ԏ�ɒ�������13:50�ł������B���ԏ�͂قږ��t�B"�R���i�Ђł����Ă���H"�Ƃ̗\�z�� �O�ꂽ�B�����A���o�P�x�R����ڎw���ĕ������B14:20�r���̐���ŁA�g�}�g�ƃL���E���𐅂̒��ɕ��荞�B �����āA�`�̗t���i��H�ׂ��B�x�����H�ŋ����A�ƂĂ��������������B���̌�A�悭�₦���g�}�g�ƃL���E�� �ɉ���t���ĐH�ׂ��B������������������B15:00���o�P�x�R��(�W��1695m �E�̎ʐ^)�ɒ������B���ԏ�̕W���� 1570m������125m�����̓o��ł���B�_�̂��鐰�V�ŁA�����������������A�C�����̗ǂ��R�s�ł������B16:10���P���̒��ԏ���o���A18:50�ޗǂ̎���ɋA�������B
2020.8.8
�ҏ���
�ޗǂł��A�ō��C����35�����ҏ���������ė����B����ł��A��E�������ɂ�25���������̂ŁA ���͐Q��O�܂�(23:00��)�Q�����[���Ă����āA���ɏA�����ɗ�[����Ă���B8��4���@13:30����15:00�܂Ńe�j�X�������B���т������ɂȂ����B�����o�[�ɓ��Ȉオ����������̂ŁA ���͈��S���Ă��邪�A���̓��Ȉ�ɂ́u����҂��~�}�Ԃʼn^�ꂽ��݂��Ƃ��Ȃ�����ˁI�v�ƒ��� �����Ă������B
8��5���@11:00����12:30�܂Ńe�j�X�������B����������"�O�����v�������̂�����E�E�E"�ƁA���V���� �e�j�X�������B�ƂɋA���āA���H��A���Q�������B
8��6���@�Ƃ̒�ł������p�̉Ԃ��A11:00�ɎԂŕ�Q��ɍs�����B��Q��A��a�S�R�̃C�^���A�����X�g������ �s���A�����`�Z�b�g(�T���_�A�s�U�A�X�p�Q�b�e�B�A�R�[�q�[)��H�ׂ��B�L���Ŕ����������X�ł���̂ŁA �ʏ�Ȃ疞�ȏ�ԂȂ̂ɁA�q�͎��Ƌ��Ȃ̑��ɂ͂Q�������ł������B�R���i�Ђ̉e���͐����B
8��7���@����̋��̉Ƃ��p���ł���]�킩��d�b������u���N�̂��~�ɂ͖K����T���Ăق����E�E�E�v�ƁB ���̐��Ƃ��p���ł��鎟��ɓd�b������u���̍s���Ă��鍂�Z�̐��k���ŋ߃R���i�Ɋ��������̂ŁA�F�� �_�o���ɂȂ��Ă���v�Ƃ̂��Ƃł������B�E�E�E�Łu���N�̂��~�͋A�Ȃ����Ȃ��v���Ƃɂ����B
8��8�� ���@���ɐA���Ă�����n�X�̍����q���傫���Ȃ��Ă��āA�������Ă��郁�_�J�̐����悪�����Ȃ��Ă����B ����ŁA���̃��_�J���A������̑傫�Ȕ��Ɉڂ���Ƃ������B���N���܂ꂽ���_�J����R(100�C�ȏ�)�����B ���̃��_�J�̂����ŁA���@���Ƀ{�E�t���͂��Ȃ��B
2020.8.2
�~�J����
8���ɂȂ��đQ���~�J�����錾���o�܂����B�~�J�̂����ŁA�ʏ�ł�����7�����{��������߂������Ƃ��o���܂����B �ł��A�_�Y���͕s��̗l�ł��ˁB����8��2��11:00����e�j�X�X�N�[����12:30�܂Ńe�j�X�����܂����B���̍s���Ă���e�j�X�X�N�[���̓I�[�v���R�[�g�� �J���J���Ƃ�̒��ł̃e�j�X�ł����B����p?�Ɉ��݂Ȃ���A�M���ǂɋC��t���Ă��܂��B�ł��A�I�������"���A������ �����ɏI�����"�Ǝv���܂��B�ƂɋA���āA�E�F�A����A���H��ۂ�A���̌�ꎞ�Ԃقǒ��Q�����܂����B���̌�A �M���������ƁA�Q�����C���o�Ă��܂����B
2020.7.30

�u���[�x���[
���N���肢���Ă����F�ɒ��̔_�Ƃ���d�b���������u�Q������Ԃ��łāA�u���[�x���[�̎��n���o���܂����v�ƁB ����5kg�����肢���āA���̔_�Ƃ܂Ŏ��ɍs�����B5kg�͎��n���邾���ő�ςł���B�_�Ƃ̕��Ɋ��ӁE���ӂł���B�ƂɋA���đ����W������������B���̐��ʂ��A�E�̎ʐ^�ł���B����ň�N�Ԗ����A���[�O���g�ƈꏏ�ɖ��키���Ƃ��o����B
�䂪�Ƃ̒�ɂ��u���[�x���[�̖��A���Ă��邪�A������͓E�܂�ŐH�ׂ�B�����āA�����͏����̉a�ƂȂ�B
2020.7.20

�����y�{��E����
���N�ɂȂ��āA�Γ��ɂ��ċL���Ă���(4.9, 4.18, 5.10)�B �Γ��Ɋւ��ẮA�ߍ]�̈��牤�R�Γ��� (�����傩��������@�����ǂ���)�ɂ�����{�ŌÂ̐Γ�:���牤���������킯�ɂ͂����܂���B�R���i�Ђ͑��傷��C�z�ł��邪�A�Ԃōs���Ηǂ����낤�Əo�����čs�����B�܊p������A�����V�c�䂩��̒n�A ���m���Ջ߂��̃��X�g�����Œ��H��ۂ�A�a������M�y�ւƓV������̌Ó���ʂ�A�����y�{��֍s�����B ���m���c���ł����������V�c���A�����y�ɗ��{�����A����ɑ啧�������͂��߂����@�Ղ炵���A���т̒��� ��R�̑b���������B�����A�u���A�m���A���@���̑b�����������A�ޗǂ̓��厛�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��A������܂� �Ƃ������̂ŁA�n���̍������ՂƂ����������ł������B
���ɁA�����A�������o�āA���牤�R�Γ����ɍs�����B158�i�Ƃ��������K�i��o��l�߂�ƁA��R�̑ۂނ����ܗ֓��̐^�� ���P����Ɍ������ꂽ���{�ŌÂ̐Γ�:���牤��(�E�̎ʐ^�A����7.5m�A����̑��ւ͌��H)���������B�A���l�̐H�̎� �ɂ����̂ł��낤�A�؍��̕}�]�ɂ����ю�(�S�ό���̎��@�A���̃z�[���y�[�W:��̉Ԃ̎ʐ^�W:�؍��@�Q��)��� �����Γ���A�z������A���h�Ŕ������Γ��ł������B�����̎R��ɂ́A��R�̌ܗ֓��Ε����������B�K�i�������āA �{���ɂ��Q�肵����A���_�������H�A���ޘa����ʂ�A17:30�ޗǂ̎���ɋA�������B �@�@�@
2020.7.13
�G��
�~�J�̖���?�̍��J������A�A���J���~���Ă��܂��B���̔~�J��������Ɩ{�i�I�ȉĂɂȂ�A�����ɎQ����X �ƂȂ邾�낤����A�J�ŊO������̂͑�ςł����A���̗������ɂ͊��ӂł���B����2016�N6��16���ɍ��ŒŊԔw���j�A�ǂ��~�}�Ԃœ��@���A7��4���ɑމ@�����B��p���邱�Ƃ����� ���Ŏ�����(�ڍׂȌo�߂͂��̍��̃u���O�ɋL�ڂ��Ă���܂�)�B���ꂩ�疞4�N���o�߂����B���������Ǝv���B �ȑO�͓x�X�M�b�N�������N�����Ă������A���������܂ł̂Ƃ��딭�ǂ��Ă��Ȃ��B�{���ɁA�{���ɁA���肪���� ���Ƃł���B����!����!�ł���B
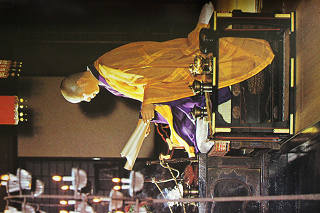 ���N�t�ɎĂ����l�ԃh�b�N�ł̌��f�́A���N�̓R���i�Ђ̔����ŁA�a�@�ɋߊ�肽���Ȃ��ĎĂ��Ȃ��B
��N�̐l�ԃh�b�N�Łu���t�������X������̋��ꂪ���邩�����ɂ��MRI��������������v�ƌ���ꂽ��
���͎Ȃ������B�����̂Ƃ���A���̎��o�Ǐ�����������Ă��܂��B�̒����ǂ��A�g�̂Œɂ��Ƃ�����Ȃ��A
�T2��̃e�j�X���y����ł��܂��B����Ȓ��q�̗ǂ��̂́A�����͑����Ȃ��ł��傤���A���肪�������ƂŁA
���ӁE���ӂł���܂��B
���N�t�ɎĂ����l�ԃh�b�N�ł̌��f�́A���N�̓R���i�Ђ̔����ŁA�a�@�ɋߊ�肽���Ȃ��ĎĂ��Ȃ��B
��N�̐l�ԃh�b�N�Łu���t�������X������̋��ꂪ���邩�����ɂ��MRI��������������v�ƌ���ꂽ��
���͎Ȃ������B�����̂Ƃ���A���̎��o�Ǐ�����������Ă��܂��B�̒����ǂ��A�g�̂Œɂ��Ƃ�����Ȃ��A
�T2��̃e�j�X���y����ł��܂��B����Ȓ��q�̗ǂ��̂́A�����͑����Ȃ��ł��傤���A���肪�������ƂŁA
���ӁE���ӂł���܂��B���̃R���i�Ђƒ��J�ŊO�ɏo��@����Ȃ��Ȃ����B����Ȏ���"�{��ǂ�"����ԗ����������A�S�₷�炮�B �蓖���莟��ɁA�F�X�Ȗ{���߂����Ă��āA�������ʐ^�ɏ��荇�����B���܂�悭�m���Ă��Ȃ��Ǝv���̂ŁA ���쌠�@�ɂ͈ᔽ���邾�낤���A���̎ʐ^�̎ʐ^���B���āA������ʼnE�Ɏ������Ă��������B �o�T��"�J���[��Ô��ꎭ�W�ޗ�(�W����)"�A�ʐ^�͓��]�g����ɂ����̂ł���B ���̎ʐ^�́A2011�N��90�˂ŖS���Ȃ���45���@�؎���Ջv�����Ƃ���̎Ⴋ���̎p�ł���B
�@�؎��{���\��ʊω����r��Ô���̉�
�@�@�@�ӂ��͂�̂��ق��������������݂Ɂ@���Ђ݂邲�Ƃ������������т�
2020.7.6

���̗ւ�����
�R���i�Ђ̉e���ŁA���̒��Ȃ�ƂȂ��Â��B�ł��A�w�Z���ĊJ����āA���������邭�Ȃ��Ă������Ƃ��F����肾�B �O�ւ̑�_�_�Ђł́A���̎����ɔq�a�O�ɎO�̊��̗ւ��݂����܂��B��_�_�Ђ̖��Ђł��闦��_�Ђ̑O��ʂ����� �q�a�̑O�Ɋ��̗�(�E�̎ʐ^)������܂����B�����āA���ӏ����Ɂu���̗ւ̂������: �q�a�Ɍ������Ċ��̗ւ�������A�E�։���Đ��ʂցA �ēx���̗ւ�������A���։���čēx���ʂցA�Ō�͔q�a�����ɒ��i���Ă��Q�������v�B���̂Ƃ��u"�݂Ȃ��̂Ȃ����̂͂炦����ЂƂ́@ ���Ƃ��̂��̂��@�̂ԂƂ��ӂȂ�"�ƌ�������ł��������v�Ƃ������B�ޗǂ̊X������ƁA�ȑO�̓}�X�N�����Ă��Ȃ��̂�"�N���̊�łȒj"�݂̂ł��������A��҂ł��}�X�N�𒅗p���Ă��Ȃ��̂��`���z�� �łĂ����B�ł��A8�����x�̐l�̓}�X�N�𒅗p���Ă���B�X�[�p�[�}�[�P�b�g�֍s���A���p��100%�ɋ߂��B���͎U���̓r���ŁA���̓����� �J�قƂȂ����ޗǍ��������ق́u��݂����鐳�q�@�@�Č��͑��ɂ݂�V���̋Z�v�W�ɓ��ꂵ���B�W���Ɂu�}�X�N�𒅗p���Ă��������v �ƒ��ӂ���Ă��܂����B
�䂫���Ł@��܂����炵�@�قƂƂ����@���܂ЂƂ����́@�����܂ق�����
�������@(�E��a�̏W)
2020.6.27
�̈�(�R�m�N��)�E�E�E����
�藎�Ƃ����I�I�X�Y���o�`�̑��ɂ́A�b���a���Q�����Ă������E�E�E����������Ȃ����B���͂��̑����E���� ���ĕ����̒u���ɂ����B���āA����̑����������B�T���V���E�̖ɓo�����B������n�߂āA�܂�����A�т����肵���B�̎}�ɑ̂� �ۂ߂��ւ������B����o�������т������Ă������Ȑg�\�����B���͎ւ͋��B���x�����̎}�����Ő藎�Ƃ����B �߂܂��l�Ƃ������f�����������֓����Č�����Ȃ������B�C����蒼���āA�T���V���E�̙�����I������A ���Ȃ��u���~�W�̖������������!�v�ƌ������B�����̒��a��20cm���B�V�̂ɂ͑�ςȍ�Ƃł������B ��|�������d���ĉ^�ׂȂ��B���ǁA����ɐ蕪�����B�u����ɂȂ����獂�����͐�Ȃ�����A���̂����� �����Ƃ����藎�Ƃ����v�Ƃ������ƂɂȂ�A���`�A�}�L�̓V�ӂ�藎�Ƃ����B���������Ă��āu�g�~�� �����Ȃ�Ȃ��̂�����A�v�����ę��肵�悤�v�Ƃ������ƂɂȂ�A�����}��藎�Ƃ����B���āA��n������ρB �藎�Ƃ����}���^��ŏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�R�₷�킯�ɂ����Ȃ��̂ő�ςł���B
�u����͐A�؉�����ɗ���v�Ƃ����ƁA�u���ɑ厖�Ȗ쑐�������ς��A���Ă���̂ɁA�����ƊĎ�����킯�ɂ����Ȃ��B �M���ł��A�����ƋC��t���Ă�!�v���B�Ƃ�����A�����I���B��������Ԗ��邭�Ȃ����B�߂ł����߂ł����B
2020.6.15
�̈�
�~�J�ɓ����āA�䂪�Ƃ̒�̖�������A�̈�(�R�m�N��:�����Ă��̉����Â��Ȃ邱��)��ԂȂ����B ����ŁA�~�J�̐���ԂƂȂ��������A��̙�����͂��߂��B�L�����N�Z�C�A�J�C�d�J�C�u�L�A���N�����A�t�W�A �X�I�E�̏��ə��肵�A�T���V���E�ւƂ����B�������肪�i�Ƃ���ŁA���̓I�I�X�Y���o�`�̑����ɂ݂� ���ɂ���̂ɋC���t�����B�����������������A�}���Ɛ藎�Ƃ����Ƃɂ����B�藎�Ƃ����u�ԁA���C�̃I�I�X �Y���o�`���o�Ă����B���͈�ڎU�ɓ������B�h����邱�Ƃ����������B����͒��~���A�Ƃ̒��Ō��Ă����B ���C���ӂ���щ���Ă����B�E�E�E�ř���̑����́A����E�E�E�Ƃ����B�킪��ǂ́@�����˂�͂���@�ւ����@�Ȃ��ɂ���Ɓ@�݂�邤�̂͂�
���@�� (�E��a�̏W)
2020.6.7

�ꔑ����̗�
���͍ŋ߂R�����قǁA�R���i�Ђɂ�鎩�l�����ŁA�����������X�g�����ł̐H���������A�Ƃł̗������}���l���� ���āA�������������������H�ׂ����Ȃ����B���l�ʼnc�Ƃ𒆎~���Ă����h���A�ĊJ���͂��߂Ă���B���̎����� �T�T�����̍炭���ł���B�����ŁA���ɐ��t�H���X�g�s�A�ɐq�˂���6��1������c�Ƃ��Ă���Ƃ̂��ƂŁA6��6�� �̏h����\���B6��6��10:00�ɎԂʼnƂ��o���B�r���A�э����̂��H������"���܂��̎p�����ƓS�Ί���"�����B���̂��X�A�ȑO �ɂ����x���K�ꂽ���A�R���ɂ���̂ɂƂĂ������������̂��C�ɓ���̓X�ł���B���̌�A�R�Ԃ̋������ɓ������B ���N�O�ɓ��[�ɐ����Ă���T�T�����������Ďʐ^���B���Ă�����A�_�Ƃ̕����u�����Ƒ�R�����Ă��鏊������܂��v �Ƌ����ĉ����������֍s�����B�`���b�g�������ȂƎv�������A��R�̃T�T�������炢�Ă����B�������C�i�̂���Ԃ͌����� �������B
14:00���ɐ��t�H���X�g�s�A�Ƀ`�F�b�N�C���B�����x�e������A���ӂ��U���B�X�̒��ɓ���ƒ�(1.5cm���̍���)�� �܂Ƃ����ĕ������B���X�ɏh�ɋA��A����Ŋ��𗬂�����A18:00����[�H�B�{�i�I�ȃt�����`�̃t���R�[�X�� �ƂĂ��������������B6��7��7:00�N���B8:00���H�B������������������B9:15�`�F�b�N�A�E�g�B��䒬���o�ɎԂ��߁A �쉈���̓�������āA�]�J����\�c�ւƕ����čs�����B�r���A�Ԃ͏I���Ă������A�C���J�K�~�̑�Q�����������B �������������Ԃ��āA11:30��䒬���o���o���A�O���Ɋ�����э����̂��H������"�����"��H�ׁA15:00�ޗǂ̎���ɋA�������B
2020.6.3

�~�̖̙���
���̉Ƃ̒�ɂ͊��̍����ł̒��a��30cm���̔~�̑������B���̖ɂȂ�~�͑嗱�ŁA�~�����ɂ���Ə_�炩���Ė����ǂ��B �Ƃ��낪�A���̔~�̖A�ǂ������C�������B�����̎}���͂�}�ɂȂ�A�~�̎����S����10�قǂ����Ȃ��Ă��Ȃ��B �V���ׂ̈����m��Ȃ����ǁA���Ƃ����Č��C�ɂ������B����ŁA�͂ꂩ�������}��藎�Ƃ��A�s�v�Ȏ}�̏d�Ȃ������ ����������B�傫�ȖȂ̂ř������ςȍ�Ƃ��B����������āA���Ƃ��I�������B��͍����ɔ엿�������Ղ�T���āA ���C�ɂȂ��Ă���邱�Ƃ�҂���ł���B��ɂ͍��A��R�̉Ԃ��炢�Ă���B���̂����̈�A�N�K�C�\�E�̎ʐ^���E�Ɏ����B
2020.5.25

�䂷�炤�߃W����
���N���䂷�炤��(�R�����~)�̎�����R�Ȃ����B�Ԃ��n���Ă����̂ł��̎���E�B13������17���܂� ��₵�āA��8kg���̎������n�����B�W���������ɂ́A�悸�A������o���˂Ȃ�Ȃ��B���ꂪ��ςȍ�Ƃł���B���w�Œׂ��Ď�� ���o���B5���ԗ]�����āA5kg�̉ʓ��E�`���A����Ƀ�����3�̂��ڂ�`��2kg�̃O���j���[���������� ��ŁA30�����������Ȃ���ς��B
�o�����W����(�V���b�v?)��r�ɋl�߂Ė������B���̖c��ȋΘJ�̂��܂��̂��E�̎ʐ^�ł���B
���̃W�����A�Ƃ��Ă����������B���̓g�[�X�g�ɕt���ĐH�ׂ�B�������ꂽ��i�Ȗ��ŁA�Ƃ��Ă����������B ���ꂾ������ƁA��N�ԁA���������������Ƃ��o����B��ςȍ�Ƃł��������A��������ė]�肪����B
2020.5.19
�����
�q���̓������H�ׂĂ�����A�����̉������Ԗڂ̎��̂��Ԃ������Ƃꂽ�B����҂���ɓd�b������u�ɂ��Ȃ��Ȃ�A 11��11���ɗ��Ă��������v�Ƃ̂��Ƃł������B11���Ɏ��Ȉ�@�ɍs������A�V�^�R���i�E�C���X(Covid-19)�����\�h�� �ׂ��u�̉��𑪂��ĉ������B37���ȏ�Ȃ�f�Â��f��v�Ƒ̉��v��n���ꂽ�B36.4����OK�B�f�Ă�����������u�y�䂪 ���������ɂȂ��Ă��邩��t���ւ��܂��傤�v�ƌ���ꂽ�B����19���ɍs������u�ی��͌�����4,4000�~������܂����A�_�炩���ގ��ł���������ǂ��Ǝv���܂��B�@���ł����v �ƌ���ꂽ�B"�������������Ɗ��Ⴂ���Ă���E�E�E"�Ǝv�������A�M���ł���r�̗ǂ�����҂���Ȃ̂�OK�����B
���̎���҂���ɊX������Ă��Ă��������B�������A����ƁA����҂���u������������B���Z���̗l�ȕ����Ȃ̂ŁE�E�E �C���t�������炵�܂����v�ƁB
���͂ÂȂ��@���݂Ȃт��͂Ɂ@�����݂��ā@���܂₿����@��܂Ԃ��̂͂�
�������@(�V�Í��a�̏W)
2020.5.10

���̐X
�ޗǎ��ӂ̓c�ɂł́A���͓c�A���̐^������ŁA���Ȃǂ��̂�т�U�����Ă���Ɖ������\����Ȃ��C������B �����ŁA����͊C��660m�̎R���ɂ���"���̐X"�֍s�����Ƃɂ����B�Ԃœޗǎs���J���܂ōs���A���H�킫�̖؉A �ɎԂ��߁A�ׂ��R����o���čs�����B�r������"�M����"��Ԃ̏������������A�V�̔��������[�g�ł������B �W����200m,���s����2km����"���̐X"�ɒ������B�����ɂ́A����̏�ɓ��g�A���̏�ɘZ�d�̊}���d�˂�ꂽ �Α���(�E�̎ʐ^)���������B�߂��ɂ����������W�ɂ��Ɓu�Ύ��͏t����(��̋ÊD��)�ŁA�����j�����r���������A ���ӂɎU�������f�Ђ���A���̓��͓�d��d�̏�Ɍ��Z�p�\�O�d���ƔF�߂���B�䂪�������̐Α����̒��ł� ���オ�Â�(�ޗǎ���A��d�E���g�ɂ͘@�ؕ��Ȃǂ̌Î��������c���Ă���)�A�`����@�����ɗޗ�̂Ȃ��M�d�Ȃ��́v �Ƃ������B2020.5.5

�ً}���Ԑ錾����
���{�͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ً}���Ԑ錾���܌����܂ʼn�������Ƃ����B�E�C���X�̕������߂� ���s�������A�}���ׂ����Ƃ�"���N�`���Ǝ��Ö�̊J��"�ł���B���E�e���̋��͂���Ǝv���B���{�̐��Ɖ�c�́A �����̐��������E����d��ȔC����S���Ă���̂��A�V�b�J�����Ă����Ȃ��Ă͍���B������ł��邱�Ƃ��v���A�w�Z�́A�\���ȑ�(�Z��ő̉��𑪂�A�M�̂���q�͋A����铙�A��p�̎�@���Q�l�ɂȂ�B) �����čĊJ������ǂ��Ǝv���B����ł��A���a���邱�Ƃ͂��邾�낤��"���̓s�x�őP�̍���u����"�E�E�E�ŗǂ��Ǝv���B
���͉^�����Ȃ��Ƒ̗͂������邵�C�����ǂ��Ȃ��B����ŁA�������ƎU���ɍs�����A�������ɂ��s���B"�A�x���͓ޗnj����ɂ� �s���Ȃ�"�ƌ��߂Ă������A�l�e�����Ȃ��̂ŁA�U���ɍs�����B�W���M���O�⎩�]�Ԃ̐l���������������ȁB
�Ԃœc�ɁE�R�ԕ��֏o�����čs���āA�Ԃ��߂ĕ����B����A�Ƃ���Ԃ�20���قǂōs���鐾���т֍s������A�������ꂽ�c��� �����ŕ����A�̕��������͎G���E����������ʂ�Ȃ��Ȃ��Ă����̂ɂ͋������B�c��ڂœc�A�������Ă���l�͎��Ɠ��N�� �̗l���B���̐�A�_�n�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��S�z�ł���B
�䂪�Ƃ̃X�Y�����͉Ԑ���ł���B����ŁA�f�R�̃X�Y�����Q���n���ςɍs�����B�Ƃ��낪�A�܂��肪�o������ʼnԂ� �F���ł������B�c�A�������Ă�����v�Ȃ��u�����̉��{���������ł��v�Ƌ����Ă����������B
�E�̎ʐ^�́A�䂪�Ƃ̒납��E��ł��Ě�ɑ}�����X�Y�����B
2020.4.30

��t
�������l�����I���B�ً}���Ԑ錾�͈ꃖ�������Ƃ̂��ƁB�����͌˘f���Ă��܂��B��t�̔������G�߂ɂȂ�܂����ˁB���厛�啧�a�ɍs���Ă��܂����B�q�ϋ֎~�ő啧�a�̔��͕܂��Ă��܂������A ���i�͕����Ă��钆�傪�����Ă���A����10m�����邱�Ƃ��o���܂����B�ʏ�͂Ƃ����Ă��鐳�ʓ��j�� �i����͂Ӂj���̊ϑ������J����Ă���A�啧�����̂����q���邱�Ƃ��o�����B���傩��啧�a�E��������� �ʐ^���E�Ɏ����܂��B����̒d��Ɏ����̂�т�ƍ����Ă��܂����B�ό��q�͂���ق���x�ł������ƎU���� �邱�Ƃ��o���܂����B
�ޗǎs���̂��X��"�앙(�{��)"���������̂ŁA���邾��(2.5kg)������߂āA�ώς����܂����B������������āA "�g�������͂�"��"�앙�̒ώ�"��������Ό�y���E��y���B
�����Ђ��Â�@�Ƃ��͂̂�܂́@���͂��@���͂˂�������@���Ђ������̂�
���啶 (�Í��a�̏W)
2020.4.23

�e�j�X
�����s���Ă���e�j�X�X�N�[���͌����V�c�˂ɗאڂ��Ă���A���j�I���v�n��Ō��z�K�����������A ���O�R�[�g�����ł���B���R�Ɍb�܂ꂽ���ŁA�E�O�C�X�A�L�W�A�I�I�^�J�A�z�g�g�M�X���X�̖쒹 ���q�ς��邱�Ƃ��o����B���O�R�[�g�����Ȃ̂œ��Ă����C�ɂ���l�ɂ͌h�������̂������o�[�� ���Ȃ��B21��13:30-15:00�̃e�j�X�X�N�[���ɍs�����B�����o�[�̓R�[�`�������7�l�B�����o�[�ɂ͈�t�������B
22��11:00-12:30�̃e�j�X�X�N�[���ɍs�����B�����o�[�̓R�[�`�������8�l�B
���B�̃R�[�g�ׂ̗ł́A���w�����e�j�X�����Ă����B�ƂĂ����C�ŁA�͈�t�ł������Ă���p�͌��Ă��Ă� �C�����ǂ��B���w�Z��w�N�Ǝv����q���B���A���C�̗ǂ��R�[�`�̐��ɗ�܂���āA�e�j�X�����Ă����B �w�Z���x�݂ɂȂ��ĉƂ��Ă��Ă���ł͂��܂�Ȃ����낤�B����͂ƂĂ��ǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B
�Ƃ���Łu"�ً}���Ԑ錾"���ŁA�s�ސT�ł͂Ȃ����E�E�E�v�ƌ���ꂻ���ł����A�����̐V����ǂނ� "�O�o���l�����������ƂŁA�^���s������^���w���X�ւ̉e�����w�E����Ă���B�W���M���O��U�����͂��߁A �����ɋC��t���Ȃ���̉^��(���O�̃e�j�X�A�S���t)�͔F�߂��Ă���B"�Ə����Ă������B
�Ƃ̒��ɂ��鎞�Ԃ������Ȃ����̂ŁA�����ł������̒��𖾂邭���傤�ƁA��̃A�P�r�A���N�����A �V���N�i�Q�A�I�_�}�L�A�T�N���\�E������Ă��Đ������B�E�̎ʐ^�͈�֑��A��֑��A�n���I�R�V�A���ߑ��A �C�J���\�E���B
2020.4.20

�D�G��
�������Ȃ��A�������Ȃ�"�D�G��"�ɂȂ�܂����B19���A���͒g�[�������܂��A�G�A�R���̑|�������܂����B �v���Ԃ�̑|���Ȃ̂Ńt�B���^�[�ɂ̓S�~�������ς����܂��Ă��܂����B�Ƃ��イ�̃G�A�R��5��̑|�����I������ ���Ă��܂����B�����C�g�̂ɂȂ������̂��B���̌�A�U���ɏo���B�I���Ǝv�����B�O�ɂ���l�������B���厛�啧�a���A���A�ᑐ�R�R�[�ƕ����čs�����B �e�q�A�ꂪ���\�����B�Ƃ��Ă��Ă��肢�Ďq�����ދ����Ă��܂������炾�낤���B�ᑐ�R�ɓo���Ă���l�����Ȃ肢���B �ł��A�V�^�R���i�E�C���X(Covid-19)�����̊댯��������l��"�l�̖��x"�ł͖����B�����S���������B �t����Ђ̓��͍炫�n�߂ł������B�䂪�Ƃ̓��͖��J(�E�̎ʐ^)�ł���̂ɁE�E�E�B��Ζ�ł͎����������Ƒ���H�ׂĂ����B �ό��q�����Ȃ��̂�"������ׂ�"���Ⴆ�Ȃ��ĕ����Ă���l�ł������B�t����Ј�̒������o�āA�������֍s�����B �������͑S�Ă̌����̔���߂Ă����B�q�a�̑O�̘k����@���R���O���A�ނ��ЂÂ��Ă������B �O��ʂ͑����̏��X���V���b�^�[�����낵�Ă���"�ً}���Ԑ錾"�̌��ʂ��o�Ă����B���������A���̃s�A�m�X�N�[���� 5��6���܂ŋx�Z�ƂȂ����B
20���@�ߌ㎩����o�āA���厛�啧�a���A���A�t���쉀�n�A�ޗǍ��������فA�������A�����_�ЁA�ޗǏ��q��O���o�� ����ɋA�����B����8500�B�l�e�͑a��ł������B19���̐l�o�͓��j�����������炾�낤�B����A�x�ɂ͓ޗnj����ɂ͍s���Ȃ� ���Ƃɂ��傤�B
�����̂���Ɂ@���������ɂقӁ@�ӂ��Ȃ݂��@�������Ă䂩�ށ@�݂ʂЂƂ̂���
�`�{�l���@(�E��a�̏W)
2020.4.18

�ً}���Ԑ錾
4��7���A7�s���{���ɋً}���Ԑ錾���o�����Ɠ��厛�ł��ό��q�͌��ς��A����O�ł����l�������Ȃ������B �����ޗǂ̃p�`���R�X�͑�ォ��̋q�ň�t�Ƃ����̂ō��������Ƃ��Ǝv���Ă�����A4��17���ɑS���ɋً}�� �Ԑ錾���o����āA�ޗǎs���͐l�ʂ肪��w���Ȃ��Ȃ����B�p�`���R�X�͂܂��J�X���Ă��邪�A�w�O�̓X�� �K���K���ł������B�l�e�̏��Ȃ��Ȃ����������A���͎U������B���8000����ڕW�ɂ��āE�E�E�B�X�֔����� �ɂ��s���B���Ȃ́u���͊������Ă��ǂ�������A���ɂ��邩��l���݂ɂ͍s���Ȃ��łق����B���� ����ł��ǂ�������A���͂܂����ɂ����Ȃ��B�v�ƌ����B����ɂ͕Ԃ����t�������B�䂪�Ƃ���3000���قǂŔʎ�ɍs����B�ʎ�͔���ɑn������A�V������ɕ��鋞�̋S�����삷�鎛�ƂȂ�A �ʎ�o�̊w�⎛�Ƃ��ĉh�����B�����ɂ͊��q����̓��厛�Č��Ŋ����v�l�H:�ɍs���i�����傤�܂j�̎�ɂȂ� �\�O�d�Γ�(�E�̎ʐ^:����12.6m)������B��d�̏�̓��g�ɂ͌����l����(������k�ɖ�t�A����ɁA�߉ށA���ӁA�̌����S��)�� ��������Ă��܂��B���łɁE�E�E�������̌d���̏��w�̓����ɐ݂���ꂽ�{��d�ɂ́A ���ɖ�t�O�����i������F�E��t�@���E������F�j�A���Ɉ���ɎO�����i������F�E����ɔ@���E�ω���F�j�A ��Ɏ߉ގO�����i������F�E�߉ޔ@���E�����F�j�A�k�ɖ��ӎO�����i�喭����F�E���Ӕ@���E�@���ѕ�F�j �����u����Ă��܂��E�E�E���N�O���J���ꂽ�ۂɎ��͔q�ς����Ă����������B
�ʎ��13���ɍs�����Ƃ��͎Q�q�q�͎������ł������B16���ɃJ�����������čs������Q�q�q��3�l�ł������B
2020.4.12
�R���i�E�C���X��
���{�ł��V�^�R���i�E�C���X(Covid-19)�̊������i�݁A"�ً}���Ԑ錾"���o���ꂽ�B����� �I�[�o�[�V���[�g(�����I�Ȋ��҂̑���)���o���邾���ɂ₩�ɂ���ׂ̕���ł���B�����I�Ȋ��҂̑��傪 �N����ƁA��Õ���(��É\�Ȋ��Ґ��ȏ�Ɋ��Ґ�������)���Ă��܂��̂ŁA���������邽�߂̕���ł���B5��6�����ɂ��̑��������܂�킯�łȂ��A�����Ґ���������葝�債�Ă������Ƃ������B�������Ď����Ă����l�� �R�̂��o����B���������͂قƂ�ǂ��ĂȂ�����A���\����Ă��銴���Ґ����͂邩�ɏ���l���������A������ �R�̂������Ă������Ƃ����҂����B5��6�����ɂȂ�ƁA�R�̂��������l�����Ȃ�ɂȂ邱�Ƃ����҂ł���B�E�E�E�ŁA ���̍��A�R�̌����𑽂��̐l�ɍs���A�R�̂��������l���瓭���ĖႤ�B������7�����x���R�̂���������A���̑����� �����Ɍ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
���́A����ɑς�����̗́E���͂����邩���Ǝv���B���̂܂܉Ƃ��Ă��Ă��āA�����ԑς�����ł��傤���H�@ ���E���ɍL�����Ă��邾���ɁA���W�r�㍑�ł͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H
����"�D�ꂽ���Ö�Ɗ�����h�����N�`��"�̔����E�J�����ɂ߂ďd�v���Ǝv���܂��B�����Ă����"�o����"�Ǝv���܂��B �ً}�Ɋ��������Ȃ���Ȃ�܂���B"�}�X�N�̔z�z"�Ȃǂɂ������g�����A"�D�ꂽ���Ö�Ɗ�����h�����N�`���� �����E�J��"�ɐl�ށE�����𒍓����ׂ����ƍl���܂��B���ꂱ��"�ً}����"�ł��B
(�lj�:Good News)�@4��13��16:24��BBC News �ɂ��� Sarah Gilbert����(a professor of vaccinology at Oxford University) �́@�u�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���̗Տ��������܂��Ȃ��J�n����B���̌�A��ʐ��Y���J�n���A9���ɂ͈�ʑ�O�� �g����悤�ɂȂ邾�낤�B�v�ƌ���������ł���B���E���ő����̌����E�J�����s���Ă��邱�ƂƎv���܂��B ���҂��܂��傤�B
2020.4.10
�����P���Ǝ̉���
�����P���Ǝ�3��18���Ɂu�R���i�E�C���X��ɂ��āA�����ɗ����Ƌ��͂����߂鉉���v(�S���̓��{���� https://www.mikako-deutschservice.com/post/�@�Q��)�����܂����B�����ւ̐����Ő^���ȌĂт����́A�����̐l �Ɋ�����^���A�[����������̂ł����B���̒��Ɂu���E���Ō����Ɍ������i�߂��Ă��܂����A�R���i�E�C���X�ɑ��鎡�Ö@�����N�`�����܂�����܂���B ���̏���������A�B��ł��邱�Ƃ́A�E�C���X�̊g�U�X�s�[�h���ɘa���A�������ɂ킽���Ĉ������� ���ƂŎ��Ԃ��҂����Ƃł��B�����҂��N�X���ƃ��N�`�����J�����邽�߂̎��Ԃł��B�܂��A���ǂ����l�� �ł������x�X�g�ȏ����Ŏ��Â�����悤�ɂ��邽�߂̎��Ԃł�����܂��B�v�Ƃ����i��������܂��B "�N�X���ƃ��N�`�����J��"�̂P�����������Ƃ��I�I�I
2020.4.9

�ߊ|��
����r�̓��ɔ�������d�Γ��������Ă��܂��B��d�̏�̓��g�ɂ͎l����(������k�ɖ�t�A�߉ށA����ɁA ���ӂ̌����S��)����������Ă��܂��B���̋߂���"���ʂ�����"�̐Δ肪����A���͉萶��������̐V�� �̔�������������܂��B���ɂ�����́A�������̌d����w�i�ɂ��āA�������Ƃ����C���ɂ��Ă���܂��B �ߊ|���̗R���́A��̒����̐�����߂��я�����������ۂɈ߂���Ɋ|�������Ƃɂ��悤�ŁA����r �̐��ɂ͍я��_�Ђ�����܂��B�����€�́@���Ƃ�肩����@�͂邵�������@�݂���Ă͂Ȃ́@�ق���тɂ���
�I�єV (�Í��a�̏W)
2020.4.5

��
�v���Ԃ��������ƁA���ߑO�A�ԂʼnƂ��o���B���x���̋߂��ɍŋ߃I�[�u���������X�g������ ���H��ۂ낤�Ɠ��X�����B�ē�����ăe�[�u���ɍ����āu�V�}�b�^�v�Ǝv�����B�قږ��Ȃō��G���Ă����B �u��ԑ����ł���͉̂��ł����v�Ɛq�˂���u�J���[���C�X�v�B����𒍕����A���X�ɑގU�����B�Ε���ł͎q���A��̐l�������������A�������͋Ă����B�����ŁA�Ê~�u�֍s�����B���ԏ�� ���Ԃł��������A�������̂Ń��b�L�[�B�V�̔������U���H��o���čs�����B�R�o�m�~�c�o�c�c�W ���������炢�Ă����B�Ê~�u�̎R��W�]��ɂ͎U��n�߂��������{���������B�W�]�䂩��B����"���T�R�E���R ����"�̎ʐ^���E�Ɏ����B
�����炿��@���̂��������́@���ނ���Ł@����ɂ����ʁ@�䂫���ӂ肯��
�I�єV (�E��a�̏W)
2020.4.4

�t
�x�݂������Ă����s�A�m�������ĊJ�����B�������u�}�X�N�𒅗p���Ă��Ă��������v�Ƃ̂��Ƃł������B �߂��ɂ���w�K�m�͊J�Z�������Ă���B���̊w�K�m�͗D�G�Ȑ��k�������̂��A�F����҂����Ԃɂ����K ���Ă���B�w�Z���x�݂��Ƃ����̂ŗV��ł���ƁA����Ȑ��k�ɂ�"�卷��t����Ă��܂�"�Ǝv���B���z�̌��������Ȃ�A�䂪�Ƃ̒�ɂ��l�X�ȉԂ��炢�Ă���B�@�̐A���ւ����I�������B���N�̏t�� "���I�����Ȃ�"�l�ŁA"�~�A�䂷�炤�߁A�u���[�x���[�̎����Ȃ�Ȃ�"�̂ł͂Ȃ����ƋC�ɂȂ�B �S�z���肵�Ă��Ă����傤���Ȃ��B��̉Ԃ�E��ł��āA�ԕr�ɐ��������𖾂邭�����B
���H��A�U���ŁA���厛�啧�a���A���A�ᑐ�R�R�[�A�t����ЁA�������A����r�ƕ������B����10298�B ���͖��J�ł������B
�݂Ă݂̂�@�l�Ɍ��ށ@�R���@�Ă��Ƃɂ���ā@�����ÂƂɂ���
�@ �f���@�t�@(�Í��a�̏W)
2020.3.29

������
���{�̐��Ɖ�c��2��24���Ɂu1,2�T�Ԃ��}���Ȋg��ɐi�ނ��A�����ł��邩�̐��ˍہv�Ƃ� ���������\�����B���{�����́A2��28���Ɂu�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��h�~�ׂ̈ɂ͂��� 1,2�T�Ԃ��ɂ߂ďd�v�Ȏ����v�Əq�ׁu�S���̏������̗Վ��x�Z�v��v�������B���{�̐��Ɖ�c��3��19���Ɂu�I�[�o�[�V���[�g�𖢑R�ɖh�����Ƃ����肤�邪�A�����O�� ���݂̊������l����A�Z���I�����͍l���ɂ�����������o�傷��K�v������v�Ƃ̌����� �������B���{�����́A3��28���Ɂu���̐킢�͒�������o�債�Ă��������K�v������v�Əq�ׂ��B
�u�Z���I�ȗ}�����݂͏o���Ȃ��āA�����I�ȐV�^�R���i�E�C���X�Ƃ̕t���������K�v�ɂȂ����v�� �������Ƃ��B���N�ɋC��t���ĐV�^�R���i�E�C���X�ɕ����Ȃ��g�̂���邵���Ȃ��������B
�I�[�o�[�V���[�g(�����I�Ȋ��҂̑���)���o���邾���ɂ₩�ɂ���ɂ�"�O�̏���(1.���C�̈��� ����ԁA 2.�����̐l�����W�A3.�ߋ����ł̉�b�┭��)"�������ꏊ���ʂ�\����������s���� �Ƃ邱�Ƃ̗l���B�������A����𐔃����ԑ����邱�Ƃ͍���낤�B����I�ɐV�^�R���i�E�C���X�� �t�������Ă��������ɂȂ邾�낤�B�P�Z���Z���B
�Ƃ��Ă��Ă���ł́A�g�͎̂�邵�A�C���߂���B�U���œ��厛�̍������ɍs���A�p���ŁA���ې� �����̐�H��(�����Ɋ����ޗǕ�s��H��敂��A��������170�N�̃\���C���V�m: �E�̎ʐ^)���� �ɍs�����B��N���͌����l�͏��Ȃ��������A���\������Ă����B
�킪��ǂ́@�͂Ȃ݂��Ă�Ɂ@����ЂƂ́@����Ȃ�̂��� ���Ђ�����ׂ�
�}�͓��Z�P (�Í��a�̏W)
2020.3.23
�g�p���f�~�b�N�h�Ƃ̓���
2020�N3��22��(��)�ߌ�9��00���`10��05���ɕ��f���ꂽ�uNHK�X�y�V�����g�p���f�~�b�N�h�Ƃ̓����` �����g��͕������߂��邩�`�v��q�ς����Ă����������B���{�̐��Ɖ�c�̃����o�[�ł����� ���k��w��w�@�����E���J�m����̂��b�͂ƂĂ��ǂ������B����̐V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA ��������̕��͂���A�����g��̃��J�j�Y�������X�ɕ������Ă��Ă���l�ŁA�����g���H���~�� �悤�ƕK���Ɋ撣���Ă���������l�q���A���̐����Ȑ����Ƒԓx����q�@���邱�Ƃ��o�����B"�N���X�^�[(���ҏW�c)"���������A�������̂�������Ȃ����Ⴊ���傷��ƁA"�I�[�o�[�V���[�g(�����I�Ȋ��҂̑���)" ���N����l�ł���B���̔ԑg�����āA���� "3��9���̐��Ɖ�A�O�̏���(1.���C�̈�������ԁA 2.�����̐l�����W�A 3.�ߋ����ł̉�b�┭��)�������ꏊ���ʂ�\����������s����v�������B"���Ƃ𗝉��E�[�����邱�Ƃ��o�����B
����̐V�^�R���i�E�C���X�̖��́A�Љ�I�ɂ��o�ϓI�ɂ�����ȉe�����y�ڂ������ɁA�����̗����Ƌ��͂��K�v�ł���B �����w�Z����ċx�Z�ɂ���ꍇ�Ȃǂɂ́A�א��҂͍����ɁA���J�Ŋ�������Ղ����������Ē��������Ǝv���܂��B
��p�̎���́A���炵���P�̃��f���ł���Ǝv�����B�Z��Ő��k�̔M�𑪂�A�M����������A��邢�͈㖱���Ɋu���B ��l���������炻�̃N���X�͕��A�����҂���l�ɂȂ�����S�Z���B�E�E�E�ǂ������Ǝv�����B
�ĕ����� �Q�S�i�j��P�P:�T�O�`�m�����n�̗\��ł��B
2020.3.20
�����̗��K
�F�m�ǂȂǂ̗��R�Ŕ��f�\�͂��s�\���Ȑl��ی삷�邽�߁A�_�����Y�Ǘ���㗝�ōs�����x�Ƃ��āu���l�㌩���x�v ������B���N�㌩���x�ɂ͖@��㌩���x�ƔC�ӌ㌩���x������B�������Ȃ��Ɩ@��㌩���x���K�p�����B���Ȃ͔C�ӌ㌩���x:"�{�l���_��̒����ɕK�v�Ȕ��f�\�͂�L���Ă���ԂɁA�������Ȃ̔��f�\�͂��s�\���ɂȂ����Ƃ� �㌩����l�i�C�ӌ㌩�l�j���A���玖�O�̌_��ɂ���Č��߂Ă������x�i�����؏����쐬�j"�𗘗p���悤�ƌ��S���A �����ɏZ�ޒ����ɔC�ӌ㌩�l�ɂȂ��Ă��炤���Ƃɂ����B
�����́A3��19���Ɍ��ؐl�����"���ȂƔC�ӌ㌩�_�������Ō����؏����쐬"���邽�ߓޗǂɗ����B �������Ȃ������A30�����ŏI������B�č��ɏZ�ގ����́u����������C�ӌ㌩�_���������v�ƌ��������A �u��������̓{�P�Ȃ��v�ƌ����āA���̌_������Ȃ������B�����A�ǂ��Ȃ�ł��傤�H
20���B�ފ݂̕�Q������A���H��ۂ�����A�����͋A���čs�����B������ԗ��s�ŃR���i�E�C���X�ɂ���Ȃ��悤 �F�O�������ł���B
�����Œg�����ߌ�A���_�J�̂���@����|�����A�@�̐A���ւ��̏����������B
���͂������@����Ђ̂��ւ́@�����т́@�������Â�͂�Ɂ@�Ȃ�ɂ��邩��
�@�@�@�@�@ �u�M�c�q (�Í��a�̏W)
2020.3.11
�����{��k�Ђ���9�N
�����{��k�Д�������9�N�������B��_�W�H��k�Ђ�9�N��ɂ́A�_�˂̊X�͕������Đk�Ђ̍��Ղ͖w�NJς��Ȃ� �悤�ɂȂ��Ă����B��Ԃ̈Ⴂ�͕����Ō������̂������������Ƃ��B�u�����ɂ͓�d�O�d�̈��S���Ă����Ĉ��S�v �Ɛ�`���Ă������d���u�z��O�̎��́v�ƌ������B���̌�9�N�o���Ă��A�����g�_�E���������q�F�����łȂ��A�R���v�[�� �ɂ���g�p�ς݊j�R���������o���Ă��Ȃ��B���S�����l����Ƌ}���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�ŋ�"���܂葱���鉘������ �����^���N�ɖ��t�ɂȂ���邩��C�ɗ���"���Ƃ��������邪�A���͂���9�N�Ԓ��߂ꂽ�̂�����A�����^���N�� 10�{�ɑ��݂��āA100�N�Ԃł�������������ׂ��ƍl���܂��B���ꂪ�����𗘗p���Ă����҂̋`�����ƍl���܂��B�����炭�́@�͂邯���قǂƁ@���������ǁ@�Ƃ߂Ă�����@�Ƃ���Ȃ肯��
����l (��ژa�̏W)
2020.3.8

�_�ˑ�w�ł̃e�j�X
���͒�N�ސE����A�_�ˑ�w�ݐE���Ƀe�j�X�����Ă������ԂƁA���T�y�j���̌ߌ�ɁA�_�ˑ�w�̃e�j�X�R�[�g�� �e�j�X���y����ł����B�������A�ߔN�ł͂��̒��Ԃ�����ɂȂ�A���Ԃ̑唼���ސE�҂ƂȂ����B�e�j�X�R�[�g�� �m�ۂ�����Ȃ�A����2-�R�N�́A���Q��ɂȂ����B����ŁA���k���āA���̎O���ŏI���Ƃ��邱�ƂɂȂ�A3��8�� ���̍ŏI��̃e�j�X��������B���E�̎Ⴂ�l���㎖���ǂ����邩�l���Ă�����邾�낤�B"�y�����e�j�X"�ɂ� ���Ԃ͏d�v�ł���B�ǂ����Ԃɏ��荇�������ƂɊ��ӁE���ӁB���ɂƂ��āA���N��3���őސE�㖞15�N�ł���B"�ސE��15�N�Ԃ����C�Ńe�j�X���y���ނ��Ƃ��o����"���Ƃ͖{���� ���肪�������ƂƊ��ӁE���ӂł���B���݁A���̓e�j�X�X�N�[���ŏT2��(1���1����30��)�e�j�X�����Ă���B�ŋ߂� 2���Ԉȏ�̃v���C�͌�ɉ�����̂ŁA1����30���̃e�j�X�͒��x�ł���B���N�̂��߂̃e�j�X�Ȃ̂ŁA���܂� �����ɂ�����炸�̂�т�y���݂����Ǝv���Ă���B
�E�̎ʐ^�͒�ɍ炢�����L�����C�`�Q�B
2020.2.29
�V�^�R���i�E�C���X��
���{���Ɖ�c�������ł�������Ύ��Ƃ̉�L���������V����2��28���[���ɂ������B����ɂ��ƁA1) 1��10�����_�ł��łɑ������̊����҂��������A�����ł̊������i�s���Ă����B
2) 2��3���ɉ��l�ɓ��`�����N���[�Y�D�̏�q�̂����Ǐ�̂łĂ��Ȃ�������q���A2��19��������ʋ@�ւŋA������̂́A ���{�����̏͂��͂�u���������߂�i�K�ł͂Ȃ��v�Ɣ��f��������B
3) �����g��̃X�s�[�h��x�点�A�����Ґ������炵�A�d�lj����i�߂邱�Ƃ��K�v�B
�Əq�ׂĂ���B
���̋L����ǂ�ŁA�ŋ߂̐��{�̑Ή��������ł����B��������2��2������t�x�݂܂ŋx�Z�ɂ����̂́A �����g�� �̃X�s�[�h��x�点��̂Ɍ��ʂ�����ł��傤�B�E�C���X�����̐��̕n�コ�E�����e�ʂ̏��Ȃ��͊����Ґ�(���� ����)�����炷�ł��傤�B�������^����ꍇ�Ɏ�f���ׂ���Ë@�ւ��Љ�Ă������������ �u���ׂ̏Ǐ��37.5���ȏ�̔��M��4���ȏ㑱���Ă���B�������邳(���ӊ�)�⑧�ꂵ��(�ċz����)������B�v �ł́A�d�lj����Ă���ɂȂ��Ă��܂��B
����܂Ő��X�̉������B�����w�E����Ă����������A�����I�����s�b�N���T���āu�C�O�̖ځv���ӎ����A ���m�ȃf�[�^���o���܂��Ƃ��Ă��邱�Ƃ����O�����B���ƁE�Ȋw�҂͐��m�ȃf�[�^���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���m�ȃf�[�^�Ɋ�Â��Ă����M�������B
2020.2.24

�����̒��j�̗��K
��q��w�Ŋw�Ԓ����̒��j��"�t�x��"���Ƃ����̂œޗǂ̉䂪�Ƃɗ��Ă��ꂽ�B21���̒���"���ꂩ��ޗǂɍs��" �Ƃ̘A���������āA�[���ɉ䂪�Ƃɒ������B22���͑���"��А�����"������ƒ��H�����܂��Ƒ��X�ɏo�����čs�����B
�䂪�Ƃɗ���ړI�̈�͎����Ԃ̉^�]���K�ł���B�Ƌ��͎擾�����������A�����Ԃ̉^�]�����Ă��Ȃ��̂ŁA �ޗǂʼn^�]���K������̂ł���B
23���A�����e�j�X�X�N�[������A���Ē��H���ς܂�����A�܂����r�^����֍s���A ��n�߂ɋ߂��̏Z��n�𑖍s�����B�������ꂽ��A��ʓ��H�ɏo�ď�ڗ����܂ōs���AU�^�[�����č��r�^����܂� �߂����B
24���A�������~�т֊ϔ~�ɍs�����Ƃɂ����B���Ȃ�U�������u�R���i�E�C���X�ɂ��x���ɂ�����Ȃ��悤�Ƃɋ���v �ƌ������B�����̒��j�̉^�]��"�䂪�Ƃ��猎�����~�т܂�(��25km)"�s�����B�������̍��G�n�_�ł͎����^�]�����B ���}���g�s�A�ɎԂ��߁A���X��"���݁E���ő��E����"���A�Y�Έ͘F���ŏĂ���"�݂�����"��t���ĐH�ׂ��B ���̌�A�~�ь����̎����������B�~��"�O���炫"�Ō����ł������B�r���̔��X��"�������Ɗ����`"�����B "������"�͍�N���Ȃ��������X�Łu��N�������܂����B���Ȃ����������ƌ����Ă����̂ł��y�Y�ł��v�ƌ�������A ��l���u����Ȃ�A���܂��������܂��B�v�ƌ����Ă��ꂽ�B�A����������̍��G�n���߂��Ă���́A�����̒��j�� �^�]���ēޗǂ̉䂪�Ƃ܂ŋA�������B�����u�����N������ɂ�������炸"�^�]�͏��"�ł������B
2020.2.20
��c�����Y����̍���
�_�ˑ�w�����Ǔ��Ȃ̋����ł����c�����Y���N���[�Y�D�u�_�C�������h�E�v�����Z�X���v�̌���� �K��āA�����Ǒ�̐��ƂƂ��Ă̈ӌ���YouTube�Ɍ��J����܂����B�����q�����āA�Ȋw�҂Ƃ��� �̗��h�ȑԓx�Ɋ������܂����BYouTube�̉摜�͍폜����܂������A����Ȕ������ĂсA�����̃C���^�r���[���Ă���������l�ł���B ���g���������Ă��鋰�������Ƃ����̂�"�e���r��c"�̗l�ȃV�X�e�����g���Ă̂��̂ł���B�Ȋw�҂Ƃ��� �̗���ŗ����Ɍ���Ă���������B�ς�҂Ɋ����������ĉ�����B
���������Ⴂ�l�����{�ɂ��邱�Ƃ��������v���B�ߘJ�ƐS�J�œ|��Ȃ��ł��������ˁB
���ӑ����O�W�O���́@���B�@�킪�����܂Ɂ@�����@���点���܂�
�`����t�@(�V��)
2020.2.15
�U��
���Ȃ́u�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��x���ɂ�����Ƃ����Ȃ�����l���݂̒��ɓ���ȁI�v�ƌ����B ���́u�����܂Ŋg��������A���߂āA�̗͂ŏ��邵���Ȃ��v�ƎU���ɏo���B�ޗnj����ɂ� �������b���l���吨����B�唼�̓}�X�N�𒅗p���Ă���B���̓}�X�N�������B���O�ɂ͂������̏����p�̒|��50�{�قǕ��ׂĂ������B�@�ؓ��A����R�_�ЁA�t����A�Љ��ւ� �i�B�ޗǍ��������ق�"���ʓW�u������V�\�k������̃J�~�\�v�A���ʒ�u�������v"���J�� ���Ă����̂œ��ق����B���{������D�ꂽ������V�����W�߂ēW�����Ă������A���ٗ�1500�~�͍��� ����Ǝv�����B
��������́@�킩�Ȃ܂��ށ@���������́@�������̂͂�́@���ӂ��₭�߂�
�`�{�l�� (�E��a�̏W)
2020.2.1

�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��x��
�ޗnj����͒����̏t�ߑO�A��������̗��s�҂������A���G���Ă����B"�Ⴂ�v�w�Ǝq���E���̗��e"�炵���l�B ���ڗ����A���́u�t�߂��@�Ɋό����ȁB�����l�͐e�q�̒��������ȁI�v�ƁA�S�������܂�z���Œ��߂Ă����B �Ƃ��낪�A�����A�U���œޗnj������������A�����l�ό��q�̐����������Ă����B�����āA�����Ȃ��ό��q �̑唼���}�X�N�𒅗p���Ă����B���̑����E�E�E�������܂�̂�ؖ]�������ł���B�^��@�̔��ɓ\�莆���������B�u�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��x���̋���Őf�ÁE��������]���ė��@ ���ꂽ���͒��ɓ���Ȃ��ł��������B�O�̃C���^�[�z���ł��b���������B���@�ł͐f�f�E�����͒v���܂���B �f�f�E�����ł���a�@�����Љ���Ă��������܂��B�v�ƁB�@��@�ɍs���O�ɓd�b���Đq�˂������ǂ������B
����R�����{�ł͉�y�̕�[���s���Ă���(�E�̎ʐ^)�B�ۑ��~���̔~�͌����ł������B
���ɂ��Ƃ��@�˂����ɂ���@�킪��ǂ́@�킩���̂ނ߂́@�͂Ȃ����ɂ���
���{�L�� (�E��a�̏W)
�@
2020.1.25

�ᑐ�R�Ă�
18:15����ԉ��ł��グ���A�t����Ђ̑�Ƃ�ǂō̉��ꂽ��_���ڂ����傩������� �����ɉ��ڂ��āA18:30�ɓ_����܂����B���̉Ƃ̓�K�ɏオ��Ɠ��̓����������邵�A �ԉE�ᑐ�R�Ă����ς邱�Ƃ��ł��܂��B�ԉ̉����ƁA�J�����������ē�K�ɏオ��܂����B �E�̎ʐ^�͂��̈ꖇ�B���N�́A�X�X�L���������Ă����̂��A�ƂĂ��ǂ��R���Ă��܂����B�₩���Ƃ��@�����͂����Ȃށ@�������̂��@�����͂�̂ЂɁ@�܂�������Ȃ�
�p������ (�V�Í��a�̏W ����� �t��)
2020.1.23

�~�̉�
�g�����������̒��A�U���ɏo�������B������t���쉀�n��ʂ�A�ۑ��~���֍s�����B���{�̔~�̖� �Ԃ��炫�n�߂Ă���(�E�̎ʐ^)�B�����̏t�߂�24������n�܂�l�ŁA�ޗnj�������������̊ό��q����w �����Ȃ��Ă����B�����Ƃ߂ā@������炴��ށ@�ނ߂̂͂ȁ@����Ȃ������݁@�����Ȃ�������
�}�͓��Z�P (�E��a�̏W)
2020.1.11
���g���I�@����M���R���T�[�g
�����ɏZ�ޒ����Ɋ��߂���"���g���I�@����M���R���T�[�g"�ɍs�����B���g���I�Ƃ����̂� �H���F��(�s�A�m)�A���싿�q(���@�C�I����)�A�ɓ��T(�`�F��)���ꂼ��̓�����AOI����Ƃ������������A ���ꂼ�ꐼ�{���Z�A���T���Z�A�ޗǍ��Z���o�āA�����Y�p��w�Ŋw�сA��67��~�����w�����ۉ��y�R���N�[�� �̃s�A�m�O�d�t����ŗD��(���{�l�c�̂Ƃ��ď��̎��)���ꂽ�B�ɓ��T������o�g���Ƃ����̂ŁA ������j����"����M���R���T�[�g"����悳�ꂽ�Ƃ̂��Ƃł������B14:00�J���ł��������A���Ƌ��Ȃ�13:10�ɉ��ɒ������B�������Ԃ�����̂ŁA�����߂��ɂ��钷�|��(�����V�c ����ɂ��s�����)��K�ꂽ�B�R���T�[�g�͎O�l�̏Љ��A�G���K�[�̈��̈��A�A���t�}�j�m�t�̑O�t��op.3-2 ���A�T����T�[���X�̔����A�T���T�[�e�̃c�B�S�C�l�����C�[���A�x�[�g�[���F���̃s�A�m�O�d�t�ȑ���op.1-1 ���y�͂Ƒ�l�y�́A�����f���X�]�[���̃s�A�m�O�d�t�ȑ���op.66�S�y�͂����t���ꂽ�B�Ⴂ�O�l�̔��͂��� ���t���y���ނ��Ƃ��o�����B
2020.1.3
���b�L�[
�P��ŁA1��2���ɂ͌̋��̊��֎s�ɍs���B��T�ԑO�ɓV�C�\������ēV�C�͗ǂ������Ȃ̂ŁA���̋A�H�� �`���b�g��蓹�����āA�匴����̓��{�匴�قɈꔑ���鎖���v�悵���B�d�b���Đq�˂���u1��4���܂Ŗ����ł��v �Ƃ̂��Ƃł������B�L�����Z���ɂ��������҂��āA����d�b�����������Ԏ��ł������B1��1���Ƀ_������ �d�b������u�L�����Z��������܂����̂ŏh�����������܂��v�Ƃ̂��Ƃł������B���b�L�[�E���b�L�[�I���Ȃ��u���s����v�ƌ������B1��2��8:00�ɉƂ��o�āA11:00�ɉƂ��p���ł��ꂽ�����ɒ������B�킪94�˂̕�� �ʓ|���݂Ă��Ă����B���X�A����ɂ����u���Ȃ��͂ǂȂ��ł����H�ƕ������������A�������Ȃ��������F������ ���ꂽ�B���O�Ōo����������A����Ƌ��ɖ��̉Ƃɍs�����B�����ɖ߂��Ē��H����y���ɂȂ�����A����Ƃ��� ���ƈꏏ�ɕ�Q��ɍs�����B���̌�A����ɕʂ�������A�f��(�S��̒�)��֍s�����B�u��N�̂��~�ɉ�Ȃ��� ������A���̋@��ɉ���Ă����Ȃ��ƁE�E�E�v�ƌ�������A�f���́u�E���A�悭���Ă��ꂽ�B�N�͍���A�Ď��� �Ȃ����E�E�E�v�ƁB�c�����̎v���o�b���b�����āE�E�E�ʂ�������A��̐��Ƃł�����Z�s�̏]��̉Ƃ֍s�����B �]�������Ă����B����}���ŁA��̕�Q��ɍs�����B
15:00���ZIC��蓌�C�k�������ԓ��ɓ���A17:00���{�匴�قɒ������B�u�w�ǂ̕����`�F�b�N�C���������݂ŁA �����炾�Ɨ[�H��19:30����ɂȂ�܂��B���H��7:00���炩9:00���炵���Ă��܂���B�v�ƌ���ꂽ�B�v�� �������ς܂��ĕ����ő҂��Ă���ƁA19:00�ɓd�b������A�u�e�[�u�����܂�������A������ǂ����I�v�ƁB �H��A�ēx����ɓ���A22:00�A���B
1��3��7:00�N���B�������Ɖ���ɓ���A9:00���H�B�}�t���j���V�Ƃ����̂�"�����������ƎG��"�ł������B ���{�匴�ق͐���ڂł��邪"����̓����ǂ��E�����͎��̗ǂ��������ȖڂŔ�������"�̂ŋC�ɓ����Ă���B ��������Ғʂ�Ŗ����E�����B10:00�`�F�b�N�A�E�g�B�ɉ�X��(����163)���o�Ē���IC���疼�㍑���ɓ���A �R�YIC��茧��80���o��14:30�ޗǂ̎���ɋA�������B�r���A�R�Y���k��ɂ��銙�q���̖��R��"�@�y�n��" ��q�ς����Ă����������B����ɁA��q�k�̒��ԏ�(450m)�ɎԂ��߁A�_��R(618m)�R���̓W�]��܂œo�� ���{�匴�قŗ[�H�̊��߂��̎c��ō���Ē��������ɂ����H�ׂ��B �@
2020.1.1

2020�N���U
�V�N���߂łƂ��������܂��B�F�l�̂����K�����F��\���グ�܂��B���N����낵�����肢���܂��B���ȂƎ��̓�l�����̐����B���G��(�卪�E���������Đ����������X�`�ɏĂ��݂�����)������A 10:30���w�ɏo���B�����_��(��������A593�N�n��)�A��������~���A�t����ЁA����R�_�ЂƎQ�q���A 12:30���厛�@�ؓ��O�̒����ł��˂��ǂ�Ƃ�����H�ׂ��B�����ŁA���厛���A���厛�啧�a �ɎQ�q���A�啧�a�ŊG�n������������15:00�A����B����13,372�Ō��\��ꂽ�B
�E�̎ʐ^�͍P��̉䂪�Ƃ̏��̊ԁB�Ԋ�͖@�����̌ÍށB�Ԃ�HK���B�|�����͍������(�@����103���ǎ�) �ɂ�鏑"�_���䖳�S"�B
���͌���78.3�ł����A���A�l�ŁA���݂Ȃ�̖�����ނ��Ƃ������A���C�ɉ߂������Ă��������Ă���܂��B 2019.1.24�ɒɂ߂��E�r�̒ɂ݂���N���ɂ͖����Ȃ�܂����B�������A�Α����ɘV�����Ă��āA��̏�ɍ��� �Ǝ�Őg�̂��x���Ȃ��Ɨ����オ��܂��A�X�^�R�����邱�Ƃ��o���܂���B�ł��A���������ƂɁA�܂� �e�j�X�����邱�Ƃ��o���A�T2��e�j�X�X�N�[���Ŋy����ł��܂��B�����A������A���_���ɂȂ邩������ �܂��A�o���邾���A���̍K���̏�Ԃ��������Ƃ��F���Ă���܂��B
2019.12.25
�䂪�Ƃ̑��z�����d
�����̌������̂��_�@�ɉ䂪�Ƃł͑��z�����d���u�������B�ݒu���Ă���5�N�Ԃ̃f�[�^�� 2016.5.19�̃u���O�ɋL�ڂ����B���̐��\�ɖ��������̂ŁA�䂪�ƂŎg���d�͂̑S�Ăz�����d�� �܂��Ȃ����ƁA2016�N9���ɑ��z�����d���u�݂����B���̌�2�N�Ԃ̃f�[�^��2018.12.26�̃u���O�� �L�ڂ����B���̌�̈�N�Ԃ̃f�[�^�������Č��ʂ��L�ڂ���B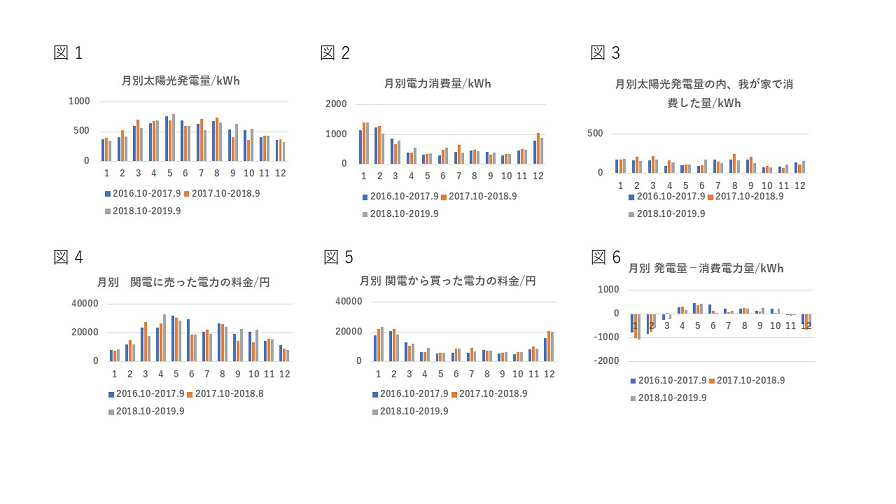
���ʑ��z�����d�ʂ�}1�ɁA���ʓd�͏���ʂ�}2�Ɏ����B���̂P�N�Ԃ̑����z�����d�ʂ�6519kWh(��N��6597kWh, �P��N��6602kWh)�ł������B���d�͏���ʂ�7585kWh(��N��7919kWh,�P��N��6976kWh)�ł������B �䂪�Ƃ̓I�[���d���ŁA��g�[�E�����E���C�E�Ɠd�E�Ɩ��S�ēd�C�ł���B�S�d�͏���ʂz�����d�ł܂��Ȃ� �Ƃ����ړI�͒B�����Ȃ��������A�܂��܂��ł���B
���z�����d�ʂ̓��A���d���ɉ䂪�Ƃŏ����d�͂͑��z�����d�̓d�͂��g�p����B���̗ʂ�}3�Ɏ����B �c����֓d�ɔ���B���ʂ̊֓d�ɔ������d�̗͂�����}4�Ɏ����B���d���ł�����Ȃ������E��Ԃ̎g�p �d�͂͊֓d���甃���B���ʂ̊֓d�Ɏx������������}5�Ɏ����B2017�N10������2018�N9���܂ł�1�N�Ԃ� �֓d�ɔ������d�̗͂�����229,776�~�A�֓d���甃�����d�̗͂�����134,274�~�ł������B �Œ艿�i���搧�x�̌_���10�N�Ԃł���̂ŁA���ƂP�N�B���̌�͈����Ȃ�̂ŁA���������̉���͏��� �ނ��������H
"���������̉��������C�ɗ���"�Ȃǂƌ����Ă��邪�Ƃ�ł��Ȃ��B"10�N�Ԃʼn����������^���N�����t�ɂȂ�"�� �����Ă��邪�u100�N�ł��A200�N�ł������^���N�݂��Ē��߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝv���B ���z�����d�͌��q�͔��d�����S�ł��芎�R�X�g�ʂł��D���Ă���Ǝv���B
2019.12.5
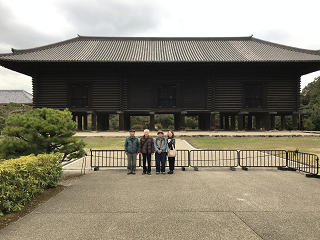
�ޗǂōĉ�
���嗝�w���ʎq���w�������̐�yY����v�ȂƓ�������T�N�Ƃ�2018.4.16�ɕ��䌧�̕���R�ɍs�������A ���̌�v��������Ă��Ȃ������B�v���Ԃ�Ɂu�������֍s�����v�Ƃ������ƂɂȂ������u�̗͂������� ���ĎR�o��̓L�c�C�v�Ƃ������ƂŁu�ޗǂōĉ�v�Ƃ������ƂɂȂ����B11:00�ɋߓS�ޗljw�ɏW���B���Ȃ́u�����ɂ��v�̂ŕs�Q���BY����v�ȁAT�N�Ǝ���4�l�œޗnj����� �U�邱�Ƃɂ����B�������T2,3������U���H�ł���B�悸�A�������������U�A�������a�� ���ق����BY�����T�N�����������Ȃ��Ă���̂ŏ����傫�Ȑ��Řb���Ă�����A�W���ɒ��ӂ��ꂽ�B �q�ς��I���ĊO�ɏo����AT�N���u�ޗǂ͏��w�Z�̉����ȗ���A����̒r���߂��ɂ���悤������s�� �����v�ƌ������B52�i�̊K�i������Č����ɍs�����BT�N�́u�Ȃ��A����ȏ����������̂��v�ƁB
�߂��̂��ǂŒ��H��ۂ�����A�t����Ј�̒������o�āA�Q����i�ނ�"�t����Ў�{����Ղ�" �̏������i�s���ł���A"�䗷��"�ł�"�_�a"�̍��i���o���オ���Ă����B��Ζ�A���厛����A�啧�a���A �u�������o�āA���q�@���q(�E�̎ʐ^)�֍s�����B���̌�A�]�Q��A�����V�c�˂��o�āA�䂪�Ƃɗ��� �����������B18:00�ߓS�ޗljw�ŕʂꂽ�B�y��������ł������B
2019.11.20

����ƊI
���N���I�̋G�߂ɂȂ����B���挧�̊�䉷��̏h���C�ɓ����Ă���B�Ԃōs���̂ŁA��̍~��O�� �s���˂Ȃ�Ȃ��B���́A�ʏ�A�V�C�\������Ă���A���O�ɗ\�邪�A�I�̋G�߂ɂ͒��O�\�� ����ɂȂ��ė����̂ŁA�ꃖ���قǑO�ɗ\���B11��18���̒���̓V�C�\��́u�ߌォ��J�v�A �K�b�J�����Ȃ���o�����čs�����B10:30�ɉƂ��o�āA14:30�����߂��̒��ԏ�ɒ������B�O��ʂ����Ȃ������W��263m�̒����v���R���ɓo��ړI������������ł���B���ɂ��J���~�肻���ȕ��͋C�� ���������A���J�Ȃ���v�ƎP�������ɂ��āA�R���ڎw���ēo��n�߂��B�o����̕W����40m�Ȃ̂� �W����220m��o��}�o�ȓ��ł���B�܍��ڂĒ��]�ǍD�ƂȂ蒹��̊X����]�ł����E�E�E���A���̍����� �J���~��o�����B���x���A�����Ԃ������Ǝv�������A�䖝����15:10�R��̊� �V��E��(�E�̎ʐ^)�ɒH�� �������B�������A�J�ʼn��E�̒��]�͖��������B�J�Ŋ���₷���Ȃ����o�R�H��p�S���ĉ���A16:00�����o���_�� �A�������B
17:00��䉷��̏h�ɒ������B�����A����ɓ������B���̏h�̉���͂��炵���B�����������̉�����N���Ă��邵�A ��̓�������ł���B���a�̕��͋C���ǂ��B18:00����[�H�B���t�I�Â����R�[�X�����\�����Ē������B ���Ƃ����Ă�"�I���ǂ�"�Ǝv���B����"�ʂ�������������"�Ǝv�����B����ɂ�"�ʂ�����"�Ƃ��肢���傤�Ǝv�����B ���̔N��ɂȂ��"���Ȃ�"���ǂ��B
11��19��7:00�N���B����ɓ�������A8:00���H�B9:30�`�F�b�N�A�E�g�B�u����łW��ڂ̂��h���ł��v�� ����ꂽ�B�ƂĂ��ǂ��h�ŁA�喞���B
11:00�A�n�����A�����ɓ����B���J�̒A�n�����A�������U��B12:00�o���A���H�͖����B15:30�ޗǂ̎���ɖ����A�������B �ޗǂ͉����B
2019.11.16
���w�Z�̓�����
11��15�����w�Z�̓�����A���֎s�q�m�ŊJ�Â��ꂽ�B���̒ʂ����q�m���w�Z�́A�����P�w�N�P�N���X�ŁA �_�Ƃ̎q�킪�唼�̏��w�Z�ł������B��������45?���� �U�N�ԓ������Ԃ� �݂��ɉe������ �w�їV�B ����ŁA�ƂĂ����������A�d�b�A�����A���ŎQ�������Ă����������B7:30�ɎԂʼnƂ��o�āA11:00�� ���ɒ������B11:30����J�n�Ƃ������Ƃ������̂ŁA�����ɂ��Ƃ���āA��̉Ƃ֍s���A���̌��Q������āA 11:25���ɒ������B���������������������Ă����B21���̎Q���҂ł������B���������炪�����Ȃ��B���̎҂� 15���Ƃ̂��Ƃł������B�Ȃ�ƁA�O���̈ꂪ�S���Ȃ��Ă��܂����B���͑O�����玕���ɂ�ł���"������Q���𒆎~�ɂ��悤����"�Ɩ��������A���������ʁX�ɑ��������ƁA�ɂ��� ���炦�ďo�����čs�����B����҂���ɂ� 18:00�ɐf�×\������āE�E�E�B
�ŋߑ��E�����l�B�ɑ����Ȃ������̂͂炩�������A���������������Ɖ���̂͊����������B���͎����ɂނ̂� "�Ȃ�Ƃ��Ă��f�×\�Ԃɂ͓ޗǂɋA�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�"�B�s���̏a���l���āA14:00�O�ɁA�F�ɕʂ���������B �u�ǂ����@�ǂ����@�F����@�����C�ł��Ă��������v�ƋF��Ȃ���E�E�E�B
2019.11.14

�e�j�X���h�@�F��H
�_�˂̃e�j�X���Ԃ�11��12��10:00�ɓޗnj�����w�ɏW�������B�ԂŔA�ܞ����o�ē��̉w"�g��H�哃"�� �x�e�����B13:00���̉w"�\�Ð싽"�Œ��H�A�U��������H�ׂ��B�������������B14:00�F��{�{��ЂɎQ�q�B���̌�A ����22�N�̑吅�Q�܂ŌF��{�{��Ђ̂��������Вn"���(������̂͂�)"�֍s�����B"���"�͌F���E������ �̍����_�̒��F�ɂ���B�F���̐쌴�͍L��Ŕ������B���̐쌴�Ő��E���A�F���Ŏ��A�g�𐴂߂��B ������"���"�ɎQ�q�����B�h�ɂ̃O���[�������h���c�@�_�扷��ɒ�������17:00�ł������B���Â��Ȃ��Ă����̂� �e�j�X�R�[�g�̗\����L�����Z���B����ɂ����Ă���[�H�B�h�ɂ̃��X�g�����͋x�݂ł������̂ŁA����̋i���X�� �[�H�B�g���J�c��H��H�ׂ��B21:00�ēx�����B�I�V���C����������������ς邱�Ƃ��o�����B22:00�A���B13�� 6:30�N���B����ɓ�������A8:00���Q�����p���Œ��H�B�����e�j�X������9:45�F�쑬�ʑ�Ђ֍s�����B �F�쑬�ʑ�Ђ̋����ɂ̓i�M�̑���������B11:00�F��ߒq��ЂƗאڂ���ߒq�R�ݓn���ɎQ�q�����B ���̌�A�ߒq���@�_�ЂɎQ�q���A13:00���̉w"�������Ƌ��Y��"�Œ��H�B"������IC"���A�ߋE���I�����A ��a���A���ޘa�����o��19:00�ޗǂɒ������B�F��O�R������"�y������"�ł������B
2019.11.07

�M�q�W����
�������o�g�̃e�j�X���Ԃ���A���N����R�̗M�q�����B���N�͕s�삾�����ƌ����Ȃ����R�����ĉ��������B ��������ŁA����"�M�q�W����"��������B������2015.11.10�̃u���O�ɋL�ڂ������A���͂�������� �K�v���Ȃ��B4kg�̗M�q��1.5kg�̃O���j���[������E�̎ʐ^�Ɏ��������̃W�������o�����B�ꃖ���Ɉ�r���B ��N�ԁA�����g�[�X�g�ɕt���Ă����������Ƃ��o����B�@�@�@�q�d�̑��҂͉�����ā@�@�@�@�����L��(1876-1952)
�@�@�@�q�d�̑��҂͉�����č�������炭�A
�@�@�@��������(�܂�)�����͒�(����)����������(�ЂȂ���)��@�A
�@�@�@�S�キ���l����ӂ����Ђ̋��
�@�@�@�_�A����(�͂₿)�A�P�͂ʂ����ɓق��ƁB
�@�@�@���ق��ƁA�Ȃ��₯��N���قƂ���A
�@�@�@�Ζq�A����̌��̂��˂���
�@�@�@�Ȃُ_���������̂킪�˂̔g���A�|�|
�@�@�@����@���ɌN�͕�����(��)�����ӂ�ށB
�@�@�@�������Αő�����(������)�̂͂Ă�
�@�@�@����(��������)�ɍ���(���Ȃ�)��Ă䂭���̂̂����A
�@�@�@�Q���Ă��܂�ӏb���ƂƂ��߂��܂͂߁A
�@�@ �@���̉e���N��ق�Ă䂯��g��
�@�@ �@�����闷�Ɉ�F�̕��J���p�A�|�|
�@�@�@�悵����A���̉Q�A�A��(����)�̗��ɁB
�@
2019.11.3
��~���Ɩ@���Z�c��
�������́u�k�~���Ɠ�~���̓������ʌ��J�v�Ɋ֘A����u���11��3����4���ɋ����������ɂ��� ��������قŊJ�Â����B11��3��13������u��~���Ɩ@���Z�c���v�Ƃ����e�[�}�ŏ������(���C�w����w�y����) ����ɂ��������������B���� "�V�F�t�Y�L�b�`��"�Ő�c�S��(�t�����`)���Ɛ��R�p��(�C�^���A��)���� �R���{���[�V�����ɂ�郉���`(2000�~)��H�ׂ���A��������قɍs���A�u���u��~���Ɩ@���Z�c���v��q�������B��~����813�N�ɓ����~�k�����̖������F���Č��Ă����p�~���ł��邪�A1180�N���d�t�ɂ���s�ē��ŏĎ������B 1189�N�ɍČ�����A�Ď������@���Z�c�����A�l�V�������A�@���Z�c�������N�c���ɂ�萻�삳�ꂽ�B �s��㮍��ω���F�����͈ȑO�̑����Č�����悤�ɍ��ꂽ���A�l�V�������A�@���Z�c�����͊��q����f���� �͋����쑢�ŁA�@���Z�c�����͕s��㮍��ω���F�ɂ��F�肷��p�ō���Ă���Ƃ̂��Ƃł������B ���̌��x��~���͉Ђɑ����Ă��邪�A�{���s��㮍��ω���F�����A�l�V�������A�@���Z�c�������ׂĂ��A ���q���̂��̂ł���Ƃ̂��Ƃł������B
2019.10.26
�V�F�t�t�F�X�^�Ɛ��q�@�W
�ޗǍ��������ق̐��E�������̓��ɂ���L��Łg�V�F�t�F�X�^�F�ޗǂ̐H�ނ��g�����V�F�t�ɂ�闿���̍ՓT�h ��10��26������11��4�����J�Â����B�L���V�F�t���{�i�����ł��ĂȂ�"�V�F�t�Y�L�b�`��"�A �{�̖����H�i�ɏo���"�}���V�F"�A�Ηq���g�����Ă�����"�s�b�c�@"�A �J�t�F���j���[�����̂��ٓ�������"�V�F�t�F�X�^�J�t�F"�A�{�i���X�g��������H�X�̗��������[�Y�i�u�� �Ɋy���߂�"�V�F�t�F�X�^����"��������B����11��ڂ����������A���͍�N "�V�F�t�Y�L�b�`��"�ŐH�ׂ������� �������������̂ŁA�����o�����čs�����B"�V�F�t�Y�L�b�`��"�̗����̓L�b�`���J�[�ŁA�V�F�t�͓��ւ��� ���ꂼ��قȂ������������B�����̗����͂���قǔ��������Ȃ��āA���͏����������肵���B�u��V�P�q�@�W�v���ޗǍ��������ق�10��26������11��14�����J�Â����B���́A�g�V�F�t�F�X�^�h�ŐH����������A �ޗǍ��������ق̕��֕����čs�����B���q�@�W������ł��Ȃ���������ق����Ē������Ǝv���āE�E�E�A�Ƃ��낪 �E�E�E�Ȃ�ƁE�E�E�K���K���E�E�E30�l��������ł��邾���ł������B"���߂�"�Ǝv�����ق����B ����͂S�P���i���o�W�S���j�̕��o�i���Ă������B�ӌ�痚�i�̂��̂��炢��j�A���h���핿���F�i������ł�̂�������j�A �S�U����u���ї��������i�Ƃ肰�����̂т傤�ԁj�v�A�����h�[����F�U��(�������傤���̂�����Ђ��傭�̂���)�A �Ԏ����U�،�~�q(�������Ԃ�ڂ��̂���)�A�g�坛�Z��(����������̂��Ⴍ)�E�Ή坛�Z��(��傭������̂��Ⴍ)�A �������^�՛�����(�ӂ���炱�������т傤�Ԃ��傤)�A�畞�䊥�c��(�炢�ӂ�����ނ肴��)�A ���╽����(����Ђ傤����)�A����Ԕ�(����̂���)�A���n�ʊG���p�{(�ӂ������̂͂�������)�A �Ԏ����U�،�~�q(�������Ԃ�ڂ��̂���)�A���픠(��ł�̂͂�) �Ȃǐ��q�@�̐��藧���Ɠ`���Ɋւ���A��ɂ��\�����q�ς��邱�Ƃ��o�����B �W���ɍH�v������Ă���A�y���ނ��Ƃ��o�����B
���N�͓������������قł��A10��14������11��24�����䑦�ʋL�O���ʓW�u���q�@�̐��E�v���J�Â����B���̂��߂��A �ޗǍ��������قł́u��V�P�q�@�W�v�́A��N�Ɣ�ׂċĂ��Ă������Ɗϗ��ł����B
2019.10.17

��~���@��ʎ�o�]�lj�
������ ��~���͐����O�\�O���ω�����9�ԎD���ł����A���N10��17���ɑ�ʎ�o�]�lj���C����܂��B �N�Ɉ�x�̊J��(9:00-17:00)���s���A13:00�����ꎞ�Ԃ̖@�v���s���܂��B���́A���H��A�o������ �s�����B���ʂ̔����J�����A�@�v���s���Ă���(�E�̎ʐ^)�B�@�v��A���ʂ̔��͕߂��A�k�ʂ̔��� �J�����A��~���̓����ɓ���Ă����������B�{���s��㮍��ω���F�����A�l�V�������A�@���Z�c�����i�S�č���j ���J���Ă��āA�����Ǝv�����B��~���̊J���͒ʏ�10��17�������ł��邪�A���N��10��17������11��10���܂ŁA�k�~���Ɠ�~�������ʊJ������܂��B �k�~���ɂ́A�{�����Ӕ@�������A�����i�ނ��Ⴍ�j�E���e�i������j�����A�l�V�������i�S�č���j���J���� ���܂��B
�k�~���̔q�ς͌���ɂ��āA���͓��厛�ɍs���A�v���Ԃ�ɉ��d���ɍs���A�l�V�������i�S�č���j��q�ς����Ă����������B ���̌�A����������Ɋ���āA���g���A�g���o���A�ؖȁA�������������ċA����B
2019.10.6
�_����
�@�@�@�@�@�@������a(��܂�)�ɂ�����܂����@�@�@���c���(1877-1945)�@�@�@�����A��a�ɂ�����܂�����
�@�@�@���ܐ_�����A
�@�@�@���͗t�U�蓧(��)���_����(���݂Ȃ�)�̐X�̏��H(���݂�)���A
�@�@�@�������I(�Â�)�ɔ��ʂ�āA��(��)����������ցA
�@�@�@����(�����邪)�ցB���Q(�ւ���)�̂��ٖ�A����(��������)��
�@�@�@����(������)�̊C�Ƃ������A
�@�@�@�o��(���肢)�̑��̂��͔�(����)�݁A�������̒W(����)�ɁA
�@�@�@���ɂ���(��)�̒�(����)�̌�o(�݂��₤)�̉���(������)�����A
�@�@�@�S�Ϗ���(�����������)�ɁA��(����)�Еr(��)�ɁA���`(���݂�)�̕ǂ�
�@�@�@������(��)���钌������̂������܂ЁB
�@�@�@���(�Ƃ���)�������Y(����)�̋{�A�֓a�[(���݂ǂ̂ӂ�)��
�@�@�@��(��)������鍁���A���Ȃ���̔��d��(�₵�ق���)
�@�@�@����(���܂�)���P(�݂�)�̂܂�͂��ɁA
�@�@�@�������͐�(��)�͂߁B
�@�@�@�V���H(�ɂЂڂ�݂�)�̐ؔ�(�����)��
�@�@�@�Ԃ�k(������)�t������ɁA�ق̂߂����Ȃ�
�@�@�@�����Ƃ��m��ʐÉ�(���Â���)�̔�(����)�����F(�˂���)�ɁA
�@�@�@�ڈ�(�߂���)���́A�ӂƂ������܂��A���O(���т���)��
�@�@�@�����(��)�̎}�ɁA��l(���Ђ���)�̊y�l(�����т�)�߂���
�@�@�@�Y(��)��݂��B���H�g(����)���낳�̂Ƃ�����A
�@�@�@�t(��)�̕Y(������)�ЂƂЂ邪�ւ�A
�@�@�@?(�܂�)�ɁA��(��)�̊�(��)�ɁA�\�\�����܂���̖@�q��(�ق�����)��
�@�@�@��(��)�̂��̂��A�[���[(�䂤�ł�ӂ�)����(����)�Ԃ��
�@�@�@�njo(�ǂ��傤)��A�\�\�����A��(����)������A
�@�@�@�����날�肫�̍�(��)��l��
�@�@�@��(���܂���)�ɂ�����(��)�ݓ���߁B
�@�@�@���͖�(��)������āA��(����)�Ƃт�
�@�@�@���ɂ����߂����a�̗[�늦(�䂤�ɂ͂���)�ɁA
�@�@�@������(��)��䂭�����t(�Ђ����)��
�@�@�@���P��(�ʂ��)�A�|(��)�A��(���ӂ�)�A����������A�t�A����(�͂т�ڂ�������)
�@�@�@��(�݂�)�䂫�̂����߂��A��(����)�ɕ����ق���
�@�@�@�Ή��L(�����킽�ǂ�)�̂������܂ЁA�U�肳������A
�@�@�@����(����炬)��A��ւ̎K(����)�ɓ���(�����)�����A
�@�@�@�ԂɏƂ�Y�ӗ[(���)�Ȃ��߁A
�@�@�@���Ȃ����]��(����)�̐�(����)�Ȃ��ɒn�ɉg(��)���͂ւ�
�@�@�@���̂��݂̊w��(�������₤)�߂�������(��������)�݁\�\
�@�@�@������a�ɂ�����܂�����
�@�@�@�����_����(���ӂ��݂ȂÂ�)�A���̂�ӂׁA
�@�@�@��(�Ђ���)������̎b(����)�������A
�@�@�@�m��܂����A�g�ɁB
�\��(�_����)�ɂȂ��Ă��������������Ă��܂������A�Q���������Ȃ��ĊO������̂����K�ɂȂ��Ă��܂����B ����A���͓��厛�A�t����Ђ�ʂ��āA�V��t���킫�ɂ���"���]�g�L�O�ޗǎs�ʐ^���p��"�ɍs���܂����B �J�Ò���"���]�g�L�u�قƂ����܁v�W"��q�ς����ĂĂ��������߂ł���B��30�_�قǂ̕����ʐ^���W���� �Ă������B���͑�ϋ������������B�ǂ̕������A���x���q�ς��Ă��镧���Ȃ̂����ǁA�ʐ^�ł���Ȃɂ� �\���ł���̂��ƁE�E�E����A�ʐ^�����炱���̏œ_���i����"�قƂ�����"�E�E�E�ɋ������������B
�A��ɐV��t���ɗ���������B�V��t���̖{���͗ǂ��B���̓V��̖����{�����̉~�`�̓y�d�̒��S�ɖ�t�@�� �����A���̎���ɏ\��_����������q���Ă���������B�ʐ^���ǂ��������A�������Ŕq�ς���̂͂܂��i�� �ł������B
�C����ǂ��Ȃ��Ă��܂����B�A�����A���m���A�Ós�ޗǂ�Ƃ��K��Ă��������B
2019.9.29
�H�̃T�V�o�T����
��̈��ł���T�V�o�́A�t�ɓ���A�W�A������{�ɔE�ɐB���A�H�ɓ���A�W�A�֓n���čs���B�H�̓n��� ���ɂ́A�傫�ȌQ������̂�"�T�V�o�̓n��"�Ƃ��Ēm���Ă���B���{�쒹�̉�ޗǎx����"�H�̃T�V�o�ܞ��s�T����"�� 9��29���ܞ��s�T���l�̐X�����ŊJ�Â��ꂽ�B����"�H�̃T�V�o�ܞ��s�T����"�ɎQ�������Ē������Ǝv���A��T�Ԓ��O����V�C�\��߂Ă����B9��29���̓V�C�\��� "�J"�ŁA�O���̉J�_���[�_�[�̗\�z�ł��u�ޗǁE���C�n����"�J"�v�ł������B����őO��A�u29���͋x�����v�Ǝv���A�������B 29��7:00�N���Ă݂�ƁA�����A���z���P���Ă����B���́u�W������8:30�ɂ͊Ԃɍ���Ȃ����A9:00���ɂ͒�����B �Q�����悤�v�ƌ��S���A���p�̑o�ዾ�A�ϑ��p�̈֎q�A������p�ӂ��A8:00�ɉƂ��o���B���ޘa�����o���Čܞ��s�ɂ� �ޗǂ���Z���Ԃōs����悤�ɂȂ����B9:00�ܞ��s�T���l�̐X�����ɒ������B30�����̎Q���҂��u���~�i�[�E�o�ዾ�ŋ�� ���߁u�钌���B15,16,�E�E�E23�H�v�Ƌ���ł������������B���͎Ԃ���"�o�ዾ�A�֎q"�����o���A���Ԃɓ���Ē������B
�S���������u���܂łɃT�V�o150�H�����ʉ߂��܂����B�����͊��҂��ėǂ��ł���v�Ƃ�����������B�����A���̒ʂ�I ���X�Ƃ���ė����B��R�̃T�V�o���㏸�C���ɏ���ė�����ɐ���㏸����"�钌"�����x���ϑ��E�ώ@���邱�Ƃ� �ł����B�r���A�T�V�o�ƕ���ō����ė��̒�����^�̑邪���ꂽ�B���́u�C�k���V�v�Ƌ��B���̌�A���́u����ȏ��� �C�k���V������̂��v�ƕs���ɂȂ����B���̓��̃x�e�����Ɋm���߂�Ɓu�C�k���V�ł��v�ƌ���ꂽ�B ��l�Ŋϑ�����ƋC���t���Ȃ��ꍇ�����邪�A���l���Ŋϑ�����Ɓh�ڂ���R����h�����ɁA�����������Ȃ��Ȃ�B �F�Ń��C���C�����Ȃ���ϑ�����̂��y�����B14:00�T����͏I���B�ʉ߂����T�V�o�h1000�H�z���h�̒T����ł������B
�u���̃T�V�o����X�̍�������z���A����A�W�A�܂ł̒���������v�Ǝv���ƁA�Q�������ċC���̗�����@�m���Ȃ��� ���Ă���T�V�o�Ɋ�������B�T�V�o�̓n��Ƀ��}����������B
����"�ܞ��s�T���l�̐X����"�ł̃T�V�o�T����ɏ��߂ĎQ�������Ē������B�����̍L��͒��]�ǍD�ŁA�����K���ȑ傫���� �����̓��A�͐�D�̊ϑ��ꏊ�ƂȂ�A�L�X�Ƃ��Ă��ċC�����悩�����B�X�ɁA�������ɂ̓J�t�F���X�g�����A�_�Y���������A �g�C���A�L�����ԏꂪ�������B����Ȃɗǂ��ꏊ�������ĉ����������Ɋ��ӁE���ӂł���B
2019.9.28
���R���싽�z���C�g���[�h�E�V�����R����
��T�ԑO�ɓV�C�\������āA26���̏h�𔒎R�[�̒��{����"�ɂ���ܗ���"�A27���̏h�𔒐싽�̕�������"�����̓��ӂ���" �ɗ\���B�V�C�\�O��邱�Ƃ����邪�K���I������26���͉����B9:30�ɉƂ��o�āA12:00�ɉz�O���ɒ������B���� �̘[�ɂ��钓�ԏ�ɎԂ�u���A�߂��̓X��"���낵����"��H�ׂ���A�R��ɂ������V��t(�W��249m)�܂œo���� �s����(�W���� ��100m)�B���̌�A�����ʂ���Ԃ���A�ɓ����a����"���������"�����B�����i�I16:30"�ɂ���ܗ���"�ɒ������B�����A����ɓ������B�ЂȂт������h�Ƃ��������ŁA���͂ӂ�ł��������A����� ���͋C���ƂĂ��ǂ������B�h����50m���㗬�֍s����"�I�V���C"���������B�[�H���A���H�����ł͂Ȃ����S�s������ �����������̂ł������B�h�̎�l���A����`����������p�E�����ȕ��ł������B����ɗ����͊i���A�ēx�K�ꂽ���� �v�����B���͂��̏h�ŁA5��ɂ������B
 27��7:00�N���B9:00�`�F�b�N�A�E�g�B�h���o���炷����"���R���싽�z���C�g���[�h(���� ���R�X�[�p�[�ѓ�)"������ł���B
���]�̗ǂ����X�ŎԂ��ߎU���B���R�W�]�䂩�猩�����R�����̎ʐ^���E�Ɏ����B��ԉ������R�ł��B�r���̎O���⒓�ԏ�
(�W��1450m)����O����x(�W��1736m)�ւ̓o�R����������Ă������f�O���A���싽�n�뗿�������o�ēV����(�W��1290m)�֍s�����B
�V�����́A���̕������O�u���͓V�����֘A��Ă����Ă���v�ƌ����Ă����ꏊ�ł��邪�A���͂�����ʂ������Ƃ��o���Ȃ������B
�ŁA���͓V�����֍s���@����f���Ă����B12:30�V�������ԏ�ɒ������B����"�V�����R����"������ɌW�����������������B
���́u�H�ו��͔����ĂȂ���ł����v�Ɛq�˂��B�u�Ƃ�ł��Ȃ��v�Ƃ̕Ԏ��B��ނ��A�������Ă���"���������"�E
�X�i�b�N�َq�E�����Œ��H���ς܂����B
27��7:00�N���B9:00�`�F�b�N�A�E�g�B�h���o���炷����"���R���싽�z���C�g���[�h(���� ���R�X�[�p�[�ѓ�)"������ł���B
���]�̗ǂ����X�ŎԂ��ߎU���B���R�W�]�䂩�猩�����R�����̎ʐ^���E�Ɏ����B��ԉ������R�ł��B�r���̎O���⒓�ԏ�
(�W��1450m)����O����x(�W��1736m)�ւ̓o�R����������Ă������f�O���A���싽�n�뗿�������o�ēV����(�W��1290m)�֍s�����B
�V�����́A���̕������O�u���͓V�����֘A��Ă����Ă���v�ƌ����Ă����ꏊ�ł��邪�A���͂�����ʂ������Ƃ��o���Ȃ������B
�ŁA���͓V�����֍s���@����f���Ă����B12:30�V�������ԏ�ɒ������B����"�V�����R����"������ɌW�����������������B
���́u�H�ו��͔����ĂȂ���ł����v�Ɛq�˂��B�u�Ƃ�ł��Ȃ��v�Ƃ̕Ԏ��B��ނ��A�������Ă���"���������"�E
�X�i�b�N�َq�E�����Œ��H���ς܂����B ���̌�A�u�i�̖�o�R�H������čs�����B���X�Ƀu���L�̋�ʂ��Ԃ牺���Ă������B�����"�F�悯"�̂��ߒ@���Đi�B
��40���œV������(�W��1400m)�ɒ������B�G�]�����h�E�̉Ԑ���ł������B�E�ɃV���q�Q�\�E�̎ʐ^�������B
�����̖ؓ���i�݁A�J���J����(�W��1360m)���琼���̖ؓ��ɓ���V����������������B15:00�V�������ԏ�ɋA�������B
���̌�A�u�i�̖�o�R�H������čs�����B���X�Ƀu���L�̋�ʂ��Ԃ牺���Ă������B�����"�F�悯"�̂��ߒ@���Đi�B
��40���œV������(�W��1400m)�ɒ������B�G�]�����h�E�̉Ԑ���ł������B�E�ɃV���q�Q�\�E�̎ʐ^�������B
�����̖ؓ���i�݁A�J���J����(�W��1360m)���琼���̖ؓ��ɓ���V����������������B15:00�V�������ԏ�ɋA�������B16:00��������"�����̓��ӂ���"�ɓ����B���͒��w��N���̎��A�Ƃ̐�y(��N�N��)�ɗU���āA���R�o�R�������B���̎��� ��������̃o�X�₩��唒��I�V���C�܂ŕ����ăe���g�����B���ł͂����܂ŗ��h�Ȏԓ����o���Ă���B��������� ���̑z���o�̏ꏊ�ł���B�����A����ɓ���A18:00�[�H�B�D�ꂽ�����l���r���ӂ���������Ŕ������������B
"�����̓��ӂ���"�͌Ö��Ƒ�����n���ȏh�ŁA"�ɂ���ܗ���"�̂ЂȂт����f�ȏh�Ƃ͑ΏƓI�ŁA��������Q�{�B ���h�Ƃ�"���{�铒�����h"�ŁA�����E�����E�z���s���Ă��Ȃ����������̉���ł������B
28��7:00�N���B9:30�`�F�b�N�A�E�g�B�A��̓��ł���B�r���A���싽�̑�\�I�Ȑ؍ȍ�������Ɖ��ł��鋌���R�ƏZ��O�� �ʂ����̂ŁA���w�����Ē������B���w��d�v������ �����R�Ɩ����قƂ��āA�����E�W�����Ă���A��Ƒ�����̃r�f�I�� �����[�������B10:30�Ђ邪�̍����ɓ����B�����A���������w������A�ׂ�"�������t�@�[�}�[�Y"�ŋ����E�`�[�Y�E���[�O���g �E�P�[�L�����H�Ƃ����B12:30�Ђ邪�̍������o���B���hIC���獂�����H�ɓ���A�����㍑�����o��16:30�ޗǂ̎���� �A�������B
2019.9.21

�����
�����������Ȃ����̂ŋv���Ԃ�ɓc�ɓ�����������Ȃ��ďo�����čs�����B�E�J�R�~�����O�̒��X�Œ��H�� �ς܂��Ă���A������̖�x�z(�₫��)�R���_�Ђ֍s���A�Ԃ��߂āA��o����ɖ��R���̕��֓c�ɓ��� �����čs�����B���B�����w�����������A�ޗǂ��炱�̕ӂ�܂ʼn��x�������Ă������A�ŋ߂͕������ꂽ �_�n�������Ĕ_��������G���ŕ�����l�ɂȂ��Ă��܂����B�͂��Ɏc��_���͎Ԃ��ʂ炸�A���͎U�� �̂��D�����B�H�̑��Ԃ����X�ɍ炢�Ă���B�E�̎ʐ^�͐�l���̉Ԃł���B���M�Ȕ������ԂŎ��͍D���ł���B�@�@�@�U���@�@�@�@�^�Ӗ�S��(1873-1935)
�@�@�@�H���s���A�H���s���A
�@�@�@�H���s���ċ���Ă��B
�@�@�@�ЂƑ��A�܂��ЂƑ��A
�@�@�@�킪�C�͉C�߂�B
�@�@�@�����A���ւ�҂���A
�@�@�@�킪���N�̓��̕ȁB
�@�@�@�E�E�E
2019.9.15

�g���͌�
���{�쒹�̉�ޗǎx���̓��A��o�X�c�A�["�������g���͌��V�M�E�`�h���T����"�ɎQ�������B 7:45�ɏW���ꏊ�̋ߓS�ޗljw�O�ɍs�����B�S�������Ɛ��l�̎Q���҂�����ꂽ�B8:00�ɏo���B �Q���҂�27���B���͌ÎQ�����A�v���Ԃ�̎Q���Ȃ̂Ŋ猩�m��͎O�����x�B���̊猩�m��� "�����N���ɂȂ����Ȃ�"�Ƃ����̂����̊��z�B�ނ�����������̊�����ē����l�Ɏv���� �����邱�Ƃ��낤�B��_�����p�ݐ����o�āA�W�HSA�ŋx�e�A�u���킶�Ԃ������v�� �������A���Ő���~�W�]��ɍs�����Ƃ��������G���Ă����̂Ŋ����A�o�X�̒��Œ��H�B13:00�ɋg���͌�(�E�̎ʐ^)�ɒ������B���͐앝���L��(2km?)�̂ɋ������B�o�X���~��T���� �J�n�B32���͂���Ƃ����J���J���Ƃ�̂��ƁA�؉A�ЂƂ�����h��������B���������Ă����� �Ŋ��オ�炸�ɍςB���_�C�`�h���̌Q�ꂪ������Y�ꂳ���Ă��ꂽ�B�L�X�Ƃ����������i�F �͐��X�����C���ɂ��Ă��ꂽ�B
15:30�o�X�ɏ��A�H�ɂ����B�W�HSA�ŋx�e��A��_�����k�_�ː��A���������ԓ����o��18:30 �ߓS�ޗljw�O�ɋA�������B�����b�����Ă����������S�������ƃo�X�̉^�]�肳��Ɋ��ӂ��ċA����B
2019.9.13
�����߂�
���炭�c���̌��������V�̓��������Ă������A�ޗǂł͍�邩��J���~�肾�����������Ƃ��Ƃ� �J���~���Ă���B���̂悤�ȓ��́A�������܂������c�ɂł�"������j"�ł������B���̊����� �_�Ђő��ۂ�@���č��}����ƁA�e�˂̒����_�ЂɏW�܂�"�b�݂̉J"�Ɋ��ӂ����B�����āA���̓��� �����̎҂��O�ł̔_��Ƃ͋x�B�����҂̔��Z�̏f���Ȃǂ́A�Ƃ̒��Řm�d�������Ă����B���Z�̏]�Z�ɓd�b���Đq�˂���u�_�Ƃ����Ȃ��Ȃ��āA"������j"�͖����Ȃ����v�Ƃ̂��Ƃł������B
�@�@�@�����@�@�@�@���蓡��(1872-1943)
�@�@�@�܂��������߂��O����
�@�@�@�ь�̂��ƂɌ������Ƃ�
�@�@�@�O�ɂ�������ԋ���
�@�@�@�Ԃ���N�Ǝv�Ђ���
�@�@�@�₳������������ׂ̂�
�@�@�@�ь�����ɂ����ւ���
�@�@�@���g(��������Ȃ�)�̏H�̎���
�@�@�@�l���Џ��߂��͂��߂Ȃ�
�@�@�@�킪������Ȃ����߂�����
�@�@�@���̔��̖тɂ�����Ƃ�
�@�@�@���̂������̔u(�����Â�)��
�@�@�@�N����(�Ȃ���)�Ɏނ݂�����
�@�@�@�ь用�̎�(��)�̉�(����)��
�@�@�@���̂Â���Ȃ�ד���
�@�@�@�N�����݂��߂������݂���
�@�@�@��Ђ��܂ӂ������Ђ�����
2019.9.4

78�˂̒a����
���͍�����78�˂̒a�����ł��B���Ɋ��S�͗L��܂��A78�˂܂Ō��C�ɐ����Ă���ꂽ���Ƃ́A��� �L����Ƃ��Ɗ��ӂ��Ă��܂��B�{���A���ȂɎB�点���ʐ^���E�Ɏ����܂��B���N�܂łɑ��E������A ���ꂪ��e�ƂȂ�܂��B������11:00����12:30���A�e�j�X�X�N�[���Ńe�j�X�����܂����B13:30����ޗǃz�e���Ńe�j�X���Ԃ� �H�������A78�˂̒a�������j���Ă��������܂����B�ƂɋA���ċ��ȂɁu�ޗǃz�e���ŐH���������v�� ��������A�����ƈ�������\�z���Ă����炵���u���j���̂��y�������C���������v�ƌ������B ���́u���߂ăP�[�L�����ł������Ă��āv�Ɯ��B�P�[�L���ɍs�������Ȃ���d�b�������� �u�P�[�L������ɋ�����ǁA���z��Y�ꂽ�̂ł����������ė��āv�ƁB
�@�@�@�H���̉́@�@���蓡��(1872-1943)
�@�@�@���Â��ɂ�����H����
�@�@�@���̊C��萁���N��
�@�@�@���Ђ������킮���_��
�@�@�@��тčs���ւ�����邩��
�@�@�@�E�E�E
2019.9.1

�����̒��j�̗��K
���ł̏A�E�Z�~�i�[�ɎQ��������łɁA�����̒��j���ޗǂ̉䂪�Ƃɗ��Ă��ꂽ�B8��29���ɓޗǂɗ��āA 8��30���͑��ւƏo�����čs�����B8��31���͎����Ԃ̉^�]���K�̂��߁A�ՐÂȏZ��n���������A��ڗ��� �܂ōs���ċA���Ă����B���\�A���ɉ^�]���Ă����B9��1����11:00�ɉƂ��o�āA��_�_��(�O�֖��_�A�䂪�Ƃ���20km)�܂Œ����̒��j���^�]���čs�����B���ԏ�� �Ԃ��߂ĎQ���ɏo��ƁA�Q�q�҂������̂ŋ������B�u����1���͋v���F�_�З�Ձi�����Ђ�����ꂢ�����j �Ȃ̂ł���Ȃ�ł��v�Ƃ̂��Ƃł������B�q�a(�E�̎ʐ^)�ʼn��ɂ���O�c������ʂ��O�֎R��q������A �ێЁu����_�Ёv�̕��֕����čs�����B�r���̒��X��"��₵�����߂�"��H�ׂ��B����_�Ђ̘e�Ɂu�O�֎R�o�q���v ���������B�����̒��j�Ɂu�o�邩�H�v�ƕ�������A�ӊO�Ȃ��ƂɁu�o��v�ƌ������B���R��(�P�l300�~)��������A �_������u���R�S��10�ӏ��v���������B��_����{����ɓo�q���J�n�����B����ȎR�͊ȒP�ɓo���Ɛ��@���Ă������A �ȊO�ɋ}�o�ŃL�c�C�B�����̒��j�͂܂��Ȃ�"�����グ��"���낤�Ǝv���Ă������A�ӊO�Ȃ��Ƃɒ���܂ōs�����B ����_�Ђ̕W����80m�B�O�֎R�R��:���Ô֍��̕W����467m�B������2���ԗ]�B���т������ƂȂ����B
2019.8.30

�M�˕a�H
�����������Ȃ��Ă��܂����ˁB�^�Ẳ��V���Ńe�j�X���������Ƃ��v���Α��v��8��29��13:00���� �e�j�X�������B���x�������Ċ��������ς��������B15:00�ƂɋA���Ă������肵�Ă���ƁA�Ȃ� ���C�������B�M�𑪂��37.5���B����͂����Ȃ��ƁA�������Ƃ��ăx�b�h�ɉ���������B ���܂�H�~�������̂ŁA19:00�[�H�͌y�����܂����B�C�͂������̂ŁAUS Open�̃e�j�X���e���r�Ŋϐ킵�A 10:30�ɏA�������B8��30�����������ɂނ̂ŁA����҂֍s�����B����҂���́u���Ɉ������͌�������܂���ˁB�Ă̔�ꂪ �łĂ�̂ł��傤�B�����l�q�����܂��傤�B9��2���ɂ܂����Ă��������v�B���̌�A���͎U��������ɍs�����B ���H��A�ƂɋA���Ă��A�܂����C���o�Ȃ��B�ŁA�x�b�h�ɓ�������悭�������B�����A���C�ɂȂ����B �[�H��AUS Open�̃e�j�X���e���r�Ŋϐ킵�A11:30�ɏA�������B
8��31���Ȃ�Ƃ����C�ɂȂ����B�̂̎���Ă���Ƃ��Ƀe�j�X������"�M�˕a�H"�ɂȂ����̂�������Ȃ��B ����Ȃ��Ƃ͏��߂Ă̌o���B���ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�E�̎ʐ^�̓^�J�T�S�����B��̂��������ɍ炭���A���܂�D���łȂ������������Ă������A��}�ɑ�R�̉� ��t���Č����ɍ炢���B�������������B
2019.8.22

��c�_�@���Ə��㒼��
2019.7.20�̃u���O�ő�c�_�@��(1791-1875)�ɂ��āA2019.8.3�̃u���O�Ōܑ��c����(1928�|2016)�ɂ��� �L�����B���㒼��(1806-1891)�͖{���@�J�䗘�\�Y�@�g�q���ƍ����A��Ƃ��Đ������B��c�_�@���ƌ�V���A �a�̂��y���ݒ���Ȃǂɘa�̂���������(�����̓��|�@���R�ʐ^�H�|)�B���㒼���͍��X�؍O�j�̖�l�ƂȂ��Ċw�� �C�߁A���ɏ�蓩��̌����ɗ�B�����̏����̐l�ł��蒃��삵�����c�_�A���ɉe�����A�M�y�ɋA���� �쓩�ɐ�O�����B�@���Ƃ͈ӋC���������炵���A�@��������т��ѐM�y��K��Ă���(�`���̐M�y�ā@���ꌧ���`�������ۑ���)�B�ʐ^�̍��́A�M�y�ĂƎv����ԕr�ɓB�����
���Â˂����@������͐�Ɓ@�ӂ鋽�́@�u��R�ł�́@�͂�̗[����@�@�@�@�@��
�ƍ����Ă���B
�ʐ^�̉E�́A�×��q�@�Z�\�ꉥ�@�g�q�����@�����ƍ����Ă���ԕr�ŎO�ʂɘa�̂��B���肵�Ă���B
���ʂɂ�
���@�@�@���L�_�n�@���ƂȂ�����ā@�Ƃ錎�́@�������ɂقւ�@�H�̉Ԃ��́@
�ƍ����Ă���B
2019.8.15
�I��L�O��
�����͑����m�푈�I�킩��74�N�̋L�O���ł���B�����m�푈�������Ȃ��Ɏ������ӔC�́A��Ƃ��� �Ȏ��B�̕���E��c�̍l���̐�͂����ɋA����Ǝv���B�����āA���̐����E�Љ���v���Ƃ��A ��X�͏d��ȉ߂����N�����Ă͂��Ȃ����ƗJ���B�l�ԂƂ����͉̂߂���Ƃ��āA���߂ċC�Â��A �O���C�����邵���Ȃ��̂��낤���B���I�푈�ɖ����ɂȂ��Ă��鎞�A��������������������ƂɌh�ӂ�\���܂��B
�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���@(��������͌R�̒��ɂ�����Q����)�@�@�^�Ӗ쏻�q(1878-1942)
�@�@�@�������Ƃ��Ƃ�A�N�������A
�@�@�@�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���A
�@�@�@���ɐ��܂ꂵ�N�Ȃ��
�@�@�@�e�̂Ȃ����͂܂��肵���A
�@�@�@�e�͐n(�₢��)���ɂ��点��
�@�@�@�l���E���Ƃ����ւ���A
�@�@�@�l���E���Ď��˂�Ƃ�
�@�@�@��\�l�܂ł������Ă���B
�@�@�@��̒��̂����тƂ�
�@�@�@�p�Ƃ��ق��邠�邶�ɂ�
�@�@�@�e�̖���㋂��N�Ȃ��
�@�@�@�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���B
�@�@�@�����̏�͂ق�ԂƂ�
�@�@�@�ق�т��ƂĂ�������
�@�@�@�N�͒m�炶�ȁA�����тƂ�
�@�@�@�Ƃ̂����ĂɂȂ��肯��B
�@�@�@�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���A
�@�@�@���߂�݂��Ƃ́@��Ђ�
�@�@�@���ق݂Â���͏o�ł܂��ˁA
�@�@�@�����݂ɐl�̌��𗬂��A
�@�@�@�b(������)�̓��Ɏ��˂�Ƃ�
�@�@�@���ʂ��l�̂ق܂�Ƃ́A
�@�@�@��݂�����̐[�����
�@�@�@���Ƃ�肢���Ŏv(����)����ށB
�@�@�@�������Ƃ��Ƃ�A��Ђ�
�@�@�@�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���A
�@�@�@�����ɂ��H���݂�
�@�@�@�����ꂽ�܂ւ�ꂬ�݂�
�@�@�@�Ȃ����̒��ɁA�����܂���
�@�@�@�킪�q��������A�Ƃ����A
�@�@�@�����ƕ��������(�݂�)��
�@�@�@��̂��甯(��)�͂܂���ʂ�B
�@�@�@�g���̂����ɕ����ċ���
�@�@�@�������ɂ킩���V�Ȃ��A
�@�@�@�N�킷����A�v�ւ��A
�@�@�@�\�����Y�͂ł킩�ꂽ��
�@�@�@����(���Ƃ�)��������v�Ђ݂�A
�@�@�@���̐��ЂƂ�̌N�Ȃ��
�@�@�@�����܂��N�����̂ނׂ�
�@�@�@�N���ɂ��܂ӂ��ƂȂ���B
2019.8.14
�̋��̕�Q��
���܂�̋��̊��֎s�Ɣ��Z�s�֕���̕�Q��ɍs�����B�䕗10�����߂Â��ė��Ă���̂� ���̉e�������Ȃ������ɂ�7:30�ɉƂ��o���B�r���A�O�d���ɉ�s��ʉ߂���Ƃ����J�ɑ��������� �֎s�ɒ����Ɛ�ł������B�Ƃ��p���ŗ{��̖ʓ|�����Ă���Ă��鎟��̉Ƃŕ��d�Ɍo�������� ��A���̉Ƃɍs���Čo���������B����̉Ƃɖ߂�A�����Ƃƕ�Q��ɍs�����B�A��ƁA���ɏZ�� ����v�w�����x�����Ƃ���ł������B�䕗10�����߂Â��ė��Ă���̂ŁA���͐���}�����B���H�̌�A�F�ɕʂ�������A���Z�s�̕�̎��Ƃ� �s�����B��N���̏]�Z���_�Ƃ����Ă���(���ł́A���ŗB��̐�Ɣ_��)�B���d�Ɍo����������A���x�A �]�Z�̎o�v�Ȃ�����ꂽ�B���͕ꂪ�S���Ȃ�����A������n���畜������܂ŁA���̉Ƃł����b�ɂȂ����B ������A�]�Z��]�o�Ƃ͌Z��̗l�Ɉ�Ă�ꂽ�B�ƂĂ����������B
�ł��A���͐���}�����B�F�ɕʂ�������A���ǐ�͔Ȃɂ����n�֍s���A��Q��������B�ޗǂ̉Ƃ̒� �œE��ł����I�~�i�G�V�ƃr�V���R���������B���̌�A��h���璷�ǐ�߂�ƁA�������Ȃ����͐���� �����B���͎��Q�̐��j�p���c���Ԃ��炾���A�̉j�����͌��ŁA���ɂ������B�j���ł���ƁA�g���S�� ���߂���悤�ŋC�������ǂ������B���Ȃ����x�Ő�グ�ċA�H�ɂ����B�I�]���߂��鍠�A���J�� �Ȃ����B�������A�K���Ȃ��ƂɁA�b���i�ނƁA�J�͎~�B18:00�ޗǂ̉䂪�Ƃɖ����A�������B
�@�@�@�_�@
�@�@�u�̏��
�@�@�Ƃ�����
�@�@���ǂ���
�@�@���Ƃ�Ɖ_��
�@�@�Ȃ߂Ă��B
�@�@�@��: �R���钹(1884-1924)�@
2019.8.12
�k�C��: ���R�E���H����
�����ޗǂ𗣂�ė������k�C����K��A�����^�J�[�ʼn���h�ɔ��܂�Ȃ�����R, ���H������K��� �����v�悵���B�s�A�m�̔��\��I����Ă���E�E�E�Ƃ����̂ŁA�o����8��5���ȍ~�B�C���^�[�l�b�g �Œ��ׂ���A�k�C���̋�`�̒��ŁA������ł͏����ʋ�`�֍s���̂�1�ԕ֗��ł��鎖�����������B �k�C���͉���R���邱�Ƃ�������A����|�������̉���h��I�B�\�ɂ͓V�C�\��͘A�� �g�����h�ł��������A�o�����ɂ͑䕗8,9,10�����������A�k�C���̓V�C�\��ł́h���s�㔼�ɉJ�h�ƂȂ����B8��6��7:25�ߓS�ޗljw�O���̃����W���o�X��9:10�ɒO��`���A10:40�ɒO��`����JA201��12:40�����ʋ�`���B �C����30���A���҂��Ă����ȏ�ɏ����̂ŁA�����K�b�J���B 13:00�����^�J�[����A�r���̋������Œ��H���Ƃ�A 16:00���ʂ�鉷��h�Ƀ`�F�b�N�C���B�����A����ɓ������B���̒ʂ�h����Ɣ������g�ɂȂ鉷��� ����|�������̗ǂ�����ł������B18:00�[�H�B���͂܂��܂��A�ʂ͎��ɂ͑��߂����B�H��A�ēx����ɓ���A 10:00�A���B�����J���ĐQ���B
 8��7��6:45�N���B����ɓ���A8:00���H�B9:00�`�F�N�A�E�g�B���ʂ�鉷��h�́A�����͈������A����ł��Ȃ����A
����͗ǎ��B�������߁I
8��7��6:45�N���B����ɓ���A8:00���H�B9:00�`�F�N�A�E�g�B���ʂ�鉷��h�́A�����͈������A����ł��Ȃ����A
����͗ǎ��B�������߁I10:30�w�_�����[�v�E�F�C���ꒅ�B���[�v�E�F�C�ŕW��1300m�̍��x5���ڂ܂ōs���A200m�قǕ����Ă��� ���t�g�ɏ��W��1520m�̍��x7���ڂ܂ōs�����B���x�R��1984m�܂ōs���̂̓L�c�C�̂ŁA�U���H�g�J���C�� �X�݂̂��h���U���B���R�A������R����ʐ^���B���Ċy����(�E�̎ʐ^�̓_�C�Z�c�g���J�u�g)�B 3:00���t�g�ƃ��[�v�E�F�C�����p���ʼn��R�B������3000�~�B�r���Ŗ��X���[������H�ׁA16:00���x����̏h �h�N��g�ɒ������B�����A����ɓ������B3��̉�����A���ʂ������A����|�������̗ǂ�����ł������B �����̓L�n�_�ŏo���Ă��Ď������A�������ǂ����͋C�ł������B18:00���[�H�B���ꂪ�f���炵�������B �V�F�t�̓Ƒn�����ӂ�闿���ŁA�ƂĂ��������������B�ʂ��K���ł������B�H��A�ēx����ɓ���A10:00�A���B ���̏h�͕W��1000m�ɂ���A��[���u�͖��������B
 |
 |
 |
| �����p���]�䂩�猩�����x | �~���}�����h�E | ������l�W�]�䂩�猩�����x |
8��9�����ɂ͍��J�x�łĂ����B8:00��蒩�H�B9:15�`�F�b�N�A�E�g�B10:30�x�ǖ�ɂ���㓡���j���p�قɒ������B �ϗ���A���p�ٓ��̃��X�g�����Œ��H(�X�p�Q�b�e�B)��ۂ�A12:30���p�ق��o���B ���̍��ɂ͉J�͎~��ł����B�x�c�K�[�f���t�@�[���ɍs�������A���x���_�[�̉Ԃ͏I���A�؊������łЂ�����Ƃ��Ă����B �ϖ�IC����L���������H�ɓ��舢��IC�ŏo�āA16:20�ɂ��̓��̏h:�R�ԉ��t���ɒ������B���̏h�́h���A�艷��� �h���{�݂�t�݂����g�����ł������B����̗��ŁA������1�Ԉ����������A����͂܂��܂��A�H���́h��V�h�œK�ʂ� �������������B���̓��̍ō��C����24���B
 |
 |
 |
| �㓡���j���p�ق̃��X�g��������̌i�F | ���H���� | �����������ԉ� |
8��11�� 6:00�N���B7:15��蒩�H�B8:00�`�F�b�N�A�E�g�B9:30�����������ԉ����B�U���10:30 �����������ԉ����o���B11:10�����ʋ�`���B�����^�J�[��ԋp�B���s����803km�B��`�̃��X�g������ �R�[���o�^�[���[�����Œ��H�B13:15����JAL2102��15:20�ɒO��`���B�ɒO��`�ɒ������ہB�@���̃A�i�E���X�� �u�����̑��̋C����37���ł��B�����n�̋C���Ƃ̍���15���ȏ゠��܂��B���̂ɋC�����Ă��A�艺�����B�v �Ƃ������B16:20���̃����W���o�X��17:30�ߓS�ޗǂɋA�������B
�����ɋA�����đ�c�ł���B�����������C�Ȃ獕�x�ƈ��x�̎R�����s�����ł��낤�ɁA����͂��Ȃ�Ȃ������B �u�N����l����Ɩ����͂��Ȃ����Ƃ��v�Ǝ����Ɍ����������āA�����E�����B����ɎO��ɓ���y�������� �������B
2019.8.5
�^�]�Ƌ��̍X�V
�^�]�Ƌ��̍X�V�ɍs�����B9:00�Ɋ����s�ɂ���"�^�]�Ƌ��Z���^�["�ɒ������B��t�ɂ�50�l���̍s�o���Ă����B �u����ҍu�K�I���ؖ����v�������čs�����̂ŁA�X�V�萔�����A���͌���������A�V�����^�]�Ƌ��� ���Ƃ��o�����B�P���Ԏ�ŏI������B���̖Ƌ��A�R�N�ԗL���B�L�������ꖘ�A�����Ă��邩�ȁH�ƂɋA���Ă���A���ȂƂ��~�̕�|���Ƃ��Q��ɍs�����B�䕗�̉e���ŕ�������A���V���ł�����������Ȃ������B
�@�@�@��̓�l�@
�@�@���B�̍Ōオ�쎀�ł��炤�Ƃ��ӗ\����
�@�@���Ƃ��ƂƐ�̏�ɍ~����(�݂���)�܂���̖�̉J�̌��������ł��B
�@�@����q�͐l���͂Âꂽ�o��̂悢���������
�@�@�܂��쎀���͉��Ԃ�̕����̂��ޒ����I�̖��������Ă�܂��B
�@�@���B�͂�������ق��Ă�����x�J���������Ǝ������܂��܂����B
�@�@���������o���ƌ������K�N�̎}�����Ɏq�ɒ܂𗧂Ă܂��B
�@�@�@��: ���������Y(1883-1956)�@
2019.8.4
�s�A�m�̔��\��
8��4���͎��̊w��ł���J���C���y�����̔��\��̓��ł���B��܂ƌS�R��z�[����18:00�J���A ���͓�Ԗڂ̃s�A�m�Ƒt��"�A�_����Ȃ̐Ⴊ�~��"�����t���邱�ƂɂȂ��Ă���B���̐��Ă� "�Ⴊ�~��"�͎�����Ȃ����A�Ⴊ�~���Ă������ɑI�Ȃ��āA���̗��K���ʂ̔��\��Ȃ̂��B������ْ����ė��K���Ă������A11:00����12:30�܂Ńe�j�X�X�N�[���֍s���āA���V���Ńe�j�X�������B �A���Ē��Q������16:00����"�Ⴊ�~��"�̗��K�������B17:40�ɂ�܂ƌS�R��z�[���ɒ������B ���ɂ��炵���搶���u���l��?�v�Ɛu���ꂽ�B�u�����̗��K���Ă���̂ōs���Ȃ��v�ƌ����ė��܂��� �Ɠ�������A�u����ȁI�A���\��Œ����Ȃ�����I�v�Ƃ�����������B
���\���A�ƂɋA���āu�听���������B�Ō�܂Œe�����I�v�ƕ����B�����āu�ƂĂ����Ȑl������� ��������v�ƕ�����A�u������O��I�A���݂����Ȑl�����������特�y��ɂȂ��I�v�� �Ԃ��Ă����B
����ɂ��Ă��A���̍ɂȂ��ċْ��ł��邱�Ƃ́A���������Ƃ��B
2019.8.3

�ܑ��c����
���ꌧ�����|�̐X�ŊJ��20���N�L�O�̓��ʓW�u�����炫�₫�|�����̒����@�t�ւ̚�|�v�� ����22�N9��18��(�y)�`12��12��(��)�ɊJ�Â��ꂽ�B�ܑ��c�����i1928�|�j�������t�� �i1927�|2011�j�́A�Ē����A���q�Đ��ɂ��M�y�Ă̓`���Z�@�����Ȃ�����A�Ǝ��̊��� �荞��i�𐧍삷�錻��M�y�Ă̓�勐���ł���B���͂��̓W������ς����Ă��� �������B���̍ۂɓW������Ă��������킪�ƂĂ��C�ɓ������̂ŁA��x�q����K��āA�C�� �������̂��݂������ɓ��ꂽ���ƍl���Ă����B�M�y�̓S���w�O�̒��ԏ�ɎԂ��~�߂�"�q���U���H"������āA��c��������̌��ɍs�����B �Ƃ̑O�ɏ�c��������̉�������ꂽ�̂Łu�ܑ��c��������̍�i�������Ă������� �����v�Ƃ��肢�����B20�_�قǂ̍�i���W�����Ă��������A�����~�����Ǝv���Ă����}�{�� ���������B�K�b�J��������������Ƃ��b�����Ă���Ƃ���ցA�ܑ��c�������o�Ă���� ���B�����u���ʓW�Ŕq�����������킪�ƂĂ��C�ɓ������̂ł����A��������������͌���� �܂��v�Ɛq�˂���u���ʓW�ɏo�����͎̂����p�ɍ�������ŁA���x���䂸���Ăق����� ���܂ꂽ�̂����ǁE�E�E�ǂ��ɂ��܂������ȁE�E�E�v�Ƃ����ĉ��ɓ���ꂽ�B���炭���� �u����܂����v�ƌ����������Ă���ꂽ�B���́u�`���P�����A�D�����f�G���B�傫 �������܂���Ɏ��܂��đf���炵���B�v�ƌ������B��c��������́u�ǂ̍�i�������Ŏg�� ���Ƃ��g���₷���悤�ɍ���Ă���B���̍�i�A���̌`�A���ɖ����ł��傤�v�Ƃ�������� ���B�b���b���Ȃ���u���Џ����ė~�����v�Ƃ��肢�����B�b���Ă���ԂɌ݂��ɋC���������� �ɂȂ��Ă����B�Ō�Ɂu�C�ɓ����Ă����������l�ɂ����Ē����̂��ǂ��v�ƌ����ď����Ă� ���������B�E�̎ʐ^�͂���"����������"�B��Ɉ��p���Ă���B
�ܑ��c��������ɂ�����x����������ƍl���Ă������A2016�N�ɑ��E���ꂽ�B
�@�@�@�_�@
�@�@�������_��
�@�@����������
�@�@�n���ɂ̂�������Ȃ���
�@�@�ǂ��܂ł䂭��
�@�@���Ɣ֏镽(���͂����Ђ�)�̕��܂ł䂭�B
�@�@�@��: �R���钹(1884-1924)�@
2019.8.2
����
�����ł��ˁB���肶��ƏƂ���鑾�z�̉������ɏo�������B���Ȃ̎w���������̂��A�x������Ă��Ȃ� �\�����ɍs�����̘a�َq������Ɋ�����B�X�����u����A���ނ��n���̂�Y��܂����v�ƒޑK�� �o���Ă���ꂽ�B���́u�ޑK�����̂�Y�ꂽ�L���͂Ȃ����ǁE�E�E�v�A����\�������L���͗L��̂ŁA ������B�����ŁH�E�E�E�{�P�Ă����炵���I�@�@�@�R�̂��Ȃ��@
�@�@�R�̂��Ȃ��̋�
�@�@�u�K(�����킢)�v�Z�ނƐl�̂��ӁB
�@�@���T�@���ЂƂƁ@�q(��)�߂䂫��
�@�@�܂������݁@���ւ肫�ʁB
�@�@�R�̂��Ȃ��̂Ȃى���
�@�@�u�K�v�Z�ނƐl�̂��ӁB
�@�@�@��:�J�A���E�u�b�Z �@��:��c�q(�C����)
2019.8.1

�u���[�x���[�E�u���b�N�x���[
�������{�ԂƂȂ�A��̃u���[�x���[�ƃu���b�N�x���[�̎������n�ƂȂ��Ă����B��̃u���[�x���[�� 2kg�قǎ��n�ł��邪�A����͎��n���Ȃ���E�܂ݐH������̂���Ԕ��������B����ŁA�W�����p�̃u���[�x���[�� ���N�A��F�ɂ̔_�Ƃ���w�����Ă���B�u���n�ł����v�Ƃ̘A�����āA�_�Ƃ֍s��5kg�����Ă����������B 5kg�̃u���[�x���[�E2.5kg�̃O���j���[���E4�̃���������ʐ^�Ɏ��������̃W�������o�����B ����ň�N�ԁE�����A���[�O���g�ɍ����ĐH�ׁA���ɂ͐��Ŕ��߂ăW���[�X�ɂ��Ē������Ƃ��o����B�u���b�N�x���[�̕c��m�l����Ղ��āA���ې�ׂ�ɐA���Ēu������A�傫���Ȃ��č��N��2kg�قǎ��n�ł����B �u���b�N�x���[�͌����ڂ͔��������������A�킪�傫���E�Â����u���[�x���[�̕����D��B���H�ł͂�����H�ׂ��Ȃ��B ����ŁA�u���b�N�x���[500g�ɐ�300cc�������A�~�L�T�[�ōӂ�����A�U���Ŏ�������������B���̍����`�ɃO���j���[�� 250g�ƃ�������̍��`�������āA20�����M�E�Z�k�����B���̔Z�k�ʏ`�́A�X���Ŕ��߂ăW���[�X�Ƃ��āE���̂܂� �g�[�X�g�ɕt���ĐH�ׂĂ����������B
2019.7.27
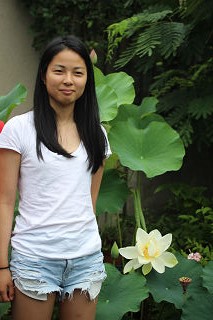
�����̒����̗��K
�č��̑�w�Ŋw��ł���(2�N���A����9������3�N��)�����̒������ċx�݂œ����ɋA�Ȃ��Ă������A �č����痈�K�����F�l���āA25���̖�A�ޗǂ̉䂪�Ƃɂ���ė����B���Ԃ͋��s�Łu���t���� ���������ό����Ă������A�y���~��̉J�ɂ����ĎP�������т���G��ɂȂ����v�ƌ����Ă������A�ޗǂ� ���������ɂ͈ߕ��������Č��C�ł������B26���A�䂪�Ƃ̒�ɂ���u�u���[�x���[�ƃu���b�N�x���[�̎���E�݂����v�ƌ������̂ŁA��Ɏh����� ���悤��"�����̃V���c�ƃY�{��"��݂��^���āA�E��ł�������B���n�����u���[�x���[�͓����ւ̂��y�Y�ɁA �u���b�N�x���[�̓W�����ɂ��ċ������B�ߌ�́A���V����2�l�œ��厛�A�t����ЁA�������̊ό��ɍs�����B ���͉ƂŃs�A�m�̗��K�������B�A���Ă��������̒����Ɂu8��4���Ƀs�A�m�̔��\�����v�ƌ�������A �u�y����Y��Ȃ��悤�ɂ��āA�r���Ŏ~�܂�Ȃ��悤�ɂ��Ēe������ǂ�����ˁv�ƌ����Ă��ꂽ�B
27���u�����̂��D�ݏĂ����Œ��H��H�ׂĂ���A������ׂ��ό����āA�����A��v�Ƃ̂��ƂŁA ���Ƌ��Ȃ��ꏏ�ɂ��D�ݏĂ����֍s�����B�Ƃ��o��ۂɁA�@�̘e�ŋL�O�ʐ^���B�����B�č����痈�K�����F�l �̋������Ȃ������̂ŁA�ʐ^�͊����������A���ǂ�"���{�̊ό�"���y����ł���悤�ł������B
2019.7.20

���c�_�A��
��c�_�@��(1791-1875)����́A���シ���A���s�m���@�̎��m�A��c�_�����q����Â̗{���ƂȂ�A17�̎��A�{�q�]�Âƌ����B ��j�������������A���������܂����B�v�̕����ɂ��A24�̎������B29�̎��A�{�q�Ô�ƍč����A�ꏗ�����A 4�N��v�͕a�v�B���V�̌�A�m���@�Œ䔯���A�@�����̂��B�a�̂͏�c�H���E����i���Ɋw�сA�����b���Ɏ��i�����B �̏W�w�C���̊����x��1872�N�Ɋ��s���ꂽ�B33�ˍ��A���v�̂��ߓ���̐�����n�߂��B��i�͗q���Ɉ˗����ďĂ��Ă�������l�ł���B35�̎��A7�̖��������A42�̎��A �{�������E�B���̌�͉���E���c�E�匴�E�k����Ȃǂ�]�X�Ƃ��A�}�{�E���q�Ȃǂ𐧍삵�Đ��v�𗧂Ă��B����̓���ɂ� �K�������̉r�̂�t�����B���ꂪ��i�ɍ�������Y���āu�@���āv�ƌĂ�Đl�C�����B�x���S�ւ́A�@����V�N�� �����ł���B�ڂ����́A�v���t���瑺��f���ҁw�@����S�W�x����ł��o�ł���Ă���̂ŁA�������������B
�E�̎ʐ^�́A�A���Ă̋}�{�B�u�����悫�@��ׂɂ��݂ā@�݂Ƃ����@���̂Ђ��̂ЂɁ@�����Ȃ�����v �ƍ����Ă���B�D���̂��B����œ��ꂽ��������"�g�����߂���"���ȁH�H�H
2019.7.15

�x�{���g
2019.7.7�̃u���O�ɋL�ڂ����ޗnj������p�ق̊��W"�x�{���g����"�ɍēx�s���Ă����B�x�{���g(1886-1963)�͖@�����ɋ߂��_���̏��n��:�x�{�Ƃ̒��q�Ƃ��Đ��܂�܂�����11�˂̎����������� �Ɠ��p���܂����B�S�R���w���o�ē������p�w�Z�}�ĉȂ𑲋Ƃ��A�����h���Ɏ���w�B�A����A������ �f�U�C�����鑍���|�p�̒S����Ƃ��āA�ؔʼn�E�h�J�E�v�H�E�����ȂǕ��L�����Ă��܂������A ���|�ɊS���������o�[�i�[�h�E���[�`�̉e�����A1913�N����Ɋy�Ă̗q��z���܂����B�����Y�̒����� �u�͗l����͗l��ׂ��炸�v�Ƃ�����ƂƂ��ẴX�^���X���m�����A�͗l�ɂ�����I���W�i���e�B�� �Njy�������܂����B�����u�������A���|������n���̔����̏�Ƃ��A����ɑË����������A�������Ɍ����� ���i��v�����܂����B
�ʐ^�͎������p���Ă���x�{���g��̓��ہB
�E��1936�N�̍�i�Łu��O�����H�����ҌO���v�Ə�����Ă���B
����1943�N�̍�i�Łu��|���u�v:���[�Y���[�X�̎��傩��o���Ƃ��ӊ�g�ΗY�̐������z�@�Ə�����Ă���B �x�{���g�Ɉ˗����Đ��삵�A��g���X�̑n��30���N�p�[�e�B�̎Q����500���]�ɔz�z���ꂽ���̈�B
2019.7.13
���T����
7��13���͓��{�쒹�̉�ޗǎx����"�ޗnj����E���T����"�̒S�������ɂȂ��Ă����B�S��������2�l�ŁA �ʏ�A���͕t�^�݂����ȕ⏕���ŏo�����Ă���̂ł����A����͂�����l�̒S����������Ђ̏o���œ��� �����Q���o���Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA���͑O���ɓޗǎx���̎������֕K�v�i�����ɍs�����B���āA7��13��8:30�ɏW���ꏊ�̋ߓS�ޗljw�O�L��֍s�����B�Ƃ��o�鎞�A���J���~���Ă������A9:00�ɂ� �قڎ~�݁A39���̎Q���҂��������B���͌ÎQ�ł��邪�A�ŋ߂͂����������Ă���̂ŁA�v���Ԃ�ɉ�l�� ���܂�ʎ��̂Ȃ��l���唼�ł���B�u�ÎQ�̐l�B�͌��N��Q�ŏo�Ă����Ȃ��v�Ƃ̂��Ƃ�"�����͉䂪�g" �Ǝv���m�炳�ꂽ�B
�T����́A���⎩�R���ώ@���Ȃ�������������B�����������ł��������A�؉A�����߂Ȃ���A�������� ���̂ŁA���\�y���߂�B���l���Ŋώ@���Ă���̂ŁA��l�Ŋώ@���Ă�����A����������@������Ȃ�A �ώ@����肫�ߍׂ₩�ɂȂ�B��b���y�����B11:30�t����Ђ̖��t�A�����e�ŁA�ώ@��������E�m�F���� "�����킹"�����ĉ��U�����B�ώ@��������22��ł������B
�킷��Ȃ���
�Ȃ���̂����̂ЂƂ��Ƃ�
�݂���̂���݂̂Â�����
�Ȃ݁@���Ƃ��Ƃ��@�����Â���
�͂��@���Ƃ��Ƃ��@�킷��䂭
��:���w�����E�A�����g �@��:��c�q(�C����)
2019.7.7

�������E������
�Q�c�@�I�����n�܂�܂����ˁB�����҂�����Ɛl�ޕs���ł��ˁB�Ƃ�����A���[���Ȃ���Ȃ�܂���B ����"�������E������"�œ��[�������B��̑����@�Ƒ��n�X(�E�̎ʐ^)�����N���������Ԃ��炩���Ă���Ă��܂��B�C�i�����������l�̂悤���B
�����́A8��4���̃s�A�m���\��ɔ����ăs�A�m�̗��K��������A�e�j�X�X�N�[���֍s����11:00����12:30�܂� �e�j�X�������B���̍s���Ă���X�N�[���ł�2��~��̃X�|�b�g�����œ��j���b�X������u�����Ă����B
15:30�ɉƂ��o�āA�k����10�����ł�����ޗnj������p�ق֍s���āA���W"�x�{���g����E�E�E �ނ͂Ȃ����{�ߑ㓩�|�̋����Ȃ̂�"��q�ς����Ă����������B�\�z���Ă��������[�����Ă���17:00�̕� �A�i�E���X�Œǂ��o����Ă��܂����B�߂��ŁA����(65�ˈȏ�)������A�ߓ����ɍēx�q�ς����Ă����������Ǝv���B
2019.6.26
�������
�����̕v�N��16���ɓޗǂ֗��āA�[���Ɏd���̂��߂Ɠ����֍s�����B21���Ɏ������(�����v�Ȃ� 3�l�̎q��)�͑���USJ�֗V�тɍs�����B22���͎�����Ƃ�"��Ԃ�����̓�"�ցA23���͓����� �Q�q������A�ēx"��Ԃ�����̓�"�֍s�����B�����āA�����̕v�N�͗[�H�㓌���֍s�����B�����͌����邳���āA���w2�N�̎q���Ɂu����Ȃɑ�R������ɐH�ׂ���A�ɂ܂��v�Ȃǂ� ���ӂ���B
�����̏��w2�N�̎��j(���j�͑���)�́A������������A�߂��̏��w�Z�֒ʊw���Ă���B�ƂĂ��ǂ��搶�̗l�ł���B
�����̏��w6�N�̎����͏��w�Z�ւ̒ʊw�����ۂ��A�T�b�J�[�{�[�����R���ėV��ł���B�č��ł� �T�b�J�[�N���u�ɓ����Ă��邻���ŁA�ƂĂ����C���B���������Ƃ�"�����e���Ă���s�A�m�̋Ȃ��o���� ����������ł���"�B
�����̒��w2�N�̒����͗����ɊS������A���͔ޏ��̍D����"�����̎ς����낪��"�A"�^�|���u�ߎ�"�� ������`�������B������"�~��"�̍��������K�������B
29���ɓ����ֈړ�����\��ł���B���Ə������B
2019.6.17

�O�}��
����_�Ёi�������킶��j�͋ߓS�ޗljw����500m���̏��ɂ���A593�N�ɑ�O�N���炪�����ɂ�肨�J�肵�� �ޗǎs�ŌÂ̐_�Ђł��B���̎O�}�Ձi���������̂܂�E���܂�j�͖��N6��17���ɍ֍s����܂��B���̂��Ղ� �ł́A�����A�����̐_���������ɐ���A���̎��͂��O�֎R�ɍ炫�����S���̉ԂŖL���ɏ���A�D��Ȋy�̉��ɂ�� �_�O�ɂ���������܂��B�����āA�O�}�Ր_�y(�ޏ����u�O�}�̕S���v����Ɏ����A�_�y�u�����݂�̕��v���l�l�ŕ�t :�E�̎ʐ^)�����B���́A�����Ƃ��̎q���B�Ƌ��ɔq�ς����Ă����������B�A�蓹�Ŋ����_�Ђ̑O��ʂ�����"���{����@���a�l�𗬎����["�Ə�����������Ă����B���͔q�ς����Ă����������� �����Ă������B�����[�͏I����Ă������A�_�O�ɂ�"����(�͂Ȃ�����)�u�O�}�Ձv"�Ə����Ă���A�T�T��������[ ���Ă������B�ǂ����A"����_�Ђ̂��܂�"�ƊW�����肻�����B
2019.6.13
�l�ԃh�b�N-���̌�(2)
2019.6.4�̎��̃u���O��ǂF�l����"�M�N�́uX��CT�ŕ�����Ȃ��Ȃ炻��ő��v�v�Ɣ��f���ꂽ�悤�ł����A ���͋M�N�ɁuMRI�ł̐�����������f�����v���Ƃ��������߂܂��B���̗��R�́A�u�X�����͕������̂ŁA �o������葁���ɔ������āA���Â��邱�Ƃ��̗v�ł���v����ł��BX��CT�ŕ�����i�K�܂Ői�s����ƁA��x��� �Ȃ�S�z������܂��̂ŁA�uMRI�ł̐�����������f�����v���Ƃ��������߂܂��B"�Ƃ�����ӌ������B �e�Ȓ����ŁA���͗L���Ɗ��ӂ����B���͍čl�����B�����āA���_���o�����B���͌���77�˂ł���B�����̐l�X(��t�E��y�E�F�l�E�w���E�Ƒ��E�e���E�אl��)�̂����b�ɂȂ�����Ă����B �d���Ƃ����w�������ł́A�����Ȃ�ɑS�͂𒍂��E�w�͂����B�����āA�����̐l�X�̋��͂Ɖ����E�K�^�� �b�܂�āA����Ȃ�̐��ʂ��グ�邱�Ƃ��o���܂����B���̂��Ƃɂ͖������A�����Ȃ��E�ƂĂ����ӂ��Ă��܂��B �ސE��́A�B�X���ӂ��āA�y���������𑗂点�Ē����Ă��܂����B��������N�Ɍb�܂ꂽ�����ł���܂��B �̗́E�m�͔͂N��Ƌ��ɐ����Ă����܂��B�e�j�X���o����悤�Ȍ��N��Ԃ͂���Ȃɒ��������Ȃ��ł��傤�B ����������������e���A�����̐s����܂Ő�����̂��l�����Ǝv���܂��B�����̔N����l����ƁA�X������ �������Ƃ��Ă��E�E�E�����łȂ����Ƃ��F�O���܂����E�E�E��e���邱�Ƃɂ��܂����B
�ƁA�����킯�ŁuMRI�ł̐��������͎�f���Ȃ����Ƃɂ��܂����v�B�������ĉ��������F�l�ɂ͐[�����ӂ��Ă��܂��B ���Ȃ͗F�l�̈ӌ��Ɏ^�����܂����B�����͎��̌��_�Ɏ^�����܂����E�E�E����ɂ͎����������B
2019.6.9
�~�̎��̍̎�E��̙���
6��8���ɒ�ɂ���~�̎��̍̎�������B�����̒��j(��2)�Ǝ���(��6)���u�~�̖ɓo���Ď�����肽���v �Ƃ����̂ŁA��Ȃ����ǂ��傤���Ȃ��A���ꂼ��ɐ��̎悳�����疞�������B�~�̎��̍̎悾���łȂ����� ������̂��ړI�ł���B���ꂪ�Ȃ��Ȃ��̍�ƂŊ��댯�ł���B�����I�����ăz�b�Ƃ����B6��9�� �t�W�A�m�E�[���J�Y���A�A�P�r�A�T���U�V�A�c�o�L�A�����A���E�o�C�A�h�F�A�T���V���E�̙���������B ���ꓙ�̙����Ƃ͋r�����g���čs���̂ŁA��r�I���S�ł���B�������A�T���V���E�ɂׂ͍�����������̂�? �����Ƃ�����Ɛg�̂��y���Ȃ�B�܂��܂���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����c���Ă��邪�E�E�E��ꂽ�̂� �~�߂��B����A�܂����C���ł���A�c��̙�������邱�Ƃɂ��āE�E�E�B
2019.6.4
�l�ԃh�b�N-���̌�(1)
5��21���ɐl�ԃh�b�N�̌��ʂ��f���ɕa�@�ɍs������A�S����Ɂu�����A�~���[�[�̒l������(152 IU/L)�̂ŁA �X�����̌��������������ǂ��ł��傤�v�ƌ����A���t�̍̎�E������X��CT�̑�������Ē������B�������̌��� ��u���ɍs�����B�S����́u���t�����̌��ʂ́ACEA:0.9ng/mL �G�X�^�[�[1:103ng/dL CA19-9: 14.4U/mL�����ǁA �g���v�V��: 765ng/mL�ƍ����BMRI���B���Č��������������ǂ��ł��傤�B�Љ��������܂�����A������ �傫�ȕa�@�ŁAMRI�ł̐����������Ă��������v�Ƃ�����������B���́uX��CT�̌��ʂ͂ǂ��Ȃ�ł���?�v�Ɛq�˂��B ��t��X��CT�̉摜���o���āu����ł͗ǂ�������܂���v�Ƃ��������B����"X��CT�ŕ�����Ȃ��Ȃ炻��ő��v" �Ɣ��f�����B�E�E�E�ŁA���́u�Љ��͌��\�ł��v�ƒf�����B"�\���Ȑ������������_����������ꂽ�S����͗ǂ��Ȃ�"�Ǝv���B2019.6.3

�����̗��K
�č��ɏZ�ގ������q��3�l��A���6��1���̗[���A�ޗǂ̉䂪�Ƃɂ���ė����B�č��̊w�Z���ċx�݂ɂȂ����̂ŁA ��ԔN���̑��q����{�̏��w�Z�Ɉꃖ���قǒʂ킹�āA���{���b����悤�ɂ���̂��ړI�炵���B�N��̖��B�� �ʂ킹�����̂����A�����ʂ�ɂ��Ȃ��Ȃ����̂Œf�O�����l�ł���B6��2�� ���H�ɂ��D�ݏĂ����֍s�����B"���D�ݏĂ�"���D���Ȃ̂ŁA������͏�����B�A��ɁA�e�����\�������B �����\�����D���ł���B�ƂɋA���āA�������������Ƌ��ɒ������B
6��3�� ���A�|�̎q(�^�|)���Ă��āA���~�����B�|�̎q�͎�����Ƃ̍D���ł���B���̈ꕔ���A�[�H�p�ɒ��������B �ߌ�A���厛�啧�a����t����ЁE�������ւƕ����čs�����B�E�̎ʐ^�͏t����Ђ̓|�ŁE�E�E�B�����������A �܂��^�Ă̏����łȂ��̂ŏ��������B����13000�]�B
2019.5.26

�x�j�o�i���}�V���N���N�ĖK
2018.5.27�̃u���O�ɋL�ڂ������s�{��O�s���R�����v�ۂ̃x�j�o�i���}�V���N���N�̔������ɖ������� ���N���ӏ܂����Ă����������B�C���^�[�l�b�g�ō��N��"�x�j�o�i���}�V���N���N�t�̊Ϗ܉�"��5��25���E26�� �ɊJ�Â���邱�Ƃ�m��A�Ԃŏo�����čs�����B10:30�ɉƂ��o��12:00�ɔ��R�����v�ی����قɒ������B �������H�𗘗p����ƁA�ƂĂ��Z���Ԃōs����̂ɋ������B�ۑS���͋�300�~���A���H�ٓ��𒍕������� �u11:00���A���肫��܂����B�R�ؓV�Ղ�Ƃ������݂Ȃ炠��܂��v�Ƃ̂��ƂŁA��������ߓ��݃e�[�u���ł����������B�����ق̗��R���x�j�o�i���}�V���N���N�̌Q���n�ŁA�ۑ���̕����u���N�͊����ĊJ�Ԃ��x���A����ƍ炫�n�߂܂����v �Ƃ���������Ă������A���Ғʂ�̔������Ԃ��ӏ܂����Ă����������B�ƂĂ��������E���M�ȉ�(�E�̎ʐ^)�Ŗ������� �܂����B
�������E�E�E�ǂ��������C�ł��Ă��������I�@�ǂ����ǂ��������C�ł��Ă��������I
2019.5.23
���̒��ւ�
���͓�K���ĉƉ��̈�K�̏��~���̕����Ƀx�b�h��u���ĐQ�Ă���B�ŋ߁A���̏�̏������ƃt���b�� ���肷�鎖������悤�ɂȂ����B�č��ɏZ�ގ������u�Z���ɓޗǂɗ��Ĉꎞ�؍݂���v�ƌ����Ă����B ������"�Y��D��"�Ȃ̂ŁA�䂪�Ƃł̓_�X�L���ɗ���Œ��O��"�g�C����䏊�̑|��"�����ĖႤ�B�������A ���̏C�U�͋}�ɂ͏o���Ȃ��B���͏���グ�ėl�q�����Ă݂��B"�V���A���ɂ���Ă���̂�"�ƐS�z�������A �K�������ł͂Ȃ��A���ɒ����Ă���x�j���̐ڒ��܂����āA�x�j�����o���o���ɂȂ��Ă��邾���ŁA �y��̍\�����͂������肵�Ă��Ă��鎖�����������B����Ȃ玩���Ŏ�����Ǝv�����B����ŁA�Ƃ肩�������̂����ǁE�E�E�A�x�j�������O���̂���ς� ��Ƃł������B"����Ⴀ����ɂ߂邩������Ȃ�"�Ǝv�����B�z�[���Z���^�[�֍s��"��̓���"���Ă��āA ����ɂ߂Ȃ��悤���ӂ��Ȃ����Ƃ������B����"�x�j����̂͑�ς�����̂Ȃ���̔낤"�� ���߂��B���ꂪ���������B�T�C�Y���v���āA�z�[���Z���^�[�ł��̃T�C�Y�ɐؒf���Ē����B��������ɒ��� �����ŗǂ��B�Ƃ������ƂŁA����"���̒��ւ�"���I���邱�Ƃ��o�����B�ł��E�E�E�ēx���邱�Ƃ͌��ցB
2019.5.21

�l�ԃh�b�N
4��23����"���A��l�ԃh�b�N"�̌��������B�u���̍ɂȂ��Ă܂���������?�v�Ə�ꂻ�������A �u�����������������v�炵���B�����A���̌��ʂ��f���ɕa�@�ɂ������B��t�́u�N����ɗ͐f���܂����A �����Ė��͂���܂���B�����A�����A�~���[�[�̒l�������̂ŁA�X�����̌��������������ǂ��ł��傤�B ���H�͐H�ׂĂ�����ꂽ�ł��傣�ˁv�Ƃ�����������B�u�H�ׂĂ��܂����v�Ɠ��R�̓����������B�uX��CT�� ��H���ĂƂ�̂ł����A�_�����ŎB���Ă݂܂����v�Ƃ�����������B�E�E�E�ŁA����"������X��CT"�� �B���Ē������B�u���ʂ�6��4���ɗ��Ă��������v�ƁE�E�E�B���̒lj�����3�����S��6,930�~�B�E�̎ʐ^�͉䂪�Ƃ̒�ɍ炢���V���N���N�B
2019.5.17
��R�鑺�ĖK
�����̏��߂ɋߓS�ޗljw�߂��̌����_�ŐM���҂������Ă�����A��R�鑺�ɏZ��ł���������s���� ���v�Ȃ��ڂ̑O�ɂ������������̂Ő��������A�߂��̎��̃}���V�����Ɋ���Ē������B���̍ہA ������ɂ��Ă��������� Gallery Den mym �̌�����p�̓W����u�����W�v(5��12��-5��25��)�� �p���t���b�g�����B2017.9.19�̃u���O�ɋL�ڂ����@���s�Ƒ��ɏZ�ޒ��ԂQ�l�ɐ�����������17�����D�s���Ƃ����̂ŁA 17��9:30�ɋߓS�ޗljw�O�ɏW�����A���̎Ԃɓ��悵�ďo�����čs�����B�u��3����"���̉w �����̋��s �݂Ȃ݂�܂��둺"��11:10�����Ă��������v�Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA���m���ՂƐ������ɗ�������āA11:10 "���̉w�����̋��s�݂Ȃ݂�܂��둺"�ɒ������B���̉w�̊e���ɎႢ��Ƃ���̍�i���W�����Ă������B
���w�E�ӏ܂̌�A���̉w�̐H���Œ��H��ۂ����B���̌�A��1����Gallery Den mym �{�قֈړ������B �����͂s���v�Ȃ̎���̈ꕔ�ł���B���w�E�ӏ܂̌�A��ł����������������B�����ŁA500m�����ɂ��� ��2����"AIR��R�鑺" �֍s�����B�A�[�e�C�X�g�؍݁E����̊قƂ���T����̉����ݗ����ꂽ���̂ŁA �u��i�̐���A�W���A�ӏ܁v�̏�ł������B
T����̐����͔_�Ƃ��̂��̂ɋ߂��A���̐����p���ɂ͊��Q�����B���N�ł����Ă����o����Ǝv�����B ��Ŏ����Ă���������{�̋ʎq�ƃG���h�E�����y�Y�ɂ��������ċA�����B�M�d�ȕ��������������B���ӁE���ӁB
2019.5.3

10�A�x
10�A�x�Ƃ����̂œޗǂ͑����̐l�œ�����Ă���B���̂悤�ȊՐl�͂��̗l�Ȏ��͉Ƃł����Ƃ��Ă���̂� ��ԗǂ��B4��27�� �_��R�֍s�����B�c�c�W�͂܂��`���z���炫�B�_�쎛�̃N�����\�E�͖��J�ł������B
4��28�� 11:00-12:30 �e�j�X�X�N�[���B
4��29�� ��̋��ɔ����L���E����A�����B
4��30�� 11:00-12:30 �e�j�X�X�N�[���B
5��1�� �@��q�c�W�O�T�̔��Ƀ��_�J�����Ă������A�����Ă݂�ƁA���̒����S�`���S�`���ɂȂ��Ă����B �C�^�`�ɏP��ꂽ�̂��B�ŋ߂܂ŖԂ������Ă����̂����A�肪�L�тĂ����̂ŊO�����B�g�������ē����̈��� ���_�J�����ꂽ�B
5��2���@�M�y�̓��|�̐X�ŊJ�Ò�(2������5���܂�)�̍�Ǝs�֍s�����B���|�̐X�t�߂�4km���s���̂ɁA�a�� �P���Ԃقǂ��������B���Ȃ����s���Ȃ����������B���{�G����̍�i�����N���������B���C�ł�����̗l�Ŋ��� �������B�A��Ɉɉ�Ă̓���s�ɂ�����������B�M�y���ɉ����R�̐l�œ�����Ă����B��Ƃ���B�ɂ����C�� ������"���������邢"�Ǝv�����B
5��3���@�䂪�Ƃ���500m���̏��ɂ��鐹���V�c�˂ŁA�V������ �W�N�i756�j 56�ŕ��䂳�ꂽ�����V�c�̌�� �@�v"�R�ˍ�(���厛��R�̑m�����Q�q�A�E�̎ʐ^)"������A�q�ς����Ă����������B
5��4���@�������k�~�������ʌ��J����Ă����̂Ŕq�ς����Ă����������B���p�~���̖k�~���A�ؐS�����̎l�V�������A �^�c�̔ӔN�̕����Ƃ��Ēm���Ă���ؑ����ӕ������A�ؑ������E���e��F�������S�č���̗D����̂ł���B ���̌�A����قɍs�����������ō��G���Ă����̂ő��X�ɊO�ɏo�ēޗnj������U���B
5��5���@11:00-12:30 �e�j�X�X�N�[���B�ޗǂ̏��X�X�͍��G���Ă��āA�����̂ɂ��̂��G�ꍇ���B
5��6���@��R�鑺���̉w�Œ��H��ۂ�A�ɉ�s�������ɂ��鉷��"��Ԃ�����̓�"�̒��ԏ�ɎԂ��߁A�ؒÐ쉈�� �̗V����������Ċ�q���������s�����������A�����B�����łQ���ԁB���̌�"��Ԃ�����̓�"�ɓ������A����B �K���A�a�͂Ȃ������B���������A����ŘA�x���I���B
2019.4.26

�^�P�m�R
���ł͍��A�^�P�m�R�̍Ő����ł���B����A�^�P�m�R�����Œm��ꂽ�ѐ����֍s����"�����̂����"���������������A �����쐫�������炸������Ȃ������B����ŁA���������̂������ō�낤�ƍl�����B�O�����J�������̂ŁA���������� ���������^�P�m�R����ɓ��邾�낤�ƁA�߂��̐��Y�Ҏ������݂̂��X�֊J�X����ɍs���āA���s�R��Y�̃^�P�m�R�� �����B�ƂɋA���āA����䥂ł�(���f������1����30���ϕ��A���߂�1���ԕ��u���A����ނ���1���Ԑ��ɂ��炵��)�B�ȏ�̉���������ς������Ƃ͊ȒP�B��Ԃ̓y���ρA�ϕ��A��|�A�����̂���сA�̉�a��(�E�̎ʐ^: ���ɁA����A �E��A�E���A�����A�^��)��������B�ѐ����̗l�ɐ�������Ă��Ȃ����A⡂̎����ǂ��A�ƂĂ��������������B�����A�����ł���B
2019.4.13

���s
���̓��͉����\�肪���������̂ŁA�ӂƎv�����āA���s�̐��ÊقŊJ�Â���Ă�����W�u�������[��Ɛ����v ���ςɍs�����B����d��"�_�{�ۑ���"�ʼn��Ԃ��A�ۑ����ʂ�𓌂։��蓌�V�����܂ŕ����čs�����B���̂�����́A �t������߂��������������ꏊ�ŁA�����Ȃ��犴�S�ɂӂ����Ă����B���̂ǂ���ɐ��Êق�����B�Z�F�t���� �������悮���l���E�ɓ���ďW�߂�"������̓W�ϐȁE�����Ȃł̒������[��Ɛ�����"��W�����Ă����B���Ƃ��Ă� �������[���蕶�l��̕����y���߂��B���Êق͐���̃R���N�V�����ŗL���ł��邪�A���̎��W�̂��������� ������̓W�ςł��������Ƃ�m�����B�ϗ����I���ĊO�ɏo��Ɖ����̏��t���a�ł������̂ŁA�܂����̉Ԃ��c���Ă��邱�Ƃ����҂��āA�����_�{�֍s������ �ɂ����B�r���̏��H���v���o�̓��ł���B�����_�{�ɎQ�q���A�_���ɓ���Ă����������B�g�}�����͖��J�������߂��� ������(�E�̎ʐ^)�A�܂��\���̉Ԃ�t���Ă����B���̐_���̍��E���a�͐t�̎v���o�̏ꏊ�ł���B
�����肫�@���̂��Ƃ��@�l���肫�@�����悭�݂�@�t�̌��@(�g��E)
2019.4.15
�F�m�@�\����
�ޗnj������ψ�����"�M����75�ˈȏ�̍���҂ł�����F�m�@�\���������A���̌㍂��ҍu�K����u���Ȃ���A �^�]�Ƌ��̍X�V���ł��܂���"�Ƃ̒ʒm���������B�{��10:30���ޗnjx�@���ŔF�m�@�\���������B���̔F�m�@�\ �����̑����_��94�_�ł������B�m�l�̏����́u96�_�ł������v�Ƃ���������Ă������炻���舫���B�ł��A�덷�̔� �͓��Ǝ������Ԃ߂��B�u76�_�ȏ��"�L���́E���f�͂ɐS�z����܂���"�̔���ŁA"����ҍu�K(2����)"�������ԋ��K���� �Ă��������v�Ƃ���ꂽ�B12:00�ɉ䂪�Ƃɖ߂�A�����A�߂��̎����ԋ��K���֓d�b���u����ҍu�K(2����)�̗\������肢���܂��v�ƌ�������A �u�{��15:00����@���H�v�ƌ���ꂽ�B����ł͂Ƃ��肢����"����ҍu�K(2����)"�����B�悸�����ŁA�Î~����1.0�A ���̎���0.3�A��Ԏ���31�b�A�E�ڎ���p�x85�x�A���ڎ���p�x85�x�Ŕ���͕��ʁB���̌�A�u�`(30��)�Ǝ��Ԏw��(60��)�� �A"����ҍu�K�I���ؖ���"���ċA���Ă����B
���b�L�[�Ȃ��ƂɈ���ōςB���Ƃ́A�^�]�Ƌ��Z���^�[�։^�]�Ƌ��̍X�V�ɍs���������B�Y��Ȃ��悤�ɁE�E�E�B
2019.4.13

�炫�܂���"���x"
�R�ŃA�P�r�̎����̂��Ă��āA�H�ׂ���̎���ɓf���̂ĂĒu������肪�o�āA���ꂪ�傫���Ȃ��� ���ł͖��N�t�ɂ͑�R�̉Ԃ��炩������t����悤�ɂȂ����B���̒��ɁA5�̑ȉ~�`�̏��t������ɂ��A�P�r�� 3�̏��t������ɂ��~�c�o�A�P�r���������B���҂��ꂼ��قȂ����Ԃ�t���A�ƂĂ��������A���͑�D���� �ԕr�ɂ������Ă���B���̂��Ƃ�_�ˑ�w�ł̔N��̋����ɘb������"�A�P�r���ǂ����ǃ��x���ǂ��ł���B�ʎ��� ���x�̕�����������"�Ƃ�����������B2017.5.2�̃u���O�ɋL�����l�ɁA���x�̕c����ɓ���邱�Ƃ��o�����B������ɐA���Ă�������A�傫���Ȃ��� ���N�͂��߂ĉԂ�t���A���ɊJ�Ԃ���(�E�̎ʐ^)�B
���x�̓A�P�r�Ȃł����A�A�P�r�͓~�ɂȂ�Ɨ��t���܂����A���x�͗��t���܂���B�V�q�V�c��������Ɏ�ɏo���������� ��ό��C�ȘV�v�w�ɏo��A�����̔錍��q�˂���A�V�v�w�́u���a�����̗�ʂN�H�ɐH���܂��v�ƌ����āA 1�̉ʎ��������o�����B���̉ʎ���H�ׂ��V�q�V�c���u���x�Ȃ邩��(�����Ƃ��ł���)�v�Ƃ���������̂ŁA���� �ʎ��̓��x�ƌĂ��l�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł���B
2019.4.1

�F��H
��N�O�Ɏn�߂����t�̌F��H�E���������h���C�u���s�����N�������Ȃ����B�o���̎O���O�ɍ�N���܂��� ���ǂ��������̕�̗��قɓd�b������O�����͖������Ƃ̂��Ƃł������̂ŏ\�Ð쉷��̘V�ܗ��� �ɓd�b������"3��29���Ȃ�ꕔ���Ă܂�"�Ƃ̂��Ƃŗ\���B�����ꔑ�������̂Œ։���̓������ق� �\��3��29��9:45�ɉ䂪�Ƃ��o�������B�哃���y�ق�"�������Ǝh�g����ɂႭ"��H�ׁA�J���̂苴������(���s�̋��Ȃ͋C���������Ɠr���ň��� �Ԃ���)������A13:00�ʒu�_�В��ԏ�ɒ������B�ʒu�R�R��(�W��1077m)��30����ōs���A���̒����ɂ��� �ʒu�_�Ђ͌F��O�R�̉��{�ł���A���̎���ɂ͎���3000�N�Ƃ�����_�㐙���͂��ߘV���E�������R���� �Ă��đ����ȕ��͋C������A���͑�D���Ŗ���K��Ă���B16:30�\�Ă��������قɓ����B�����A����� �������B�E���͋C���ɗǂ������B�I�V���C�ɓ����Ă���ƃA�I�o�g�̖��������������B�[�H�E���H�� �R�̍K�Ɛ�̍K�����āA��������Ă��ĂƂĂ��������������B��������͏\�Ð�_���ƎR�X�����߂��ƂĂ� �Â��ł������B
3��30��9:30�`�F�b�N�A�E�g�B9;45�F���E������E��c��̍����_�̒��F�ɂ�����(������̂͂�A����22�N �̑吅�Q�܂ŌF��{�{��Ђ��������ꏊ�A�E��̎ʐ^)�ɓ����B���̘e�ɂ͌F���̍L��ȉ͌�������A���� ���C�ɓ���̏ꏊ�ł���B����A���̉͌��Ő��E���Ă��āA�ޗǂ̎��̕����̑O�̒�ɒu���Ă���B
�V�{�����_����311�����ɓ���A�쒆������o�X�₩�璆�ӘH������F��w�̐l�X�̍A������������:�쒆�̐����� �s�����B�߂��̒��ԏ�ɎԂ��߁A���̏�ɂ���p�����q(���q�͌F��Ó��ɂ���_�l)�֍s������A�ׂɂ��� �Ö��Ƃ��炲�w�l���o�Ă���"�쒆�̐����œ��ꂽ�����ł�"�ƍ����o���Ă����������B"�ߗׂ̗L�u������ �ڑ҂��Ă��܂�"�Ƃ̂��Ƃł������B�p�����q�ɂ͐��{�̐��̘V��(�쒆�����)������A���j�����������Ă��ꂽ�B
���̉w �F��Ó����ӘH�Œ��H��ۂ����B���̓��̉w�͌F��Ó����߂��ɂ���A�Ó�������l���x�e���Ă����B 20�l���̉��Đl(�c�̂łȂ��A1�l�܂���2,3�l�̃O���[�v)�����āA���{�l�͐��l�B�F��Ó�������͉̂��Đl�� �l�C������悤���B���Ƌ��Ȃ��F��Ó��������������ƎR���ɓ��蔢�܁i�͂�����j���܂ōs�����B ���ɂ͂ɂ����⸈i�ߘI�̕�:�j�Ƌ��n���q�i���イ�ǂ���:���Ɣn�̓ɏ�����ԎR�@�c�̗��p�� �Â�Œ���ꂽ�Ε��j���������B�����Ŗ�ꎞ�ԁB
 16:30�։���̗��قɒ������B�����A����ɓ������B���ق̍ŏ�K(4�K)�ɉ�����A�ڂ̑O�͊C�A���]���ǂ��A
���ǂ������B18:00���[�H�B"���h�̗���"�Ƃ����������B����̐��ǂ�����"�܂��ǂ�"�Ƃ��傤�B
���H�̖��X�`�͔������������B�ׂ̗��ق͕܂��Ă����B���ƂȂ�"�։���͊��C������"�Ɗ������B����ɂ��Ă��A
���Ƃ����������A���̐����͋ꂵ���Ȃ����B���葱����Ƃ����Q�]���肽���Ȃ�B���Ƃ����A�������
"���C�V��"�ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B
16:30�։���̗��قɒ������B�����A����ɓ������B���ق̍ŏ�K(4�K)�ɉ�����A�ڂ̑O�͊C�A���]���ǂ��A
���ǂ������B18:00���[�H�B"���h�̗���"�Ƃ����������B����̐��ǂ�����"�܂��ǂ�"�Ƃ��傤�B
���H�̖��X�`�͔������������B�ׂ̗��ق͕܂��Ă����B���ƂȂ�"�։���͊��C������"�Ɗ������B����ɂ��Ă��A
���Ƃ����������A���̐����͋ꂵ���Ȃ����B���葱����Ƃ����Q�]���肽���Ȃ�B���Ƃ����A�������
"���C�V��"�ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B3��31��9:30�`�F�b�N�A�E�g�B42������k��B�r���̊C��(�E���̎ʐ^)�œr�����ԁE�U��B13:00�a�̎R��֍s�����B ���̉��ɃV�[�g��~���ĉԌ������Ă���l�������ς��ł������B16:00�ޗǂ̎���ɋA�������B
2019.3.28

���炭
�����Ԓg�����Ȃ����B�Ƃ̒��Ɏ�荞��ł��������O�ɏo�����B��̔~�̉Ԃ͂�������U�����B�A�P�r�� �J�Ԃ�����B�P��N�A�������x�ɉԉ�炵�����̂��t���Ă���E�E�E�ǂ�ȉԂ��炭���y���݂ł���B���H��̎U���œ��厛�啧�a�̑O��ʂ�����A�啧�a�O�̒�ɐ����Ă�������ܕ��炫�ł������B ����ŁA�v���Ԃ�ɑ啧�a�ɓ������B�E�̎ʐ^�͒���e����B�����ʐ^�ł���B���̍��͂܂��`���z���J�� �ł���̂ɁA���̍��͔������炢�Ă����B
�X���_�Ђ̎}�������ςɍs�����B���̌����Ȏ}�����͂������萊���đ����}�͌͂�Đ����A�͂��� �c�������}�Ƀ`���z���Ԃ����Ă��邾���ł������B�e�ɐA����ꂽ������h�ɉԂ��炩���鍠�ɂ́A ���͂��̐��ɂ��Ȃ��B
2019.3.23
���̗��K
���֎s�ɏZ�ޖ��̒�����"����̕���i���ߓS�f�p�[�g�ޗǓX��3��20-24���ɔ̔�����̂œޗǂ̃}���V���� �ɏh�������Ăق���"�ƌ����Ă����B����"�ǂ����E�ǂ���"�ƌ������B��������A�������̍�"�ޗnj���"���������� 2�l��19���ɓޗǂɂ����B21���ɂ́A���A���ȁA���ƎO�l�ő�a�S�R�ɂ����ɔފݎQ��ɍs�����B�A��ɁA��a�S�R �̃C�^���A�����X�g�����Œ��H��ۂ�����A�ߓS�f�p�[�g�ޗǓX�ɗ������"����̕���i"��q�ς����Ă����������B �u���[�`�⎨�����q�ς������Z���X�̗ǂ��I�V�����ȕi�ł������B������"�Ȃ��Ȃ�����Ȃ�"�Ƃ̂��Ƃł������B22���ɂ́A���É��ɏZ�ޖ��̎����Ƃ��̒���������Ă��āA�}���V�����͓��₩�ɂȂ����B25���ɂ́A�d�����I���� ���̒������������"�ޗǂ̋x��"���y���ޗ\��ł���B
2019.3.15

�t�̓���
���厛���̏C���(�������)���I�����B�ޗǂł�"������肪�I��Ət������"�ƌ����Ă��邪�A���̒ʂ� �����͓V�C���ǂ��A�g�������ł������B���͘@�̐A�ւ��������Ȃ����B����A�Ȃ��Ȃ��̏d�J���ł���B�ł��A �����I�������B���H��A�U���œ��ɍs���r���A�C�����I�����m���������V�A���Ă����̂ɏo������B�����I���ăz�b�Ƃ��� �l�q����������ꂽ�B���ł�"��������X����������"���s�Ȃ��Ă���(�E�̎ʐ^)�B����́A�C���Ŏg��ꂽ ���ؖX���q���̓��ɂ̂��Č��₩�Ȑ������肤�s���ł���B���́A��ꃖ���Ԃ�ɖ@�ؓ��̒��ɓ���Ă������� �{���s��㮍��ω���F�A���V�A��ߓV�A�����͎m�i���݁j�A�l�V������q�ς����Ă����������B
2019.3.9
�ޗnj����E���T����
3��9���͓��{�쒹�̉�ޗǎx����"�ޗnj����E���T����"������A���͒S�������ɂȂ��Ă����̂ŏo�����čs�����B ���͓��{�쒹�̉�ޗǎx���̉���ɂȂ��Ă���40�N���邪�A�ŋ߂͂��܂�M�S�ł͂Ȃ��Ȃ����B�Ⴂ���ɂ͑�� �����b�ɂȂ����̂ŁA���߂ĒS�������Ɏw�����ꂽ���ɂ͎Q�������Ă��������Ă���B�U�����鎞�A���̖����E�p �������ۂ�"���̖��O�ł��m���Ă������w�y���߂邾�낤"�Ƃ����̂��A�����쒹�̉�ɓ���Ă����������������� �ł���B���̓��̒T����ւ̎Q���҂�58���B�����A�����Ȃ����B����҂������Ȃ���"�����������āA���̖����E�p�� �y������"�Ƃ����l�������Ȃ����Ǝv����B9���ɋߓS�w�L��ɏW�����āA11:30�����厛�������t�߂�"�����킹( �o��������̖��O�̊m�F�A���̓���29��)"��������A���U�����B
���͂��̌�A�ޗǍ��������ق֍s���A�n���̃��X�g�����Œ��H��ۂ����B�����ĊJ�Ò��̓��ʒ�"�������"�� "���q����̓����Ɖ�������"��q�ς����B
���̉� (��c �q �C�������)
�퐶�������A�͂�
�C�̂��Ȃ��̐Â�������
�ւ��Ă��ʁA���ꂵ�������B
�t�̂͂ԁA�ɂقЂ�q�ނ�
���T�A��낱�т̂����
���Ɣ��Ƃ̐����Ȃ�
�t�̐S�̕��p�B
�E�E�E
2019.3.4
���̎U����(1a)
2017.11.28�ɋL�����啧�a������̑����ł���B�啧�a���̓���^���������ɐi�ށB����ƁA���Ɏ���B���������2019.1.12�ɋL�����R�[�X�Ɠ����ł���B ���ꂪ�A�����ł������I������R�[�X�ł���B���́A���ł͏C���(�������)���s���Ă���A���H��ɍs�� ���Ă�̑m�����H��ł��낢�ł���p��������B�ۑ��~���ł͎�X�̔~�̉Ԃ����J�ł���B
�ޗǂ̂��َq������ł́A���̎����A�������Ŏg��"�ւ̑���"�Ɉ����َq�\�����Ă���B�ǂ�� �������Ė��͓I�ł����A���͋e����"�J�R��"���D���ł���B���厛�J�R���̖���"�Ђ��ڂ�"�Ɏ������a�َq �ŁA�F�E���Ƃ��ɗǂ��B���p�̒���ŁA�����������������A���������a�َq�����������B�����̎��ł���B
2019.2.27

��������
��N���Ƃ��̎����A���͐�i�F�����邽�߁A�k���̉����K�˂闷�ɏo��̂����ǁA���N�͖k���ɐϐႪ�قƂ�ǖ����B ����Őϐ�̑������k�n���̉����K�˂邱�Ƃɂ��A���������I�B�h�̎�z�A�S���ؕ��̗\��̓X�}�[�g�z���ōs�Ȃ����B2��24��8:28�ߓS�ޗǔ��ɏ��A���s�w�œ����܂ł̐ؕ��A�����w�œc��܂ł̐ؕ������A15:09�c��Ήw�ɒ������B �����[�c��ΊԂ̗�Ԃ͖��Ȃł������B�\�Ă����ėǂ������I�c��ŏ�Ԃ���o�X�̔��Ԏ������h�ɒm�点���B �A���p���܂����̃o�X��ɏh�̎Ԃ��҂��Ă����B16:30��������̏h�F�߂̓�(�E��̎ʐ^)�ɒ������B
�ϐ�͐����܂łقƂ�ǖ����A���B���ǎR�A�����R�A�D�`�R�������R�Ɍ����邾���ł��������A�H�c�V�����ɂȂ�� �����̕��n�ɂ��ϐႪ����悤�ɂȂ�A��������ɂȂ�Ɛϐ��1m�ȏ�ɂȂ薞���ł������B�߂̓��ɂ͉���5����A ���قȂ萬�����قȂ�Ƃ̂��Ƃł��������A�ǂ�������̂����ł������B30�l�͓����j�������̘I�V���C���������B �[�H�͎R�E�L�m�R�����S�ŁA�R���̒c�q�`���������������B���̓C���i�E�A�}�S�̐싛�����B �R���̏h�̖����y���܂��Ē������B
 2��25�� ���H�����܂��ĉ���ɓ�������A���R�̓����R(�G�X�q�x1477m)�ւ̓o�R���ɓ���A�o�R�҂̑��Ղ�H����30���ق�
������(�E���̎ʐ^�͂��̓r��)���A����ȏ�͊댯�Ɣ��f���Ĉ����Ԃ����B
2��25�� ���H�����܂��ĉ���ɓ�������A���R�̓����R(�G�X�q�x1477m)�ւ̓o�R���ɓ���A�o�R�҂̑��Ղ�H����30���ق�
������(�E���̎ʐ^�͂��̓r��)���A����ȏ�͊댯�Ɣ��f���Ĉ����Ԃ����B�߂̓��ł̘A������]���������t�̂Ƃ��ƂŁA1km�قǗ��ꂽ���ɂ���ʊ�:�R�̏h�ɁA���H��ړ������B�n���̖؍ނ��g���� ����6�N�Ɍ��Ă�ꂽ�����̌����ŁA�����3�őS�đݐؐ��ŁA���̗l��1�l�œ���҂ɂ́A�������������Ȃ��Ǝv�����B ��i�F�߂Ȃ���̉���͊i�ʂł������B�U�����������ƊO�ɏo�����A�ԓ��ȊO�͐ϐႪ1m�ȏ゠�����̂ŁA�ԓ���������B �Ԃ�����Ɗ댯�ł��邪�A�ő��ɗ��Ȃ��̂ŁA��i�F���y���ނ��Ƃ��o�����B
�͘F�����͂�ł̗[�H���������������A�R���̒c�q�`�̂����ɂ��肽��ۓ�ł������B
2��26�� 10:30�h�̃o�X�ŃA���p���܂����������Ă��������A�H���o�X��11:30�c��ɒ������B 12:12�H�c�V�����ɏ��A18:50�ޗǂ̎���ɋA�������B
�߂̓��A�R�̏h���ɁA�e���r�͖����A���������E�l�����A�̂�т肨�߂����������Ƃ����h�ł������B�܂��K�ꂽ������h�ł��邪�A �����炾�Ə��X��ʔ�����̂����_�ł���B
2019.1.12

���̎U����(3b)
2019.1.9�ɋL�������q�@��������̑����ł���B����͖k�ɐi�B100m���i��ʼnE�܁E���ɐi�ޓ���100m���i��ō��܁E�k��30m���i�ނƁA�����ɋ�C��������B �O�@��t��C���J������ŁA���厛�̖����ł���B���̗��R�ɂ́A�����ȍ~�̓��厛�ʓ��̕悪����B��C�� 810-814�N�ɓ��厛�ʓ��ł������B
��C������100m���k�ɐi�ނƁA�܍��@������B���̎������厛�̖����ŁA���q����ɏĎ��������厛�啧�a���Č� �����助�i�E�d����l���n���������ł���B�����ɂ́A�]�ˎ���ɏĎ��������厛�啧�a���Č������助�i�E���c��l �̌ܗ֓�������B
�܍��@����300m���k�ɐi�ނƍ��ې�ɂԂ���B����n�炸�k��300m���i�ݍ��܂��Ėk��500m���i�ނƎO�}�쉀 �ւ̓����������B�O�}�쉀�̏㕔�Ɋ��q����̓��厛�ʓ��̕悪����B�d����l�̕�E�ܗ֓�������A�ޗǂ���]�� ����B
�O�}�쉀�ւ̓�����O��200m���i�ނƍ��ې�ɂԂ���B���ې쉈���̓���300m���i�ނƁA�g�q�_�Ђ�����B���N11��19�� �̗�Ղɂ́u��̌����v��������������키���A���i�͂Ђ�����Ƃ��Ă���B�����Ԃ��č��ې��n��A�쉈���ɕ����� �ʎ�����_��n��A�k��200m���i�ނƔʎ�O��(���q����E����A�E�̎ʐ^)�̑O�ɏo��B
�ʎ�O��O�̓��́u���X���v�ŋ��s�Ɠޗǂ����ԌÓ��ł���B�ޗǎ���ɐ����V�c�����鋞�̋S�����̂��߉����� ���Ă��Ɠ`��鎛�ł���B���q����ɕ��d�t�̓�s�Ă��ł��̍����ƂȂ�A�����͏ĖS�����B���݁A�����ɂ͗��h�� �\�O�d�Ε�(�d��)�����邪�A���q����ɑv���痈�������H�E�ɍs���ɂ���Č������ꂽ���̂ł���B
�ʎ���狌�ޗǏ��N�Y�����̑O��ʂ�A����隬�Ɍ��O�}���w�Z�̉��A�����V�c�ˑO��ʂ�A����B����8000�B
2019.2.9

�����̒��j�̗��K
��q�吶�ł��钷���̒��j�q���A�t�x�݂ɂȂ����Ƃ����̂ŁA2��4���̗[���䂪�Ƃɗ��Ă��ꂽ�B5�� ���̓e�j�X�X�N�[���ɍs���A���ȂƂq�͒��H�ɂ��D�ݏĂ����֍s�����̌�ޗnj������U�Ă����B ���Ȃ́u�ꖜ���ȏ�����Ĕ�ꂽ�v�ƌ������B
6�� �q���ޗǂ֗���ړI�̈�͎����Ԃ̉^�]���K�ł���B�Ƌ��͂Ƃ����������^�]���Ă��Ȃ��̂� �^�]���o��ێ�����K�v������̂��B����ŁA���H��A��ʗʂ̑����Ȃ����܂Ŏ����^�]���Ă����A ���̌�q���^�]�����B���\�A�^�]���o��ێ����Ă���̂ɂ͊��S�����B
7�� �q���^�]���A�������ɁA���Ȃ��㕔���Ȃɏ���āA�Ƃ���10km���̏��ɂ��郌�X�g�����s�����B���H��ۂ�A �A�H���q���^�]�����B��������M�������̂����Ȃ͋A�H�̎Ԓ��ŋ���������Ă����B
8�� �����̉J�Ńe�j�X���o�����A�^�]���댯�Ȃ̂Ŗ����B
9�� �q���^�]���A�������ɁA���Ȃ��㕔���Ȃɏ���āA��ڗ����֍s�����B���O�̒��X�Œ��H��ۂ����B���̒�ɂ� �������������J�ł������B�X�̐l�ɐq�˂�Ɓu"������"�ł��v�Ƃ�����������B��ڗ����̒뉀�̐������Ƃ��I���� �Ă���"�X�b�L��"���Ă������A�Ȃ�"�V�z"�Ƃ����������ł������B�{���̋�̈���ɔ@���̏C�����n�܂��Ă��āA ��̂��ޗǍ��������ق̏C�����ɂ��o�����ɂȂ��Ă��ĕs�݂ł������B�ܔN�����ċ�̂̏C�����s����l�ł���B �E�̎ʐ^�͖{���E�뉀���o�b�N�ɂ����X�i�b�v�B�A�蓹�̓r���ŎԂ��߂āA�_�����U���B�A�H���q���^�]�����B
���̃z�[���y�[�W��HTML�t�@�C���Ƃ��č쐬���AFFFTP�ŃT�[�o�[�ɕۑ�(�A�b�v���[�h)���Ă���̂ł����A �ꕔ�̕�����"��������"�������č����Ă����B�q�͏�H�Ȃ̊w�����Ƃ����̂ő��k������A�����Ɍ������𖾂� �������Ă��ꂽ�B���I�ƁA���ӁE���ӁB
2019.2.3

�ߕ�
�����ߕ��ł���B�����������������Ȃ����B��̐ߕ���(�E�̎ʐ^)���Ԃ��炩���Ă���B�ߕ����Ƃ� �ǂ��������O�ŁA���N�ߕ��̍��ɍ炭�B�������������ŁA�����̉ԕr�ɐ�����ƁA�������肪���� �����ς��ɖ�����B?�~�������ł���B��N�̕��ɁA�T���V���E�̐Ԃ����̂Ȃ����}���Ēu������A �Q���c���ŁA�����O�ɍ炢���B���̐����͂̋����Ɋ����ł���B�ߕ��̍s���Ƃ���"���܂�"���䂪�Ƃł�����B"���͓�"�Ə����Ȃ���A�Ƃ̒��̊e�����ɓ����܂��B �Ō�ɁA���ւ̃h�A���J����"���͓��A���͓��A���͓�"�Ə����ĂR�x�����܂��A"�S�͊O"�Ə����ē����܂��� �h�A��߂�B�����āA���̌�͊O�ɏo�Ȃ��B���܂��̌�A���������̍̐������͂�(��x�Œ͂߂���K�^)�A ���̓����B�����ŏ��ɒ͂̂�67�B10�lj������B
2019.1.26

�ᑐ�R�R�Ă�
���N���Ďᑐ�R������Ƃ�������ƐႪ�ς����Ă����B�����̎R�Ă��͒��~���ȁH�Ǝv�����B �����͐_�ˑ�ł̃e�j�X�̓��ł���B�g�̂̕��͂܂������ɂ݂��c���Ă��������P�b�g��f�U�肷��� ���ƂȂ��o�����B����ŁA�o�����čs�����B�܂��܂��A�y���ނ��Ƃ��o�����B�������S�B�e�j�X���� �Ⴊ�������~��o���āA���ƂȂ����}���e�B�b�N�ł������B�ߓS�ޗljw�ɒ����Ēn��ɏo��ƁA�ᑐ�R�ʼnԉ��オ���Ă����B�ԉ��N�X�Z�p�����サ�Ă���̂��A �������ԉ������Ă����悤�ȋC������B6:30�ᑐ�R�R�Ă����n�܂����B�����A�䂪�Ƃ̓�K�ɏ��A ���������Ă����������B�E��̎ʐ^�͉䂪�Ƃ̓�K����B�����B
���Ȃ��݂��I�[�X�g�����A�I�[�v���e�j�X�ŗD�������B���D���̃N�r�g�o������悭�撣�����B �ǂ��������������Ă����������B���Ȃ��݂���͂܂��܂������Ȃꂻ���ł��ˁB
2019.1.24
�e�j�X
�I�[�X�g�����A�I�[�v���e�j�X�ł́A�ѐD������₳�劈��Ŋy���܂��Ă��������Ă���܂��B ��₳��͌�����܂Ői��ł���A�����ł��ˁB�e���r�ŃI�[�X�g�����A�I�[�v���e�j�X���ϐ킵�āA���̓e�j�X���������ƃE�Y�E�Y���Ă��܂����B 23���̒��A�e�j�X�X�N�[���̃R�[�`����d�b��������"����11:00����̃��b�X���͑��̃����o�[�� �S�����Ȃʼn��������ł����ǂ����ł����H"�ƌ���ꂽ�B����"�R�[�`���ǂ���A���͂��܂��܂���"�� �������B�ŁE�E�E�A���k�͎������̌l���b�X���ƂȂ����B�R�[�`��"�������K���������Ƃ���܂���"�� ������������̂ŁA����"�T�[�u�̎�قǂ������Ă�������"�Ƃ��肢�����B�ŁE�E�E�A�ꎞ�Ԕ��݂�����A �T�[�u�̎�قǂ������B�ƂĂ��ǂ����b�X���ł������B
�Ƃ��낪�E�E�E�A24�����A�E�r���ɂ��ďオ��Ȃ��B�N�����Ɣ��͒x��Ă���Ă���B�O���͂Ȃ�ł� �Ȃ������̂ɁE�E�E�B�[���ɂȂ��āA�Q���A�ɂ݂����Ȃ����Ă����B���āA�����̒��͂ǂ����낤�E�E�E�B
2019.1.17
1.17
1995.1.17�̍�_�W�H��k�Ђ���24�N�A�V���ł͒Ǔ��L�����傫�����グ���Ă���B�傫�Ȕ�Q���� �_�˂��A���ł͂������蕜�����Ă���B�����̐l�E���Ƃ̎x���̂��A�ƁA�������ӂ��Ă���܂��B�����̌ߌ�A���Ȃ�������̎�p�����B���͕t���Y���ŁA�Ԃɋ��Ȃ��悹�A�����ȑO�ɔ�����̎�p�����a�@ �֘A��čs�����B���Ȃْ͋����Ă������A���͋C�y�ł������B�����̂��ƂłȂ��ƑS���C�y�ł��邱�Ƃɋ������B ��������Ȃɍ�������A����Ă����B
2019.1.12
���̎U����(3a)
���Ȃ�14���ɋ��s��"�Ղ̉��t��"�ɏo�����邻���ŁA���̒��O���t���K�̂���7:00�O�ɉƂ��o�ċ��s�֍s�����B 13�������s�֍s�������ł���B���͂̂�т�U���ɏo���B2019.1.9�ɋL�������q�@��������̑����ł���B
����͓�ɐi�B100m���i�ނƓ��厛��̒r������ɂ���B���̎�O�ō��܁A���q�@�쑤�̓��𓌂ɐi�ށB ���q�@���q�̌��w�H�������߂��A���厛�u�����̖k�[�A���������@���߂������œ�i�A�哒���̎�O�ō��܂� ���ɍs���Q�q�B�����ŁA�@�ؓ��A����R�����{�ɎQ�q�̌�A�t���쉀�n�A�ޗǍ��������ق̓������ ���āA�ۑ��~���A�Љ��A�t����Ј�̒������o�ċ������Ɏ���B�����O�\�O���ω����̑��ԎD���̓�~�� �ɎQ�q������A�O��ʂ�ɏo�A�₷�炬�̓���k�i���A���ۋ���n���āA���ɐi�ށB�V������n���č��܁A ���c����n����50m�ʼn䂪�Ƃɖ߂����B��8000���B
2019.1.9

���̎U����(3) �����V�c�˂���]�Q��
���̉Ƃ̑O�̓���k��100m���s���ƈ��ʂɏo��B�����܂ł͎��̎U����(2)�Ɠ����ł���B ���̈��ʂ𓌂ɐi�ށB100�����i�ނƍ�(�k��)�ɐ����V�c�˂�����B�����V�c�˂̓��ɂ͌����c�@�� ������B��˂ɂ͍L�t������R�����Ă���B����ŁA���ĂɂȂ�ƃt�N���E�̈��ł���A�I�o�Y�N ���Z�ݒ����āA�z�b�A�z�b�Ɩ钆�ɖ��̂��䂪�Ƃł���������B���ʂ𓌂ɂ����1km��i�ނƓ]�Q�傪����B�]�Q��̑O���k�ɋ����X��(�͓̂ޗǂƋ��s�����Ԏ�v���H) ���ʂ��Ă���B�]�Q��(�E�̎ʐ^)�͎O�Ԉ�˔��r��̌`���������X�Ƃ�����ŁA�V������̓��厛�̉������z ��z���ł���B��̈�\�ł���B���A�ꂪ����͎̂���R�����{�̍炪���̊�d��ōs���邱�ƂƊ֘A�� ����炵���B
�]�Q��̘e��ʂ��āA����ɓ��i�ނƐ��q�@�ɂԂ���A��k�ɓ����ʂ��Ă���B��i�ނ��E�k�ɐi�ނ��A ���̓��̋C���ŕ������B
2019.1.7
����
2��8:00�ɎԂʼnƂ��o�āA���܂�̋��̊��֎s���������B�T�RPA�ŋx�e���A11:20��̏Z�ގ��Ƃɒ������B ���ɓ���ƁA�i�F�����ƂȂ������ꂽ���̂ɂȂ�A���������C���ɂȂ邩��ӎv�c�ł���B���H��A��� �߂��ɏZ�ޖ��̉Ƃɍs�����B��R�̂��y�Y���āA��̉Ƃɖ߂�����A���ɏZ�ޖ��킪���ƎO�l�̑���A��� ����ė����B�Q������̗{��ɕʂ�������A�F�ŕ�Q��ɍs�����B���̌�A���͎���̗��ł�����Z�s�ɍs���A �]�o�E�]��Ɖ�����B15:00��Q��ɍs���A���̌�A�ޗǂւƌ��������B18:30�䂪�ƂɋA�������B3�� �����߂Ŕʎ�S�o�Ƃ��̖��������B��N�̂Ɣ�ׂāA���܂�i���Ȃ��B
4�� �O���̏����߂ɏd��Ȍ�肪�������̂ŁA�����������B�ʎ�S�o�̗������i�B
5�� �_�ˑ�w�֍s��"�e�j�X�̑ł�����"�������B���N�����C�Ƀe�j�X���y���߂܂��l�ɁI
6�� �e�j�X�X�N�[���֍s���ă��b�X��(90��)�����B���̃��b�X���ŕ�����4000�B�e�j�X�̌�A�����U��(4000�])�� �o�āA1���̕����ڕW8000��B�������B
7�� �ޗlj��R�̍ō��� �F�R(�ق�� 518m)�ɓo�����B�o�R���̐�����(�ӂ邳��)�܂ŎԂōs�����B���Ԃ��āA �n���̂��N���ɁA����q�˂��B"����ȂƂ��s���Ď��E����Ƃ��Ă�"�ƌ���ꂽ�̂ɂ͎Q�����B�X�}�z�� YAMAP������Γ���q�˂鎖�����p�BYAMAP�͂ƂĂ��L�p�E�E�E���ꂳ������Γ��ɖ������Ƃ������B�F�R�R���ɂ� �����U�݂��Ă���A���j��������������̂��������B
2019.1.1

2019�N���U
�V�N���߂łƂ��������܂��B���N����낵�����肢���܂��B���ȂƎ��̓�l�����̐����ł���B���G��(�Y�ł��݂��Ă��āA�卪�E���������Đ����������X�`�ɓ����) �����B���̂��G�ρA���������͌˘f�������A���ł͂������莔���Ȃ炳��āA���������B 11:00���w�ɏo���B�悸�A���_�ł��銿���_��(��������A593�N�n��)�ɎQ�q�B �����ŁA��������~���A�t����{�A�t����ЁA����R�_�ЂƎQ�q�����B12:30���厛�@�ؓ��O�̒����� ���˂��ǂ��H�ׂ��B���厛�啧�a�ɎQ�q���A�G�n�����������ċA����B15:30�ŕ���12,614�ł������B
�E�̎ʐ^�͍P��̉䂪�Ƃ̏��̊ԁB�Ԋ�͖@�����̌ÍށB�Ԃ�HK���B�|������"�啧�@�ق̑�{":���厛 �啧�̍����Ă�����@��̎���̘@�قɖђ��肳��Ă���߉ޔ@���̑�{�B���̘@�فA��x�̉ЁE�啧����� ����ł��邪�n�����̐����Ȃ���\���ł���B
���A�����̃G�l���M�[���͍Đ��\�G�l���M�[�ɂ��ׂ��Ƃ����܂��B�ޗǂ̎��̉Ƃł��A�����ɑ��z�����d �p�l����ݒu���āA�䂪�Ƃŏ����唼�̃G�l���M�[���[�����鎖���o���܂����B���z���̃G�l���M�[������� �ɑ傫�����Ƃɋ����Ă��܂��B���d���������P���i�ނł��傤�B"���Ԃ����̔��d�ł͂ӓs��"�Ƃ������͒~�d�r�� ���ǁE���P�ʼn����o����Ǝv���܂��B�����Ԃ̓d�C�����ԉ����i�ނƌ����Ă��܂��B�]���āA�~�d�r�̉��ǁE ���P�͏d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���̐i�W������Ǝv���܂��B
��K�͂ȑ��z�����d�p�l���͌i�ς��Ɣ�����l�����܂����A�댯�ɂ܂�Ȃ����q�͔��d�̎g�p�ς݊j�R���E �j�p�����̂��Ƃ��v���Ύe�ׂȂ��ƂƎv���܂��B
2018.12.29

�N�̐�
2018�N�����Ə����B�u�₩�ȋC�����ŐV�N���}���悤�ƁA�Ƃ̑�|����������A�ςݎc���̎d����ЂÂ��Ă���B ����ł��A���������đ̂����킵�Ă͈Ӗ����Ȃ��̂ŁA�ڂ��ڂ��ł���B���N�Ђ�����������낻��H�ׂ�ꂻ���Ȃ̂ŁA��N�Ђ����ÒЂ������o����"�ґ��"��������B �Â�����̓��������������ς��ɏ[�������̂ɂ͎Q�����B�ł��A�����������������Ŋ������B
�U���Ŏ�����R�_�Ђ�ʂ�����A���h�ȍ�(�E�̎ʐ^)�����������Ă������B�t����Ђ̂���Ղ�ł́A ��h���ɍ��E��E賁E��e���䋟����邪�A������R�_�Ђł�����Ȑ_��������̂��ƒm�����B
2018.12.26
�䂪�Ƃ̑��z�����d
�����̌������̂��_�@�ɉ䂪�Ƃł͑��z�����d���u�������B�ݒu���Ă���5�N�Ԃ̃f�[�^�� 2016.5.19�̃u���O�ɋL�ڂ����B���̐��\�ɖ��������̂ŁA�䂪�ƂŎg���d�͂̑S�Ăz�����d�� �܂��Ȃ����ƁA2016�N9���ɑ��z�����d���u�݂����B���̌�1�N�Ԃ̃f�[�^��2017.10.9�̃u���O�� �L�ڂ����B���̌�̈�N�Ԃ̃f�[�^�������Č��ʂ��L�ڂ���B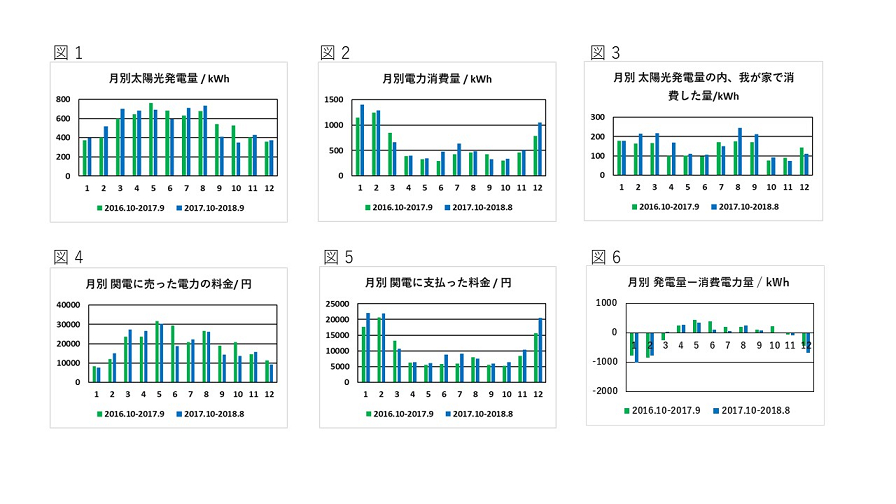
2016�N10������2017�N9���܂ł̃f�[�^�Ƌ��ɁA2017�N10������2018�N9���܂ł̌��ʑ��z�����d�ʂ�}1�ɁA ���ʓd�͏���ʂ�}2�Ɏ����B���̂P�N�Ԃ̑����z�����d�ʂ�6597kWh, ���d�͏���ʂ�7919kWh�ł������B �O�N�͂��ꂼ��6602kWh, 6976kWh�B�䂪�Ƃ̓I�[���d���ŁA��g�[�E�����E���C�E�Ɠd�E�Ɩ��S�ēd�C�� ����B�S�d�͏���ʂz�����d�ł܂��Ȃ��Ƃ����ړI�͒B�����Ȃ��������A�܂��܂��ł���B
���z�����d�ʂ̓��A���d���ɉ䂪�Ƃŏ����d�͂͑��z�����d�̓d�͂��g�p����B���̗ʂ�}3�Ɏ����B �c����֓d�ɔ���B���ʂ̊֓d�ɔ������d�̗͂�����}4�Ɏ����B���d���ł�����Ȃ������E��Ԃ̎g�p �d�͂͊֓d���甃���B���ʂ̊֓d�Ɏx������������}5�Ɏ����B2017�N10������2018�N9���܂ł�1�N�Ԃ� �֓d�ɔ������d�̗͂�����226,944�~�A�֓d���甃�����d�̗͂�����135,705�~�ł������B�T�Z�ł��邪�A ����10�N��ŏ��������̌��͂Ƃ��B
���z�����d�͉Ă͌������ǂ��E�~�ɂ͌����������B���{�ł͖k���{����{�C���ł͌����������A�����m���E ���˓��E��B�ł͌������ǂ��B�����̗ǂ���B�ŋ�B�d�͂����z�����d��ے肵�A���q�͔��d�ɒ��͂��� ����̂͂Ȃ����낤�H�H�H �@�@
2018.12.14

�c�O�~�̗��K
���N���c�O�~���䂪�Ƃ̒�ɂ���ė����B���͂������ƃT���V���E�̐Ԃ�����H�ׂĂ���B �Ԃ�����2,3���̒��ɓ����ƁA���ۂ̂����ؔ��̉��ɗ���B�b������ƁA���̒������� �͂������B����ŁA�����ؔ��̎���ɂ́A���Ɏ킪100�قǎU����Ă���B��������ȃs�A�m�� �e�������Ă������Ȃ��B�����ƒ��������Ă���B�����̍s���́A��N�̃c�O�~�ƑS�������ł���B ����Ŏ��́A���̃c�O�~�͍�N�̂Ɠ����̂��Ɗm�M�����B���̃c�O�~�A�����Ƃ肵�Ă��āA�A�I�W�A���W���A�V�W���E�K���������Ă��I�R�ƒ��߂Ă��āA �ǂ��������Ƃ����Ȃ��B�q���h���ɂ͒ǂ�������邯�ǁA�����ɂ͓����Ȃ��B�����ƃq���h���� ��������̂�҂��āA�������Ȃ��������̂悤�ɁA�T���V���E�̖ɖ߂�Ԃ�����H�ׂĂ���B ���́A"��������������������Ȃ�"�ƁA���S�ɂӂ����Ă���B
2018.12.6
���ʌv����
�����֕v����̂ЂƂ���"���ʌv����-�������Z�t�̓Ɣ�"�@�ޗnj������ޗǂ܂��Z���^�[�s���z�[�� �ŁA12��6��18:30����J�Â��ꂽ�B���͊X�p�̃r���ł����m��A�d�b�ŗ\�ďo�����čs�����B �����֕v����́A2011�N�̕����������̂��ނɂ����N�nj�"���ʌv����"���������낵�A2017�N���� ���{�S�����������Ă���������B�r��15���̋x�e�������āA20:45�ɏI�������B�����̊댯���E���_�� ����������N�nj��ł������B���͖��Ȃł������B���̘N�nj�"���ʌv����"�͒P�s�{ISBN978-4-88059-411-8 �Ƃ��Ă���������Ă��܂��B1200�~�����֕v����͌�����"���͌���78�˂ŁA���ꂪ52��ڂ̌����A�����͑��Ō����B�،͂��䎟�Y�ȗ��̖Z�����ł��B ���̌��C�̌���'�{��'���ȁB"�Ƃ�����������B�E�E�E���Ȃ��������I
���̌����̊ϋq�͑唼���N�z�҂ł������B��҂����Ȃ��B���̂��낤�H�@"�،͂��䎟�Y"��m���Ă��鐢�� �Ɍ����Ă���́H�H�H
2018.12.3
�g��猩�����s
���s�̔N���s���ł���"�c���� �g��猩�����s ����������̕���"���ϐk�⋭�H�����I��������ōs���Ă���B ����ɓd�b����"�{���̖�̕��̃`�P�b�g�͂܂�����܂����H"�Ɛu�˂���"�ꓙ�ȂȂ�����܂�"�Ƃ̂��Ƃ��� ���̂ŁA�o�����čs�����B14:30����ɒ����ă`�P�b�g�����B�ԓ��e�̗ǂ��Ȃ����Ƃ��o�����B16:50�J�� �Ȃ̂ŁA���Ԃ�����B���͔���_�Ђւƕ����čs�����B���������ƂɁA�a�ӂ��𒅂��Ⴂ�l����R�������������B ���{��A������A�؍����b���l�B���A�ǂ������Ȃ��Ă������������B����_�ЂɎQ�q��A�~�R�����ւƕ����� �s�����B�a�ӂ��𒅂����������{�l�̏����ɐq�˂�"�ǂ����������ł��ˁB���̘a�ӂ�������Ŏ肽��ł����H"�ƁB "���𐮂��A�����Ă������4000�~�ł�"�Ƃ̂��Ƃł������B16:10����ɖ߂����B���x���̕����I������Ƃ���ŁA�ϋq���o�ė����鏊�ł������B�������̏����E�|�q�E ���q����B�̔������₩�Ȏp�߂Ȃ���A�����҂����B16:30����B�C���z���K�C�h����A���ԂɐH�ׂ� �ٓ���\���B �ŏ��ɁA�w�`�o��{���x�̎��E�����ᓢ���E�������F�Љ��m���q��A�Љ��F���Y�A�Љ���V���̐e�q���O�セ����Ă� �o�������蕨�B���̌�̋x�e���Ԃɕٓ���H�ׂ��B���ŁA�w�ʂ��Ԃ�x�F�����쎡�Y��������̐U�t�ŗx�����B�����A �w�ٓV�����j���Q�x�F �ٓV���m�e�V����Љ����V���A���{�ʉE�q��𒆑��Ŋ�A�싽�͊ۂ��s��E�����A�Ԑ��\�O�Y�� �����F���Y�A���M�����𒆑��쎡�Y�������A�ٓV���m��"�m�炴�������ĕ������₵�傤"����n�܂郁�C�䎌�A��쐨���� �ɂ�����"�ԓ��ł̓n��䎌"�A"�{����ł̘A��"���A�y���ނ��Ƃ��o�����B�Ōオ�w�O�ЍՁx�F�Ⴂ�Љ���V���ƒ�����V�� �����̍���������Ƃ����x��Œ��߂��������B�I����10:00�B
���A�l�ŁA���N��"�g��猩��"���y���ނ��Ƃ��o�����B���ӁE���ӂł���B
2018.12.1

���̎U����(2) �����@����s�ގ�
���̉Ƃ̑O�̓���k��100m���s���ƈ��ʂɏo��B���̓��͕��鋞�����ɂ́A�����Ɠ��厛�����Ԏ�v���H �ł��������A���͎Ԃ�����Ƃ���Ⴄ���Ƃ��o���铹�ł���B���̈��ʂ𐼂�10m���i��k�ւ̏��H�� ����B���̏��H��50m���i��A���܂��Đ��i����B200m���i�ނƊ������H"�₷�炬�݂̂����ɏo��B ���f������A�ēx���i���鏬�H�ɓ���B1km���i�ނƋ����@�i�E�̎ʐ^�A����Ԃ���A�B�R��:�@�@�R�A �{���͖ؐS��������ɔ@���y�ї��e����-�ޗǎ���A�����ω���F����-����͓ޗǍ��������قɊ���j �ւ̎Q���ɏo��B��O�̏����𐼐i����ƁA���c���A�ޗǍ��Z�A�����_�Ёi����������A715�N�n�J�j �̑O��ʂ�B���̕ӂ�͍��ێR�ƌĂ��B�唺�Ǝ��̉��~�����̕ӂ�ɂ������炵���A�̔�����X�ɂ���B�܂��肭�˂�������������ɐ��i����ƕs�ގ��i�ӂ������A�����R �ӑޓ]�@�֎��A845�N���ƕ��ɂ��J��j �ɒ����B�����̖{��:�ؑ����ϐ�����F�����́A�����̂�����ɑ傫�ȃ��{����t���Ă���������B �����A�f������A�V��̏Z�E���{���ɂ��������������A�����s���R�ő|�����܂܂Ȃ�ʗl�ł������B �L���������쎝����̂���ςł���Ǝv�����B
���̃R�[�X�͍��ۘH���U����̂ł���B������8000����ł������B
2018.11.20
�J�j�̃V�[�Y��
���N���I�̃V�[�Y��������ė����B��N���s������䉷��̊�䉮��"���t�I�Â����R�[�X"��\���B 19��9:30�ɎԂʼnƂ��o���B���H�́A�r����SA�Ŗ�Ɍ�y�������邩��"���ǂ�"�ōς܂����B13:00����� �e�̒��c�_�Ђɒ������B�_�Ђ̒��ԏ�ɒ����āA�_�傳���"�隬�ɍs���������ǒ��ԏ�͂ǂ��ɂ���܂����H" �Ɛu�˂���"��R�̒��ゾ�����炱���ɎԂ��߂Ƃ��ēo��邯�ǁA�����Q���Ԃ͂�����܂��B�隬�����Ȃ�A �x�e�̒��ԏ�܂ōs����15���قǂœo��܂��B"�Ƌ����ĉ��������B���c�_��(�Êi���闧�h�Ȏ�)�ɎQ�q������A �������֍s�����B�V��t��E�Ƃ����������͖����������A�����ȐΊ_������A��������̓W�]���ǂ������B15:30��䉮�ɒ������B10�N�قǑO�A�̐l�ƂȂ�ꂽ���̏�������ɐ����Ă���"�}�C�d���\�E"���@��N�����Ă� ���������B�����ޗǂ̉䂪�Ƃ̒�ɐA������?���A�������Ԃ��炩���Ă����l�ɂȂ����B����A��䉮�� ��"��ł��Ă��܂���"�ƕ������B����ŁA����A�䂪�Ƃ�"�}�C�d���\�E"���@��N�����Ď����čs�����B 18:00����[�H�Ƃ����̂ŁA�����A����ɓ������B��䉮�̕��C�͌Êi�������āA�����M�̒ꂩ��o��"��������"�� �D����̂ł���B�����ǂ��A���C��̕��͋C���ǂ��B���̂��C�ɓ���ł���B
"���t�I�Â����R�[�X"�͑�ϔ��������������A�ʂ����������B���̗l�ɘV��ɂȂ��"�����������̂�����"���ǂ��B �����"������̗v�]��ǂ��`���āA�\������Ȃ���E�E�E"�Ɣ��ȁB���H�����������������A�T�[�r�X�E�ڋq���ǂ��B ��䉮�͎��̂��C�ɓ���ł���B
20��9:30�Ƀ`�F�b�N�A�E�g�B�A�H�̓r���ɂ���"�e�a�썂����O����Z���^�["�ɗ������A"�e�a��̑�j"���������A "�e�a��̐X"���U���B12:30�A�H�ɂ��A�O���̗[�H�E���̓��̒��H���^�b�v���ł������̂ŁA���H�͏ȗ����āA 15:30�ޗǂ̎���ɋA�������B
2018.11.12

�M�q�W����
���N���M�q���R�����������̂ŁA�����W������������B������2015.11.10�̃u���O�ɋL���Ă���B 4kg�̗M�q��1.6kg�̃O���j���[������E�̎ʐ^�Ɋς��邾���̗M�q�W�������o�����B����A�Ƃ��Ă� ���������B�����g�[�X�g�ɕt���ĐH�ׂ�B�P�r�łP�����A12�r�łP�N�ԁA�����y���ނ��Ƃ��o����B ���ׂł��Ђ�����A���̃W�����łƂ��āA�I���������Ĉ��ށB���Ȃ�"����͔��������̂ŐH�ׂȂ��悤�ɁI�@�H�ׂ��������玩���ō��悤�ɁI"�Ɛ錾�����B ���Ȃ́A���̃u���O�̃��V�s����������\��ł���B
2018.11.6
���c�k���W
���s�����ߑ���p�قœ��c�k���i1886?1968�j�̖v��50�N���L�O������ړW��10��19���` 12��16���ɊJ�� ����Ă���B���͂�����D���ł͂Ȃ����A�Ǝ��̊G�搢�E���m�������̑�ȉ��:���c�k���̍�i������ق� �Z�܂��ēW�������@��͂܂��ƂȂ��Ǝv���A�o�����čs�����B12:30�ߓS�ޗljw���̋��s�s���}�s�ɏ��A �|�c�w�ō��ۉ�ٍs���̒n���S�ɏ��ւ��A�G�ی�r�œ������ɏ�芷�����R�w�ʼn��Ԃ����B������10���ق� �ŁA���s�����ߑ���p�قɒ������B�v���Ԃ�̋��s�ł���B����ȂɒZ����(1����20��)�ŗ�����Ȃ�A�����������ɂ� ���s�ɗ��Ă��ǂ��ȂƎv�����B���p�قւ̓������̒��́A����Y��ŗ��h�ȓX�������Ɗ������B�W�����"�����F�̉��n�Ƒ@�ׂȕ`���ɂ�闇�w"�̑�\�삪�W�߂��Ă���A�N�㏇�ɁA"���i��A�ё���A���w�A �@����"���̃e�[�}�ʂɂƓW�����Ă���A���c�k���̉�ƁE�l�Ԃ��T�Ϗo����f���炵���W����ł������B
2018.11.1
�C���t���G���U�\�h�ڎ�
����"�C���t���G���U�\�h�ڎ�͂��Ȃ��B���ʂ����m�łȂ����A�Ȃ�����Ȃ�����"�Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪�A �e�j�X�X�N�[���̒��Ԃɂ���҂�����"���ʂ͂���܂���B����ɁA���������łȂ��A���̐l�ɂ����� ���Ƃ����ϓ_�ł��A�\�h�ڎ�͂��Ƃ����ق����ǂ�"�ƌ���ꂽ�B���ƂȂ������͂��������̂ŁA���̂���҂��� �̏��֍s���āA�C���t���G���U�\�h�ڎ�����Ē������B���̍ہA����҂���̉����o�Ă���"���˂��˂��b �͎f���Ă���܂�"�ƈ��A�ɂ���ꂽ�B����̃e�j�X�X�N�[���ł�"����������āA�C���ǂ��A����Ă�낤" �Ǝv�����B2018.10.29
��70�q�@�W
���N�̐��q�@�W�́A10��27������11��12�����J�Â���Ă���B�����͗ǂ��V�C�������̂ŁA���H��̎U���ɏo�āA �Ă���A���A������R�_�ЁA�t���쉀�n���o�ēޗǍ��������قɎ������B���q�@�W�p�ɒ����e���g�������� ���������A�s������������ɓ��ꂻ���������̂œ��ق����B�ٓ�������Ȃɍ��G���Ă��Ȃ��āA��������ǂ݂Ȃ��� �������Ɣq�ς��邱�Ƃ��o�����B���j���͌��ꂩ���E�E�E�B���͖��N���q�@�W��q�ς��Ă��邩��A�W���i�� �����͔q�ς������Ƃ����邪�A�W���̎d�����H�v���i��ł��āA�y�����q�ςł����B2018.10.22
�V�j�A�h���C�o�[�Y�X�N�[��
JAF(���{�����ԘA��)���J�Â��Ă���A�V�j�A�h���C�o�[��Ώۂɂ���"���g�̉^�]��U��Ԃ�A����̗\�h���S �ɖ𗧂Ă邱�Ƃ�ړI"�Ƃ����X�N�[���ɎQ�������Ă����������B���͐\���ґ����Œ��I�ɗ��������A���ގ҂� �o�ċ}篎Q���������肽�B�e���̃}�C�J�[���g�p���A��ʈ��S�̊�{���Ċm�F���邽�߂̍u�K��ł���B���́A11:45�ɉ��ł��銀�����������Ԋw�Z�ɒ������B�w�����̕��X���҂��Ă����������āA��ۂ悭 �ē������Ă����������B��t�葱����������A������ԍŏ��ł������B�߂��̃��X�g�����Ńg���J�c��H(780�~) ��H�ׂĖ߂�����A�Q����19���S���������Ă����B12:30����X�N�[�����n�܂����B�J���L��������
�P�D���������^�]�u�� (���w�u�K�j
�Q�D�^�]�̊�{�̊m�F�i�^�s�O�_���E�^�]�p���̊m�F�E�Ԃ̎��p�m�F�j
�R�D�����_�ł̈��S�Ȓʉߕ��@ �i���i�K��~�j
�S�D�X���[�Y�ȃn���h������ �i�X�g���[�g�X�����[���j
�T�D�������u���[�L���� �i�}�����̌��j
�U�D��i���S������ �i�`�r�u�j�̌� :�Փ˔�Q�y���u���[�L�E�딭�i�}������@�\
�U�D�ȊO�͑S�āA�Ƌ������Ƃ������Ԋw�Z�ŏK�������Ƃł��邪"���S�^�]�̂��߂̊�{�̏d�v�Ȃ���"�� �ĔF���E�Ċw�K�o���āA�ƂĂ��ǂ������B�w�����̕��X�̘A�g���ǂ��A�f���炵���X�N�[���ł������B 16:30�ɃX�N�[���͏I��������A���X�����C���ʼnƘH�ɂ����Ƃ��o�����B
2018.10.18

�ᑐ�R
�����͗ǂ��V�C�ł������B���H��A�U���ɏo�ē��܂ōs�����Ƃ����"�v���Ԃ�Ɏᑐ�R�̓o�낤"�Ƃ����C�ɂȂ����B �H���a�ł���قNJ����������Ƃ������W��270m�̈�d�̒���ɒ������B�����ɂ���l��80%���O������̊ό��q�ł������B �����炵���ǂ�(�E�̎ʐ^)�A�u���ł������B�ƂɋA���ċ��Ȃ�"�ᑐ�R�ɓo���Ă���"�ƌ�������A���Ȃ�"����Ȃ��ƌ����Ă��ꂽ��E�E�E�����s�������̂ɁE�E�E"�� �������B����"���O�͑�����ēo��낤"�ƌ�������A�v���v���ɓ{���Ă��܂����B
2018.10.17
10��17��
���N10��17���͋������̓�~���ő�ʎ�o�]�lj�J�Â���A�����̔q�ς���N�ł��̓������������B����ŁA ���͊J����9:00�ɓ�~���ɍs�����B �����ɂ͖{���E�s��㮍��ω������i�ӂ�����������̂����j�A�@���@�i�ق��������イ�j���m�U�l�̖@���Z�c�����A �l�V��(�����V�A�����V�A�L�ړV�A�����V)���������u����Ă����B���ꓙ�́A���q����̕��t�N�c�Ƃ��̒�q�����ɂ�鐧��i�ŁA �S�č���ł���B�l�V�����͉��u������C�Z�c���͍���قȂǂ���ŋߓ�~���Ɉڂ��ꂽ�B�Ƃ��Ă��s�ςł������B���ꂾ���� ���A1�N��1���������J�Ƃ����ܑ͖̖̂����Ǝv���B�Ȃ��A����܂œ�~���ɂ������l�V�����͒������Ɉڂ��ꂽ�B���̌�A�e�j�X�X�N�[��(11:00-12:30)�ɍs������A������̎�p�����a�@�֍s���A��p��80���̒�����f�����B "�o�߂͗ǍD�ŁA���͂�1.2�ň���B���͎O������Ɍ��f�ɗ��Ȃ����B"�ƌ���ꂽ�B��l�̊�Ȉオ�w��o���ł��x�݂Ƃ��ŁA �\�čs�����̂�3���Ԃ��҂�����ĕ������B
2018.10.7

���������������c
714�N�Ɍ������ꂽ�������̒������́A���т��яĎ����Č�����Ă������A1717�N�ɏĎ����Ĉȗ��n��ȉ����ł������B ���̂��ёn�������̎p�ōČ�����A10��7�����痎�c�@�v���n�܂����B������7���͋������ɂ��@�v�B8���͐����O�\�O���D����A 9���͓�s���厛�A10���͔�b�R����ɂ��@�v�������A11���Ɍ��肷��B����7���̖@�v�ɗՐȂ����Ă���������(�E�̎ʐ^)�B�@�v�̌�A�^�V�����������̓��w�ɓ���Ē������B �]�ˎ���ɑ������ꂽ�ؑ��߉ޔ@��������������\�蒼����Ė{���Ƃ��Ē������Ă���ꂽ�B���̗��e�ɖؑ��i�₭�����j��F������ ���i�₭���傤�j��F�����i�d���j���������������B�{��d�̎l���́A��~������ڂ��ꂽ�^�c��̎l�V�������i����j �������߂Ă������������B���́A����Ȃ�܂��܂��̔z�u���Ǝv�����B
�W�Ҋe�ʂ̂��w�͂̂��A�ŁA�������̒��j���o���A���@�Ƃ��Ă̌`���o�����ƌc��̈ӂ�\�������Ǝv���܂��B
2018.10.3

�{���C����̃m�[�x����w�E�����w��
�X�E�F�[�f���̃J�������X�J�������́A�Q�O�P�W�N�̃m�[�x����w�E�����w�܂��A�Ɖu���䕪�q�̔����Ƃ��Âւ� ���p�������s�����{���C�i�ق�E�������j���s��w���ʋ����ƕăe�L�T�X�B����w�̃W�F�[���Y�E�A���\�����m�i�V�O�j �Ɏ��^����Ɣ��\���܂����B��b�����ɂ��d�v�Ȕ����Ƃ��ꂪ�����̊����҂̎��Ö�ɂ܂Ŕ��W�������Ƃ͊��������Ƃł��ˁB �{���C������̍v���Ɍh�ӁE���ӂ���Ƌ��ɁA���̕���ł̑����̗D�ꂽ�����҂���Ă�ꂽ�̑��ΏC�搶�̌��т͑���Ȃ��� ���Ǝv���܂��B�E�̎ʐ^�́A��̃A�P�r�̂�ɂȂ����A�P�r�̎��B
2018.10.2
���̉���
2016�N��6��16���ɍ��ŒŊԔw���j�A�œ��@��7��4���ɑމ@�����B���̌ナ�n�r���ɓw�߂āA2016�N���ɂ͊��������B ���̌�͍��̏�Ԃ��ǂ��A�M�b�N�������N�������A���ŒŊԔw���j�A�œ��@�����ȑO��蒲�q���ǍD�ł������B ����"���S�Ɏ�����"�ƌ������Ă����B�����ɖ��f���������B2018.10.2�̌ߑO���ɏd���ו����^�ԍ�Ƃ������B���̎��͉��������Ȃ��������A���H��ɂȂ��"�Ȃ������ɂ�" �Ɗ����������B�[���ɂȂ��"���������߂�ƒɂ݂�����A���ɗ͂����邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ���"�B�[�H��A���C�ɓ�������A ���ɒ������B"�y���M�b�N����"�Ƃ��������ŁA�Q�Ԃ������Ƃ��ɂ����ɒɂ݂��͂������B
10��3���Ƃ̒��E������낻��ƕ������x�B�������낷�Ƃ��A���ɒɂ݂��͂������B���N�ł��邱�Ƃ̗L���Ɋ�����B �[�H��A���C�ɓ���A10:00���ɒ������B
10��4���ɂ݂͂��邪�A������悤�ɂȂ�A�ߓS�ޗljw�߂��܂ʼn��������B����4844
10��5���ɂ݂����Ȃ��Ȃ�A�����U�������B����5156
10��6���_�ˁE�Z�b�����s���A��H�����B�ɂ݂����܂芴���Ȃ��Ȃ����B
10��7���������������̗��c�@�v�ɎQ���B
10��8�������狻�����ւƎU���B�������E����ق�q��
10��9���e�j�X�X�N�[�����x�݁A�������������̗��c�@�v�ɎQ���B
10��10���e�j�X�X�N�[�����x�݁A������t���쉀�n�A�Љ����o�ċ������ւƎU���B
10��11���ԂŊI�����֍s���A����̔��P��:�߉ޔ@��������q�ρB����������ق̎R�c�����玝���Ă����Ƃ��������� ���S�`��z�������闧�h�ȕ����Ɍ��������B
10��12���s�A�m�����֍s�����B���̌�A���厛�~���[�W�A���A���ւƎU���B����10127
10��13���u���b�N�����|��Ȃ��l�ɁA�S�_�E�S���ŕ⋭�����B����8274
10��14��������t���쉀�n�A�Љ����o�ċ������ւƎU���B����9245
10��15�������@�A�ޗǍ��Z�A�����_�ЁA�헤�_�Ђƕ����A�ނ��������n���ċA�����B����10525
10��16���e�j�X�X�N�[���Ńe�j�X��������A�������B����8536
10��17���������̓�~���Q�q��A�e�j�X�X�N�[���Ńe�j�X�B���̌�A��Ȉ�@�֍s�����B
10��18���ᑐ�R�ɓo�����B����13270
10��19���ԂŖ@�����֍s���A�Q�q��A�@�N���A�@�֎��ւƎU��B����11847
10��20���_�ˑ�w�Ńe�j�X�������B����11028
�O�T�Ԃ��o�āA�ɂ݂������Ȃ�A�قڊ����B���ꂩ��b���āA�Ĕ��h�~�ɓw�߂����B
2018.9.20
�V�F�t�F�X�^ in �ޗ�
�ޗnj����Ŗ{�i�I�ȗ������y���߂�g�ޗǂ̐H�ނƃV�F�t�̍ՓT:�V�F�t�F�X�^�h���A�ޗnj����o��H���n�� 9��15�� - 9��24���ɊJ�Â���Ă���B�����10��ڂŁA�ޗǂ̐l�C�V�F�t���{�i�����ł��ĂȂ��V�F�t�Y�L�b�`���B �{�̖����H�i�ɏo���}���V�F�B�Ηq���g�����A�Ă����Đ�s�b�c�@�B�J�t�F���j���[�����̂��ٓ��� ���ԃV�F�t�F�X�^�J�t�F�B���X�̂��X���W�܂��Ă��܂��B�V�F�t�Y�L�b�`���́A�L���V�F�t�����ւ��ŁA�L�b�`���J�[�Ŏ����̗�������Ă��܂��B�����͂����ɂ��̉J �������̂ŁA���͒��C�𗚂��A�P�������ďo�����čs�����B���X���ՎU�Ƃ��Ă����̂ŁA���̓V�F�t�Y�L�b�`���ɓ���A �����`(2000�~)�𒍕������B�����̓X�y�C�������̃��X�g����"�A�R���h�D"�̃V�F�t�쓇 �����S�����Ă������������B �����́E��a���̃��[�X�g�Ǝ��̕Ă̎ύ��݁C��a�ۉ֎q�ƃn�[�u�B �E�씗��A�}�S�̃t���b�g�Ɛ�̍���̃N�[���B �E�ޗǎY�哤�̓����ƂԂǂ��̃A�z�u�����R�C�V�F���[���̃W�����B �̂R�i����Ȃ�A�ƂĂ������������B2000�~�͊i���B���N�������Ă�����A�쓇 ������̒S�����ɍs�����Ǝv���B
2018.9.9

�d�z��t��
����A�U���̓r���ŁA�������̕a�Ɠ������ɓ������B���̍ہA9��9���ɓ얾���ōs����d�z��t��̃p���t���b�g�����B �얾��(�Ȃ�݂傤��)�͓ޗǎs�̍x�O�E�����X�������ɂ���A771�N�̑n���Ƃ�����Î��B�{���͊��q����̊���(�d��)�ŁA ���������ɖ{����t�@���A���Ɏ߉ޔ@���A�E�Ɉ���ɔ@��(���������������A�d��)�����u����Ă��܂��B����ɁA�����ɂ� ��⸈�(���q����)�A�\�O�d�Γ�(��������)�Ȃǂ�����܂��B�������A���݂͖��Z�̂����ƂȂ��Ă���A�{�����w�̔q�ς͗v�\�� �ł����A�d�z��t��ɂ͌��J�ł���B���͏o�����čs���āA12:00�ɓ얾���ɒ������B�d�z��t���13:30����J�Â����Ƃ̂��ƂŁA�{����t�@���̑O�ŁA �V����B�����O�̑ō��������Ă���ꂽ(�E�̎ʐ^)�B���Ԃ�����̂ŁA�~�Ǝ��O�̒��X�Œ��H��ۂ�A13:30�ɓ얾���ɖ߂����B �d�z��t��@�v�́A�e�Ԃ�����������t�@���̑O�ŁA���y(�U�g)�A�m�������A�y��A���y(�h����)�A�U�A�njo�A���y(�M��)�A �_�`�A�m���ގ��ƍs��ꂽ�B���̌�A�e�̉Ԃт���ׂ������E�������B�����ȑ��ł̌É�ȍÂ����y���܂��Ă����������B
2018.9.5
�������p��P�������f
������10:00-11:30�̊ԃe�j�X�X�N�[���ɍs���e�j�X�������B�O���̑䕗�ŁA�R�[�g���ɂ����̏��}��t���� ���U����Ă������A�R�[�`���|�������Ă����ĉ��������c��Ƃ̂��Ƃł������B�������p��P�������f��15:00�ɗ\�Ă������B�ŁA14:45�Ɋ�Ȉ�@�֍s�����B�O�����䕗�ŋx�f�ɂȂ����e���H�A 16:30�ɂȂ��Đf�@���Ă����������Ƃ��o�����B���f�̌���"�����ɐi��ł��܂��B��������X�|�[�c�����Ă��悢�ł���" �ƌ���ꂽ�B���̓e�j�X���ĊJ���Ă��邱�Ƃ́A�ق��Č��Ȃ������B
2018.9.4

77�˂̒a����
�����́A����77�˂̒a�����ł���B���Ɋ��S�͖�����"�ǂ��������܂Ő����Ă���ꂽ"�ƁA���ӁE���ӂł���B ���Ȃ��C���t���Ȃ����ꂪ����̂ŁA�ꂩ���قǑO�A���͉Ƃ̋߂��ɂ�����{�����X�ɗ[�H��\�Ă������B �Ƃ��낪�A�����䕗21�����A14:00�ɐ_�˂ɏ㗤���A�ޗǂł������\���J�ƂȂ����B�\�Ă��������{�����X ����A16:30�ɓd�b���������B�c�ƒ��~�̘A�����Ǝv������"�����͏������Ă��܂�"�Ƃ̂��Ƃł������B����ŁA �\�Ԃ�18:00�ɁA���̓��{�����X�ɓ������B�X�̎�l��"���Ȃł������̂ɃL�����Z���ŁA�����ɂȂ��Ă��܂��܂���"�Ƃ�����������B���̂������A������� �ʂ����������ł�������"�ƂĂ�����������"�B���́A�ޗǂł�"��Ԃ̓��{�����X"�Ǝv���B���X�ۛ��ɂ��āA ��ɂ��Ă����Ȃ��Ă͂Ǝv���Ă���B
2018.9.1
����Ƌ㌎
���N�̉Ă͏����āA�Ȃ��Ȃ����ԂɊO������C���N����Ȃ������B������9��1���A�ޗǂł͒��������Ȃ��ĉJ���~�����B �ō��C����30���A�����������Ȃ����B�ŁA���H��A�J�P����Ɏ����A�U���ɏo���B���厛�Ă���A���i���O���o�āA ���d���֍s���A�v���Ԃ�Ɏl�V����(�V������̍ʐF�Y��)��q�ς����Ă����������B�|�{���̑����V�Ǝ����V�A ���ڂ��Ђ��߂đO�������߂�L�ړV�Ƒ����V�A�S�Đl�ԓI�ō������_�����ӂ�鑜�E����ł���B�����ŁA�w�} ���֍s�����B�@�R��l�̉摜���{���ł������B�����ŁA���֍s�����B�k�Q�ď��Ŋǒ����u�������Ă���ꂽ���A ���͑f�ʂ肵�Ė@�ؓ��֍s���A�����ɓ���Ē������B���p�̐{��d���C�������̂��@��ɁA�{���̂Ӌ�㮍��ω���F�A ���e�ɞ��V�A��ߓV�A���̑O�Ɉ��A�����͎m�A�l���ɑ����V�A�L�ړV�A�����V�A�����V�A�w��̐��q�Ɏ������a�i�镧�j ��10�[�����ɂȂ�A�S�ĒE�������̓V������̑��E����ŁA�n�������̔z�u�ɋ߂��Ȃ����H(�ȑO�ɂ����� �����E������F�A�ٍ��V�A�g�˓V�A�n����F�A�ӓ������͓��厛�~���[�W�A���Ɉړ�)�B���́A�������肵�ē��� ���̂ꂽ�Ǝv���B���d���Ɩ@�ؓ��̑�����q�ς��āA�V����������\�����Ă����������B�����ŁA����R�_�ЂɎQ�q���A���厛�{�V�O��ʂ�����"�����|�吶�ɂ����W"���{�V�ōs���Ă����̂Ŕq�ς����B ���厛�͍ŋ߁A"�����|�吶�ɐ��ʔ��\�̏�"��x�X���Ă���B�ǂ����Ƃ��v���B�����ŁA����A�X���_�БO�A ���������o�āA�A����B����10,200�B�v���Ԃ�Ɉꖜ�������B
2018.8.29
�e�j�X�ĊJ
�������p���Ă���20���o�����B��Ȉ��"30����łȂ��ƃX�|�[�c�̓_��"�Ƃ�������������A �g�̂͌��C�Ȃ̂�����"20�����ĂΉ���͎���"�Ə���ɍl���āA�e�j�X�X�N�[���ɍs����28����13:30-15:00�A 29����10:00-11:30�̃N���X�ɎQ�������Ă����������B���V���Ŋ������������A�ǂ������v�̗l�ł���B �ł��A�v���Ԃ�̉^���Ŕ�ꂽ�E�E�E�B2018.8.27

�ɐ��R
�v���Ԃ�Ɉɐ��R�ɍs�����B9:30�ɎԂʼnƂ��o���B�փ���IC���o�Ă���A��蓹�Ŕ��Z�������Ղ� �K�˂��B���H�킫�ɓ���230m,��k250m�̎���Ղ����@��������Ă����B���P���̍ݒn�����̎����ՂɁA ���Z���������������ꂽ�Ƃ̂��Ƃł������B"700�N���ɂ͂��̒n�ɑ傫�Ȑ��͂������������������Ȃ�" �Ƃ̊��S�ɐZ��A���w�����Ă����������B13:00�ɐ��R�h���C�u�E�F�C�I�_�̒��ԏ�(�W��1260m)�ɒ������B���ԏ�e�̃��X�g�����ł��˂��ǂ��H�ׁA ���o�R������o��n�߂��B�ɐ��R�͍��R�A�����L�x�ʼn��x���K�˂����Ƃ�����̂����ǁA2,3�N�O�ɓo�������A ���ɍr�炳��Ė��c�Ȏp�ɂȂ��Ă����̂ŃK�b�J�����āA�b���ɐ��R�ɍs���C�����Ȃ������B���̌�̗l�q�� �m�낤�Əo�����čs�����̂����ǁE�E�E�A���o�R����o��n�߂āA��R�̃T���V�i�V���E�}���炢�Ă���̂� �ڂɂ��āE�E�E�z�b�Ƃ����B�t�F���X�������͖̂ڏ�肾���ǁA����ɂ���Ď��ɍr�炳��Ȃ��Ȃ����l�ł���B �����g���m�I�A�C�u�L�g���J�u�g�A�����h�E�A�N�T�{�^���A�C�u�L�t�E��(�E�̎ʐ^)�A�������R�E�A�^�����\�E ���X�̉Ԃ����\���邱�Ƃ��o�����B�R���̒��X�Ń\�t�g�N���[���ƈɐ������������������B�����o�R�������R���A 16:00���ԏ���o�����A18:30�ޗǂ̎���ɋA�������B
2018.8.17

������������
���̔������p��̌o�߂͏����̗l�ŁA��Ȉ�͐f�@��"�o�ߗǍD�ł��B����9��5���Ɍ��f�ɗ��ĉ������B"�ƁA������������B �ł��A����܂�"�^���X�|�[�c�֎~"�ł���B�E�E�E�ł��A�����Ɏ���Ă�����Q���Ă��܂��B�ŁA�[���A�U���ɏo���B ���厛���A������o�āA�������ɍs�����B���̏H�A10��7���ɗ��c�@�v���\�肳��Ă���"������������"�̕������O����Ă���(�E�̎ʐ^)�B����10�N����"�������̍Č�" ���n�܂����B�����A"�������鍠�A���͐����Ă��邾�낤��"�Ǝv�������ǁA�ǂ���琶���Ă���"���������������c�@�v"�ɎQ�� �����Ă������������ł���B�ȑO�́A�]�ˎ���Ɍ��Ă�ꂽ�n��ȉ��������������Ă������A�V������̌������Č����闧�h�� "������"���o���āA��c�ł���B
2018.8.10
��Ȉ�@�̑ҍ���
���̔�����̎�p�͖����ɏI�����A�����͉E��̎�p��R���ڂ̌��f�Ɋ�Ȉ�@�֍s�����B���͏����C�y�ɂȂ��Ă���̂ŁA �܂����ώ@�����B������̎�p�̊��҂���������H���A�ҍ����ɂ���l�̔������炢��70�˒��Ǝv����B��p�O�y�� ��p���͉Ƒ�������v������Ă���̂ŁA�v�w�A���e�q�A�ꂪ�����B�Y��ȕꖺ�Ǝv����80��50��̓�l�A�ꂪ��������Ⴝ�B���̖�����A30�N��ɂ͂��̕�e�̗l�ɂȂ���E�E�E�Ǝv�����B
�אȂɍ����Ă������w�l���b�������ė���ꂽ�B"���A85�˂Ȃ�ł�����5�N�O�ɕv��S�����܂��Ĉ�l��炵�Ȃ�ł��B�ł��A �����͋߂��ɏZ��ł��閺���ꏏ�ɗ��Ă���܂����B"�ƁB����"����͗ǂ��ł��ˁB�������d�b���Ă���܂���?"�ƌ������B ����ƁA����܂ŃX�}�z���������Ă���������"��͎��������āA�Ƃɍs���Ȃ��ƁA�b���ʂ��܂���"�Ƃ�����������B�ׂ�̂��w�l "���A�悭����ׂ�܂����ǁA���ɂ��������܂���"�Ƃ�����������B
80�ˈʂ��Ǝv���鑫�̈����j�����Ō�t��"�����҂́H"�ƒ�����āA"���A�Ƃ�҂ł�"�ƋB�R�Ƃ����ԓx�œ����āA ���ӏ��ɃT�C�������Ă���ꂽ�B���̐l�A�����Ɨ��h�Ȑl�i�҂��Ǝv�����B
���l�ȍ���҂��ςĂ��āA���̍��A�����Ŕ��Ȃ��A�����Ɍ����������������Ƃ́@"�N�ł����Ƃ�Ɛ����Ă������̂��B ���������A�]�T�������āA�������Ɛ������Ă������Ƃ�����B�����ɂ��A���l�ɂ��E�E�E"�@�ƁB
2018.8.8
�������p
������̎�p�����B���̋L�^�B7��3��10:30����p�̐�����B���ȓ����B��P���ԁB
7��13��15:00����������Y�̌����E�f�@�EHIV���̊����nj����̂��ߌ��t�̎�B�l�ԃh�b�N�̐��я���o�B �N���r�b�g�_�����w�������B
8��1��15:30����p�����̐����B���ȓ����B��P���ԁB��p�菇�̐����������A�_���̓_����K�������B ���Ȃ�"���@�o����悤������A���@���Ď�p������H"�Ǝ�������Ȃ��Ƃ��������B
8��3��12:00��Ȉ�@�ɓ����B���ȓ����B30�����Ƀ~�h����P(�����J����ږ�)�_��B13:30����̔������p�J�n�A13:45�I���B ���������Œɂݖ����B��т����ċA��B�^�N�V�[��2800�~�B�P�t���b�N�X�J�v�Z��250mg(�ۊ����ǂɗp����R������)�H��A �O���Ԉ��ݎn�߂�B��p��3���Ԃ͐��E�����͋֎~�ł���B�E�Ⴞ���ł̓e���r�����Ă��Ă��A�ڂ�����B�[�H�シ���A���B �钆�ɒɂ݂͊����Ȃ������̂Œɂݎ~�ߖ�͈��܂Ȃ������B
8��4��8:30��Ȉ�@�����B��т��Ƃ���E�f�@�B��������ƌ�����悤�ɂȂ����B�����s�N�s�N���z�����������̂ň�t�ɑ��k������ "���̂����ɂ����܂�ł��傤"�ƌ���ꂽ�B���̒ʂ�A�ꎞ�ԂقǂŎ��܂����B�E��͓܂��Ă��Ȃ��Ǝv���Ă������A��p��������� ��ׂ�Ɠ܂��Ă��邱�Ƃ����F�o�����B�N���r�b�g�_���(�ۂɂ���̊����ǂ�}���A���ǂɂ��ɂ݁E�͂�E����݂����P����)�A �T���e�]�[���_���(��̉��ǂ�}����)�A�W�N���[�h�_���(��p��̍����ǂ�h�~) �H��_��J�n�B��p��V���Ԃ�������30���ʂ̃E�I�[�L���O���J�n���Ă��ǂ����A����܂ł͈��ÂɁI�ƌ����Ă���B �O�͏������A���������Ă͂����Ȃ��̂ŁA��[�̌����������ɂ��������܂܂ł���B���E�����͋֎~����Ă��邪�A�S�[�O����t���āA �y���V�����[�𗁂т��B�Q��Ƃ��͊��ی삷�邽�߃M�b�^�[��t�����B
8��5�����֎~�ł��邪�A���A�E����A����ȊO���y��������B�N���r�b�g�_���A�T���e�]�[���_���A �W�N���[�h�_���H�㍶��ɓ_��(8��10��)�B���͉������������������Y��I�������B�����͖��_�����߂��ł����\�����āA �V���ł��ǂ߂�B�������A�ߎ��ዾ��t���������y�ɓǂ߂�B�Ⴊ���肵����ߎ��p���K�l���w�����Ȃ���Ǝv���B �Ƃ��Ă��āA�Ǐ��E�s�A�m�E�K�������Ă���B�g�̂��a���Ă��܂��B
8��6�����A�E����A�ʏ�ǂ���Ɋ�������B10:00��Ȉ�@�����B���f��A��t��"�����Ɍo�߂��Ă��܂��B�����͉E��̎�p�ł��ˁB" �Ƃ�����������B����������ċA����B�ߓS�ޗljw��莩��܂ʼn��V����������B�A�����V�����[�𗁂сA�Ό��ő̂������B
8��7��13:30��Ȉ�@�ɓ����B���ȓ����B30�����Ƀ~�h����P�_��B15:10�E��̔������p�J�n�A15:25�I���B���������Œɂݖ����B ��т����ċA��B�P�t���b�N�X�J�v�Z��250mg�H��A�O���Ԉ��ށB��p��3���Ԃ͐��E�����͋֎~�ł��낪�A�V�����[�𗁂сA ��̓^�I���ŕ������B���Ⴞ���Ńe���r�����āA���ւ��܂���킷�B10:00�A���B�钆�ɒɂ݂͊����Ȃ������B
8��8��8:30��Ȉ�@�����B�Ō�t����т��Ƃ��Ă����������B�E�����������ƌ�����悤�ɂȂ����B��t�͐f�@���� "�����Ŗ�肠��܂���"�Ƃ���������B����̎��Ɠ�������ċA�����B
����ŁA�ЂƂ܂����S�ł���B��́A8��10����8��14���ɐf�@���邱�ƂɂȂ��Ă���B8��20���܂ł͗��s�E����E�U���֎~�B 9��8���܂ʼn^���X�|�[�c�֎~�B���d����Ό��̐����ɖ߂ꂻ���ł���B
���̂����b�ɂȂ��Ă����Ȉ�@�͔������p�̑������I�Ȉ�@�ł����������ł���B�@���ȊO��10�l���̈�t��������B �S����t�͌��߂�"�ǂ̈�t���f�Ă��������Â��o����"�����b�g�[�ɂ��Ă���������l�ŁA�f�@�E�����p�E�f�@�E�E���p�E�f�@�� �S�ĈقȂ��t(�S������)���S�����Ă����������B�������E�Ō�t�̑Ή����e�L�p�L�Ƃ��Ă���e�ł������B���̒m�����A �ł��i��Î{�݂ł���B
2018.7.31
�s�A�m�̔��\��
29���Ƀs�A�m�̔��\���܂ƌS�R��z�[���ł������B����17:00�J���̑�O��6�Ԗڂɉ��t�����B ���̑O�ɑ�w���Ǝv�����҂������V���p���̃m�N�^�[��Op.9.2��h�r���b�V�[�̌��̌��������� ���t�����B���̉��t�Ȃ̓S���h���̉S�A���V���ē̉f��"������"�̍ŏI�͂Ō����̃u�����R�ɗh�� ��Ȃ���u�������̂��Ă����̂ł���B����ȕ��ɉ̂�����ƃS���h���̉S��I�B���āA���̔Ԃ������B���t����������E�E�E�O�t���e���Ȃ��B�d������������A�C�[�m�`�~�W�B�J�V�E�E�E �ƒe����Ƃ��납��n�߁A�O�Ԃ܂Œe�����B���ďI��낤�Ƃ��Č�t�ɓ������疔���������Ȃ����B �ł��A���͂��炵�Ă���Ȃ��Ǝ���Ԃ߂��B���̉��t�̃r�f�ICD���v���̃J�����}�����B���Ă��� ���̉��t���������̂��̂�5000�~�Ŕ�����Ƃ����B�����"�Q�l�ɂȂ�B�����ȉ��t���ʔ����낤�E�E�E"�ƁA ���͒��������B
�ƂɋA���Ă��A���Ȃ�"�ǂ�������?"�Ƃ��q�˂Ȃ��B�ł��A�C�ɂ����Ă���������ɂ��̕�����B
30���A�������s�A�m�ɂނ����S���h���̉S��e�����B�Ȃ�ƁA�O�t���e�����B�ْ����Ă����낪���h���Ă����炵���A �ł��A���̍ɂȂ��Ă�"������"���Ƃ��o����̂͊��������Ƃ��B�C���C���A���������e������ł����悩�����̂��B �Õ��Œe���Ă�l����R�����B�y�����Ȃ��Ă��e����l�ɗ��K���悤�I�I�I
2018.7.26
�s�A�m�̗��K
29���Ƀs�A�m�̔��\�����B����"�S���h���̉S"�����t���邱�ƂɂȂ��Ă���B�O��A�y���� �Y��čs���āA�r���Œe���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������ŊJ�Â����B���̓��x���W�������Ă��邪�A ���Ăǂ��Ȃ邱�Ƃ��E�E�E�E�E�E�B�ŁA���O���K�ɗ��ł���B�Ƃ��낪�A���Ȃ͂��������B�����o�Ă��邩����K���Ă���� ���������Ă���̂ɁA��������吺�ŌĂԁB���K���ɁA�}���̗p���ł��Ȃ��̂ɘb�������Ă���B ���̃s�A�m��"�ǂ��ł��悢�G��"�Ǝv���Ă���炵���I�I�I
�܂��A����ȃs�A�m������E�E�E�d�����������B�D�D�D�ł��A�䖝�ł��Ȃ��čR�c�����B
2018.7.25
���ʓW"���݂̂قƂ�"
�ޗǍ��������قł�7��14���i�y�j�`8��26���i���j�ɓ��ʓW"���݂̂قƂ��\���� �ԐD�c����䶗���?���\" ���J�Â���Ă���B���̓W����͒ԐD�c����䶗��̏C���������L�O���A�ԐD�Ǝh?�ɂ�镧�̑����ꓰ�ɏW �߂���ʓW�ŁA�V����?���i�Ăケ�����イ���傤�A���{�����A����j�A �ԐD�c����䶗��i�Âꂨ�肽���܂܂�A�c�������A����j�A �h?�߉ޔ@�����@�}�i�����イ���Ⴉ�ɂ�炢�����ۂ����A�ޗǍ��������ّ��A����j���ꓰ�ɉ����ŁA ����炪�����ɔq�ςł���@��́A���������Ă���Ԃɂ͖����Ǝv���A�������̌ߌ�o�����čs�����B����������ʂɓV����?�����������B���{�����ł͂��邪�A���{���Ŕq�ςł���͕̂����i�ŁA �{���͓ޗǍ��������قŕۑ�����Ă���ʏ�͔q�Ϗo���Ȃ��B���́A���Q�����P�ዾ�����o���A��������q�� �����Ē������B�����n�E�������n�@�����h?�@�c88.8cm ��82.7cm���������A���̒��ɁA������w�ɕ\�����T�� �S�̂��������A���Ƃ��ƕS�̂������Ƃ̂��ƂŁA�傫��?���ł��������Ƃ����͒m�����B�V����?���ɂ��� �L�ڂ����L�^�����W�����Ă������B
�ԐD�c����䶗��͓ޗǎ���ɒ����P(���イ���傤�Ђ�)�ɂ���ĐD��グ���Ɠ`�������Sm�l���̑��䶗� �ł���B�}�l�͋Ɋy��y�̗l�q�𒆐S�Ɋϖ��ʎ��o(����ނ�傤���カ�傤)���G����������e�Ƃ̂��Ƃł������� �Â��Ȃ��Ă��Ĕ��R�Ƃ��Ȃ��B�������ɁA�ԐD�c����䶗��Ɠ����ō]�ˎ���쐬���ꂽ�h?�c����䶗� (�^���Ɋy�����E�E�E�^���Ɋy���͐^�@���ŁA���͊w������ɉ��h�����Ă��������Ă���)���W�����Ă���A ����̕������m�Ȃ̂ŁA���ł̃r�f�I�͂�����g���ĉ�������Ă����B
�h?�߉ޔ@�����@�}�͔������n�@��?�@�c211.0cm�@��160.4cm�ŁA�����ɐԂ��U�����܂Ƃ����߉ޔ@���A �߉ނ̌��ɂ͌�?�A����ɂ͓V�W�Ǝ�������A�߉ނ̍��E��14�l�̕�F�������A10�l�̑m���Ƌ��{�� �������͂݁A�߉ނ̏�����E�ɂ�12�l�̂��܂��܂Ȋy���t�ł��V�������B���́A�@���������̕lj�� �ގ����Ă���Ǝv�����B
�h?��h�R�߉ޔ@�����@�}(�����イ��傤���ス�Ⴉ�ɂ�炢�����ۂ����A��p�����ّ��A �������n�E���n�@�����h?�@�c241.0cm�@��159.5cm�A������j���ǂ������B20���I�����ɒ����E���������A �Ŕ������ꂽ?��(���イ�Ԃ�)�ŁA�����ɐԂ��U�����܂Ƃ����@�������A�@���̍��E�ɘe��(���傤��) �̕�F��2�l�̑m���������������B
���̑��ɂ���R�̓W���i�����������A���͈ȏ�̕����d�_�I�Ɋϗ����āA�A�r�ɂ����B���̉Ƃ���ޗǍ��������� �܂Ŗ�Qkm�ł���B
2018.7.12


�����̃n�X
�䂪�Ƃ̘@���Ԑ���ɂȂ����̂ŁA�����̘@���Ԑ���ł��낤�Ɛ������āA�����֍s���Ă��܂����B �@�͌ߑO10�����߂���ƕ��n�߂�̂ŁA�������s���˂Ȃ�܂���B8:40�ɉƂ��o�āA9:00�ɓ����� �����܂����B�����A�@�̂��鏊�֍s���ƁA���h�ȃJ��������������q�����l�������������B���ɔ����� �Ԃ̘@����R�������ɂ��Ă���܂����B�ʐ^�͓���@�ł��B�ƂĂ��������ł��ˁB��������̓���N�� ���Ȃ�Ŗ��߂������̂ł��傤���H�������ł������A�����͎��̍D���Ȃ����ł��̂ŁA�{�V����J�R���A�Ӑ^�a���_�A�u���ւƈړ����A �Ō�ɁA������Ḏɓߕ������A��t�@�������A���ω���������q�ς����Ă����������B
2018.7.10


���n�X
�{�i�I�ȉĂ̓����ł��傤���A�������������܂Ԃ����ł��ˁB���̉��V����13:30����15:00�܂Ńe�j�X�� ���܂����B���̒ʂ��Ă���e�j�X�X�N�[���͎��O�R�[�g��������܂���B���͂�������������Ă����Ă��܂��B �ł��A���̔����ɔ�����̎�p����̂ŁA�����̓e�j�X���ł��܂���E�E�E�ŁA���̂����ɓ��Ă������� �����˂A�������ɂ͐^�����ɂȂ��Ă��܂��E�E�E�n��������A����Ȃ��ƂȂ����I�����A���A���̑��n�X���炫�܂���(�E�̎ʐ^�A�E���͂Q����)�B��ւ̔������Ԃł��A�ԕt���̈����@���Ǝv���Ă��܂������A �엿���^�b�v�����A�t���ς��傫���Ȃ�A���̖T�炩��ԉ肪�o�Ă��鎖��������܂����B���N�́A����� ���n�X�̔��ɉԂ��t���܂����B
2018.7.7

�䕗���
�����Ƃ��̒����A�����Ƃ���3�l�̎q�����䂪�Ƃɑ؍݂��Ă���(�E�̎ʐ^)���A�{���F�œ����ւƈړ� ���čs�����B�����̎q���B�͗c���̂ŁA���X�����B���������Ă����"�Ⴍ�āE�n�͂������Ǝq��Ă� �ł��Ȃ��Ȃ�"�Ƃ��Â��v���B�����Â��Ȑ����Ɋ���Ă���̂ŁA���Ȃǂ͊������Ă��܂��B �ł��A�F�����C�ɐ������Ă���Ă���̂ł��肪�������ł���B�����{�ł͍��J�ő�ςȔ�Q���łĂ��邪�A�䂪�Ƃ͖����ł���B�������A�䕗��߂̗l�ȎU����� �Ƃ̒��̐����͂��ꂩ��ł���B���Ȃ́A�O�o����A���"��ꂽ"�ƌ����ĐQ�Ă��܂����B�[�H�̏o�� �����ɋN���Ă���"��������"�ƌ������B�ǂ���猳�C�ł���B
2018.7.3

�����̗��K
7��1���ɓ����ɏZ�ޒ������A�č�����ċx�݂ŋA���Ă�����w���̒�����A��āA�ޗǂ̉䂪�Ƃɗ����B �����͊w��o�ȂŒ��Ԃ͂��Ȃ��B�����͊����ƂȂ̂ŁA�A���F�B�ƈ����Ƃ��ŖZ�����B���́A������10:30����J�Â��ꂽ�������p�̐�����ɏo�Ȃ����B�ߌ�̓e�j�X�X�N�[���ɍs������ �v���Ă�����A������"15:00�ɏ��w�Z�֍s���Ē��j���}���A�A�蓹�Ő܂莆���ė��Ăق���"�ƌ������B �����̗��݂͒f��Â炢�E�E�E�ŁA������������čs�����B�����̒��j�͏��w��N���̃N���X�ɓ���� ������������"�����h�Z���������͖̂l������"�ƌ����āA�����ɐV���������h�Z�����Ă�������B �����āA��������������w�Z�ɍs���Ă���B�搶�Ɋ��ӁE���ӂł���B
����7�l�̗[�H�̏�������ςŁA���p�[�g���[�������Ȃ��č��f���Ă�����Ȃ��~�ς��邽�߂ɁA������ �߂��̃��X�g�����ŗ[�H��ۂ���(�E�̎ʐ^)�B���邳�����������Ă�q���B�̗��K�œX����������f���� ����ꂽ���ƂƐ��@���A���d�ɂ���������ċA���Ă����B
2018.6.29


�@
���N���A��������o�Ď��̉Ƃɗ��������@(�����͂����)���炫�܂���(�E�̎ʐ^)�B������ɏo��ƁA �������Ԃ��J�Ԃ��Ă��āA�v�킸�����o���܂����B���N�A�䂪�Ƃōŏ��ɍ炢���@�̉Ԃł��B�ƂĂ����^�� �C�i�ɖ������ԂŁA���͂ƂĂ��C�ɓ����Ă��܂��B���̘@�͂ƂĂ��ԕt���̗ǂ��i��ŁA���N�Ԃ� �炩���Ă���܂��B���̔��ɂ��Q���łĂ��āA���ꂩ�玟�X�ƍ炩���Ă��ꂻ���ł��B�����̕v�N��28���Ɉ�l�č��ɋA���čs���A���͎����ƎO�l�̎q�����䂪�Ƃɋ��܂��B���X�����̂ŁA �����̃y�[�X�����A26. 27, 28���ƘA���Ńe�j�X�X�N�[���ɍs���܂����B���̍s���Ă���e�j�X �X�N�[���͎��O�R�[�g�����Ȃ̂ŁA�J�V�̐U��ւ������āA�V�C�̗ǂ����Ƀe�j�X�X�N�[���ɍs���B 30���̉��V���ŁA�т�����芾�𗬂��Ẵe�j�X�ł���B1���Ԕ���1���b�g���̐������ށB���N�g�ɂ� ���ĂȂ��āA�ƂɋA����1���Ԃقǒ��Q������B�܂��A���\�ȕ�炵�ŁA���ӁE���ӂł���B
2018.6.24

������Ƃ̗��K
6��18�����A��̘@���ɂ��郁�_�J�ɉa������Ă�����A�h�[���Ƌ����㉺�U���̒n�k���������B �����e���r�������"���k���𒆐S�Ƃ����ő�k�x�U��̒n�k"�Ƃ̂��Ƃł������B �_�˂ł̒n�k�̌o������A���̒��x�Ȃ���v�Ə������S�����B�E�E�E���āA���̓��̗[���A������ �v�N����l�̖��B�Ɗ�ɓ�������\��ł������B��̌�ʏa��S�z�������A�[���ɂ� ��������������Ă��āA�\����30�����̒x�ꂾ���ŁA�O�l�Ƃ����C�œޗǂ̉䂪�Ƃɓ��������B�����̈�ƑS��(5�l)���䂪�Ƃɂ�������B�Ƃ̒��͂����Ⴒ����ɂȂ�"�Y��ɑ|��"�̐��ʂ͖��� �Ȃ��Ă��܂����B����"��l�����̐Â��Ȑ���"�Ɋ���Ă���̂ŁA���₩�Ȃ̂͊��������A�̒��� �����Ă��܂��B����Ŏ��́A�o���邾��"�����̐���"���y���ނ��Ƃɂ��A�ʏ�̃y�[�X�Ńe�j�X�X�N�[�� �ɍs���A�s�A�m�̗��K�����A�������y���ނ��Ƃɂ��Ă���B�����̈�Ƃ�"���R�C�܂܂ɍs�����Ă���"�B
6��24���S�����s���悭�Ȃ����̂�"�ޗnj����֍s����"�Ƃ������ƂɂȂ����B�䂪�Ƃ���k���ŁA �Ă����ʂ�啧�a�ɍs����(�E�̎ʐ^�͑啧�a�K�i���ł̃X�i�b�v)�B�q�ό�A�啧�a��O�̃��X�g������ ���H��ۂ����B���̌�"�t����Ђɍs��"�Ƃ����̂ŁA���͊F�ƕʂ�āA���厛�{�V�ŊJ�Â���Ă��� "�Ô��p����݂铌�厛�̔��E�E�E���Ă��o�Ɠ��̊ۖ~�𒆐S�ɁE�E�E"�̔q�ςɍs�����B���Ă��o�� ���̊ۖ~���"�吹��(�������傤��)"�Ƃ����鐹���V�c�����ʂ��ꂽ�Ƃ��������o�̒f�Ȃ������[�� �q�ς����Ē������B���Ƃɂ͖���"���킢�̂��鎚"�ł���A�����V�c�̐l�����o�Ă���Ǝv�����B
2018.6.13

�����̗��K
�č��ɏZ�ގ��������j(6�I�A���w1�N���B�䂪�Ƃ̒�ŎB�����ʐ^���E�Ɏ���)��A��� �ޗǂɗ����B����10���̗[���A�����ۋ�`�܂ŎԂŌ}���ɍs�����B�č��̏��w�Z���ċx�݂ɂȂ����̂ŁA2,3�T�ԓ��{�̏��w�Z�ɓ���Ă��������āA���{�� �Ɋ��ꂳ����ړI���ƁA���͐��@����B11���ɂ͎��������ɑ؍ݏƖ������炢�A���̌�A �s�����ւ����Ď葱�������A�����ŁA���w�Z�֍s���āA12������ʊw�����Ă��������l�� ���肢�����Ă����B
12��7:45�ɉƂ��o�āA���w�Z�֍s���A16:00���}���ɍs���������Ƌ��ɋA���ė����B���� "�ǂ�������?"�Ɛu�˂���A"�y��������"�ƌ������B���b����搶����ςł��낤�Ɛ��@�E���ӂ���B
���āA�����ł��邪�A�ޏ����Y��D���ł���B����������Ƃ����̂ŁA�ߋ��̌o�������āA ���Ȃ͑䏊�╗�C��̑|�������Ă������B�E�E�E�Ƃ��낪�A�����H��"�����I�ڂ������Č����Ȃ� �̂��낤���`�����g�|�������Ȃ����B�����ŏo���Ȃ�������A���������Y��ɂ��Ă��炢�Ȃ���" �ƌ������B�����āA�|���@��Ɩ�܂��Ă��āA�����E���C�E���ʏ��E����@�̑|���������B �����̊��C��̃t�B���^�[�܂Ő��|�����B���Ȃ́A���������������_����̂ɁA�������������Ƃɂ� ���������f���������Ă���B
2018.6.8

��̙���
������Ă��ğT���Ƃ��Ă����B6��7���~�̎��n�����˂āA�~�̖̙���������B �䂪�Ƃ̔~�̖͂��Ȃ�̑�ŁA����5m�͂���B���̖ɓo���Ĕ~�̎������B �����Ď�̓͂��Ȃ����̂́A���̎}�����Ő�B�����̂�A���������B �~�̖͂��Ȃ苭���̂ł��邪�A�����������Ȃ��̂ŁA�T�d�ɍs���B���Ă���� ��Ƃ��r���ۂ��Ȃ�̂ŁA��ꂽ�ȂƎv������x�e����B�i���g�J�����I�������B �ł��A������ꂽ�B
6��8���T���V���E�̖̙���������B�T���V���E�ɂׂ͍�����������̂��A�����o���č�Ƃ���� �`�N�`�N�ɂނ̂ŁA�����E��܁E�h���l�b�g�����čs�����B�����ŁA���A���`�A���A���A�A�P�r�A �T�l�J�Y���A�m�E�[���J�Y���A�h�F�A�ցA���̙�����s�����B �����ɂ́A��X�̎R�쑐���A���Ă���̂ŁA�A�؉�����ɂ͗��߂Ȃ��B���Ȃ̊Ď��̂��Ƃł̍�Ƃł���B ��ςł��邪�A���̓��̍�Ƃ͊댯�������Ȃ��̂ŋC�y�ł���B
����������肵�āA���邭�Ȃ����B���������ł���B�E�̎ʐ^�͒�ɍ炢���J�����i�f�V�R�B �u�v
2018.6.4
������
���͍��Ⴊ�E��Ɣ�ׂāA�K���X���܂������̗l�Ȍ�����������B���퐶���ɂ͍���Ȃ����A���ɖ{�E�V�� ������œǂނ��Ƃ��o����B�������A���ƂȂ������炢�B�Ԃ��^�]����Ƃ��A���K���X���܂��Ă���̂��� �Ǝv�����Ƃ����X����l�ɂȂ����B��Ȉ�@�Ō��f���Ă�����������"������ł��ˁA��p��������E�E�E"�� ����ꂽ�B����ŁA������̒ʉ@��p���邱�Ƃɂ����B���̃X�P�W���[����7��3��10:30����p�̐��������A�Ƒ������ŗ���悤�ɂƌ���ꂽ�B
7��13��15:00����p�O�̌����E�f�@�B���̍ہA�l�ԃh�b�N�̐��я������Q����ƌ���ꂽ�B
8��1��15:30����p�����A�_��̗��K�B�N���r�b�g�_��B�Ƒ������B
8��3�������p�B�Ƒ������B
8��4��9:00��p�����f�@�B
8��7���E���p�B�Ƒ������B
8��8��9:00��p�����f�@�B
��p��2���Ԃ́A���E�����֎~�B2�T�Ԃ͗��s�E����֎~�B�ꂩ���Ԃ͉^���֎~(�e�j�X���o���Ȃ�!!)�B 30���قǂ̃E�H�[�L���O��1�T�Ԍォ��B���X�Ȃ��Ȃ���ςł���B
2018.5.27

�x�j�o�i���}�V���N���N
���嗝�w�����w�Ȃł̓������ł���s�N����"���s�{��O�s���R�����v�ۂŃx�j�o�i���}�V���N���N�̉Ԃ� ������̂ōs���Ȃ���?"�Ƃ̗U�����A�������S�l�ōs�����ƂɂȂ����B�W�����Ԃ�9:00��JR�j��w�O �ɍs�����B�Ƃ��낪�A9:20�ɂȂ��Ă��s�N�����Ȃ��B�s�N�͌g�ѓd�b�������Ȃ��̂ŘA�����o���������Ă� ����A9:30�ɂ���ė����B"�X�s�[�h�ᔽ�ŕ߂܂����B15km/h�I�[�o�[��ŁA�z���}�ɂЂǂ�! ���ʂ͌����� �����B1,2000�~������āA�z���}�ɂЂǂ��E�E�E"�ƁB�s�N�ɗ��������Ē����āA�s�N�̎ԁE�s�N�̉^�]�ŁA���R�X����ʂ��āA11:30���R�����v�ۂɒ������B �����ق̒��ԏ�ɎԂ��߁A�ۑS���͋��P�l300�~���x�����āA�������ɂ��鐙�т̕��֕����čs�����B ���������ƁA���̗����Ƀx�j�o�i���}�V���N���N�̉Ԃ������l�ɂȂ����B����ɐi�ނƁA����s���N�� �������Ԃ���R�̌�����悤�ɂȂ����B�C�i�̂���A���M�ȉԂŁA�ƂĂ��������̂Ɋ��������B �E�ɂ��̂����̈�̎ʐ^�������B"�Ԃ̎�������T�Ԃق�"�Ƃ̂��ƂŁA���N��5��20���A27���A28���̎O���� �������J���Ă���Ƃ̂��Ƃł������B�ۑ���̕������X�ɂ���ꂽ���A���̔������Ԃ��ǂ��ۑ�����Ă���ƁA ���̂��w�͂Ɋ��ӁE���ӂł���B
�����ّO�̍L��ł́A�R�̓V�Ղ�A���ɂ���A�n����̔̔����s���Ă���A����"�R�̓V�Ղ�"���� ���������ĐH�ׂ��B�ƂĂ��������������̂ŁA"�[�H�p��"�ƒlj��w�������B�߂���"�@�@�̑�"�̉��ɂ���͌��� �A�x�����H�ٓ���H�ׂ���A���R����Ԃ��̗��������U�A16:30JR�j��w�O�ɋA�������B�r���ŁA�X�s�[�h �ᔽ�ŕ߂܂邱�Ƃ������E�E�E�A
2018.5.20
�Ƌ�̈ړ�
�č��ɏZ�ގ�����"6���Ɏq����A��ēޗǂɍs���B�ޗǂ̉Ƃ̓�K�ɔ��܂肽�����A�\�y���n�k�̍ۓ|�� �Ă������Ŋ댯�ł���B���̕����Ɉړ����Ă����Ăق����B"�ƘA�����Ă����B�Ⴂ���Ȃ牽�ł��Ȃ��� ���̗l�ɗ���Ƃ������̂ɂ͑�ςł���B������"�֗����T�[�r�X�𗊂߂悢"�ƁE�E�E�B���̕����Ɉړ�����ɂ��A�ړ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ŁA���̖{�������A�ǂނ��Ƃ� �����Ǝv����{�����Ă��B�X�y�[�X���o�����̂ŁA�\�y�̈ړ������݂��B�����o����S�Ď��o���A�㕔 �����������グ�Ă݂��B�ӊO�Ɍy�������̂ŁA���ȂɎ�`�킹�āA�㕔�����ړ������B�����ŁA�������ړ� �����B�����ŁA�����o�����ړ����A���Ƃ��\�y�̈ړ����o�����B
���ł��ɂ߂���ߎS�Ȃ̂ŁA�T�d�ɍs�����B�������A�b������ƁA���r�ɗ͂�����ƒɂ݂��������B ��������"�����ȗ͂���ꂽ"�炵���B�܂��A�d���������B�b���A���d�B
2018.5.8
�l�ԃh�b�N
4��17���ɔ����̐l�ԃh�b�N���f�����B���̍�(76)�ɂȂ��Ă�"�܂������������H"�ƌ���ꂻ������ "80�܂ł͌��N�Ő�������"�Ƃ̎v���������āA���N���l�ԃh�b�N���f�����B���̌��f���ʂ̕��ɁA�{���a�@�ɍs�����B��t��"�@�\�̒ቺ�͑��X���邪�A�N����̂��̂� ���ˁB����͂���Ƃ��āA�����Ⴊ����悤�������Ȃɍs���ďڂ����������Ă��炢�Ȃ���"�Ƃ�����������B ���͍��Ⴊ�E��Ɣ�ׂĉ������������悤�ł��鎖�����o���Ă����B����ŁA�������p�Œm��ꂽ��Ȉ�@ �Ɍ��f�����肢�����B���Z�炵��"��ԑ�����40����ɗ\��o���܂�"�ƌ���ꂽ�B���͌��f�\��������B
2018.4.29

���V�g����
�A�x�Ńs�A�m�������e�j�X�X�N�[�����x�݂ł���B����ŁA�d�����������牷��ɂł��s�������Ǝv�������A ��䉷��̗��قɓd�b������"5��2���Ȃ�Ă܂������̑��͖���"�ƌ���ꂽ�B�V�C�\��ɂ���5��2����3 ���͉J�E�E�E�Œf�O�����B�_�����Ƃœ��V�g����̎R�����ɓd�b������"����(4��28��)�Ȃ�Ă��܂�"�� ����ꂽ�B����ł́E�E�E�Ƌ}篁A�o�����邱�ƂɂȂ����B11:30�ɎԂʼnƂ��o�āA�r���̑�F�ɒ��œV���� ������H�ׁA15:30���V�g����̏h�ɒ������B�`�F�b�N�C�����ς܂�����A�U���ɏo���B�唗�_���̌Ί݂̎R�� ����������A�R���痎���Ă��������R�����āE�E�E���Ƃ��X�������_�̓��ŁA�����A�ꂽ�͍̂K�^�ł������B�R������39���A����500L�̗N�o�ʁA�����̑������蓒:�Y�_�d����Ƃ̂��Ƃł������B�̗����ł���Ȃ���A �����ł��邱�Ƃ�������Ȃ��قǂɉ����F�̐ΊD���̐͏o�����t�����Ă����B�͈ꗬ�ł���Ǝv�����B �h�͖��h�ɋ߂��A��y���͂Ȃ����A�f�p�Ȃ��̂ŁA�����ł�����̂ł������B
4��29��9:00�`�F�b�N�A�E�g�B�߂��̂ŁA���P���֍s�����Ƃɂ����B10:30���P�����ԏ�ɒ������B���������ƂɁA �ԂŖ��t�B��R�̎Ԃ��ԓ��ɗ������Ď~�܂��Ă������R�����������B500m�͉����čs���Ȃ���E�E�E�Ɗo�債����A �^�ǂ���䂪�A���čs�����B���b�L�[�E���b�L�[�B
���X�Ŋ`�̗t���i���w�����A11:00�o�R�J�n�B12:00���o�P�x�R��(1695m)�ɒ������H�B���̌�A�������A���h�҂��o�� 14:30���P�����ԏꒅ�B18:00�ޗǂ̎���ɋA�������B�E�̎ʐ^�͐��ؗ䂩�猩�����o�P�x�B���t���͉萁���������Ƃ���B
2018.4.26

�����̖I����
���N�͒�̋����̖Ɏ�����R�Ȃ����B������Ƃ��Ă���"�����̖I����"��������B���̍������L���Ă����B1. �����𐅂ŐA�U���Ő��������B
2. �����ɂ��A�f�U�[�g�p�̏��^�z�[�N���g���Ď���o���B
3. ����(600g)���ɓ���āA���̏ォ��I��(150g)�𐂂炵�A���ł��������Ȃ���10�������B
�@�@�������琅���o�Ă���̂ŁA���͉����Ȃ��B
4. �����������������Ə`��[���Ɉڂ��A�d�q�����W�łT�������B(�d�q�����W���g�����Ƃɂ��A�ł������Ɩ��� ���������������邱�Ƃ��ł���B)
�E�̎ʐ^�͏o���オ����"�����̖I����"
2018.4.25

�����
�U���̋A�蓹�ŋ������֍s�����B�����ɓ���Ɖ�y���������Ă����B�d���ɋ߂Â��ƒt���s�� �����Ă����B������"�����͋������̕����̓���"�ƋC���t�����B����25���͕����F�̉����ł��邪�A �������ł�4��25����"�����K���s����B�������������̕����F(����)�͌Â�����w��m�̐M�� �W�߂Ă����B�����ł͕����F�̒q�b�������낤�ƒt���̍s����B�����������ɒ�������(15:00) �t���̍s�������ɒ������̂ł������B�������̑m�B���擱���ē������ɓ����čs��(�E�̎ʐ^)�̂� �q�����邱�Ƃ��o�����B�t���s��ŁA�s���̏��w�������o�̈�߂�1�����������ĕ�[�����K��"�ꎚ��"���z�Ԃɏ悹�āA �t���B�����������čs���B����"�ꎚ��"�́A��N�ԁA�������̑O�ɏ����Ă���̂Ŕq�����邱�Ƃ��o����B
2018.4.16

����R
���嗝�w���ʎq���w�������ł̐�y�x����v�ȁA�������̂s�N�A���Ƌ��Ȃ̂T�l�� ����s�ƎI�]�s�̋��ɂ��镶��R�i���コ��A�W��365m�j�֍s�����B�s�N�� "�J�^�N�����������Ă��ĉԂ�����"�ƗU���Ă��ꂽ�̂ł���B9:00�ɋߓS�|�c�w�O�ɏW���A�s�N�̎Ԃɏ悹�Ă��������A12:10�ɕ���R���o�R���ɒ������B ���ԏ�őԐ��𐮂��A���l�x�ڂƂ����s�N�̈ē��āA�o�R���J�n�����B�s�N�����̎R���� ����A�O�{�̊ۑ����̂��鏬���n��ہA���Ȃ��������点�ď���ɓ]���A��]���� ����ɐK���痎�����B�������̂ŔG��邾���ōς��A�O�r������v�킹���B�g������ �������̂�"���̂�������"�Ɠo�R�𑱂����B�܂��Ȃ��J�^�N���̌Q�����o�R�������Ɋς�� ��悤�ɂȂ����B�Ԑ���͏I����Ď����t���Ă���̂��唼�ŁA�܂�ɉԂ̕t�����̂��c���� �����B�s�N��"�Ԑ��������ɂ́A�l���ɂȂ������T�Ԗ��ɗ��Ȃ�����E�E�E"�ƌ������B ���x���オ��ɂ��A�c�{�X�~���A�V���E�W���E�o�J�}�A�C�J���\�E�A�~���}�J�^�o�~�A�R�u�V�A ���}�u�L�̉Ԃ�������悤�ɂȂ�A���J�̃J�^�N���̉Ԃ���R������悤�ɂȂ����B ����ɐi�ނƁA�I�I�C���J�K�~�̌Q��������A��������(�E�̎ʐ^)��t���Ă����B�L�����\�E�A �c�N�o�L�������\�E�̉Ԃ�����ꂽ�B14:00������R��(296m)�ɓ����A�����ŁA�ٓ����L�����B �x�����H�ł������B�A�H������̂ŁA����R����͒f�O���ĉ��R�����B15:15���o�R���ɋA���B 18:15�ߓS�|�c�w�O�ɖ����A�������B
2018.4.8

������
�g�����Ȃ����̂ŁA����4��1���ɒg�[���A�~���ߗ���Еt�����B�Ƃ��낪�A����2,3���C���������� �������Ȃ����B�t���ߗ����d�˒����Ă��̂��ł���B�������������Ȃ�E�E�E�ƁB�����͊������ŁA���H��ɎU���ɏo�����͔������āA���͎�܂��Ƃ�ɉƂɖ߂����B�ďo������ �b�������ƁA���x�͓����������ƂɋC���t�����B�ēx�߂�̂͂��������Ȃ̂ő����ŕ������Ƃɂ����B ��������~���ɍs������A���O�ɉԌ䓰(�Ԃŏ���������)���݂����Ă���A�������̒a������ �����Տ�Ɉ��u���Ă������B�|�̕��ۂŊÒ��𒍂��A�Ò���q�������Ă����������B4��8���͎ߑ��a�� �̓��ŁA�e���ŕ��������B���厛�啧�a�O�ɂ��Ԍ䓰���݂����Ă������Ƃ��v���o���A���� ���厛�啧�a�ւƕ����čs�����B�������Ɠ����悤�ɁB�{�̂�̐��t�ŕ����A�n���̉Ԃ� �ւ̉Ԃő��������Ԍ䓰���݂����Ă���(�E�̎ʐ^)�B
15�����䂪�ƂɋA���������A���̍��ɂ͑��z���o�Ă���A�����ł͊����o���B
2018.3.31

��I�̗�
��N�������A��I�̗��������B��N�͋ʒu�_�Ђɍs�������ɂ͐Ⴊ�~���Ă���������͉��� �ł������B���̗���"�V�C�\��݂āA�V�C���ǂ��ꍇ�ɗ��ق�\��"�B���R�l������E�E�E�� ���ł���B29��9:45�ɎԂʼnƂ��o�āA�\�Ð�Œ��H(�L�m�R����)���Ƃ�A14:00�ʒu�_�Ђ̒��ԏ�(�W��900m)�ɒ������B �o�R�C�ɕς��ăX�e�b�L�������A��쓹�ɓ���A14:40�ʒu�R�R��(�W��1077m)�ɒ������B �E�̎ʐ^�͎R���ł̂��́A�w��ɓߒq�R�E�F��傪������B�����̎ʐ^�������"�����N��������Ȃ�"�Ɗ�����B ���ꂪ�����Ȃ̂��E�E�E�ƁB�}�ȎΖʂ�����Ƌʒu�_�Ђɒ������B�����ɂ͎���3000�N�Ƃ�������M���ɁA ��R�̐��̌Ö��ї����Ă��芴����������B���[���R���̐_�ЂƂ��ẮA�ƂĂ����h�ł���B 17:00����̏h"���Â܂�"�ɒ������B�����B����ɓ������B�Â��ؑ��̓����̒��ɁA�������̓��M������A 100%����Ƃ��������ۂ������L�̉���͑f���炵�������B�����E���M�E�h�̕��͋C�͊�䉷���"��䉮"�Ɠ��i�A ����̐�"���Â܂�"��������A�����E�T�[�r�X��"��䉮"����c�c�Ƃ����̂����̊��z�B
30��9:00�`�F�b�N�A�E�g�B������U��E���q�ɎQ�q������A�F��{�{��Б���i������̂͂�: �F���E������E��c��̍����_�ɂ��钆�F�ŁA1889�N�̑吅�Q�܂ŌF��{�{��Ђ��������ꏊ)�֍s���A �F���̉͌��ŗV�B10:15�V�{�ɂ���F�쑬�ʑ��(�F��O�R�͖{�{�A���ʁA�ߒq)�֍s�����B �БO�ɋ���ȃi�M�̑���������B�Q�q��A�����e�ɂ��鍲���t�v�L�O�قɓ������B�����͓����ɂ���������� ���a�n�߂��Ɉڒz�������̂ŗ��h�Ȃ��̂ł������B�����t�v�N�ǂ�"�H�����̉�"��^���e�[�v�ŕ������Ƃ��o�����B ���̌�A���{���o�đ哇�֍s�����B�́A�����������w���ł��������A���N�K�ꂽ���������ꏊ�ł���B���̍� �h�������z�e���̂������ꏊ�ɍs������A�z�e���͖����Ȃ��Ă���A�v�[���������̘̂Ԏc���Ă����B 4:30���{�ɂ���z�e���ɒ������B�ǂ��ɂł����郊�]�[�g�z�e���ł���B����ɓ�������A5:30���[�H�B
31��9:00�`�F�b�N�A�E�g�B������K�ꂽ��A13:30�I�O�䎛(�����ω������ԎD��)�ɒ������B�������J�ŁA �Q�q�҂œ�����Ă����B�x�����H(���˂��ǂ�500�~)��ۂ�����A��H�ޗǂցB17:00����ɋA�������B
2018.3.28

��H��
���̉Ƃ̓����͍��ې�ł���B�Ƃ��牺���ɂPkm���s��������"��H��"�ƌĂ�����170�N �̍��̖����{����B���̌ď͓̂ޗǕ�s�߂���H��敁i���킶�Ƃ�������j�ɗR������B��H��敂�1801�N�啪�����c�s�ɐ��܂�A1846-1851�N�ɓޗǕ�s�i��s���̏ꏊ�͌��݂� �ޗǏ��q��w�j�߂��B���̌�A�����s��O����s�߁A1854�N���V�A�g�߂ƌ��� ���I�a�e�������B1868�N�]�ˊJ��̂��킳���Ď��E�����B��H��敂͓ޗǕ�s�Ƃ��� �P�����s���Ƌ��ɁA�������Ⓦ�厛���獲�ې�̒�܂Ő���{�̍��ƕ��̖�A�����B ���݁A����r�̖k��"�\��i"�̊K�i�����������"�A�����V��"������A��H��敂̌��т� ��������Ă���B
�����͉����Œg�����A�ޗǂ̍�����C�ɖ��J�ƂȂ����B���̓e�j�X�X�N�[������A���Ĉ�x�݂�����A ���ې�ׂ�̍������ɍs�����B�E�̎ʐ^��"��H��"�ł���B���݂����C�Ŗ��N�������Ԃ������Ă����B
�����ς�Ǝv���o���g��E�̉� "�����肫�@���̂��Ƃ��@�l���肫�@�����悭�݂�@�t�̌�"�A
���s�@�t�̉� "�˂��͂��� �Ԃ̂����ɂ� �t���Ȃ� ���̂����炬�� �]���̍�"�B
2018.3.15

�t�̓���
�����͉����Œg�����A�ޗǂł͍ō��C����22���ɂȂ����B"�������"�����������s�ł���B ���H��̎U���Ŏ������֒��������A�m�B�����ł̎Q�q���I���āA���̊K�i���� ����J�R���֖��s�̕Q�q�Ɍ�������Ƃ���ł�����(�E�̎ʐ^)�B�܂��A���̓쑤�ł́A ���s�O�����̍s�@�̍ۂɔ�������ؖX��c���ɂ��Ԃ���ƌ��N�Ɉ�Ƃ����̂ŁA�q���� �A�ꂽ�l�B���s��������āA�����q�����ؖX�����Ԃ��Ă��炢�L�O�ʐ^���B���Ă����B���͂���ɁA�@�ؓ��A�t������o�āA�ۑ��~���֍s�����B�~�̉Ԃ͖��J�ŁA�����̐l�������� ���Ă���ꂽ�B�g�����āA���͏㒅��E���AT�V���c�ꖇ�ɂȂ��ĕ������B"�������"���ς�ŁA �t�̓����ł���B
2018.3.1

����R�����{
���H��̎U���œ��ւ������B���ł�"�������"���n�܂��Ă��āA�����s�������ɂ� ���s�O(�Ă�̑m)�̒��H��ŁA���߂𒅂����s�O�������h���ɍs���Ă��낢�ł��������� ���ł������B���ŎQ�q���Ă������y���������Ă����̂ŁA����R�����{�֍s�����B�������������� �܂悭"�C�g"�̉��t���n�܂����B"�C�g"�͌�������掵���u�g�t��v�ŁA�������������� �Ƌ��ɕ������y�̋Ȃł���B���͕�[����Ă��Ȃ��������A�������ȂŊ��\�����Ă����������B �E�̎ʐ^�͂��̉��t���i�B
2018.2.26
��T��
�{�i�I�ȋ������𖡂킢�����Ɠ�T����O�̕Z���ɍs�����B���͑�w��N���̎��A��T�������� ���h���Ă����B�n�R�w���ŕZ���Ȃlj�������������"��x�͓����Ă݂���"�Ǝv���Ă��āA50�]�N ���o�āA�悤�₭���������B�̂т�������"�����������Η���"�����\�����Ă����������B���̌�A��T���������U���B��O�̎Q���̖k���͐����ϓ����Ă������A�쑤�̘͐̂Ԃł������B �O�傪���J����Ă����̂ŘO��ɓo�点�Ă����������B���艏����̒��߂͐�i�ł���B�����ŁA �����E������(���ɍ���)�����w�����Ă����������B�����̋��ɏ�lj��"�����׃f�W�^������"�� ���������A������̏�lj�͂܂��{���ŁA���T�H�̍�Ƃ�����"�����݂̌�"�͌��������������B �뉀�����h�Ő���K�ꂽ���m������T���̕����ǂ��Ǝv�����B
�w������ɂ����b�ɂȂ��������̏��ɍs���Ă݂����A�V���������������A�̖̂ʉe�͖����Ȃ��Ă����B �ł��A��T�������͉��������A�F�X�ȑz���o�̏ꏊ������A�y����������߂������Ă����������B
2018.2.22
�_��
2017.9.19�̃u���O�ɋL����"���s�Ƒ��ɏZ�މ��w����������N�̉����̒���2�l"�̓��� 1�l(I����)����u���s�̋_���߂��̉�L�Ŏʐ^�̓W��������v�Ƃ̈ē������B����1�l(K����) ����u������@���3�l�W�܂낤�v�ƌĂт���������A����I����Ɂu�����������H�̂��X��!�v�� ���肢�����B�u2��22��11���ɓ���O�ɏW���v�Ƃ̂��ƂŁA�o�����čs�����B10:00�ߓS�ޗljw���� �d�Ԃɏ������A10:45�ɋ_���l���ɒ������B��L�Ŏʐ^�W(20�l�]�̃t�H�g�T�[�N������̍�i�W)�B�ʐ^�̗ǂ�������Ȃ����́A����Ɏ����� �������q�ׂA�P���Ԃقnj��w�����Ă����������B���̌�A�������_���̊X���݂��U�AI���� �̗\�Ă����ĉ����������X�g�����֍s�����B���ꂪ�Ȃ�ƒ|�����P(���s��d�̏d���A���� �����M�͎��)�̋��������p�������̂ŁA�����͍ŏ����ʼn����̗l�q���M���m���f���炵������ �������B�����̓C�^���A���ł��������A�ƂĂ������������\�����Ă����������B
�H��A���䎛�A����̓��ӂ���U�A���m���֍s�����B���͋��s�Ŋw���E�@��������߂������� �����nj��m����K�ꂽ�L���������B�_���̋ߕӂɌ��m��(���{�ɑT�������炵�A�����L�߂��h���T�t���J�R) �����邱�Ƃ�m���ċ������B���m���Ƃ����A�U���@�B�ɂ�镗�_���_�}?��(2�Ȉ�1�o���{���n) ���L���ŁA�������ɓW�����Ă������B����ɂ͓��R����̉�ƊC�k�F���ɂ�鉦�G�u�_���v�A �u�|��7���v�A�u�Պ�����v�A�u�R���v���������ł������B�ł��A�����S�Ă�"�����׃f�W�^������"�� ���邱�Ƃ�m���āA�Ȃ��K�b�J�������B���_���_�}?��(����)�͋��s���������قɊ�����Ă��� �Ƃ̂��Ƃł���
2018.2.19
�V��t��
���H��A�U���ɏo���B�Ė���o�ē��厛���d���ɍs���A�v���Ԃ�(���N�Ԃ�?)�ɁA�V������̌��� �l�V����(�Y���A����)��q�ς����Ă����������B���̌�A�ǂ��@�����V��t���̏\��_���� �q�ς����Ē������ƁA���厛����A�t����ЁE���̔H�X�����o�ĐV��t���֍s�����B�V��t���̓������Ɛ��ʂɁA�ꌩ���ēޗǎ���̌����Ƃ킩��{��������B�����āA����� �����a��(���厛����n�����A752�N��������n�n����)�̌䎕��(�Γ�)������B������ ��������q�ς�����{���ɓ���ƁA�{���@��t�@������(�J���̈�ؑ���A�ޗǎ���A����)�̑O�ŁA ���Z�E�̒��c��d���Q�q�҂ɐ����E���b���J�n���ꂽ�Ƃ���ł������B���c��d����͍�N �C���h�֗��s�����ہA�����ŏh���������Ƃ̂��鋌�m�ł���B���b�̓��e���ǂ��������A�Â��� �����ŔM�S�Ɍ����p���ǂ������B�u�����A13,14,15,16��������������Ă���v�Ƃ̂��Ƃ� �������B���̎Ⴂ�m(40�ˈ�?)�̂��b�������ł����l������Ǝv���E�E�E���̂��E�߁B
��t�@�������͗��h�ł��邪�A����������ƈ͂�Ō�q���Ă�����\��_��(�Y���A����A �{�����i���т�j�叫���݂͍̂]�ˎ��㖖���̒n�k�œ|�A���a6�N�ɍגJ���y�����)�� �f���炵���B
�Ƃ܂ŕ����ċA���āA����11135�B
2018.2.16

�t�̒���
�����̒��j��15���̒��H��A�����A���čs�����B�D�N�Řb���Ă���Ɗy�����B�C���͐����O�Ɣ�ׂ�Ɛ����g�����Ȃ����B��̃��E�o�C���J�Ԃ��n�߂��B�������Č���ƁA �Z�c�u���\�E���炢�Ă���(�E�̎ʐ^)�B��������J�B���������J�Ԃ��Ă����B�����A�t�� �����܂ŗ��Ă���B
�����A�s�A�m�����̌�ŁA�U���œ��ɍs�����B���̎Q�U���O�ɂ́A�ď����Ɏg�� �|����R����ł����B��������(3��1������)������肪�n�܂�B�ޗǂł́u������肪 �I���Ət�ɂȂ�v�ƌ����Ă���B
2018.2.12

��
���N����ƒ�ɂ��������(2-3cm)�Ⴊ�ς����Ă����B�O�C�͗₽���Đ�͂ς��ς��Ƃ��Ă��āA �Ԃ̏�ɐς�������͕����ƊȒP�ɗ������B�c������𐅓����ŗ����āA�c���������^�I���� �ӂ���낤�Ƃ�����A�X�ɂȂ��Ă����B11:30�����̒��j�̉^�]�Ŗ��������ɍs�����Ƃɂ����B��������i�F�����҂��āE�E�E�B�r���ɂ��� ����̋������Ɋ���Ē��H��ۂ낤�Ƃ��ē��X������15�l���̍s��ł������E�E�E�Œ��߂āA�Ε��� �Õ��̘e�ɂ���A���������c�̃��X�g�����Œ��H��ۂ����B���̌�A��̏㗬�ɍs���A��� ������(�j�j)��q�ρB�����Ŋ��X�̊�����(���j)�̔q�ςɍs�����B�r���ŐႪ�X��ɂȂ��Ă��āA�Ԃ� �X���b�v���������̂ŁA�����Ċ�����(���j�A�E�̎ʐ^)�܂ōs�����B1��11���ɕt���ւ���ꂽ�l�� �^�V���������B���ɓn����������͐N�����Ă��鏔�X�̈��u�E���Q�������Ŗh�䂷��Ƌ��ɁA ����̎q���ɉh�E�L����F�肷����̗̂l�ł���B
2018.2.9
�U��
���̓��ɂ͖w�ǔ��������悤�Ɍ����邪�A�P�����Ɉ�x���炢�U���ɍs���Ȃ��Ɛ��̖т��L�т� ���ƂȂ��C�����������B����ŁA���͂قڂP�����Ɉ�x�U���ɍs���B�ȑO�͕��ʂ̎U��������ɍs���Ă����B ���P�Ŕ����Ȍ��z��t���Ċێ��ɂ����U��������̘r�Ɍh�����Ă����B������4320�~�ł������B �Ƃ��낪�A�P�N�قǑO�Ɂu�o���J���Ŋۊ���ɂ��Ē����Ă��卷�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ǝv���āA����Ȃ� �����̈��������X�ɍs�����Ǝ��݂��B�u�o���J���Œ���5mm�Ŋۊ���v�ɂ��Ē������B�����͕E���E�V�����v�[�� �����1700�~�ł������B���ȂɈӌ������߂���u�S�R�ς��Ȃ��v�ƌ������̂ŁA�Ȍ�A�����̈��������X �ł����b�ɂȂ��Ă���B�w�ǔ��������悤�Ɍ����铪�ł��A�ӊO�ɔ�������悤�ŁA�U���̌�ɂ͓��������B���Ȃǂ͊����� �ڂ��o�߂��B�X�q�����Ԃ��ĐQ����A�����ł����B
2018.2.8


�����̒��j�̗��K
�����̒��j(��q��w�R�N)��2��5���ɓޗǂɗ��Ă��ꂽ�B�R�N���ŏA�E�����������n�܂��Ă���l�ł��邪�A ���l��̎���Ȃ̂Ŋy�ς��Ă���̂��E�E�E�A�t�x�݂𗘗p���Ă̗��K�ł���B���s��R��E����(�Ƃ���)�ɂ����ڗ����ւ́A���̉Ƃ���Ԃ�20����ōs����B��ڗ����͖�����Ɛ��ʂɉ��r ������A���̐����ɋ�̂̈���ɕ��̂���������{���A���r�̓����ɖ�t�@���̂���������O�d��������B ���̖�t�@���͔镧�Ŗ����W��(�V�C���ǂ����)�����J�������B
�����͗ǂ��V�C�������̂ŁA12:00�����̒��j�̉^�]�ŏo�����čs�����B��ڗ����̖�O�ɂ��钃�X"������"�ŁA ��Ă����ǂ�A�Ƃ�닼���A�R���ǂ�Ƃ��������A�����̒��j�A���Ȃ̂��ꂼ�ꂪ�H�ׂ��B���̓X�̒뉀�� ���t�ɂ͉Ԗ��炫����ĂƂĂ����������A�A�I���W�̉Ԃ��c���ł�����x�ł������B
��ڗ����̖������āA����������ƎO�d���̐��ʂ̔����J����Ă��ăz�b�Ƃ����B�����̖�t�@���͕ۑ���Ԃ��ǂ��A �ʐF�̗ǂ��c���������������ł���B�����̕ǁE���E�V�䂪�ʐF�E��������Ă���l�ł��邪�A�c�O�Ȃ��炻��͔q�� �o���Ȃ������B
�A�H�ɓ�����啧�J�ɂ��鈢��ɔ@�����R��(�����������A�ԛ���A����260cm)��q�ς����B
2018.2.2

�ጩ�̗�
���N�͖k���ł͍~�Ⴊ�����悤�ŁA���͐ጩ�̗����v�悵�A�R�`���߉��s�̓��c�쉷��ɏh������ �v��𗧂Ă��B�����m�������Ȃ��u�����s���B�R�`�͉�������B����ɂ͗�Ԃ��������������B�v �Ɛ�����B����ŁA���䌧��z�O���́u�Ԃ͂����܂�܁v�ɏh������ጩ�̗������邱�Ƃɂ����B2��1��9:00�ߓS�ޗljw���̓d�Ԃɏ��A9:48���s����JR�ΐ����V����"�։�s��"�ɏ�����B���c���߂���� ��i�F��������悤�ɂȂ����B�։�ŕ���s���̕��ʗ�Ԃɏ��A11:55�����ʼn��Ԃ����B�����͐�̑������� ���܂łɐ���K�ꂽ���Ƃ�����B�w�O��"�����q"�������ɓ���A�������苼��(900�~)��H�ׂ��B���̌�A �����̋��X�����U���B�����͖{�w�A�e�{�w�A�≮������A�����̗��Ă③������������Ĕɉh�����h�꒬�ł���A �������h�ȌÂ��������c���Ă��Č�����������B
13:56����������s���̗�Ԃɏ��A14:03����ʼn��ԁB�h����̑��}�Ԃɏ悹�Ă�������14:20�u�Ԃ͂����܂�܁v �ɒ������B�`�F�b�N�C�����ĉו����ɒu���A�����J�������������Đ�i�F���ςɍs�����B�ӂ�̐ϐ��70-80cm �����āA���Ⴕ�Ă��鏊���������Ȃ������B�h�̑O�̎����ԓ��𓌕��ւƕ���30���قǂ̏W���u�������v�ɓ���A ����ɐi�ނƏW���̂͂���ŏ���͖����Ȃ����̂ň����Ԃ����B
16:00����ɓ������B�L�������Ő�i�F�����Ȃ���������Ɗ������Ƃ��o�����B17:30����[�H�B��������������� �u�I���i�R�[�X�v�𒍕����Ă������B�������������B�ł��A���������ʂ����Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv�����B����ɂ́A �ʒ������Ƃ��đI�����ǂ������ł���B20:00�ēx�A����������ďA���B
2��2��7:00�N���B������A8:00���H�B�ʂ����x�Ŕ������������B9:00�J�������������Đ�i�F���ςɍs�����B �����ŁA�T���O���X�������Ă��Ȃ������̂���������B�O���Ɠ������A�W���u�������v���U���B�E�̎ʐ^�� �W���̂͂���ł̂��́B10:00�`�F�b�N�A�E�g�B�h�̎ԂāK����w�܂ő����Ē����A10:40���̕��ʗ�Ԃœ։� �܂ōs���A11:16�։ꔭ�̃T���_�[�o�[�h��12:20���s���B12:30���s���̋ߓS�d�Ԃɏ��A13:30�ޗǂ̎���ɒ������B �����āA�s�A�m�̗��K���������āA15:00����̃s�A�m�����֍s�����B
2018.1.27

�ᑐ�R�R�Ă�
�����������A���_�J�E�@�̔��ɂ͌����X���͂��Ă����B11:13�ߓS�ޗljw���̓d�Ԃɏ��A�_�ˑ�w�ł� �e�j�X�ɍs�����BJR�̗�Ԃ͗���Ă������A12:40�Z�b���ɒ������B�w�O�ʼn����[�����ƃM���[�U��H�ׂ� �s�o�X�ɏ��A13:15�_�嗝�w���O�ō~�肽�B���ւ������āA�����̑������A�e�j�X���n�߂��B�ŏ��́A ���Ⴊ������Ă������A���z������o���g�����Ȃ����B16:00�e�j�X���I�����A�V�����[�𗁂т���A 16:58�Z�b�����̉�����Ԃɏ��A18:10�ߓS�ޗljw�ɒ������B�n���̉w����n��ɏo��ƁA�ᑐ�R�̕��ʼnԉ��オ���Ă����B18:30�䂪�ƂɋA���B�����A��K�� �o���đ����J����ƁA�ᑐ�R�R�Ă����n�܂����Ƃ���ł������B�����A�ʐ^�@�����o���āA�B�e���� �̂��E�̎ʐ^�B�䂪�Ƃ̓�K�͐�D�̊ϗ��ꏊ�ł���B
2018.1.21
���V
�`��̎o�̒��j(���Ȃ̏]�Z�A84��)�`���S���Ȃ��āA���̑��V���{���������B�����ɏZ�ޒ��������O�ɂ����b�ɂȂ��� �̂ŎQ�����Ƃ����̂ŁA���ȁE���E�����̎O�l�ŏo�����čs�����B�`����͋���H�w���d�C�w�Ȃ𑲋ƌ�A �N�����ɓ��Ђ���N�ސE����q��Ђ̏d���Ƃ��Ċ��ꂽ�B�ŋ߂̌ܔN�Ԃقǂ͒n������s�̑��z�����d���Ƃ� ���グ�E�^�c�ɕ��������Ƃ��ĎQ�悳��A��N�ɂ͌o�ώY�Ƒ�b�܂���܁A�V���ɂ����̎p�E���ʂ�����Ă����B �`����͍�N���ɐS����p�����A�̒��s�ǂƂȂ葼�E���ꂽ�B�������肵���D�������ł������B�����������F�肢���� �܂��B���̑��V�̉�H�ŁA�`��̎o�̕v(�`����̕�)�a����Ɋւ��鋻���[�����b���A����̕�����f�����B�a����� ���啨���w�ȑ��̊w���ŁA���a18�N�ɗ��R��w�Z�̋����ɂȂ�ꂽ�B���a20�N�ɏ��Z��O�ɂ��āu�Ȋw�҂Ƃ��Č���ƁA ���̐푈�͕�����ȁv�Ɣ������A���a20�N3����"�����ƐE�E��������"�𖽂����A42�˂ő卲������ɗ��Ƃ���āA �������ꋞ��(���\�E��)�֑���ꂽ�B�I���A�����A�����ꂽ���A�����R��w�Z�����̌����̂��߃p�[�W(���E�Ǖ�)�� �Ȃ����B�ߋE��w�̋����ƂȂ��N�܂ŕ�E���ꂽ�B�a����͋`��Ɛe���������̂ŁA���͉��x������������Ƃ� �L��܂����A���̂悤�Șb�͏��߂ĕ������B�`�������邱�Ƃ͖��������B
�`����̍N�b�����"������"����ɂ��Ă����������āA�������x���Q�������Ē����A���P�x�E�����P���E�����R���� �A��čs���Ă��������Ƌ��ɁA�ޗNjߍx�̊e�n���ꏏ�ɕ������Ă����������B�b�����"�b���͈�l��炵"�ɂȂ���l�ł���B ����Ȃ̂ŁA�����"������������"����ɂ��āA�c��̐l�����y����Œ��������ƋF�O���邵�����ł���B
2018.1.20
�t�����R�V����
2017.11.2�̃u���O�Ŏᑐ�R�ɓo�������Ƃ��L�������A���̍ہA�t�����R�V�����͒ʍs�~�߂ɂȂ��Ă����B �����͒g��������̓��ł������̂ŁA���H���"�t�����R�V�����������"�Əo�����čs�����B���N�� �������o�R�C�������Ȃ��܂܌ÂтĂ����B����A�����Ă�Ԃɉ���o�R�ł��邩�S���ƂȂ��B����ŁA �U���ɏo��ۂɂ��o�R�C�𗚂����Ƃɂ����B�y���o�R�C�Ȃ̂ňӊO�ɎU���ɂ����K�ł���E�E�E�ŁA �o�R�C�𗚂��ďo�������B13:10�ɉƂ��o�āA�Ė�A�啧�a���A���A����R�_�ЁA�ᑐ�R�R�[���o�āA13:40�t�����R�V�������� �ɒ������B���������ƌÂ��ΕW������"�V�R�L�O���t���R���n�с@������"�ƋL���Ă������B���������߂� ��ƁA��E�Ö������Ȃ�"���n��"�������ł���B����10�N�ȏ�O�ɂ́A�����̗l�ɁA�t�����R�V������ �K��Ă��܂������A�����2.3�N�Ԃ�ł���B�w�Ǖω��͖����A���������v���ŕ������B"�ƂĂ��ǂ��ꏊ���Ȃ�" �Ǝv���Ȃ���������B�����J�x�e�ɂ̋߂��̎R���ɕ��ꂽ�ꏊ������A���̉��ɒ��a2m���̐��̑�̐؊� ���������B14:30�O��ʍs���~�߂�ꂽ���⏊�ɒ������B�W���̕��ɐq�˂���u��N12���ɒʍs�ɂȂ�܂����B ����700�N���̐�����N�̑䕗�œ|��Ă��āA���̏��u���ς�Œʍs�ɂȂ�܂����B�v�Ƃ�����������B 14:50�ᑐ�R�R������˂ɒ������B
���H�Ɠ�������ʂ��ċA�����B���̏t�����R�V������30���قǂ̐l�ƍs�����������A���̎O���̈�����O���l�� �������̂�"����"�ł������B���̂����̈�l�A�I�[�X�g�����A���痈���Ƃ�����҂Ɏ��͐q�˂��B�u����ȓ��A �ǂ�����Ă݂��܂������H�v�ƁB�u�X�͐l�ň�t������A���R�̒�����������Ǝv���ĕ����Ă��āA���R ���̓��������ĕ����Ă����v�Ƃ����Ԏ����Ԃ��Ă����B16:20�䂪�ƂɋA�������B����16968�B
2018.1.8

�V���o�V��
�ޗǂ̍����͍��N��Ԃ̊����ŁA���_�J�E�@�̔��ɂ͌����X���͂��Ă����B���̂悤�ȗ₦�����ɂ́A �ׂ��X���W�܂��ď��������グ��l�ȑ������o����B�q���̍��A���Z���`�����钷�������݂��� �V�L�����v���o�����B�䂪�Ƃ̒�ɂ́A�V�\�Ȃ̏h�������N���ł���V���o�V���Ƃ����A��������܂��B�H�ɔ����Ԃ�t���܂��B �s�͒f�ʂ��l�p�`�����Ă���A�͂��Ɩ؎������܂��B�悭�₦�����ɁA�͂ꂽ����������ƁA�s���� �X������o���A�������o���܂��B"�����͂��̑�����������̂ł͂Ȃ���"�Ɣ`���Ă݂�ƁA�����ȑ��� ���o���Ă��܂���(�E�̎ʐ^)�B �n���̍����ې��\�͂������Ă���A�эnj��ۂɂ�蓱�ǂ��o�Ēn���� �����オ���Ă��āA���ꂪ�͂ꂽ�s�̓r�����炵�ݏo�āA�O�C�ɂӂ�ē������́B
2018.1.8
�̂�т�Ɖ���
���Ȃ��u1��7���ɋՂ̔��\�����A���̌�A���s�ŏh������v�ƌ������B����ŁA������������ ���قɏh������v��𗧂Ă邱�Ƃɂ����B�����͏������m�ŗ��s�������悤�����A�j�F�B�� �u�ꏏ�ɗ��s���傤�v�ƌĂт�����Ɓu�Ȃ��A�Ȃ����Ƃ����Ȃ��́H�ƌ����v�ƌ����Ēf����B ���ɂ͈ꏏ�ɍs���Ă����悤�ȏ��F�B�͎c�O�Ȃ��炢�Ȃ��B�����ň�l���ƂȂ�B��l���ƂȂ�� �����̗��قŒf����B����ŁA�C���^�[�l�b�g��"�P�l�ł����܂�鉷��"�Ō��������B���̌��ʁA�L�n����ɏh���\�ȏh�������邱�Ƃ��o�����B�L�n����Ȃ��y�ŁA���̉Ƃ���d�Ԃ� ���p���ĂQ���Ԕ��]�ōs�����Ƃ��ł���B�i�b�v�U�b�N�ɒ��ւ��A���ʋ�A�P�Aipad�A�{(�Y���ꂽ���l: �J�Y�I�E�C�V�O����)�����A7��12:30�ߓS�ޗljw���̓d�Ԃɏ�����A15:00�\���L�n����̏h�ɒ������B
�������Ɖ���ɂ���"�̂�т�߂�����"�Ƃ̌v��ł���B�悸�A����ɂ���A�����ł������ƓǏ��B 17:30����[�H�B���Η����Ŏ����玟�ƃ^�C�~���O�悭�������o�Ă��Ĉ�l���ł��y���߂��B�H��x�e������A ����ɂ���A����ɁA22;00����ɂ�������A���B8��7:45�N���B9���ԗ]�������薰�����B����ɓ�������A 9:00��蒩�H�B10:00�`�F�b�N�A�E�g�B�L�n����͎�y�ŗǂ��B���ꂩ���"����ɂ����Ă̂�т�"������ �Ȃ�����"�L�n����I"�Ƃ������Ƃɂ��傤�B
�A�蓹�ŁA�_�ˎs�������قŊJ�Â���Ă���u�{�X�g�����p�ق̎���W�v�ɍs�����B�J�͗l�̓V�C���K�������̂��A ����قǍ��G���Ă��炸�A����Ȃ����Ă������ӏ܂��邱�Ƃ��o�����B�Ñ�G�W�v�g���p�A�������p�A���{���p�A �t�����X�G��A�A�����J�G��A�ʼn�E�ʐ^�A������p�ƕ����ēW�����Ă���A���i�����\���邱�Ƃ��ł����B
2018.1.1

2018�N���U
�V�N���߂łƂ��������܂��B���N����낵�����肢���܂��B���N�͋��ȂƎ��̓�l�����̐����ł���B���U�̂��G�ς�����A��N�̔@���A���w�ɏo���B �悸�A���_�ł��銿���_��(��������A593�N�n��)�ɎQ�q�B�����ŁA��������~���A �t����{�A�t����ЁA����R�_�ЁA���厛���̏��ŎQ�q���A�啧�a�ŊG�n�������������B �r���A���厛�@�ؓ��O�̒����ł��ǂ�ł��H�ׂ悤���Ǝv�������A�����ł������̂Œf�O���A �䂪�ƂɋA���Ēx�����H���Ƃ����B10���ɉƂ��o�āA�A�����14���ł������B����12000�B
�E�̎ʐ^�͍P��̉䂪�Ƃ̏��̊ԁB�Ԋ�͓��厛�啧�a�̌ÍށB�Ԃ�HK���B�|������"�́X":���� �i��Ȃ����� ������A������)�̃T�C���Ɨ�����A�S���Ȃ������`�ꂪ�D��ŏ����Ă����B ���鎞�A�`�����������p�ق̊w�|���ɊӒ肵�Ă��������ɍs���A"�U��"�ƌ����ċA���Ă����B ����ł��A�`��́u����ɂ͕i�i������v�Ƒ�ɂ��Ă����B
2017.12.30
�N������
2017�N���I��낤�Ƃ��Ă���B���A���̍ł��S�E�뜜���Ă�����͖k���N���A���q�͔��d�A ���@����(��)�ł���B�g�����v�č��哝�̗̂l��"�͂Ŗk���N�����������悤�Ƃ���"�̂͂ƂĂ��댯�ł���Ǝv���B�k���N��ICBM ������������O�ɕ��͂Œ@���ׂ����Ƃ����̂̓A�����J�̗���B���{�͂���Ȑ푈�ɂ܂����܂�Ă͂Ȃ�Ȃ��B ���Ĉ��ۏ�������A�č����k���N���U������A���{���Q��A�č���葽��Ȕ�Q����B ���͏Փ˂͉��Ƃ��Ă������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������"�b�����������Ȃ�"���Ƃ��̂ɖ����A�h�������E �S�苭���A�k���N�ɓ��������邵���Ȃ��̂��B���ق��E�E�E���܂苭�������"���l�L������"�B�K���{�� ������"�č��U���Ɍ�����������"��S���ׂ��Ǝv���B
���q�͔��d�͂��܂�ɂ��댯���B�j����ɂ��n��ɖ��������댯�Ȋj�p���������o���A���ł܂�10���N ��v����̂��B���̂悤�Ȋj�p�����͈��S�Ǘ����邱�Ƃ͕s�\�ł���B���q�͔��d���́A�푈�ɂȂ�Α��� �U���ڕW�ɂȂ肤��B�Đ��\�ȃG�l���M�[�̗��p�E�Z�p�J���ɗ͂𒍂����Ƃ���Ǝv���B
���@�����肵��"�������肵���R��������"�Ƃ����ӌ������邪�E�E�E����͋ɂ߂Ċ댯�ł���Ǝv���B ���Ĉ��ۂ���Ƃ��R�������ĂA�푈�Q���̉\�����i�i�Ƒ��傷��B�{���Ɏ��͂ŕ����E���q���悤�� ����A�j���킪�K�v�ɂȂ�B�ł��A�j����������Ă��A���{�͎��������Ő����Ă͂����Ȃ��B�����Ƃ� ���Ֆ����ł͐����Ă͂����Ȃ��̂��B����͗ǂ����Ƃ��Ǝv���B�����ƒ��ǂ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��B������E�E�E�A �����Ƃ����ǂ�����čs���˂Ȃ�Ȃ��B���@����(��)���A�����Ƃ̊W���P�ɗ͂𒍂����Ƃ������ ���͎v���B
���āA�����ɂ��ďq�ׂ�ƁA���A�l�ŁA���N��N���N�Ō��C�ɉ߂������Ă����������B���肪�������Ƃł���B �N���̑�|�����A���������ςB���ւ̔����T���h�y�[�p�[�Ŗ����A�`�a��h�����B�����A���A�����t����� �����̏��������ł���B���ӁE���ӁI�I�I
2017.12.18

�㉃�V���\
����12��17���ɂ�11:00����12:30�܂Ńe�j�X�X�N�[���Ńe�j�X�������B���̌�A16:00���䗷���ɍs���� �c�y(�ł�)�ƍגj(�����̂�)������q�ς��ċA����B12��18���ɂ́A��{�_�͊ҍK����ĕs�݂Ȃ̂����A�䗷���O�̕����13:00�����[���o�A14:00���� �㉃�V���\���Â����B����14:00����̎��\��q�ς����B����͖����ŁA����̑O�����ɍ��邱�Ƃ� �o�����B�ŏ��ɔ\"�H��"��������ꂽ(�E�̎ʐ^:�V�e�����E�A���L�����m�o)�B�����ŁA����"�_��" �V�e�ΎR��O�Y�A�A�h�ΎR�@�F�E�ԒJ�����B�����ŁA�\"�ԑm"�V�e���t�䍂�A���L�����a�K�Ƃ������� �����o�[�őf���炵�������B�K���V�C���ǂ��āA���\���y���ނ��Ƃ��o�����B���҂̔������f���炵�� �ǂ����������B�ہE�\�ǁE���ۂ̋������ǂ��A�\�y���ł͖��킦�Ȃ����̂ł������B
���t���͎��ɐl�ނ������Ă��đO�r�Ɋ�]�����Ă�Ǝv���B��X��"�������Ɣ\�y���ɍs���āA ����グ�Ȃ��Ă͂����Ȃ�"�Ǝv�����B
���Â��v���ɁA�ޗǂ�"����Ղ�"�͑f���炵���B���́A�����Ƒ����̐l���W�܂�Ȃ��̂ł��낤�H �������炩�H�H�H�D�D�D����̕��������E�ӏ܂��₷�����E�E�E�B
2017.12.15

��h����
�ޗǂ̍ő�̂��Ղ�"�t����{�����"��12��17���Ƀs�[�N�ƂȂ�A �J�K�̋V(�����̂��A�ߑO0��)�A�ō�(�����������A�ߑO1��)�A�{�a��(�ق�ł��A�ߑO9��)�A ���n�莮(���킽�肵��:�����s��A����)�A���̉���(�܂̂��������A�ߌ�1��)�A���n(�����A�ߌ�2��)�A �t�����L�n(������Ԃ��߁A�ߌ�2����)�A�ߌ�3�������10�������܂Ō䗷��(��{�_�̉���a)�Ő_�y(������)�E ���V(�����܂�����)�E�c�y(�ł�)�E�גj(�����̂�)�E���y(���邪��)�E���y(�Ԃ���)�E�a��(��܂Ƃ܂�) ����[����A�ҍK�̋V(�����̂��A�ߌ�11��)���s����B����ɐ旧���A12��15���ɁA�����ɂ����h��(�������キ����:�́A����ՂɎQ�����a�m�����Ղ� �旧���Ă����ɔ��܂肱�݁A���i���ւ������ꏊ)�ő�h���Ղ��s����B���̓s�A�m�����̌�ɁA �U�������˂đ�h���֍s�����B�O��ɂ͌䓒��(�傫�ȓ����ŁA���̓������Őg�ɂӂ肩���g�𐴂߂�)�� ����(���t���̏����Ɏ�{�_�ւ̕��Ƃ��Ă�賁A��E���̉��Њ������������Ă���:�E�̎ʐ^)���������B
���̑O��ŁA����҂ɖ����ŁA�̂����`(�卪�A�l�Q�A�S�{�E�A�����A���g���̓����������X�`)�� �ӂ�܂��Ă����B��������������������B�ǂ�Ԃ肢���ς��̔M�X�̂̂����`�͔������������B
2017.12.12
�c�O�~
���̕����̑��ۂɁA10�N���O�Ɏ��삵�����I������B���̓��I�̉��ɁA�����Ē�߂�p �ɂƁA��n�����B���̔��������A�A�ؔ�����ׂ��ɂȂ����B���̑�̏オ�S�n�悢�̂��A�����c�O�~������ė���B��̏�́A�c�O�~�̕��炵�����̂� �U�݂��Ă���B���̃c�O�~�͉䂪�Ƃ̒���e���g���[�ɂ��Ă��āA�T���V���E�A�T�l�J�Y�� �Ȃǂ̎�������A��̗��t���Ђ�����Ԃ��Ē���T�����肵�Ă���B
���̃c�O�~�A�K���X���z���Ɏ������Ă��A���R�Ƃ��Ă���B��������ȃs�A�m��e���Ă��A ��̏�ŐS�n�悳�����Ɏ����X���Ă���B��Ȓe���I����Č���Ƃ܂�����B���̓A���R�[���� �����čēx�e�����B�Ȃ�ƁE�E�E���荞��Ŏ����X���Ă����B�B��̎��̃t�@���ł���B
2017.12.10
�ޗǃ}���\��
���̉Ƃ̑O�̓���100m����ɍs���ƁA�����ɒʂ��铹������B���̓��𐼂�200m���s���� ���ې�ɉ˂��鋴"���ۋ�"������A��k�ɒʂ���L�����H"�₷�炬�̓�"�ƌ�������B ����"�₷�炬�̓�"��k��1.5km���i�ނƁA����"���r���㋣�Z��"������B "�ޗǃ}���\��"��"���r���㋣�Z��"���X�^�[�g�n�_�Ƃ�"�₷�炬�̓�"���ւƐi��� �s���B�A�H�ł�"�Ė�"����"���ۋ�"�ւƐi�݁A"���ۋ�"�ʼnE�܂��ăS�[��"���r���㋣�Z��" �i�ށB�����͂���"�ޗǃ}���\��"�̊J�Ó��ł���B9:00��"���r���㋣�Z��"�ʼnԉ��オ�����B ���̉����āA����"���ۋ�"�֑����čs�����B"���ۋ�"�܂�10m���̎��ɁA���o�C�� �擱���ꂽ�擪�W�c���ʂ�߂��čs�����B���̌�A���X�ƃ����i�[���������B�����l���� ����B�t���}���\���̎Q���҂�12000���A10km��ڂ̎Q���҂�4000���Ƃ̂��Ƃł������B �u�������Ȃ��B���C��Ȃ��B���̌��C�͎��ɂ͖����Ȃ��B�v�Ɛ��ɏo������A�ׂɂ��� �ߏ��̂�����u���炻����B�����̍A�l���Ă݂��v�ƌ���ꂽ�B
���C�ɑ����Ă���l������̂͊y�����B�t���}���\���ŃS�[���ԋ߂܂ł��ĕK���ɑ����Ă��� �l�����āA�v�킸����������Đ��������B�������ċA�H�ɂ��l�B�̊��"���ꐰ��"�Ƃ��Ă����B
2017.11.28

���̎U���� (1)�Ė傩��啧�a��
���͌��N�̂��߂P����8000���ȏ�������Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă���B����8000�����Ƃ����ƁA ���ɂƂ��ĒB�����Ղ�����ł���B�Ƃ���X�܂Ŕ������ɍs���ė���Ɩ�5000���E�E�E ����ł͏���������Ȃ��B�����lj������8000���ɂȂ�B��N�A�ŊԔw���j�A���� ���Ĉȗ�"�������Ƃ͂ƂĂ��C�����̗ǂ�"�Ɗ�����l�ɂȂ����B����A�U���ɏo�������ہA �ߏ��̂��͂�Ɂu�܂��U�����B�N�����R������āA�C�y�ł����́v�ƌ���ꂽ�B���̉Ƃ���100m����ɓ����ɒʂ��铹������B���̓쑤�͓ޗǏ��q��ł���B���̓��𓌂� 1km���i�ނƁA�Ė�(���厛�����ՁA�]�ˎ���ɏĂ��č��͑b�������c��)�Ɏ���B �����300m���i�ނƑ啧�a���Ɏ���B���̓r���Ŋς��i�F���E�̎ʐ^�ł���B���݂��� �g�t���Ĕ����������B
2017.11.18

�����R
�v���Ԃ�ɍ����R�ɓo�邱�Ƃɂ����B�����āA�������"���̏t�ɗ�������Ĕ������������������� ���i������Ŏ��i��H�ׂ邱��"���ړI�Ƃ����B11:00�ɍ����R�̑哻���ԏ�ɒ������B���J��������A�������������B���͖h���@�\�̂���Y�{�� �Ə㒅���o���Ē����B�o�R�C�𗚂��A��܂𒅗p���A�X�e�b�L��Ў�ɋC���������߂ēo�R���J�n �����B�����R�͂���܂ł�100��ȏ�o���Ă���̂ŏ���m�����R�ł���B����ł��A����ȂƂ���� �J�ɔG�ꂽ��A�����œ����Ă��܂��Ǝv�����B20���������ƓW�]���ɒ������B���������ƂɁA�������� ��͈�ʖ��X�ɕ����āA�X�͐^�����ł������B�J�͎~�݁A�_�Ԃ��������悤�ɂȂ����B ���x�~�̌�A�����40���������ƒ���ɒ������B�X�͖��X�ɕ����Ĕ����������B"�G�r�̂�����" �ƌĂ��A���ɗ�����閶���X�����A���������Ă�������ɉ��т����������`�ł���B���̓��ɁA ���������X���݂���Ƃ͗\�����Ă��Ȃ������̂ŁA�������ЂƂ����ł������B�E�̎ʐ^�͒��ォ�� �����k���̌i�F�ł���B����t�߂̖X�͖��X�ŕ����Ă��邪�A�����͍g�t�ł���B13:10�哻���� ��ɋA�������B
13:40�������̂��H�����u���݂�v�ɒ������B���i���Ǝv���Ă����͎̂��̎v�����݂ŁA���ǂ� ���j���[�ɂ������B�ł��A���i�̓��C���ł���A����"��ɂ���"�𒍕������B�ԏo�`�t����2160�~�B ���Ғʂ�������������B�ŋ߂�"�����������i��"�͏��Ȃ��Ȃ������A���̒l�i�ł��̔��������A ���͓X��ɐ[�����������āA�������ċA�H�ɂ����B
2017.11.17

�M�q�W����
���N���������̋��Ƃ��鏗�������R�̗M�q��Ղ����B�����A��������ŁA�M�q�W���� ���ɖv�������B�����̃��V�s��2015.11.10�̃u���O�Ɍf�ڂ������A���N�͍����̗ʂ� �M�q�̗ʂɑ��A�Q�F�T�̔䗦(�d��)�ɂ����B4kg�̗M�q����E�̎ʐ^�Ɏ��������̃W�������o�����B����ň�N�Ԗ����A�g�[�X�g�ɕt���� �H�ׂ鎖���ł���B�����]�T������̂ŁA�������ɂ�"�M�q��"�ɂ��Ċy���ނ��Ƃ��ł���B �쐬�ɂ����������Ԃ͌��Ԏ�B���������ɍ���Ă���̂ɋ��Ȃ͎�`�����Ƃ��邱�Ƃ��Ȃ� �u���ꂶ�Ⴀ�A��ɐQ���ˁv�Ɠ�K�֍s���Ă��܂����B
2017.11.12

���t�K�j
���N�����t�K�j�̃V�[�Y���ɂȂ����B����40�ˍ���"���t�K�j"�̖���m��Ȃ������B�L���o�g�� K���_�ˑ�w�̎��̌������ɂ��āA12����"�Ë��R�p�ɖʂ������h�ŊI��H����ꔑ���������s"�� �A��Ă����ĉ��������B�����A���͖��N"���t�K�j�𖡂키�ꔑ���s"������悤�ɂȂ����B�����{�ł͊I�ɂ��܂�S���Ȃ��Ǝv���܂����A���E�k���ł͊i�ʂł���Ǝv���܂��B����� "�I�͑N�x�����"�����炾�ƁA�ŋ߂ɂȂ��ĕ�����l�ɂȂ����B
���{�C���͐Ⴊ�~��B���̎Ԃ͓~�p�^�C����t���Ȃ��̂ŁA��̍~��O�ɍs���˂Ȃ�Ȃ��B �����āA�o����Ή���̂��闷�ق��ǂ��B����܂Ő���K�ꂽ���Ƃ̂����䉷��̗��قɓd�b������ ���b�L�[�Ȃ��Ƃ�11���̖邪�Ă����B���̏h��"���t���ɂ�����"�͏��X�l�i�����������������B �����N���Ƃ��Ă����̂�"���̓��������킦�Ȃ�"�ƁE�E�E�v�������ė\���B
11��9:45�ɉƂ��o����A13:30�ɒ��挧�����S�ɂ���O���R�O����(�݂Ƃ�����Ԃ�)�ɒ������B ���ԏ�e�̐H���ŋ���(500�~�A������������)��H�ׂ��B���X���J�̓V�C�ł��������A�g�t�������� �����B�ӂ��Ƃ���300m�̐Βi��o��ƎO�����{���ɒ������B���̎��̖ڋʂ́A�����Ȓf�R�Ɍ��� ������(�Ȃ�����ǂ��A����)�ł���B�{�����̓���C�s��t������W����200m�E�����Q���ԂƂ� ���Ƃł������̂ŁA���߂��B14:40�O�������ԏ���o�����A16:10��䉷��̏h�ɒ������B
�[�H��18:00����Ƃ��āA�悸�A����ɓ������B���̗��ق̉���͑f���炵���B�������Ă����܂� �����Z����[�����D�E�����V��݂̐����ǂ��B����ɕ~�������̐^������N����������̂܂ܗ��p�� �Ă���B������܂�Ƃ��������ł��邪�A���i����100%�j�B�N���o�����܂܂̐����Ȃ�Ȃ� ���A�V�N�ȏ�Ԃ̂܂܂ŗ��������Ă���u����|���������v�ł���B
"���t���ɂ�����"�͔������������B䥂ŃK�j�A���Ɏh���A�Ă��K�j�A���ɓ�E�G���܂ŁA�{���̏��t ���ɂ��ܖ������Ă����������B�܂��ɁA��i��"���t���ɂ�����"�ł������B���̔���������"�I�̗ǂ��E �V�N��"�Ɋ���Ǝv���B
12�� 7:00�N���B������A8:00��蒩�H(�����������������)�B9:00�`�F�b�N�A�E�g�B2009�N�ɏh���� ���ہA���̏h�̏������A��ɐ����Ă���"�}�C�d���\�E"���@��N�����ď����ĉ��������B���� "�}�C�d���\�E"�͉䂪�Ƃ̒�ŔɐB���Ă���B�ł��A���̏�������͐��N�O�ɑ��E���ꂽ�B���Ƃ��p���� �Ⴂ����������f�G�Ȑl��"�R�쑐�̏h"���p���ŁA���W�����Ă�����B�܂��A�߂������A�K�ꂽ�� �h�ł���B
�A�蓹�Łu�A�n�����A�����v�ɗ������A15:00�ޗǂ̎���ɋA�������B�E�̎ʐ^��䥂ŃK��B
2017.11.2
�ᑐ�R
�����͏H����ŐS�n�悢�����ł������B���H��A�O���ɍs������̙���̌�n���������B ���̌�"����ȍD�V�̓��ɂ͉Ƃɋ�����O�������"�ƎU���ɏo���B���厛�̓��֍s������A �Q�U��(�������̎��A�Q�U����m�����h������ꏊ)��"�̕����ܓW"������Ă����B�̐��� ���Ǝt�Ǝ����F�g���ŁA�J���t���ȕ���ł������B���ɔ�������m���������������B���� ��m���`���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł������B����グ�̈ꕔ�͓��厛�����È�a�@�Ɋ�t����Ƃ̂��� �ł��������A���͔���Ȃ������B�@�ؓ��A����R�_�Ђ�ʂ�A�ᑐ�R���ɏo���B�ᑐ�R�ɂ́A���B���q���̍��ɂ͉��x���̂ڂ������A �������N�̊ԓo���Ă��Ȃ��B"�ǂ��V�C�����v���Ԃ�ɓo�낤"�ƌ��ӂ��A���R��150�~�����B �����̕W����150m�A����̕W����342m�ł���B�ŋ߂͐l�C�������̂��A�l�e�͂܂�B�r���̒��X�� �R�J�E�R�[�����A30���قǂŒ���ɒ������B�ᑐ�R�����Łu�t�����R�V�����́A�䕗21���œ|�� ������A�ʍs�~�߂ł��v�ƌ���ꂽ���A"����m������������ʂ��Ă�낤"�ƌ��߂Ă����B�Ƃ��낪�A �t�����R�V�����̓�����ɋ߂Â�����A�x����������āu�t�����R�V�����́A�|��R���ꂪ����A �ʍs�~�߂ł��v�ƌ���ꂽ�B"���v�A�s����"�Ǝv���������d�˔j���邱�Ƃ��o�����A�����Ԃ����B
�v���Ԃ�Ɏᑐ�R�ɓo�����B�߂������A�̗͂������āA"�ᑐ�R�A�悭�o�ꂽ�Ȃ�"�Ǝv�����ׂ̈ɋL���B
2017.10.29
���s���������فu����v�W
���s���������قŊJ�Â���Ă���"�J��120���N�L�O ���ʓW����u����v"���ςɍs�����B 10�����܂ŗL���ȓ��ꌔ���������̂ƁA29���͑䕗22���̗��P�Œ�����J�ł������̂� �o�����čs�����B9:00�ߓS�ޗǔ��̓d�Ԃɏ��A10:00���s���������قɒ������B������ ���ƂɁA�J�̒��ł������s��B���ɓ��������ɂ�10:45�ł������B����200�_�����W�����Ă������B���̔������͔q�ς����������邪�A�M�d�Ȗ��i���낢�� ���������������B"�j�ϓV��"�ɂ͒��ւ̗�ŁA"���P�����ԓ� �� ����"�ɂ͌����l�͑a�� �E�E�E��`�Ƃ͋��낵���B����"�j�ϓV��"�̓p�X�����B���̓����A�P�ዾ�������čs������ �傢�ɖ𗧂����B
11:00�ɏo�ق����B�����w�߂��̂��X�Ń����`�Z�b�g"�ɂイ�˂ƈ銪"��H�ׂ��B�ɂイ�˂� �����Ă�������l�M���������������B�E�E�E�ŁA���́A�A�蓹��"����l�M"�����B
2017.10.28

���q�@�W
�{�N�̐��q�@�W�́A10��28���i�y�j�`11��13���i���j�ɓޗǍ��������قŊJ�Â����B�{���� �䕗22���̉e���ŁA�V�C�\��͉J�ł������B�ߑO9:10�A�J�͍~���Ă��Ȃ������B����"�������Ȃ� �Ă��邢�邾�낤"�Ɨ\�����āA�o�����čs�����B9:30�����قɒ�����"�҂�����30��"�ł������B���ق������A�ٓ��͂���قǍ��G���Ă��Ȃ������B���́A�O���ɓޗǍ��������ق̃z�[���y�[�W�� "��ȏo�i"�̉����ǂ݊��P�ዾ�������čs�����B����ŁA������ǂޕK�v���Ȃ��A�P�ዾ�� �����̋����̕����܂܂Ɋς邱�Ƃ��o�����B11:00�ɏo�ق������A���َ҂̍s��͖��������B
�A�蓹�ŋ������̓����E�����O�ɏo��ƃe���g����R�������B�߂Â��Č����"�ޗǃt�[�h�t�F�X�e�B�o��" ���J�Â���Ă����B��^�L�b�`���J�[�ŗL���V�F�t���r��U�邤�Ƃ���"Chef's Kitchen"�ɓ����āA �C�^���A�������`(1500�~)��H�ׂ��B���͂܂��܂��B����"�ޗǃt�[�h�t�F�X�e�B�o��"�͐��q�@�W�̊��Ԓ� �J�Â����l�ŁA"Chef's Kitchen"�̃V�F�t�͓��ւ��Ƃ̂��Ƃł������B
�����ŁA"�ޗǍH�|�t�F�X�e�B�o��"�̂����Ȃ��Ă���"�Ȃ�H�|��"�֍s�����B���̍����珬�J���~��o�����B �ƂɋA���āA���ȂɁu���т͐H�ׂĂ����v�ƌ�������A�u�ǂ����A�������낤�Ǝv���Ď����ς܂����v�ƌ������B
�E�̎ʐ^��"���Ԃ葐"
2017.10.19
���ʓW�u�^�c�v
�������������� �����قŁA�������������Č��L�O���ʓW�u�^�c�v��9��26������11��26���܂� �J�Â���Ă���B��v�ȓW�����͓ޗǂɂ�����̂Ȃ̂ŁA���͉�����q�ς������Ƃ�����B �������A�܂��q�ς������Ƃ̂Ȃ��É��E�萬�A�@�̔�����V�����A�a�̎R�E���������̔��哶�q�����A �_�ސ�E��y���̈���ɔ@�������E���e�������E�s�����������E������V�����A���m�E��R���� ���ω���F���������o�i����Ă���Ƃ̂��ƂŁA���͏o�����čs�����B7:56�ߓS�ޗljw���̓d�Ԃɏ������11:30�ɏ��w�ɒ������B�悸�A�������������ٓ��̃��X�g������ ���H(�V��)���Ƃ�A�����قɓ��ق����B���قɍs��͖����������A�W�����͓�����Ă����B �W���́A��1�� �^�c�n���[�N�c����^�c�ցA��2�� �^�c�̒����[���̓Ƒn���A ��3�� �^�c���̓W�J�[�^�c�̑��q�Ǝ��ӂ̕��t�A�ƕ��ʂ��Ă���A���҈ȏ�̈����ł������B �Ɩ����H�v���ēW�����Ă���A�g�߂Ɋ��ڍׂɔq�ς��邱�Ƃ��o�����B ���́A�P�ዾ�����Q�������A����͑�ϖ𗧂����B�B��A������F�����E���e��F���������́A������ �k�~���Ŕq�ς����ق����ǂ��Ǝv�����B
14:15�����o���B�{�قɓ����ĕ���W���q�ς���\��ł��������A�\�����������̂Ńp�X�����B 18.05�ߓS�ޗljw�ɋA�������B�ƂĂ��ґ�ȂP���ł������B
���N��4��8������6��4���܂œޗǍ��������قœ��ʓW�u���c�v������A���͔q�ς����B����A���ʓW�u�^�c�v ��q�ς��āA�u���c�v�Ɓu�^�c�v�ƈႢ���ǂ������ł����B��������̌Z��̗l�ȓ�l�ł��邪�A �u���c�v�͒[���Ŕ��������삵�`���I�ȕ��t�Ƃ��đ听�A�u�^�c�v�͓��̂�ǂ��ώ@�������Ƃ��Ă̗v�f ��������ĐV���n���J�������t���Ǝv���B
2017.10.15
�o��
 �ߔN�A�N��������������H�A���Ȃ��ւ܂����邱�Ƃ������Ȃ�A���{��ۂ����Ȃ����B
���Ȃ̎��������Ȃ����̂ŁA�傫�Ȑ��Řb���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ƁA���Ȃ�"�{��ꂽ"
�Ǝv���āA�������Ă���B����"�ȂI�{�P�₪���āI�������肹���ȁI"�Ǝv���ĕ�炵
�Ă����B"�`���b�g�������Ƃɂ������{��B���������ƂɂȂ���"�ƒ��߂Ă����B�E�E�E�E�E�E
�ߔN�A�N��������������H�A���Ȃ��ւ܂����邱�Ƃ������Ȃ�A���{��ۂ����Ȃ����B
���Ȃ̎��������Ȃ����̂ŁA�傫�Ȑ��Řb���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ƁA���Ȃ�"�{��ꂽ"
�Ǝv���āA�������Ă���B����"�ȂI�{�P�₪���āI�������肹���ȁI"�Ǝv���ĕ�炵
�Ă����B"�`���b�g�������Ƃɂ������{��B���������ƂɂȂ���"�ƒ��߂Ă����B�E�E�E�E�E�E�Ƃ��낪�E�E�E�ꂩ�����O�A���͊o�������B�u�{�P��̂����ʂȂE�E�E�Ɓv�A �u���ꂪ���ʂȂE�E�E�Ɓv�B����ƁA���Ȃ�����ڂ��قȂ��Ă����B����ɒ��߂���悤 �ɂȂ����B�����āA���͋C�y�ɂȂ����B
����ƁA���Ȃ̑ԓx���ς���Ă����B����"�ȂI�{�P�₪���āI�������肹���ȁI"�� �v���Ă���̂��A���Ȃ͖����̂����Ɋ����āC�����E�ْ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B "���Ȃ��C�y�ɂȂ���"�Ǝv���B
�ŋ߂ł́A���Ȃ��{���Ă��E�E�E�u���������E���������B�܂��A����Ȃɓ{��Ȃ��łˁv�� ������悤�ɂȂ����B�u���ꂪ���ʂȂE�E�E�v�Ǝv���A�������C�y�ɂȂ����B
�E�̎ʐ^�͍��G�z�g�g�M�X�B
2017.10.9
�䂪�Ƃ̑��z�����d: ���݂���P�N
�����̌������̂��_�@�ɉ䂪�Ƃł�2011�N5���ɑ��z�����d���u�������B�V���[�v���Z��p���z�d�r ���W���[��(ND-163AW: 1.165x0.990m)��18��(=20.8m2 �ő�o��2.934kW)��ݒu�����B��p��280���~�B �ݒu����T�N�o�߂������ʂ�2016.5.19�̃u���O�ɋL�ڂ����B���ʂ���A���z�����d�ʂ̐������������A �R�X�g�p�t�H�[�}���X�������Ȃ����Ƃ����������B���z�����d���u�������@�ɁA�䂪�Ƃł̓I�[���d���ɂ��A�䏊�̎ϐ����E���C�E�G�A�R���E�d�M��E ���g�[�E�d�C�@��ȂǁA�S�ēd�͂ł܂��Ȃ��Ă���B���d�����ŁA������d�̗͂������قڃJ�o�[�o�����B ������������d�͗ʂ̔������x�����A�䂪�Ƃ̑��z�����d���u�ł̓J�o�[�o���Ă��Ȃ������B �䂪�ƂŎg���d�͗ʂ̑S�Ă�₤���Ƃ̏o����l�ɂ������Ƒ��z�����d���u�ݒu��Ђɑ��k���A�V���ɁA �V���[�v���Z��p���z�d�r���W���[��(NU-215AE: 1.318x1.004m)��15��(=19.8m2 �ő�o��3.255kW)�ݒu�����B ��p��130���~�B5�N�O����p�͔������A���d���������P���Ă���l�ł���B�Ǝ҂ɂ��Ɓu���z�����d�� �d�͔��承�i�͉������Ă��Ă��邪�A���u�̉��i�������Ȃ��Ă���̂ŁA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͈����Ȃ� �Ă��Ȃ��v�Ƃ̂��Ƃł������B
2016�N9���ɑ��z�����d���u�݂��A1�N���o�߂����̂ŁA���̌��ʂ��܂Ƃ߂��B�����̌��ʂ�_�O���t �ɂ����B10,11,12����2016�N�̃f�[�^�ŁA1-9����2017�N�̃f�[�^�ł���B
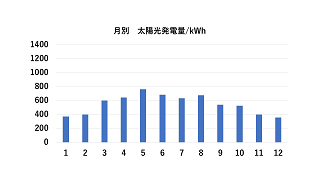 |
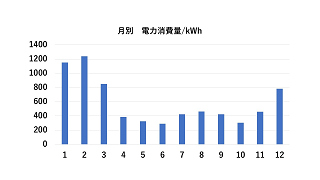 |
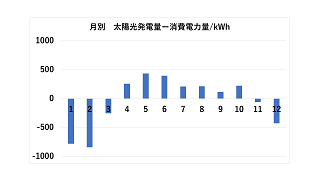 |
| �䂪�Ƃ̑��z�����d���u�̌��ʔ��d�� | �䂪�Ƃ̌��ʓd�͏���� | ���ʔ��d�ʂ��猎�ʓd�͏���ʂ��������� |
�̎Z�ʂ����Ă݂悤�B�֓d�ɔ������d�͂̌��ʋ��z�A�֓d���甃�����g�p�d�͂̌��ʗ����A �֓d�ɔ������d�͂̋��z����֓d���甃�����g�p�d�͂̋��z�����������ʋ��z�A���ꂼ���_�O���t �ɂ����B
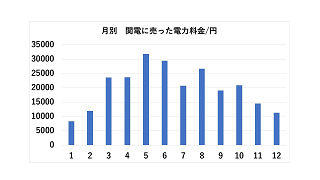 |
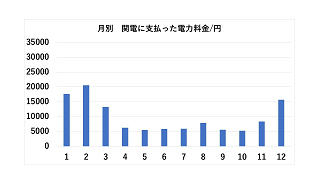 |
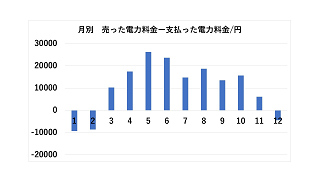 |
| �֓d�ɔ������d�͂̌��ʋ��z | �֓d���甃�����g�p�d�͂̌��ʋ��z | �������d�͗������甃�����d�͗��������������ʋ��z |
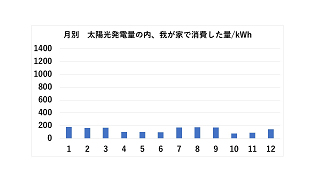 ���z�����d�̔��d�ʂ̓��A�䂪�Ƃŏ�����P�N�Ԃ̑��ʂ�1633kWh�ł������B����͔������ꍇ�̓d�͗�����
���Z�����241,968x(1633/6602)=59,850�~�ł���B���z�����d�̔��d�ʂ�S�Ċ֓d�ɔ��p����ƂP�N�Ԃ�
241,968+59,850=301,818�~�ɂȂ�B��������280+130=410���~���l�������15�N�ō̎Z���Ƃ��B
���z�����d�̔��d�ʂ̓��A�䂪�Ƃŏ�����P�N�Ԃ̑��ʂ�1633kWh�ł������B����͔������ꍇ�̓d�͗�����
���Z�����241,968x(1633/6602)=59,850�~�ł���B���z�����d�̔��d�ʂ�S�Ċ֓d�ɔ��p����ƂP�N�Ԃ�
241,968+59,850=301,818�~�ɂȂ�B��������280+130=410���~���l�������15�N�ō̎Z���Ƃ��B�V�z�̉Ƃ̉����ɑ��z�����d�V�X�e����ݒu����A��p�����Ȃ��čςށB�S�ẲƂɑ��z�����d�V�X�e���� �ݒu����A���q�͔��d���͕K�v�Ȃ��B�d�͂̈��苟���ɉΗ͔��d�����p����悢�B ���z�����d�V�X�e���̓����𐭕{�͏���E�������ׂ��Ǝv���B�����l���͂��������Ă����B
����̐V���ɂ��A���{�͕����̑�P-�R���q�F�̎g�p�ς݊j�R���u�[���ɂ���g�p�ς݊j�R���̏��� ���Ԃ�3�N��������(3�N�O��3�N�Ƃ��A����܂�3�N�Ƃ����B���ӂ̕��˔\�������A���o�����@���������� ���Ȃ��̂��B����ł�3�N��ɍčēx3�N�ƂȂ肩�˂Ȃ�)�B�n�Z�������q�F�̔p�F�ɂ͉��N�����邩�H �g�p�ς݊j�R����p�F�ɔ����j�������͏����̎d�l�������B �댯�ɂ܂�Ȃ����q�͔��d�͎~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
2017.10.1
�ޗǕX���_�З��
 �ޗǕX���_�Ђ̗��Ղ͖��N9��30���ɏ��{�A10��1�������6:30����[���̕��y���X���_�Е��a��
��[�����B����5:30�Ɂu�X���_�Ђɍs���Ă���v�Ƌ��Ȃɍ������B���Ȃ́u�Ȃɂ�����́H�A
�����s���v�ƌ������B6:10���X���_�Ђɂ����B�Q�����狫����"�P�ӂ�15cm���̗����̂̕X�Ɍ���
�āA���̒��Ƀ��[�\�N�𗧂Ă�����"����R���ׂĂ������B
�ޗǕX���_�Ђ̗��Ղ͖��N9��30���ɏ��{�A10��1�������6:30����[���̕��y���X���_�Е��a��
��[�����B����5:30�Ɂu�X���_�Ђɍs���Ă���v�Ƌ��Ȃɍ������B���Ȃ́u�Ȃɂ�����́H�A
�����s���v�ƌ������B6:10���X���_�Ђɂ����B�Q�����狫����"�P�ӂ�15cm���̗����̂̕X�Ɍ���
�āA���̒��Ƀ��[�\�N�𗧂Ă�����"����R���ׂĂ������B�u�P�l1000�~�̕�^�����ƕ��a�̋߂��ɂ���Ȃɂ�����v�Ƃ̂��ƂŁA2000�~�����ĐȂɒ������B �ŏ���"���V(�����܂�����)":�����N���̕����̕��E�������ォ��̐_�����B����[����A�����ŁA
"�U�g(�����)":����̎C���뉹���A���F�镑�A
"���Ίy(�܂��炭)":�P��������������c��̕��A
"����y(���炭)":����N�Ԃɍ��ꂽ���Ίy�ƈ�ƂȂ�c��̕��A
"��a(���Ă�)":�j��̕��A
"�o�V�y(�Ƃ��Ă�炭)":�؊G�����𒅂银���A
"���ˉ�(����傤����)":�V���ו����������A
"�[�]��(�Ȃ���)":���҂��������A
"����(�Ƃ�)":�e��ҏb�ɎE���ꂽ�q�����ҏb��T�����߂ĎE���Ƃ��������̕��ŁA�啧�J�ዟ�{�ʼn�����ꂽ�����ł���A
"���L(�炭����)":���҂�������
����[���ꂽ�B
����ŏI������B���傤��21:00�ł������B�e���y�̏��߂ɁA�_���ɂ�����������A�f�l�̎��ɂ��������₷�� �y���ނ��Ƃ��o�����B�_���ɂ��ƁA��s�ł̕��y�́A�ޗǕX���_�Ђ̐_�����]�ˎ���܂œ`���Ă��Ă���A�t����Ђ� ����Ղ�Ⓦ�厛���ł̕�[��S�����Ă����l�ł���B���݂͓�s�W�s��E��s�����y�`�����[�B ���͍���ŎO��ڂ̔q�ςł������B���Ȃ݂ɁA�ޗǂŐ��܂��������Ȃ́A���ŏ��̔q�ρB�ƂĂ��f���炵�����y��[�� �Ղ�Ȃ̂ɁA�w�ǒm���Ă��Ȃ��B �E�̎ʐ^�͖��Ίy�B
2017.9.29
�����R�n�C�L���O
 ���Ȃ̏]�Z�̍N����Â���������"9���̃n�C�L���O�@�����R(�W��586m)�Ɗ}������"�ɎQ��������
�����������B9:00JR���{�w�O�ɏW���B�Q���҂�8��(�j��2�A����6�A���ϔN��80?)�ł������B
�w�O�L��ŏ����̑���������A20���قǕ����ƒ��x��(824�N�ɏ~�a�V�c�̒���ōO�@��t���n���B
�{���͈���ɎO��(�d��))�ɒ������B�{������������ɋȂ���ƁA�����R�o�R���̕W�����������B
�͔|�������ꂽ�Ǝv����`�̖ؔ��̒��ɂ��铹��i�ނƁA��Ղ��I�o�����o�R���ɂȂ����B
���̓��͉J���~��Ɛ��H�ɂȂ���̂ł������B�Ƃ���ǂ���ɐΕ�������A�G�ؗт̒���i�ޓ��œ��A
�ɂȂ��Ă���A���K�ȓ��ł������B12:00�ɗ����R�R���ɒ������B����5.4km�A�W����506m�̓o�R�ŁA
���́u����҂̓o�R�ő��v���ȁv�Ǝv���Ă����̂����ǁA��������"������"�̃����o�[�ł���A
�S�����]�T�������Ē���ɒ������B
���Ȃ̏]�Z�̍N����Â���������"9���̃n�C�L���O�@�����R(�W��586m)�Ɗ}������"�ɎQ��������
�����������B9:00JR���{�w�O�ɏW���B�Q���҂�8��(�j��2�A����6�A���ϔN��80?)�ł������B
�w�O�L��ŏ����̑���������A20���قǕ����ƒ��x��(824�N�ɏ~�a�V�c�̒���ōO�@��t���n���B
�{���͈���ɎO��(�d��))�ɒ������B�{������������ɋȂ���ƁA�����R�o�R���̕W�����������B
�͔|�������ꂽ�Ǝv����`�̖ؔ��̒��ɂ��铹��i�ނƁA��Ղ��I�o�����o�R���ɂȂ����B
���̓��͉J���~��Ɛ��H�ɂȂ���̂ł������B�Ƃ���ǂ���ɐΕ�������A�G�ؗт̒���i�ޓ��œ��A
�ɂȂ��Ă���A���K�ȓ��ł������B12:00�ɗ����R�R���ɒ������B����5.4km�A�W����506m�̓o�R�ŁA
���́u����҂̓o�R�ő��v���ȁv�Ǝv���Ă����̂����ǁA��������"������"�̃����o�[�ł���A
�S�����]�T�������Ē���ɒ������B����́A�����ɏ\�s���̎R�邪���������ŁA��a�O�R�A�����E����E ����R����]�ł����B���̒���Œ��H�B13:00�������ɂ����B����2km�A�W����100m�̊ɂ₩�ȎR���� �����14:10"�}������"�ɒ������B���͂��鋼��(540�~)��H�ׂ��B15:00"�}������"����^�N�V�[�ɏ�� JR�����w�Ɉړ��B�����ʼn��U�B�S���A���C�Ŋy�����n�C�L���O�ł������B
�E�̎ʐ^�͎R���t�߂ɍ炢�Ă������}�W�m�z�g�g�M�X�B
2017.9.21
�с@�v������
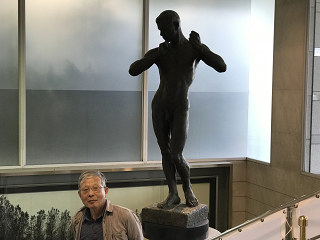 �с@�v������͒����ԁA�����w�������̎�C�������߂�����"���w�����ɑ���O������̉e��
�Ɋւ��錤��"�̑��l�҂ł���B�с@�v������Ǝ��͓����N�ŁA���͌�������A�с@�v������Ɛe
���������E���_���Ē������B
�с@�v������͒����ԁA�����w�������̎�C�������߂�����"���w�����ɑ���O������̉e��
�Ɋւ��錤��"�̑��l�҂ł���B�с@�v������Ǝ��͓����N�ŁA���͌�������A�с@�v������Ɛe
���������E���_���Ē������B���̗ыv�����A�X���ɑ��ɏZ�ޖ�����̎�`��(���̖ʓ|�H)�ׁ̈A���ɗ����邱�Ƃ�m�����B ����ŁA���͗ыv������Ɂu�������Ԃ��Ƃ��Ȃ琥��������v�Ƃ��肢�����B�������� �u9��21���Ȃ�s�����ǂ��v�Ƃ̘A�����������B����ŁA21��11����JR���s�w�ő҂����킹���B ��N�ސE�ȗ�������Ă��Ȃ��̂ŏ����S�z�ł��������A�̂̂܂܂̎p�������Ĉ��S�����B �ыv������́u�����̎ʐ^���B�邱�Ƃ���ɂ��Ă���̂ŁA�����ّ�w�̈ߊ}�Z�ɂ֍s���āA "�킾�ݑ�"��"���b�`������"�̎ʐ^���B�e�������v�Ƃ�����������B����ŁA�n���S�ƃo�X�����p���� �ߊ}�Z�ɂ֍s�����B"�A�J�f���C�A����21"�Ƃ����������ɂ����̑���������(�E�̎ʐ^��"�킾�ݑ�"�� ���̘e�ɗ��ыv������)�B�����Łu�߂��ɖ���L�O�ق����邩�炻���ɍs�����v�Ƃ�����������B ����L�O�ٓ���"���씎���_�����̓���"�������Ċ��X�Ƃ��Ďʐ^���B���Ă���ꂽ�B
���H��A���́u���������V�t���p�قŗՍϑT�t1150�N�E���B�T�t250�N��恋L�O�̑T�є��p�W���J����Ă��� ����s���܂��傤�v�Ɛ擱���čs�����B�Ƃ��낪�A�ٓ��ō����"���w�c���n��"�A"���B�T�t�̎O�c�t�}"���� �O�ɂ��Ă����̋�����������Ȃ��B�u���͖V����͌������B�`���v���J���v���̂��Ƃ������Ĉ̂����ɂ��Ă���B ���ꂾ���ĉ��̂��Ƃ��������ς�킩���v�Ƃ�����������B
������A�����Ȏ���b�����B�y��������ł������B"���N�ɉ߂����āA�ĉ�o���邱�Ƃ��I" �ƐɊ肤���肠��B �@�@�@ �@�@�@�@�@
2017.9.19
��R�鑺�K��
 ���N�U���U����"���w����������N�̉����"�ʼn�������Ԃ̈�l�s����N�ސE��A��R�鑺�̌Ö��Ƃ�
�����Ĉڂ�Z��ŋ����邱�Ƃ�m�����B���̉Ƃ���Ԃňꎞ�Ԓ��̏��Ȃ̂Łu���K�˂��������v�Ƃ�
���ē������B�������p���t���b�g�ɂ��ƁA�ނ̍N�͑���Gallery Den ���J�݂��Ă���������
�����A�ނ̈ڏZ�ɔ����A��R�鑺�̌Ö��Ƃ̈ꕔ��Gallery Den mym�Ƃ���Ƌ��ɁA�߂��Ɂ@Artist In Residence"����"
���J�݂��Ă����邱�Ƃ�m�����B����ɁA�z�[���y�[�W��9��17��-9��30���ɖk��K�i����ƒ����߂��݂���
�̌W���J�Â���A9��17���ɂ̓I�[�v�j���O�C�x���g�����邱�Ƃ�m�����B
���N�U���U����"���w����������N�̉����"�ʼn�������Ԃ̈�l�s����N�ސE��A��R�鑺�̌Ö��Ƃ�
�����Ĉڂ�Z��ŋ����邱�Ƃ�m�����B���̉Ƃ���Ԃňꎞ�Ԓ��̏��Ȃ̂Łu���K�˂��������v�Ƃ�
���ē������B�������p���t���b�g�ɂ��ƁA�ނ̍N�͑���Gallery Den ���J�݂��Ă���������
�����A�ނ̈ڏZ�ɔ����A��R�鑺�̌Ö��Ƃ̈ꕔ��Gallery Den mym�Ƃ���Ƌ��ɁA�߂��Ɂ@Artist In Residence"����"
���J�݂��Ă����邱�Ƃ�m�����B����ɁA�z�[���y�[�W��9��17��-9��30���ɖk��K�i����ƒ����߂��݂���
�̌W���J�Â���A9��17���ɂ̓I�[�v�j���O�C�x���g�����邱�Ƃ�m�����B���Ƌ��s�ɏZ��"���w����������N�̉����"�̒��ԂQ�l�ɌĂт����āA�ꏏ��Gallery Den mym��17���� �K�₷�邱�Ƃɂ����B17���͑䕗�̂��߉����B18��10:10�ɋߓS�ޗljw�O�ɏW���A���̎Ԃɓ��悵�ďo�����čs�����B �v���Ă������߂��A45�����œ�R�鑺�̌Ö��Ƃɒ������B�z130�N�Ƃ����Êi�̂��闧�h�Ȍ����ł������B ���i�͐��Ƃɒ����đՂ������A�y�ǂ܂Ŏ����œh�����Ƃ���������Ă����B����"�q���̍��Ɋς��_��"���������� �v���o�����B�����w�����������Ă����s���A���R�L���ȎR���Ɉڂ�Z�݁A�n��̐l�B�ƒ��ǂ��_��Ƃ�����Ƃ��� ���̐l�����y����ŋ�����̂ɂ͊��������B
�s����̍N�����݂̐l�ł͂Ȃ������B���̉ߑa�̒n�ŁA�Ⴂ�|�p�Ƃ���Ă銈�������Ă���ꂽ�B�Ö��Ƃ̈�p Gallery Den mym��"��i�W��"���邾���łȂ��A�߂��ɁAArtist In Residence"����"��ݗ����A��i�̐���E���\�E�ӏ� �̏������Ă���ꂽ�B
��ϊy��������ł������B���ԂƂ̉�b���y���������B16:30��R�鑺�ɕʂ���������B
�E�̎ʐ^�̓X�~�i�K�V (�Ö��Ƃ̒�ł̃e�B�[�^�C���ɁA�ڂ̑O�̃e�[�u���ɔ��A�e�[�u����̍����`?��I�R���r�߂Ă���)�B
2017.9.17
�f��u�݂���̋u�v
 NPO�@�l�ޗǍ��ۉf��Վ��s�ψ����Ẩf���f���ޗǏ��q��w�u���ōs���邱�Ƃ��A�u���O��
�ʂ����ہA���ĊŔ����Ēm�����B������ǂ�ŁA�ʔ������������̂ŁA���̉f����ςɍs�����B
NPO�@�l�ޗǍ��ۉf��Վ��s�ψ����Ẩf���f���ޗǏ��q��w�u���ōs���邱�Ƃ��A�u���O��
�ʂ����ہA���ĊŔ����Ēm�����B������ǂ�ŁA�ʔ������������̂ŁA���̉f����ςɍs�����B�f��̑�ڂ́u�݂���̋u�v�ē�:�U�U�E�E���V���[�A���썑:�G�X�g�j�A�E�W���[�W�A�A2013�N��i�B ���̉f��̔w�i�Ƃ��āA�����m��������
1). �W���[�W�A�i�O���W�A�j��1991�N�Ƀ\�A����Ɨ���錾�B1992�N�ɃA�u�n�W�A���W���[�W�A����̓Ɨ��� ���߂����Ƃ��畐�͓������u���B���ۓI�ɂ͓Ɨ���F�߂��Ă��Ȃ����A2008�N���V�A�̓A�u�n�W�A���a���� ���F���A������Ɨ���Ԃɂ���B
2). �W���[�W�A��19���I�Ƀ��V�A�鍑�ɕ������ꂽ�ہA���V�A�ɓG�����Z���̑���������ǂ��A���̑� ���ɃG�X�g�j�A�l���ڂ�Z�W�����A�u�n�W�A�ɂ������B
���̉f��́A�݂���͔|������G�X�g�j�A�l�̏W��������B�W���[�W�A�ƃA�u�n�W�A�Ԃɕ������u�����A �����̃G�X�g�j�A�l�̓G�X�g�j�A�ɋA���������A�݂���̖ؔ����̃C���H�Ƃ݂���_�Ƃ̃}���K�X�Ƃ͎c ���Ă���B������A�ނ�͐퓬�ŏ�������l�̕��m���C���H��ʼn�����邱�ƂɂȂ�B�ЂƂ�̓A�u�n�W�A�� �x������`�F�`�F�����A�n���h�A�����ЂƂ�̓W���[�W�A���j�J�œG���m�������B �ނ�݂͌��ɓ����ƂɓG�������邱�Ƃ�m���āA�E�ӂɔR���邪�A�C���H�̂Ƃ�Ȃ��Ɛl�Ԑ��ɂӂ�A����� ����𗝉��E�F�ߍ����l�ɕω����Ă����B�E�E�E��������A�A�u�n�W�A��������x�����郍�V�A�̏���������� ���āE�E�E�E�E�E�B
�푈�̕s�𗝂Ɛl�Ԑ��̑����B"���E����@�I�ȏ̂Ȃ��ŁA�l�Ԃ炵����ۂ��Ƃ̑��" ����点��f��ł������B
����"�k���N�͂Œ@���ׂ���"�Ȃǂƍl���Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B���䌧�̌��q�͔��d�������P�b�g�U�� �����A���n���͏Z�߂Ȃ��Ȃ�ł��傤�B���̒n�������l�ł��B�푈���n�߂�A�k���N�ɏZ�ޑ����̐l�X�A ���{�ɏZ�ޑ����̐l�X�A���̑��̍��X�ɏZ�ނ̑����̐l�X���n���ɗ����܂��B"�b�������������͖���"�Ǝv���܂��B
2017.9.7
���H
 �X���ɂȂ��ēޗǂł͒��[���������Ȃ�܂����B���Ԃ͂܂�������������܂����A���Ƃ����N�̉Ă�
���z���邱�Ƃ��o�����E�E�E�Ǝv����悤�ɂȂ�܂����B
�X���ɂȂ��ēޗǂł͒��[���������Ȃ�܂����B���Ԃ͂܂�������������܂����A���Ƃ����N�̉Ă�
���z���邱�Ƃ��o�����E�E�E�Ǝv����悤�ɂȂ�܂����B9��4���͎��̒a�����ŁA��76�˂ɂȂ�܂����B����Ƃ��������S������܂��A���C�Ŋy�������X �𑗂点�Ă��������Ă��邱�Ƃ͗L����Ƃ�"���ӁE����"�ł��B
���̕����ɂ͖����������w���̎��ɍw�������s�A�m������A��Â�ɓ��w��e���Ă��܂��B����� ��B���܂���"����̉��D��"�Ƃ͗ǂ����������̂ŁA��l�y����ł��܂��B
���̕����̃\�t�@�[�ɍ���A���C�ɓ���̒���ŁA�̂�т�A������������T��A�e�����\���� �Ă����"�K��"�������܂��B�����̓쑤�͏Ɏq�˂ŁA10�N���O�Ɏ��삵�����I������܂��B���̓��� �����傫���Ȃ�A���N�t�ɂ�100�{�ȏ�̓��̉Ԃ����ꉺ����܂��B���̓��̉Ԃɕt������(��)�𐔖{ �炸�Ɏc���Ă�������A���ł͐����傫���Ȃ��āA���ɐ�����Ă����Ɨh��Ă��܂��B ���ꂪ�܂�"�Ȃ��Ȃ��̕���"�ł���܂��B
����H�̌i�F�ɂȂ��Ă��܂����B�ᖒ�g�A�j�[�A���Y�ԁA���q�A�����炢�Ă��܂��B���Ȃ��u����Ďז��v �ƌ����Đ������̎}���A���͏E���Ă��āA�ԕr�ɑ}�����B
�E�̎ʐ^�̓��n�W�L�̉ԁB
���t�W�Ɂu�킪��ǂɁ@���ӂ�y�j(���n�W�L)�@���������@������ʂЂƂ́@������ɂ����ȁv�Ɠǂ܂�Ă��܂��B
2017.8.31
�����q�K
��N�A�ŊԔw���j�A�œ��@�E�×{�������A������@��ɓd�q�}���ʼnĖڟ��̍�i���ēǂ��A �قڑS��i��ǂ܂��Ă����������B�ŋ߂͐����q�K�̍�i��d�q�}���œǂ܂��Ă��������Ă���B �����q�K�����]���|����a�̋ꂵ�݂̒��ŁA�D�ꂽ���q���c���Ă���̂ɂ́A�B�X���S�E���h����B����܂łɔq�ǂ����̂́A�u�n�`��H�v�A�u�a�v�A�u�aଘZ�ځv�B�ŋ߁A�q�ǂ��Ă���̂́u�aଋ��v�B �����q�K�𗝉�����ɂ͐悸�A�ނ�"�a"�𗝉����Ă���E�E�E�Ǝv���ēǂݎn�߂��̂�����ǁA ����"�a"���s��Ȓ��ŁA�D�ꂽ���M���R�₵�Ă�����B�e�����F�l�E��q�ɑ��Ă�"���݂̂Ȃ� �ӌ��E�ᔻ"�����Ă�����B�E�E�E���ꂪ�܂�"�F�l�E���l�E���Ȃ̍��g"�Ɍq�������Ǝv���܂��B �E�E�E"����͖{��"�Ɗ����܂����B�܂����ǂ̐����q�K�̓d�q�}����30���قǂ���܂��B�y���݂ɂ��Ă��܂��B
(��)�@�����̓d�q�}���͑S�Ė����Ń_�E�����[�h�ł��܂��B
2017.8.21
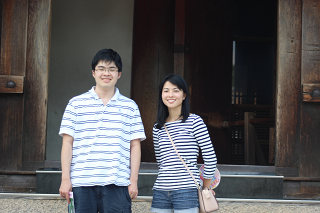
�����̎q���B�̗��K
8��13���ɒ����̎q���B:���j(��q��w�R�N��)�ƒ���(���̂X���ɕč����V���g����w�ɓ��w)���ޗǂ� ���Ă��ꂽ�B�{��8��21��"�ޗǂɂ����̂�����E�E�E"�Ƌ��Ȃ��܂߂ĂS�l��"�@����"�֍s�����Ƃɂ����B"�@����"�ɂ� �u�����������X�g�����͖��������v�ƌ����̂ŁA�u��a�S�R�̃C�^���A�����X�g������12:00�ɗ\��v���� �o�����čs�����B�Ԃ̉^�]�́A�����̒��j�������B�ޗǂɗ��Ĉȗ�"�Ԃ̉^�]���K"�����Ă����̂ŁA�^�]�� �]�T�������ďo����l�ɂȂ����B�\���C�^���A�����X�g�����̓s�U�����蕨�̓X�Ȃ̂ŁA�s�U�ƃp�X�^ ���Q�l�O��������4�l�ŕ����ĐH�ׂ��B
�@�����ɒ��������ɂ͉����ł���Ƃ�̉ċ�ł������B������������"���@�����̒��傪�C����"�� �傫�ȕ������������B�u�C������������͕̂���30�N�x�v�Ƃ̂��Ƃł������B�Y���̐m�����͔q�Ϗo���Ȃ� �������A�����A�d���A�u���͂����ʂ�ɔq�Ϗo�����B�d���̎l�ʂ̑Y����q�ς�����A������q�ς� ���B��(���P)����̎����q�ς����Ă���������"�ǂ������ꂾ���̕����ۑ�����Ă���"�Ɖ�������l�B �̓w�͂Ɋ��ӂ����ɂ͂����Ȃ��B
�����ŁA�������q���J���Ă��鐹��@�A�Z�ω��E����ω��E�S�ϊω����̂����@��q�ς��A����� (����Ɠ��厛�̓]�Q�傪��������ޗǎ���̎O�����̖�)��ʂ��āA�������ϐ��̎�ꂽ���a��q�ς����B �������������璆�{���ɂ��s���Ĕ���v�҂̔������@�ӗ֊ω���q�ς����B���͂��̕��l��q�ς��閈�� " ���w�̏C�w���s�̎��A�܂��{�a���J���Ă���ꂽ���̑����ԋ߂ɔq�ς���������"���Ƃ��v���o���B
�E�̎ʐ^�́A�@���������̓�����ɗ������̎q���B�B
2017.8.10
�C�^�����A���v�X
���[���b�p�A���v�X��������́A����܂łɃX�C�X:Interlarken, Les Diablerets, Zematt, Grindelwald, �t�����X:Chamonix, �I�[�X�g���A:Innsbruck�EHeiligenblut�ɑ؍݂��Ċy����ł����B�c��̓C�^���A�� ����B���N�g�ɂ͏��Ă��̗͂������Ă����B"���łȂ��Ă͂����s���Ȃ��Ȃ�"�Ǝv���A�C�^�����A���v�X ������v��𗧂Ă��B���Ȃ͏a���Ă������A�����u�P�l�ł��s���v�Ɛ錾������A�a�X�u���s����v�ƌ������B���̓��s�҂�"�ʐ^��"�ł���B�i�F���ς���A�������ʐ^�ɎB������悢������B�R�ɓ��s���āA���Ȃ��Ԃ� �ʐ^���B����"�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ�"�̂ɃC���C�����āA�u����Ȃ炢�����A�����ʐ^���B�낤�v�Ǝ����Ԃ̎ʐ^�� �B��悤�ɂȂ����B�E�E�E�����"����ɉԂɊS��"�悤�ɂȂ�A��R������Ƃ��̊y���݂���������B
���͍q�A�z�e���A�o�X�̐ؕ����A�S�ăC���^�[�l�b�g�ŗ\���B�֗��ɂȂ������̂ł���B
�C�^�����A���v�X�Ȃ�A�����u�����ƃ}�b�^�[�z�������C�^���������璭�߂��鏊�ƌ��߂Ă����B���s�� ���Q�l�ɂ��āA��-�~���m(2��)-�N�[���}�C���[��(4��)-�`�F�����B�j�A(3��)-�~���m(2��)-��(�@��1��) �Ƃ����B������"���{�̍ł�������"�Ƃ���̂��P��ł���B
7��27��(��) 6�F00�ߓS�ޗljw�O���̃o�X�ɏ��7:30�B10:10��LH741��15:20�t�����N�t���g���B 17:10�t�����N�t���g����LH254��18:20�~���m��`�ɓ����B�t�����N�t���g�ł͉J���~���Ă����̂Ƀ~���m�� �����A�C��27���B�o�X�Ń~���m�����w�܂ōs���A�o�X�₩��300m�������ăz�e���ɓ����B�ו���u���Ē����w �̒n���ɂ���X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ŕ����B�ʕ��A�����A�p���A�n����H�ׁA������A23:00�A���B����4978�B
 |
 |
 |
| �~���m�����w | Duomo�吹�� | Duomo�̉��� |
 |
 |
 |
| �����u�����R观̐} | Entreves�����猩�������u�����R� | Mont Blanc de Courmayeur(4751m) |
 |
 |
 |
| �����u�����R观�]�� | Dent du Grant(4014m) | �O�����h�E�W�����X(4203m)�͉E�[ |
7��30��(��) 6:00�N���B�����B''�����u�����̒�����ς���''��2km�ق�Dora Baltea��̏㗬�̕��֕����čs�����B ����炵�����̂͌����������_������A�S�e�͔q�ςł��Ȃ������B8:30�z�e���ɋA���Ē��H�B9:30�z�e������1km �قǂ̂Ƃ���ɂ���inf(�C���z���[�V�����Z���^�[)�ɍs���A�F�X�̏�����A�P�[�u���J�[�ƃ��t�g�����p ����Col Checouit(1952m)�ɍs�����B�R�����̃I�[�v���e���X�ŋ��y�����̒��H��ۂ����B���̍����瓯�s�҂Ɍ��C�� �����u�C�������������ɂ��v�ƌ������B��ςȂ��ƂɂȂ����ƁE�E�E15:00�z�e���ɋA�������B19:30-21:00�[�H�B 22:00�A���B����13619�B�C��25-15���B
 |
 |
 |
| Scabiosa lucida�ɗ��܂�Lysandra albicans | Colchicum alpinum | Col Checouit�̎R���� |
7�N31��(��) 6:00�N���B���s�҂̑̒����K���ɂ��ĉ��P�B���H��A8:49�z�e���O�Ń����u�����E���[�v�E�F�C (Skyway)����Pontal(1300m)�s���̃o�X�ɏ��9:00�ɓ��������B���[�v�E�F�C��Pavillon du Mont Frety(2173m) �ɍs�����B���̏㕔�̉w�͉_�̒��ł������B�Ԑ��𐮂�����A�g���b�L���O�H���C�܂܂ɁA���R�A���̎ʐ^���B��A �Y��Ȍi�F���y���݂Ȃ���U���B15:00�܂ŔS�������A�c�O�Ȃ���Monte Bianco(�����u���� 4810m)���ς邱�� ���o���Ȃ������BSkyway����Pontal��������ăz�e����16:30�A�������B19:30-21:00�[�H�B21:30�A���B����7660�B �C��25-15���B
 |
 |
 |
| Pavillon du Mont Frety����̃g���b�L���O�H | Achillea millefolium�ɂƂ܂�Lycaena disper | Arnica montana�ɂƂ܂�Fabriciana adippe |
8��1��(��) 6:00�N���B�����B�u����Ă���ԂɃ����u�����߂悤�v�ƁA���H��H�ׂ��A7:14�z�e���O����H���o�X �ɏ��AEntreves���̃o�X��ō~��A500m�قǕ�����7:25Skyway����ɒ������B����̓��[�v�E�F�C�����p���ŁA Punta Helbrocner(3466m)�ɍs�����B�L���W�]��ɁA���̎��ɂ͎��B�������Ȃ������B�����ŁA360�x�̓W�]�ŁA �O�����h�W�����X�A�}�b�^�[�z�������̖�����ς邱�Ƃ��o�������A�̐S�̃����u�����͉_�̒��E�E�E ���X�A��������ӂ��`�����Ă���邾���ł������B11:00�܂ŁA�����ɓ����Ȃ���E�E�E�R�e�������Ă����̂� �҂������ʖڂł������B���̌�Punta Helbrocner�W�]����̃��X�g�����Œ��H��H�ׂȂ���҂������A����ɉ_�� �����Ă��Ď��E�������Ȃ����̂ŁA�O���ɍ~�肽Pavillon du Mont Frety�ɍs���A�g���b�L���O���J�n�����B�r���ɁA �X�͂���̐��������삪����''�n��̂͊댯''�Ǝv��ꂽ�̂ň����Ԃ����B�J�~�i������A�J���~�肾�����̂ŁA �}���Ń��[�v�E�F�C����Pavillon du Mont Frety�ֈ����Ԃ����B���[�}���ォ��̓`��������������Â��W��Entreves�� �̃o�X�₩��o�X�ɏ��z�e����15:20�ɋA�������B19:30-21:00�[�H�B22:00�A���B����11094�B�C��25-5���B
 |
 |
 |
| �W�]�䂩��ς��@�O�����h�E�W�����X�R�� | �ጴ�ɓo�R�҂������� | �����u�����R�� |
8��2��(��) ���̓��́A�}�b�^�[�z����(Matterhorn, �C�^�����ł�Cervino, 4477m)�̘[�̒�Breuil-Cervinia(�`�F���r�j�A) �Ɉړ�������ł���B 6:00�N���B6:30�����u�����̒��オ������̂����҂��āA2km�قǕ����čs�����B�������A �c�O�Ȃ���ς邱�Ƃ͂��ł��Ȃ������B7:45�Ƀz�e���ɋA�������B���H���ς܂���8:45�`�F�b�N�A�E�g�B�z�e���̎Ԃ� �N�[���}�C���[���̃o�X��܂ő����Ă����������B�o�X��œ��{�l�̂��v�Ȃɑ������B�u�������N�A���āA���̂�����̂�K��Ă���v �Ƃ���������Ă����B 9:35Courmyeur pmb���̃o�X�ɏ��AAosta�AChatillon�ŏ�芷���A 12:25��Breuil-Cervinia(�W��2012m)�ɒ������B12:30�z�e���Ƀ`�F�b�N�C���B�����Ɉē�����āA���͏���肵���B�����̑��̐��ʂ� �}�b�^�[�z�������ނ��Ă����B���̃z�e����12�������̂�����܂��mounten chalet�ł��������A1865�N7��17���� �C�^���A������}�b�^�[�z�����ɏ��o������Abbe Ame Gorret���A���̍ۏh�������Ƃ����`������z�e���ł������B 13:00�s���̃��X�g�����Œ��H�B14:00�C���t�H���[�V�����ɍs���A�n�}�����B17:00����U��ɏo����Cror de Paret(2300m) �̏�܂ōs���Ĉ����Ԃ����B19:00�X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ŕ��������āA����ŗ[�H�B22:00�A���B����15945�B�C��23-15���B
 |
 |
 |
| Breuil-Cervinia�̃o�X�� | Cror de Paret�ɂ� | �z�e���̕������猩���}�b�^�[�z���� |
8��3��(��) 7:00�N���B�����ł��邪�}�b�^�[�z�����̎R��͉_�ɕ����Ă����B8:00���H�B9:00���[�v�E�F�C�� Plan Maison(2550m), Lago Cime Bianebe(2982m)���o��Platau Rosa(3480m)�֍s�����B�W�]�͗ǂ��� �}�b�^�[�z�����̎R��͉_�ɕ����Ă����B�X�͂ŃX�L�[������l�B����R����ꂪ�A���������E�����E�C�����Ⴍ �C�����ǂ��Ȃ��̂ŁA20���قǑ؍݂����ネ�[�v�E�F�C��Lago Cime Bianebe�ւƈړ������B�w�̋߂����U�A ��k�̋߂���Picnic lanch���Ƃ����B���s�҂������ċC���������Ƃ����̂ŁA60���قǎU����P�[�u���J�[�� Plan Maison�ւƈړ������B
�S���h���̒��ŁA�������[�v��������痂���10�l���̈�c�Ƒ��������B�S��������"�R�x�~����"�̃}�[�N��t���� ����ꂽ�B�u�ʐ^���B���Ă���낵�����v�Ɛu�˂���A�|�[�Y���Ƃ��ĉ��������B�u�P���ɗ��܂����v�Ƃ̂��Ƃ� �������B
Plan Maison(2550m)�͒g�����A��R�̍��R�A���̂��Ԕ����Ԑ���ł������̂ŁA���s�҂̋C�����ǂ��Ȃ�A �g���b�L���O���y���B�r���ŃC�^���A�l�̘V�v�Ȃɑ������B���B���Ԃ̎ʐ^���B���Ă���ƁA���̉Ԃ̖� (�C�^������)��S�������ĉ��������B�uNO English�v�Ƃ���������Ă������A�g�U���U��Ō𗬂��A�Ō�� ���肵�ĕʂꂽ�B
15:00���[�v�E�F�CBreuil-Cervinia�Ɉړ����A�z�e���ɋA�������B 18:00�s���̃t�H���f����僌�X�g�����Œn���A�I�X�^�Y�̃t�H���e�B�i�`�[�YFontina���g�����{��̃t�H���f���� �H�ׂ��B���������̂ő�R���������Ė����ɂȂ��Ă��܂����B22:00�A���B����6500�B�C��23-5���B
 |  |
 |
| Platau Rosa�̕X�͂ŃX�L�[������l�B | �~�����̑����B | Leontopodium alpinum(�G�[�f�����C�X) |
8��4��(��) 6:00�N���B�����Ńz�e���̕�������}�b�^�[�z�����͉_�ЂƂȂ��悭�݂����B�\���ύX���āA �O���s����Platau Rosa �ɍēx�s�����Ƃɂ����B7:30���H�B�O���Ɠ������[�v�E�F�C�� 9:30Platau Rosa(3480m)�ɒ������B���̓��͕��������g�������B�}�b�^�[�z�����̎R����ǂ��݂����B �[�����\�����̂ŁA11:00Lago Cime Bianebe�ւƈړ������B
Lago Cime Bianebe(2982m)�ł����s�҂̋C���͗ǂ������̂ŁA����3km�قǂ̒r��������鎖�ɂ����B�������D�� ���R�A�����������Ԑ���ł������B�Ƃ��낪�A2km�قǍs�������ŁA�X�͂���̐�������Ă����3m�قǂ̐�ɒ��ʂ����B �[�����ł��G�܂ł��炢�ŁA���������قNj������������B���s�n�͂��邱�Ƃɂ��āA�Y�{���E�C����E�������g�p���c �ЂƂɂȂ��ēn�����B�ƂĂ��₽���Đ����͂����Ă���̂����X�ł������B�n�͂ɐ��������̂ŁA������j���� ���H�Ƃ��A�s�N�j�b�N�����`��H�ׂ��B���̍��ɂ̓}�b�^�[�z�����̎R��͉_�ɕ����Ă����B�[�����������̂ŁA 14:00���[�v�E�F�C�ɏ�艺�R�����B
17:00�X�ɏo�Ĕ�����������A18:00�p�X�^�����̃��X�g�����ŗ[�H���ς܂����B21:00�A���B����10311�B�C��23-5���B
 |
 |
 |
| Platau Rosa���猩���}�b�^�[�z���� | �w��̒r��������� | �삯�ē�������A�C�x�b�N�X |
8��5��(�y) 6:00�N���B�����B���̓��̓~���m�Ɉړ�������ł���B7:40���H�B�z�e���̕����ʼn_�ЂƂ����}�b�^�[�z���� �߂Ȃ���߂����B9:50�`�F�b�N�A�E�g�B10:25Breuil-Cervinia���̃o�X�ɏ��AChatillon�ŏ�芷���A13:30�~���m�� Lampugrano���B�n���S�ɏ���ă~���m�����w�֍s���A14:30�w�O�̃z�e���ɒ������B�~���m�̋C����35���ł������B 16:30�~���m�����w����n���S��Duomo�֍s���A������������ăX�J�����֍s���A���X�X���Ԃ�Ԃ炵����A�A�[�P�[�h�X�� �J�t�F���X�g�����ŁA17:00�T�t���������~���m���]�b�g�A�s�U�A��T���_��H�ח[�H�Ƃ����B19:00�z�e���ɋA��A 22:00�A���B����7053�B�C��35-20���B
 |
 |
 |
| �z�e���̕������猩���}�b�^�[�z���� | �z�e���̕������猩���}�b�^�[�z���� | �X�J���� |
8��6��(��) 6:30�N���B7:30���H�B8:30�z�e�����o�āA�n���S�ɏ���āA�~�P�����W�F���̉悢��''�Ō�̔ӎ`''���ςɁA �T���^�E�}���A�E�f�b���E�O���c�B�G����֍s�����B���w�͗\�ŁA���͓��{��"9:30����̉p��K�C�h�t"��\���B ���w��15���ł������B���w��A�����ău�����G��ق֍s�����B ���̌�A1900�N����p�ق����w������A���X�X���Ԃ�Ԃ炵���B���s�҂Ɂu���̕��A�Y��ȐF���ˁA��������?�v�Ə��߂Ă� �u����Ȃ̉����Œ���̂�v�B�u����Ȃ̒��Ē�d��������J�b�R�C�C���v�ƌ����Ă��ʖځB�����P�ɒ��̎ʐ^���B���� �y����ł����B
16:00���������[�H���ς܂��A18:00�z�e���ɋA�����B21:00�A���B����15916�B�C��36-26���B
 |
 |
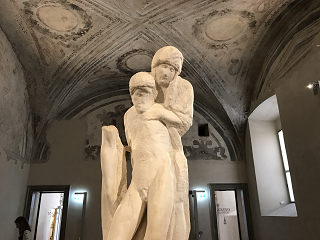 |
| �T���^�E�}���A�E�f�b���E�O���c�B�G���� | �~�P�����W�F���̉悢��''�Ō�̔ӎ`'' | �~�P�����W�F����"�����_�j�[�j�̃s�G�^" |
8��7��(��) 5:30�N���B6:20�`�F�b�N�A�E�g�B6:45�~���m�����w���̋�`�s�o�X�ɏ��7:50��`���B 9:40�~���m����LH0247�ł�11:00�t�����N�t���g���B13:20�t�����N�t���g����LH740��8��8��7:40��ɒ������B
����̗���"�C�^�����̓c�ɂ̐l�B�͐e�ŁA�f�p�ŁA�l�̍D����������"�Ɗ����܂����B
�����"���[���b�p�A���v�X�����闷"�͊������܂������A�ēx�K���Ȃ�h��Courmyeur�łȂ��AEntreves���� mounten chalet�ɏh�������ق����ǂ��Ǝv���܂��B
�����u�����ł͊��ɃC�^����Pontal�ƃt�����XChamony�Ԃ����[�v�E�F�C�Ō���Ă��܂��B�}�b�^�[�z�����ł� Platau Rosa ��Klein Matterhorn�ԂŃ��[�v�E�F�C�����݂���������B�߁X�ɃX�C�X���ƃC�^�������� ���[�v�E�F�C�Ō����l�ł��B
���s�҂́u�C�������������ɂ��v�����́A���v���ƁA"�~���m�œ��˕a�ɂȂ����̂ł͂Ȃ���"�Ɛ��肳��܂��B�������V�����A ���������Ɏ䂩��āA����������̂������Ȃ������Ǝv���܂��B
���͂Ƃ�����"�����I���o����"���ƂɊ��ӁE���ӁB "�y���������o����"���ƂɊ��ӁE���ӁB
2017.7.20

���厛�̏r�擰�Ƒ哒��
���厛�ł�7��1���`31���̊ԁA�u�r�擰�i����傤�ǂ��j�v�Ɓu�哒���i�������j�v�� ���ʌ��J���Ă���B���́A���H��A���V��������Ĕq�ςɍs�����B�r��[�d����l(1121-1206)��1180�N�̓��厛����̌�A�����厛�助�i�Ƃ��Ċ��q���̓��厛 �����ɑ傫�ȍv���������B�r�擰���ɂ͏d����l�����i����A���q�j�A����ɔ@������(�d���A���q�@���c��)�A ������������(�d���A����)�����u����Ă����B���m�̐��������������A���܂�ɂ��܂�Ȃ��̂ŁA���͔�� �o�����B�Ȃ��A�r�擰�́A�ʏ��7��5���i�r����j��12��16���i�Ǖي��j�ɂ������J����܂���B
�u�哒���v�́A�������J�B����(�d���A���q)�͏d����l�ɂ���čČ�����A1239�N��1408�N�ɉ��C���Ă���B �������ɂ́A���a3m�E�[��1m���̂ǂ����肵���S���D(�d���A���q)���������B
�E�̎ʐ^�́A��̔��ɍ炢�����n�X�̉Ԃł���B�t����Ђ̖��t�A�����Ŏ���Ă��āA���_�J�̔� �ɓ���Ēu���������o�����B�������ĂāA���N�ŌܔN�ځB����ƉԂ��炢���B�������ˁB
2017.7.13