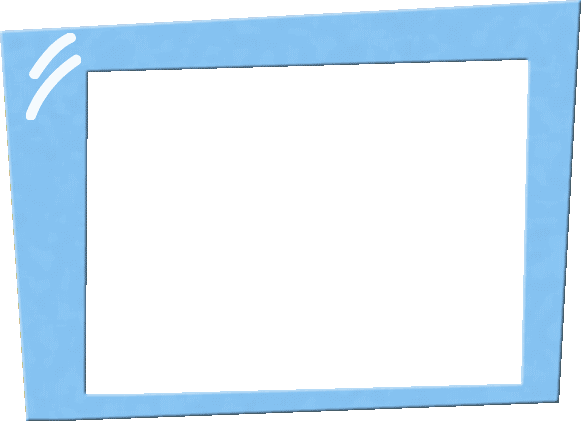(かいじゅうくかすがじんじゃふきん)
関ヶ原(せきがはら)の戦い後に戒重城を得(え)たのは、織田信長(おだのぶなが)の弟の織田有楽斎(うらくさい)長益(ながます)でした。
その後、1615年に4男の織田長政(ながまさ)に譲(ゆず)られ、戒重に陣屋(じんや)を置(お)きました。
江戸時代の中ごろ
現在(げんざい)の戒重区春日神社付近には、古くは第30代敏達天皇(びだつてんのう)の訳語幸玉宮(おさださちたまのみや)があったところではないかといわれています。その後、南北朝時代(なんぼくちょうじだい)には、戒重城(かいじゅうじょう)がつくられ、江戸時代(えどじだい)の初(はじ)めには織田戒重藩(おだかいじゅうはん)の陣屋(じんや)がありました。
戒重陣屋の古い地図
(戒重区所蔵〈しょぞう〉)
第3問の答え 織田小学校
戒重の陣屋は、第7代藩主織田輔宜(すけよし)の時代、1745年に、芝村(しばむら)、今の織田小学校のある場所に移転(いてん)しました。
第2問の答え 織田信長
第1問の答え 戒重城
有力者(ゆうりょくしゃ)の戒重西阿(かいじゅうさいあ)が造った戒重城があり、この付近で戦(たたか)いがありました。
南北朝時代1337年~1392年
江戸時代1603年~1867年の初め
春日神社
春日神社境内(けいだい)にある説明版(せつめいばん)