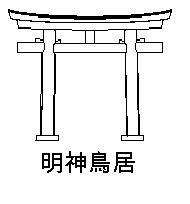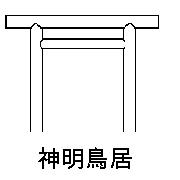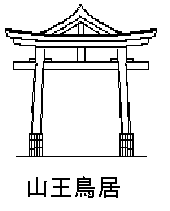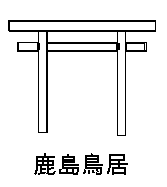あいなめさい
相嘗祭
【神】
古代、新嘗に先立ち、特定の神社に新穀を供えた祭。
あまてらすおおみかみ
天照大神
【神】
別名 大日霎貴
天照大神(あまてらす・おおみかみ)は日本の神様の中で最高神の地位を占める神様で、太陽の神であり、高天原(たかまがはら)の主宰神。
天照大神の信仰が日本書紀に最初に登場するのは崇神天皇の巻で、天皇の娘である豊鍬入姫(とのよすきいりびめ)が天照大神を大和の笠縫邑(かさぬいのむら)に祀ったという記事がある。そして次の垂仁天皇の代になって、今度は垂仁天皇の娘である倭姫(やまとひめ)が天照大神を祀るのにふさわしい場所を探して各地を尋ね歩く話が出てきます。
倭姫は宇陀の篠幡、近江の国、美濃、とめぐった後で伊勢に入りますが、その時「ここは辺鄙な土地だけど波が打ち寄せる美しい国である。私はここに留まりたい」という神託があって、倭姫はそこに宮を建てて天照大神をお祭りした。
この天照大神を祀る仕事は次の景行天皇の代になると、またまた景行天皇の娘である五百野皇女に引きつがれています。この天皇家の娘が伊勢で天照大神を祀るという制度は「斎宮(さいぐう)」または「斎王(いつきのみこ)」と呼ばれ、この時代に始まって後醍醐天皇の皇女祥子内親王まで続いた。その後は祭主が代って神宮を主宰しています。
あめのみなかぬしのかみ
天之御中主神
【神】
造化三神(ゾウカノサンシン)の一柱で、別天神(コトアマツカミ)五神の第一神。
天地開闢(かいびゃく)神話で宇宙に一番最初に出現し、高天原の主宰神となった神である。その名が示すとおり宇宙の真ん中に在って支配する神で、日本神話の神々の筆頭に位置づけられている。
【神】
漢字ではいざなぎは伊耶那岐神・伊耶那岐命・伊弉諾尊・伊弉奈枳・伊佐奈枳命・射奈芸・伊佐奈伎命 。いざなみは伊邪那美命・伊弉冉尊等がある。
『古事記』によれば、天津神に命を受けた二人は、天浮橋に立ってアメノヌボコを降ろして混沌をかき混ぜることにした。すると、矛の先から滴る潮から淤能碁呂島(オノゴロジマ)ができた。二人はその島に天下って、天御柱(アメノミハシラ)と八尋殿(ヤヒロドノ)を建て夫婦となった。
最初に生まれたのは骨のないヒルコだった。悲しんだ二人は、ヒルコを葦の船に乗せて流してしまう。ヒルコの漂着したところは兵庫県の西宮で現在、西宮エビスは「恵比須」の字を使わず「蛭子」を使用している。
二神は本州、四国、九州など八つの島々を生んで国生みを終え、さらに風、水、海、山、草など次々に神を生んでいく。その数35神である。
イザナギ・イザナミ神話は有名なのでここでは省略するが、イザナギは、日向の橘の小門の阿波岐原で、けが穢れをみそ禊ぎによって落とした。そこから沢山の神が生まれるが、左目をすすぐと天照大神(アマテラスオオミカミ)が、右目をすすぐと月読命(ツクヨミミコト)が、鼻をすすぐと素戔嗚尊(スサノオ)が生まれた。
一木造
一木造りといっても腕・膝などは別材であることが多い。
ひび割れを防ぐため像底や背面から木心を取り除く内刳りが行われる。
平安前期が全盛である。
いわくら
磐座
【神】
神の鎮座する場所。
印相
釈迦如来は定印(じょういん),降魔印(ごうまいん),与願印(よがんいん),施無畏印(せむいいん)が多い。
大日如来は知拳印が多い。
【神】
えびす様は一般に漁業と商売繁盛の神様としてだいこくさまとともに庶民に人気がある。このえびす様には実は主として3つの系統がありる。
蛭子説
えびす様の出自で最も有名なのは、蛭子神(ひるこのかみ)であるという説で、蛭子大神は日本の創成神である伊弉諾(いざなぎ)神・伊弉冉(いざなみ)神の最初の子供で、足腰がたたなかったため、そういう子は葦の舟に乗せて流すとよいという伝説により海に流された。そして漂着したのが兵庫県の西宮で、ここで成人し、漁業の神・商売の神となったもの。
少彦名神説
次にえびすは少彦名神(すくなひこなのかみ)であるという説。少彦名神は一寸法師の元型とされる小人神で、大国主神と一緒に日本全国を歩いて、開拓をして回った。その際各地に温泉を見つけており、その代表は愛媛県の道後温泉、出雲の玉造温泉、神奈川県の箱根温泉です。これらの地区では少彦名神をえびす様としてお祭りしている。
事代主神説
最後にえびすは事代主神(ことしろぬしのかみ)であるという説があります。事代主は大国主神の息子の一人で、託宣を司る神ともいわれ、天照大神のお使いが来て、日本の国土を天照大神に譲るよう言われた時、交渉に当たった神の一人。
えま
絵馬
【神】
【寺】
祈願や報謝のために、社寺に奉納する絵の額。馬または木馬を奉納する代わりに馬の絵を描いたが、後に馬以外の画材も扱われるようになった。もともと干ばつや大雨に際して馬を水神に奉ったのが始まり。
えんぎしき
延喜式
【神】
奈良時代に律令制度が整い、平安時代にその細目を定めた「格式」という補助法が作られた。「格」は法律、「式」は施行細目で、神社行政もここに組み込まれた。927年に定められ50巻のうち最初の10巻は「神祇式」といわれ、内9,10巻が「神明帳」である。全国の3132の神社が掲載され、式内社といわれる。官幣社573,国弊社2288,その他地方の神社が記された。
おおくにぬしのみこと
大国主命
【神】
別名、大穴牟遅神(おおなむちのかみ)(大己貴命)、葦原色許男(あしはらのしこお)、八千矛神(やちほこのかみ)、宇都志国玉神(うつしくにたまのかみ)。
大和政権の祖先としての神ではなく、国津神として出雲国の地方政治権力であり、後世において大和政権の(高天原における)高津神へと昇格したのではないかと思われる。
また、記紀では大国主神(おおくにぬしのかみ)の和魂(にぎみたま)にあたられる神様を大物主神と言っている。大物主神は、大三輪神社の祭神である他、金刀比羅宮の象頭山に祀られている。
かえるまた
蟇股
【神】
【寺】
梁などの水平部材の間をささえる部材で柱と柱の間の上部に目を向けると見つけることができる。ただし、禅宗寺院や天竺様とよばれる建物には見られない。
神楽
かつおぎ
鰹魚木
【神】
千木(ちぎ)と千木の間の棟の上に、棟に対して直角に並んだ数本の木のことを「鰹木」といいます。
鰹木の語源については、文字どおり形そのものが鰹を干したものに似ているからともいわれていますが、他にも「葛緒木」あるいは「堅緒木」「勝男木」という書き方もされていて諸説あります。
本来は、棟の押さえを目的として用いられた、いわば一種の補強材だったようですが、現在の鰹木は、千木と同様に装飾的に用いられています。
多くは、白木で造られていますが、両端に金や銅などの薄板で装飾を施したものも見られます。
なお、使用される鰹木の本数は、二本から十本ぐらいまでで、神社によってそれぞれ違います。
一般的に本数が奇数の場合は男神を祀(まつ)っていることを示し、偶数の場合は女神を祀っていることを示すといわれていますが異なる場合もあります。
かとうまど
花頭窓
【寺】
一休さんの漫画などでお馴染みの寺の窓。アーチ型の窓で、当初禅宗の寺の窓に用いられたが、後には他宗の寺院にも使われるようになった。元来は「火頭」字を使用する。
かみむすびのかみ
神産巣日神
【神】
天之御中主神、高御産巣日神についで高天原に現れた神。造化三神(ゾウカノサンシン)の一柱、子は少彦名神。
別称:神産巣日御祖神(カミムスビミオヤノカミ)、神皇産霊尊(カミムスビノミコト)
。
天地造化、万物生成の根本神という性格を持つことから、両神は本質的に同一神格とするのが定説になっている。
瓦
【神】



官国弊社
これを総称して官国弊社、官社と略する事も有る。
きねんさい
祈年祭
【神】
毎年二月四日を祭日とし、幣帛(へいはく)を受け、その一年の豊穣を祈願する。
きはな
木鼻
【寺】
紅梁(こうりょう)が両側の柱から両側に突きだした部分。
光背
こうらん
高欄
【神】
【寺】
縁や階段に取り付けられた欄干や手摺り。
「組高欄」水平の部材どおしが角で交わりその両先端が外側に突きだしているもの。
「擬宝珠高欄」縦の柱の上に擬宝珠を載せたもの。
こうりょう
虹梁
【寺】
【神】
建物内部の柱間に渡した最下部の梁。これを水平に架けると目の錯覚で垂れ下がった様に見えることから、ゆるいアーチ形にして安定感を持たせる。この紅梁の両端が柱の両側に突きだした部分に彫刻を施したものを木鼻という。

国分寺・国分尼寺
正式には、僧寺を「金光明四天王護国之寺」、尼寺を「法華滅罪之寺」という。
国分寺には20人の僧と国分尼寺には10人の尼が常住し、各地における仏教の中心的な存在として鎮護国家を祈念した。
こまいぬ
狛犬
【神】
【寺】
「狛」は高麗(こま)の意味であるが朝鮮半島を指すのでなく遠い国という意味で外来の犬という意味です。その起源はインドやペルシャにあるといわれ、中国では寺院、宮門、陵墓の前に獅子などの獣像を守護として置く習俗がある。開口、閉口の2像を一対とするのは阿吽両像を一対とする仁王などの仏教彫刻の影響を受けたものである。
式内社
これに名があるということは、その当時すでに国家によってその存在を認められていたことを意味し、現在でもその神社に格があるように使われている。
しめなわ
注連縄
【神】
神社や神棚などに見られるように、神聖な区域に懸け渡し、内と外を隔てて、不浄にふれさせないために用いられるものです。
つまり、ここが特別な場所であることを、人々に明示するためであります。 ですから、紙垂を垂らすというのも、注連縄を目立たせて、縄の所在をはっきりさせる目印なのです。
注連縄は、その形状によって大根注連(だいこんじめ)、牛蒡注連(ごぼうじめ)といった種類がありますが、いずれも新しい藁(わら)で左綯(ひだりない)にして作ります。
神棚に取りつける際には向かって右に太い方、左に細い方が来るようにして、これに紙垂を四垂(よたれ)はさみ込む。
しゅみせん
須弥山
【寺】
世界の中心にそびえ立つという高山。海中にあり頂上には帝釈天が住み、中腹には四天王が住むという仏教の世界説。
神宮寺
【神】
【寺】
すさのおのみこと
須左之男命
【神】
別名、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)
素戔嗚尊とも書く。天照大神の弟神で、凶暴な性格の持ち主で、天照大神を怖がらせ、天の岩屋戸へ隠れさせてしまった。そのため高天原から追放され、地上である中津原へ下ることになる。
一方、地上に下ってからは出雲国で八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を斬って天叢雲剣(アメノムラクモノツルギ)を得て天照大神に献じたり、朝鮮の新羅に渡っては、船材の樹木を持ち帰り、植林の道を教えたりと、善神として活躍する。
国津神の最高神とされ、彼の子孫である大年神、大国主などが国津神である。なお八岐大蛇を斬って手に入れた天叢雲剣は後の草薙の剣で、また退治に使った剣は父・イザナギから譲り受けた十拳の剣(トツカノツルギ)である。須佐之男命を奉る神社は、氷川神社をはじめとして関東に多く点在し、武神、航海、農耕の神として祀られている。
そうりん
相輪
【寺】
三重塔、五重塔の最上部の細く尖っているところ。上から宝珠、竜車、水煙、九輪(宝輪)、請(受)花、覆(伏)鉢、露盤で露盤が屋根と接しているところ。
造化三神
たかみむすびのかみ
高御産巣日神
【神】
天之御中主神のつぎに高天原に現れた神。造化三神(ゾウカノサンシン)の一柱。
別称、高皇産霊尊(タカミムスビノミコト)、高木神(タカギノカミ)、高天彦神(タカマヒコノカミ)。
神産巣日神(女性的神格)とは一対の神格として男女の産霊(ムスビ)の神とされる。
「日本書紀」の顕宗天皇の条に、その事績として「天地を鎔造した功あり」と記されている。鎔造とは金属を溶かして型にはめてものを作ることであり、日本の金属文化とも関わりの深い神としての姿もうかがえる。つまり、金属を鍛造して農具や武器などを作り出す文化を司る神格でもあるということ。
たばさみ
手挟
【神】
【寺】
本堂、本殿への階段の上の階隠(はしかくし、雨水を避けるために階段を覆う庇)は傾斜しているため、これを支える柱と階隠の屋根の内側に三角形の空間ができる。この空間を埋めて安定感を与える物が手挟である。
たまがき
玉垣
【神】
神域や禁制の地を囲うための施設で、正確には神殿に近接する垣を瑞垣といい、その外側を囲む垣を玉垣、荒垣、板垣という。
たまぐし
玉串
【神】
榊に紙垂(かみしで)を付けたもので神前に捧げることにより神への恭順な心を示し、神との一体感を確認するものである。
たるき
垂木
【神】
【寺】
屋根の裏側の外に向かって何本も取り付けてある角材。一重二重三重のものを一軒二軒三軒という。細かく垂木を渡してあるものを繁垂木、少し荒いものを半繁垂木、木更に荒いものを疎(まばら)垂木、二本ずつ組にして間隔を空けたものを吹寄垂木という。
ちぎ
千木
【神】
社殿の屋根の両端の所で、交差し高く突き出ている部分のことを「千木」といいます。
千木の起源は、日本の古代の住居(三本の木材を交差させたものを二組作り、それを建物の両端に立てて、その交差部分に棟木(むなぎ)をかけ渡した構造)の建築様式からきたとされています。
この建築様式の場合、交差した木材の先端は屋根よりも高く突き出ています。
その部分が、のちに千木といわれるようになったのでしょう。 千木は、屋根を支えるための大切な構造材だったのです。
しかし、現在ではほとんどの神社の千木が、一種の装飾的な意味合いの強い「置千木(おきちぎ)(二本の木材を交差させたものを、棟の上にのせた造りの千木)」になっています。
茅輪
ちょうずや
手水舎
【神】
参拝に先立ち手と口を清めるための施設。
つきなみさい
月次祭
【神】
毎年二回、六月と十二月の十一日に、幣帛を受ける祭。
つまかざり
妻飾
【神】
【寺】
切妻屋根や入母屋屋根の妻側(側面)三角形の部分の飾り。
垂直、水平に木を組み合わせた物を「竪横式」、破風の内側に破風と平行に二本の斜めの部材を組んだ物を「豕扠首(いのこぎす)」、妻側の紅梁の上に蟇股(かえるまた)を載せたものを「紅梁蟇股式」、蟇股の代わりに徳利形ののもを置いたのが「紅梁大瓶束(こうりょうたいへいづか)」と呼ばれる。
妻に出た棟木の切り口を隠すために用いられた飾りを「懸魚(げぎょ)」という。
破風の頂点内側にあるものを「拝懸魚(おがみげぎょ)」、屋根の下部にあって桁を隠すものを「降懸魚(くだりげぎょ)」という。
懸魚には「猪の目」ハート型で目の穴が空いている、「蕪」、「三花」蕪形彫刻が三方にある、「梅鉢」六角形の梅花形、「雁股」下側が鏃の先端のようになっている、ものがある。
天部
4天王(広目天、持国天、増長天、多聞天)、帝釈天、弁財天、伎芸天、十二神将等
この内多聞天は単独では毘沙門天と呼ばれる。
ときょう
斗★(木へんに共)
【神】
【寺】
大きな屋根の寺院の軒下を見ると部材が組み合わされて屋根を支えているのが見える。これを斗きょう又は組物という斗は枡形の部材でキョウは肘木と言い外側に伸びている部材。
組み合わせの数により一手先、二手先・・という。最上段の斗きょうは垂木を支える。
また、柱の真上にある斗を大斗と言い、京都千本釈迦堂の大斗は大工の棟梁が誤って柱を短くって困り果てているとき、妻のおかめが「短い一本に合せ全部の柱を切れば」と助言をし、大斗を置いて高さ調整をしたと伝えられています。おかめひょっとこのモデルのおかめさんです。
【神】
神社の入り口に建つ一種の門であり、神さまの聖域と人間世界との境界を示したものだといわれています。
大きな神社では、たいがい二つ以上の鳥居がありますが、その場合は外側にある鳥居から一の鳥居・二の鳥居・三の鳥居と呼んでいる。
なおらいでん
直会殿
【神】
祭儀終了後、神職や参列者が直会を行うための建物
にいなめさい
新嘗祭
【神】
毎年十一月に、幣帛を受け、その一年の収穫を祝う。
如来
手には通常何も持っていない。
釈迦・薬師・阿弥陀如来などがあり、衲衣をまとっただけの姿で表わされるが、大日如来は装飾をつけた姿をとっている。
はいでん
拝殿
【神】
神職などが祭典を行い、参拝者が礼拝するための建物。一般的には本殿より大きく、素人はこれを本殿と間違わないこと。
はふ
破風
【寺】
切妻屋根の妻側(側面)の三角形の部分。山形破風(神明造、大社造、流造)、千鳥破風、唐破風(権現造)等がある。
ひもろぎ
神籬
【神】
神霊が宿っている自然物の周囲に常盤木(ときわぎ)を植え、玉垣で囲んで神聖を保ったところ。
ぶでん
舞殿
【神】
神楽などを奉納するための建物。平安末期に常設の建物となり、鎌倉時代に全国に普及した。
へいでん
幣殿
【神】
幣帛(へいはく)を祀るための建物。通常は本殿と拝殿との間に建てられる。祝詞殿(のりとでん)を持たない神社ではここで祝詞が捧げられる。
へいはく
幣帛
【神】
広義では、神に献る礼物。狭義では、天子・国家・地方官から神に奉る礼物の意味。
宝髻
菩薩
宝冠・瓔珞(ネックレス、ブレスレット等)などの装飾をつけ、手には珠、蓮の花、水瓶等を持つことが多い。
観音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、勢至菩薩、日光菩薩、月光菩薩、弥勒菩薩、虚空蔵菩薩等があるが、地蔵は僧形の姿をとる。
みけ
神饌
【神】
神に捧げる飲食物。神酒、水、、塩、飯、餅、魚介類、野菜、果物、海草、鳥等
みけでん
神饌殿
【神】
神さまの食事の準備をする建物。通常は拝殿などに併設される。
みずがき
瑞垣
【神】
神域や禁制の地を囲うための施設で、正確には神殿に近接する垣を瑞垣といい、その外側を囲む垣を玉垣、荒垣、板垣という。
明王
密教で信仰される。
不動明王、愛染明王、大元師明王などがある。
もんぜき
門跡
【寺】
皇子、貴族などの住まいする特定の寺の称、またはその寺の住職。
宇多天皇が出家して仁和寺に入ったのが始まり、室町時代に寺格を表す語となり、江戸幕府は宮門跡・摂家門跡・准門跡などに区分して制度化した。
寄木造
平等院阿弥陀如来を造った仏師定朝が一定の法則を完成させたと伝えられる。
よりしろ
依代
【神】
古くは、神は祭りの時だけ降臨し、祭りが終わると再び帰っていくと信じられていた。その降臨する対象となるもで石や樹木等自然物であった。
後、依代が神そのもの表すご神体として祀られるようになった。
れんじまど
連子窓
【寺】
古くから寺の窓として縦に格子が付いているもの。古い物ほど講師の間隔が広い。
格子を横にしたものを「横連子窓」という。