mansongeの「ニッポン民俗学」
 奇数の文化と偶数の文化
奇数の文化と偶数の文化
一昨日は「平成十一年十一月十一日」だった。私鉄の記念切符が発売されたりしていたが、この日の午前十一時十一分を期してある行事を行なったという記事も今日の新聞では見かけた。いわゆる「ぞろ目」の日であるが、日本人は「一」が好きである。そして「三」や「五」、「七」も好まれる。
ところが一方で、「二」は分かれる(別れる)、「四」は死、「六」はろくでなし、といような具合であまり評判がよろしくない。奇数が好まれ、偶数はそうでもない。例外は、末広がりの「八」と苦の「九」である。
さて、ある友人が「新二千円札」の発行に絡めて、こんな疑問を投げかけてくれた。「新二千円札への違和感は、実は、奇数を尊ぶ日本文化の根源に関わる問題を孕んでいるように思える」と。拝すべし。
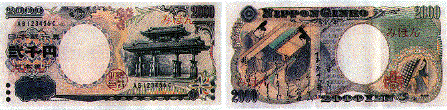
友人はさらに言う。「一月一日の元旦から始まり、五節句(正月七日の七草・三月三日の雛祭・五月五日の端午・七月七日の七夕・九月九日の重陽)はすべて奇数日である。和歌も「五・七・五・七・七」、応援団も「三・三・七拍子」。それにお年玉や祝儀、また葬儀の香典もすべて奇数で施すものだ。中国の「陰陽五行説」で奇数が陽数であるためか」。一々ごもっともである。
しかし「欧米諸国では違う。英語では、偶数を「even」(ちょうど)、奇数を「add」(付け加えられたもの)から転じた「odd」(奇妙な・半端な)[注]と言い、明らかに偶数優先主義である。モーゼは「十戒」、キリストの弟子は「十二使徒」、オリンピックや米大統領選挙は四年に一度だ。外国紙幣では、二十米ドルや二万インドネシアルピアなど、偶数のお札は不思議ではない」。一体、これはどうしたことなのだろう。
まず「数」自体について考察しよう。「一」は「たった一つ」ではなく、「ただ一つ」(唯一)である。あるいは「すべて」を表現している。第一のもの、完全、全体である。しかし、これははなはだ神秘的な感覚である。「二」は「一」の「分割」「分断」であり、「根源的な対」を表している。上下、左右、雌雄、昼夜、陰陽などである。
次の「三」が曲者である。「一」と「二」、あるいは「二」と「一」とバランスの崩れを表している。ところが、「二」という対(例えば男女)が産んだ「子」がもう一つの「一」としたら、「三」は「二」の発展であり、さらに新たな調和、統合と考えられる(これが正・反・合の「弁証法」だ)。図形で言うと「三角形」であり、一つの安定数である。
「四」は「三」以上の安定数である。東西南北、上下左右、春夏秋冬など、2分割の2分割(「二」をさらに分けたもの。一世紀を四分割する「四半世紀」という言葉が典型的だ)である。「四角形」よりも、交差線(十字形)と考えた方がよい。完全数である。
以上「一」から「四」までを見ただけであるが、このように奇数の「一」や「三」には神秘的思考(志向)が交ざっており、偶数の「二」や「四」には合理的思考(志向)が交ざっていることだけは感じていただけるだろう。そもそも「わかる」とは、「分別」と言うように「分ける」(分割する)ことである。それが「二」や「四」など偶数の背景にある。
話がやや逸れるが、「右か左か」という問題もおもしろい。これは「二」(対)がある場合、どちらを優先するかという問題である。例えば「男女」という対では「男」(英語で「man」はそのまま「人間」一般を表す)というのが現在では一般的な通念であろうが、これはヨーロッパ・キリスト教的な考え方である。やはり神が男性であったからだろう。わが『古事記』や『日本書紀』ではご存知の通り、「主神」に天照大神を仰ぎ、イザナギ・イザナミの男女神を対等に扱っている。
右と左では、左利きは「ぎっちょ」(逆利き)とされ、右利きが優先されている。一番を表すのに「右に出るものがない」という言い方もある。ヒンズー教でも右手は「浄」で左手は「不浄」とされ、左手を使わず右手で食事する。最近では「右脳」「左脳」という話題があるが、「右脳」の重要性が専ら説かれているようだ。しかしわが律令体制下ではどうだっただろうか。トップ官職は「太政大臣」だが、次はなんと「左大臣」である。そして「右大臣」と続く。「左」重視の時代が確かにあったのである。実はこれは南方文化である。
中国という国は「南船北馬」の国である。南方の海洋文化(道教系)と北方の騎馬文化(儒教系)が融合して出来たのが「漢」民族とその文化である。話を奇数偶数の方に戻しながら、中国文化を考えたいのだが、やはり(?)寄り道をしてしまう。ヨーロッパと同じ言語族に属するインドだ。
現代もインドを拘束しているカーストは「四」姓制度だ。ペルシャ高原のゾロアスター教は善神アフラ=マズダとダエーヴァ(悪魔)が闘争する「二」元論を説くが、この古形がインドに流れ込んだのが、悪魔である「阿修羅」(アシュラ)と聖典『ヴェーダ』のデーヴァ(神々)の対立である。ギリシャ神話の「ゼウス」とはインド・ア−リア語族の「神」(デーヴァ、デウス)のことである。ペルシャでは善悪神が逆転してしまっているが、これがゾロアスターの宗教「改革」であったのだろう。
さて、そのインドで生まれた仏教であるが、四門出遊、四苦八苦、四聖諦、四天王、六道輪廻など、偶数語が浮かぶ。しかし、三界や五蘊(ごうん)、三十三天に三十三間堂というものもある(まあ、六波羅蜜寺もあるが)。全体的には偶数がやや優勢であろう。
そして中国だ。歴史からいくと、春秋十二侯、春秋五覇、戦国七雄、三国志、五胡十六国、六朝、五代十国と、奇数偶数が入り乱れている。特に「五胡十六国」と「五代十国」がおもしろい。とても中国的なのだ。奇数プラス偶数の組合せで、実に「南船北馬」なのである。その最たるものこそが「陰陽五行」(二と五)の考え方である。
漢詩に「五言絶句」「七言絶句」「七言律詩」などと言った形式があるが、奇数詩かと思いきや、単純にそうでもない。それぞれ順に、五言(語)四句(行)、七言四句、七言八句から成っている。それから「十二支」があるが、これに「十干」を組み合わしたものが六十の「干支」である。やや偶数寄りのところでは、日本にも伝わる「二十四節気」や中国星座の「二十八星宿」などがある。
ようやくわが日本であるが、例はすでに挙げられているので、和歌論を少しやってからまとめに入りたいと思う。前回では「和歌」に触れて「日本人にしかわからない」と述べた。これを今回前述の言い方をすると、日本語がわかる「日本人にしか分けられない」ものが和歌だと言える。和歌とはもろに「日本語」という一言語の総体を踏まえた営為なのである。
まず意味の上から言うと、主客の見分けにくさや含意の多重性がある。これに絡まって、同音声における多義語の豊富さが日本語にはある。掛詞でありしゃれである。また縁詞や序詞も、このような日本語の海から産まれている。
次いで、これらを可能にしている「拍」(リズム)の問題である。和歌を「韻文」と言うが、これははなはだ中国的、あるいはヨーロッパ的な物言いである。「韻」とは第一にメロディーのことだ。確かに和歌を「歌謡」と呼び、節回しをつけて朗詠することもできる。しかし日本語は「拍」の言語なのである。
不思議に思われるだろうが、英語や中国語に「五十音」のようなものはない。日本語で「犬・いぬ」は「い」と「ぬ」の音であり、五十音で「ね」の音を覚えて、「い」と組み合わせると「稲・いね」と発音できる。が、英語では「ドッグ・dog」は「d」と「o」と「g」と発音するのではないし、アルファベットを覚えても「デイ・day」は発音できない。日本語は一仮名一仮名で区切れ、それぞれに固有の音がある。それが日本語の「拍」である。
こういう「拍」の言語・日本語は、一字の語を嫌う。なぜなら、音声が聞き取りにくく、かつ意味も分かりにくいからだ。殊に会話では助詞を飛ばして話すことが多いので、余計にそうだ。「ついく」「はいたい」「かさした」、何のことがお分かりだろうか。それぞれ「津(に)行く」「歯(が)痛い」「蚊(が)刺した」である。だから関西地方では一字の語は音を延ばして発音する。たとえば「歯あ、痛い」と。
そういうわけで、日本語は二字以上の語が多く、二字の語が基本である。山、川、海、空、花、と言った具合だ。日本語の「拍」は二字(音)を求める。次に三字(音)の語がこれに続く。赤い、白い、開ける、閉める、魚、体、桜、頭、…。
和歌はこのような「拍」を自然に踏まえている。それが「五」字(音)であり「七」字(音)である。その基本音数は「一」プラス「二」(または「二」プラス「一」)である。「一」が短のリズムで「二」が長のリズムである。五七(七五)調は長短のリズムの組み合わせから出来ている(モールス信号だな)。
「一」と「二」を合わせると「三」である。日本人の「三」好みは今さら言うまでもない。日本三景、三筆、三夕から始まり、御三家、三冠王、三国一と来る。会社も三井、三菱、三越だ。三社祭に大和三山に三重苦。三人姉妹、三人組、三大珍味、三大名物など、三大○○などはごまんとある。イギリスのディケンズの小説に『二都物語』(パリとロンドン)というのがあるが、日本ではやはり「三都」(江戸、京、大坂)であろう。
日本でとりわけ「数」に気をつかうときとは、贈答のときである。前述の友人の言う通り、祝儀や不祝儀には必ず奇数を使う。日本では奇数は呪数なのである。贈答と言えば昨今評判がよろしくないが、これは臣従あるいは友愛のしるしである。大人の世界ではいざ知らず、子どもたちの世界では「プレゼント」という贈答がいやます盛んである。
その贈答品とは贈り主そのものである。嫌な相手からの贈答品なぞ、その人同様ぞんざいに扱われるのが落ちだろう。だからこそ、心を込める。それが呪術である。そこで用いられるのが呪数としての奇数である。ここには神秘主義がある。合理を超えた願いがある。だからこそ奇数なのである。
そう考えると「新二千円札」とは、日本の奇数呪術を解こうとするものなのだろう。それを欧米価値重視主義への屈服や追随と取るか、日本人の内発的な合理への目覚めと取るか。いずれにしても「新二千円札」が果たして奇数呪術を解くことに成功するかどうかはまた別の問題である。見守りたい。
なお、偶数合理主義文化のヨーロッパ文明の中で、神秘主義は奇数とともに現れた。キリスト教の「三位一体」が典型的にそうだろうし、かのドイツの大哲学者ヘーゲルは「三」狂いの人で、その彼の論理が「二」の対立を超えた「一」を産み出す「弁証法」であった。ヘーゲル哲学は近代合理哲学の完成と言われているが、その「三」の弁証法の源とは古代ギリシャの神秘主義であった。
[注]
- 在米読者の葛西氏、またSakai Kiku 氏より、ご指摘のメールを頂戴した。英語で奇数は「add」ではなく「odd」とのこと。これは筆者が早とちりの引用ミスで、友人・三宅氏は初めから上記修正済みのような形で正確に述べられていた。お許しを。
- くだんの畏友三宅氏からまたも面白いお話を頂いた。聖徳太子の「十七条憲法」の「十七」とは、一桁で最大の偶数(陰数)「八」と奇数(陽数)「九」の和で、これで世のすべてを包摂しようという願いを込めた呪数とのこと。さらに鎌倉幕府・北条泰時の『貞永式目』(五十一カ条)の「五十一」というのも、その「十七」を3倍した意図的な呪数とのことだ。魔術が生きていた時代たち!、と言いたいところだが、今もかしら?
-
三宅善信「もうひとつのY2K問題」(主幹の主観)レルネット
五木寛之・福永光司『混沌からの出発』中公文庫
吉本隆明『言語にとって美とはなにか』(吉本隆明全著作集)勁草書房
金田一春彦『日本語』岩波新書 新版