mansongeの「ニッポン民俗学」
 神の坐す風景の中のニッポン的都市文明
神の坐す風景の中のニッポン的都市文明
家屋文鏡に描かれた大王の宮廷の模写図
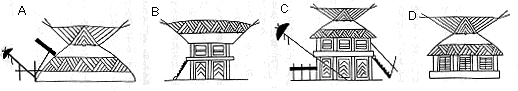
「家屋文鏡」とは、佐味田宝塚古墳(奈良県北葛城郡)出土のある銅鏡の通称。四世紀前半に作られたもので、その背面に丸く四棟の家屋が描かれていることからそう名付けられた。描かれた家屋とは、大王の宮廷建築物と考えられる。Aは集会施設(大室屋)、Bは倉(高殿)、Cは王の公宮殿(殿)、Dは王と王妃の私宮殿(大屋、妻屋)であり、AとBは「外廷」であり、CとDは「内廷」である。AとCには、王権のシンボルである衣笠が見える。
ある方から、こんな問題提起を頂いた。それまでの古墳文化から次の飛鳥・白鳳文化との間には大きな断絶(あるいは飛躍と言うべきか)があるように見えるが、それはなぜか。仰せの通りである。その方自身が言及されているが、仏教がその秘密の鍵を握っているに違いない。
我がニッポンがいかにして出来ていったかについてはまだまだ謎が多いが、極東の島国であったことが、文明の「輸入」にある型を与えたことは確かなことのように思える。それは、文化や文物だけの、あるいはその文明文化の知識・技術をもった人間集団が渡来の如何を問わず、必ず「完成品」として移植されているということである。
「完成品」とは何か。これは「終極」に達していることではなく、すぐさまそのまま現実に行なえるように知識や技術が実用的なノウハウとしてあるということである。改めての試行錯誤が不要な状態であるということだ。そして、そのためには移入文明は「プロジェクト」でなければならない。
たとえば、稲作がそうであった。稲作は稲の種を蒔けば出来るというものではない。いつ何をどうするのか、細かい知識や技術が必要であった。また、これを効果的に行なうためには関連・付属の道具類を揃えることも必要であった。さらに言えば、その民俗・風習・宗教までくっついてやって来たであろう。それらの一括りの知識・技術・思想などの体系全体を「プロジェクト」と呼びたい。
その次の大きな文明プロジェクトが「仏教」である。当時の仏教は、宗教思想であるばかりではなく、土木・建築・彫像・工芸・薬学・葬送術までを包含する、実学知識・技術の総合テクノロジーだった。実際、文明としての仏教を信仰しようとしたら、いかに信仰すればよいかのノウハウが要り、また寺院や仏像その他の製作も必要となる。仏教の「公伝」とはそういうことでなければならない。
後ちの世のこととなるが、たとえば、僧行基や空海の土木や治水工事は、「仏教」のもつこの総合テクノロジーの一つとして発揮されたものだし、道鏡が称徳天皇に寵愛されるきかっけとなった女帝への奉仕は、僧がもつ薬学知識による病気治療であった。
わがニッポンでは、仏教公伝以前は、もっぱら土木に力が注がれていたように思われる。それが前方後円墳の造営だ。ただし、古墳をいまの姿から想像してはならない。うっそうと木々が繁る、水濠に囲まれた緑の小山が古墳ではない。緑なぞ一点もない、土と石で造られた、そこに埴輪で装飾を施した、徹底的に人工的な造築物が古墳である。それは、日光や月光を照り返して、白く光り輝く反自然的な巨大モニュメントである。
話がわき道に逸れるが、弥生から古墳時代までと、室町時代後期は、日本史の中で特異な時代である。他の「木の文明」と言うべき時代に対して、別原理の「石の文明」への志向が認められる時代であった。もしかしたら、そこから別のニッポンが産み落とされる可能性もあった。共同体を濠や壁で囲み、境界を限ることは「都市」への第一歩である。都市は「石」でこそ築かれるものだ。建築物が立ち並ぶ、永久都市の文明への幻を垣間見させる。
では、実際はどうだったか。古墳時代の建築としては大王が住む宮殿がある。しかしこれは孤立した「都」で、すなわち「都市」の中にはない建築だった。しかもそれは恒久的なものとして築かれたのではなく、一代ごとに建築し直すのがむしろ通例だ。また、都の場所も一代ごとに変転した。これでは都市とは成らない。やはりニッポン人は、城壁を巡らし境界を限って都市を固定し、その中心に永久の宮殿を築き、まわりを建築物で満たそうというような発想からは遠かったのだ。
初めての「都市」(ただし城壁はない)は、藤原京(後ちの名)である。重要なことは、都市の中に寺院が建築されていることだ。寺院造立のためには土木工事・建築技術が必須で、仏像および付属物品の製作には彫像や工芸の技術が必要だ。それらは宮殿建築などにも少なからぬ影響を与えたことだろう。総合テクノロジーのプロジェクトとしての仏教は、ニッポンに「文明」をもたらしたのだ。
ところで、神社建築はどうだったのだろう。私たちは神社建築と言えば、たとえば伊勢神宮や出雲大社を思い浮かべたりするが、それは後ちの姿だ。「神社」は建築ではない。神はふつう仏のように像となって姿を現すことはなく、ある固有の風景の中に溶け込んでいる。むしろ、その風景こそが神である。神と出会うには、その固有の場所に行き、社(祭場)を結界して、依り代を立て、祀るのである。その場所こそ「社」である。かくして、神は都市の中には坐さなかったのである。都市にはもっぱら仏が棲み賜うた。
では藤原京の神はどこに坐したのか。たとえば、吉野山に。この都市を築いた持統帝は、初めて仏教による火葬を受け容れた天皇であるが、同時に女帝は吉野に足繁く行幸したことが、ニッポン人にとっての都市の跛行性を象徴している。ニッポン人にとって都市は、都市であって都市ではない。
土木と建築は別個の技術である。ニッポンの建築は、「石」によるものではなく「木」によるものだ。もちろん、素材の選択は風土の違いによるところが大きいだろう。ニッポンの家は長い間、竪穴式の室(むろ)であった。その茅葺きの屋根が木の柱で持ち上げられたのが、その後の家である。柱はいかにして持ち上げられたか。大工は船を造っていた。陸(おか)に上がった船が柱をもつ家である。
文明という言葉は多義的だが、文明と文化という言い方をすれば、前者は物質的な後者は精神的な意味合いが含まれる。木は石に比べれば朽ちやすく、その選択はむしろ積極的に「建て替える」ことさえを包含している。遷都もそうだし、遷宮もそうだ。「日本文明」とはあまり言わず、「日本文化」の方が多用されるのは、文明の物質性、つまり石による建築・建造物の少なさから来ているのかも知れない。
文明には、もう一つ「都市化」という意味がある。石の文明による都市は、繰り返してきたように、城壁をもつものだ。木の文明による我が都市は、神の坐す風景を「城壁」とする。こうして都市はニッポン的に変容し、本来ならば仏しか棲み得なかった都市に、寺院にならってしだいに神社も「建築」され、そこに固有地から勧請された神が棲まれることになったのだ。
ニッポンには実は、全き人工的・反自然的な都市文明はなく、神の坐す風景をもった巨大な田舎しかない。江戸もその後の東京も、そういうニッポン的風景である。
Copyright(c)1996.09.20,TK Institute of Anthropology,All rights reserved