mansongeの「ニッポン民俗学」
 鳥居論---ニッポン人の鳥信仰とその出自
鳥居論---ニッポン人の鳥信仰とその出自

▼「飛ぶ鳥の・明日香」から「鳥居」というトポス(場)へ
日本古代史にとって重要な地名の一つに「飛鳥」がある。これは不思議な名である。まず、なぜ「飛ぶ鳥」を「アスカ」と読むのか。それに、なぜ「飛ぶ鳥」なのか。前者については諸説ある。筆者は「飛ぶ鳥の・明日香」と呼び習わされ続けることで、いわゆる枕詞に当たる「飛(ぶ)鳥」の文字をもって、「アスカ」と読むおしゃれが成立し、これが定着したとの見方を採る。では「枕詞」とは何か。それは各々の神を呼び出す呪文に違いない。
「飛ぶ鳥の」の場合、「明日香」という地の神を呼び出すための呪文である。これが二番目の問いに関係する。アスカとは「鳥」が密接に関わる地なのである。特別な鳥が飛ぶ特別な地、それが「飛鳥」である。それから、日本古代史にとって忘れられない地名に、もう一つ「鳥」の関わるものがある。聖徳太子ゆかりの「斑鳩」である。「イカルガ」とは何か。これはイカルという鳥(スズメ目アトリ科)の別名である。古代日本には鳥がつきまとっている。
本稿では「鳥居」というものを考えてみたい。鳥居とはいったい何だろうか。用字を信ずれば、鳥の宿り木のようなものということになるのか。鳥居に止まる鳥。確かに似つかわしいようにも思える。結論を先取りすれば、今から述べることはほぼそれを肯定する作業である。ただし、これに留まるものではない。さらには、翼を休めるその鳥たちはどこからわがニッポンに飛んできたのかも重要な問題であろう。
▼鳥居は村を悪霊から守る結界門だった
日本の鳥居は、今では神社境内の境界に結界門として立つ。コンクリート製のものも珍しくないが、もとは木製であったことは言うまでもない。さらに遡れば、自然樹であったとも想像できるだろう。その鳥居にはたいてい締め縄(〆縄)が左右に渡されている。そしてそこには幣(ぬさ)が垂れている。こういう鳥居の形式はどうやら中国・江南が発祥地のように思われる。今では、日本を含めて、その周縁地域に伝承されるばかりだが。
 鳥越憲三郎氏は「倭族」という概念で、中国南部や東南アジア、それから朝鮮南部および日本に共通して残る習俗を括る。その氏によって、雲南省やそこに隣接する東南アジア北部の山岳地帯に棲むタイ系諸族(アカ・ハニ族など)に「鳥居」が見出されている。それは左右二本の柱の上に笠木(横に渡す木)を載せたものだ。ただし、これは「社(やしろ)の門」ではなく「村の門」(「ロコーン」と言う)だ。「鳥居」の起源は、共同体(村)へ侵入する悪霊を防ぐ結界門だったのである(「締め縄」とはそういう意味だ)。
鳥越憲三郎氏は「倭族」という概念で、中国南部や東南アジア、それから朝鮮南部および日本に共通して残る習俗を括る。その氏によって、雲南省やそこに隣接する東南アジア北部の山岳地帯に棲むタイ系諸族(アカ・ハニ族など)に「鳥居」が見出されている。それは左右二本の柱の上に笠木(横に渡す木)を載せたものだ。ただし、これは「社(やしろ)の門」ではなく「村の門」(「ロコーン」と言う)だ。「鳥居」の起源は、共同体(村)へ侵入する悪霊を防ぐ結界門だったのである(「締め縄」とはそういう意味だ)。
そして、果たしてその門の笠木には木製の鳥が止まっていた。実は、吉野ヶ里遺跡を始め、わが国の弥生時代の遺跡からは木製の鳥が頻出している。だが「鳥居」は残っておらず、どこにどう止まっていたのかは分からない。「村の門」には左右の自然木に「締め縄」が渡されただけのものもある。それらにはしばしば「鬼の目」がぶら下がっている。鬼の目とは竹で編まれた悪霊を追い払う呪具(「籠目」もその一つ)で、現代の日本の締め縄にも吊されている。




|
▼朝鮮南部の様々な「門」と鳥

 視線を朝鮮半島南部に移そう。ここにも聖なる「門」がある。一対の石積みの塔(タプ)である(多くは現代になってから壊され、わずかしか残っていない)。その上には石や木で出来た鳥が止まる。これは『三国志』(魏志)など(注)が馬韓の民俗として記した「蘇塗」(そと)の末である。蘇塗とは聖域(つまり「聖林」=「社」)も指した。この石積みの塔という形自体は北方ツングース系に由来する。しかし、鳥が止まる結界門という習俗は南方の「倭族」のものである。
視線を朝鮮半島南部に移そう。ここにも聖なる「門」がある。一対の石積みの塔(タプ)である(多くは現代になってから壊され、わずかしか残っていない)。その上には石や木で出来た鳥が止まる。これは『三国志』(魏志)など(注)が馬韓の民俗として記した「蘇塗」(そと)の末である。蘇塗とは聖域(つまり「聖林」=「社」)も指した。この石積みの塔という形自体は北方ツングース系に由来する。しかし、鳥が止まる結界門という習俗は南方の「倭族」のものである。| (注) | 「…蘇塗を立て、大木を建て以て鈴鼓(鈴や鼓)を懸け、鬼神に事(つか)う。…」 |
| 『後漢書』(東夷伝・馬韓) | |
| 「…諸国には各別邑(べつゆう:特別の区域)あり、之を名づけて蘇塗と為す。大木を立て、鈴鼓を懸け、鬼神に事(つか)う。…」 | |
| 『三国志』(魏志東夷伝・馬韓) | |
| 「…別邑を置き、名づけて蘇塗といい、大木を立て鈴鼓を懸く。その蘇塗の義は西域の浮屠(ふと:円錐状の仏塔)に似るあり。…」 | |
| 『晋書』(四夷伝・馬韓) |


 この蘇塗のそばに二本の木が立てられている。一本は竜がくねくねと天に昇るようなもので、もう一本は先端に木製の鳥が止まる「ソッテ」(鳥杆・とりざお)である。『後漢書』の記述では、これが「蘇塗」であるとも読める。今でも四年ごとに「ソッテ祭り」というものがある。そこでは幣つきの「禁縄」(クムチュル:締め縄)も登場する。「門」近くには、ソッテの他に、「チャンスン」(長い杙・くいの意)という一対の「人面」柱もある。
この蘇塗のそばに二本の木が立てられている。一本は竜がくねくねと天に昇るようなもので、もう一本は先端に木製の鳥が止まる「ソッテ」(鳥杆・とりざお)である。『後漢書』の記述では、これが「蘇塗」であるとも読める。今でも四年ごとに「ソッテ祭り」というものがある。そこでは幣つきの「禁縄」(クムチュル:締め縄)も登場する。「門」近くには、ソッテの他に、「チャンスン」(長い杙・くいの意)という一対の「人面」柱もある。人面の頭部を持つチャンスンの胴体には「天下大将軍」「地下大将軍」(あるいは「地下女将軍」)と墨書されている。これは村の境界の守り神である。いわゆる道祖神の原形である。実は先述のタイ族の「門」のそばにもヤダ・ミダという男女二体が置かれていた。道祖神(サイの神)は性神となっていったが、そういう非対称の対が結界を作るという人間の神話思考は、はるか寺院の門を守る阿吽(ア・ウン)像や、ア・ウンを交わす神社の狛犬などにつながっているのだろう。
▼世界樹としての芦笙柱とソッテ
 再び中国大陸に戻ろう。南部に住む苗(ミャオ)族の村の中心には芦笙(ろしょう)柱というものが立ててある。苗族の神樹・楓香樹で出来ている。てっぺんに木製の鳥が止まるのだが、その柱には竜が巻き付いている。しかも柱の上部には牛の角が左右ににょきと突き出している。ここに正月(苗年)祭りのときには、一対の神聖な銅鼓(どうこ)が下がられていたはずだ(というのも今ではもうほとんどの銅鼓が失われている)。
再び中国大陸に戻ろう。南部に住む苗(ミャオ)族の村の中心には芦笙(ろしょう)柱というものが立ててある。苗族の神樹・楓香樹で出来ている。てっぺんに木製の鳥が止まるのだが、その柱には竜が巻き付いている。しかも柱の上部には牛の角が左右ににょきと突き出している。ここに正月(苗年)祭りのときには、一対の神聖な銅鼓(どうこ)が下がられていたはずだ(というのも今ではもうほとんどの銅鼓が失われている)。実は朝鮮のソッテでも一本柱の場合、鳥杆に竜に見立てた綱が巻かれる。芦笙柱、そしてソッテとはもう明らかだろう。神話的世界の中心にそびえる「世界樹」である。文字通り、木である場合も、山である場合もある。そして、それは聖林となり、社となった。天に向かいそびえるもの、すなわち、神を呼ぶもの、依り代が世界樹の本質である(注)。そして、鳥は神を運ぶ神使であり、依り代でもある。
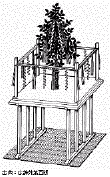 (注)神籬(ひもろぎ)こそ、そういう宇宙である。榊などの神木もそうである。そしてそこにぶら下げられた鏡とは、銅鼓と同じ意味を持つものである。
(注)神籬(ひもろぎ)こそ、そういう宇宙である。榊などの神木もそうである。そしてそこにぶら下げられた鏡とは、銅鼓と同じ意味を持つものである。幟(のぼり)や幡(はた:旗)とはそういうものである。聖林は神が降りる林である。沖縄の御嶽(うたき)も聖林である。「鎮守の杜(森)」とは逆で、森(「盛り」であり山のこと)があってこその社なのである。ちなみに、コイノボリは「鯉幟」であり、私たちはやはり神が依る柱を天にかざしているのである。筆者の想像だが、銅鐸(どうたく)はソッテの鈴や鼓、芦笙柱の銅鼓のように神木に吊されていたのではないだろうか。なお、哀れな音を響かす「鈴」とはその成れの果てのように思える。
▼「柱」から「門」へ。そして「倭族」へ
筆者の考えを整理しておけば、まず世界樹として「柱」(自然木・山)があったように思う。柱とは述べてきたように、神が降り立つ目印であり、依り代である。そこから、神威が及ぶ結界という観念が生じる。諏訪神社・御柱祭りの四本柱もそういう段階である。これが神域=聖林=社となる。当初は村全体がそうして神に守られていたのだ。ついにと言うか、神は人間の都合により、境界の守り神として立たされる。これが単なる「門」の神の段階である。
最後に、ここでは示唆するに留めるが、「倭族」の習俗とは稲作の文化である。中国江南、北緯三十八度以南の朝鮮と日本とは同一の生態系ラインにある。いわゆる「照葉樹林文化」圏に属するのだ。そこに鳥信仰の、さらには太陽への信仰の秘密がある。広大な中国は「南船・北馬」の国である。この言葉には分裂と統合がある。稲作と麦作、左と右、奇数と偶数、鳳凰(および蛇=竜)と龍など、いろいろ面白く興味が尽きないが、別の機会に述べたい。
[主なネタ本]
-
鳥越憲三郎『古代朝鮮と倭族』中公新書
鳥越憲三郎『古代中国と倭族』中公新書
萩原秀三郎『稲と鳥と太陽の道』大修館書店
-
mjf-052 古代朝鮮・韓民族の形成とニッポン