河合隼雄
かわい はやお
97.10.13
「ユング心理学と仏教」岩波書店
河合隼雄はおもしろい。
これは米国連続講演のための日本語による論考集。ユング派心理学者・臨床家である著者が、本来西欧思想であるユングの考えをいかに東洋・日本において実践しているのか。また、東洋人・日本人としていかなる変容を体験し、東洋的・日本的な思索を深めるに至っているのか。著者の個人的な体験と普遍的な思索が明晰かつ平易に語られている好著。
「心」の問題において、仏教的なアプローチは西欧思想とは対極的な位置にある。西欧思想の異端としてのユングは、西欧的な「心」論から、仏教的な方向へのアプローチを試みた思想といえるのではないか。
西欧の醒めていくという「自我」の方向性、これに対して仏教の意識底、さらに無意識底に沈んでいく「覚」という方向性。分ける・分かる文化と、分けられない文化。因果と縁起。進歩と反進歩。語る宗教と語らない宗教。救う治療と救わない治療。父性と母性。切断と包括。あれかこれか、あれもこれも。個人と普遍(非個人)。
そして著者は、もう一つのアプローチを排除しないという意味で東西思想の「統合」を唱えて講演を締め括る。
97.11.20
「村上春樹、河合隼雄に会いにいく」
(村上春樹 共著) 岩波書店
- 前書き
- 第一夜 「物語」で人間はなにを癒すのか
コミットメントということ/阪神大震災と心の傷/言語かイメージか/「理屈」で回答するか、「人情」で答えるか/小説家になってびっくりしたこと/日本的「個」と歴史という縦糸/「言語の違い」の深層/いまは発熱の途上/自己治療と小説/物語をつくる・物語を生きる/結婚と「井戸掘り」/夫婦と他人
- 第二夜 無意識を掘る"からだ"と"こころ"
物語と身体/作品と作者の関わり/結びつけるものとしての物語/因果律をこえて/治ることと生きること/個性と普遍性/宗教と心理療法/ノモンハンでの出来事/暴力性と表現/日本社会の中の暴力/痛みと自然/われわれはこれからどこへいくのか
- 後書き
97.11.24
「子どもと悪」岩波書店
たいへん豊かな書である。子どもばかりか大人も含めた人間存在について、智慧を与える啓蒙の書。
悪、すなわち反価値と看做されているものやことに、どれほどの意義があるかを再発見させてくれる。善、それだけではうすっぺらい。たとえば「よい子」は人間的に豊かか。うそ、盗み、秘密などを自己消化してこそ、人間的にバランスのとれた大人になれるのではないか。死の際を見切った人間がより豊かな生を生きるように。
ここには逆説がある。あるいは弁証法がある。「にもかかわらず」。これが宗教の本質だ。「死と再生」の秘密だ。
創造は破壊を含んだものである。攻撃や暴力、性、引き蘢り(ネクラ)など、悪は抑圧されている。悪の抑圧は再生への道を閉ざし、人間を創造しない。
97.12.16
「ユング心理学入門」培風館
著者にとり比較的初期に書かれた著作であろう。が、その咀嚼ぶりには脱帽ものの本である。ユング理論の咀嚼ばかりではない。自身の心理療法家としての経験や考察までもが見事に読者のユング理解を助けるように配されている。単なる紹介や説明ではなく、一人の日本人としてユングの考えを読者に伝えている。
この人は文が巧みである。達意な文である。この頃からそうだったのかとあらためて感慨した。
今後も返るべき本であろう。つまり、古典である。
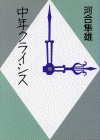 2003.02.02
2003.02.02
「中年クライシス」朝日文芸文庫
禅師としての河合隼雄
中年とは何だろうか。それは、自分がこれまで歩んできたのとは違う別の人生を生きることを、突如として強いられることではないかと私には思われる。壮年だと自ら感じている間はよい。しかしそれが中年も後期にさしかかり、これが更年期かと自覚し始めると様相はたちまち一変してしまう。
まず視力が衰え、身体の一つ一つが脳の発する指令について来られず、わずかずつだが思い通りには働かなくなる。一連の記憶も水底に沈んだように切れ切れにしか浮かび上がってこない。そして、浅いがいつまでも乾かぬ水たまりのように、漠然で鬱とした名付けられぬものがいつも気分を薄く透明に包み込んでいる…。
河合隼雄は12篇の「中年の物語」を読み解き、禅師のように人生の公案を私たちに差し出す。以下、三点に絞ってそれらを考えてみたい。
一つ目は「いかなる因縁でいまの自分があるのか」である。人間は一人ひとり主観的な存在である。デカルト流に言うと「われ在り、故に世界も在る」だ。だからこそ困難や不幸に出遭うと、「なぜ自分だけが」とひどく嘆くところとなる。その原因の探求はたいてい伴侶など周囲の人々へと向かう。あるいは、現在の環境のせいにして過去や未来へ逃避しようとする。
「あいつのせいだ」とする人間関係はその言葉通り「関係」であり、その成立のためには相手と同様に自分も欠かせない。つまり、関係とはパチンと打った手の音が左右両手から出たようにあるものなのだ。それをどちらかだけのせいにしようとすることは、その音が左右どちらの手から出たかを突き止めようとすることに似ていて、不毛である。「でも、あいつが先に」と言うのもニワトリとタマゴの関係のようなもので、いつまで経っても「最初」の原因は見つけられない。関係は因果にあるのではなく、関係そのものなのだから。
「あの時ああしておけば」とか「あの頃はよかった」と不平をかこつのは、いまを生きているからである。想い出された過去は現在からながめた「過去」であり、そのときの「現在」を生きているわけではない。あるのはいつも現在だ。現在にこそ、過去も未来もある。だから、過去にいまの状況の原因を求めるのには矛盾がある。なぜなら、過去のその一点のみから現在が生成しているのではなく、そこから現在に至る途上はそのつど「現在」であった無数の過去によってびっしりと埋め尽くされているのだから。
こうして、世界の因果は共時的にも通時的にも現在の自分に戻ってくる。「われ思う、故にわれと世界在り」。
二つ目は「どんな理想を求め、自分はいまを生きているのか」である。メーテルリンクの『青い鳥』の物語は誰でも知っている。しかしこの物語は果たして日常に満足せよと説いているものなのだろうか。いや、そうではないだろう。おそらく日常を冒険せよと勧めているのだ。私たちは知らず識らずに、押し付けられた日常を生きている。しかし現実は実に多層的で、自分にとっての真実はいくつもある。
「ユートピア」という言葉はおもしろい。「どこにもない場所」という意味なのだが、ではそれはどこになら在り得るのだろうか。そう、「青い鳥」に似ている。つまり、今ここにしか在り得ない。でもそれは、皆と共有している時計と地図で測られる時刻や位置で指し示されるような「いま」や「ここ」にはないだろう。それは、誰にも頼らず、たった一人自分の眼で見、耳で聞いたことを恐れずに信じることから始まる。
私たちの眼と耳は様々な約束事でがんじがらめだ。それもそのはず。思考を、実はどこにもいず誰でもない「他人」が作り上げた無責任な「常識」で自縛していることに無自覚だからだ。客観的な現実なぞない。世界は虚構かも知れず、この生は夢かも知れない。死を恐れることもない。むしろ、この生が永遠であるかも知れないことを恐れなければならない。日常としての現実と自分を裏切ること。
「青い鳥」は確かに飛んでいる。見ようとしているかどうかではない。人は見たいものだけしか見えないのだ。
三つ目は「いま生きている自分は本当の自分であるのか」である。そもそも「本当の自分」なぞないことは初めから分かっている。だから言い直せば、「自分はいま十分に生きているのか」である。ところで、青少年少女の「切レル」という現象が云々されることがある。これは、それまでの理性的な回路が突如ぶち切れて、コントロールできない怒りが噴出する意味で使われているのだろう。生理的な表現である「ムカツク」にも同じような匂いがあり、自分でもコントロールできない感情の表出を表現しているように思える。
ここには、人間は「獣性」を理性でかろうじて包み込んで生きているという仮説が看て取れる。確かに私たちは文化の格子の中に棲んでいる。自らを「ホモ・サピエンス」と呼んで以来、人間は「理性」的な動物だと自己規定してしまった。しかし、人間もまたやはり動物なのである。人間性には動物的な自然や野性もまたしっかりと埋め込まれている。
ただ、動物一般は決して野蛮ではない。それに対して、人間は時として野蛮である。なぜか。理性的な存在であろうとし過ぎるからだ。少し利口な動物程度の存在だと認めないからだ。だからこそ、「人間」の衣をぬぎ捨て「野獣」の姿をしてしか、自らの中の自然や野性を表現できないのだ。人が本当に生きているとは、その自然や野性を含めて自己表現できている状態をいうのだろう。自己表現を閉じ込めることが、かえって人間として無責任な怒りを噴出させるのだ。体内の「毒」の上手な放出は何ら不自然なことではない。
善人として生きようとする者は必ず悪人となるであろう。自分に、理性と野性の区切り線なぞない。すべてが本当の自分である。
中年とは、他者である自分を発見する人生の季節・秋である。それは、意識に支配されない「身体」の存在にようやく気づくときでもある。しかしこれは叛乱ではない。今という時間、自分だけの身体を超えて、永遠とすべての存在とのつながりが開ける季節なのである。生の峠なのである。
Copyright(c)1997.07.27,"MONOGUSA HOMPO" by Monogusa Taro,All rights reserved
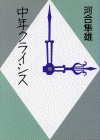 2003.02.02
2003.02.02