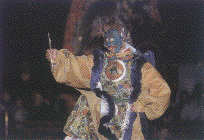| 七月一日
|
|---|
| 午後二時 | 流鏑馬定
(やぶさめさだめ) | 明治維新までは毎年六月一日に興福寺の別会の五師の坊に集まり、その年の流鏑馬を定める事を以て「例祭礼(こさいれい)事始」としていた。この行事の歴史は大変古い。維新後、流鏑馬が執行されなくなったと共に、その儀式も廃せられたが、昭和六十年の流鏑馬旧儀復興に伴い、この伝統が甦った。
|
| 十月一日
|
|---|
| 午前十一時 | 縄棟祭
(なわむねさい) | 縄梯祭は、お旅所の行宮(あんぐう:仮御殿)の起工式で代々「春日縄棟座」として大柳生の片岡家が奉仕する。
早朝より雌松五十二本と縄五十二尋(ひろ)を用いて屋形を組みあげ、その前へお供えを献じてご幣を奉る事などがある。昔は大円鏡や小円鏡という鏡餅が百余面も供えられ、祭事の後で振舞われたという。
|
| 十二月一日
|
|---|
| 午前十一時半 | 馬長児僧位僧官授与式
[馬長児のお位うけ]
(ばちょうのちごのおくらいうけ) | 馬長児は興福寺の学侶(がくりょ:学問僧)の中から選び出される馬長が奉仕させる稚児で、祭礼当日法印権大僧都の格式を許されるものである。
現在、興福寺へ参上して五条袈裟と褊杉衣(へんざんえ)の装束に身を包んだ稚児たちは、古式に則り別当より僧位僧官を授けられる。
この儀式は、“春日惣の神”と尊崇される赤童子の御前にて執行されることとなっている。
|
| 午後一時 | 装束賜式
[装束賜りと精進入り]
(しょうぞくたばりとしょうじんいり) | 御祭に参勤する人々が決定すると十二月の初めに装束と参勤辞令を授与する「装束腸り」がある。これは往昔、田楽頭役の学侶が田楽々頭に授与したのにちなむ。この時には祭礼当日着用する装束に袖を通し若宮社前にてお祓いを受け、この日より精進に入る家々は門口に榊の枝を掲げ、注連縄を張り、「春日若宮御祭礼致斎之事」(かすがわかみやごさいれいちさいのこと)と誌された神事札を立てて出来得る限り外界との交渉を断つ。
|
| 十二月十五日
|
|---|
| 午後一時 | 大宿所詣
(おおしゅくしょもうで) | 大宿所は、御祭の願主役(がんしゅやく)、御師役(おしやく)、馬場役(ばばやく)を勤める大和士が、神事奉仕に当って精進潔斎を行う参籠所である。(旧遍昭院趾)
「センジョ(遍昭)行こう マンジョ(万衆)行こう センジョの道に何がある 尾のある鳥と尾のない鳥(兎)と センジョ行こう マンジョ行こう」と子供に囃されたのは懸物(かけもの)のことで大和の大小名より献じられた雉や兎が懸け並べてお供えされたのである。現在も地元篤信者による懸物が境内に寄進されている。
その他境内には、渡りの武具といわれる野太刀、馬長児の笹などが人目をひき、ご殿の中では神前の珍しい献菓子や流鏑馬勤仕の稚児よりお供えされる稚児の餅、装束類が所狭しと並べられている。
十五日午後二時半からは地元各商店街による大宿所詣行列の為に、午後四時半からは旧儀による大和士の為に、又午後六時からは一般参拝者の為に「み湯」が立てられる。湯立巫女の腰にまく“サンバイコ”は、安産の霊験あるものとされ、特に妊産婦の参拝が多い。また御祭の名物料理“のっぺ汁”が地元商店街の人たちの手によって振舞われ終日大宿所内は活況を呈する。午後五時より、御祭の無事執行を祈願して大宿所祭が行われる。
|
午後二時半
午後四時半
午後六時 | 御湯立
(みゆだて)
|
| 午後五時 | 大宿所祭
(おおしゅくしょさい)
|
| 十二月十六日
|
|---|
| 午後二時頃 | 大和士宵宮詣
(やまとざむらいよいみやもうで) | 宵宮祭は、翌十七日に行われる遷幸の儀に先立って、若宮神前に“御戸開(みとびらき)の神鱗”を奉り、祭典の無事執行を祈る行事で、この後若宮ご殿は白の、み幌(とばり)で覆われる。
これに先立って午後二時からは大和士が流鏑馬児と共に神事参勤の無事を祈って若宮社前へご幣を奉り拝礼を行う宵宮詣の事がある。続いて午後三時からは田楽座も本社と若宮で田楽を奉納する。
|
| 午後三時頃 | 田楽座宵宮詣
(でんがくざよいみやもうで)
|
| 午後四時 | 宵宮祭
(よいみやさい)
|
| 十二月十七日
|
|---|
| 午前〇時 | 遷幸の儀
(せんこうのぎ) | ●若宮本殿よりお旅所へ
若宮様をお旅所へお遷し申しあげる神秘の行事(写真撮影は禁止)
若宮神を本殿よりお旅所の行宮へと深夜お遷しする行事であり、古来より神秘とされている。現在も参道は皆灯火を滅して謹慎し、参列する者も写真はもちろん、懐中電灯を点すことすら許されない。これらはすべて浄闇の中で執り行われることとなっている。
神霊をお遷しするには、当祭においては大変古式の作法が伝えられ、榊の枝を以て神霊を十重二十重にお囲みして、お遷しするという他に例を見ないものである。全員が口々に間断なく「ヲー、ヲー」という警蹕(みさき)の声を発する。又、楽人たちが道楽の慶雲楽(けいうんらく)を奏で、お供をする。
|
| 午前一時 | 暁祭
(あかつきさい) | ●於 春日野お旅所
お旅所へお遷りの若宮様に朝の御饌をお供えし神楽を奉納する。
満天の星空のもと寒気が一入身にしみる午前一時、庭燎に火が入って暁祭がおごそかに執行される。
遷幸の儀の際、行宮の前には神を迎えた事を示す植松(うえまつ)が立てられ、ご殿の中央には瓜灯籠が幽かな光を投げかけているその神前には、海川山野の品々が献じられる。続いて旧称宜大宮家より古式による「素合の御供」(すごのごく)が奉られ、そして、宮司の祝詞に続いて社伝神楽が奏せられる。清らかな歌声と鼓や笛の音が春日野に静かに鳴りわたっていく。
|
| 午前十時 | 本殿祭
(ほんでんさい) | ●於 春日大社本社若宮
若宮御祭の無事斎行を祈る祭典
古くは「御留守事」(おるすごと)と申し上げ春日大宮若宮へ「御留守事の神供」を奉る行事で相嘗祭(あいなめさい)に相当する。
|
| 正午 | お渡り式
(おわたりしき) | ●奈良県庁前広場出発
十二月十七日の当日、旧興福寺境内、現在の奈良県庁前広場を正午に出発する行列は新しく加えられた番外行列を除いて一番から十二番まで、平安朝の日使(ひのつかい)の一行より始まり、亟女(みかんこ)、細男座(せいのおざ)、田楽座(でんがくざ)、猿楽座(さるがくざ)、大和上(やまとざむらい)、と各々古来の仕来りを守りつつ進み、最終は江戸時代、大和国内の大名が出仕した大名行列です。この行列も奈良独特の姿を伝承し、「ヒーヨイヤナ」の掛声で有名なものです。以上総勢千余名が古式に則り都大路を練り歩きます。
ご神霊が多くの供奉(ぐぶ)を従えてお旅所の行宮へ遷られることを一般にお渡りと言うが、御祭の場合はご神霊の行列ではなく既に行宮へ遷られた若宮神のもとへ、芸能集団や祭礼に加わる人々が礼参する行列の事をいう。この様子は、意匠を凝らした華やかな風流の行列として御祭の大きな魅力の一つとなっている。明治以降加わった番外の行列と古式を伝える伝統の行列が、登大路を西に下り、近鉄奈良駅より油阪を経て、JR奈良駅前からまっすぐ東へ三条通りを登り、一の鳥居を入ってすぐ南側の「影向の松」の前で「松の下の儀」を行ってお旅所へ練り込む。
中心は平安時代から江戸時代に至る風俗を満載した伝統行列の部分である。創始の際には「楽人・日使・巫女・伝供御供・一物・細男・猿楽・競馬・流鏑馬・田楽」とその骨格を整えており、旧儀が長く守られながら、時代の流れに応じた姿を見せるのがこのお渡りである(お渡り行列の衣裳は、十二月十五日から大宿所で拝観できる)。

| | 〈梅白枝・祝御幣〉
| 
| | 〈陪従〉
|
第一番 日使
赤衣(せきえ)に千早(ちはや)と呼ぶ白布を肩にかけ先を長く地面に引いて進むのが「梅白枝」(うめのずばえ)と「祝御幣」(いわいのごへい)で、次に青摺りの袍を着けた「十列児」(とおつらちご:騎馬。四人。巻纓冠・けんえいかん・に桜の造り花を挿し、お旅所では東遊・あずまあそび・を舞う)、頂に鶴を飾った風流傘を差掛けられた「日使」(騎馬。一人。黒の東帯・そくたいに藤の造り花を冠に挿す)が続く。日使(ひのつかい)とは関白藤原忠通がこの祭に向かう途中、にわかに病となり、お供の楽人にその日の使いをさせたことに始まるといわれる。関白の格式を表わすものとして、この行列の中心的な存在といえる役である。その後には緋色の衣冠に山吹の造り花を冠に挿したお供の陪従(べいじゅう:楽人。二人)が続き、松の下では馬上で短かい曲(音出・こわだ・し)を奏する。
第二番 巫女
白の被衣(かずき)をいただき、風流傘を差しかけられながら騎馬で進む女性が巫女(みこ:拝殿八乙女)である。春日大社では巫女を伝統的にミカンコと呼ぶ。錦の袋は「御蓋」(おんかさ)で、春日明神が影向された時に用いたものと伝えられている。他に「郷神子」(ごうのみこ)「八嶋神子」(やしまのみこ)「奈良神子」(ならのみこ)も参勤する。
第三番 細男・相撲
浄衣(じょうえ:白衣)姿に清浄感を漂わせながら騎馬で進む六人の人々は細男(せいのお)の一座である。神功皇后の伝説に因む独得の細男の舞を演じる集団である。松の下では馬上で袖の拝をする。あとには、細纓老懸(さいえいおいかけ)の冠に赤や緑の袍を着た十番力士行司・支証が続く。
第四番 猿楽
猿楽(さるがく)は能楽の古名である。後に続く田楽(でんがく)一座も盛んに能を演じていた時代があったので、今もこの名が踏襲されている。今は金春座が出社しているが、もとは観世・金剛・宝生を含めた大和猿楽四座が出仕し、御祭はその格式高い競演の場として古来有名である。松の下では「開口」(かいこう)「弓矢立合(たちあい)」「三笠風流」を演じ、お旅所入口では金春大夫が「埒(らち)明け」を行う。
第五番 田楽
華やかな五色のご幣をおし立てて、綾藺笠(あやいがさ)をつけ、編木(ささら)・笛・太鼓を持つ集団が田楽座である。御祭で行われる芸能のうちで最も興福寺と深い関係をもってきた芸能集団で、かつては祭礼当日までのさまざまな行事に加わっていたが、今でも十六日には本社及び若宮社への宵宮詣、十七日にはお渡りに先立って初宮神社(市内鍋屋町)への初宮詣、松の下・お旅所と各所で芸能の奉納を繰り広げている。奈良一刀彫りの起源といわれる人形を飾った大きな花笠を頭上に乗せた笛役の二藹(ろう)はひときわ人目を引く。松の下では「中門口」「刀玉」(かたなだま)「高足」等を演じる。

| | 〈馬長児〉
|
第六番 馬長児
山鳥の尾を頂に立てたひで笠をかぶり、背中に牡丹の造り花を負った騎馬の美しい少年は馬長児(ばちょうのちご)である。もとは興福寺学侶が輪番で頭人となり稚児を出していた。
その後には、五色の短冊をつけた笹竹を持ち、龍の造り物を頭にいただき、腰に木履を一足吊り下げた従者が二人ずつ従う。これは「一(ひと)つ物」と呼ばれるが、もとは児そのものが「一つ物」ではなかったかと言われ、馬長児はお渡り行列の一つの中心であった。
|

| | 〈競馬〉
|
第七番 競馬
赤と緑の錦地の裲襠装束(りょうとうしょうぞく)に身を固め、細纓冠をつけた騎者は競馬の一行である。かつては、興福寺三綱から出された。もとは五双(二騎ずつ五回)が参道を疾走していた。馬出(まだし)の橋と馬止(まどめ)の橘はその時のスタートとゴール地点であった。現在は馬出橋から出発し、お旅所前の勝敗榊まで競う。舞楽の蘭陵王と納曽利はこの競馬の左右の馬の勝負によって演奏された勝負舞であるので、競馬の勝敗により左舞の蘭陵王と右舞の納曽利の順番が決められる。
|
第八番 流鏑馬
赤の水干に笠(つづらがさ)をかぶり、背に箙(えびら)を負い重藤(しげとう)の弓を手にした少年は揚児(あげのちご)・射手児(いてのちご)である。大和国内の士らは華やかな流鏑馬を神前で繰り広げた。このいわば稚児の流鏑馬ともいえるものは、かがり火をたいて夜中に催され、この時神前ではこれの前に行われた競馬の勝負の舞として舞楽が奉納されたという。
旧儀通り揚児を先頭に都合三崎の稚児が、一の鳥居内の馬場本を祝投扇(いわいのなげおうぎ)の所作をおえて走り出し、一の的より三の的まで順次射ながら進んでいく。
第九番 将馬
将馬(いさせうま)は、かつて大和の大名家中より奉った引き馬の名残りで、神前に馬を献じた古習を示すものでもあろうか。馬上には人を乗せず、その名の示すように、かつては馬をはやして勇みたたせたようである。

| | 〈野太刀〉
|
第十番 野太刀他
五・五メートルほどもある見事な大型の野太刀を先頭に中太刀・小太刀・薙刀(なぎなた)・数槍(かずやり)と続く。太刀・槍などのいわばオンパレードで、お渡りにひときわ偉観を添えているが、風流行列の趣きをよく伝えるものである。
第十一番 大和士
射手児を先頭に流鏑馬を奉納した大和武士の伝統を受け継いでいるのが、願主役(がんしゅやく)・御師役(おしやく)・馬場役・大和士などの一団である。御祭はもとは興福寺衆徒が主宰していたが、衆徒(僧兵)国民(武士)が大小名化すると、若宮祭礼流鏑馬願主人を名乗り、ついには御祭全体の主催者のようになった。彼らは六党に分れて交代で願主人等を勤めていたが、豊臣秀吉の全国制覇で壊滅してからも、六党の一つ長谷川党の法貴寺氏人が願主人に仕立てられ、さらに明治維新後は旧神領の人々がこれを勤めて現在に至っている。

| | 〈大名行列〉
|
第十二番 大名行列
大名行列は、江戸時代からお渡りに加わったもので、武家の祭礼の伝統を大和国内の郡山藩・高取藩などが受け継いで供奉した。一時衰退していたものを昭和五十四年に奈良市内の青年達の手によって大名行列保存会が結成され、「ヒーヨイヤナー」「ヒーヨイマカセー」「エーヤッコラサノサー」の若々しい掛け声が聞かれるようになった。その後、子供大名行列や郡山藩の行列も整えられ、お渡りの最後をしめくくるにふさわしい心意気をみせている。
|
| 午後十二時五十分頃より | 南大門交名の儀
(なんだいもんきょうみょうのぎ)
|

| | 〈交名の儀・衆徒〉
|
●於 興福寺南大門跡
古来お渡り式は興福寺内を出発して一の鳥居までを下の渡り、一の鳥居よりお旅所までを上の渡りと称している。下の渡りの中心的な行事がこの交名である。祭礼の主催権を持つ興福寺への敬意を表し、またお渡り式に遺漏が無いかを改めるこの式は現在、旧南大門跡に衆徒の出仕をみて執行されている。
特に興福寺より出仕した役柄は名乗りの事があり、競馬は「○○法印(又は法眼)御馬候(おんうまのそろ)」などと名乗り、馬長児は僧位僧官を名乗る。これらはいずれも大童子が行う。また大和士は御師役が懐中している文名を声高らかに読み上げるなど古式床しい行事である。読み違いや、不作法があると、再度引き戻してやり直させるという故実もある。
|
| 午後一時頃より | 松の下式
(まつのしたしき)
|

| | 〈松の下式・田楽座〉
|
●於 一ノ鳥居内影向松
一の鳥居の内、南側の壇上に「影向の松」(ようごうのまつ)がある。この松は能舞台の鏡板に描かれている松といわれ、春日大明神が翁の姿で万歳楽を舞われたという由緒ある場所である。
ここを通過する陪従・細男・猿楽・田楽は各々芸能の一節や、所定の舞を演じてからでないと、お旅所へは参入できない事になっている。
松の下を通ってお旅所へ参入した十列児は馬より降りて、装束の長い裾を曳きながら馬を曳かせて、芝舞台を三度廻り、馬長児は馬上のまま三度舞台を廻って退出の時、ひで笠に付けた小さな五色の紙垂を、大童子が神前へ投ずるという、珍らしい所作などがある。
それにもう一つ有名であるのは「金春の埒(らち)あけ」と言われるもので柴の垣に結びつけた白紙を金春太夫がお旅所前で解いてから祭場へ入るというもので「埒があく」という言葉もこれからおこったと伝えられている。
なお、正午過ぎから松の下において興福寺ゆかりの宝蔵院流槍術の型奉納が家元により行われる。
|
| 午後二時頃より | 競馬
(きそいうま) | ●一ノ鳥居内馬山橋よりお旅所勝負榊まで
|
| 午後二時半 | お旅所祭
(たびしょさい)
|

| | 〈神子お旅所祭礼拝〉
| 
| | 〈お旅所祭・宮司奉幣〉
|
●於 お旅所
「お旅所祭」は御祭の本番ともいうべき中心行事です。仮御殿へお遷りになられた若宮様の御前、芝居という言葉の語源と言われる芝舞台の上で、厳粛な祭典を斎行します。この時には“御染御供(おそめごく)”といわれる珍しいお供えが神前に捧げられ、宮司や日使(御祭を始めた関白忠通公はその当日急病でお供の楽人にその役を務めさせた事より、日の使と呼ばれています。)の奉幣や祝詞の行事に引続き神楽を始めとする珠玉の古典芸能が夜の十時半頃まで、絶え間なく奉納されます。
お旅所には正面の一段高い所に若宮神の行宮があり、その前に小高く約五間(九メートル)四方の芝舞台がある。その前には左・右に太鼓が据えられ、それをとり囲むように周囲に幄舎が設けられている。
お旅所祭は午後三時に始まる。最後の大名行列のかけ声が、まだ参道にこだましているなかを神職が参進し、左・右の太鼓が鼕々と打ち鳴らされ、奏楽のうちに神様にお供え(神饌)が捧げられる。このお供えは、お米を青黄赤白に染め分けて飾る「御染御供」(おそめごく)という珍しいものなどである。
続いて宮司がご幣を捧げ、祝詞を奏上してのち行宮の下に座を進め、神職が退いたあと日使の奉幣・祝詞があり、各種団体の代表、稚児や願主役、大和士などの拝礼がおこなわれる。
このあと午後四時から神楽が舞われる。そして、田楽・細男・猿楽(能楽)・舞楽など、午後十一時近くまで各種芸能が奉納される。まさに生きている芸能の歴史を目のあたりにするようで、けだし圧巻である。
|
| 午後二時半頃より | 稚児流鏑馬
(ちごやぶさめ) | ●一ノ鳥居より馬山橋辺まで
|
| 午後三時半より十時半頃まで | 神楽・東遊・田楽・細男・猿楽・舞楽・和舞 |

| | 〈社伝神楽・宮人〉
|
神楽(かぐら)
春日社伝神楽は、八人の巫女による八乙女舞を骨子としたもので、その源は遠く平安時代初期の延喜年間(901〜922)にまで遡ることができる。伴奏は地方(じかた)といい、芝舞台の東側に西面して着座するが、巫女の上藹が琴師を勤め、歌を唱う本歌の役が笏拍子を打ち、付歌は銅拍子と小鼓を打つ。笛役は神楽笛を奏し、それぞれ神職が勤める。
正装した六人の巫女が、「進み歌」に合わせて、楽舎から舞台まで敷き延べられた茣座(ござ)の上を、桧扇を胸にかざしてしずしずと進む。舞は、先ず二人舞の「神のます」、次に白拍子舞の進み歌「鶴の子」に合わせて一の巫女が楽舎より舞台に進み出で一人舞の「松のいはひ」を舞う。次に六人舞の「宮人」、四人舞の「祝言」(せんざい)と合計四曲が舞われ、「立ち歌」によって退下する。お旅所における神楽は、春日大社の多くの祭典のなかでも最も大儀で華やいだもので、その装束も最も格式あるものを用いる。
東遊(あずまあそび)
神楽が終って、行宮の瓜灯籠と舞台の周囲六ケ所に設けられた篝火に火が入れられると、東遊が始まる。
安閑天皇の御代、駿河国の有度浜に天女が降り、舞い遊んだという故事から起った東国の風俗舞といわれる。
青摺の袍に太刀を侃き、巻纓の冠をいただいた舞人四人(童児)が凛々しく「駿河舞」と「求子舞」の二曲を舞う。子どもが舞うのは他に例がなく、珍らしい。

| | 〈田楽〉
|
田楽(でんがく)
田楽の起源については、神に五穀豊穣を祈る楽であるとか、農民を慰労するために演じた所作であるとか、田舞から出たもの、又は散楽(奈良時代に中国から伝わった曲芸の類)から転じたものなど種々の説がある。
春日田楽は御祭が行われた当初から奉納されており、かつては田楽能もあり、名人もいた。世阿弥が十二才のとき、御祭前日に行われる装束賜りの能に田楽の喜阿弥が尉を演じるのをわざわざ見に行って感服したと「申楽談義」にのべている。
はじめは本・新座それぞれからの奉幣で、一が五色の大幣を各一束ずつ神前に献じる。次いで「中門口」の囃子を奏し、曲芸の「刀玉」「高足」となる。このあと「もどき開口、立合舞」という短い能を演じる。

| | 〈細勇〉
|
細勇(せいのお)
神功皇后の故事にちなむもので、筑紫の浜で、ある老人が「細男を舞えば磯良と申す者が海中より出て千珠、満珠の玉を献上す」と言ったのでこれを舞わしめたところ、磯良が出てきたが顔に貝殻がついていたので覆面をしていたという物語りが伝わっており、八幡神系の芸能と考えられている。
白い浄衣を着けた六人の舞人が白い布を目の下に垂らし、うち二人が小鼓を胸から下げ、二人は素手でいる。あとの二人は笹の役である。小鼓を打ち、袖で顔を覆いながら進み、また退きして拝舞する素朴なものであるが、独得の雰囲気をかもし出す実に神秘的な舞である。わが国芸能史のうえでも他に遺例のない貴重なものである。
|

| | 〈神楽式〉
|
神楽式(かぐらしき)
神楽式とは、翁を略式にしたものである。翁は新年や大事な演能会・神事の能のはじめには必ず行われて、天下泰平を祈願する儀式である。
常の翁はすべてがぎょうぎょうしいものであるが、この神楽式は、シテの翁と三番三が白の狩衣(浄衣)に白の大口をはき、面はつけずに舞う。千歳は出ない。地謡や囃子方は裃を着、大鼓はなく小鼓は一丁になる。
後見が最初に正先へ鈴を出し、囃子方と地謡が座に着いてから、シテの翁と三番三がある。三番三は翁返りのあとすぐ鈴の段を舞う。
明治の初年、時の大夫金春広成が、金剛の大夫氏成と協議の上定められ、御祭お旅所神前の特別な翁として現在に至っている。
|
舞楽(ぶがく)
舞楽は、飛鳥・白鳳から奈良時代にかけて古代朝鮮や中国大陸から伝えられ、わが国において大成されたもので、のちに日本で作られたものも含めて、その伝来や特徴から左舞及び右舞に分けられている。
左舞は中国や印度支那方面から伝えられたもので、赤色系統の装束を着け、右舞は朝鮮地方や渤海国等から伝えられたもので、緑色を基調とした装束で舞われ、左舞は唐楽、右舞は高麗楽とも呼ばれ、演奏は普通、左舞・右舞を一対(番舞という)とし、その何組かが舞われるのが例となっている。御祭では五番、十曲が舞われる。
これらの舞楽は、天下の三方楽所といわれた京都、奈良、天王寺に伝わり、それぞれ特色ある芸能をうけついで来た。現在、宮中の楽部にはこの三方から楽家が奉仕されているが、奈良は春日大社を中心に社団法人南都楽所がこの南都舞楽の伝統をうけついでいる。

| | 〈振鉾三節〉
|
振鉾三節(えんぶさんせつ)
舞楽の始めに舞われる曲で国土安穏、雅音成就を祈る。まず鉾を持った赤袍の左方舞人、ついで緑袍の右方舞人がそれぞれ笛の乱声に合わせて舞い、最後に二人が鉾を振り合わせる。
|

| | 〈萬歳楽〉
|
萬歳楽(まんざいらく)=左舞
隋の楊帝が楽正白明達に作らせたもので、鳳凰が萬歳と唱えるのを舞に表したものといわれている。慶賀の際には必ず舞われる荘重閑雅、気品の高い曲である。舞人は四人、赤の常装束に鳥甲を冠っている。
|
延喜楽(えんぎらく)=右舞
延喜年間(901〜922)に山城守藤原忠房が作曲、敦実親王が作舞したもので、高麗楽の形式によっている。四人舞。緑色の常装束で萬歳楽と一対となり、同じく慶賀必奏の舞である。
賀殿(かてん)=左舞
仁明天皇の嘉祥年間(848〜850)に遣唐使判官藤原貞敏が琵琶の譜によって習い伝えた曲に、楽人林真倉が舞を振りつけたといわれている。すこぶる変化のある動きの早い舞である。四人舞。袍の両肩をぬいだ形で、裾と前掛をつける。

| | 〈長保楽〉
|
長保楽(ちょうぼうらく)=右舞(地久と隔年で奉仕)
保曽呂久世利(ほそろくせり)を破の曲に賀利夜須(かりやす)を急の曲として一條天皇の長保年間(999〜1004)に一曲にまとめたもので、その時の年号を曲名としたといわれている。四人舞で、蛮絵(ばんえ)装束に巻纓冠(けんえいかん)を着して舞う。
以上の萬歳楽から長保楽までの四曲を平舞(ひらまい)という。
|

| | 〈和舞〉
|
和舞(やまとまい)
和舞は大和の風俗舞で、春日社では古くから行われてきた。今、神主舞が四曲、諸司舞八曲及び進歌・立歌・柏酒歌・交替歌・神主舞前歌等が伝えられている。
神主舞は一人または二人で、諸司舞は四人または六人にて舞われる。舞人は巻纓の冠に採物として榊の枝や桧扇をもち、青摺の小忌衣をつけ虎皮の尻鞘で飾られた太刀を侃く、諸司舞の四段以降は小忌衣の右袖をぬぐ、歌方は、和琴・笏拍子(歌)・神楽笛・篳篥(ひちりき)及び付歌・琴持にて行われる。
御祭では神主舞一曲、諸司舞二曲が舞われるのが近年の例となっている。
|

| | 〈蘭陵王〉
|
蘭陵王(らんりょうおう)=左舞
中国・北斉の王、蘭陵王長恭という勇将が戦の終ったと善、諸軍士と平和を寿いたといわれている舞である。一説には印度から伝わった曲であるともいわれている。
長恭は美青年であったため戦場におもむく時は、いつも恐ろしい面をつけ軍を指揮し、その武勇は轟いていたという。
舞人は竜頭を頭上にし、あごをひもで吊り下げ金色の面をつけ、緋房のついた金色の桴をもち、朱の袍に雲竜を表した裲襠装束をつけて勇壮に舞う、舞楽の中でも最も代表的なものの一つである。
|
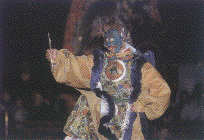
| | 〈納曽利〉
|
納曽利(なそり)=右舞
伝来不詳であるが、竜の舞い遊ぶさまを表した曲といわれ、破と急の二楽章から成る曲である。竜を象どった吊りあごの面をつけ、毛べりの裲襠装束を着け銀色の桴をもって舞う。
蘭陵王とともに一対をなし、競馬の勝負舞として右方の勝者を祝って奏されるものである。
|

| | 〈散手〉
|
散手(さんじゅ)=左舞
散手破陣楽といい、林邑五破陣楽の一つの雄壮な武舞である。
これは神功皇后の時に率川(いさがわ)明神が先頭にたって軍士を指揮したさまをあらわしたものといわれている。
舞人は赤い隆鼻黒髭の威厳のある面をつけ別様の鳥甲をかぶり、毛べりの裲襠装束を着け、太刀を侃き、鉾をもって舞う。
その舞い振りは勇壮活発で、武将らしい荘重な感じが漂っている。一人舞である。序と破が伝わっている。
|

| | 〈貴徳〉
|
貴徳(きとく)=右舞
漢の宣帝の神爵年間に匈奴の日逐王が漢に降伏し貴徳侯になったという故事によっている。舞人は白い隆鼻白髭の面をつけ、別様の鳥甲をかぶり、毛べりの裲襠装束を着け、太刀を侃き、鉾をもって舞う。その舞い振手りは気品高く勇壮である。
破と急とが伝わっている。
散手と番舞(つがいまい)として「中門遷(うつり)の舞楽」といい、かつて興福寺一乗院宮、大乗院御門跡、春日社司らがこの間に出仕したという。
|

| | 〈抜頭〉
|
抜頭(ばとう)=左舞
天平時代に林邑(今のベトナム地方)の僧仏哲(ぷってつ)が伝えた曲で、舞人一人が裲襠装束で太い拝をもって舞う。
猛獣を退治した孝子の物語を表わしたもので、太鼓と笛の部分は獣と格闘する場面、合奏の時は復仇を了え、山路を両手でわけつつ、喜踊して降ってくる状を表す。
|
落蹲(らくそん)=右舞
納曽利の二人舞をいう。枕草子に「落蹲は二人して膝踏みて舞ひたる」とあるのがこれで、南都楽所の右方舞である大神(おおが)流独特のものである。相撲の勝負舞として舞われ、抜頭と一対をなす。
以上の三番(六曲)を走舞(はしりまい)という。
|
| 午後十一時 | 還幸の儀
(かんこうのぎ) | ●お旅所より若宮本殿へ
若宮様に御殿へお婦りいただく神秘の行事(写真撮影は禁止)
遷幸の儀と還幸の儀の間は二十四時間以内でなければならない事になっている。つまり二日間に亘ってはならないのである。だから遷幸の儀は十七日午前零時過ぎであり還幸の儀は十七日午後十一時頃から開始され、十八日午前零時にならぬうちに若宮神社へお帰りになるのである。
お旅所行宮において神秘の行事ののちご出発となる。遷幸の儀にくらべ、お還りになる還幸の儀の道楽(みちがく:還城楽・けんじょうらく)、つまり旅情をお慰めする音楽は、テンポもやや早く軽やかなものとなる。
遷幸の儀と同じく大松明が道を清め、沈香の香りが漂う中を警蹕の声と共にお帰りになる様子は江戸時代の郷土史家村井古道が、正に神代の昔にかえったような感動を覚えると書き残しているとおり、荘厳かつ神秘なもので他に例を見ないものである。
若宮神社では、お帰りを待ち受けている神人等によって待太鼓が打ち鳴らされ、その太鼓の音と微妙に溶け合った道楽のしらべにのって、若宮神は無事に元のご殿へとお鎮りになる。
その後、神楽殿で社伝の神楽が奏せられ、華麗な祭りの幕が閉じられるのである。
|
| 十二月十八日
|
|---|
| 午後一時 | 奉納相撲
(ほうのうずもう)
|

| | 〈相撲・土俵清祓〉
|
現在はお旅所祭の翌日、十八日午後一時よりお旅所南側の特設土俵で、奈良県相撲連盟、奈良市体育協会、奈良市相撲協会の協力のもとに執行されている。
遠い昔は真剣な勝負がなされたことであろうが、中世には儀式化されていたようである。勝者には掛布が肩から掛けられたものでこれは興福寺の正法院と愛染院が負担した。
|
| 午後二時 | 後宴能
(ごえんのう) | (※ 平成十三年度)
能 室君(むろきみ)
シテ(韋堤希夫人)金春 晃實
ツレ(室君) 前田 茂穂
ツレ(室君) 金春 穂高
ツレ(室君) 福井 哲也
播磨国室の明神では、天下泰平の時には室の津の遊女たちを舟に乗せ、囃子物をして神前に参る御神事があった。
今も天下泰平であるので、神職(ワキ)がこれを行なうよう命じると、多勢の遊女たちが小舟に棹さして集まってくるのであった。そして、棹の歌を謡い、囃して神楽を舞うと、あたり一面妙なる香りがたちこめ、室の明神の本地である韋堤希夫人が現れ舞を舞うのであった。そのありがたく、神々しい姿を目の当りにした人々は、感涙にむせぶのであったが、春の夜の明けるとともに、空高く舞上がって行くのであった。
神、仏を扱ったありがたいストーリーでありますが、能の分類上は、四番目物(劇的夢幻能)とされています。
この能は、シテである韋堤希夫人には、一句の謡もないという珍しい能です。
またこの能では、ストーリー上では多勢の遊女(室君)が、たくさんの小舟に乗って登場する設定になっていますが、ご覧になっているあなたは、何人の室君と、何艘の舟が見えたでしょうか。そして、妙なる香りを昧わうことはできましたでしょうか。
心豊かな気持ちでご覧ください。
狂言 口真似(くちまね)
太郎冠者 茂山 七五三
主 茂山 逸平
何某 茂山 あきら
主人に、もらい物のよい酒を一緒に飲んでくれる人を捜してくるようにと言われた太郎冠者(シテ)は、酒癖が悪いので有名な人物を連れてきてしまう。それを見て主人は太郎冠者を叱るのだが、仕方なく座敷へ通すことになる。主人は太郎冠者に、以後は自分の言う通り、する通りに振る舞うよう言いつける。
おもしろく思わない太郎冠者は、何から何まで主人の言う通り、する通りに真似をくり返す。
主人が太郎冠者に注意をすれば、太郎冠者はその通りのことを客人にしてしまうように、太郎冠者が律儀に主人の言いつけを守れば守るほど、かえって主人が困り、客人が痛い目に合うことになる。
能 阿漕(あこぎ)
前シテ漁師・後シテ阿漕の亡霊 金春 欣三
西国の旅僧(ワキ)が、伊勢神宮へ参る途中に阿漕が浦に立ち寄る。するとそこへ殺生を業とする身の前世を嘆きながら一人の漁師(前シテ)がやって来るのであった。旅僧は、この地が阿漕が浦であることを知ると、「伊勢の海 阿漕が浦に 引く網も たび重なれば 現れぞする」と言う和歌を口ずさむ。すると漁師も「会うことも 阿漕が浦に 引く網も たび重なれば 現れやせん」と詠ずるのであった。
漁師は、阿漕が浦の由来を教え、菩提を弔ってほしいと言い残し、舟に乗って漁を始めると、急に疾風が吹いたかと思うと「なんでやねん!」と言い残し波間に消えてしまうのであった。
旅僧が、菩提を弔っていると、阿漕の亡霊(後シテ)が現れ、漁を再現して見せるのであるが、地獄の責めの凄ましさを表し、その苦しみから「助けてちょうだい!」と言い残し、また波間に消え失せてしまうのであった。
後シテでは、紅蓮地獄に大紅蓮地獄、焦熱地獄に大焦熱地獄でどのような責め苦にあうかが謡に現れています。類曲として、「善知鳥」があげられます。また、「阿漕」「善知鳥」「鵜飼」の三曲を三卑賤と言います。
|
*