

20180615 東寺








| 観智院 客殿 |  |
鎌倉時代、後宇多法皇によって東寺の寺僧の住房が計画され、南北朝時代の延文4年、1359年頃に杲宝が創建しました。杲宝の弟子、賢宝は、本尊の五大虚空蔵菩薩を安置しました。 ここで杲宝や賢宝は、東寺に伝わる数多くの文書類を編纂。杲宝や賢宝が集めた密教の聖教類は1万5千件以上あり、その数もさることながら質的水準も高く、わが国における貴重な文化遺産となっています。 |
東寺の境内も見学、国宝「金堂」です


| 教王護国寺 金堂 |  |
東寺の中心堂宇で、諸堂塔のうちもっとも早く建設が始められ、東寺が空海に下賜された弘仁14年(823年)までには完成していたと推定される。 |
国宝の「五重塔」


| 教王護国寺 五重塔 |  |
東寺のみならず京都のシンボルとなっている塔である。高さ54.8メートルは木造塔としては日本一の高さを誇る。天長3年(826年)空海により、創建着手にはじまるが、実際の創建は空海没後の9世紀末であった。雷火や不審火で4回焼失しており、現在の塔は5代目で、寛永21年(1644年)、徳川家光の寄進で建てられたものである。 |
講堂の立体曼荼羅の仏様も見学しました


| 木造五大菩薩坐像 4躯(中尊像を除く、講堂安置)(教王護国寺) |  |
金剛波羅蜜菩薩(金剛波羅蜜多菩薩とも)を中心に、周囲に金剛宝菩薩、金剛法菩薩、金剛業菩薩、金剛薩埵の各像を配す。中尊の金剛波羅蜜菩薩像は江戸時代の作。他の4体は後世の補修が多いが、当初像である。一木造に乾漆を併用し、作風・技法ともに奈良時代風が強い。金剛波羅蜜像を除く4躯が「木造五大菩薩坐像 4躯」として国宝に指定され、金剛波羅蜜像は国宝の附(つけたり)指定とされている |
| 木造五大明王像(講堂安置)(教王護国寺) |  |
不動明王像を中心に、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王像を配す。東寺御影堂の不動明王像とともに、明王像としては日本最古の作例である。 |
| 木造梵天坐像・帝釈天半跏像(講堂安置)(教王護国寺) |  |
梵天像は法隆寺などにある奈良時代の像と異なり、4面4臂の密教像であり、4羽の鵞鳥が支える蓮華座上に坐す。帝釈天像は甲を着け、白象に乗り、左脚を踏み下げる。両像の台座、帝釈天像の頭部などは後補である。 |
| 木造四天王立像(講堂安置)(教王護国寺) |  |
4体のうち持国天像は表情に怒りをあらわにし、激しい動きを見せるが、他の3体(増長天、広目天、多聞天)の表現は抑制されている。多聞天像は後補部分が多いが、修理の際に後世の彩色を除去したところ、面部などは当初部分が良好に保存されていることが確認された |
御影堂は工事中、国宝の不動明王は工事の無事を祈願するため建物内に安置されていました


弘法大師像は仮御影堂に安置されていました


| 教王護国寺 大師堂(西院御影堂) |  |
かつて空海が住房としていた、境内西北部の「西院」(さいいん)と呼ばれる一画に建つ住宅風の仏堂である。前堂、後堂、中門の3部分からなる複合仏堂で、全体を檜皮葺きとする。昭和33年(1958年)の国宝指定時の名称は「大師堂」であるが、寺では主に「御影堂」の名称を用いている。 |
| 木造弘法大師坐像(康勝作、御影堂安置)(教王護国寺) | 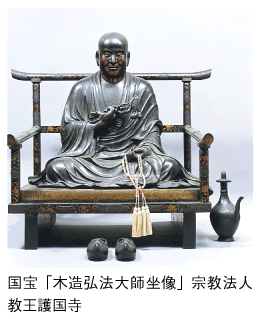 |
東寺の親厳の依頼により、天福元年(1233年)運慶の4男康勝が制作したもので、空海の弟子の真如が描いた空海の肖像とほぼ同じといわれている。 |
| 木造不動明王坐像(御影堂安置)・木造天蓋(教王護国寺) |  |
大師堂(御影堂)安置空海の念持仏とされる。厳重な秘仏で非公開であるが、日本の不動明王像としては最古の作例の1つである。 |
ちょっと外側に出て、国宝「蓮花門」も拝見


| 教王護国寺 蓮花門 |  |
鎌倉時代再建の八脚門。本坊西側、壬生通りに面して建つ |