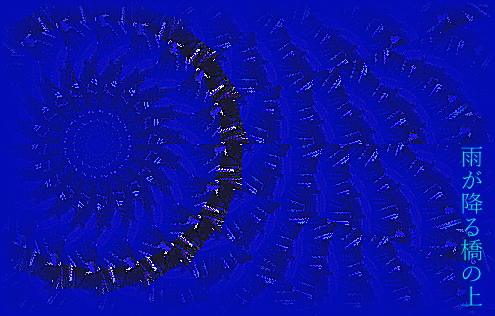
どこにある橋の上だったのか、大人になった今でははっきりと思い出せない。
記憶の中の私は、雨がそぼ降る橋の上でしゃがんで泣いていた。
保育園に通っていた頃、園の女の子ふたりと遊んでいると、ひとりが突然思いついたように親戚の家に一緒に行こうと言うのでついて行くことにした。
最初は、知らない場所に行くので少しワクワクしていたものの、電車道を渡り、神社の鳥居の前を過ぎ、いつもの行動範囲を越えた辺りから段々と不安になってきた。
「どこまで行くの」と聞いたとき、示し合わせたようにふたりが急に走り出した。
私も置いて行かれないようにと走るが、水たまりに足をとられて転んでしまった。
ようやく立ち上がったときには、ふたりは巧みに私をはぐらかして横路のどこかに消えてしまっていた。
最後に振り返ったふたりが、少し笑っているように見えたのを覚えている。
小さな悪だくみだったのだろう。
不安と心細さの中、とにかく知らない道を闇雲に走った。
雨なのか涙なのかわからない水が頬を濡らしていた。
そして疲れ果ててたどり着いたのが大きな橋の上だった。
不安な心が見せた光景なのだろうか、まだ夕方になっていないはずなのに、辺りはうす暗く靄(もや)がかかっていた。
ちらほらと通り過ぎる人はいたけれど、しゃがんで泣いている私に声を掛けてくれる人は誰もいなかった。
若いカップルが通り、祖父に似た老人も通り過ぎた。
一様にこちらに視線を向けるものの、無言のまま白い幻のように靄の中に消えていった。夢の中のような、音も時間もないモノクロームの静謐な世界だった。
泣き疲れた私は恐怖心を抱く余力もなく、通り過ぎてゆく人をぼんやりと眺めていた。
そんな光景が変わったのは、ある種の諦めが心に浸潤し始めたころだった。
視界が少し明るくなって靄が晴れてゆき、周りの景色が見えてきた。
先ほどまでは色のない冷たげな場所だったのが嘘のように…
橋の下には当り前のように川が流れていた。子どもの記憶なので|覚束《おぼつか》ないが、その手前の川辺に小さな掘っ建て小屋のような家があった。
その木造の家を眺めていると、開け放たれた勝手口のようなところから女の人が顔を出して私を見上げた。
「どうしたの?道に迷ったの?」
私は声を出せずにただ頷いた。
すると、女の人は少し笑って
「そこで待ってて。お米を研いだら知ってる場所まで連れて行ってあげる」
そんなことを言ったように思う。
やがて、女の人はどこからか橋の上に上がってきた。自分の子どもなのだろうか、2~3歳くらいの女の子も一緒だった。
「おうちはどこ?」と聞くので
「〇〇小学校の近く」と答えると
「そう」と言って歩き出した。
歩いている間中、家に帰れる安堵感からか、見知らぬ女性に対してすっかり饒舌になり、迷子になった経緯などを一方的に喋っていたように思う。
おしゃべりに夢中になっていたせいか、感覚的にはほんの5、6分で見慣れた場所が目の前に開けた。
「ここまで来れば、大丈夫ね」
そう言って、女の人は女の子と手をつないでもと来た道を引き返して行った。
私は幼いながらも、あふれる感謝の気持ちでふたりを見送った。
家に帰ると、台所の土間にいた祖母が私を見るなり
「こんなに遅くまでどこに行ってたの。それに泥だらけじゃないか」
そう言って足を拭いてくれた雑巾は、橋の上で冷え切ってしまった心を完全に解かしてくれるくらい温かく感じられた。
それにしても、親切な女の人のことは言わないでおこうと決めていたのはなぜだろう。子どもながらに、大人には信じてもらえないような不思議な出来事だと判断していたのだろうか。
あれから20年、いや30年経っても、雨が降る橋の上の暗く幻想的な光景が時々脳裏をかすめることがあった。
機会がある度に、それらしき川沿いの場所を訪れて確かめてみるものの、橋があってもその下に家があるわけでもなく、そこから見慣れた神社がある界隈へ短時間で行けるルートもまだ確認できずにいる。
そもそも古都と呼ばれる町中の橋の下に掘っ立て小屋などというもの、あるいは、その痕跡が未だに残っているはずもなく、あの橋の存在自体も今となっては怪しい。
子どもの心は大人よりも自在に幻想を作り上げるものなのかもしれない…そんなふうに結論づけて終わるのが常だ。
しかし、あの橋は違う次元、はっきりと言えば霊界に近い次元に存在したのかもしれない、あるいは、並行世界のようなものだったのだろうか…などと時々妄想したりもする。
とすれば、靄から現れて靄に消えていった人々が私に無関心で、あちら側へと私を連れて行かなかったのは幸いと言えるのかもしれない。
そして、私を元の場所に返してくれたあの親子がこちら側に存在する人たちであったなら、そしてもう一度会えるのなら、今でもあの女の人にお礼を言いたいと思っている。
「こちら側へ連れて帰ってくれてありがとう」と。
とは言え、あの母娘(おやこ)が一番の幻だったのかもしれない…
などと思ったりもするのだ。