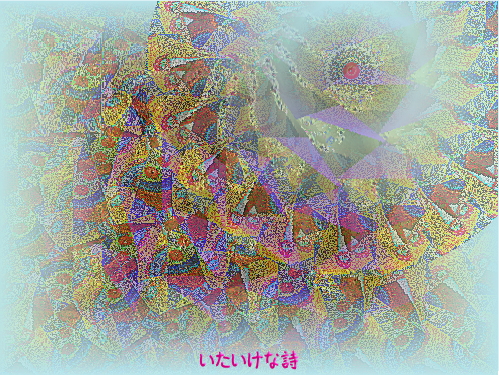
空青く晴れた日には
遠くに富士山が見える
高台の鉄筋の白い建物に
女たちは住んでいた
社会に張り巡らされた
目に見えない有刺鉄線に
堕ちて傷つき羽が折れ
収容された村は
緑深い自然の中にあった
世間の向こう側にあった
知能指数という基準が
無意味に思える聖地で
生をまっとうするのが
彼女たちの務めだった
その中に
ひとりの詩人がいた
貧困に喘ぐ閉鎖的な時代に
名も知らぬ男がくれたのは
愛ではなく
空しい快楽と
日々脳を蝕む宿痾だった
山の移ろいを眺めながら
風に耳をそばだてながら
雨の音に瞑想しながら
彼女は書いた
心の中で
むやみやたらと
もつれ合っているもの
その一端をつまみ上げては
不器用に絡まりをほぐし
言葉にしていった
言葉にすることで
その日を生きていた
それはたぶん
誰にも書けない
幼気(いたいけ)な詩だった