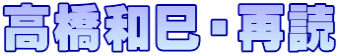
Learning from Kazumi
Takahashi
宮門正和(京都府・宇治市)
Masakazu Miyakado (Uji, Kyoto, Japan)
(described June, 2019)
目次をクリックすると、その箇所に移動します。
**********************************************
※CTRLキーを押して、下線を引いた文字をクリックすると、目的の場所に移動することが出来ます。
「対談:三島由紀夫vs高橋和巳、大いなる過渡期の論理(1969年夏)」
**********************************************
今年、令和元年の歴史クラブ・文集のお題が「京都ゆかりの文学」に決まったと聞いた時、私には特に思い浮かぶテーマはなく、しばらく浮遊の状態が続いた。 京都の文学といえば、王朝文化が華やかなりし頃の、紫式部の「源氏物語」を筆頭に、清少納言の「枕草子」、少し後の時代になるが卜部兼好作とされる「徒然草」がある。 平安時代中期以降、王朝文化が隆盛をきわめる時、京都は日本の政治・文化・宗教の中心であり、文芸活動の殆どは京都から発信された。 しかし、私は、それら「京都ゆかりの文学」に親しんできたかというと、中・高生時代に受験教材として、それら古典の断片を若干、拾い読みしたという程度の記憶しかない。
なかでも、「源氏物語」は、人の心を慈しむ情緒に優れ、また、時には人のエゴを鋭く突く壮絶な人間ドラマといわれる。 しかし、その文量は膨大、かつ、原文は難解に過ぎ、私はかろうじて田辺聖子氏や、谷崎潤一郎氏の現代語訳で、物語のあらすじを追った程度である。 そして、読書中には多少の興趣もあったが、ひとたびページを閉じると、その時代背景や、複雑に過ぎる人間模様など、しかし、私の記憶に留まるものは少なかった‥‥。
日本の国が大きく近代国家へと脱皮する明治時代以降、国内外から様々な影響を受けて、日本の近代文学は多方面に展開した。 しかし、残念ながらそれは京都ではなく、ほとんどが東京から発信された。 文学関係の主な出版社は、新潮社、河出書房、岩波書店、文芸春秋社など東京にあった。 また作家も、その結果として東京に集まった。 例えば、1935年(昭和10年)に創設された新進作家の登竜門である芥川賞の受賞者は、これまで計169名を数える(第161回、2019年下半期まで)。 その受賞者を出身地別で見ると、東京33名、大阪15名、北海道12名、福岡11名、神奈川10名であり、京都を出身地とする作家は少ない(ちなみに、京都を出身地とする作家は、第21回・小谷剛、第50回・森泰三、第130回・綿矢りさ、第143回・赤染晶子、第149回・藤野可織の5名である)。 「京都ゆかりの近代文学」を、俎上にあげるのはいささか無理筋であろう。 確かに、多くの作家が京都を舞台にして優れた作品を残している(例えば、「高瀬川」森鴎外、「羅生門」芥川龍之介、「城崎にて」志賀直哉、「細雪」谷崎潤一郎、「古都」川端康成、「金閣寺」三島由紀夫、「ノルウェーの森」村上春樹、など)。 明治以降の近・現代文学は明らかに東京主導である。 では、京都で活動した作家は?
今から約半世紀前の1971年、39歳の若さで早逝した京都大学で中国文学研究を本職とした高橋和巳(たかはしかずみ)がいた。 我々世代以外の人には馴染みの少ない名前かもしれない。 しかし、当時、我々の多くは、高橋和巳の小説に夢中になった。 最近、手元にある数冊を再読してみた。 当時の出版物の活字は小さく、インクは薄くて、読みづらい。 しかし、あの頃の風景や空気感など、半世紀前に同時代を生きた自らの体験と重なって、思い出すことは多い。
まず、高橋和巳の経歴を記す(以下、高橋和巳名は高橋と略記させて戴く)。 高橋は1931年(昭和6年)に大阪・浪速区で生まれた。 戦争中は疎開で香川に移住。 1949年に新制の京都大学文学部に入学。 同級に大島渚、小松左京らがいた。 同人誌などを発行。 中国語中国文学科を専攻(指導教官:吉川幸次郎氏)。 その後、立命館大学、明治大学などで教鞭をとり、1967年に京都大学文学部中国文学科の助教授に就任。 1969年3月に大学闘争の渦中、学生を支持し、京都大学の助教授職を辞す。 この間、積極的に執筆、講演、対談等の活動を行った。 1971年(昭和46年)5月3日に結腸癌のため死去した(享年39歳)。 葬儀委員長は埴谷雄高氏。
以下、大阪生まれではあるが、京都で執筆活動をした高橋の著作を再読して思ったところ記すことで、私の
「京都ゆかりの文学記」としたい。
高橋は文壇に衝撃的に登場した。 その第一作が長編の処女小説「悲の器」(新潮社刊、第1回文藝賞を受賞)であった。 (当時、中学3年生の私が、この作品を手にしたのは、受賞4年後の1966年の事である)。
そのストーリーの概略は、 『権威の中枢である国立大学(おそらく東京の)法学部の正木典膳教授は、学績豊かで、日本の刑法学会の重鎮であった。 彼の理路整然とした法体系には畏敬の念が注がれ、エリートの権化であった。 やがて、正木は次期の学部長候補に推挙されるようになる。 家庭生活においては、若き頃、その才を認められた正木は、学閥の長の姪を妻にした。 しかし、その妻は結婚後、幸せに過ごしたが、やがて病死してしまった。 家庭の中は家政婦の米山みきと一見、静かに生活が送られているように見えた。 正木に大学教授の令嬢との再婚話が発表された時、正木に妊娠させられた家政婦の米山は、婚約不履行の慰謝料請求の訴えを起こし、正木の素性が世間に知られることになった。 正木は、苦悩するが「自分は決して法にあたるようなやましいことはしていない」と名誉棄損で米山を訴え返した。 しかし、正木は次第に理性と愛の相克の深い悩みに落ち、社会的、精神的に破滅していく‥‥。』 というものである。
まだ社会経験に乏しく、初めて知る大学者の愁鬱の心の中は、当時の私には衝撃であった。 刑法の権威である人物の揺れ惑う心中が暴かれた。 話はそのうちに明るくなるだろうとの期待もむなしく、主人公の自己逡巡は暗く巡った。 高橋の文体は硬質で、全般的には淡々とした記述ではあるが、中にハッと目を見張る表現に出くわす。 「悲の器」の話しの展開は憂鬱至極で、読み通すには相当の忍耐を必要とした。 この本は、山の仲間であった文系の友人の薦めで、手にしたものである。
余談:実は、1967年の秋、私(達)は高橋本人に会っている。 当時、上記、山の仲間と南アルプスの稜線で幾日かを過ごした時、「海外の山に登りたい!」と漠然とした願望を共有した。 資金的、技術的、組織力から言って、ヒマラヤ、カラコルム、中国・雲南の山々は我々の力量にははるかに及ばないことは明白であった。 「では、せめて富士山よりは高いところ」ということで、中華民国(台湾)の玉山(ゆいしゃん)(新高山、3952m(当時の公式標高は3997mであった))に目標を定め、諸々の準備に入った。 当時、中華民国は本土・中国と厳しい戦争状態下にあったため、山岳地域に入るには、中華民国・体育局・山岳協会の招聘状が必須であった。 そのためには、日本・山岳連盟から推薦状を取得し、云々‥‥、と所定の手続きに奔走した。 67年の秋に、中華民国・山岳協会から招聘状が届いた。 我々は天を舞うほどに喜んだ。それは当然の事ながら、中国語(漢文)で書かれていた。 全体からは、招聘許可の文意は読み取れるが、二、三の文意が不明であった。 どうすればいいか?そこは学生の軽いノリで「文学部の中国文学科に行こう」ということになり、教官室を訪ねた。薄暗い教官室に一人の先生がおられた。 招聘状を見せて、不確かな個所の文意を尋ねた。 「これは台湾の言葉だね。」との説明の後、不明の文意を明瞭に解説して戴いた。 この間、約10分ぐらいであったか。 その時、我々はお互いが「この方は、高橋先生!」と認識しつつも、突然のことで、読者であることを告げることもなく、その場を辞した。 背は高く、物静かな語り口が印象に残る。 その後、高橋が論壇の錚々たる人物と対談する本を何冊か読む機会があったが、あの時の物静かな語り口と、対談時の論陣を張った発言には随分と落差を感じた。 もう少し何か会話をしておけばよかった。 後悔は今もある。
本題に戻る。 『私は思い惑った。 ひとたびはその場を糊塗してすましたとはいえ、私はやがてふたたびおとずれるだろう自治会の役員の設問に、自ら愧ずることなく答えなければならなかった。 教壇外の、受講者の私事にいちいちかかわる必要も義務も教授者にはないが、ことは法の問題だった。 ‥‥もちろん、私は平静な学究、学問の中立性を楯に外部の騒音を拒むこともできる。 だが、この警職法改正案の問題は、ある暗い連想の先端で、私の青春、そして私たちの若かった時代、さらには私自身の生き方への設問にもつらなるものをはらんでいた。 (第11章)』 主人公・正木典膳の独白である。
正木は表面的には冷静で論理的な刑法学者を装っていたが、内心、自らに砂地獄に落ちる獲物を見た。 そして、これから先の、心穏やかでない生活を思った。 これは数年後、全共闘運動で揺れる大学内での高橋の立ち位置を象徴するようである。
この長編小説の最後には、 『私は友情の名において、他の力によってではなく、君たちの苦悩する地獄へと、君たちをたたきのめすために赴くであろう。 私たちは格闘し続けるであろう。 人間が人間以上のものたりうるか否かを、どちらかが明証してみせるまで。 さようなら、米山みきよ、栗谷清子よ。 さようなら、優しき生者たちよ。 私はしょせん、あなたがたとは無縁な存在であった。 〈完〉(第32章)』 と締めくくられる。 最後の最後まで、正木は自らの自意識に執着する。 その先に待っている破滅を知らないように。 読み終わっての感想は、ある状況に落ちこむと、暗くて深い闇から抜け出られない知識人の哀しさであった。 ああ、高橋世界!! 原稿用紙1000枚を超えるこの大作をレビューするのは無謀な試みだが、半世紀前の高橋の思考の軌跡をいくらかでもが掠められたらと思う。
続いて高橋は「邪宗門」、「憂鬱なる党派(1966年)」を長編小説として発表し、「我が心は石にあらず(1966年)」、エッセイ集「孤立無援の思想(1966年)」、「日本の悪霊(1968年)」そして「わが解体(1969年)」へと続く。 主題は大学世界・法曹界から、宗教世界の興隆・弾圧・衰退に至る軌跡、学生活動家の卒業後の鬱な展開など、「悲の器」の世界から場面は180度転換するが、いずれにおいても、主人公の「志」を曲げないぎりぎりの生き方が書かれている。 世間でいうところの、成功者のストーリーではない。 この高橋世界を、そのスケールと強烈な鬱から、「和製ドストエフスキー」と例えた人もいる(梅原猛)。
そのあらすじは以下の通りである。 『昭和の初期から第二次大戦後に至る間の「ひのもと救霊会」という世なおしを志向する宗教団体の興隆期、被弾圧期、破滅期と、それにかかわる人々の歓喜、苦悩、絶望が語られる。(その舞台である救霊会本部は仮想の地、「神部」にある。 だが、そこはほとんど京都近郊の盆地を思わせる。) 全編に登場する千葉潔は、その幼児期は孤児であり、青年期を経て、成人するにしたがって、誠実に深く教団にかかわり、それを掌握するが、やがては教団にかかわるすべてを破滅へと導くというのがその基本ストーリーである。 特に、民間信仰を基とする教団の教義は、盛んに農民、労働者との共生を説いた。 これは、戦時中には国家思想(国体)と相容れぬところとなった。 結果として、国家からは厳しい指弾を受け、教団幹部も信者も教義を断つことを強いられた。 戦後、救霊会は急速な復活を遂げるも、正常なバイアスを失っており、過激化、武装化の道をたどった。 国家権力(警察)や、進駐軍に対しての武装蜂起を叫ぶが、結局は微塵も残るものがないほどに粉砕されてしまう。』というものである。
宗教信者の世界を外から見ると、時として異様なものを感じる。 それに戦慄を覚えたとき、人々はそれを「邪宗」と見做し、排撃を始める。 これは世界の宗教史の中でしばしば起こることである。 「邪宗門」は、その日本版を小説で、生々しく再録したものである。 特に、その冒頭は、母と死別し、その死肉を食して命をつないだ千葉潔は、その遺骸を手にして、教団の玄関に現れるところから始まる。 その哀れな母は救霊会の熱心な信奉者であった‥‥という異様な設定からこの長編小説は始まるのである。
2000枚を超す高橋のこの宗教大河小説は、1965年の1月から翌年の5月にかけて朝日ジャーナルに連載され、のちに単行本として出版される時に大幅な増補が加えられた。 その「あとがき」に高橋はこの作品に込めた意図を解説している。
『‥‥むろんそれは書くことが苦痛であると同時に精神のまたとない充実であるように、呵責であると同時にひそかな自律の誇りでもある。 しかしながら、やはり時として、自己を解放するよりはむしろ呪縛するに等しい道を選んだのかと一種後悔に似た感慨におそわれなくもないのである。』 高橋は自らの心的な葛藤を正直に表現している。
『発想の端緒は、日本の現代精神史を踏まえつつ、すべての宗教がその登場の始めには色濃く持っている<世なおし>の思想を、教団の膨張にともなう様々の妥協を排して極限化すればどうなるかの、思考実験をしてみたいということにあった。 表題を「邪宗門」と銘うったのも、むしろ世人から邪宗と目される限りにおいて、宗教は熾烈にしてかつ本質的な問いかけの迫力を持ち、かつ人間の精神にとって宗教はいかなる位置をしめ、いかなる意味をもつかの問題性をも豊富にはらむと常々考えていたからである。』
『この作品の準備期間中、私は日本の現存の宗教団体の二、三を遍歴し、その教団史を検討し、そこから若干のヒントを得た。 とりわけ背景として選んだ地理的環境と、二度にわたる弾圧という外枠は、多くの人々にとって、ああ、あれかと思われるだろう類似の場所および教団が実在する。 だが、ここに描かれた教団の教義・戒律・組織・運動のあり方はもちろん、登場人物とその運命のすべては、長年温め育て、架空なるゆえに自己自身とは切り離しえぬものとして思い描いた、我が<邪宗>の姿であって、現存のいかなる教義・教団とも無縁であることを、ある自負をもって断っておきたい。 ここに描いたものは、あくまで「さもありなむ、さもあらざりしならむ」虚実皮膜の間の思念であり、事件であり、人間関係である。』
これはこの宗教集団を通じて、『自らを確かめ、自らを深めるためには、私が生まれ育った日本の現代精神と私の夢とを、人間をその総体において考究しうる文学の領域において格闘させることが必要だったのである。』と結論付けている。
高橋は暗澹たる闇に沈む人間を主人公に据えた悲惨小説家であるが、「邪宗門」においては、その悲惨さは、個人に対してではなく、教団をとりまく様々な不条理に向けられている。 その最初の部分には、千葉潔少年と、教団幹部の子女である阿礼や阿責が、中・小学生として登場し、盆地という田舎の閉鎖社会の中で、のびのびとして子供らしく楽しくふれあう生活が描かれている。 しかし、彼らも大人になるに従い、教団を取り巻く様々な弾圧、差別などの不条理に対して、それぞれ三者三様の方法で抵抗を試みる。 最終的には労働争議への介入や、学生ストライキ、そして国家権力との相克(戦争)という予期せぬ事態に突入する。 また、教団信者の多くも同じように悲惨な状況に翻弄される。 ここまで複雑で混迷した事態を冷徹に表現する高橋に「高橋教の教祖」を感じる。 それは邪宗の教祖ではなく、共に苦難に向きあおうとする「さもありなむ教」のリーダーである。
日本の社会にも戦後、いくつかの新興宗教勢力の勃興と消滅があった。 武装闘争をかかげ、戦争に突入しようとする不穏当な集団もあった。「ひのもと救霊会」は単なる絵空事ではない。 その後の日本社会に潜む大きなうねりを感じて、この小説を読み返せば、人の心、または集団に潜む深層意識をえぐり出すことが出来よう。 これまでとは全く違った読み方が出来る気がする。 創造力をかき立てる一大河小説である。
小松左京が書き残している。
小松:「今度の「邪宗門」な――ええぞ。 すごくええ。 何回ぐらいつづくんや」
高橋:「編集部が、何千枚でも書きたいだけ書け、言うてくれるねん。 そう言われると、うれしうて、うれしうてな」
小松:「お前、俺のアパッチのやり方をパクッたんとちゃうか? そやろ」
高橋:「ばれたか」‥‥‥
うれしいことに彼らの会話はベタベタの関西弁である。 ますます親近感を覚える。(このころ、友人の小松左京は「日本アパッチ族」という大阪を舞台にした痛快・破天荒な小説を発表し、一躍、時代の寵児になっていた。)
「対談:三島由紀夫vs高橋和巳、大いなる過渡期の論理(1969年夏)」
高橋は文人としての三島由紀夫をこよなく尊敬し、彼の審美的な文章に陶酔していた。 高橋は長年、三島との対談を希望していた。 1969年、文人者として芽を出した高橋にその機会が巡って来た。 この対談は、その年の「潮」の11月号にスクープ掲載された。 文武両道を歩む三島と、大学を憂慮し全学連(全共闘)を支持し、「悲の器」で文壇に登場した新人・高橋という異色の組み合わせであった。
この対談が行われる少し前の1969年5月に、三島は東京大学全共闘の集会に呼ばれ、「観念語が連射され、怒号で応酬しあうが、じつは和気あいあいの対決(団交)」(サンケイ新聞)を体験した。 (会場の入り口にはゴリラの漫画絵の看板が立てられ、飼育料(入場料)として参加者の学生に100円以上を申し受けていた。 集会当日の夜にはTV 放送があり、後日、朝日ソノラマから激論(?)を録音したソノシートが発売された。)
対談が行われた当日、消化器系統の疾患で病んでいた高橋は、一口のジュースを口にして対談に臨んだ。 一方の三島は、彼の美学の結実作である「天人五衰」の最終巻「豊饒の海」の構想をほゞ固め、もともとコンプレックスを抱いていた虚弱な体を、ボディビルで強靭な体躯に改造し、人生の絶頂期にあった。
三島:「‥‥全学連のやっていることで、戦局を変えるようなことは、なにひとつやっていませんよ。 少なくとも正義運動だとしたら、それは政治じゃない。 政治じゃなかったら効果なんか考えるべきじゃない。 無効でいいんだ。 無効でいいならば何千万人に知られるという事は考える必要はないんだ。 ‥‥言葉を刻むように、行為を刻むべきだよ。 彼らは言葉を信じないから行為を刻めないんじゃないか。」
高橋:「それは彼ら自身も感じはじめているんじゃないですか。 納得しないものは何もしない戦後の民主主義のいい面を持っていますから、極限状況をつくり出して,耐えて見せるか、自滅するかというところまで急激に行くかどうかわかりませんけど、何度かやっているうちに無効性に気が付いてきた。 ‥‥なかには、軍事訓練云々をやらんといかんというセクトもあるようです。」 この後、高橋は、中国の辛亥革命の中で起こった様々な戦術上の議論(空間的解放区を成功させた)、その時に革命勢力の果たした役割などを解説する。
話は変わって、自民党論に議論が及ぶ。
三島:「高橋さん、自民党は国民にイチかバチか選択させる自信があると思いますか。」
高橋:「ないんじゃないかと思います、それは。 日本人がこれまで自民党を選んできたのは、はっきり計算したうえで庶民の人々が選んでいるのであって、進歩的文化人の言うように意識が低いからじゃない。 自民党というのは、いろいろな面で放っといてくれるわけですよ。 放っといてくれる政党として選んでいるんじゃないかと思うんです。」
三島:「確かにそうだ。」
高橋:「人間というのは無限の適応力を持っているので、政治的な強権でもってそういうふうに畸型に押し込むのは困るのですが、アレッと思うような考え方がふいに出て来て、しかもそれが急速に一般化するということは、割合ありそうな気がしますよ。」
三島:「それは現に起こったんですね、日本でも。 これは必ずしも人工的に起こったとは思わない。 偽善はいつかばれるというだけのことで、全共闘がやっていなくても、戦後二十年の偽善はまた別の形で露呈したのでしょう。 そしてまた、また新しい嘘や偽善が山ほどできてきますよ。 また、十年もすれば、ばれてくるでしょう。」
起伏に富んだ対談の一部の引用からだけでは、その場の緊張感は伝えにくいが、両者は執筆という行為を共有し、文字を刻む楽しさと苦しさ、そしてその限界を知っていた。 過激な言葉の応酬はなく、お互いの洞察力を探りあう大人の会話であった。 ただ、三島は、この対談の翌年の11月に自衛隊駐屯地に乱入し、衝撃的な割腹自殺を遂げる。 一方、高橋はさらに、その翌年の1971年5月に闘病叶わず病死する。 この二人の対談の陰には“死”が迫っていたことを、後に我々は知るのである。
1968年のはじめ、東京大学・医学部のストライキが泥沼化・長期化するに従い、大学を取り巻く状況は教授会の専制支配体制への疑問や、学生の自治要求などにエスカレートし、やがて全国に波及していった。 大学当局と学生との意見交換会は、要求の請願から、やがて団体交渉という怒号が飛び交う場へと変質していった。 学生の間では、フランスの5月革命との連帯を主張するセクトや、中国の文化大革命を賞賛するなど、様々な主張が交錯した。 次第に、全共闘運動は目標が四散する様相を呈し、収束する気配は見えなかった。 この様な中、高橋は(京都大学の)学生の、とりわけ全共闘の運動に支持を寄せ、一方で、だんまりを決めこむ多くの教官達(教授会)からは離れていった。 そして、1969年の3月には大学に辞表を提出し、自らの立ち位置を明確にした。 混迷する大学と決別した高橋は、これまでほとんど発信されることのなかった大学内の状況を彼の視点から報告した。 その著「わが解体」は、この年の「文芸」6~10月号に連載され、当時の混乱する教授会や、学生組織内の様々な議論が知られるようになった。 一方で、この連載の後半では、高橋自身の体を蝕んでいる「絶対安静と絶食」を繰り返す病気の経過が箇条書きで報告され、このことは関係者や読者に大変な衝撃を与えることになった。
「わが解体」は、これまでの高橋の緻密に推敲された文章とは違って、経時的に事実を淡々と記述している。 つとめて冷静に事実経過を報告しようとしたのである。 また病気の経過については、彼の母や妻が残した日誌によるところが大きい。 ここに至って、高橋は、もはや文章を推敲する気力の限界にあったと思わせるほどに事態は切迫している。
『二年前、創作も批評も研究も、等しく時代の文学不可欠の構成要素ながら、その内部に占める比重を大きく転換させる決意をして京都大学に赴任したとき、私は母校の学風に対する信仰に近い幻想を持っていた。 そしてわずか二年後のいま、確かに私を育ててくれた母校への思想的決別の文章を綴ろうとしている。 肉体疲労し、神経はズタズタになり、従来のようには筆も進まず、読書も殆ど出来ぬ支離滅裂の状態であるゆえに、その訣別の辞も荘重重厚である事などは到底望みえないが、心離れようとする悲哀の瞬間にこそ、執着の際には見えぬことの本質がより鮮明に洞察されるということもありうる。』
『京都大学の文学部では、教授会とストライキ実行委員会とのパイプが切れてしまってから、教授会は学内では行われず学外で点々と所在をかえながら秘密裡に行われることになった。 ‥‥その秘密教授会の会場を学生たちが包囲したことで、後に誰か教授会内部の者で学生たちに日時と会場を通報し、攪乱を謀ったものがいるのではないかという疑心暗鬼に教授諸氏がとらわれたからだった。 そしてそういう事が問題になるとすれば、真先に疑われるのは全共闘支持の立場を表明している孤立者である私だった。』
ある日、学外教授会の終了後、路上で相当時間、教授達を包囲して学生たちの糾弾があった。 様々な疑念と猜疑心に取り囲まれていた高橋は、迂闊にも 『‥‥‥私はO君のことで連絡すべきことがあり、そこに来ていたK君とちょっと立ち話をした。 そしてそれがまたいけなかったのだ。誰が、教授会の場所と日時を学生に通報したのか。 疑心暗鬼になっていた人々の目に、デモ隊の一員に近寄って行った私の行為は別な意味をもって映ってしまったのだった。』
他の学部、他大学の経過についても把握しているところを詳しく報告している。 最後に締めくくるのは、 『そして恐らくその全過程を完全に、書ききったとき、まぎれもなく、私自身は解体する。 考えてみれば、これまで、文弱な性格のゆえもあって、あまりあからさまな敵対者は身辺に持たなかった。 人生の半ばに到る経歴上の歩みも、どちらかと言えば、知己に恵まれて幸運であったと言えるだろう。 だが、全国の学園闘争から言えば、些細な事件にすぎないとはいえ、内紛というものが避け難くもつ、芋蔓式に連なった憂鬱な人間関係のからみあいとその矛盾があばかれれば、芋蔓式につらなるものゆえに、生涯許されざる不倶戴天の敵対ともなるだろうし、また他者に加えた批判は、必ず自らに照り返すゆえに、同時にそれは自らのよって立つ地盤を奪うことにもなるはずである。 なぜこんなことになったのか。 なりつつあるのか。 数か月前の自分と比較して今昔の感に耐えないが、しかし誰も恨むことはない。 自ら選んだ自己解体の道なのであるから。』 壮絶な自己解体の表明である。 言葉を失う。
つづいて「わが解体」は最終章「三度目の敗北―闘病の記―」に続く。
『四月三十日(木)入院。 電車ストの日、車混乱して鎌倉東京間に三時間かかる。 部屋番号二六二五、東京女子医大消化器センター。 午後三時より病状悪化。 間歇的激痛。 医師の問診、触診、鎮痛剤注射。 ブドウ糖点滴。
五月一日(金)朝五時より尿のフィッシュバーグ濃縮試験。 七時半より尿によるPSP腎機能検査。 便の検査。 血便。 点滴。 高圧浣腸二回、十一時半、十二時半。 大腸レントゲン、肛門よりバリウム、苦痛甚だし。 夕刻、炎症性大腸狭窄と判明。 二段階に分けて手術と決定。 第一段階の手術(腹部に穴をあけ、便を流し出すための手術)は明日午前中と決定。 夜、吐き気、絶食、鎮痛剤三種。 手術準備の剃毛、その間も苦痛に輾転反側‥‥‥(以下、略)』 淡々と病状の変化が記される。
『‥‥手術前後の、かすかなる思念の総ては今は伝ええず、また直叙形で期すべきことでもないが、ただ一つ、何故か想起する事象が少年期に限られた記憶の蘇りのあいだに、大学時代からの友人小松左京の言葉が何度か浮かんで消えた事だけはいっていいだろう。 いつのことだったか。 戦後の解放気分が、朝鮮戦争をさかいに急速に閉塞感にかわってゆき、学生運動も共産党分裂のあおりを食って瓦解していった時期、場所は何処でだったかはっきりと覚えないが、彼は「おれたちは二度負けた」といったことがあった。 一度目は、言うまでもなく一九四五年の敗戦。 二度目は、日本の社会及び国家の構造を戦前・戦中とは全く異なったものに組みかえるべき運動の最初の挫折。 ‥‥(私は運動の)渦中にいた友人ほどの痛切な敗北の実感はその当時なかったはずだが、奇妙にその言葉が、ある重みを伴って蘇生し、病中の悲哀をかきたてた。』
瀕死の床にありながら、高橋の脳裏にはますます鋭敏な思考が巡る。 二回の敗北に続いて、次に来る「三度目の敗北――死」を覚悟して。
‥‥住み果てぬ世にみにくき姿を待ち得て、何かはせむ。命長ければ
辱(はじ)多し。
長くとも、四十(よそじ)に足らぬほどにて死なんこそ、めやすかるべけれ。
兼好法師によると、「四十歳という年齢は、人生の「清」・「濁」を分かつ分水嶺ならぬ、分水齢」らしい。 高橋は三十九歳で亡くなった。 そして、それから五十年がたった。
もし、高橋が四十路を過ぎて生き、作家活動を続けていたら、どのような作品を残しただろう。 中国を題材にした、高橋にしか書けない世界を描いただろうか? やはり、奈落の底を覗き見する物語が続くのか? 私は兼好師には同意しない。 高橋の「三十九歳の死」はどう考えても、あまりにも惜しい。
<参考文献> 高橋和巳作品集(全9巻、別巻1) 河出書房新社(1970年)。
(完)