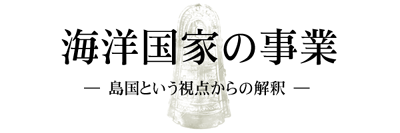|
縄文国家の存在を示唆する痕跡に関して話をすすめるが、まずはその活動実態を示すいくつかの事業事績を見て行きたい。
目的は、もちろん前章からの縄文国家をさらに確かなものとすることであるが、同時に、縄文期から弥生に続く国家が、どのような民によって創られ、そして運営されてきたのか、その社会を支える制度とはいかなるものであったか、を探ることも視野に入れている。
そのための第一の手掛かりは稲作だ。日本書紀成立の前時代、わが国に稲作という食糧資源が登場する。計画的生産が可能で、貯蔵にも適した、国家財政の礎となる技術だと言われている事業である。この稲作は、誰がいつどこでどのようにしてわが国に導入されたのかをテーマとしたい。
■稲作の伝来の「真」解釈
稲作伝来の定説を簡単に紹介する。
伝来時期:紀元前4〜5世紀頃
※時期に関しては、放射性炭素年代測定から、もっと古い時期だとするデータも上がっている
伝来場所:北部九州 ※北九州から各地に伝播したとされる
伝来経路:中国から朝鮮半島を経由し、北部九州に伝播
媒介者:水稲耕作の技術をもった渡来人の集団 ※彼らが弥生人だとされている
伝来の手段:偶然の漂着、或いは集団移住
概ね以上のようなポイントで語られる。
この項目の中で、「媒介」と想定された渡来人の集団がやがて弥生人になったことは、別項で述べたように、すでに成り立たないことが判明している。
そしてもうひとつ、伝来の「経路」に関しても、それを否定する科学的データが発表されているので紹介しておきたい。
稲作は中国から朝鮮半島を経て日本に伝わったというのが従来から堅く信じられてきた伝達ルートである。また、この朝鮮半島を経由したという点が、距離優位の観点に基づき、北九州への伝播を考える上の左証となったポイントなのだが、DNA分析の結果、日本産のジャポニカは朝鮮半島を経ずに、中国の東南部から直接日本に伝来し、さらに、日本で品種改良されたものが、後に朝鮮半島に流れたということまでが研究によって明らかにされたというのである。
その根拠となった研究結果は次のようなものだ。
ひとつは、稲作の起源に関してだが、日本の稲作は陸稲で約6500〜7000年前、水稲が3200年前くらいまで辿れると云うのだ。それに比べ朝鮮半島側の水稲は日本に遅れること1700年。紀元5〜6世紀程度までしか遡れないらしい。弥生どころか日本の古墳時代の話である。
もう一点は、遺伝子構成。日本の古代米のDNAを分析してみたところ、満州系遺伝子の交雑は多く見受けられたが、朝鮮系遺伝子はまったく確認できなかったと云うのである。
以上の結果は水稲伝来ルートを論じる上で決定的な裏付けとなるものだろう。
稲作が渡来系(朝鮮)民族によってもたらされ、持ち込んだ民族が弥生時代という新しい国家を伴う社会を形成したという従来のお話はこれではなにひとつ成り立つ余地がないわけだ。つまり、多くの科学的裏付けを持つ研究によって、多く語らずとも、すでに日本の水稲が朝鮮半島から伝来したという説は成立する足場をすべて失っていたことになるのだ。
以上の改められたベースを踏まえたうえで稲作をもう一度検討してゆこう
■ワープホールとしての海域
稲作が朝鮮半島からの伝播ではないという事実が強烈に印象付けるのは次のことだ。
「稲作に限らず技術や文物の伝播は、発信地が遠い地域であっても、間の国を通り抜けて飛び火することもある」
という点である。
つまり、隣国であることは決して絶対条件ではないということだ。特に島国のわが国には云えることである。
これまでの定説が意識して来なかったことは、わが国が他国から海によって隔てられていることであろう。海と云うものは想像以上の「障壁」であると同時に、どの国とも直接繋がることができる「ワープホール」でもあるのだ。その認識が欠如していたのだ。陸続きの国であれば、隣り合う立地は絶対的な優位条件であると云えるかもしれないが、「海」となると状況はまったく違うものになる。
中国から水稲が直接伝わったとすると、通らねばならないルートは東シナ海、対馬海峡がそれに該当する。海が「障壁」であると書いたが、その航路が決して穏やかではないことは鑑真の渡日譚でも実感できるだろう。水稲が朝鮮半島を経由していないということは、この荒々しい東シナ海を渡って伝わったことになる。

中国と日本の間に流れる海流は右図のようになっている。
大陸から離れる海流は朝鮮半島に沿ってまた中国に戻るものと、太平洋に向かって流れ、日本列島を北上するものとに分かれる。対馬海峡に流れ込むのはその中の一部の海流だけである。わが国の大陸への航路は、朝鮮半島に沿って海岸線を辿るルートと、沖縄の島々を伝ってから西に向かうルートの二つがあった。その二つが選ばれた理由として、食料や水分補給の必要性や航海の安全性からということは当然あげられるが、海という環境を最大限利用することを考えると、必然的に海流に沿ったこの二つのルートが低コスト故に選ばれたであろうことは想像に難くない。
そのような意味も踏まえて、この海流を見る限り、稲作技術が朝鮮半島に到着する以前に、偶然我が国に流れ着いたという可能性は限りなくゼロに近く、海流を見る限り、流れ着くとしたらわが国でなく、まず朝鮮半島なのである。だからといって、日本を目指してやってきた、という考えも成り立つわけではない。なぜなら、わざわざ他国の発展のために、危険な東シナ海を渡って、無償で優れた技術をもたらすというような慈善は誰も行わない。国家間での技術の提供とは、自国の利益につながるからこそ行われる。いわゆる互恵的利他主義という行動である。そのことは、稲作が、陸続きの朝鮮半島にさえ5世紀になるまで伝わらなかったという事実がはっきりと示しているではないか。朝鮮諸国を飛び越して、わが国だけに友好的であってくれたなどという都合のいい話などない。その矛盾を立証出来ない限り、享受説は決して成り立たない。
■伝来でなく「求めた」稲作
では、朝鮮半島からの伝播でもなく、大陸から海を渡って伝わった可能性もないとすれば、どうしてわが国は稲作という技術を手に入れたのだろうか。そんな疑問の声が聞こえるが、その答えは、ここまで執拗なまで語った「流通」に隠されている。
黒曜石、翡翠、縄文土器の国境を越えた分布が物語るように、日本は、国内はもちろん、ロシア、朝鮮、中国などへ、資源の輸出、土器技術の発信など、石器時代から縄文期を通して、交流・交易を行っていたことが明らかになっている。その貿易や国交を担っていたのはどのような集団であったか。それは考えるまでもなく、太平洋、オホーツク、日本海、東シナ海、これらの海を縦横無尽に航海していた海洋系氏族しかないだろう。
そのような広範囲に及ぶ交易ネットワークを有する海洋民族が、何度となく訪れた中国の地に、稲作と云う素晴らしい財源があることを知りながら、それを見て見ぬふりをして、大陸から偶然に素晴らしい技術を持ってやってきてもらう僥倖をじっと待っていたという光景など考えられるだろうか。ありえないことだ。彼らは常に貪欲に情報を求め、それを利益に変えるために、海原を駆け巡っていたのである。
稲作と云う技術、それも当然、わが国の海上ネットワークを構築していた集団がいち早くその価値に気付き、自らの判断でもたらしたものであるはずである。
他国との間に陸路を持たない日本において、国外の最新情報を海洋氏族が真っ先に握ることになるということは疑う余地のない事実である。稲作だけでなく、後の金属器など新しい技術も海洋氏族が「求めて」、技術者とともに日本に持ち帰ったものであるはずだ。
以上の考えは、想像でも、個人的な思い込みでもない。むしろ「摂理」といってもよいかもしれない。それを証明するのは、「陸稲」の起源である。
近年注目されるプラント・オパールの研究で、水稲が始まる遥か以前の縄文前期にあたる紀元前4000年頃の島根県と岡山県の遺跡においてプラント・オパールが発見され、当時すでに陸稲栽培が行われていたことが判明したのである。
プラント・オパールの調査結果は次のようなものだ。
縄文前期 岡山 朝寝鼻貝塚
縄文中期 岡山 姫笹原、熊本 古閑原貝塚、鹿児島 鹿児島大学、倉敷市 矢部貝塚・福田貝塚、備前市 長縄手
縄文後期 甘木市 大原野、福岡県 法華原、総社市 南溝手、岡山市 津島岡大、福井県 浜島、八戸市 風張
縄文晩期 福岡 四箇東、山鹿市 東鍋田、熊本 ワクド石、倉敷市 上東
水稲栽培の発祥地とされる北部九州は、陸稲においては瀬戸内地方と比較してもまだまだ後になる。縄文中期になりようやく九州にも広がり、そこから縄文後期には日本海側の福井、東北の北端八戸にまで陸稲生産が広がっていたことが示されている。「伝播」というメカニズムにおいては「陸稲」も「水稲」も同じである。大陸に近い九州北部から徐々に広がったという、安易に距離優位性に依る考えが明らかに間違いであったことがここから読み取れる。そして、この陸稲の伝播ルートと分布領域を見れば、それをもたらしたのが海洋氏族であることが一目瞭然にわかるであろう。
■水稲は如何に普及したのか
陸稲栽培という農業生産がやがて新たな技術である水稲へと進んでいくことは、自然な流れである。その水稲を九州北部の縄文人だけが他の地域に知られることなく取り入れたということは、これまで見てきた流通国家である我が国においてはあり得ないであろう。技術は九州の民ではなく、海を支配する海洋氏族が真っ先に入手できるのである。
陸稲が主流であった縄文社会は、新たな技術として海洋氏族がもたらした水稲栽培を全国規模で取り入れることを目指したが、水稲栽培のための熱帯ジャポニカはその名の通り気温が高い地域、当時は九州、或いは四国など南に位置する地域でしか育たなかった。大阪の高槻からも約2500年前の水田遺跡が発見されていることから、九州、四国から程なくして、やはり気候的に適した関西の太平洋側でも水田が開かれたのであろう。
その後、縄文社会を支える国家はわが国の全域に水稲を広めるため、熱帯ジャポニカを温帯ジャポニカへと気長に改良を行い、涼しい地域でも栽培できる品種に変えて行き、その甲斐あって、水稲は青森という北辺にまで広がるのである。そこにかかった月日は導入開始の縄文晩期から数えて3〜400年後、紀元前後の時代に及ぶ長大な事業である。
前テーマで、日本書紀の神代が弥生前期から中期頃の話である可能性を述べたが、まさにその頃進められていた水稲の気長な国内への普及政策が、大國主と少彦名神の説話となって伝わっているのである。そして、神在月の伝承。稲の収穫期にあたる旧暦10月、出雲に全国の神が集まるという言い伝えも、稲作が統一国家による普及事業であったことをリアルに物語っているのではないだろうか。
■列島の産業と力関係
日本書紀の神代には面白い事実が記されている。冒頭にも紹介した素盞嗚神の説話だが、彼は海原を治めていた。月読命、天照大神、素盞嗚神が与えられた夜・海・高天原の統治権はある意味、権力分立政策、現在の省庁の前身と考えられる。そこで素盞嗚神は海原を与えられたにもかかわらず、母の国である根の国を求める。根の国は恐らく東海地方である。根の国に向かう前に、素盞嗚神は天国の姉、天照大神に会いに行くが、そこで水稲の田植え期や収穫期を狙って、水田を荒らしまわるのである。しかし天照大神は武力で勝る素盞嗚神に屈するしかなく、抵抗も出来ないまま岩戸に隠れるのである。この説話が重要な意味を持つのは、水稲栽培の導入が軍事力と直接結びついてない、そのような事実を伝えている点である。
従来説では、稲作が安定した食料獲得をもたらした結果、それが富国強兵へとつながったとするが、稲作を精励する天国は、海洋氏族である素盞嗚神に抵抗することも出来ずただただ屈するだけだったのである。
考えてみればそれは当然のことである。
稲作は収穫までに準備期間を含めれば一年という長い時間を要する。また、農家の方ならわかるが、稲作の作業量の大部分は田植えや刈り取りの一時期に集中する。その時期に限り、家族・親戚、或いは地域で協力し、ローテーションを決め、短期間で一気に地域の田植え・刈り取り、さらに脱穀などを行わなくてはならない。農家でなくとも季節商品を扱っている企業などでも繁忙月と閑散月は極端に表れる。その場合は派遣社員、アルバイトなど人員を急遽大幅に増やすことで乗り切るという方法を採らざるを得ない。稲作の繁忙月、家族総出による田植え、刈取りを強いられるこの時期に、もし敵軍が襲ってきたらどうだろう。成人男性を徴兵し迎撃すれば、農作業が停滞し、その上、田畑が戦場となり、収穫前の作物は踏み荒らされる。
よしんば敵兵を追い払うことが出来たとしても、それは決して勝利などでなく、次年度の兵糧を失う敗戦同等の結果となるのである。このような虚弱体質が簡単に予想できる水稲社会が、交戦好きな海洋氏族に勝てるだろうか。
中国の歴史において、春秋時代、五胡十六国、三国志、様々な戦いが描かれるが、戦いは相手の稲が育つ頃を狙って行われる。戦闘には脱穀器なども武器とともに持ち込み、刈り取り直前に敵国に攻め込んで、城を包囲する。包囲しているから、敵国の穀物は刈り放題である。ゆっくりと敵の農作物を収穫して、包囲を続ける、というように兵糧は敵の領地で賄うのが戦争の常套手段であった。それは戦いの定石。誰もが考え付く初歩的な作戦である。つまり、稲作を導入したからと云って、国力が圧倒的に有利になることはないということなのである。
このように農耕、特に稲作は決定的な弱点を持っている。働けど一年後にしか実らない稲の収穫を待って悠長に構えていたら、その苦労して植え付けた稲に、海の民が収穫期を狙ってやってきたらひとたまりもない。圧倒的に弱い立場なのである。
それに比べ海の民は一年を通して安定して運搬で利益を上げることが出来る。その上、彼らの主たる生業である漁労は、乾物も豊富にあったであろうが、その日に揚げてすぐに食す。つまり、兵糧もすぐに調達できる利点もあるのだ。
大國主が素盞嗚神と手を結んだのも、頷ける。また、海彦山彦の説話でも、山彦が同盟したのは海神であった。守りである稲作産業は、機動力のある海軍を保有する勢力の防備なくして成り立たない危うさを持っている。その日本書紀に書かれた素盞嗚神の伝承も当時頻繁に起こっていた有事の史実を反映したものなのであろう。
弥生時代になり、環濠集落が発生する。その成り立ちを戦争の始まりと考え、その時点に国家の誕生を想定する考えがあるが、それほど単純ではない。戦争は稲作以前からあったものだ。ただし、環濠を作ってまで守るべき「保管財産」がなかっただけである。稲作が始まれば収穫した稲を蓄える場所が必要となる。それは今後一年の大切な食料となる。環濠集落とはその財産を守るためのものだ。先程書いたように、海の民によって略奪されることもある。或いは山(陸)の民同士で奪い合う場合もある。稲作の発展によって戦いの形式が変わったのである。それが環濠集落を発生させた要因なのである。
■国家事業を伝える記録
素戔嗚の説話にはまだ続きがある。この説話は、古代国家のまた違う側面を伝えている。素盞嗚神の暴挙の結果、天照は神隠れする。そして天照と組んだ高皇産霊が統べる政治組織、いわゆる八百万の神によって、素盞嗚神は根の国に追いやられる。これは日本の片隅の小さな部族の戦いを描いたものではない。集権国家(八百万神)が合議の上で、素盞嗚神の狼藉を罰するシーンである。
ただ、この説話は、素盞嗚神という国家が高皇産霊の国家に屈したという話ではない。国と国の戦いだとは語られていない。ここから読み取れるのは、水田耕作が重要な国家プロジェクトであったこと。そして、日本という連合体において各勢力自身がそれぞれ水稲政策を推し進めていく過程で、勢力間で妨害を伴うような抗争があったこと。そしてそれを連合国家の議会を構成する「八百万神」が結束して安定的生産活動を期して阻止したこと。そのような古代の一時的な姿がこの説話には残されているのである。
しかし、話はそこで終わらない。国家事業を伝える記事はさらに続く。根の国に追いやられる素盞嗚神であるが、彼もまた別の国家プロジェクトの責任者であった。史家にはピンとこない話だと思うが、企業は常に目標の達成が要求される。それが稲作であれば単位面積当たりの収穫量であり、貿易であれば差益である。素盞嗚神が伊弉諾神の下で、海原を統べる権益を一手に握っていたことは、海上交通事業の発展を要求される立場にあったことを示す。その業務使命に応えるべく行ったのが、新羅に渡り、杉などの材木の苗を持ち帰り、配下の五十猛とともに進めた植樹事業である。
植樹と云えば現在の感覚からだと「建築資材」というイメージを持たれるが、もちろんこの当時も建築資材としての需要もあったが、それは一部の使い道であり、木材の主な利用目的というのは造船事業である。杉やヒノキとは海洋国家ならではの用途であろう。特に船舶の場合、船体構造の中心となる龍骨(キール)には真っすぐ伸びた木材しか適さない。もちろん接ぎ木では強度が保てないため、一本から切り出す。また、船体を覆う棚板にせよ梁にせよ、目地止めを確実に行うにはすらっと伸びた木材が求められる。
雑木林やブナ林が占めていた日本では造船のための材木が不足気味だったと云える。日本書紀の神代に、最初に現れる船は「?樟船」で、これはクスノキを主材とする船だ。クスノキは大木になったとしても、高さとしてはそれほどではない。そこから長い一本の木材は得られないのである。そのために素盞嗚神が実施したのが「杉・ヒノキ」の植林である。
素盞嗚神の説話の後には、熊野諸手船(亦名天鴿船)が出現する。この船はガレー船のように両舷に多数の漕手を並べて推進するタイプのもので、積み荷や兵も搭載するためかなり大きな船であったであろう。まさに植樹がもたらした成果である。
この時代、海上交通をより発展させ、輸送能力を高めることが国力を高める重要な課題であった。日本書紀においても、造船記事は多く現れる。
崇阳十七年秋七月丙午朔、詔曰、船者天下之要用也。今海邊之民、由無船以甚苦歩運。其令諸國、俾造船舶。冬十月、始造船舶。
応神五年冬十月、科伊豆國、令造船。
仁徳六十二年夏五月、遠江國司表上言、有大樹、自大井河流之、停于河曲。其大十圍。本壹以末兩。時遣倭直吾子籠令造船。
皇極元年九月 復課諸國、使造船舶。
孝鄹元年冬十月 遣倭漢直縣・白髮部連鐙・難波吉士胡床、於安藝國、使造百濟舶二隻。
素盞嗚神は「此阳性惡、常好哭恚。國民多死。青山爲枯。」と表現されているように、造船のため一時的に貴重な森を壊したのかもしれない。その意味で確かに山の民にとっては、木を伐採し青山を枯らす「性悪」な神であっただろう。しかし、国家としては造船という国策を見事発展に導いた英雄であり、枯山の対策として行った植樹という事業は今日までわが国の林業の礎となっているのである。
このように国家の存在を認めれば、単なる作り話とされてきた書紀の記述の中に、当時の公共事業や経済活動の姿がリアルに描かれていることがわかってくる。神代は、わが国が様々な政策を実施してゆく過程を記述した貴重な「記録」でもあるわけだ。
|