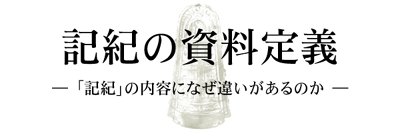|
日本の古代を伝える二大史書である古事記と日本書紀。この二書の比較研究で、両書の間に多くの違いがあることは既に知られているが、なぜ、そのような違いが生じるのか。
「神武東征」を語るにはこの両書を避けて通れない。この両書の記述があるからこそ「神武東征」があるからだ。であれば、両書の間の隔たりは、単なる「違い」で捨て置く訳にはいかない。古事記とは何か、日本書紀とは何か、八年という短期間に同じ王朝がふたつの史書を編纂した。そこにどのような意味があるのか、そして記紀それぞれの役割は何なのか、これまで多くの史家によって研究がなされ、ほぼその定義は出尽くされた感もある。一般的にはそう思われている。しかし、その定義は果たして正しいのであろうか。そこを含め、再考してみたい。
■「日本書紀」「古事記」の定義
確認のため、これまでに一般的に唱えられてきた記紀の資料性格を紹介しておく。
〔古事記〕
天皇の支配・皇位継承の正当性示す目的で国内向けに編纂された史書
〔日本書紀〕
漢文を装い、東アジアに通用する対外的な体裁をもたせた正史
かなり略した形での紹介となったが、様々に唱えられていても、このくらい短く要約できる程度の意味しか持たないのが実情だ。
この定義を見て、最初に強く受ける印象は、両書の「比較の前提」となっている考えが「古事記、日本書紀、どちらもが国史である」という無意識の先入観ではないかということだ。もちろん古事記は六国史には含められておらず、その他の史書という位置づけではあるが、定義にあたっては「日本書紀と同等の資料」として扱われているかのように見える。
従来の定義に対して、最初に否定させていただくのはこのポイントである。
両者を国史(正史)だと無意識に思い込んだからこそ、そこに「同じ日本政府が何故二種類の国史を作ったのか」という問いが生まれる。古事記は「国内向け」日本書紀は「対外的」であるという性格分けなどはまさにその結果生まれた定義であり、間違った先入観によって「国史を用途に分けて二種類編纂した」という、どこに根を持つかわからない結論に一気に飛躍させてしてしまっているのだ。
まずはその点を一度リセットし、スタート地点に立ち返って、正しい定義を述べておきたい。ただし、「鶏と卵」の問題ではないが、記紀の定義は定義付けをしたとしても、それが正しいかどうかは、まずは記紀が記述する世界を正しく把握してこそ証明されるものであるため、ここでは定義のみを示すこととしたいが、本稿の定義はこれまでの考えとは180度違うものであろう。と云っても、ここで示す定義はわたしが単にそう思ったという定義ではない。一般的な常識、そして今述べた記紀の正しい理解から導かれた結果であることを念押ししておきたい。
〔日本書紀〕は日本国の国史である
〔古事記〕は「古事」を記録した書である
以上である。
どうであろう。もし今、「そんな分かり切ったことを何を今さら云っているのだ。」と感じた方がおられるのであれば、その方は、まだ間違った解釈のままなのかもしれない。恐らくその方は、日本書紀を「倭書紀」だと理解しているのではないだろうか。
同じ勘違いは古い時代から続いている。「釈日本紀」の中に「延喜私記」からの引用が見えるが、そこに以下のような記述がある。
「又問ふ、何ぞ倭書とは云はずして日本書と云ふは如何、説に云ふ、本朝の地東極に在り、日出づる所に近し、又嘉名を取りて、仍ち日本書と号く」
この私記を記した筆者は、日本書紀を「倭国」の正史だと考えているのは明らかだ。故に、何故「倭書」でなく「日本書」としたのかを問うているのである。これこそが多くの史家、いや、すべての史家が陥っている勘違いである。
しかし、またここで疑問を持たれたのではないだろうか。日本と倭国は同じものであるのに、なぜ「倭国」の史書とするのが勘違いなのかと。よい疑問である。まさにそこが「このテーマが古代史上で最も重要な問題だ」と書いた理由でもある。
日本書紀がなぜ「日本書紀」と題されているのか。
書の標題というのは、その書そのものを最も端的に表す肩書なのである。「日本」と冠されている書物、それはその書が「日本」の史書であるからこそそう名付けられたのだ。「倭」でも「大和」でもない。これ以外の理由はない。
それは同様に、古事記にも云える。古事記は倭国の史書でもなければ、日本の史書でもない。今云ったように、書物と云うものはその内容を端的に表す書名が冠されるものだ。古事記は史書でなく「古事」を記したから「古事記」であり、先代旧事本紀も先代の旧事を、古語拾遺も古語を集めた故、その名が付けられたのである。先ほど、「一般的な常識」としたのはこのことである。書物の標題の常識、考えるまでもない当たり前のことである。
加えて、釈日本紀に見えた「嘉字(嘉名)」に関しても、一言述べておこう。
何故「日本」が「倭」の嘉名だと考えたのか。まずその発端が何であったかを推し量ると、恐らく「倭」も「日本」も「ヤマト」と訓される習慣があったからであろう。しかし、それは理屈として明らかにおかしい。日本書紀は「やまとしょき」ではなく「にほんしょき」なのである。仮に、「倭」を「やまと」と読ませて、元々が「倭書(やまとしょ)」だったとしても、「倭(大倭)」の嘉字は「日本」ではなく、「和(大和)」である。その流れから「大和書紀」とされたのであれば嘉名と云えるだろうが、冠されたのは「大和」でなく「日本」なのである。これでは嘉名変換になるはずはないのだ。つまり「倭=ヤマト=日本」という読みの符号に引きずられた結果の考えであることがわかるのだ。
その上で、もう少し踏み込んで記紀を定義するならば、以下となる
〔日本書紀〕
日本書紀とは、倭国、また大和勢力(※1)の史書ではなく、「日本国」の国史であり、日本と云う国、そこの主権者と政府が、自身の目線から、自らが関わって来た(自らの活動に関連した)歴史事績を集めて編纂した、日本国だけの歴史をしるした史書である。それ故、「倭書紀」でも「大和書紀」でもなく、「日本書紀」と題される。
(※1、大和に朝廷を置いた統治組織を意味し、天皇家を指すものではない)
〔古事記〕
古事記は国史でなく、後の日本国を統治するに至った天皇家の古事を記したものであり、その古事とは、倭国政権下において、倭国の一員として政権に参加していた自らの家系の古事、及び家系の縁起に所縁ある古事のみに特化して記録されたものである。故に「古事」の記とされる。
これが、まったく何の含みもない、純粋にそれぞれの題名と文面から導かれる記紀の資料性格である。
これまでの国学の考えとは全く違う。ひとつは「倭の国史」でなく「日本の国史」だと、倭と日本を区別した点。ふたつめは「後の日本国を統治するに至った天皇家」と天皇家と日本国を区別した点。そしてみっつめがその日本国が倭国の下位の一員だとする点。この三点がこの定義の根底となっている。
以上の性格定義は、どこに根拠があるのか、また、それをどう証明しようというのか、という点に関しては、先ほど言ったように記紀の理解が前提であるため、ここでは行うつもりはない。
当サイトにおいて以降様々なテーマをに取り上げていくが、記紀に対する新しい、そして正しい解釈が積み重なっていく過程で、自ずと上記の定義の正しさが証明されていくはずである。
少しその一端を示しておきたい。上記の定義に従うならば簡単に解ける疑問である。それは、これまで記紀両書間の差異として疑問視され、理由がまったく見えなかった問題である。正しい定義はそれらの答えも指し示してくれる。
たとえば、次のような疑問だ。
Q「天孫降臨の主導者の違い」
「記」では天照大神と高皇産霊が同等な扱いをされているが、「紀」では天照大神は出て来ず、高皇産霊だけが降臨を主導したように描かれている点
Q「天照大神の扱いの違い」
「記」では、高天原の最高神として表現されているが、「紀」では単なる日の神という扱いである点
Q「大國主の説話」
「記」は大國主の説話を多く掲載し、八千矛の神との攻防、妻問い、因幡の白兎、など「紀」には登場しない話が紹介されている点
Q「出雲の扱いの違い」
「記」では出雲大神への奉仕記事を採用しているが、「紀」では省かれ、出雲は崇敬の対象としては描かれていない点
Q「最後の天皇の違い」
「記」は「紀」と同時期、天武朝に編纂を始めたにもかかわらず推古天皇までしか扱わないが、「紀」は完成時近くの持統天皇までの事績が記されている点
Q「神代での倭の記述」
「記」の神話記事には「倭」の文字が多く現れるが、日本書紀の神代には一切出てこない点
Q「古事記に日本が現れない」
ほとんど同じ時期、すでに「日本国」が列島を統治して久しい時代に生まれた二つの「書」が、方や「日本」という国名を高らかに名乗っているにもかかわらず、古事記だけは「日本」という文字を一切拒否して「倭」と云う文字だけを頑なに使用している点。
これらの諸問題は、従来の史書定義ではただの一つも解決に導かれることはないが、今ここに示した定義であればすべてに対して無理なくその解を示してくれるはずである。その解がどのように導かれるか、当サイトの最終段階で改めて示すこととする。
|