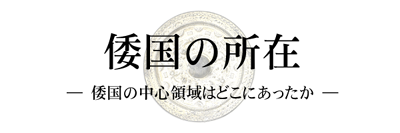|
�����ł́A�N�����T�����߂�u�`���v�̒��S�̈悪�ǂ��ł������������������B
���T�C�g�ł��u�������v�̒��ŁA�`�E���{�̓ǂ݂́A���̂܂܁u��E�ɂق�v�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��q�ׂĂ���B�܂��A���ǂ݂ɂȂ��ĂȂ��ꍇ�́A���̃e�[�}�ɐi�ޑO�Ɉ�ǂ���������Ǝv���B
�`�E���{�̓ǂ݂��]���̂悤�Ɂu��܂Ɓv�łȂ��Ƃ������ʂ́A�����炭�m���ɁA������n�̓V�c�x�z�Ƃ����Œ�T�O���ꂩ��l����������[���ƂȂ���̂ł��낤�B�܂��A�����ɁA�הn�䍑�_���ł���Ȃ�̎s�����Ă����B�������Ȃǂ���u�̂����ɐ��藧�]�n���Ȃ������ƂɂȂ�B
���̒��S�n�ł����������Ƃ̏���
�܂��B�L�I���L�����u�`���v�u�`�v���u��܂Ɓv�łȂ��A�u�킱���v�u��v�ł���̂��Ƃ���ƁA��̉����ς��̂��A�ł���B
���̂܂܃V���v���ɍl��������B�u�`�v���u��v�ł���Ƃ������Ƃ́A���R�̋A���Ƃ��āA�L�I�{���ɋL���ꂽ�u�`�v�́u�`�i��j�v�ł��邱�ƂɂȂ�B�u�`�i��j�v�Ƃ͉����B�����܂ł��Ȃ��A鰎u�Ȃǂ̊C�O�j�����]���Ƃ���́u�`���v�ȊO�ɂȂ��B
����͔���l���ł͂Ȃ��B�ނ���A���ꂱ���������Ƃ��m�[�}���ȑ��������Ɖ]����B
�킪���́u�`���v�������̂��B���̂ǂ̍��ł��Ȃ��A�C�O������u�`���v�u�`�l�v�ƌĂ�Ă������Ȃ̂ł���B���́u���v�������̒n�ŕҎ[���ꂽ�j���ɓ��X�Ɠo�ꂵ�Ă����Ƃ��Ă��A������ُ킾�Ƃ͒N�������Ȃ��ł��낤�B�`���͂��悻�V���I�܂Ŋm���ɑ��݂��Ă����B���̘`�����������Ă��������`�����j���u���{���I�v�Ɂu�`���v�����o������Ȃ����ƁA�t�ɂ��̂ق����y���Ɉُ�ł͂Ȃ����B
����܂ł̌Ñ�j�̘_�_�����Ă݂悤�B�הn�䍑�A�`�̌܉��ȂǁA�Ñ�j�����ŌJ��L����ꂽ�����̘_���́A�C�O�j���ɂ͌���ė���킪���̖���ł���u�`���v���A���̂��A�L�I�Ȃǂ킪���̎j���Ɍ����Ȃ��Ƃ����_���傫���W���Ă����B���{���I����ׂ̏��ł���Ƃ��A�^�����B�����Ă���Ƃ��A�L��ʌ��^���������Ă����̂��A���ׂĢ�`����̕s�݂����������̈��q�ƂȂ��Ă������Ƃ͊m���ł���B
�������A�^���͂����ł͂Ȃ��B�����Ƃ��Ă����̂͌����҂̕��������B���{���I�͕ʒi�u�`���v���B�������̂ł͂Ȃ������B����A�B���Ɖ]���Ӑ}�Ȃǔ��o���Ȃ��A���鏈�Ř`��������̂܂܈����Ă����̂��B�܂�A����܂ł̐S�Ȃ��ᔻ�͂��ׂāA�u�`�v���u��܂Ɓv�ƊԈ���ēǂp����Ă������ƂŔ���������Ȃ����J�ł���A�������č����̓ǂ݂����m�ɂȂ������ƂŁA���{���I�͐琔�S�N�̒����ɂ킽�����u�l�߁v���悤�₭���炷���Ƃ��ł����̂ł���B
�����͍�����{���I���^�����ƂȂ��A�f���ɓǂނ����ł悢�B�����āA���{���I���L�����u�`���v���u�킱���v�ł���Ȃ�A����܂Ř_�����₦�Ȃ������`���̏��݂����l�ɖ��炩�ɂȂ�B���{���I�ɂ����āu�`�v�͂ǂ̒n���w���Ďg���Ă��邩�B�L�������̂܂܃s�b�N�A�b�v���Ă݂悤�B
�`�����W
�`�}�D�W
�`���V�R粓�
�`���p�c�l
�`���Y��S�R��
�`�����S��铈
�`�����s�S
�`������A�×W�i�����̒n���̂��E���{�����s���w���Ƃ����j
�Z���\�L�̂��̂������o���Ă݂��B�����ɋ�B�̒n���͂Ȃ��B���ׂē����n��������Ă���B���̒n�͌��݂̓ޗnj��ł���B�܂�A���{���I�̏،�����A�������w���ޗǎ��ӂ̒n�������u�`���v�̒��S�n�ł������Ƃ������ƂɂȂ�̂��B
���̌��_�����l�A�܂����������ɒl���Ȃ����̂��B�הn�䍑��ޗǂ̒n�ɋ��߂�l�����a����Ƃ����T�O�����̍��w�������Ĉȗ������ɂ킽�菥�����Ă����̂��B�������l��������B���{�̂ǂ̎������Ђ������Ă��A�䂪���̒��S�n�͓ޗǎ��ӂɂ������߂��Ȃ��Ƃ���������������������������A�琔�S�N�̊ԁA���̍l�����h�炪�Ȃ������̂ł���B
�����āA�ŐV�̉Ȋw�������猩�������Ñ�̎����A��n�Ɏc���ꂽ�l�Êw�����ȂǁA���ׂĂ̋L�^�Ɍ����Ȃ܂łɂ��̌��ʂɍ��v����̂ł���B
�����炢���Ă݂悤�B
�@�Ñ�l��DNA�������ʂ���́A�ꕶ���Ɩ퐶���ł̐l��̒f��͔F�߂�ꂸ�A�퐶����͓ꕶ������̓��������A�܂�ꕶ�l�ɂ��c�܂�Ă������Ƃ��L�͂ƂȂ����B�i���Q�Ɓj
�A�܂��A�Ί펞��Ȍ�A�ꕶ���ɂ����Ă̗��l�����z�͓����{�ɑ傫�����Ă���A�䂪���������{�𒆐S�Ƃ��Ĕ��W���Ă������Ƃ���������f�����B�����D�ʂ̍\�}�͖퐶���ȍ~���ς��Ă��炸�A�����̗͊W�͈�т��ē����{�Ώd���ێ�����Ă����Ɖ]����B�i���Q�Ɓj
�B�Ί펞���荕�j�ɑ�\����鎑���������Ɏ~�܂炸�C�O�܂Ō��Ղ���Ă����悤�ɁA�ɂ͌Ñ��荂�x�ȗ��ʖԂ��\�z����Ă����B���ʂ͎�ɊC�m�����ɂ���čs���A�ނ�͑S�������S�ɍq�s���邽�߂̌f�����ɂ��ʐM�V�X�e����Z�������Ă����B�i���Q�Ɓj
�C���ʂ�ʐM�V�X�e���̑��݂���A�ɂ͂����̐��x������I�ɉ^�c���鍑�Ƃ����݂����ƍl������B�i���Q�Ɓj
���̂悤�ɉ䂪���ɂ͌Â����獑�Ƃ����݂��Ă����B�����āA�Ί�E�ꕶ������l����ς�炸�A�̗̓o�����X�ɂ��傫�ȕϓ��Ȃ��퐶�E�Õ�����Ɏ������Ƃ������Ƃ́A���̍��Ƃ̑̐��A�܂����̑g���E�\���l����ς��Ȃ��������Ƃ��Ӗ�����B
�퐶�Ɖ]���Δނ̗L����鰎u�̓�����ł���B���̎���A�䂪���́u�`���v�ƔF�m����Ă���B�ł���A���ɂ�������䂪���ׂĂ������Ƃ������u�`���v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�A�̐l�����z���ڂ������ߋE�`�����{��n�ՂɌN�Ղ��Ă��������u�`���v�ł���Ƃ������Ƃ́A���̏��݂��A�L�I���،�����悤�ɓޗǂ̒n�Ƃ���邱�Ƃ́A�̗��j��������R�Ȃ��Ƃł���킯���B
���C�O�j���̏،����Ƃ̑���
�����Ƃ��A��ɓ��L����܂ł��Ȃ��A��X�́A�`�����퐶�������͂邩�ȑO�ɑ��݂��Ă������Ƃ��悭�m���Ă���͂����B
���Ƃ��A�����n���u�͎��̂悤�Ɍ��B
�u�٘Q�C���L�`�l�@��ਕS�P���@�ȍΎ����ٌ��]�v�i��F�v��y�Q�C���ɘ`�l�L��A����ĕS�]�����ׂ��A�Ύ����Ȃ��ė���Č������Ɖ]�Ӂj
���̊����̋L���́A�I���O�̘b��`����L�^�ł���B
�܂��A�u�_�t�v�ł�
�u�����V�������@�`�l����鬑��v�i��F���̎��A�V�������ɂ��āA�`�l������Ē����������j
�u�������@�z����賁@�`�l�v鬁v�i��F�����̎��A�z�ւ�賂������A�`�l�͒������v���j
�u�����V������ �z���ٔ�� �`�l�v鬑� �H��賕�鬑� �s�\�����v�i��F���̎��͓V�������A�z�ւ͔�賂������A�`�l��鬑����v���B��賂�H��鬑��p������A�������������킸�j
���͋I�N�O��Z�l�Z�N������O��ܘZ�N���̉����ł���B�����i�I���O��Z���N�`��Z�Z��N���j�͂��̎��̓��ڂ̉��ŁA�݈ʔN��͋I���O��Z�Z�Z�N�O��ł���B�䂪���̗��j�삷�铮�@���Ȃ������̋L���ł���B���́u���v�����{�Ɂu�`�l�i�`���j�v���݂�A�e�������������Ƃ�`���Ă���̂ł���B
���̋q�ϓI�ȋL�q�́A�`�����A�I���O��Z�Z�Z�N���̓ꕶ����ɁA���łɒ��v�̎g�𑗂�܂ł̑g�D�̂Ƃ��ĔF�������ɂ����Ă������Ǝ����Ă���̂ł���B�����ȑ������܂��܍s�����v���Ȃǂł͂��肦�Ȃ��B�����Ƃ��Ă̎g�҂Ȃ̂��B�܂�A�`���Ƃ��������̓��{�̖���ł��铝�ꍑ�ƂƂ��Ă̍v����`���Ă���L���Ȃ̂ł���B
�����āA�����ɂ͋�B���D�ʂ��ȂǂƘ_����悤�ȍޗ��i����͔|�j����������Ȃ�����A�{�B�������瓌���{�ɂ����Ă̒n�悪���|�I�ɒ��S���������̘b�ł���B
�����ŋ�B�������͗��n�_�������B�����j�����q�ϓI�����Ƃ��ē`����ꕶ���̘`���̑��݂́A������l�Êw��̎������x������悤�ɁA�`���������ċ�B�Ɖ]���Ӌ��̏����Ȓn��ɔ������������łȂ��A���\���鍑�ƂƂ��āA����ɑ����������ɐ��܂ꂽ���Ƃ��ؖ����Ă���̂ł���B
���̎���̒��S�n�B���̍��Ƃ���s�Ƃ���ɂӂ��킵���n�́A�����ċ�B�łȂ��A�ߋE�ȓ��Ȃ̂ł���B
���V�n�̍�������]�����Ƃ̈Ⴂ�h��鍑�Ɗ�
�A���A�ޗǎ��ӂ��u�`���v�ł��邱�Ƃ́A�הn�䍑��a�����̗���ɂ͌��X����l���ł���B�����܂ő傢�Ɏ��ʂ������Đ����Ă����ɂ�������炸�A���Ǐ]�����珥�����Ă������m�̌��ʂɎ����������̂悤�Ɍ����Ă��܂����A�܂����������ł͂Ȃ��B
���̌��ʂ́A�c���j�ςɎx����ꂽ��a���Ƃ͍��{�������Ă���B
����_�́A�`���̐��������ł���B��a���͐_���̓����ɂ���Ę`�����n�܂����ƍl���邪�A�������瓱���������͂����ے肵��̂ł���B�`���́A�_������������y���ȑO�A�ꕶ�����炻�̒n�ɂ��������Ƃ������Ă���킯���B
���̈Ⴂ�́A�V�ƒn�قǂɑ傫���B
���̈Ⴂ�͈�̌Ñ�j�̃V�i���I�ɂǂ̂悤�ȕϓ��������炷�̂��́A�܂��ʍ��ɂďq�ׂčs�������B
���`�����ِ݂̈����Ƃ͈̔�
�����A�`���̈ʒu�ɂ��ẮA���̓��{�̒��łȂ��A�����ɑz�肷���������B�O�̂��߂����ŏЉ�Ă������B
�ЂƂ́u�`�v�𒆍��嗤�̈ꕔ���Ƃ�������B
�u�W��������`�k�`�����v�i��F�W���͋��ɍ݂�A���̓�A�`�̖k�A�`�͉��ɑ����v
�E�̈��p�́A�����ŌÂ̒n�����ł���R�C�o�i�������傤�j�̒��̋L���ł���B
���̈�߂Ɍ����̂́u���v�u�W�v�u�`�v�̎O���ł��邪�A���͒����̎��ォ��퍑����ɂ킽����݂������ł���A���݂̖k�����܂ޒn��ɂ��������ł��邱�Ƃ��������Ă���B
���́u�W�v�����A���̍��̏��݂Ɋւ��Ă͒��N�������Ƃ���l�������W���[�ł���B�����A���N�������Ƃ���Ɩ�肪������B�R�C�o�́A�W�͉��̓삾�Ɖ]���Ă���̂��B���̐��ɏ]���Ȃ�R�C�o�̋L�q�ɔ����āA��łȂ����ƂȂ��Ă��܂��B��������𓌂��Ɩ������P���Ȃ���u�`�v�����̂܂����ƂȂ�A�����ɂ͓��{����������Ă��邽�߁A�n���I�ɂ����v����킯���B
���̂悤�ȋ����ȉ��߂���������̂́u�R�C�o�Ƃ͗l�X�Ȓ��҂̋L�q���W�߂����̂ł���B�̂ɁA���̋L���͐M�p����ɒl���Ȃ��v�Ƃ��������̐M�����Ɍ�����Ɖ]���w�i�����邩��ł��낤�B

�������A���܂�ɋ����Ȑ������ɁA���R�����s���Ƃ�����������B���ꂪ�u�`�̏��݂𒆍��嗤�ɋ��߂�v�Ƃ����l���ɂȂ�킯�ł���B
�����ɒ����Ɍ������Ȃ�A��͓�ł����āA���Ƃ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����āu�`�����v�����̂܂܃X�g���[�g�ɉ��߂���ƁA�`�͉͖k�Ȃɂ������ƍl������Ȃ��A�ƂȂ�B
�m���ɂ��̉��߂́A�������߂̎p���Ƃ��Ă͉��ЂƂԈ���Ă��Ȃ��B�����A�������p���ł���̂����A���̍l���͎s������܂łɂ͎���Ȃ��̂ł���B���̂Ȃ�A���ɎR�C�o�̋L�����A����ɑ�����߂��A�ǂ�������������̂��Ƃ��Ă��A�Ñ��蒆���Ƃ������Ƃ��u�`�v�Ƃ��ĔF�����Ă������́A���̓��{�̓����ł��邱�Ƃ͓����̑��������������ĔF�߂Ă��邱�Ƃł���̂��B���̎����͎R�C�o�̋L�q���l�ȏ�ɑ傫���A�����Ĕے�ł��Ȃ����Ƃł���̂��B
��������l����A�R�C�o�Ɋւ��Ắu���̂悤�ȔF�����A���鎞���ɂ͂������̂��낤�v���x�Ŏ~�߂����A���i����`���̏��ݖ��̏�Ɉ�������o�����̂ł͂Ȃ��Ɖ]���邾�낤�B
�ӂ��ڂ̏��ݐ��́A�㊿�����Γ`����B�����̎u��ŏo�y�����u���ϓz������v�Ƃ̊֘A�ŗL���Ȏ��̋L�q���甭������̂��B
�u����������N �`�z����v���� �g�l���i��v �`���V�ɓ�E�� �������Ȉ���v
���̈�߂ɂ���`�z���́u���Ɓv�ƌP����A����Ɍ�����u�ϓz���v�Ɠ����Ƃ����B���̍��́A鰎u�ɂ��u�ɓs���v�̕\�L�Ō���A���݂ł��u�����v�Ƃ��Ēn�����c���Ă��邱�Ƃ�����A��B�k���ł��邱�Ƃ��m��������Ă���B
�������A�����Ŗ��ƂȂ�̂��u�`���V�ɓ�E��v�̕����ł���B�㊿���͒��N������݂̋�ؚ���`���̖k�݂��Ƒ����Ă���A�������n�_�ɁA�`���̍œ�[���u�`�z���v���Ə����Ă���̂ł���B�����ł܂��Ǝ��̉��߂����܂��B�܂�㊿���̒n���F�������̂܂܍̂����A�`���͒��N��������C���Ԃ̓��X�o�āA��B�k�[�ɂ܂����鍑���Ƃ���l���ł���B

�������A���̍l���͕��ʉ��ߏ�ł͈ꌩ���藧���Ă���悤�Ɍ����Ă��A�����ł͐�������l���ł���B���̂Ȃ�A�`���̈悪��B�k�݂��œ�[���Ƃ���ƁA鰎u���`�z������ɂ���Ƃ���z����הn�䍑���`���łȂ��Ȃ��Ă��܂����ƂɂȂ�B
�s��͂��ꂾ���łȂ��B�����ƒv���I�Ȗ�肪����B����͍����ʂł���B���Ƃ͌o�ϊ����ɍ��ƌo�c�̍��������߂���̂����A�C�݂��������̒n���Ȃ��Ƃ���A��̉��ɍ��������߂�̂��A���ꂪ��������Ȃ��̂��B�`�����ׂď������Ă���킯�ł͂Ȃ����ߊC�^�ƈ�{�ł̉^�c�������ł��낤�B
����ɓy�n�����Ȃ��Ɖ]�����Ƃ́A�����ɐ�������l������Ⴕ�ď��Ȃ��Ȃ�B���ہA鰎u�������Δn����̌ː��́A�z���A���n���ȂǂƔ�ׁA���Ⴂ�ɏ��Ȃ��̂��B���Y�͂�R���͂����߂��f(x)�͂��ׂĂ͐l���̒l�Ō��܂�B�����C�ݐ������̓y�������Ȃ������������Ƃ��Ă��A�ԈႢ�Ȃ������Ɏ��͂̍��Ɉ��|�I�ȕ��͍��ɂ���Ėłڂ���Ă��܂����낤�B�܂�A���̉��߂͂ǂ��l���Ă����藧���Ȃ��̂ł���B
�ł́A�u�`���V�ɓ�E��v���ǂ��l��������̂��B�㊿���̋L�q��O���O���M�p����ԓx�����ʂ��Ȃ�A�`�z�����ϓz���A�`�z�����ɓs���Ƃ�����������������Ȃ��ł��낤�B
�킽���͂�����\�����蓾����@���ƍl����B�Ȃ��Ȃ�A�u�`���V�ɓ�E��v�́u�`�v�́i���x���]�����j�u��v�ł���B���Ƃ���ƁA�u�`�z���v�́u�`�v���u��v�ƓǂށA���ꂪ�{�����������[���ł͂Ȃ����낤���B�܂�u�`�z���v�́u���Ɓv�ł͂Ȃ��A�u��Ɓi�ǁj�v�u��ʁv�Ɠǂނ��Ƃ̂ق����������Ɖ]����̂ł���B�������߂���A���Ƃ���S���āA��������B�k���ɑz�肷��K�v���Ȃ��Ȃ�̂��B
�����Ƃ��A���̉��߂̐�ɂ́A�ł́u�`�z�i��Ɓj���v�͂ǂ��ɂ���̂��Ƃ����^�₪���܂�A����ɉۑ��w�������ނ��ƂɂȂ�킯�����A������ɂ���㊿���̖��͔��z�̓]���Ȃ��ł͉������Ȃ��ł��낤���Ƃ͊m���Ȃ̂��B
����ł����A�u��̋���Ɓu�`�z���v�����ѕt�����悤�ƍS�D��������̂ł���A�L��A���]����鰎u�̋L�q�Ƃ̖����╨���I�ȏ�Q�Ƃ��������s�\�Ȗ����ǂ��܂ł��i���ɕ��������邱�ƂƂȂ�B����͊o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ñ�j�ɂ́A�����̂Ȃ����H�������������B����͂킽���̌l�I�ȕ��j�Ȃ̂����A���|���_������̎����̂Ȃ����Ɋւ���āA�����@�葱���邱�Ƃ͎��Ԃ̖��ʂ��ƍl���Ă���B�������A�_���̓r��ł̒o�܂ʌ�������N���C�Â��Ȃ����������̔�����������邱�Ƃ����邩������Ȃ����A��������y���Ɋm���ȍޗ����p�ӂł��郋�[�g�����ɂ���̂ł���A�킽�����S�O���Ȃ���������̃A�v���[�`��I�Ԃ��낤�B
���̏��ݖ��ł�����͕ς��Ȃ��B
�m���ɘ`���̏ꏊ���A��B�⒩�N�����A�����͑����̒n��������Ȃ��Ƒz�������炷���Ƃ͊y������������Ȃ��B���}��������B��B�������Ȃǂ�ǂ�ł���Ɗ��S����قǖL���ȑz�����W�J����Ă���A�����A�킽�����`������B�ł���\����^���ɍl�������Ƃ��������B
�ɂ�������炸�A���_�Ƃ��ēޗǎ��ӂ̒n�Ɂu�`���v�̒��S�n���߂��̂́A�����܂łɌ�������������𗊂�ɓ������̂ł͂Ȃ��A��ΓI�ɔے�ł��Ȃ��u�v�����邱�Ƃ�ɐɊ����Ă�������Ȃ̂ł���B
�@������u�v�ł��邾���ɂ�����w�p�I�ȍ����Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�킽���͂��̈�_�����ł����Ă��u�`�v�̏��݂͓ޗǎ��ӂł���Ɖ]�킴��Ȃ��Ǝv���Ă���B����́A���̃��[�g����̃A�v���[�`��I�B
���́u�v�Ƃ͉����A�����œ��������Ă������B
�u�`�v�𑼍����B�ɋ��߂悤�Ƃ�����ɁA���̂��Ƃ��l���Ă������������B
�����u�`���v�����̓��{�̍��łȂ������Ƃ���Ȃ�A�����͋�B�Ƃ����Ӌ��̒n�ł������Ȃ�A�Ȃ��A���{���I��Î��L�́u�`�v�u�`���v�Ƃ���������ޗǎ��ӂ̍����Ƃ��Ďj���̒��Ɏg�p�����̂��B���ɂ��̓ǂ݂�����܂ŏ펯�Ƃ��ꂽ�u��܂Ɓv�������Ƃ��Ă������ł���B
�Ȃ��A���́u�`�v�Ƃ����u�����v��ޗǂ̒n�̖��̂ɏ[�Ă��̂��B����́A���{�����g����Ɂu�����v�Ƃ����߂邱�ƂƂȂ�悤�ȕ����ł���̂��B����ȕ������Ȃ��g�����̂��B�����_���I�ɂ��̗��R������ł���̂ł���A���Ђ������������������Ǝv���B
|