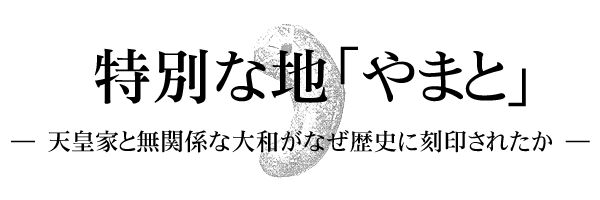|
■「やまと」は特別な地国家の中枢
国名問題で、棚上げしていた「やまと」についての考察を差し挟もう。
ただし、あらかじめ断っておくが、「やまと」に関しては、資料のどこを探しても提示できる明らかな根拠はまったく発見できなかった。予想はしていたとはいえ、非常に悲しい状況である。そのため、ここはあくまで「私見」を述べる場とならざるを得ない。
本来であれば、「私見」だけで進めたくはないのだが、「やまと」だけは何故か放っておけない、そうさせる不思議さがあるのだ。
「やまと」という地は、どこか特別な存在である、と云ってきた。
この地名が他とは明らかに違う点は、正式な漢字表記がないということだ。
国名問題の章で引用した「万葉集巻三 三一九 高橋虫麻呂詠不盡山歌一首 并短歌」を思い出していただきたい。その歌の中で「甲斐」「駿河」などその他の地名は現在と変わらぬ表記で登場するのだが、「やまと」は「山跡」とされている。他の歌においても、吉備や筑紫、山背(山代)など、皆、古来よりほぼゆるぎない固有の文字で表され、その表記が現在に及ぶまで現存しているにも関わらず、大和だけは、山跡、山戸、山処など、地形呼称を思わせる借字でしか表記されておらず、正式な地名を定める様子もなく、ようやく、「大和」に落ち着いたのは、律令時代になってからという遅さである。
それとまた、天皇家は「大和朝廷」と呼ばれるが、その実「やまと」という地は、特別、天皇家にとって謂れのある場所というわけでもない。むしろ、関係度から見ると、他の地と比べてもつながりは薄いくらいだ。
神武とて「やまと」を目指してきたのではない。以後の天皇も「やまと」という宮に居た記録もない。そしてその後、最終的に天皇家が自国の国名として採用したのは「日本」であって、「やまと」は畿内一国の名に成り下がっているのである。つまりは、「やまと」は天皇家にとって、神聖な地でも、由緒がある場所でもなく、せいぜい畿内の一地方に与えた名称という程度の価値しかなかったことになるのだ。
国学は天皇家に「大和朝廷」という架空の用語を冠し、我々も古代の王朝を「大和朝廷」として学習させられて来た。しかし、国学が定めたように、「大和○○」と呼べるような「やまと」に関係深い政府が現在に至る政権を受け継いできたのであれば、「やまと」は奈良の国名ごときに甘んじることはなかったであろうし、我が国は「日本」でなく、「大和」になっていてもよかったのだ。
万葉集などでは他の地方と比較にならないくらい多く題材とされていながら、何故か「やまと」は我々の了知とは逆に、天皇家との関連性も、日本国とのつながりにも欠ける地であったのだ。それでも「やまと」は消し去られることなく、五畿に列せられる奈良の古称として残った。そこに「やまと」の秘密があるだろう。
■「倭・日本」と「やまと」の関係国家の名称
天皇家との関わりは薄いが、「やまと」が太古より特別な場所であったことは、歌という世界での根付きから見ても確かであろう。
そこに強く感じるのは、「やまと」と云う地は、地方の若者が首都東京に憧れるように、列島の住人にとって誰もが目指したいと思った場所だったのかもしれない、ということだ。その憧れの場所が「やまと」と呼ばれた場所・地域であったのではないか、そう思える。
「やまと」が正式な表記を持たないことについては先に触れたが、それも当然のことかもしれない。「やまと」は国名などではなく、地形名称が一種の通り名として定着したものであるからだろう。国名でないが、人々の間では誰もが馴染んだ地名であり、万葉集など歌謡を通して、理想郷のようにきらびやかな、都を象徴する名として呼び継がれて行った。それが、結果的に「倭」や「日本」の読みに被せられるという誤読につながる状況を生み出したのであろう。
奈良の地とその周辺、つまり葦原中國を含む地域はもちろんのこと、かつては「倭(わ)」であった。その「倭」の一部である古より「やまと」と呼ばれた場所。そこは「倭」でもあり「やまと」でもあった。そしてその「やまと」と呼ばれる地にいつの頃か政府機関である「大倭(おおわ)」という機関が置かれた。当初はその表記の通り「おおわ」として通じた名称であっただろうが、「やまと」に置かれていた機関であったため、そのまま「おおわ」と呼ぶより、馴染みある「やまと」の呼称を付加する方がその所在が分かりやすかったのかもしれない。そのため、「大倭」は本来の正式な呼称ではなく、むしろ所在地の名を被せた「おおやまと」と呼ばれることが慣例となり、やがてそちらが正式な呼称となったのであろう。
大倭と同じように慣例の呼称が正式名称となる現象として良い例がある。
東漢氏、西漢氏。この氏族は「やまとのあやし」「かわちのあやし」と読まれる。これは「東=やまと」「西=かわち」と読むからではない。
「類聚名義抄」にも「東西=やまとかわち」ともあるが、そのような読みが最初からあったわけではない。あくまで東は「ひがし」で西は「にし」である。本来は単なる漢氏であるが、信貴生駒・葛城の山々を境に河内側と大和側に分かれて居住していたものが、区別上振り分けられて、西側は「にしのあやし」、東側は「ひがしのあやし」と名付けられた。
しかし、人々の間では耳に馴染んだ居住地名で呼ぶことが分かりやすかったのだろう、正式な氏族名としては東西であるのたが、「やまと方のあやし」「かわち方のあやし」と呼ぶことが慣例となってしまい、時が経ち、それがそのまま現在に続く読みとして独り歩きしたという例である。
「やまと」に関しては、漢氏のような明確な経緯は残っていないが、「倭(わ)」から「やまと」に変化した痕跡だけは存在する。前述した「大倭」である。これは「おおやまと」と読む。しかし、元々は「おおわ」と読んでいたものである。
そのことは魏志倭人伝の記述からもわかる。
收租賦有邸閣國國有市交易有無使大倭監之
交易を管轄する役職として「大倭」という機関(またその役人)が登場する。
この魏志の「大倭」と「大倭(おおやまと」との関連はこれまで一度も説かれたことがないが、同じものである。
この文は次の三つの文節で構成されている。
收租賦有邸閣國 ・・・租賦を収むるに國に邸閣有り
國有市 ・・・国は市を有す
交易有無使大倭監之 ・・・交易の有無(租賦と商いの利潤)を大倭に監せしむ
ここで云う大倭とは、先に触れたやまとの地に置かれた中央政府機関のことだ。魏志のこの記述は、二章の国家システムで述べたように「交易利潤」がすべて大倭と云う中央政府によって管理されていると解説しているのである。
では、その大倭はどう読まれていたのであろうか。
海外では「倭」は「倭国」の「わ」であり、読みも「わ」である。「大倭」の「倭」も同様であり、これは云うまでもなく「おお」+「わ」と読まれる。もちろんそれは、倭国側から示された情報が「おおわ」或いは「大倭」であった故に、その表記となったのであり、もし「おおやまと」と伝えていたのなら、まったく違う表音表記を充てられていただろう。
このように三世紀前後の段階では、まだ「大倭=おおやまと」という読みの慣習はなかったことが魏志の記述でわかる。しかし、それが時代を経て、古事記が記される頃には「おおやまと」と読まれているのである。このことから、「大倭」の読みの変遷は、東漢氏、西漢氏と同じメカニズムであったことが推察せられるのだ。
「やまと」が歴史ある地であり、地名であることは間違いないであろう。しかし「日本(俗に大和朝廷と呼ばれる勢力)」との関連がないにもかかわらず、「大倭(おおやまと」などの名で我が国の歴史に登場していた理由は(もちろん確証はないが)以上のようなメカニズムがあった、そういう理由付けは一応可能なのである。しかしである。なぜ、「やまと」が歴史ある地で、憧れの場所であったのか、そこが一番の疑問である。
また少し余談とはなるが、その背景には、彼の有名な話も控えているのではないかと想像が広がる。そう卑弥呼だ。
邪馬台国の在り処を奈良の地に求める研究者は「やまと」こそが邪馬台国だと説くが、もし里程問題を無視して考えるならば、確かに最も妥当な想定だと云えるだろう。妥当だと云うのは「邪馬台=やまと」の「音」だけではない、今見て来た「やまとが特別な場所」であったという理由からである。「特別」であることの根拠もまったく見当たらないにもかかわらず、現実に特別扱いされている地名であるのだ。もし、「邪馬台=やまと」が正しいとすれば、特別な理由が一気に氷解する。
国号問題で、倭国が正史に登場しないのは可笑しいと述べたが、邪馬台国も同様である。
魏志に我が国の都がある場所とされている地が、正史から抹殺されているとは考えられない。もちろん、日本書紀は倭国でなく日本の史書である。そこから考えると日本書紀が意図して「邪馬台」を記録しなかったとしても不当ではないが、日本書紀はためらいもなく倭国を記していた誠実さの実績があるのだ。その日本書紀が「邪馬台」だけを消し去るだろうか。そこが想像を掻き立てるポイントである。
そう思うと「やまと」こそが「邪馬台」ではなかっただろうか、と思えてならない。
「やまと」は天皇家とは実質関係のない地であるにもかかわらず、同時に様々な資料に登場していることも事実なのである。日本の史書である日本書紀が、倭国の都である「邪馬台」を記載する義理などないかもしれないが、日本にまつわる歴史だけを拾い上げて編纂したとしても、「都」の存在は何らかの形でそこここに顔を覘かせるはずだ。その名残りが「倭」の地名が「やまと」という読みをかぶせられた現象であり、「邪馬台」の影こそが「やまと」であったのかもしれない。
そうなると面白い符号が見えて来る。「邪馬台」という表記だ。
「邪馬台」=「やまと」であるならば、魏志の時代、そこは卑弥呼が都を置いた場所でありながらも、当時から「やまと」は正式な地名表記を持たなかったことになる。つまり、万葉集などの「やまと」と「邪馬台」の間に「正式表記がない」という関係式が浮かび上がるのだ。
景行紀には「伊都縣道邊」という人物が登場するが、その地は魏志でも「伊都國」とまったく同じ文字で表記されている。つまり、景行の時世も卑弥呼の時代も、我が国はすでにれっきとした「漢字」での地名表記を使用していたことがこの部分で証明されるのだ。
倭国は、地名を伝える際、漢字を使って地名を中国側に伝えていた可能性が大きい。そしてそれは倭国内にもシュアされた情報であったわけだ。故に、魏志と日本書紀の中で、同地名が同じ表記で記されているのだ。
それに反し卑弥呼の都は「音」でしか伝えられていなかった。それは日本書紀や万葉集などの「やまと」と共通する特徴である。山跡・山常・山戸・夜麻登。登場する場所でその場かぎりの文字で表されるという特徴だ。そのため、魏志編者は「やまと」を「音」を頼りに「邪馬台」と表記するしかなかった。
この「邪馬台」という表記は我が国の資料にないものだ。ないことで「邪馬台」は「謎」となったが、それは今言った正式表記の欠如に起因する。そう思えるのだ。
そして、「やまと」が古代より特別であったのは、卑弥呼に代表されるアニミズムの象徴である「巫女」が囲われていた聖地であったことも一因なのかもしれない。
そう云えば、「やまと」と呼ばれる地は大神神社のある三輪地域ではなかっただろうか。
そこは勢夜陀多良比売、倭迹迹日百襲姫、活玉依比売など巫女を想わせる女性と大物主神との婚姻譚が、語り継がれる土地であったはすだ。記紀はその話を自らの歴史ではなく、単なる説話としてサラリと扱っている。もし天皇家が、倭国の政治を担う立場であったならば、そのような男女の怪しい言い伝えを史書に載せる筋合いはないのだが、サラリとは云え、決してぞんざいではない扱いで掲載していることもまた、それが伝えなくてはならない、無視できない記事であったことを物語るのではないか。
以上が「やまと」と「邪馬台」の関係についてのあくまで個人的な考えである。
見ての通り根拠と云える材料は一切用意できない。また以降何か新しい証拠が見つかるという僥倖も期待できないだろう。
ただ、敢えて、主張できる論拠を挙げるとすれば、仮に一部の研究者が唱えるように、日本書紀、或いは天皇家がその国策として「倭国」の痕跡を消し去ろうと計ったのだと仮定しところで、我が国を縄文期から七世紀という永き年月にわたって統治した倭国と云う政府、その都「邪馬台」の痕跡を、完全にこの列島から一字たりとも残さず消し去ることが出来たかどうか。本当にそう云えるのかどうか、という点だ。それは風土記や歌謡だけではない、ありとあらゆる末端までである。
わたしは不可能だと思う。倭国が記紀に公然と現れているごとく、「邪馬台」の存在も確実に記紀に残っている。そう思うのだ。それは、地名の「音」という形で。
|