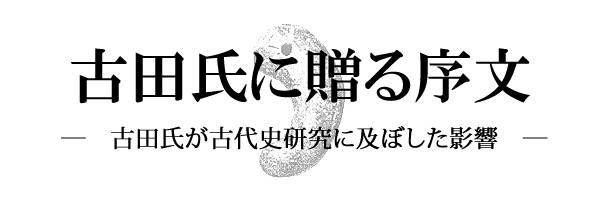|
■古田武彦氏の功績
古代史という研究分野における古田武彦氏の貢献度は、他のどの研究者よりも高いとわたしは思っている。その理由のひとつは、市井の研究者など、古代史に興味をもつ者の探求心に火をつけ、大きな勇気を与えたその影響力が上げられる。しかし何よりも特筆すべき点は、これまで勝手気ままな想像ばかりが蔓延していた古代史研究に、学術的な研究とはどのような形で行うべきかという公正かつ明確なルールが氏によって示されたことではないだろうか。
学校教育で教えられる歴史を私たちはそのまま疑いもせず受け入れてきた。そのような刷り込みによって植え付けられた固定観念に対して、氏は古代史研究にこれまでなかったロジカルな手法を導入することで、その堅い地殻に亀裂を入れ、古代史に眠るロマンを誰もが見える地表面に浮かび上がらせてくれたのだ。
もちろん、学会の常識に対しメスを入れる説を提唱した研究者は氏以前にも少なからずいたのだが。そのような説の多くが、立脚する土台の脆さ故に風化し消え行く中、氏が突き付けた説だけは、決してパフォーマンスに寄りかかりこともなく、虚構が積もる古代史の廃墟に、論理的方法論という武器を掲げて乗り込み、有無を云わせぬ鋭い刃で固定概念を断ち切る力を示してくれのである。
古田氏が世に出した古代史研究の数々は恐らく今後もその輝きを失わないだろう。氏が用いた方法論には欠陥らしき点もまったく見られないし、氏が論証で辿ったその道筋のどれもが見事なものであったと云ってよいし、中でも氏の専門分野とも云える文献批判においては、その手際や論点の鋭さ、そして資料に向き合う姿勢のどれもが、史家の誰しもが見習うべきものであり、リスペクトされるべきものであると云える。
日本中に多くの賛同者を持ち、「古田史学」という言葉まで生み、学会に衝撃を与えた業績は素晴らしく、氏の残した遺産はそのほとんどが輝かしいものであったとわたしは堅く信じている。
ただし、惜しむらくはたったひとつの過ちを覗いて・・・である。
■古田武彦氏の大きな過ち
氏が犯した過ちとは、スタート地点の選定ミスである。多くの史家が陥る、ある意味、史家に特有の病と云ってもよいかもしれない。古田氏もその病を長く、亡くなるその時まで患っていたのだ。
例えば、富士山に登ろうとして、間違って赤城山の麓から登り始めてしまったならば、どれほど高性能な装備で完全武装しても、豊富な登山経験や技術で踏破したとしても、富士の頂には決して到達しない。多くの、ある意味、ほとんどの史家は、間違った登山口を登っている。そしてそれに気づくことなく、或いは間違えたと薄っすら気付いたとしても、頂きに立つことのない登山道をひたすら辿り、時に脇道に逃げてみたり、また道標や案内図まで都合よく書き換えて、そこを富士山だと思い込もうとし、下山することなく登り続けるのである。
古田氏も残念ながら、他の史家と同じ道を歩んでしまったと云える。
古田氏はは九州を邪馬台国の地として選んだ。理由はひとつ、日本書紀など天皇家を我が国の代表だとする「国史」と中国側が伝える我が国の記録がまったく違うからである。中国が伝える我が国の統治国は「倭国」である。そして魏志倭人伝に登場する邪馬台国もまたその倭国の首都とされる地なのである。
天皇家は神武の東征によって、近畿(大和)に都をおいた(とされる)。その天皇家の事績や歴史が中国側から認識されていないということは天皇家の勢力範囲である近畿は倭国ではない、そう古田氏は考えた。そして邪馬台国の候補地を、近畿に対し、より大陸に近く、弥生文化が真っ先に花開いた北九州こそが倭国の首都の地にふさわしいと、尤もらしいが、根拠のない考えに傾いてしまった。
一旦そう思い込んでしまうと、客観的な視点を失い、只管それを裏付ける証拠だけを一心に求めることになるものだ。求める気持ちが強ければ強いほど、証拠となりえないものですら、そこにちょっとした関連性を無意識に附会し、画餅を本物の餅と信じるようになる。
しかし、氏が信じた九州の地は倭国というこの日本列島の統治国の首都には成りえない、そのことだけは明らかなのである。残酷ではあるが、氏のすべての業績は、研究史のひとつとして素晴らしい価値は要するが、説そのものは無価値な空論なのである。
恐らく古田氏の信奉者、および九州王朝を自説とする史家は猛反発するだろうが、残念ながら、どこから攻めても、邪馬台国九州説は成立しない。
■古田武彦氏の説を捨て去った理由
わたしを古代史の世界に引きずり込んだのは父である。いい意味でも悪い意味でもこの父から様々な影響を受けた。物理学、天文学、絵画、カメラ、登山、オーディオなどなど、趣味を並べるとどれもが父親の好きだったものばかり浮かんでくる。父に気に入られたいとか、そのような感傷的な動機は微塵もない。ただ、日常的に幼いころから耳元でささやかれ、結果「洗脳」されてしまっていただけのことである。故に反発心などもなく、何事も物理学的な論理思考で考える気質も生涯抜けないであろうし、未だにカメラも、撮るより機器を集めることが好きだったりとか、意外と素直に影響を受け続けている。
古代史もそうだった。父は当初から邪馬台国は九州にあると考え、幼いわたしにもそう語り続けてきた。当然、古田氏の著作も読んだことがあったのだろう。わたしも古田氏の著作はほすべて所持している。そう、わたし自身も実は、邪馬台国九州説という産湯の中で育った生粋の九州説信者だったのだ。
古田氏は「天皇家こそが我が国の唯一の王朝」という考えをある種の「信仰」と呼んでいた。同じ意味で九州王朝という古代史観に染まっていた古田氏もこのわたしも九州論の得度を受けた「信仰者」だったわけだ。
しかし、そのわたしが、今ではその九州論を打ち砕く先鋒に立とうとしている。
毛細血管まで九州説の血液に染まったわたしがなぜ「ころんだ」のか。その理由は単純だ。論理的にも学問的にも九州説を客観視してみるとそれが空論でしかないと思えたからだ。
わたしは古代史が好きであると同時に物理学もそれ以上に好きである。物理学は数学を共通言語に置き、その堅牢さに支えられている学問だ。数学とは常に明快な解を導出し、決して矛盾を許さない学問ジャンルである。その土壌に慣れ親しんだ私は、どうにも矛盾というものが生理的に許せないのである。
九州論を信じてきた頃、どっぷりと身を沈めていたその時ですら、九州説には多くの矛盾や現実味を感じられない違和感を抱いていた。
幾多の矛盾やリアリティが欠如した感覚は、おそらくすべての九州論者も少なからず抱いている思いではないだろうか。多分、古田氏もそうだったのだろうと思う。彼が何冊も何冊も内容の重複した書籍を重ね、少しずつその説を補強し、更訂を繰り返してきたのも、研究を進めれば進めるほど先々に立ちはだかってくる矛盾への恐怖心からだったのかもしれない。自論を固めようとしてもいつまで経ってもすっきり納得できず、常に何か釈然としないものを感じていたのだろう。
もっとも、わたしの場合は、そんな恐れなど微塵も感じなかった。わたしは論理的に絶対的に正しい選択肢しか選ばないという意識のほうが、九州論を信じ続ける想いよりも遥かに強く勝っていた。故に、あっさりと「ころび」、正しい道に鞍替えしたのである。
|