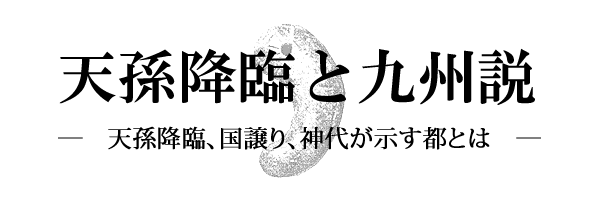|
■九州に都があった痕跡はあるのか
「九州論が成り立たないこと」は天孫降臨でも証明することができる。
天孫降臨は、書紀では「神代」「人代」という形で、神武東征を境として区別され、神話のごとき扱いを受けている歴史の記録(或いは伝承としてもよいが)に含まれるイベントで、神代中、最も盛り上がる場面だと云える。大国主が登場するあの有名な「国譲り」も天孫降臨のシナリオのひとつである。このイベントは、大国主らが治めていた旧倭国を天孫が降臨して攻め落とす事変のように解釈される傾向にあるが、その解釈はまったく間違いであることを指摘しておきたい。
その点も含めて、天孫降臨を読み解いてみよう。
天孫降臨と云えば、瓊瓊杵尊のことばかりが注目されるが、降臨したとされる人物は瓊瓊杵尊ひとりでなく、記紀など史書に記載にあるものだけでも五人。記載されなかったものを含めると、幾度となく行われていた政治的なイベントだと云える。
天孫降臨をことさら「神話」めいた解釈をすることなく、神武東征までの期間で整理してみると以下のようになる。
(降臨者) (派遣者) (降臨場所) (結果)
第一 天穗日命 高皇産靈尊 葦原中國 大己貴神に媚て不報
第二 大背飯三熊之大人 高皇産靈尊 同上 同上
第三 天稚彦 高皇産靈尊 同上 使者を殺したため、高皇産靈尊に討たれる
交渉 経津主神・武甕槌神 同上 出雲国 <国譲り>大己貴神に皇孫を降臨させることを迫る。事代主神は承諾。
第四 瓊瓊杵尊 同上 日向 降臨成功
第五 饒速日 不明 大和 高皇産靈尊や天皇家とは無関係な勢力から派遣された人物
これを見ると当初、天孫が降臨地として目指していた場所は一貫して葦原中國とされている。そして、降臨の主導者は高皇産靈尊で、降臨先の葦原中國を治めているのは大己貴神だという勢力構造も浮かび上がる(ただし、大己貴神の本拠は出雲である)。
また、降臨に当たって「葦原中國を治めるべきは天孫だ」といきり立っている様子からも、未だに天孫はなかなか政治の中枢に加われず、その場所を治めることが出来ないでいる時代が続き、何度か降臨させた「天姓」の人材も、大己貴神に媚びるばかりで高皇産靈尊の思惑通りには動いてくれず、いつまで経っても大己貴神の言いなりになっていたという、そういう歴史がありありと見えてくるのである。
それ故に、苛立った高皇産靈尊は軍事行動を起こし、「国譲り」交渉に出たのである。
国譲りは一見、成功したかのように描かれているが、それとは裏腹に、国譲りの後に、天孫が葦原中國を治めたという記録は一切ないのである。ほとんどの史家は、成功したからこそ瓊瓊杵尊の日向への降臨が為されたのだ、と思い込んでおられるのだろうが、何を根拠にそう考えたのだろうか。
今回のポイントはそこにある。「九州論が成り立たない理由」のふたつめである。
もし国譲りに成功していたのであれば、瓊瓊杵尊の天降った日向こそが倭国政府の中心地にあたるわけだ。果たしてそれが正しいのか、である。そこをはっきりさせよう。それには、神武東征の理解が一番近道である。なぜなら、神武は瓊瓊杵尊の降り立った日向から東征を行ったのだ。であれば、東征とは倭の都から地方を組み入れていく目的で行われ軍事行動でなければならない。
東征の「動機」を史書の記事から検証してみよう。日本書紀と先代旧事本紀はそっくり同じ記事を掲載している。原文を抜き出してみた。
於鹽土老翁。曰、東有美地。青山四周。其中亦有乘天磐船而飛降者。余謂、彼地、必當足以恢弘大業、光宅天下。蓋六合之中心乎。厥飛降者、謂是饒速日歟。何不就而都之乎。
日向の地において、彦波瀲武??草葺不合命の子とされる、彦五瀬、稲飯、三毛野、狭野(後、磐余彦)ら四兄弟が、塩土老翁の命令で、いわゆる東征を決意した場面が語られている。その時に塩土老翁が彼らに下した言葉である。
意訳すると「饒速日なる者が降り立って治めているという東の美地がある。我らもそこに行き天下に評されるべく大業を成し、都で職に就こう」というものだ。この訳とともに、原文をよくよく見ていただきたい。ここに「東征」という名称を与えられたイベントらしく、「攻め込み、奪う」という意図が見えるだろうか。どこをとってもそのような言葉は見当たらないのである。
それどころか、鹽土老翁の「激励」としか思えないセリフには穏やかさまで感じられる。しかもそれは、従来説の解釈であれば、すでに都に居して、倭国の王となっているはずの神武に対して、東の美地の「都」を目指せば、天下に大業を成すチャンスが訪れるということを勧めるという、なんとも解せない台詞なのである。
以上のことから二つの状況が浮かび上がってくる。
まずひとつは、神武東征の最終地が大和であったという事実から、「美地」とは大和であり、そこは天下に大業を成す夢が満ちた希望の地であったこと。もうひとつは、瓊瓊杵尊が降臨した日向は、美地でなく、希望の持てない、そこに居る限り天下からは程遠い不遇の地、つまり、定説から想定される神武の境遇とはかけ離れたものであったということ。史書に記された内容を見る限り、そういう対比が見えてくる。
陰陽、二つに分かれたこの対比が何を意味しているかはもうお分かりだろう。
瓊瓊杵尊が降臨した日向は美地(都)から遠く離れた土地であったわけだ。つまり、天孫降臨は必ずしも「天孫族が前勢力に政権交代を迫るため都へ侵攻した歴史」を指すのではなく、美辞麗句という修飾表現を削り落とせば、ただ単に、人材を「赴任」させる行為をそう表現しただけのものであったことになるのだ。現代風に言えば「人事異動」である。
しかし、先ほども疑問を呈したように、国譲り後も天孫が活躍した記録は何も描かれていない。その中にあって、幸いにも、瓊瓊杵尊は僻地ではあるが一応役人として日向という地に赴任することが叶ったわけだ。恐らく、神武を祖とする天皇家にとっては、僻地への赴任であろうが、後世に誇れる立身出世ストーリーのスタートポイントであったのだろう。
ただ、天皇家、つまり記紀という史書を編纂した勢力にとってはそこだけを伝えれば十分目的は果たせたのだろうが、彼らの上位勢力である天孫側に再び視点を移すとどうだったのだろうか。国譲りというあれほどのイベントでなにも結果を残せなかったということは考えにくい。事実としては、あの時点で大己貴神を退任に追い込み、天孫が思惑通り政権をにぎったのかもしれない。天皇家にとっては自家の出自を語ることが最重要であるため、他の天孫の歴史には触れる必要がなかったという推測も成り立つ。
ただ、九州論が成り立たない理由に立ち返ると、いずれにせよ、日向を含む九州という場所は、都を思わせる要素を何一つ要していないことが、この天孫降臨から再認識させられる。
そして、さらに鹽土老翁の言葉に従って美地を目指した神武たち兄弟の行く末を「神武こそが我が国の始祖などという」先入観を払いのけて見て行くと、我が国の古代における本当の勢力構造とその変遷が見えてくるのである。
|