mansongeの「ニッポン民俗学」
 日本の祭り(祀り)の古形を求めて
日本の祭り(祀り)の古形を求めて
祭りの基本構造については、「天神祭」に即して一度述べたことがある。要点を示すと、次の通りである。
- 神は社に常在せず、祭りのときのみ、降臨する。
- 神はそのつど、別な場所に降臨する。
- 祭りとは、神を迎え、社にお連れし、またお送りするものである。
- 神の降臨および帰還は、夜間に行なわれる。
- 昼間の行事はすべて後世の追加や移動である。
よく知られているように奈良の大神(おおみわ)神社には本殿がない。三輪山を望む拝殿があるのみで、玉垣に囲まれた山自体が御神体とされる。誤解のないように言っておくが、山そのものが神なのではない。山全体が聖域であり、神はこの山を棲み処とされているという意味である。
 しかし、筆者の考えからいうと、これは本当ではない。神が降臨される際、この山のどこかに降りられる、そういう場なのだ。三輪山には今も、奥つ磐座(いわくら)、中つ磐座、辺つ磐座と呼ばれる古岩がある。これら磐座とは、神の第一の依り代である。降臨された際、まず依られるもの(神座、かむくら)である。
しかし、筆者の考えからいうと、これは本当ではない。神が降臨される際、この山のどこかに降りられる、そういう場なのだ。三輪山には今も、奥つ磐座(いわくら)、中つ磐座、辺つ磐座と呼ばれる古岩がある。これら磐座とは、神の第一の依り代である。降臨された際、まず依られるもの(神座、かむくら)である。しかしながら、まだここにも後世の「智恵」が加わっている。と言うのは、神が初めに降りられる場所は固定できない。だから決められた磐座なぞ、神の論理ではなく人の論理なのである。神が一度降りたと見なされた岩には、注連縄(しめなわ)が張られ聖別される。毎年、この注連縄が張られた磐座が増えていく、これが古形の神山の姿である。
また、葵(あおい)祭りで知られる京都の上賀茂社では、神の不在を明言するかのように、葵祭り直前の夜に社裏の神山から神を迎える。神を山頂の磐座からたいまつで導き、ふもとの御阿礼(みあれ)所で「ひもろぎ」(神籬)に移し、そのひもろぎを祭場である神社に運んでいる。
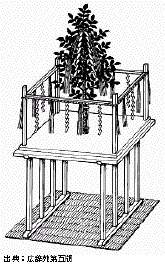
御阿礼とは「み生れ」で、神が生まれること、つまり神が姿を現すことである。それでも、依り代である榊(さかき)に確かに依られたと言うまでであるが。ひもろぎとは、依り代の榊の枝とそれを立てる結界台をセットにしたようなものだ。
いまのひもろぎは、「みてぐら」(御手座、幣束、御幣)同様、ハンディな(持ち運びし易い)ものである。しかし、その榊の枝の原型は根っこつき(根こじ)の常緑樹であり、さらにその前には大地に植わっている自然木そのものであった。つまり、ひもろぎとは、聖別された土地と、そこに植わっている神座である木なのである。
これは何を意味するのか。ここには祭りの古形、そして祭場(社、屋代、やしろ)の古形が隠されている。ひもろぎとは、実は「やしろ」そのものである。神が降臨した神座(岩だけではなく木も神座となる)を中心に、一定域が神庭として注連縄などで聖別される。その場所が古形の祭場であり、すなわち「やしろ=ひもろぎ」なのである。
そして神が降りられる岩があり木が植わっている山こそ、神山である。たとえば三輪山がそうであるように。つまり、三輪山は壮大な「ひもろぎ」なのである。そういう意味で、山全体が神座(かむくら)であり御神体なのである。いまのひもろぎとは、神が依られた木を、結界した土地付きで切り取ったミニチュアである。
ところで「みてぐら」は、今では榊の枝(神木)に紙の垂(しで)を付けたお祓いの道具のようになっているが、もちろんもとはそうではない。みてぐらも、もとは根こじの榊であり、それをコンパクトにした依り代なのである。『古事記』の天の岩戸の祭りに、こんなみてぐらが登場する。根こじの榊に、鏡や玉など神宝(かむだから)を付けたみてぐらである。
このみてぐらは祝詞とともにアマテラス神に捧げられたものであるが、要するに、榊(常緑樹の依り代)に神宝(捧げもの)を付けたものがみてぐらなのである。いまのみてぐらは榊の枝(神木)に紙垂を付けた姿をしているが、この紙はもともと布で神への捧げものであった。
このように、みてぐらとは神の依り代が、神への捧げものに転じたものである。さらに面白いことに、捧げられた神宝も神の依り代となる。たとえば、鏡がそうであり、刀などもそうである。地上に降臨するニニギ命にアマテラス神が「これの鏡は、専ら我が御霊として、吾が前を拝くがごと、いつきまつれ」と宣われたのはあまりにも有名である。
日本の神々の世界では、神の依り代は同時に神への捧げものであり、その逆も真という不思議がある。みてぐらが「幣束」や「御幣」と書かれ、「幣」(ぬさ、神への捧げものの意)という字を含むのも、こうしたいわれなのである。
さて、神の祭場(やしろ)の話である。ひもろぎの山、神座のある山、これこそが祭場のもとの姿である。森とは「杜」(もり)である。単なる自然の森林ではない。そして神社に杜(もり)がついているのではない。杜(もり)とはひもろぎ、神庭であり、そこが祭場なのである。その祭場にたつ建て物が、いま「神社」と呼ばれているにすぎない。
祭りは神の都合ではなく、人の都合に合わせて変化してきた。神は本来、気まぐれだ。神は自分の神庭である杜(もり)に降臨する。それはよいのだが、そのつど違う岩や木に降臨するのである。古形の祭りは神が降りた所を探すことから始まる。では、どのように探せばよいのであろうか。
天から降る神は落雷となって現れる(これを「かんとけ」と言う。かんとけは神の「み生れ」である)。だから、落雷の跡を探すのである。たとえば、落雷によって裂けたり、焼け焦げた木がそうだ。その横にある、いわくありげな岩がそうだ。のちには、弓矢を放ち、矢が当たった木を神木とした。神座は固定したものではない。
最初の祭りはその神座の前で行なわれた。そこが祭場であり、これが初めの「社」(やしろ)である。それは建て物ではなく、神庭=祭場を意味する言葉であった。注連縄がその神庭の境界を結界していた。祭りの場所は、毎回変わった。人が神の御前にそのつど進み出ていたのだ。
三輪山も拝殿から拝むだけのものでは決してなく、山に分け入り祭りをする所である。なお、三輪山は参詣のためなら、だれでも入山することができる。しかし「祭日」には不可である。それは、いまもそこで祭りが行なわれているからだ。

ところが、ふもとまで神を連れ出すことが始まる。神が降臨した木を根こじにして、ふもとの祭場まで運ぶようになる。あるいは磐座からみてぐら(依り代)に移して運ぶようになる。上賀茂社の「み生れ」儀礼も、最初はふもとではなく、山中で行なわれていたはずだ。
こうするメリットはもちろんあった。ふもとで事前準備ができるから、より整った祭りが可能であり、祭場としても立派にできる。祭りのための建て物(仮設の祭殿。ただし供え物を置く程度のもの)も作られるようになる。それでも、祭りは屋外で行なうものであった。
人の都合で、さらに立派な祭場が望まれるようになる。より適地に神庭が定められる。しかし新たな問題が発生した。神木などの依り代をこの新祭場まで運ばねばならないのである。上賀茂社では今では上述のように、ハンディなひもろぎが運ばれる。しかし当初は、根こじの神木を特別な「屋台」に乗せて運んだであろう。
「屋台」はのちの「神輿」と考えてもよいが、実はその形こそ「ひもろぎ」である。注連縄で区切られた新たな常設祭場の真ん中に、「神が依っている神木を乗せた屋台」=ひもろぎが置かれる。これまでは、祭りの道具や建て物などは祭りのつどに、作られてはこわされてきた。屋台であるひもろぎもそうであったろう。
しかしそれが、しだいに立派なものになっていき、祭りで何回も使われるようになる。すなわち、神を乗せる屋台が固定化していく。動座としての宮(御屋)の誕生である。これが新祭場に固定されれば、社殿である。こうして宮、神社ができたことは、上賀茂社の流造り、春日社の春日造りが土台を組んだ上に社殿が立てられる建築様式であることにもしのばれる。
このような変化には数百年を要した。この長い時間は始源を見失わせるに十分であった。祭場=神庭、つまり「社」(やしろ)とは建て物であり、神はそこに常在するものである、ということにいつの間にかなってしまった。祭りは何の疑いもなく神社で行なわれ、今ではそのプログラムの一つに神輿による「渡御」(とぎょ)がある。
祭りのときにのみ、神は神社を離れ、お旅所という縁地へお出かけになる。しかしこれは逆である。その前に「お旅所」とは何か。もとの祭場である。上の例で言えば、神山のふもとの祭場である。このやしろ(=ひもろぎ)での祭りが長く続いたのだ。その記憶が、神社が成立してからも、お旅所へ渡御することを現在もなお続けさせている。
ただし、行きと帰りの方向は正反対である。神は杜(もり)に降臨して、それから祭場(=お旅所)に行くのである。神社からお旅所に行くのではない。お旅所こそ、より古形の社(やしろ)である。いまとなっては方向も目的もわからない神の旅が、あの華やかな渡御行列なのである。
(参考)「天神祭の構造---鉾流しと船渡御とウルトラマンと」