mansongeの「ニッポン民俗学」
 水神の話:「河童駒引」をめぐる動物考―馬・牛・猿
水神の話:「河童駒引」をめぐる動物考―馬・牛・猿

▼神話的思考から見た河童の正体
河童の話であるような、またそうでもないような話をいくつかしたい。あらかじめお断りしておくが、河童はここでは主役ではない。小論は、河童が日本に生まれ出るまでの全人類的な記憶、あるいはニッポン人の深層を断片的に素描することにとどまる。ユング流に言えば「集合的無意識」、折口信夫流に言えば私たちの「古代」をめぐる話を、そしていくつかの脱線的なエピソードを予定している。
さて、柳田国男によれば、河童は水神の零落した姿だという。「河童駒引」というのは、河童が馬を水中に引き込む話だ。その馬を守るのが猿なのである。この「河童駒引」をユーラシア大陸に広く伝わる水神信仰の大海の中に位置づけたのが、石田英一郎著『河童駒引考』だ。それにしても、河童はなぜ馬を水中に引き込むのか。それは河童=水神の正体が馬であるからだ。また同時に、馬は水神への犠牲なのである。
ここには、西田幾多郎の絶対矛盾的自己同一のような、神話的思考がある。例えば、天照大神を想起されたい。この神は先行する神々に祈りを捧げる神であると同時に、人々に祈られる神である。神に祈る巫女こそ、神そのものなのである。それ故、次のような一見奇妙な行為がなされる。人々はある神のためにその神自身を犠牲として捧げるのである。神話そして宗教の論理は絶対値で出来ている。犠牲(神の死)は降臨(神の生)であり、強敵はその同類によってしか倒せない[注1-1]。
-
[注1-1]征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷の大酋長アテルイを破り得たのは、神話論理的には田村麻呂自身が蝦夷であったからだ。
ここでは、もう一つだけ述べておきたい。河童は水辺や水中に遊ぶ馬や人の「尻小玉」(しりこだま)を抜くと言われる。肝心の尻小玉とは何だか不明なのだが、肛門から奪われる何かのようで、おそらく「肝」(きも)ではないかと思われる。肝とは実物としては肝臓でありながら、現代人が捉える肝臓ではない。それは「肝が据わる」や「肝を冷やす」や「肝をつぶす」の用例に見られるような、生き物の心や生死に関わる特別な臓器である。
この河童は「トイレの花子さん」に似ている。いや、逆だろう。河童は花子さんとなって、今もなお生き続けているのである。問題は水である。水は地下水となって、どこにでも通じている。水神はこの水路を使って、自由自在に移動する。故に、水神は竜宮[注1-2]の海神でもある。そして水は生命の源である。奈良東大寺二月堂の新春の祭りである「お水取り」の聖水は、若狭からの送り水であるとされるが、これは地下を経た変若水(おちみず:若返り、再生の霊水)である。
-
[注1-2]「竜宮」は「竜」の宮だ。つまり、海神の正体は竜だということになる。竜については後述したい。
-
[注1-3]全くと言ってよいほど似た話に、玉依姫命(京都の下鴨神社に鎮座)が丹塗りの矢で、賀茂別雷命(上鴨神社に鎮座)を宿したというものがある。
▼地上の馬と交わり名馬を生ませる神馬
 馬は雨に関わる犠牲の動物だった。しかし、やがて貴重な生き馬を犠牲にすることは取り止めになり、土で作った馬や絵に描いた馬で代用されるようになった。神のための祭場と言えば神社であるが、神への捧げ物としての馬は、神社にいまも「絵馬」として生き続けている(もっとも、願い事は雨乞いなぞではなくなったが)。ちなみに雨乞いの際は黒馬、晴乞いの際は白馬というのが習わしであった[注1-4]。
馬は雨に関わる犠牲の動物だった。しかし、やがて貴重な生き馬を犠牲にすることは取り止めになり、土で作った馬や絵に描いた馬で代用されるようになった。神のための祭場と言えば神社であるが、神への捧げ物としての馬は、神社にいまも「絵馬」として生き続けている(もっとも、願い事は雨乞いなぞではなくなったが)。ちなみに雨乞いの際は黒馬、晴乞いの際は白馬というのが習わしであった[注1-4]。-
[注1-4]平安期に朝廷行事として、正月七日に行なわれた「白馬(あおうま)節会」も、水神への祭祀に関わりがあるものと思われる。
この水中の神馬というモチーフは、日本や中国にとどまるものではない。中央アジアを経て、ロシアや全ヨーロッパにも広がっている。また、アラブ世界の古典『千夜一夜物語』のシンドバッドの冒険譚にも見出せる。ある島での奇習として語られるのだが、雌馬を海岸につないでおくと、やがて海から種馬たちが現れ、交尾する。それを見届けた後、人間たちが種馬たちを追い払う。島の住民たちはこうして名馬を得ていたという話だ。
それから、興味深いことに、世界中の水神説話には共通する魔除けの呪具が登場する。それは鉄や金属である。北欧では水怪退治に焼き串や小刀が用いられるが、わが国の河童も鎌や庖丁を嫌う。古事記にある三輪山の蛇神もその正体は針によって明かされる(同型の説話には、針に塗った毒で大蛇が命を落とす話もある)。中国には、水神(水怪)を鉄(金)の鎖につなぎ留める話もある[注1-5]。
-
[注1-5]すでにお分かりかと思うが、神話要素の善悪にあまり意味はない。つまり、水神でも水怪でも同じなのだ。要は絶対値的な強度だけが問題だ。
ここで脱線して、馬と人の関わりについて述べたい。数多くいる動物の中で、ある条件を満たせるごく限られたものだけが人間の家畜となれた。その条件とは、食べ物を中心に人間に手間をかけさせ過ぎないことである。食べ物の選り好みが激しいとか、習性が狂暴だとか、体力が弱すぎたりすると、忙しい人間にはとても面倒見切れないからだ。その点、馬は草食で比較的おとなしく、角や牙もなく、しかも丈夫だった。
馬は草食だが、森林ではなく、草原をあえて選んで棲んだ。生存のための棲み分けだ。その顔が長いのは、目と口を離すことで、食事中も肉食獣の接近に目を配れるようにだ。敵が来れば、速く走って逃げる。足指の爪が蹄(ひづめ)となって発達した。さらに、人間にとって奇跡のようなことがある。馬の歯は目と口が離れたせいで、前の切歯と後の臼歯の間にすき間ができていて、そこに手綱となるものをかけることができたのだ。
 現在のヒトは、ネアンデルタールなど先行する人類から多元的に生まれたのではなく、アフリカの「イブ」と仮称されるただ一人の染色体から広がったとされる。実は、現在の家畜馬もただ一つの染色体から生まれ広がったことが分かっている。もと野生であった馬は氷河期ごろまでは世界中にいた。ところが、家畜となった種と野生の一種を残し、他の馬はすべて人間によって狩猟・食され、絶滅したのだ[注1-6]。
現在のヒトは、ネアンデルタールなど先行する人類から多元的に生まれたのではなく、アフリカの「イブ」と仮称されるただ一人の染色体から広がったとされる。実は、現在の家畜馬もただ一つの染色体から生まれ広がったことが分かっている。もと野生であった馬は氷河期ごろまでは世界中にいた。ところが、家畜となった種と野生の一種を残し、他の馬はすべて人間によって狩猟・食され、絶滅したのだ[注1-6]。-
[注1-6]現在も残る野生馬は、プルツェワルスキー種(動物園などに保護されて生存)と言い、染色体数は66である。これに対して、現在の家畜馬の染色体数は、ポニーからサラブレッドまで例外なく64だ。アメリカやヨーロッパ大陸に氷河期まで、野生馬がいたことは化石や洞窟壁画から証明される。その後、馬は姿を消した。
馬はユーラシア大陸中央部で生き延びたようだ。馬と人との再会は、馬が棲む草原と、農耕地帯の周辺で狩猟採集を行なう人々が住む森林の狭間で実現した。黒海北岸のウクライナ地方の遺跡から、現在最古に家畜化されたと思われる状況の化石が発掘されている。紀元前4000年ごろのものと推定される。馬の歯には、手綱をかけた時にできる摩滅や変型の跡もあった。しかし、遊牧生活というものは最初なかったと考えられる。
まず農耕生活が始まって、その地帯あるいは外周で羊や山羊、牛が家畜化されるようになる。そして、やがてそこが文明の中心となっていく。ずっと遅れて、まだ狩猟採集が残る周辺地帯で、野生動物の家畜化が試みられるようになり、そこで馬が家畜化される。最初は食肉用だっただろう。同時に、乗馬も試みられるようになったと思われる。前の遺跡から犂(すき)や車が発見されていないことから、摩滅し変型した馬の歯は乗馬していた結果だと推定できる。
その後、周辺地帯へも農耕と牧畜という生活スタイルが広がるが、しだいに気候の乾燥化が進み、そこでの定住生活が困難となっていく。そうして、生存への適応戦略として、移動しながら放牧する「遊牧」という生活スタイルが生まれたものと推測される。「騎馬遊牧民」の誕生である[注1-7]。ただし、これがそのまま乗馬の全面的普及、大集団の結成や侵略的な騎馬軍団の成立を意味するわけではない。
-
[注1-7]「騎馬民族」という表現ではそういう特定民族があるように思われる、との本村凌二氏の指摘は妥当である。
文明発祥の地メソポタミアで「車」が発明される。しかしこれはロバが引いていたようで、文明地帯では馬はまだ知られていなかった。馬が引く「戦車」を発明したのは、インド・ヨーロッパ語族である。この命名は後ちの拡散地によるもので、彼らの本拠は馬が最初に家畜化されたユーラシア大陸中央部と見てよい。乾燥化し生活環境の悪化した紀元前2000年以降、彼らは次々に文明地帯に襲来し始める。西に進んだのがヒッタイト人など、東に進んだのがアーリア人である。
馬の力は圧倒的であった。鉄製の武器をも手中に収めたヒッタイト人らは古バビロニア王国に襲いかかる。また、アーリア人はインド・ガンジス河流域を席巻した。この馬の力と早さは、はるか後世に蒸気機関が生み出されるまで、数千年にわたって人間の歴史を支配することになる(力の方は「馬力」という日本語として今も残っている)。これに対抗するために、エジプトなどの古代世界に、馬とこれを用いた戦車が急速に普及する。
しかし、東オリエント世界で初の覇者となったのは、戦車ばかりではなく騎馬軍団をも編成したアッシリアであった。紀元前1000年ごろに革新があったと思われる。すなわち、乗馬技術などの確立である。以後、馬は車を引かせるばかりではなく、乗るものだという考えが普及していく。アッシリアの崩壊後、ペルシャ帝国が全オリエントを統一し、古代ギリシャ世界と出会うことになる。ここらで下馬し、水神に戻ろう。
▼海の神にして馬の神であるポセイドン
 ユーラシア大陸にあまねく水神は、ギリシャではポセイドンとなる(ローマに入ってネプチューンと同一視される)。ポセイドンが主神ゼウスの兄弟神にして、海神であることはご存知であろう。この神は馬神でもある。馬に化けて逃げる地母神デメテル(デーメーテール)を自らも馬になって追いかけ、神馬アレイオーンを生まし、鬼神メドゥーサとの間には天馬ペガサスがある。ポセイドンには、泉や海で生き馬の犠牲が捧げられていた。
ユーラシア大陸にあまねく水神は、ギリシャではポセイドンとなる(ローマに入ってネプチューンと同一視される)。ポセイドンが主神ゼウスの兄弟神にして、海神であることはご存知であろう。この神は馬神でもある。馬に化けて逃げる地母神デメテル(デーメーテール)を自らも馬になって追いかけ、神馬アレイオーンを生まし、鬼神メドゥーサとの間には天馬ペガサスがある。ポセイドンには、泉や海で生き馬の犠牲が捧げられていた。ポセイドンは三叉の戟(さんさのほこ)を持ち、乗馬する姿で描かれることが多い(馬が引く戦車に乗ることもある)。ところで「三叉の戟」とは何か。魚を突く銛(もり)である。また、「馬首・魚身」で表現されることもあり、「船の救い主」とも呼ばれる。このように、ポセイドンは海の神にして馬の神なのである。しかし、なぜ馬神が海神(もちろん逆でも良い。海神がなぜ馬神)なのであろうか。
 こう考えられる。ギリシャ人はインド・ヨーロッパ語族の一派であり、早くから馬の文化を知っていたのだろう。そのギリシャ人が南西への長い旅の末、地の果てで見たのが地中海である。そこには白波が走っていた。いまでも「白波」を英語で "sea horse" と言う。すなわち、彼らは海に馬を見たのである。遠い記憶が甦る。それに舟も、あたかも海を行く馬ではないか。こうして、海の神が馬の神となったと[注1-8]。
こう考えられる。ギリシャ人はインド・ヨーロッパ語族の一派であり、早くから馬の文化を知っていたのだろう。そのギリシャ人が南西への長い旅の末、地の果てで見たのが地中海である。そこには白波が走っていた。いまでも「白波」を英語で "sea horse" と言う。すなわち、彼らは海に馬を見たのである。遠い記憶が甦る。それに舟も、あたかも海を行く馬ではないか。こうして、海の神が馬の神となったと[注1-8]。-
[注1-8]実はギリシャの地形は起伏が激しく、馬を乗り回せる平地は少ない。だから、ギリシャでの戦争では馬を使わないことが普通であった。ペルシャ戦争でも、ギリシャ人は「重装歩兵」で戦った。しかし、彼らの嗜好が馬にあったことは確かだ。オリンピア競技での最大の注目競技は戦車競争であった。ローマ人も戦車競争を好んだ。コロセウムは言わばそのために作られたのだ。ギリシャ人(正しくはマケドニア人)で騎馬軍団を使いこなしたのは、ペルシャを征服したアレクサンドロス大王であった。蛇足だが、その愛馬はブーケファロスという。
 さて、ポセイドンは何と牛の神でもであるのだ。三叉の戟を右手に、左手には花の咲く大枝をもって、雄牛にまたがるポセイドン像がある。ポセイドンは「雄牛なる」と冠をつけて呼ばれるのが常であり、雄牛を自分の意志で自由に操った。さらにポセイドンへの正式の犠牲が雄牛だったことをホメロスも証している。一体全体、どうなっているのか。ポセイドンは海神にして、馬神であり、さらに牛神でもあると言うのか。
さて、ポセイドンは何と牛の神でもであるのだ。三叉の戟を右手に、左手には花の咲く大枝をもって、雄牛にまたがるポセイドン像がある。ポセイドンは「雄牛なる」と冠をつけて呼ばれるのが常であり、雄牛を自分の意志で自由に操った。さらにポセイドンへの正式の犠牲が雄牛だったことをホメロスも証している。一体全体、どうなっているのか。ポセイドンは海神にして、馬神であり、さらに牛神でもあると言うのか。実はそうなのである。神話学者ハリソンによれば、こうなる。神は信仰者自身である。つまり、祈る者こそ神である。だから、ポセイドンとは、海を行く民であり、馬を飼う者であり、牛を使い農耕する人なのだと。果たして、そんなギリシャ人がいたのか。エーゲ海のクレタ島でミノア文明を築いた人々こそが実はそうだったと。そこで崇拝されていたのは、クノッソス宮殿の迷宮にひそむ、半牛半人の怪物ミノタウロスだった。
では、ポセイドンの正体とはミノタウロスなのか。確かにポセイドン信仰は、ミノア人が植民したギリシャ各地で見出せる。おそらくエジプトから伝わった牛神ミノタウロスの信仰は、ギリシャ本土ではしだいにポセイドンという馬神へと変貌を遂げ、ついにオリンピアの神殿に駆け上ったのだ[注1-9]。そう言えば、ポセイドンは兄弟神であるゼウスと対抗し、いつも敗退するという、どこか外来神としての性格を匂わしていた。しかし、ポセイドンは本当に水神なのか。
-
[注1-9]古代ギリシャの歴史家ヘロドトスによれば、馬神ポセイドンの信仰は北アフリカのリビア(地中海を隔ててギリシャの南方、エジプト西方に位置する地域)人によって、ギリシャへともたらされたという。彼の同時代には、確かにリビアは良馬の産地として名高かった。しかしすでに見たように、馬とその文化は東方から侵入したインド・アーリア語族によって、紀元前二千年紀以降に持ち込まれたのだ。初めからリビアに馬がいたわけではない。
オリエントやインド方面とは別に、ヨーロッパ方面に進んだインド・アーリア語族の一派(ゲルマン語族)がいた。ギリシャ人やローマ人などである。だから、こう考えるべきかも知れない。ギリシャやローマへは彼ら自身が馬と馬の文化を持ち込んだのだと。その際は、彼らは馬車(戦車)に乗って、やってきたのだと(当時は騎馬習慣はまだない)。もしそうだとすれば、彼らの戦車好きにもよく合点がいく。
▼馬の仮面の下に見えるポセイドンの深層
歴史の順序を再確認したい。おそらくインド・アーリア語族が、ユーラシア中央部で紀元前4000年ごろに馬の家畜化に成功した。そして同2000年ごろ馬につなぐ戦車を発明し、それを使って文明世界に侵入することによって、馬と戦車が世界に知られるようになったのだ[注2-1]。では、それ以前の数千年にわたる東西の文明世界、すなわち「馬のない」オリエントや地中海沿岸地帯、インド、それに中国[注2-2]などの農耕地帯ではいかなる生活があったのか。それは家畜化された牛とともにある生活だった。事実、馬の到来までは、牛こそが神であった。インドのヒンズー教の牛信仰は、アーリア人侵入以前の古信仰をいまに伝えるものと言ってよい。
-
[注2-1]騎馬と騎射の技術はこれよりも遅れる。紀元前1000年ごろまでに、インド・アーリア語族あるいはウラル・アルタイ語族の「騎馬遊牧民」が確立し、広めたものと思われる。
[注2-2]中国への馬とその文化の到来は、オリエントなどに比べるとやや遅れ気味だった。それと、その伝播にはウラル・アルタイ語族系の騎馬遊牧民が「中継者」として深く関わっている。
海の神であるはずのポセイドンへの犠牲は、古くは海へではなく淡水の泉に捧げられていた。地母神であり農業神であるデメテルとの関わりも曰わくありげだ。ポセイドンが左手に持つ「花の咲く大枝」は、彼自身が大地の神であったことの証なのだ。つまり、こういう順序になる。本来、大地の神および地中の冥府の神だった古ポセイドンは、地を支配するが故に農業に関わる神となる。それと同時に農業に必須の水を操る神ともなる。一方、地中から陸ではない海に出ることもでき、そこも彼の支配する所となった。そして、最後に付け加わったのが新しく到来した馬の文化だった。習合神ポセイドンはこれをも貪欲に吸収し、ついに馬神の仮面をかぶったのだ。
▼ポセイドンとスサノヲの共通性
ポセイドン神のこの複雑な性格は、実はわがスサノヲ命によく通じるところがある。まず、各神話の主神の兄弟神であり、その主神と争い、結局は敗れること。言わば、腹違いの継子扱いを受けている。スサノヲは追放されさえした。外来神的な扱いなのだ。しかしこれは、こう考えるべきだ。彼らこそ、より古くから信仰を集めてきた神々であったと。だから、本当の外来神とは、実はゼウスであり、アマテラスだったのだ。馬から牛ではなく、牛から馬だったことを忘れてならない。新しい神たちが排斥しきれなかった固有の神が、ポセイドンでありスサノヲなのだ。
三神を生んだイザナギは、日本書紀では、アマテラスに天を、ツキヨミ(月読)に海を、スサノヲには地を与え、それぞれの支配を命じる。だが、古事記では、アマテラスに天の、ツキヨミに夜の、スサオヲには海の支配を命じている。ここには、明らかに「世界」概念の混乱が見える。天−地(・海)、昼−夜(太陽−月)、地−海、という対概念が入り交じっている。これは、ツキヨミとスサノヲを分離したせいである。本来、彼らは一体のものだったのだ。古スサノヲは、天や太陽(昼)と対になる、大地・冥府(根のカタス国=黄泉国)の神であり、海の神であり、月(そして夜)の神であった。まさにポセイドンと同じ領域を、同じ原理で支配する神だったのだ。
さらに、スサノヲには面白いことがある。アマテラスが天の岩戸に隠れることになったスサノヲの乱行の中で、馬が登場する。スサノヲは馬の生皮を引き裂き、機織り殿へ投げ入れる。従来はこれを単にスサノヲの非農耕的な縄文性と取り、弥生の農耕文化への反抗としてだけ読むことが多い[注2-3]。しかしこれは、前に言った神話論理的に述べれば、スサノヲこそ馬神であるとも、犠牲として馬を捧げている叙述とも読めるのだ。
-
[注2-3]縄文が半農耕文化であったことは判明している。しかし水田稲作ではなかったのだ。次に見るオオゲツヒメは稲の神というより、それ以前の穀物神である。すなわち、古スサノヲへの信仰は、古いスタイルの農耕文化に基づくものと思われる。
-
[注2-4]一つだけ、先に述べておく。古事記だが、イザナギに海を統治せよと言われたスサノヲは、妣イザナミの棲む黄泉国へ行きたい泣き叫ぶ。その時、山の水を枯らし、川や海まで枯らしてしまったとある。これはスサノヲの涙が「地の水」そのものであり、彼が水神であることを言っていることに他ならない。
 ここで、私たち人間の古代生活を想い起こそう。狩猟採集から農耕生活の始まりの中での「世界原理」とは、果たして何であっただろうか。それは太陽ではなく、月の光であった。光のない月立ち(ついたち:朔:新月)に始まり、徐々に膨らんで上弦の半月を経て、15日目には真円の満月(もちづき:望)となる。すると、今度はしだいに痩せていき、下弦の半月となり、ついには闇に中に見えなくなる(つごもり:月籠もり:晦)。この周期が正確に繰り返される。そうした不思議を、古代人は月が持つ「死と再生」の力と読んだ。
ここで、私たち人間の古代生活を想い起こそう。狩猟採集から農耕生活の始まりの中での「世界原理」とは、果たして何であっただろうか。それは太陽ではなく、月の光であった。光のない月立ち(ついたち:朔:新月)に始まり、徐々に膨らんで上弦の半月を経て、15日目には真円の満月(もちづき:望)となる。すると、今度はしだいに痩せていき、下弦の半月となり、ついには闇に中に見えなくなる(つごもり:月籠もり:晦)。この周期が正確に繰り返される。そうした不思議を、古代人は月が持つ「死と再生」の力と読んだ。月には魔力があった。人間の女を、月経周期を通じて支配していたのだ。それは一人ひとり違うが、毎月同じ月の形で始まり、また別の同じ形で終わる。月の魔力が女性に乗り移ったとき、月経は止まり、やがて子どもが誕生した。そして再び、月経は始まる。つまり、月は生殖力を光のエネルギーとして放射していたのだ。この魔力は、人間にだけではなく、地上のあらゆる動植物にも照射されていた。やがて、農耕の始まりとともに、それは大地の力と同一視される。すなわち、「母なる力」である。
また、月は水をも支配した。洪水は月によって引き起こされるものと理解された。その証拠に、新月と満月は海岸線の干満の差が大きい大潮を、正確に統御していた。農耕を左右する雨も、月によって支配されていたのだ。「暦」は「日読み」(かよみ)が転じたもので、そういう日の推移から気象を知る賢者を「日知り」(聖)と言う。これと同様に「月読」(つきよみ)とは、月の満ち欠けを読み、人々を導くことで、これが古代信仰の神名ともなっていたわけだ。
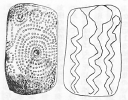 ▼月・大地(母)・水、そして牛
▼月・大地(母)・水、そして牛農耕開始と前後して家畜化された牛は、犂(すき)の発明とともに、犂を引く、農耕に欠かせぬ動物となる。大変興味深いことに、その牛の「角」が古代人には「月」と見えたようだ。三日月のような角を持つ牛は、月の聖獣となる。こうして、月は大地(母)と水と牛とに結びつく。一度結びついたものは、神話論理的に変換が可能となる。例えば牛は、水の中に棲み「再生」能力を持つと考えられた動物、カエルや蛇とも変換される。また、月の力は「渦巻き文」として抽象的にも表現された。

 世界共通に見られる太古の母神像は女性崇拝ではなく、大地の「母なる力」を表現している。中には、牛の角を手にかざす像もある。また、バビロニアの大地母神(大地の神・豊穣の神)イシュタルは月神の娘とされ、雌牛がトーテム(聖獣)だ。エジプトの大地母神イシスも雌牛の角や頭を戴く[注2-5]。インドに渡れば、ヴェーダの主神インドラ(仏教では帝釈天)は雷神だが、その祖神は「豊穣の雌牛」である。三主神の一つ、シヴァ神の聖獣は雄牛ナンディだ。
世界共通に見られる太古の母神像は女性崇拝ではなく、大地の「母なる力」を表現している。中には、牛の角を手にかざす像もある。また、バビロニアの大地母神(大地の神・豊穣の神)イシュタルは月神の娘とされ、雌牛がトーテム(聖獣)だ。エジプトの大地母神イシスも雌牛の角や頭を戴く[注2-5]。インドに渡れば、ヴェーダの主神インドラ(仏教では帝釈天)は雷神だが、その祖神は「豊穣の雌牛」である。三主神の一つ、シヴァ神の聖獣は雄牛ナンディだ。-
[注2-5]大地を支配する女神たちは地下の冥界とも結びつく。「再生」は「死の世界」を経てこそ成し得る業であり、秘儀であるからだ。
-
[注2-6]柳田国男の『遠野物語』にあるオシラ様の起源を物語る説話(69)で、人間の娘と最後は殺される馬との悲恋が描かれる。これは豊穣神への馬の犠牲譚であると同時に、豊穣神となった馬神への乙女の人身御供の話としてこそ、よく理解できる。次のヤマタノオロチの話でもわかるように、怪物=神は乙女との婚姻=犠牲を求めているのだ。
スサノヲ命は天を追放され、地に降り立つ。そこで、わが娘クシナダ姫を人身御供を要求するヤマタノオロチに悩み苦しむ国つ神に出会う。ヤマタノオロチは氾濫する川のことではないかとしばしば指摘されるが、スサノヲがこの怪物を退治してみると、果たして大蛇がその正体であった。大蛇とは水神に他ならない。面白いことに、その尾からは鉄が出る。天叢雲(あまのむらくも)の剣(つるぎ)、すなわち草薙(くさなぎ)の剣である[注2-7]。
-
[注2-7]不要とも思われるが、若干解説しておく。乙女は水神への犠牲である。それを退治できたのはスサノヲも水神であり蛇であったからだ。死んだ水怪が鉄を残したのは、それを嫌ったからだ。剣名の「叢雲」(むらくも)とは、雨を呼ぶ雷雲のことである。
なお、この後、スサノヲは地中の「根のカタス国」に向かう。一方、スサノヲとクシナダの末裔に大国主が生まれる。大国主と同体とされる大物主(三輪神社の祭神)が蛇身だったことは言うまでもない。
天満宮の雷神菅原道真は牛に乗る。天満宮はそもそも天神社であった、天神とは雷神であり、雨の神である。その牛とは天神そのものであり、同時に天神への捧げものなのだ。ところで、雷を「神立」(かんだち)とも言う。「夕立」は今では雨を言うにすぎないが、本来、神の降臨(降り立ち)を意味する。「祟り」も神の「立ち現れ」を指す。神は雷として雨とともに、地に降り立った。その地の姿はしばしば蛇身であった。そして、天に昇った蛇は竜となる。「竜」(りゅう)を「たつ」と訓じる背景にはこれらのことがある[注2-8]。
-
[注2-8]大和の竜田(=立つ・た)神社とは、おそらく著名な落雷地としてあったのだ。すなわち、その地が神のよく降りる神地・祭場として定められたことが社名に残されていると思われる。
以上の水神としての馬と牛の相互変換を、中国における「竜」の合流と変貌としてまとめておきたい。中国は南船北馬の国と言われ、南北の本来異なる文明文化が混合して出来上がった文明だ。北方中国は、「天」・男性原理に関わる儒教的な中国で、「馬の文明」と言える。これに対して南方中国は、「地」・女性原理に関わる道教的な中国で、「牛の文明」であると言える。これは北方中国が、馬の文化が由来する中央・北方アジアにつながっていることからも当然であろう。
今では混同される竜と蛇は本来異なるものである。これは竜が空想の産物だからということではない。竜は元を質せば馬であり、天のものだからだ。それに対して、蛇は地のものであり、その正体は今まで述べてきたように牛である。前者は遊牧文化を、後者は農耕文化を背景にしてある。遊牧文化における馬は、水神ではなかった。それは水神にではなく、至上の天に捧げる供物(主に白馬)であった。しかし、農耕地帯である中国に入った馬はしだいに変貌していく。
空を自由に駆けめぐる天馬が竜馬であるが、馬が牛に代わる水神への犠牲獣となることによって、竜は天から雷となって地へと向かう。一方、地下水を通じて全世界を行き来できるとは言え、地の水中に封じ込められていた蛇も、空中の降雨あるいは虹を伝って、天へと向かう。南北文明の融合を幾度も繰り返すことで自らを形成した中国文明は、このようにして馬であり蛇(牛)である「竜」を生み出したのだ。
▼水神としての猿
河童の異名は多くある。ガアタロ(壱岐)、カワッソウ(肥前)、カワロ(但馬)、ガタロ(播磨)、カワタロウ(畿内)、ミズシ(能登)、ガワラ・ガメ(越中)等々。そういう中で「エンコウ」と呼ぶ地方がある。出雲から長門にかけての山陰西部、および伊予・土佐の四国西方だ。これはずばり「猿猴」(えんこう)、つまり猿のことだ。九州では、姿形ばかりか泣き声も猿に似ていたという報告がある。また、大和の「猿沢池」が代表例だが、猿を含んだ水辺の地名は数多い。猿もまた水に親しい動物だったのだ[注3-1]。
-
[注3-1]河童のイメージは2系統ある。東日本系の「亀・スッポン」と西日本系の「猿・カワウソ」だ。これが合体して、よく知られた河童像が誕生した。すなわち、ざんばら髪に皿を載せ、背中には甲羅を背負って、口はクチバシのように尖り、指の間に水掻きを持った男童の妖怪である。頭の皿以外は、河童の異名もその身体的特徴も、この2つの原像からほぼ想像できる。
では、頭の皿とは何か。まず、男童の妖怪であることから、初めはおかっぱ頭だったと考えつく。そして皿は成人した武士の月代(さかやき)をヒントに考案=想像されたものだろう。だから、これは割れたりする「皿」そのものではない、と考えるがどうだろうか。ちなみに折口信夫は、皿の重要性をことさら指摘する。しかも皿は伏せられてあると言う。皿は河童が神であることを証明する「笠」であると考えたのだ。
なお、河童が男童であることは「桃太郎」や「座敷わらし」などの幸運(あるいは不幸)をもたらす「小さ子」伝承の系譜にもある存在だということを示している。
-
[注3-2]面白いことに、このテーゼは現代にも適用できる。これに従うと、アフガンとイラクの政権を武力打倒した米ブッシュ大統領は、ビン・ラディン、サダム・フセインと同類ということになる。現代の「物語」もそういうふうに出来ている。

 ところが、馬や牛と違って、猿と水との結びつきは、西洋にはなく、日本・中国・インドなどの東洋世界に限られている。これは野生猿の生息圏と一致しているのだ。日本では日枝大社[注3-3]の神使としての猿やお伽噺、中国ではあまりにも有名な猿猴・孫悟空、インドでは『ラーマーヤナ』に登場する猿猴ハヌマーン(ハヌマンタ)など、多くの猿物語がある。そして、猿と馬との関わり、さらに猿が馬を守るという伝承はどうやらインド始原のようだ。
ところが、馬や牛と違って、猿と水との結びつきは、西洋にはなく、日本・中国・インドなどの東洋世界に限られている。これは野生猿の生息圏と一致しているのだ。日本では日枝大社[注3-3]の神使としての猿やお伽噺、中国ではあまりにも有名な猿猴・孫悟空、インドでは『ラーマーヤナ』に登場する猿猴ハヌマーン(ハヌマンタ)など、多くの猿物語がある。そして、猿と馬との関わり、さらに猿が馬を守るという伝承はどうやらインド始原のようだ。-
[注3-3]「ひえ」大社と読む。比叡山延暦寺の地主神。東京・永田町にあり「山王祭」で有名な日枝神社は、これの勧請神である。
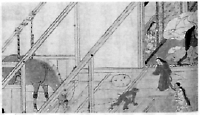 正月を言祝ぐ猿回しは明治時代まで見られたが、それが見せ物だけではなく、馬医者を兼ねていたと述べたのは柳田国男だった。事実、中世の絵巻物『一遍聖絵』や『石山寺縁起絵巻』には、馬を飼う厩(うまや)に猿がつながれている絵がある。猿には馬を病気やけがから守る霊力があると信じられていたのだ。それが「河童駒引」につながっていると思われる。中国地方では、厩の柱に猿の頭蓋骨やミイラ化した腕をかけて、牛馬のお守りとしている所もあった。
正月を言祝ぐ猿回しは明治時代まで見られたが、それが見せ物だけではなく、馬医者を兼ねていたと述べたのは柳田国男だった。事実、中世の絵巻物『一遍聖絵』や『石山寺縁起絵巻』には、馬を飼う厩(うまや)に猿がつながれている絵がある。猿には馬を病気やけがから守る霊力があると信じられていたのだ。それが「河童駒引」につながっていると思われる。中国地方では、厩の柱に猿の頭蓋骨やミイラ化した腕をかけて、牛馬のお守りとしている所もあった。インド北部には、猿を厩につないでその守護とする習慣が今も残っているという。また、古い説話には火事で火傷した馬を、猿の髄から作った薬で治療したという話がある。さらに、中国・晋朝にはインド伝来かと思われるが、猿が死んだ馬を蘇生させた話もある。宋代には、猿は馬の疫病を防ぐとされ、厩に猿を飼う習慣が中国に広がったようだ。病はかつては悪霊のなせる業であったから、これが馬の尻小玉を抜く「河童駒引」となったのかも知れない。
▼日光東照宮の三猿と庚申信仰
 ところで、猿と言えば、何を思い出すだろうか。「三猿」、つまり「見ザル・言わザル・聞かザル」はご存知だろう。これがかの日光東照宮にもある。名匠・左甚五郎による作という代物だ。同じく左甚五郎作と伝わる木製白馬のための「神厩舎」の欄干に彫り込まれている。やはり、ここでも猿は厩につながれていたのだ。では、この三猿とは一体何なのか。また、それがどうして徳川家康の墓所である東照宮なぞにあるのだろうか。
ところで、猿と言えば、何を思い出すだろうか。「三猿」、つまり「見ザル・言わザル・聞かザル」はご存知だろう。これがかの日光東照宮にもある。名匠・左甚五郎による作という代物だ。同じく左甚五郎作と伝わる木製白馬のための「神厩舎」の欄干に彫り込まれている。やはり、ここでも猿は厩につながれていたのだ。では、この三猿とは一体何なのか。また、それがどうして徳川家康の墓所である東照宮なぞにあるのだろうか。 三猿とは、中国伝来の庚申(こうしん)信仰に基づくものである。庚申とは、干支の一つ「庚申」(かのえさる)の夜、人の腹中に棲む3匹の虫「三尸」(さんし)が人の睡眠中に身体から抜け出し、天帝にその人間の罪過を告げて早死にさせるというもので、長生きするにはその夜は徹夜して、三尸が身体から抜け出さないようにしなければならないと説く信仰である。その徹夜の行事を「守庚申」や「庚申待ち」などと言う。
三猿とは、中国伝来の庚申(こうしん)信仰に基づくものである。庚申とは、干支の一つ「庚申」(かのえさる)の夜、人の腹中に棲む3匹の虫「三尸」(さんし)が人の睡眠中に身体から抜け出し、天帝にその人間の罪過を告げて早死にさせるというもので、長生きするにはその夜は徹夜して、三尸が身体から抜け出さないようにしなければならないと説く信仰である。その徹夜の行事を「守庚申」や「庚申待ち」などと言う。この庚申待ちは、日本でも早くから行われていて、平安時代の日記などを見ると、詩歌管弦、碁、双六などの遊びをして徹夜したことが記されている。それが、室町時代半ば以降、仏教や修験道が関わりをもつようになり、それまでの遊宴中心の宮廷行事から、僧侶や修験者が指導する信仰行事へと変化していったのだ。江戸時代以降には、村ごとに「庚申講」が作られ、村人がそろって庚申待ちで一晩夜明かしをしていた。
 今でも田舎の道辻に行けば、その頃の庚申塔が残っていることがある。その石塔には、天の邪鬼を踏みつけて立つ「青面金剛」(しょうめんこんごう)像が刻まれ、たいてい一緒に三猿がある。この庚申信仰の民間普及には天台宗系の修験者が関わっていた。その中で青面金剛が庚申信仰の主尊になったのだ。また、申(さる)を動物の猿と見なし、三尸をそれぞれブロックする猿として「見ザル・言わザル・聞かザル」が登場したのである。これには、天台宗の総本山延暦寺の地主神日枝大社の神使が猿であるとする伝承の影響が大きかった。
今でも田舎の道辻に行けば、その頃の庚申塔が残っていることがある。その石塔には、天の邪鬼を踏みつけて立つ「青面金剛」(しょうめんこんごう)像が刻まれ、たいてい一緒に三猿がある。この庚申信仰の民間普及には天台宗系の修験者が関わっていた。その中で青面金剛が庚申信仰の主尊になったのだ。また、申(さる)を動物の猿と見なし、三尸をそれぞれブロックする猿として「見ザル・言わザル・聞かザル」が登場したのである。これには、天台宗の総本山延暦寺の地主神日枝大社の神使が猿であるとする伝承の影響が大きかった。さらに、家康の信認篤く、その死後の東照宮造営に深く関与した天海は比叡山に学んだ僧であった。彼は「山王一実(さんのういちじつ)」という独自の神道を創始した。山王とは日枝大社のことで、その神使である猿を神聖視した。そのことが、東照宮・神厩舎の欄干に三猿を刻ませ、また江戸初期に庚申信仰と三猿を爆発的に普及させる後押しをすることになったのだ。
▼石川五右衛門と夏目金之助、そして乗馬猿
そろそろ、この話も締め括りたい。庚申塔はどういうわけか、たいてい道辻にある。そしてそこには道祖神や馬頭観音もある。馬頭観音とは、文字通り馬の首を頭に載せた観音様だ。その庚申塔に三猿が刻まれていれば、猿は馬と近接して置かれているということになる。どういうわけでそうなったのかは分からないが、辻とは村の果てのことであるから、馬を神に捧げた場所ということなのかも知れない。
さて、大泥棒石川五右衛門の誕生日の干支をご存知だろうか。もちろん伝承だが、庚申の日(あるいは庚申の夜に宿った)ということになっている。すなわち、庚申に生まれると盗人になる運命であるらしい。その日に生まれた大作家がいた。誰あろう、文豪夏目漱石その人である。両親は大いにあせり、「金之助」と名前を付けた。これは陰陽五行説の「金」に基づく魔除けだが、筆者には、水神である猿(申)が金属を嫌っているように見えて面白い。
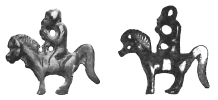

大団円である。ついに猿は馬に乗る。「乗馬猿」というモチーフがユーラシア騎馬遊牧民にある。なぜ、野生猿がいない北部ユーラシアにそんなモチーフがあったのかは謎である。インドあるいは中国から伝わったとしか考えられないが、馬具の装飾に確かに乗馬猿が刻み込まれていた。ともあれ、こうして牛・馬・猿となった水神は、日本では河童となり、同類である猿がこれまた同類の馬を守るという配役で「河童駒引」という劇を演じるようになったのである。
-
柳田国男「河童駒引」(全集/第5巻『山島民譚集』所収)筑摩文庫
折口信夫「河童の話」(全集/第3巻『古代研究(民俗学編2)』所収)中公文庫 中公クラシックス版
石田英一郎『河童駒引考』岩波文庫
本村凌二『馬の世界史』講談社現代新書
新谷尚紀『なぜ日本人は賽銭を投げるのか』文春新書