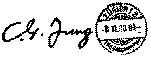mansongeの「ものぐさ本舗」創刊記念号
 ユングによる「宮沢賢治とグノーシス」
ユングによる「宮沢賢治とグノーシス」
日本における宮沢賢治の文学は、一つの奇跡である。二度目の世界大戦は世界に終わりをもたらしてしまったからだ。それからというもの、万物と交感する文学は絶えて久しい。このことは同時に次のことを意味している。すなわち、人間の万物からの孤立であり、ひとつひとつの魂が彷徨を続けることである。端的に言うと、人間は夢を見なくなった。人間は自我の奥の無意識を捨てたのだ。

第一次世界大戦、いやこれは後になっていう言い方だ。世界大戦、これが正しい。つまり、初めてであってかつ今後はない最終戦争、と見做された戦争。世界はこの戦争で画期されたのだ。世界に「大戦以前-以後」の意識が成立した。
この世界大戦は文化史的には奇妙な豊饒をもたらした。古来、皮肉にも戦争が人々に認識の変容を強いてきたが、この世界大戦はヨーロッパの没落意識と引き換えに、統合された新たな世界認識を拡げた。20世紀という新時代を迎えて沸き立っていたヨーロッパは相対的に世界を取り戻したのだ。こうして当時の最先端科学の諸成果と相まって「地球的」「宇宙的」「四次元的」世界認識が成立した。
ロシアでは、のちにロシア・アバンギャルドと総称される百花撩乱の一大芸術運動が巻き起こっていた。ロシア革命すら、このアバンギャルドを産湯にして起こったと言ってもよいかも知れない。フランス、ドイツでも次々に芸術運動が怒涛のように押し寄せていた。また、科学・技術分野での新発見や新発明も相次いだ。それもアインシュタインの相対性理論が典型的なように、世界認識に革命をもたらす構造的な激震として世界を襲った。
要するに、世界は根底から変わろうとしていた。新しい世界を夢見ていた。これは無意識の噴出である。事実、われわれの20世紀はそうして出来上がったのだ。結果の善悪はともあれ、ロシア革命とナチズムは、その最も明瞭な変革モデルにすぎない。現実化しなかった夢想モデルや、挫折した変革モデルは数知れない。しかしこの「世界大戦」後の世界地平には、まだ結末は見えていなかった。むしろ、地平線は無限に続くように見えていたはずだ。モダニズムへの信頼は揺らいでいなかった。宮沢文学もこのような「戦後」の世界認識が生んだものといえる。
さて、グノーシスとは何か。一般的には初期キリスト教の異端と看做されている。確かにそうではあるのだが、これにとどまるものではない。グノーシスとは、人間にとって普遍的な宗教のあり方の一つなのである。それもたいへん重要なあり方なのである。
ちなみに、宗教とは何か。これは簡単には言えない。ここでは何らかの神を戴く世界観・人間観としておく。もしそうだとすると、その神の有り様は人間の有り様を語っている。つまり、キリスト教の神はキリスト教徒の、グノーシスの神はグノーシス教徒の考える人間の構造が示されている。
グノーシスは、神の流出を説く。天上のプレローマ界という最高天からアイオーンと呼ばれる善神が流れ出た。最後に誕生したのはソフィアだ。あるとき、そのソフィアが地上に落下する。地上でソフィアはデミウルゴス(ヤルダバオト)を作った。デミウルゴスは地上の創造紳として悪神アルコーンのほか、地上の宇宙を創造する。デミウルゴスは無知にして、自身の誕生を知らず、自らこそが最高神と思い上がる。ソフィアはデミウルゴスが作った人間の肉体の中に霊的な種子を忍び込ませていた。
このようなことからグノーシス教徒は、創造神を否定し現世を拒否し、プレローマ界への霊的な回帰を目指す。人間神化の思想、人間と神とのつながりを認める思想といえる。
これに対しキリスト教はどうであろう。キリスト教では神と人間との断絶が特徴だ。人間は原罪を背負って神の恩寵をひたすら待つ。かろうじて神が人間化したことがただの一度だけある。
私が言いたいのはこういうことだ。グノーシスは人間の心の底に何者かの存在を認め、キリスト教はそれを認めない。キリスト教的な人間観は薄っぺらな自我を生み、グノーシス的な人間観はそれ以上の何かを生んだ。それは無意識と呼ばれるものを含んだ自己だ。
19世紀までの自我は貴族たちのものだった。20世紀の各国のアバンギャルドたちはこれを打ち破る運動を起こしたのだ。また、世界大戦によるヨーロッパの没落はヨーロッパの自我意識を弱めることになった。ここに20世紀前期の人間観の登場がある。
宮沢賢治は言うまでもなく、仏教徒である。仏教はグノーシス的な宗教だ。仏性(=神性)を人間の中に認める。ただし、彼は保守的な宗教人ではなかった。彼を狭い意味での仏教徒と解しては間違いである。彼は世界人であった。20世紀前期の人間観を間違いなく抱いていた。それは、地球的宇宙的四次元的宗教科学とでも言うべきものだった。
彼が文学において試みていたことは結局、自己の探求ということではなかったのだろうか。自分を探すこと。自分が何者であるかを知ること。彼の文学が、少年文学にならざるを得なかったのはこのことに起因している。
彼の童話世界はユートピアだ、どこにもないという意味で。なぜどこにもないのか。心(ゼーレ)の中にあるからだ。心の中にあるから、読者の共感も得るのである。彼は夢見ていた、世界の変革を。夢のような世界が来ることを。そのとき、霊の問題が起きる。仏に成れるのか…。
童話に比べて彼の詩には、自己の探求という性格がよく出ている。
 うしろから五月のいまごろ
うしろから五月のいまごろ黒いながいオーヴァを着た
医者らしいものがやつてくる
たびたびこつちをみてゐるやうだ
それは一本みちを行くときに
ごくありふれたことなのだ
(中略)
この人はわたくしとはなすのを
なにか大へんはばかってゐる
それはふたつのくるまのよこ
はたけのおはりの天末線(スカイライン)
ぐらぐらの空のこつち側を
すこし猫背でせいの高い
くろい外套の男が
雨雲に銃を構へて立つてゐる
あの男がどこか気がへんで
急に鉄砲をこつちに向けるのか
詩集「春と修羅」小岩井農場より
実はこの影元型以上に顕著な、彼の元型はアニマ(女性)である。
-
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゆとてちてけんじや)
詩集「春と修羅」永訣の朝より
宮沢文学における象徴なら、読者の方が詳しいあろう。だが、鳥と夜とについては一言しておこう。
鳥は天と地をむすぶ者、すなわち意識と無意識をむすぶ者だ。よだか、「オホーツク挽歌」の鳥、「銀河鉄道の夜」の鳥捕り男、すべてそうだ。ふつうに言う、生と死をむすぶ者だ。これらは彼の心の中の象徴である。
それから、夜。いうまでもなく、ムードや暗さのことを言っているのはない。それは秘儀の時間である。四次元が、つまりあらゆる越境が許される、世界が開く時間が夜である。死と再生の夜。だから銀河鉄道は夜に走らねばならない。明らかに彼は夜の意味を知っていたと言わねばならない。
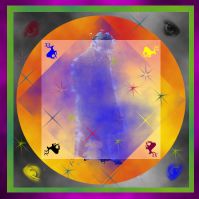
夢。宮沢賢治は夢を生きていた。それは無意識の中をゆく旅だ。彼の描く世界はまるで映画のようだ。映画は、現世とは別の時空間、異次元を生きる、まさに四次元的な世界だ。
彼の童話はなぜ読者の心を打つのか。読者は思い出すのだ、自分の人生より前にあった出来事を。彼は自身の普遍的無意識を語ることによって、読者の普遍的無意識を呼び起こす。人生は個性化されるが、普遍的には同じことの永遠なる繰り返しなのだ。これは同じ夢を見ることではない。同じ元型であるということだ。
彼はマンダラのような童話をたくさん作った。どれもこれも元型的である。神話的だと言ってもよいかも知れない。神話は、世界が更新される時代の文学である。その意味からいっても、宮沢賢治の文学は20世紀前半期の文学である。現代、つまり第二次世界大戦後の世界では、これは青少年が大人になる時期の文学であろう。この第一の個性化の時期、自己を創るとき、人間は神話的である。これ以降は、人生に行き詰まりでもせぬ限り、現代人は非神話的であり、意識・自我に固執しがちだ。
第二次世界大戦がもう一度世界の意味を変えてしまってから、われわれは普遍的無意識とのつながりを失いつつある。人間にとっては目覚めることとともに、夢見ることも大事なことである。私は宮沢賢治の文学がいつまでも愛されることを願って止まない。