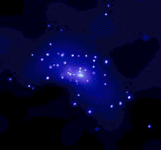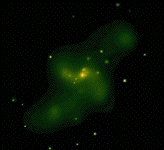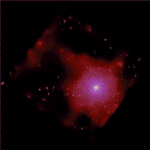mansongeの「ものぐさ本舗」第19号
世界内存在としての人間による自然の科学
▼科学は人間に限界づけられている?
先日ある機会があって、日本の理論物理学の第一人者である佐藤文隆氏[注1]とお会いできた。そこで次のような興味深い話を聞いた。20世紀の二大基礎理論である相対性理論と量子力学には、不思議なことにいつまで経っても破綻が訪れない。これは完璧な理論であるというより、かえって人間の限界を示しているのではないだろうか。人間の認識機制(システム)が変わることがない限り、この両論は破れることが「出来ない」のではないだろうかと。
[注1]湯川秀樹の弟子で、京都大学名誉教授、湯川記念財団理事長。若くしてアインシュタインの重力方程式の新しい解を発見し、それまでただ暗黒イメージだったブラックホールが、過去が未来でもあるという「裸の特異点」であることを解き明かしたことなどで知られる。
これは科学とはそもそも何であり、人間とは全存在すなわち宇宙の中における何者なのかを反問する問いかけであろう。そして、「人間は人間を超えられない」という一見自明のように見えて、実は科学史の中においては問うことが無意識的にであれ、長らく看過されてきた問いをもう一度問い直すことに他ならない。だが、科学は人間の限界を超えることによって発展してきたのではないのか。私たちは深いパラドックスに落ちる。
そう、問題はパラドキシカル(逆説的)なのだ。「人間とは何か」を問うために「存在とは何か」を問い直し、パラドキシカルにあるいは自己言及(「私は嘘つきであるが、これは嘘ではない」のような矛盾を抱え込んだ言明の仕方)的に、自身の存在を唯一認識できる存在者として人間を措定したハイデガーに倣うように、問題のありかを足元から見つめ直さなければならないのだろう。
▼「世界内存在」としての人間
生物学者ユクスキュールは「環境世界」というコンセプトで、各生物はそれぞれの認知世界の内に生きていることを示したが、そもそも私たち人間が無限定に「世界」と呼び慣わしているものは、単に人間の認知できる一「環境世界」にすぎないのではないか。また、私たちが特別扱いして止まない人間の「精神」も、そういう環境内行動のための一戦略機能ではないのか。
植物が精神を持っていないのなら、それは脳や神経組織を持っていないからではなく、精神を持つ必要がないからであろう。動物の精神も同様で、彼らには意識が必要であっても人間の理性なぞ不要なのだろう。進化とは、高等や下等という言葉遣いに含まれる優劣の構造ではなく、それぞれの生物が棲むべき「環境世界」とそれに見合う認知機能の分化の構造にすぎないとも思われる。
一生物である人間は、宇宙を外側から一度たりとも眺めたことがない。つまり人間は、ハイデガー流に言えば「世界内存在」である。「世界内存在」という意味はこれにとどまらない。徹頭徹尾、世界=宇宙内部の生成物として人間という存在者があるということだ。人間の認識機制は「世界内存在」として、世界を内側から眺める者として、あらかじめ厳密に内的に規制されているのである。
生物は自身にとって意味あることしか認識できないように出来ている。それ以上と以下(あるいはそれ以外)は知る必要がないとも言えるが、おそらくより重要なことは、その生物にとっての有意味な認識をなすべき対象と方法の構造的な選択にある。それは思考経済(ムダなことは考えない)に似た認知経済(分からないことは知らない)であるようにも見えるが、そうではない。ある選択をしなければ対象認識の意味を失う、という認識行為にとっては決定的なある構造なのだ。意味とは客観的な何かではなく、現象学で言う「ノエシス(意識)−ノエマ(対象)」のように、主観と客観(対象)との相関的な出来事以外の何者でもない[注2]。[注2]言うまでもなく、各生物にもそれぞれの「ノエシス−ノエマ」があり、それに従った認知が行なわれているのだろう。これは「世界」の多義的解釈の可能性を意味する。つまり、人間の認識がいかに優れたものであれ、一立場の見方にすぎないという相対化を要請する。
▼西欧が生んだ科学とは何か
ここで、科学というものについて改めて考え直してみたい。普遍的つまり世界中どこでも通用する科学は、ただ西欧にしか生み出されなかった特殊で奇妙な営為である。なぜ西欧だけに生まれたのかという問いははなはだ悩ましい。その宗教の本源を同じくするユダヤ教やイスラム教の地帯、さらにはキリスト教でもギリシャ正教の地帯では「科学」は生まれなかった。ただローマ・カトリック教(とその分裂体であるプロテスタンティズム)の西欧にのみ「科学」は誕生したのだ。
筆者には、科学者の目は外在的であると言った精神分析学者ラカンの言葉が示唆的に思える。すなわち、科学は神の視線で世界=宇宙を捉えようとする営為なのだ。ニュートン物理学はその典型である。この外在性=神の目は、西欧人が確立したキリスト教による神と世界理解に密接に関わっている。おそらくローマ・カトリック教の「神が人となったイエス・キリスト」という神理解が、人間の精神に神性が分有されているという解釈を生み、やがて人間一般を「神」としたのだ。
このことを「宣言」したのはデカルトであり、それが万人の有する「理性」(デカルト自身の言葉では「良識」)である。デカルトもニュートンも神を必要としたが、それは当時の宗教上の配慮である以上に、人間の目=認識を神の視線の高さにまで高めること、つまり神のような外在性を得るためである。外在性とは、現実には超えたことがない、また出来もしない宇宙の外から世界を眺めることが可能な理論的な立場である。これは宇宙などの極大世界だけにではなく、極小の世界への視線でも同様だ。
中世の宗教世界に対する近代科学の勝利として何度も語られるコペルニクスとガリレオの地動説は、常識的に考えれば明らかにおかしい。神の目から世界を眺める「科学」とは、たとえ正しくとも人間の日常性を、生活人としての人間を裏切る営為であることを忘れてはならない。それから、デカルトの理性理解が近代社会の基礎となる神聖なる(=神性ある)「個人」概念[注3]をもたらし、ニュートンの唱えた均質な宇宙概念が要素還元主義[注4]をもたらしたことを言い添えておこう。
[注3]いまや万能で「普遍的」となった「個人」も、「科学」と同様、現実を超越した神性を備えたものだ。これが西欧にのみ生まれた、はなはだ疑わしい代物であることだけは銘記願っておこう。
▼量子力学が暴いたヒューマニズムとしての科学
[注4]全体は要素から成り、要素の総和が全体であるという思想。世界は分割できない「アトム」(原子)から出来ているというアトミズムが典型であり、現代も続けられている物質の究極素子を探究する試みもこの流れの中にある。後述するが、ここには人間が神の目を持つことが暗黙に前提されている。
それまで神の視線であったはずの科学を異化したのは量子力学である[注5]。あらかじめ結果が予想できない「シュレジンガーの猫」の喩えで知られるように、微小世界で人間は神ではなかったことを思い知らされたのである。これはなぜか。この階層レベルの認識が本来人間には不必要であったからだ。知っていけないものではない。しかし無限定には知る必要がないから、つまり人間が生きている環境世界ではないから、人間がそのままには理解できないように人間自身がそうできているのだ。
[注5]天才アインシュタインの相対性理論も、それまでの物理理論から言えばもちろん奇妙な世界理解だった。しかし量子論のような「不確定性」なぞはなかった。量子論との違いはアインシュタイン自身が「神はサイコロ遊びをしない」と言って、最後まで量子論を認めなかったことにも表明されている。
普遍的と見なされる数学の論理性も、よくよく考えてみれば「人間だけが理解できる」論理である。人間という存在者によって規定された一パターン認識であると言える。「自然は数学という言語で記述されている」と言われるが、あまり正確な表現ではないだろう。あくまで人間論理による自然世界の読み取りにすぎない。かと言って人間の妄想でもない。それが証拠に、ロケットは数学で描かれた軌道・弾道の上を正しく飛んでいく。客観とは人間を離れたものではなく、あくまで両者の相関的な出来事だとさえ理解できればよい。
人間があるいは科学が対象だとか客観だとか言ってきたものは、実は人間を基準にした対象であり客観であったのだ。科学認識が神の認識だと思い込んだことが誤謬であり、それはヒューマニズム(人間中心主義)だったのである。人間の目こそが神の目に等しいと、のぼせ上がっていたのだ。量子力学はそういう「ヒューマニズムとしての科学」を暴いたとも言えるだろう。
▼科学とは「人間による自然の科学」
それでも、そんなはずはないと「科学の絶対性・超越性」を信じようとする向きもあろう。特に、宇宙の果てを眺める電子望遠鏡、微小を捉える電子顕微鏡、また人間が本来なら認知できないはずの赤外線センサーなどで、これまで認知不可能であった世界が知れることから、現に人間は人間の認識機制を超えているではないかとの反論が当然あるだろう。しかしそれは考え違いだ。それらは人間の認知限界を拡張するものではない。人間が認知しているのはあくまで人間が認知できるものだけだ。それらは人間が認知できるように、言わば「翻訳」された「訳文」にすぎず、リアルなモノ自体(カントの物自体?)ではなく、人間の認知範囲そのものには何の拡張もない[注6]。
[注6]脳を含めた人間が有する身体的な限界、つまり人間の認知器官の限界だとひとまず考えてよい。だが、思念世界のイデア(観念・概念)についても同様だ。例えば「三角形」や「直線」という概念、また時間や空間の認識形式も、アインシュタインの四次元世界ではあまり有意味ではない。例えば犬というイデアが人間に普遍的に通用するように見えるのは、むしろ「人間の限界」を人間として等しく共有している証ではないか。
養老孟司氏の「唯脳論」という考え方があるが、これも人間知のトートロジー(同語反復)を説くものだと思う。すなわち、私たちは私たちの脳が認知できるものしか認知できないのだ。パスカルの、人間は宇宙の「中間者」だというパンセ(思索)は正しい[注7]。私たちは宇宙=存在全体の中空階層に立つ一存在者にすぎない。翻って、逆説的に私たちのヒューマニズムは正しいのだ。ただし、それがあくまでヒューマニズムであるということを思い知ることが必要なのだが。
[注7]いま科学の世界では、世界構造の「存在階層」に関心が注がれている。微小世界へのそれは要素還元主義的なもので、クォークの下位階層は振動する「ひも」ということで一件落着しようとされている。だが、真相は知るべくもないのだ。存在階層は無限に遠のいて行く。これは極大の世界、拡張する宇宙についても同様だ。一「世界内存在」者である人間には原理的に探究不可能なのだ。私たち人間は全存在の中空に立つ中間者にすぎないのである。冒頭の佐藤博士の言うこともこのことであろう。
自然言語を数学論理から切り離したいという欲望が科学者にはあると思われる。しかし、それは直観的に両者が同源だと感じ取っているが故である。どちらも人間が、しかも人間だけが認知できる論理だ。言わば「環境内言語」だ。言語と数学による自然世界の記述の無限性がその認識のヒューマニズムを証している。人間と対象、見る人間と見られる対象によって無限の記述は成立している。無限定な、つまり一義的(あるいは「全義的」と言うべきか)な神の認識は、人間には原理的に不可能なのである。
例えば「虹は何色か」という簡単な認識問題を取ってみても、人間としての普遍性は得られない。それは自然世界をそう見る必要があって、あるいはなくて、日本人だけが七色と見え、外国人には六色以下にしか見えないのだ。構図なり文脈の中でこそ、「認識」というものが成立しているということだ。アインシュタインが示したことの一つは、「原因→結果」が人間的論理にすぎなかったということだ。私たちは「原因→結果」の構図なり論理の中に世界を切り出して見ていたのだ。それが人間にとり有意味な論理であったからだ。
繰り返しになるが、必要な「意味」は絶対の自然ではなく私たちの方が決めている。「生物が複雑であり、気体が単純だ」というのがその典型だが、それはそういう風に理解することが人間にとって有意味だからだ。目的によって観測のあり方が規定されているのだ。科学とは絶対的な「神の認識」ではなく相対的な「人間による自然の科学」であったということである。
[主なネタ本など]
佐藤文隆『宇宙論への招待』岩波新書
佐藤文隆『アインシュタインが考えたこと』岩波ジュニア新書
養老孟司『唯脳論』ちくま学芸文庫
新宮一成『ラカンの精神分析』講談社現代新書
Copyright(c)1997.07.27,"MONOGUSA HOMPO" by mansonge,All rights reserved