生産品一覧
ほうれん草
 |
葉や茎が縮んでしわしわになったホウレンソウが注目されています。ホウレンソウが寒さに耐えるために葉に糖などを蓄える性質を利用して、冬の冷たい空気にさらすことにより、通常のホウレンソウよりも甘くなった「寒締(かんじめ)ホウレンソウ」です。糖度が上がるだけでなく、ビタミン類の含有量も高くなります。葉の色も濃くなり、甘味だでなく濃厚な味になるといわれています。 |
小松菜
 |
ホウレンソウに比べ、栄養面で落ちるかのように思われがな小松菜ですが、これは誤解で、ビタミンAひとつをとっても、小松菜のほうが多く含ンでいるうえ、カルシュウムでは約4倍と大きく上回ています。加えてアクの少ない小松菜は生で食べられるのもうれしい点です。この場合、壊れやすいビタミンCもホウレンソウより多くとることができます。粘膜や皮膚を強化するA、発がん物質の作用を弱めるC細胞の老化を促す過酸化物質を抑えるEと、老化を防ぐ3大ビタミンを含むのが小松菜の特徴です。 |
スイカ
 |
大和スイカの本場で糖度10以上のスイカを生産しています。農薬ほとんど使わず、祭りばやしを栽培しています。またスイカには、果肉や種子に含まれるカリウムは疲労回復ならびに利尿作用があるため、暑さで体力を消耗し水分を過剰摂取することで起こりがちな夏バテに効果があるとされている。スイカから発見され、他のウリ科の作物に含まれる機能性成分としてシトルリンが注目されているが含有量は低い。 |
かぼちゃ
 |
完全に熟してから食する。ビタミンAを豊富に含む。皮は硬いが長く煮ることで柔らかくして食べることができる。サツマイモと同様にデンプを糖に変える酵素含んでおり、貯蔵によってあるいは低温でゆっくり加熱することによって甘味が増す。従って収穫直後よりも収穫後1ヵ月頃が糖化のピークで食べごろになる。冬至にかぼちゃを食べる習慣があるが、前述のように糖化に時間がかかり晩秋以降に食べごろになる。 えびすかぼちゃを栽培しております。 |
甘とう美人
 |
食べた感じも万願寺唐辛子とよく似ており、果肉の厚さは中程度で柔らかく、青臭みや苦味、クセなどはなく、風味も良く食べやすい唐辛子です。健康効果抜群の甘とう美人。辛くないのでたくさん食べて十分な栄養を摂取できる点も魅力です。 |
たまねぎ
 |
野菜の中で最も糖質が多く、果糖、ブドウ糖、ショ糖がほぼ同量ずつ含まれます。糖類はほとんどがエネルギー源として消費されます。カリウム、亜鉛、リン、ビタミンB1、B2、Cなどを含みます。特質すべき成分は、たねぎの刺激成分である硫化アリルなどのイオウ化合物です。硫化アリルは非常に揮発性の高い成分で、たまねぎを切った時に涙がでるのはこの成分が原因です。硫化アリルは加熱すると非常に糖度の高いプロピルメルカプタンという物質に変化します。たまねぎを加熱すると甘くなるのはこのためです。 |
ジャガイモ
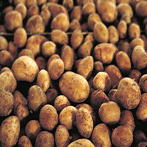 |
「ジャガイモ」といいう呼び名について、「ジヤガ」とはジャガのジャガトラ(ジャカルタ)から伝播したことに因む。これが変化して現在のジャガイモという名になった。ただし異説もあり、ジャワ島の芋の意味のジャワイモが変化したもの、天保の大飢饉でジャガイモのおかげで餓死を免れたことからも呼称された「御助芋」が転じたものなどともされる。また、1年に2〜3回収穫できることから「にどいも」「さんどいも」呼ばれる。「南京イモ」「ごしょいも」とも呼ばれることもあります。 |
キャベツ
 |
キャベツは、甘藍(カンラン)、玉菜(タマナ)とも呼ばれ、原産はヨーロッパの地中海沿岸および大西洋沿岸地帯の野菜です。キャベツはビタミンC、ビタミンK、カルシュウムが主な栄養素です。ビタミンCは粘膜や血管、骨の健康を維持するコラーゲンの生成を助けます。加熱すればたくさんの量を食べられますが、ビタミンCは熱に弱いため、摂取量は低下してしまいます。加熱する場合はサッと蒸す程度にとどめると良いでしょう。葉は柔らかく癖のない味なので様々な料理に使われる野菜です。
|
白菜
 |
生ではシャキシャキした歯ざわりがあり煮込むと柔らかくなる。植物繊維やミネラルが豊富で、煮物、汁物、炒め物、なべ料理、漬物、糖に使われる。味は、比較的淡白であり、キャベツなどに比べると柔らかい白菜を目指して生産しています。白菜の中は黄色、オレンジになる品種を主に生産しています。 |
ブロッコリー
 |
緑色の花蕾と茎を食用とする。ビタミンB、ヒタミンC、カロテンや鉄分を豊富に含む。日本ではゆでマヨネーズなどの調味料をつけて食べることが多いが、欧米ではサラダなどで生食されることも少なくない。スープやシチューの具、炒め物、天ぷら、糖漬けにすることもある。茎の部分の外皮は、繊維質で硬く食感が悪いことがあり、その場合は、剥いてから調理するとよい。 |
ロマネスコ
 |
日本でのロマネスコという名前は、イタリア語での呼び名である(ブロッコリー・ロマネスコ、ローマのブロッコリーの意)に由来する。未成熟のつぼみと花弁を食用にする。アブラナ科の野菜の中では比較的穏やかで微かに甘い芳香を持つ。花蕾群の配列がフラワタル形状を示す特徴を持つ |
カリフラワー
 |
花頭の部分を食用にする。花蕾のさっくりとした歯ざわりが特徴。味にはわずかな苦みを感じる人もいる。葉も食用となるが青っぽさと苦みが強い。これはケール同様、原種に近いためと考えられている。カリフラワーに含まれるビタミンCの量はブロッコリーに比べ若干少ないが、加熱による損失に強く成分が失われにくいため、調理後の含有量は同程度となる。 |
大根
 |
食材としての大根はビタミンCに富み鉄分・リン・カルシウムを含む。カロリーは少なく、ジアスターゼを多く含み消化を助ける効能も有るため、ダイエット・フードとしても注目されている。葉付き大根はそのまま置くと栄養価が下がるので、葉を切り落として二等分にし、切断面を密封して立てて保存するとよい。きめの細かい、よく煮える大根を目指して生産しています。主に「あじみまる」を生産しています。 |
水菜
 |
秋に苗床に播種し、晩秋畑に定植して管理する。耐寒性が強く、旬は晩秋から冬。 独特の芳香と繊維分をもつ。ビタミンA、ビタミンC、カルシュウムが多く含まれている。 |
紅はるか
 |
柑紅はるかは開発の目的どおり、外観が優れ、しかも蒸しいもにした時の糖度が高く、とても美味しい芋です。橘類の中では耐寒性が強く、極東でも自生できる数少ない種である。また、柑橘類に多いそうか病、かいよう病への耐久があるためその高い糖度の糖質の中でも麦芽糖が占める比率が高い傾向にあると言われ、食べてみると強い甘さにもかかわらず後口はすっきりした感じの上品な甘さを感じさせてくれます。果肉の色は黄白色で、やや粉質で、加熱するとしっとりとした食感に成り、焼いた時の甘さはあの安納芋とも比較されるほどで、非常に甘く美味しい焼き芋の資質をそなえています。 |
ユズ
 |
柑橘類の中では耐寒性が強く、極東でも自生できる数少ない種である。また、柑橘類に多いそうか病、かいよう病への耐久があるため、ほとんど消毒の必要なく、他の柑橘類より手がかからないこと、無農薬栽培をしています。 |
シイタケ
 |
一般的にシイタケの原木栽培(ほだ木)では長さ1m程度に切断した広葉樹を原木として利用し、原木は秋から初冬に伐採し、過度な乾燥を避け保管し翌早春に種菌を接種する。種菌を接種した原木は、約1年森林の下で寝かせ菌糸体の蔓延を待つ。種菌の接種から16〜18ヵ月経過後にほだ木場と呼ばれる栽培場所に移し、棚にかけかけるように原木を並べて子実体の発生を待つ。子実体が発生するのは、通常18〜24ヵ月後で、3〜4年採集が可能である。品質改良が進んでおり、シイタケが発生する最適な時期はそれぞれの品種によっても異なっている。地域の気候に最も適した品種を選択し栽培しています。 |