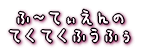
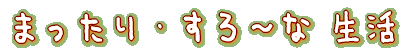 |
| 怘傋傞偙偲丂丂丂丂丂 | 丗丗 | 憪鋾揈傒仌僕儍儉嶌傝 | |||
| 傜偭偒傚偆娒恷捫偗 | |||||
| 傜偭偒傚偆娒恷捫偗Part.2 | |||||
| 攡庰 | |||||
| 攡僔儘僢僾 | |||||
| 攡僒儚乕 | |||||
| 攡姳偟 | |||||
| 彫偝側僄僐 | 丗丗 | 僄僐僶僢僌 | |||
![]()
![]()
| 丂仒仒 傜偭偒傚偆娒恷捫偗乮2007.5.26奐巒乯
仒仒 |
|||||||||
| 丂嵟嬤僗乕僷乕偱偪傜傎傜尒偐偗傞傛偆偵側偭偨揇晅偒傜偭偒傚偆丅 丂嶐擭捫偗偰旤枴偟偐偭偨偺偱丄崱擭傕挧愴偟偰傒傛偆偭!! 丂崱擔丄嬈柋僗乕僷乕偱幁帣搰嶻偺偱偐偄棻偺傜偭偒傚偆偑偁偭偨偺偱峸擖丅偪偲夎偑弌偡偓偰偄傞偺偑婥偵擖傜側偄偗偳丄傑偀傛偟偲偡傞丅廳検偼栺侾嘸偩偭偨丅 亪佹亪丂墫捫偗丂亪佹亪丂(2007.5.26)
亪佹亪丂娒恷捫偗丂亪佹亪丂(2007.6.4) 丂10擔娫墫捫偗偟偨偟偨傜偭偒傚偆傪悈偵偮偗偰墫暘傪敳偔丅 乮2帪娫偖傜偄偮偗偰偍偄偨偗偳丄杮棃偼10%偺墫悈偵捫偗偰1擔偔傜偄偐偗偰墫敳偒偡傞曽偑偄偄傒偨偄乯丅
亪佹亪丂娒恷捫偗傜偭偒傚偆怘傋偰傒偨丂亪佹亪丂(2007.6.29) 丂僇儗乕傪嶌偭偨偺偱丄傕偆怘傋傜傟傞傫偠傖側偄偺乣丠偲傜偭偒傚偆傪怘傋偰傒偨丅 丂偆傫丄偽偭偪傝捫偐偭偰偄傞偭!!丂僇儕僇儕怘姶偱偍偄偟偠傖傫乣侓 丂崱夞偺偼朓枿偱嶌偭偨娒傔偺枴偩偭偨偗偳丄偙傟偖傜偄偱傕傛偄傢乣丅偨偩丄傜偭偒傚偆偺捫偗廯偑戺偭偰偄傞偺偑庒姳婥偵側傞偗偳丅 丂嫀擭偺偙偲傪峫偊傞偲偒偭偲偡偖偵怘傋偒偭偪傖偆偩傠偆偟丄傑偩傑偩僗乕僷乕偱傜偭偒傚偆傪攧偭偰傞偐傜丄傕偆堦夞捫偗偰傒傛偆偐側偀乧丅 |
![]()
| 丂仒仒 傜偭偒傚偆娒恷捫偗Part.2乮2007.7.4奐巒乯
仒仒 |
||||||
| 丂嬈柋僗乕僷乕OK偱搰崻嶻偺傗傗彫棻傜偭偒傚偆傪埨偔攧偭偰偄偨偺偱丄攦偭偰偟傑偭偨丅廳検偼栺侾嘸庛丅 亪佹亪丂墫捫偗丂亪佹亪丂(2007.7.4)
亪佹亪丂娒恷捫偗丂亪佹亪丂(2007.7.17&7.19) 丂10擔娫墫捫偗偟偨偟偨傜偭偒傚偆傪5%掱搙偺墫悈偵偮偗偰墫暘傪敳偔丅墫偑懌傝側偐偭偨偺偋乧丅 丂1擔墫悈偵捫偗偰偍偔偮傕傝偑丄2擔偵側偭偰偟傑偭偨丅偪傚偭偲墫悈偑戺傝婥枴偵側偭偰偰傗偽偦偆側忬懺偵側偭偰偄偨丅偁偲1擔曻抲偟偰偄偨傜晠偭偰偨偐傕偟傟側偄乮娋乯丅偙偺帪婜弸偄偐傜婥傪偮偗側偄偲偄偗側偄丅斀徣乣丅
|
![]()
| 丂仒仒 攡庰乮2007.6.11奐巒乯 仒仒 |
|||||||||
| 丂惵攡1kg乮柧擔崄擾嶌暔捈攧強偵偰350墌乯丄儂儚僀僩儕僇乕1.8噂丄昘嵒摐1戃偱栺1,500墌丅 丂挬偐傜8帪娫悈偵偮偗偰偁偔敳偒偟偰偍偄偨惵攡傪偞傞偵偁偘偰姡偐偡丅 丂捾梜巬偱僿僞偺晹暘傪偒傟偄偵庢傞乮偟偭偐傝姡偄偰偄傞傎偆偑庢傝傗偡偄乯丅 丂壥幚庰梡偺時傪幭暒徚撆偟偰姡偐偟偰偍偔丅巆偭偰偟傑偭偨悈揌偼儂儚僀僩儕僇乕偱傆偒庢傞丅 丂惵攡傪壥幚庰梡偺時偵堏偟丄儂儚僀僩儕僇乕傪偦偭偲拲偓偄傟丄嵟屻偵昘嵒摐傪堦捦傒乮栺100g乯傪擖傟偰屻偼曻抲丅 丂3儢寧屻偖傜偄偐傜堸傔傞傛偆偵側傞丅 丂1擭慜偵嶌偭偨攡庰偼崱偼偐側傝弉惉偑恑傒丄噫噙怓偱崄傝傕傛偔偰杮摉偵旤枴偟偄丅偐側傝巁枴偺嫮偄攡庰偵側傞偗偳丄昁梫偱偁傟偽偍岲傒偵墳偠偰摐暘傪懌偣偽傛偄偟丅偁偨偟偼偦傫傑傑儘僢僋偱堸傓偺偑岲偒侓乮崱偼嬛庰偩偗偳乧乯
|
![]()
| 丂仒仒 攡僔儘僢僾乮2007.6.12乯 仒仒 |
|||||||
| 丂惵攡1kg丄朓枿1kg乮崱夞偼嵿惌擄偺偨傔拞崙嶻580墌乯丅 丂崱夞偼嵒摐偱偼側偔朓枿偱僩儔僀丅扙婥傪偟偨偐偭偨偺偱枾暵偱偒傞時傪媮傔傞乮3噂梡1,200墌偖傜偄乯丅 丂8帪娫悈偵偮偗偰偁偔敳偒偟丄偞傞偵偁偘偰惵攡傪姡偐偡丅捾梜巬偱僿僞偺晹暘傪偒傟偄偵庢傞丅 丂時傪幭暒徚撆偟偰姡偐偟偰偍偔丅 丂惵攡傪時偵擖傟偨屻丄朓枿傪偐偗傞丅 丂晍嬓傪掙偵晘偄偨撶偵時傪擖傟丄時偺7暘栚偖傜偄傑偱悈傪擖傟傞乮撶偺娭學偐傜6暘栚偖傜偄偩偭偨偗偳乯丅偦傟偐傜壩偵偐偗偰30暘偖傜偄暒摣偝偣傞丅 丂乮偪傚偭偲攡偑廮傜偐偔側傝偡偓偨柾條丅僔儚僔儚偵側偭偰傞傕偺傕偁傞偟丅偪傖傫偲條巕傪傒側偑傜攡偑傆偭偔傜偟偨偖傜偄偱壩傪巭傔側偄偲僟儊偩側丅15暘偖傜偄偱傕OK偐傕偟傟側偄乯丅 丂壩傪巭傔偰偡偖偵奧傪暵傔扙婥丅偙偺傑傑曻抲偡傞丅 丂嶐擭偼嵒摐偱嶌偭偨偺偩偑丄崱夞偼朓枿丅偟偽傜偔偼偙偺傑傑曻抲偟偰偍偙偆丅偳傫側枴偵側傞偺偐妝偟傒侓
|
![]()
| 丂仒仒 攡僒儚乕乮2007.6.14奐巒乯 仒仒 |
|||||||
| 丂嬤偔偺彫攧揦偲傃摽偱媑栰嶻惵攡傪僎僢僩丅100g20墌偲偄偆埨偝側偑傜攡偼偲偰傕偒傟偄丅偙傟偼偍攦偄摼偩丅 丂偝偭偦偔悈偵偮偗偰偁偔敳偒丅 丂500g偼攡僒儚乕梡偵偡傞乮500g偼攡忀桘梡乯丅 丂徚撆偟偨儕僇乕時偵偁偔敳偒偟偨惵攡傪擖傟偰丄傂偨傂偨偵側傞偖傜偄暷恷傪擖傟偰姰惉乮娙扨偡偓傞乯丅 丂攡僒儚乕偼攡偑堔偊偰偔傞1乣2儢寧偖傜偄偱巊偊傞傛偆偵側傞傜偟偄丅偟偽傜偔條巕傪尒傛偆丅 丂攡500g偠傖偁傑傝偵彮側偐偭偨偺偱丄6/18偵惵攡傪1kg捛壛偟丄偦傟偵崌傢偣偰暷恷傕捛壛丅偮偄偱偵昘嵒摐傕300g掱搙壛偊偰傒偨丅 丂偝偰丄偳傫側攡僒儚乕偑偱偒傞偐側丅
|
![]()
| 丂仒仒 攡姳偟乮2007.6.17奐巒乯 仒仒 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 丂偲傃摽偱峸擖偟偨媑栰嶻姰弉攡1kg乮200墌乯傪巊偭偰攡姳嶌傝奐巒丅崱擭偺媑栰嶻攡偼偳偆偟偰偙傫側偵埨偄偺偩傠偆?? 丂嫀擭偼弶傔偰攡姳偟傪嶌偭偰傒偨丅墫暘偼偪傚傃偭偲尭墫婥枴偱15亾偱帋偟偰傒偨丅僇價傕惗偊側偐偭偨偟丄崱偱傕忢壏曐懚偟偰偄傞丅 丂崱擭偼丄傕偆彮偟尭墫偟偰栚巜偡偼10亾掱搙偺攡丅攡偺2抜捫偗偱僇價偵棫偪岦偐偆偧乣!! 亪佹亪丂墫捫偗戞1抜丂亪佹亪丂(2007.6.17) 丂姰弉攡傪愻偭偰2帪娫悈偵偮偗偰偁偔敳偒丅 丂偦傟偐傜偞傞偵忋偘偰姡偐偡丅 丂姡偄偰偐傜捾梜巬偱傊偨傪庢傝彍偔丅 丂幭暒徚撆偟偨價儞偵攡傪擖傟丄偦偺忋偐傜180g乮18亾乯偺墫傪壛偊傞丅 丂攡偺忋偵價僯乕儖戃傪2廳偵偟偰抲偒丄廳愇戙傢傝偵悈傪拲偄偱姰惉丅 丂偝偰丄偳傟偖傜偄偱攡恷偑忋偑傞偐側?? 丂6/22攡姳偺攡恷偺忋偑傝偑僀儅僀僠埆偄偺偱丄廳愇偺悈傪庢傝彍偄偨屻丄時傪梙偡偭偨傝揮偑偟偨傝偟偰攡傪摦偐偟偰傒傞丅 丂偦傟偐傜傑偨悈偺廳愇傪嵹偣偨傜丄栭偵偼攡偺敿暘偖傜偄攡恷偑忋偑偭偰偒偨!! 丂側偺偱丄價僯乕儖偺廳愇偺悈偺検傪彮偟尭傜偟偰傒偨丅 丂6/23偵攡恷偑傗偭偲忋偑傝偒偭偨丅傑偩掙偵偼梟偗偒傜側偄墫偑巆偭偰偄傞偗偳丅堦埨怱!! 亪佹亪丂墫捫偗戞2抜丂亪佹亪丂(2007.6.25) 丂偲傃摽偵偰100g30墌偺姰弉撿崅攡L傪1kg峸擖丅 丂傛偄崄傝傪曻偮傎偳偺姰弉攡偩偭偨偺偱丄悈愻偄傪偟偰姡偐偟丄僿僞傪庢傝彍偄偨偺傒丅 丂攡恷偺偁偑偭偨戞1抜偺墫捫攡傪庢傝弌偡丅 丂時偵僿僞偲庢傝彍偄偨撿崅攡傪擖傟丄15g偺墫傪忋偐傜僷儔僷儔偲怳傝偐偗傞丅 丂偦偺忋偐傜庢傝弌偟偰偍偄偨攡傪攡恷偛偲搳擖丅 丂寉傔偺價僯乕儖廳愇傪偡傞丅 丂怴偟偄攡偺1/3偖傜偄傑偱攡恷偵怹偐偭偨忬懺偵側偭偨丅偝偰丄偳傟偖傜偄偺帪娫偱攡恷偑忋偑傞偺偐側?? 丂尭墫攡偼惉岟偡傞偐側?? 丂攡恷偼堦廡娫屻偖傜偄偵姰慡偵忋偑偭偨丅屻偼丄愒巼慼搳擖傪懸偮偺傒丅
亪佹亪丂巼慼捫偗丂亪佹亪丂(2007.7.11) 丂7/11偵攡姳梡偺巼慼捫偗嶌嬈傪峴偆丅 丂嬤揝昐壿揦偱攦偭偰偒偨愒巼慼偼揇偑偮偄偰側偔偰偒傟偄偩偗偳丄梩偭傁偑彫偝偄偺偑擄揰偩丅 丂惗偺帪偼寢峔側検偩偭偨偺偵丄嘊偑廔傢偭偨帪揰偱傕偺偡偛偔彫偝側夠偵曄恎丅偙傫側傕傫偩偭偨偭偗偐側偀乧丅 丂嵽椏丗愒巼慼1戃丄墫50g 丂嘆巼慼偺梩傪宻偐傜奜偟偰悈偱愻偆丅 丂嘇偁傞掱搙姡偄偨傜丄愒巼慼偵墫傪怳偭偰5乣10暘曻抲偟偰偟傫側傝偝偣傞丅 丂嘊巼慼偺梩傪嫮偔墴偟側偑傜潌傓丅崟偄廯偑弌偰偒偨傜偦傟傪幪偰偰巼慼傪峣傞丅 丂嘋巼慼傪寉偔傎偖偟偰墫傪怳傝丄潌傒丄峣偭偰崟偄奃廯傪幪偰傞丅偙傟傪2乣3夞孞傝曉偡丅 丂丂仸悈偱愻傢側偄偙偲!! 丂嘍攡恷傪愒巼慼偵戝3攖掱搙偐偗丄傛偔潌傫偱巼慼傪峣傝丄廯傪幪偰傞丅 丂嘐儃乕儖偵攡恷偲愒巼慼傪擖傟偰丄梩傪傎偖偡乮嬥懏惢偺偍偨傑偼巊傢側偄偙偲乯 丂嘑攡偺梕婍偺忋偐傜愒巼慼傪攡恷傪擖傟丄寉偔廳愇傪偟偰搚梡姳偟傑偱曐懚丅 丂梻擔偼偐側傝愒偄怓偵愼傑偭偰偒偰偄偨丅 丂3擔屻偵偼慡懱偑恀偭愒偭偐偩傢乣侓偄偄姶偠丅
亪佹亪丂搚梡姳偟丂亪佹亪丂(2007.7.31) 丂崱擭偺攡塉柧偗偼抶偐偭偨丅7/31偵傗偭偲偙偝搚梡姳偟傪奐巒丅 丂攡傪偞傞偵庢傝弌偟丄挬偐傜擔岝梺丅 丂悢帪娫屻偵傂偭偔傝曉偟偰偁偘傞丅偁傑傝挿偄帪娫曻抲偟偨傑傑偩偲丄攡偑偞傞偵偔偭偮偄偰偟傑偆乧丅 丂攡恷偼時偵擖傟偨傑傑丄摨偠偔擔岝梺丅 丂崱擭偼栭偑椓偟偐偭偨偺偱丄攡偼偦偺傑傑壆崻偺偁傞偲偙傠偵弌偟偰偍偄偨丅 丂梻擔傕挬偐傜擔岝梺丅 丂偟偐偟丄偦偺梻擔偼揤婥偑曵傟傞偲偄偆偙偲偱丄崱擭偼2擔娫偩偗姳偡嶌嬈傪偟偨丅 亪佹亪丂枴尒丂亪佹亪 丂偍枴偼乧!! 丂偍偄偟偄乣丅拞傑偱偟偭偲傝偟偰偰丄偡偭傁偄偭丅偱傕嫀擭偺偵斾傋傞偲巁枴偼梷偊傜傟偰偄傞偲巚偆丅 |
![]()
| 丂仒仒 僄僐僶僢僌 仒仒 |
|||||||
| 丂嵟嬤丄僄僐僶僢僌偲偄偆尵梩傪偁偪偙偪偱傛偔帹偵偡傞丅儗僕偱價僯乕儖戃傪傕傜偆傫偠傖側偔偰丄帩嶲偟偨戃傪巊梡偡傞偙偲偱僑儈傪尭傜偦偆偲偄偆傕偺丅 丂僗乕僷乕偵傛偭偰偼丄儗僕戃晄梫僇乕僪偼敪峴偟偰偄傞偲偙傠傕偁傞丅椺偊偽丄僄僐僶僢僌帩嶲偺搙偵僇乕僪偵1偮僗僞儞僾傪墴偟偰偔傟丄20夞偱100墌偺偍攦偄暔寯偑傕傜偊偨傝偡傞偺偱丄偦傟偱彫偝側岾偣傪姶偠偨傝偡傞侓丂偁傞偄偼丄僄僐僶僢僌帩嶲偑婯掕抣偱偁傝丄儗僕戃傪梫媮偡傞偲5墌側傝10墌側傝偺儗僕戃戙傪暐偆僗乕僷乕傕偁傞傛偆偩丅 丂崱丄偁偨偟偑垽梡偟偰偄傞僄僐僶僢僌偼俀偮偁傞丅
丂偦傟偐傜偼丄攦偄暔偺検偵崌傢偣偰2偮偺僶僢僌傪巊偄暘偗偟偰偄傞丅帪偵偼丄椉曽偲傕偁偨偟偺榬偵梙傜傟偰偄傞偙偲傕偁傞丅 丂傎傫偺偝偝偄側僄僐偩偗偳丄偙傟偐傜傕懕偗偰峴偙偆偲巚偆丅 |