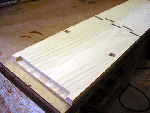 |
デザイン図に基づいて木取り、木作り アシュ材を使って、天板と側板は5枚組み接ぎ、底板は包み打ち付け接ぎ、抽斗受け桟は二方胴付き用の穴加工をしてあります。 側板-天板-側板と連続した木取りで木目の柄が回り込むようになります。 |
 |
仮組 仮組状態で細部の寸法、目違い等を確認し、修正を加えます。 抽斗受け桟も木作りをして全体構成の確認中。 天板と側板の5枚組接ぎ部はツノが出ている状態(最終接着後に切り落とす)です。 |
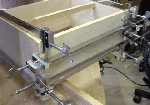 |
本体部組み立て接着 組み立て接着中。 仮組での確認、修正後接着剤を用いて組み上げます。底板部は包み打ち付けで端がねは直ぐ外せますが、5枚組接ぎ部はボンドが完全に接着するまで半日クランプ状態で待つことになります。 (接着剤のボンドのはみ出しは大敵!塗装不良につながるので念入りに拭き取ります) |
| 前面飾り桟 このデザインのポイントとなる十字の飾りは、赤色材(ペンシルシダー)を使用し相欠き接ぎで組み立てます。 |
|
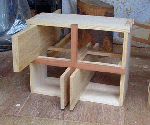 |
本体組み上げ 抽斗桟と飾り桟を取り付けて本体組み上げは完成です。 抽斗用部材を抽斗高さに合わせて木作り、寸法を合わせて行きます。 この後、本体の組接ぎのツノを切り取ります。 |
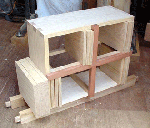 |
抽斗部材達 抽斗の材料となる部材を各寸法に合わせて作り上げます。 抽斗各側板と向こう板は抽斗毎に寸法を合わせて加工します。 本体左にある部材は前板です。 |
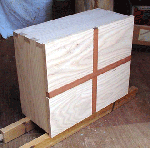 |
最終イメージ 本体に前板を載せて組み上げ前の最終イメージを確認中。 救急箱として解りやすいモチーフをポイントに構成しました。 やっと形が見えてきました。まだまだこれからが大変です! |
 |
抽斗つくり(仮組で収めた状態) 抽斗の仕様に合わせて加工し組み立てます 側板は胴付き仕様、包み打ち付け接ぎの組み合わせで抽斗それぞれに 加工位置サイズが異なるので、慎重に加工を行います。 |
 |
抽斗ダボ埋め 釘打ちで取り付けた部分を、丸加工したダボで埋めます この後、面にカットして平滑にします。 |
 |
本体5枚矧ぎ部分の仕上げ 4コーナーを丸く面取り加工をします 薬箱として、優しいイメージを強調するために本体は4コーナー丸く加工しました。 |
 |
仕上げ加工-1 抽斗部を最終本体に合わせて、動きを確認しながら微調整してスムースな動きをするようにします。 抽斗部前板も本体に合わせて、丸みを持たせています。 |
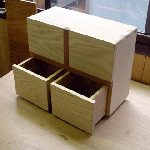 |
仕上げ加工-2 本体及び抽斗前板を仕上げ鉋で仕上げた後、最終400番のサンドペーパーで 表面を整えました。 本体との勘合具合、抽斗との組み合わせ形状部等、細部にわたり調整 加工を終えました。下部の引き出しを出したところです。 左右の引き出しの形状が異なるのが解ります。 |
 |
仕上げ完成 本体部の仕上げが全て完了しました。 台輪(だいわ)は本体がアール形状のため、この後制作します、裏板はシナベニヤを採寸加工して、塗装が終了した時点で取り付けます。 塗装は人に優しい「リボスオイル」仕上げの予定です。 |
