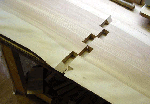 |
デザイン図に基づいて木取り、木作り 今回のデザインコンセプトは、チェリーの一枚板をそのまま生かした文机の制作。幅広で長さが天板・側板と廻すのに最適なサイズを入手出来たことを生かしたものです。サイズを決定した後、天板と側板を7枚組み継の留(45度で組合せる)タイプで加工しました。両耳を生かしたために基準面が平面しかなく、加工精度を上げるのは苦労します。 |
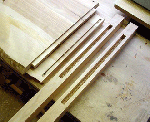 |
畳摺り桟加工 本体の仮組状態で細部の寸法、目違い等を確認し、修正を加えます。 今回は先に、畳摺り桟を側板に合わせて加工しました。角鑿盤で畳摺り桟にホゾ穴をあけそれに合わせて、側板にホゾ加工をしました(基準面がないためトリマーでホゾの加工を慎重に)。 |
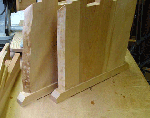 |
畳摺り桟組み立て接着 仮組での確認後、面取り加工、畳摺り部のざぐり加工をした後、接着しました。 |
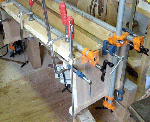 |
組立て接着 幕板等の加工・仮組での確認後、いよいよ組立て接着です。 クランプ・端金を総動員してカネテ(直角)を確認しながら、締め付けていきます。木の厚さと机寸法の関係もあり強力なポニークランプは有用でした。 |
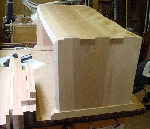 |
本体組立て完成 一晩の接着状態の後、本体が組みあがりました。 次は抽斗部の加工に入ります。あらかじめ木作りをしておいた抽斗用材料(本体左にある材料)の墨付けに入ります。本体の組みあがり寸法を確認しながら抽斗の最終寸法を決定し加工に入ります。 |
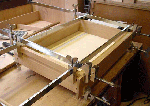 |
抽斗部仮組 前板と側板部は包み打ち付け継、抽斗は吊桟方式のため側面にレール溝加工をしました。仮組状態で目違いなどを確認した後、修正加工を加えて左右完成させました。 |
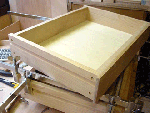 |
抽斗完成 端金で接着中の抽斗と、完成した抽斗。 向こう板は前板より0.5mm短くして、抽斗の出し入れをスムースにさせます。 側板はそれぞれ釘で打ち付け接着ですので、端金は直ぐに外すことが出来ますので時間が節約できます。底板はシナベニヤをはめ込んであります。 |
 |
抽斗調整 抽斗用の吊桟を取り付けた後、接着完成した抽斗を収まるように調整していきます。天板が扇形状に開いていることと、基準面がないため引き出しの取り付けた状態を念入りに確認しながら微調整して、スムースに収納出来るようにします。 |
 |
抽斗ダボ埋め 釘打ちで取り付けた部分を、同じ材料で丸加工したダボで埋めます この後、面にカットして平滑にします。 抽斗の下部はトリマーでC面カットして抽斗をより薄く見せると共に流れるラインを強調させました。 |
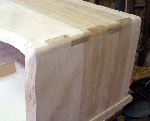 |
本体7枚矧ぎ部分の仕上げ 両コーナーを丸く面取り加工をしました。 |
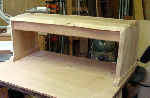 |
仕上げ完成-1 本体部仕上げ状態。#120、最終#400の2段階でサンドペーパーにて仕上げました。抽斗は前で合わせ面が隣り合うので、面一になるように微調整して仕上げました。 |
 |
仕上げ完成-2 抽斗を片側外した状態です。 |
 |
仕上げ完成-3 抽斗の吊桟です。ストッパーの役割もしています。 抽斗の落下防止のためのストッパーは塗装後に取り付けます。 今回は初めての挑戦として塗装は「柿渋」で着色して仕上げる予定です。 柿渋は自然素材で、人に優しい塗料とされています。 |
