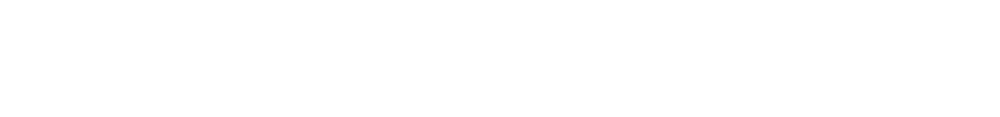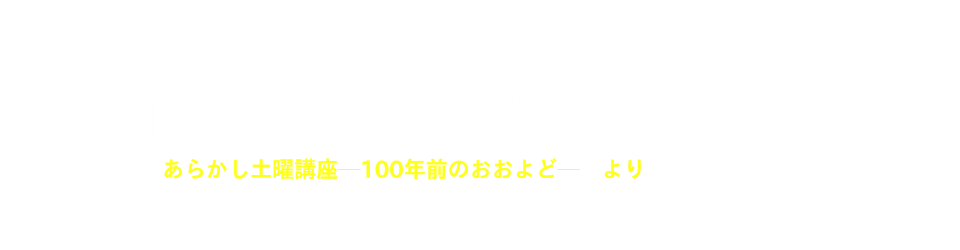私たちの暮らす大淀町は明治22(1889)年4月に大淀村として発足をしました。当初は江戸時代以来の交通手段しかありませんでしたが、鉄道の発達により、木材の集散地として、又千本桜の吉野への門戸として発展をしました。
大正10(1921)年には大淀町の発足があり、当時の大阪朝日新聞には大きく取り上げられました。
「町」になった大淀 僻地にも似ず會社の数が非常に多い
「大淀の祝賀 三日間休業」
大淀の祝賀式 明正校庭で報告祭 全町の盛なる景気
と紹介されています。
大淀村合併の際の「合併村願」には
「古史上に称スル大川ノ澱ノ名称ヲ保存センガ為メ茲ニ村名ヲ大淀村ト撰定ス」と表されています。
詳しい資料は「大淀村風俗誌」をご覧下さい。入手は困難ですが国立国会図書館の「近代デジタルライブラリー」(Kindai.ndl.go.jp)で無料公開されています。
閲覧、印刷、ダウンロードも自由に出来ます。
吉野軽便鉄道



わが町の鉄道 わが町を走れ
吉野山地に鉄道を敷設する第一歩は土倉庄三郎さんの木材を中心とする物資輸送の計画に端を発します。その「吉野鉄道株式会社」は明治32年に政府によって認可されるのですが資金の調達が思うに任せず会社解散に至ったのです。明治41年になって大淀村の森栄蔵さんによる「馬車鉄道」の計画に至るのですが、43年に軽便鉄道法の制定に便乗して軽便鉄道として請願をしたのですが、これまた資金調達思うに任せず断念となりました。この状況を見ていた吉野郡長の谷原岸松さんの鉄道が郡の発展に結び付くとの決意を固め郡の有力者である阪本仙次さんを口説くと共に鉄道建設の必要性を説き明治44年6月12日の工事認可に繋がっていきます。
当初の吉野軽便鉄道は吉野口、下市口、吉野(現在の六田)の3駅から出発しました。しかし吉野軽便鉄道の持つ駅は下市口と吉野だけで、吉野口駅は国鉄の駅を利用させて頂いておりました。大正2年5月に吉野鉄道と名称を改め線路の延長と電化へと進んでいきます。大正12年12月5日に吉野口~橿原神宮前間が開通、昭和3年3月25日に六田~吉野間が営業開始となりました。
大阪阿部野橋から吉野へは直行便があるのですが、なぜ京都からは直行便がないのでしょうか。この疑問は軌条幅を見ると解決をします。機関車の発明者であるスチーブンソンが主張した4フィート8インチ半(1.435m)のゲージを標準軌としていますが、京都線は標準軌を使い、阿部野橋から吉野のそれは標準軌より小さい3フィート6インチ(1.067m)の狭軌である為運行が出来ません。因みに新幹線や大手の私鉄の一部が標準軌を使用していますが、旧国鉄(JR)の在来線は狭軌を使用しています。シベリア鉄道(1.524m)やスペインの鉄道(1.668m)は標準軌よりも広いので広軌と呼ばれています。
参考資料並びに文化講座による
成瀬 匡章 さん(森と水の源流館)
浦西 勉 さん(龍谷大学教授)
松藤 貞人 さん(奈良県の軽便鉄道著者)
松田 度 さん(大淀町教育委員会)
奈良県の軽便鉄道 増補版 松藤定人 著
大淀村風俗誌─竹山清文 編─
あらかし土曜講座─100年前のおおよど─
大淀町教育委員会(視聴覚教室にて)
追記 奈良周辺での軽便鉄道
①長谷鉄道 ②吉野鉄道 ③天理軽便鉄道 ④大和鉄道
⑤生駒鋼索鉄道 以上が奈良県内
周辺
①大阪鉄道 ②大阪高野鉄道 ③南海鉄道 ④加太軽便鉄道
⑤山東軽便鉄道 ⑥野上軽便鉄道 ⑦有田鉄道 ⑧新宮鉄道
以上が大阪
全国では135ヵ所に軽便鉄道がありました。
記述:田中 伸次