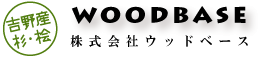吉野林業の歴史 ~植林のはじまりから現代に至るまで~
かつて吉野山から大峯山山上ケ岳にかけての一帯は古代より世に広く知られた聖域でした。山岳宗教の聖地ではありましたが都からも遠く、山深い土地であったことから木材を伐り出すことは非常に困難なことでした。
中世になり密教を中心とする修験道信仰がさかんになると、この地方でも白鳳年間に蔵王堂(吉野町)などの巨大寺院が建てられ、天然林が伐られはじめます。
機内都市の発達も吉野地方の材木需要を増やしました。
需要に刺激された百姓は所有する山畑に植林し、農業のかたわら林業を営むようになったのが人工造林のはじめといわれています。
中世末期から近代にかけては吉野林業の発展~確立期にあたります。
安土桃山時時代にはこの地方は豊臣秀吉が領有し、大阪城や伏見城などのお城づくりに利用されました。江戸時代には 日本中に都市が出現し木材需要がさらに増えたこと、吉野川の上流から流筏が可能になったことなどが手伝い、吉野林業は発展をつづけ優れた技術を確立させてゆきます。

とりわけ、酒樽の板材料、樽丸材に吉野杉が最適とされたことによって吉野杉の名声が広まりました。これに目をつけた村外の資本家が有利な投資先として吉野林業地帯に進出してきます。土地と立木の所有権が分離し所有と経営をも分離する「借地林業」という吉野独特の制度を生み出してゆきました。
また、植林され始めたころは20年という短い伐期が、樽丸生産がはじまった頃には80年~100年へと伐期が延長され、密植・多間伐・長伐期という施業体系が確立したのです。
こうして長い歴史の中で発展した吉野林業の基盤があり、近代では吉野杉は磨き丸太や高級建材として広く知れ渡りしました。
吉野杉の品種
 吉野杉はもともとこの地方に自生していたものに、奈良県の三輪山や春日山、鹿児島県の屋久島などから優良種を移植し、品種を改良しながら現在のハイクオリティブランドといわれる銘木に育てあげられました。
吉野杉はもともとこの地方に自生していたものに、奈良県の三輪山や春日山、鹿児島県の屋久島などから優良種を移植し、品種を改良しながら現在のハイクオリティブランドといわれる銘木に育てあげられました。 -
吉野林業年表
1500年頃 ・ 奈良県川上村で人工造林がはじまる
・ 大阪城・伏見城の建築用材として吉野材が使われる~筏流し時代~ ・ 大阪で木材問屋が成立し、木材市場が開かれる 1670年頃 ・ 銭丸太の製造がはじまる 1700年頃 ・ 借地林業・山守制度がはじまる 1720年頃 ・ 樽丸製造がはじまる
・ この頃 密植、多間伐、長伐期の施業体系が確立した1865年頃 ・ 木材需要が増し、材価が高騰する
・ 村外者の山林所有者が増える1915年頃 ・ 東吉野村で人工絞り丸太の製造がはじまる
・ この頃ほぼ現在の大山林所有形態になる
・ 索道による集材がはじまる1936年頃 ・ 大和上市駅まで鉄道が延長される
・ この頃 樽丸生産が最盛期をむかえる1937年 ・ 吉野貯木場の開設 1940年頃 ・ 樽丸から柱角に生産目標が移行する
・ この頃 磨き丸太生産が最盛期をむかえる1951年頃 ・ 筏流送が終わり、トラック輸送となる
・ 山守の素材業への進出が増える1954年頃 ・ 桧箸の製造がはじまる 1970年代 ・ ヘリコプター集材がはじまる
・ この頃には吉野材ブランドとして確立をむかえる1980年 ・ 桧、杉 集成材単板(集成材の化粧用板の原板)が製品化する 2006年 ・ 株式会社ウッドベース 設立