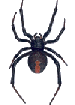ゴケグモ属の概要-分類-
○セアカゴケグモ Latrodectus hasseltii Thorell,1870 (英名:Red back,Red Back Spider )
《分 類》 ヒメグモ科 Theridiidae ゴケグモ属 Latrodectus
ゴケグモ属は色彩や斑紋に変異が多く、そのうちの数種類は世界中に広く分布しているため、分類はまだ確立されていない。かつては30種以上が記録されていたが、その後整理されて、一旦6種程度にまとめられた(Levi,1959)。現在では、その後の記載種も含めて約30種類が認められている。ここでは、概ね Platnick (1993)に従い、西川・金沢(1996)により補充した。ゴケグモ属の最も簡単な形態的な区別点は、腹部腹面の斑紋が赤色ないし薄色の四角形~砂時計形~双三角形であることと、糸器の間突起が大きいことである。
《分 布》
オーストラリア、ニュージーランド、マクロネシア、ポリネシア、スンダ列島、インド、ビルマ、中国海南島、台湾などが知られている。原産地はどこかよく分かっていないが、東南アジアには船の貨物などについて広がったと考えられている。日本では、大阪府と三重県及び和歌山県で見つかっており、斑紋パターンがオーストラリアのものと似ており、同じ集団に起因すると考えられる。かって、石垣島(1953年)や西表島(1955年)などの南西諸島から報告されたものは別種であることが分かっている。
《特 徴》
体長15㎜ぐらいで、脚を広げると30㎜程度。セアカゴケグモのメスは、黒色で腹部背面に目立つオレンジ色~赤色の縦の縞があり、腹部下面に「砂時計」の形をした薄赤色の斑紋がある。体色は黒色で成熟すると茶色がかり、縦縞の色も薄くなる。大さなえんどう豆形をしており、ほっそりとした脚を持つ。産卵直前には、腹部は膨らんで直径が約10㎜にもなり、縞模様の色は褪せる傾向がある。産卵後は、腹部の大きさや色彩パターンも元に戻ってはっきりとする。オスの体長は、3~5㎜くらい。頭胸部や脚は褐色で、腹部背面は灰白色で中央に縁取りのある白い斑紋があり(メスの赤い斑紋にあたる)、その両側に黒紋が2列に並ぶ(時に後半でつながって黒条になることもある)。成熟したオスは、腹部が細く頭部の触肢が生殖器官として発達し、丸く膨らんでいて区別できる。幼クモは、オスと見分けにくく、成長するにつれて、メスは白いスジがなくなり、背中の赤斑がはっきりしてくる
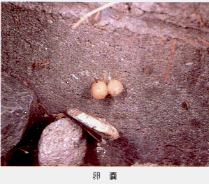
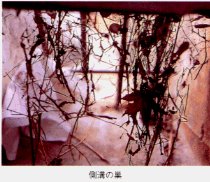
○クロゴケグモ Latrodectus mactans (Fabricius,1775) (Black widow)
北アメリカ南部に分布し、家屋周辺に普通に見られる。色彩や斑紋には変異が多い。西メキシコ産では腹部色彩紋様はストライプが多く明るい色調を持つ。しかし、同一卵のうから発生したクモでも、その紋様はバラエティに富んでいる。成熟したメスは、腹部腹面の赤斑以外は漆黒色、脚も全部黒色である。
○ハイイロゴケグモ L. geometricus C.L.Koch,1841(Brownwidow)
世界中の亜熱帯地域に広く分布する。灰褐色で腹部側面にヒョウ紋があるか、黒色で腹部背面に白い縁取りのある赤い斑紋が並ぶ。黒色型は、成熟すると背面が黒褐色になる。若クモはセアカゴケグモと区別しにくいが、卵のうは房状の綿毛のイボイボがあって容易に区別できる。フロリダにも住み着いており、建物の周辺に生息する。刺咬性は弱く、刺咬されたときの毒液の注入量は少ない。成熟メスでも脚は間接部のみ暗色。低温にも強く、メス1頭当たりの総産卵数は5000個にもなるといわれている。東京都(品川区)、神奈川県(横浜市)、愛知県(名古屋)、大阪府(大阪市)、福岡県(北九州市)、沖縄県(那覇市・浦添市)の港湾部で見つかっている。沖縄のものと横浜・大阪のものは、斑紋や大きさ、生育状態が異なり、別集団と推定される。大阪産の成熟したメスは大形で最大4個の卵のうしか持っていなかったが、横浜産は10~12個と多く、1年以上繁殖経過していると考えられる。沖縄産の港湾部のものは卵のうが1~2個でほとんどが未成熟個体であったが、繁殖集団の存在があると考えられる。港湾部と物資移動先の農村部のあちこちで見つかっている。
《外見の特徴》
イ) 変異が大きく、通常は黒色、茶色又は灰色である。
ロ) 成体の体長は、メスで12㎜、オスで3㎜。
ハ) 腹部背面の斑紋は灰色~黒色、斑紋は複雑で変異がある。
ニ) 腹部の腹面に砂時計型の赤色紋が目立つ。


○アカゴケグモ L. bishopi Kaston,1938 (Redwidow)
脚は赤色。卵のうは小さく白色である。フロリダ中南部に分布している。砂地の松の疎林の palmetto(ヤシ科)についている。
○キタゴケグモ L. variolus Walckenaer,1837(Northern widow)
腹部腹面の砂時計型の赤色斑は鮮やかだが上下に分離している。卵のうは茶色である。フロリダ北部からカナダ南部まで見つかっており、ブリティッシュ・コロンビアには普通に生息が見られる。樹の根元、切り株、石壁などについている。
○L. hesperus Chamberlin & Lvie,1935 北アメリカ・イスラエル
○ジュウサンボシゴケグモ L. tredecimguttatus(Rossi,1790) 地中海北側に分布。赤斑は列状に並ぶ。
○L. antheratus (Badcock,1932) パラグアイ・アルゼンチン
○L. curacaviensis (Muller,1976) 西インド諸島小アンチル列島・南米
○L. diaguita Carcavallo,1960 アルゼンチン
○L. apicalis Butler,1877 ガラパゴス諸島
○L. dahli Levi,1959 ソコトラ島・イスラエル~ソ連
○L. pallidus O.P.-Cambridge,1872 リビア~ソ連
○L. erythromelas Schmidt & Klass,1991 スリランカ
○L. kapito atritus Urquhart,1889 ニュージーランド
○L. rhodesiensis Mackay,1972 アフリカ東南部
○L. corallinus Abalos,1980 アルゼンチン
○L. mirabilis (Holmberg, 1876) アルゼンチン・南パタゴニア
○L. quartus Abalos,1980 アルゼンチン
○L. veriegatus Nicolet, 1849 チリー・アルゼンチン
○ヤエヤマゴケグモ L. sp