公務員時代記録
 |
公務員時代(環境衛生監視員)36年間の記録 | 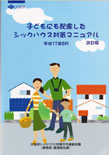 |
||
| 大阪府への採用 | 最初の移動 | 本庁への移動 | ||
| 浄化槽行政担当 | 二つの出会い | 花博開催保健所 | ||
| 環境衛生第一係 | 係長拝命 | 生活衛生室へ | ||
| 企画課長補佐 | 東大阪市へ | 最後の勤務地 | ||
| 華やかな公務員時代・・今は亡き公務員時代 | ||||
〜No4 浄化槽行政担当へ〜
7 ビル管理から望んだ浄化槽行政担当へ
ビル管理行政の主担は5年間続き、その2年前頃から浄化槽を担当したいと係長や主査に直訴していた。
本庁5年目の春、角倉係長が主幹に昇格し転出し、環境衛生第二係長は植村氏に代わり、保健所から植村氏と同年齢の朝比氏が異動で環境衛生第二係に配属された。
植松、朝田両氏は強面で、とりわけ浄化槽業界との対等な立場を堅持するに向いていると揶揄されたが、係在籍期間の最も長かった私の願いが受け入れられ、浄化槽業務を任されることとなった。
浄化槽の関係団体は、し尿のくみ取り業者で組織する協同組合が過去から存在感が強く、後発の浄化槽の製造・施工・管理などの業界が設立した社団法人は、浄化槽の急速な普及を背景に発言力を増していた。その協会の会長職には、業界の要望を受け、発足初期から社団を認可した部局の部長級OB職員が就任していた。
当時の浄化槽は、単独処理し尿浄化槽が最盛期で、下水道が引かれるまでの一時的なトイレ排水の浄化装置として位置づけられていた。この単独浄化槽はミニ住宅開発と水洗化のニーズの波に乗り、ピーク時には府下で年間に約1万基が設置され、保健所では、竣工時の検査や設置以後の悪臭、水路汚染などの苦情に追われた。
浄化槽による悪臭の発生や河川汚染は全国的にも問題となり、昭和53年には、廃棄物処理法が改正され、浄化槽の設置者に、年一回、知事の指定する機関の検査を受けることが義務づけられた。
浄化槽法定検査制度の発足を担当した田邊氏は、浄化槽協会を検査機関として指定し、検査制度を軌道に乗せるため、毎夜時間外に協会に詰め、採用新しい検査員の指導や検査体制の整備に献身的な努力をした。
田邊氏の後、浄化槽業務を引き継いだ植村氏は、国が主導し設置された全国団体の職員とも親密で、後に環境省に出向しそのまま国の職員となった兵庫県庁の由田氏と並び、都道府県の浄化槽担当者会議等で発言力を持つ一目置かれた存在であった。
その後を継いだ私は、大阪府協会の内部に入り込み、協会役員と職員との距離を縮め、業界との意思疎通を図ることに専念した。当時の浄化槽を取り巻く環境は激動の時代で、業界にも行政にも大きな課題が山積し、初代会長と製造、施工、管理などの各業種から選出された副会長は、再三、業界からの強い要望を携えて府を訪れた。
特に、新たに制定された浄化槽法により新設された保守点検業者及び施工業者の知事登録は、業界要望を汲んで協会を申請窓口としたため、協会に属さない会員外の業者をいかに扱うかが大きな論点で、折衝は白熱し長期化した。
さらに、浄化槽法の制定で新たに発足した、浄化槽竣工後6ヶ月以内の検査実施に向け、新設浄化槽の全数検査を実現する仕組みをいかに作るか最大の懸案で、そのためには施工業者の全面的な協力を得ることが最重要課題であった。
時、丁度、協会が創立15周年を迎え、記念事業準備委員会に記念誌を作る作業部会に、行政から建築指導課の盛山主幹とともに編集委員として参加し、発行責任者であった施工部門代表の副会長に親密な協力を続けた。
そのかいもあって、法律7条の新設浄化槽検査は全国的にも例のない施工業者が検査手数料を徴収する前納制のシステムを作り上げ、全数検査実施のスタートが切れた。
この新たな法定検査を実施するため、検査員の確保は急務で、今も協会に在職している第二世代のほとんどの検査員の採用面接に立ち会い、その後も親しくしている。
浄化槽新設時の7条検査は全数検査が実現できたが、法11条に基づく年一回の法定検査は罰則もなく、受検の申し込み待ちでは検査数の確保が見込めないことから、市町村が設置する浄化槽に的を絞り、協会の藤田課長、大重氏などと受検啓発に市町村を訪問した。
公共施設は徐々に受検依頼が増加し制度が浸透したが、民間施設は受検啓発の有効な手段を見いだせないまま、今だ、大阪府下の受検率は1割にも満たない状況にある。
協会では、初代大塚会長を始め、山口事務局長と藤田課長、検査部門に大重、齊藤が行政との窓口になり、理事会の開催や法定検査などの打ち合わせなどで毎日のように事務所に通った。団体との付き合いもまださほど厳しくない時期で、大塚会長、山口局長や検査員とは、時間外、度々酒席を共にした。
一方、平成の初期まで毎月開催された浄化槽協会理事会には、建築指導課と環境衛生課の参事が理事として出席し、業界と行政との毎回の激しいやりとりに、矢面に立つ参事を担当者と協会事務局長がフォローする会議の図式が定着していた。
この時の建築指導課の担当者は、盛山主幹兼係長と山根主査で、多くの苦労を共有した盛山主幹は、50歳代前半の早くに府を退職し建築事務所の共同オーナーとなり、山根主査は課長級で定年退職後、建築確認指定検査機関に勤めた。
環境衛生第二係在籍の後半に席を隣にした朝比氏は、植村氏の後の環境衛生第二係長に就き、主幹に昇格後は保健所の衛生課長を歴任し退職後、数年協会事務局長の職を勤めた。ビル管部会と同様、職能で組織された浄化槽部会も活動が活発で、公衆衛生研究所の山本主任研究員と浄化槽をテーマとする様々な調査研究に取り組んだ。
府下で25万基の設置基数を数えた単独浄化槽については、機能検査と放流水の水質検査を行い、調査結果は、部会報告としてとりまとめ浄化槽技術研究集会に発表した。
その後に開発された屎尿と生活排水を一緒に処理する合併処理浄化槽は、国が、河川浄化に寄与する生活排水処理の有益な施設として位置づけ、補助金制度を創設して普及促進に乗り出した。当時の厚生省で一際目立った浄化槽対策室長は、合併処理浄化槽PRにと「瀬戸の花嫁」の替え歌を作り、都道府県浄化槽担当者会議で披露した。
室長の主張は、「下水道は膨大な税金を投入し生活環境の改善を図ってきたが、下水道の導入区域外や計画があっても近い将来に見込めない地域の国民は不公平な扱いを受ける。下水道区域を見直し、生活排水の処理を下水道と浄化槽で役割分担する必要がある。下水道と同様、浄化槽の設置にも税金を投入する補助金のシステムが作る。」との意気込みで浄化槽に対する思いと普及にかける熱意があった。
当時の大阪府の事情は、府域全域が下水道区域として指定されており、補助対象区域から外れることから補助金制度の導入は将来的にも困難と思われた。しかし数年後、後に環境衛生監視員として三代目の環境衛生課長となる辻氏が下水道区域に風穴を開け、大阪府内においても下水道と浄化槽の棲み分けが行われることとなった。
8 事件と環境衛生課長の代々
環境衛生課は、戦後から昭和47年度まで、厚生省から国家上級公務員のキャリア医師が派遣され、課長の職に就いてきた。昭和40年代前半から3代続いた大阪府の環境衛生課長歴任者は、国に戻ってから数年後に揃って生活衛生局長に就いた。
国からの医師派遣が止まった昭和48年度には、環境衛生課から水道、防疫、健康影響調査部門などが切り離され、新たに環境保健課が組織された。この時の環境衛生課長には事務職が、環境保健課長は医師が当てられた。この分裂した組織は昭和52年度まで続き、53年度に再び2つの課が統合し、環境保健課長の広済医師が環境衛生課長に就任した。
広済課長は、7年間の長きに渡り環境衛生課長を勤め、昭和59年、同じ医師の南波課長に引き継いだが、南波課長就任間もない4月上旬に課職員による汚職事件が発覚した。
環境衛生課の技師と機器販売業者との癒着による事件が深夜テレビで放映され、翌日には早朝から検察による環境衛生課の家宅捜査が行われた。
当時はマージャンが盛んで、勤務時間終了間際に卓を囲むメンバーが募られ、谷町筋にある天満橋会館に貸し卓の予約が入れられた。この常連のメンバーに事件の当事者が含まれ、捜査前日にも一緒に卓が囲まれていた。翌日、技師は逮捕され、職員の机の中身は押収され、しばらくの間、一部業務に支障がでたが、他の職員に疑惑が及ぶことは無かった。
南波課長は次の年度に異動し、環境衛生課長の職を医師から事務職の上村参事に譲った。
上村氏は商工部に長く在籍し、最初の衛生部では保健所次長でブロック次長会を盛り立て、環境衛生課参事を経て環境衛生課長に就任した。その上村氏とは、参事の時から飲む機会が多く、週2回から3回は府庁界隈の立ち飲み「大安」に誘われた。最初は、おでんを肴にビールで乾杯、続けて各人日本酒を5合飲み干すのが定番で、日によってはタクシーで南の宗右衛門町に足を伸ばし「スナックアミー」でカラオケに興じた。
課長に就任された後は、環境衛生監視員など技術職と事務職員の和を大切にされ、保健所との風通しも良い課にとの心遣いがあった。また親睦では、香住へのカニ旅行やスナックで知り合った町役場の職員を頼って能登旅行などを共にし、上村参事と課長の通算4年間は沢山の楽しい機会があった。この課長時代から退職後も正月には、地下鉄谷町線千林大宮駅に課職員が集合し、上村氏の自宅に押しかけて近江八幡特産の鮒寿司付きの正月料理をいただく恒例が長く続いた。
上林氏は環境衛生課長を2年勤めて退職し、千里万博記念跡地を管理する社団法人の常務に就き、数年後専務理事に昇格した後、団体の定年制を67才と自ら定めて全ての役職から退かれた。
上村課長のあとは、事務職が6代続き、平成12年度、待望の環境衛生監視員からの環境衛生課長が誕生した。初代塩田課長は定年2年を残して、無名の山下課長に職を譲り、その後、浄化槽行政に手腕を発揮した辻課長、平成20年度からは水道行政に精通する桐山課長が引き継いでいる。私の府庁就職時からの目標は、環境衛生課長になることであったが、夢を潰したのは山下氏であると今も思っている。彼が課長時代は、私が補佐として2年間支えたが、できの悪い対応や答弁などに怨みを込めて上司に対する評価を最下位のDランクとした。その評価が裏目に出て参事昇格が3年間遅れた。
なお、辻課長のラインを引いたのは私であり、当時は神戸氏が有力な課長候補であったが辻氏を陰で応援した。桐山氏の課長は規定の路線であるが、次の課長は全く読めない
information店舗情報
セアカゴケグモ事件と旅行記
〒631-0022
奈良市鶴舞西町1-5-104
TEL.070-8302-2546
