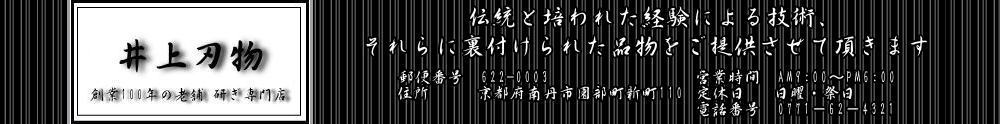| |
 メンテナンス・保管 メンテナンス・保管
|
|
どのような物でもそうですが、
手入れを怠ると早く壊れ易かったり、悪くなり易かったりします。
刃物も使った後に適当に放置しておくと、
傷んでしまったり、使い難くなったりします。
|
| |
 錆(サビ) 錆(サビ)
|
|
刃物にとって、一番の敵はサビです。
ステレンスや特殊合金など、サビ難い素材のものもありますが、
きちんと管理をしていないとサビてしまいます。
サビとは金属が腐食していることで、
どうして問題なのかというと、強度が落ちてしまうからです。
分子の結合上、サビた部分は脆くなっているので、
切れ味が落ち易かったり、カケる原因になってしまったりします。
表面に軽く浮く程度なら取り除けば問題ありませんが、
酷い状態にまでなると金属の中にまで浸透してしまい、
刃物の寿命を限りなく縮めてしまいます。
|
| |
 対処法 対処法
|
|
サビの要因は、
主に塩分(塩化物イオン)と水分です。
魚やお肉を切った後に洗わなかったり、水気を切らずに放置したりすると、
サビてしまいます。
また汗や血液にも塩化物イオンが含まれているので、
手で触った後には取り除かなければなりません。
対処法としては、
塩分を含むものに対して使ったときは、
きちんと洗剤で洗って、その後に水気を取って乾かすことです。
そうすることで原因となる塩分と水分が取り除かれて、
サビを防ぐことが出来ます。
また椿油などで拭いておくと、
外気中の湿気から刃物を守ってくれます。
|
|
 脂(ヤニ) 脂(ヤニ)
|
|
樹木に含まれる有機成分です。
品種によって含有量は変わりますが、
幹や枝を切ったり落としたりすると付着します。
放置しておくと刃にこびり付いて、切れ味を悪くしてしまいます。
そのまま使い続けると、切れなくなってくるので力回せになってしまい、
カケや割れの原因になったりする、という悪循環に陥ります。
|
| |
 対処法 対処法
|
|
食材を切る刃物は衛生面を気にして洗われたりしますが、
そうではない刃物はその必要がない為に、
使用した後に放置されることが多いです。
確かに手間ですが、それを惜しむとさらに苦労することになります。
ヤニが付着しても、乾燥してこびり付かない限り楽に取り除けます。
取り除く道具ですが、
市販の刃物クリーナーというものが売られているので、
そちらを使って頂いても宜しいですし、
ガソリン、灯油などの揮発性油で拭いて頂いても大丈夫です。
注意して頂きたいのは、
ヤスリや砥石などで削り取らないことです。
ヤニだけを取り除ければ良いのですが、
刃を傷付けてしまったり、間違って研いでしまったりする可能性があります。
特に鋏などは、刃先同士が交差するときに引っ掛からないような仕組みになっていて、
やり過ぎるとその特性がなくなってしまうからです。
|
| |
 粘着性テープ 粘着性テープ
|
|
ガムテープやセロハンテープなどのことです。
鋏などで切って使われたりすると思いますが、
何度も使っているうちに開閉が困難になってきます。
原因は接着剤です。
粘着性テープには裏側に接着剤が塗布してあったり、
接着剤がテープ状になっていたりするからです。
刃物に接着剤が付くことによって、
引っ掛かったり滑りが悪くなったりして、上手く切れなくなってしまいます。
|
| |
 対処法 対処法
|
|
接着剤を分解してくれる
アルコール成分を含んだものを使って下さい。
消毒用アルコールやウエットティッシュ、除光液などがお勧めです。
また、接着剤が付かないように加工された鋏を購入するのも、
一つの方法だと思います。
|
| |
 短期間 短期間
|
|
毎日、使う場合や二、三日後また使用するときの保管方法です。
ヤニ、接着剤を取り除くことは基本です。
後はサビささないようにするだけです。
塩化物イオンが付いているなら、
洗剤を使って洗ってから、水気を完全に取るようにして下さい。
布巾などで拭いても構いませんし、火で炙って水分を飛ばす方法もあります。
そのときは火に近付け過ぎないようにして下さい。
焼きが戻って鋼が甘くなり、脆くなる場合があるからです。
その後に椿油を塗っておくと、さらに錆難くなります。
油が保護膜の機能を果たし、水気から守ってくれるからです。
後は湿気の少ない場所に置いて下さい。
補足ですが、台所で使用した刃物などは、
洗い物置きに入れておくのは避けるようにして下さい。
お皿などの水滴が付くと錆びる可能性があります。
|
| |
 長期間 長期間
|
|
しばらく使う機会がない場合は、
短期間の行程の後に、
(くれぐれも椿油を付けるのを、忘れないように気を付けて下さい。高確率で錆びます)
(食用油は時間が立ち過ぎると、酸化して粘ついてしまうことがあります)
新聞紙に包んで、
湿気の少ない風通しの良い場所に保管しておいて下さい。
新聞紙には適度な通気性があり、湿気を飛ばしてくれるからです。
トップページへ戻る
|