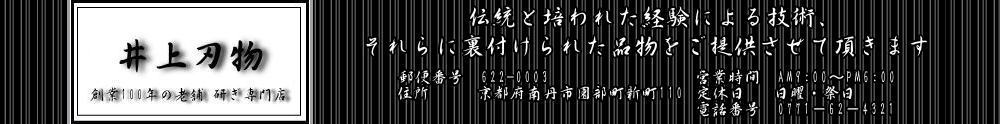| |
 使用方法 使用方法
|
|
種類が沢山ある分、使い方も様々です。
誤った使い方をしてしまうことも多々あります。
当店に来て下さっているお客様にもお伝えしていることですが、
大切な刃物を長く使って頂く為にも、
使い方と経験上、注意して貰えたら、と思うことを載せています。
あくまで参考程度ですので、
詳しく知りたい方は専門書などを購入して下さい。
|
| |
 包丁(ほうちょう) 包丁(ほうちょう)
|
|
切れ味が落ちる原因は、
主にまな板との接触によって起こります。
使用する度に刃先が叩き付けられて、切れ味がなくなってきます。
さらに切れ味が落ちると力を込めるようになって、やがて本当に切れなくなります。
長く使って頂く為には、
必要以上に力を入れて切らないことです。
包丁は引くだけで切れる、ということです。
後は、薄い包丁で固い食材を叩いたり、切ったりしないことです。
太い骨を叩いたり、カボチャや半解凍のお肉などを切るときは、
ついつい、同じ包丁を使ってしまいますが、
分厚い包丁(出刃包丁)などに変えた方が良いです。
薄い包丁は骨を叩くような作りはしていませんし、
切り難い為に力を込めてしまい、結果的に捻ってしまうからです。
刃物全般に言えることですが、
捻る、という行為はもっともしてはいけないことです。
形状からもわかりますが、
上下からの力には強いですが、横からの力には非常に弱いです。
捻るだけで簡単に欠けてしまいます。
落とす以外で欠ける原因は、主に捻ることによって起こります。
それと、他の場所でも書きましたが、
片刃の包丁を研ぐ場合、
裏側をあまり研がないようにして下さい。
平面(内側は反っています)になっていて研ぎ易い為に、
ついつい裏側ばかりを研いでしまったりしますが、
平面でない砥石で研いでしまうと捲れてしまいます。
(研ぎによって砥石が凹んでしまうと、弧を描くように研いでしまうことになり、丸くなってしまいます)
片刃本来の切れ味を出せなくなるので、表側を出来るだけ研ぐようにして、
カエリ【バリ】を取るときだけ裏側を研ぐようにして下さい。
|
| |
 鋏(はさみ) 鋏(はさみ)
|
|
交差させる鋏ですが、種類が豊富にあります。
紙、布、枝、葉、髪、金属、そこからさらに細分化されたりもします。
注意して頂きたい点は三つあります。
一つ目は、全ての鋏に共通していることですが、
挟んだ後に捻らないで下さい。
上下から力が掛かっている状態ですので、
捻ることによってカケてしまったり、刃先が潰れてしまったりします。
それと挟むときは、
刃先同士に、正確に力が加えられるように挟んで下さい。
離すようにして切ってしまうと、刃先同士が開いてしまう可能性があるからです。
わかり易く言うと、
隙間が出来て切り難かったり、切れなくなったりします。
二つ目は、本来の用途に応じた鋏を使う、ということです。
紙はちょっと別ですが、
布なら布を切る鋏(一部例外があります)、枝なら枝を切る鋏、金属なら金属を切る鋏、
ということです。
理由は対象物を切る為の構造が、それぞれ違うからです。
使えば使うほど切れ味が落ちてしまうのは当然ですが、
もっとも傷む原因は、
刃先同士が噛み合うこと(対象物を切らずにお互いの刃を切ろうしてしまうこと)や、
本来、使わなければならない鋏とは異なる鋏を使って、対象物を切ることです。
前者は刃先が傷付いたり、凹んだりしてしまいますし、
後者は対象物が硬くて切り難かった場合、力を込めて切ろうとする為に、
刃先がカケてしまったり潰れてしまったりするからです。
そうなると使い物にならなくなり、即修復しなければなりません。
三つ目は、研ぎです。
鋏は交差させて切る刃物なので、バランスが重要になってきます。
上手く取れなければ刃先が正確に交差しなくなりますし、噛んでしまう要因になってしまいます。
研ぎは誰にだって出来ることですが、細かな知識が必要になります。
当店にお越し下さっているお客様によく伝えることですが、
裏側の刃は研がない方が良いです。
鋏は裏側の状態が要になるからです。
鋏の裏側の多くは平面になっていることがほとんどで、
裏スキをしてある和鋏は、裏側を平面の砥石で研いではいけません。
ほんの少しならわかりませんが、何度も研いでいるうちに刃先が面になっていき、
本来の切れ味を失ってしまうからです。
また、傷んでいる部分まで平面になるように研ぐのは至難です。
慣れていなければ研ぐ動きが一定でなくなり、
砥石も凹んで捲れるような研ぎになってしまうからです。
そうなると刃先が正確に交差しなくなって、切れなくなってしまいます。
研ぐなら裏側でなく表側だけですが、それでも限度があることを知って貰っています。
|
| |
 鎌(かま) 鎌(かま)
|
|
鎌が著しく傷む場合は、
石などに当ててしまうときと、枝を払ったときに切れなくて捻ってしまうときです。
主に薄鎌、中鎌、下刈鎌などは草を切り払うときに使います。
草の成長を出来るだけ抑える為に、地面のすぐ間近で切り払ってしまいます。
また岩や壁際、階段際の草をなくそうとして使ったりします。
そのときに石や岩、壁、階段などに当たってしまい傷んでしまいます。
上質な鎌ほど鋼が丈夫で耐久力がありますが、安価な鎌はすぐにカケてしまったりします。
上手く使うコツは、
石に当てないように少し上の部分を刈ることと、
壁際などは避けることです。
少し手間は掛かるかも知れませんが、手で引き抜いたり、
ねじり鎌などの引っ掻き切るものを使うことです。
厚鎌やナタ鎌は蔦を掃ったり、小枝を切ったりするときに使います。
鎌の切れ味が落ちていたり、枝が太かったら切り落とせなくて食い込んだりしてしまいます。
切りたい欲求や食い込んで離れなくなると、捻ってしまいます。
そのときにカケてしまいます。
切れなかったり食い込んだりした場合は、
無理せずに真っ直ぐ引き上げると防げます。
出来るだけ石などに当てないように扱うこと、食い込んだ場合は捻らないこと、
この二つが長く使う為の条件です。
|
| |
 鉈(なた) 鉈(なた)
|
|
樹を削ったり、枝を切り払う為の刃物です。
剣鉈【山刀】のように、先端が丸みを帯びて尖っているものは、狩猟に用いられたりもします。
厚鎌やナタ鎌も枝を払ったりしますが、
それよりも専門性に富んでいるので、勢い良く使用されます。
扱い方ですが、専門的な分野に精通している人は別ですが、
多くの方は正確に振り下ろすことが困難だと思います。
どうしてもブレてしまったり、先端に力を集約出来なかったりするからです。
太い枝を何度が打ち付けて払うときは、
手に近い刃元で打ち付けると安定します。
他の刃物と同様に、後は捻らないことです。
同じスイングで打ち下ろし続けて下さい。
檜などの硬い樹の場合は、
専用の鉈がありますのでそちらを使用して下さい。
檜鉈というのですが、
刃先が斧のように弧を描いていて、食い込んだ後に離れ易くなっています。
それと、切れないからといって、
背の部分を別の刃物や金属で叩かないようにして下さい。
構造的に叩くように作られていないので、ひしゃげてしまいます。
形が崩れてしまうと、枝を切り払うときに邪魔になったりします。
これは出刃包丁にも言えることです。
|
| |
 斧(よき) 斧(よき)
|
|
鉈よりもさらに叩くことに特化した斧ですが、
叩いて割る、というイメージが強くて、カケさせてしまったりします。
理由は割り斧ではなく、切り斧を使ってしまったからです。
斧は厚みによって用途が違います。
刃の厚みによって、切り斧、割り斧に分けられます。
さらに丸太などを割るときに使われたりする、金矢、というものもあります。
この金矢には柄がなくて、背の部分が鋼になっています。
食い込ませた後に、ハンマーで叩いて割る、という仕組みです。
鉈同様、それ以外の斧は背の部分を叩くようには出来ていないので、
くれぐれも気を付けて下さい。
当店では柄付けもしておりますが、
よく柄を折られて持ってらっしゃいます。
打ち付けるときに、刃先ではなく柄を当ててしまったからです。
力を入れなければいけませんが、怪我の元にもなりますので注意して下さい。
最後にもう一つだけ、
斧の柄付けですが、ご自分でやられる場合は、
すんなりと入る状態で差し込み、センダンで抜けないようにするのは避けて下さい。
効きが甘いと抜けてしまい、こちらも怪我の元になってしまいます。
|
| |
 鑿(のみ) 鑿(のみ)
|
|
木材の加工や彫刻に対して、
金槌で叩いたり、削ったり、引き剥がしたりします。
叩く場合は、カツラ(金属の輪)が付いていることが大前提で、
柄の上部を正確に金槌で叩いて下さい。
また鑿はカツラを下げて扱わないと、柄が傷んでしまいますので、
カツラを下げを行ってから扱うようになさって下さい。
どの刃物でも同じですが、
間違った方法で使われると、折れたり欠けたりしてしまいますし、
柄が潰れてしまったりします。
鑿の中にも、追入、叩き、差し、造作、彫刻などの種類があります。
金槌で叩けるものや叩けないものや、また刃の角度が違っていたりします。
注意して頂きたいのは、
食い込みを良くする為に、鋭角に研ぎ出してしまうことです。
削るだけなら大丈夫ですが、
食い込ませた後に引き剥がすと、カケてしまうことがあります。
刃先が薄くなっている為に、強度が落ちてしまっているからです。
引き剥がす厚みや研ぎの角度にも寄りますが、
硬い木材ならそれが顕著に表れます。
また追入も叩きもカツラ(柄の上に付いている金属の輪っか)が付いていて叩けますが、
首(刃と柄の間にある鉄で出来た部分)の太さが違います。
叩きの方が丈夫なので、叩きと同じように追入を扱ってしまうと、
首が折れたり、刃が欠けたりしてしまいます。
上記のことから当然のことにはなりますが、
カツラがない鑿は叩かないようにして下さい。
柄の上部が崩れてしまいます。
|
| |
 鉋(かんな) 鉋(かんな)
|
|
利き手にもよりますが、
大体は右手で鉋台を掴み、左手で鉋台の先を掴みます。
それを上下に引くことによって削れますが、
上手く削るには練習が必要です。
削れる感覚を掴まなければならないからです。
慣れてないと、削るときに木材から浮かしてしまったり、
真っ直ぐ引けなかったり、余分な力を込めてしまったりします。
今はもう少なくなっているとは思いますが、
大工さんなどは刃先の出し方を調整して、荒、中、仕上げ、の三台を常に持っていたりします。
削れる分量が違うので、用途に合わせて使い分けるからです。
鉋の難しいところは、
刃先が尖っていたら削れる、ということにはならないところです。
刃が切れることはもちろん、
台の状態が正常ではないと、正確には削れません。
道具として使えるようにするには、台を調整しなければなりません。
中古で買われたり、使用し続けて削れなくなったりしたときは、
刃物屋さんなどに持って行かれるのがよろしいと思います。
台直しをして貰えるはずです。
また刃の状態にも気を付けなければなりません。
鉋刃は片刃(例外もあります)なので、裏側が沿っています。
その反りが研ぎよってなくなってしまっても、正確に削れなくなってしまいます。
その場合は、刃の表側を叩いて裏出しをしなければなりませんが、
力加減を誤るとカケてしまったりします。
もしご自分でなされる場合は、十分に注意して下さい。
カケるということは、その分、刃物の寿命が縮まるということです。
それと刃を研いだ場合は、裏金の付いている鉋なら、
合わせたときに隙間が出来ていないか、を確かめないといけません。
裏金は逆目止めの(繊維が裂けてしまわないようにする)役目を果たしているのですが、
それが機能しなくなってしまうからです。
裏金にも研ぎが必要になる場合もあります。
後、研ぎによって刃の状態が変わると、
鉋台に合わなくなったり、削りカスが鉋台に引っ掛かったりしてしまいます。
台を再び合わしたり、刃を削ったりしなければなりません。
研ぐときは十分、注意をして、闇雲に研がないようにして下さい。
刃の調整をするときは、木槌を使って下さい。
金槌を使うと鉋台が傷むからです。
使用中に気を付けてほしいのは、釘を挽いたりしないようすることです。
繊細な仕事をする刃物なので、研ぎ直しが必要になります。
|
| |
 彫刻刀(ちょうこくとう) 彫刻刀(ちょうこくとう)
|
|
鑿もそうですが、彫刻刀も様々な形状をしていて、
削りたい場所や、深さなどによって使い分けられます。
上手く扱うには、
どの程度の角度までなら削れるのか、力を抜いて削れる角度どこまでなのか、
を知ることです。
削る木材や場所によって変わりますが、
食い込み過ぎると無理をして、刃をカケさせてしまう原因になります。
また余分な力を込めない方が、本来の性能を発揮してくれます。
当然のことながら、捏ねたり、捻らないようにして下さい。
|
| |
 鋸(のこぎり) 鋸(のこぎり)
|
|
昔どこかで聞いたのですが、
日本は引く文化で、西洋は押す文化、という言葉が耳に残っています。
(間違っていたらすみません)
長年、紡がれたものによって、日本人は引くという行為が得意なのかも知れません。
日本の鋸も同様です。
使われたことがない方は、前後どちらに動かしても切れると思われているかも知れませんが、
日本の鋸は押しても切れないようになっています。
引くときに削り取れるようになっているからです。
そのような仕組みになっているので、
押すときには力を抜いて、引くときに力を入れるようにして下さい。
力を込め過ぎると引っ掛かり過ぎて、上手く削れないので、
どの程度、力を入れれば良いのかを引きながら調節して下さい。
真っ直ぐ綺麗に切る為には、態勢を整えることが重要です。
木材などを加工する場合は、動かないようにしっかりと押さえるようにして下さい。
鋸にも様々な種類のものがあります。
切る対象や、繊維の向き、また用途によって変わってきますので、
それらに合った鋸を使わないと切り難かったり、疲れたりし難くなります。
当然ながら長持ちにも繋がります。
どれを使ったら良いかわからない場合は、
購入する前にお店の方に訊ねると選んで貰えるはずです。
参考程度にですが、
切り口を綺麗にしたいなら細かい刃、
素早く作業をこなしたいなら荒い刃、
木材を繊維に沿って切りたいなら縦引き、
樹木の節の部分を切りたいなら枝打ち、
などです。
鋸が酷く傷む原因になるのは、
木材を切るときに釘を一緒に挽いてしまうことと、
樹の根元を切ろうとするときです。
鋸は釘を切るように出来ていませんし、
樹の根元には、成長過程で引き上げられた小石などが付いていたりするからです。
昨今では、なさる方も減ってきましたが、
目立ての知識と道具がない限り、ご自分で目立てをするのは避けた方が良いです。
正確に磨ること自体、難しいのですが、
一番の理由は、
アサリ(刃先の隙間のことで、削りカスが出ていくようになっています)が付けられないからです。
磨っている間にアサリがなくなってしまうと、
対象物を切ろうとしたときに詰まってしまい、削れなくなってしまいます。
それと替刃式の鋸が普及していますが、
目立てをするようには作られていませんので、買い換えて下さい。
磨ろうとしてもヤスリが滑ってしまい、刃を付けるのが困難な為です。
|
| |
 チェーンソー チェーンソー
|
|
起動の仕方は、購入したときの説明書を読んで下さい。
扱い方や注意点ですが、
チェーンソーの刃が切れなくなったら、無理して使わない、ことです。
力を込める為にエンジンに付加が掛かり、故障の原因になります。
回転を支えているバーにも熱が籠って焼きが入り、
変形したり耐久性が落ちて、刃が外れたりすることによって怪我をする恐れがあります。
また チェーンソーには刃をスムーズに回す為に、
チェーンオイルが入っています。
なくなった状態で使うと、同じようにバーが焼けてしまいます。
しばらくの間、使用しない場合は、燃料(混合燃料)を抜くようにして下さい。
燃料が劣化してしまうと、故障の原因になります。
それと、間違った燃料を入れるのも避けて下さい。
また付着した木屑を放置しておくと、詰まることがありますので、
掃除は怠らない方が良いです。
刃を長く持たせるには、小石や釘などを挽かないことです。
樹木を伐採したり、木材を切ったりしますが、その中に紛れ込んでいる場合があります。
特に地面を引き摺った木材を切ったり、
鋸のところと同じで、樹の根元の切ろうとしたときです。
チェーンソーは高速で回転しているので、
硬質のものに触れると、火花が散ります。
そのときに切るのをやめればまだ軽微ですが、
無理して使い続けると、当事者では直せない状態にまでなってしまいます。
また刃がダメになって、目立てすら出来ない状態になることもあります。
また丸ヤスリなどで目立てをされる方もいらっしゃいますが、
刃がわずかでも動く状態だと正確に磨れないので、
しっかりと固定して目立てをして下さい。
理由は、どうしても捲れるような形になってしまうので、
本来の切れ味が戻らないからです。
それと間違った磨り方をしないように気を付けて下さい。
ある程度は大丈夫ですが、
最悪の場合
チェーンソーの刃がカケて飛んできたり、外れたり、千切れたりするからです。
|
| |
 チップソー チップソー
|
|
注意して頂きたいのは、
切断する対象によって種類が変わることです。
正確に扱う為にも、間違えないようにして下さい。
チップソーにも安価なものや値の張るものがあります。
チップの硬度や溶接されている部分の強度などが違う為です。
硬度が高ければ長持ちしますし、強度があればチップが飛び難いという利点があります。
価格にもよりますが、
信頼出来る目立てをして貰えるお店を見つけておけば、
使い捨てをするよりも良いですし、作業も楽に進められます。
刈払機のチップソーが傷む主な原因は、
地面にある小石や岩、壁などに当ててしまうことです。
草刈りに手間が掛かる為、ついつい地面スレスレで刈ろうとしてしまったり、
際に生えている草まで刈ろうとするからです。
小石が当たらない程度の高さで使って、
岩や壁などに触れないようにする方が良いと思います。
余談ですが、普通は回転方向に振らないと切れませんが、
切れ味の鋭いものは、回転方向と逆に振っても切れるので、作業効率が二倍になります。
電動丸鋸用のチップソーは、
木材に紛れ込んだ釘やビスを切ってしまうことで、チップが傷んだり飛んだりします。
ただし、普通に使っている限りそのようなことはほとんどありません。
通常は切れ味が落ちてくるだけなので、
酷い状態のものはあまりないのが現状です。
目立てをしても上手く切れない場合は、
きちんと目立てが出来ていなかったり、チップが飛んでいたり、
チップソー自体が使用中の付加によって曲がっている場合です。
大工さんなどにとっては当然の如く知られていることですが、
木材を切断中に目詰まりが起こると、キックバックします。
前方へ動かしていた高回転の刃が、瞬時に戻ってきて大変、危険です。
使用するときは、
チップソーのライン上の後方に、身体の一部を持ってこないようにして下さい。
木材を他者に押さえて貰うときも同様です。
|
| |
 電気・自動カンナ 電気・自動カンナ
|
|
注意事項があるなら、
釘やビスを一緒に挽かないことです。
高速で回転しているので、
一発で刃先がやられてしまいます。
また硬質で研ぐのが困難ですので、
研げる業者さんにお出しになられた方がよろしいと思います。
チップソーも同様で、
業務用の機械でないと正確には研げません。
|
| |
 植木バリカン 植木バリカン
|
|
植木バリカンには、切断出来る長さが決まっています。
それを超えて使用していると、モーターに付加が掛かり故障の原因になりますし、
刃先が開いていって、切れなくなったり曲がったりしてしまいます。
造園の方は作業効率上、仕方がないかも知れませんが、
長くお使いされるなら、指定の範囲を超えないように扱って下さい。
それと他の機械にも言えることですが、
むやみに分解しないようにして下さい。
仕組みがわかっていないと元に戻せなくなってしまいますし、
修理に出すときに、余分に費用が掛かってしまう場合があります。
専門家に任せるのが無難です。
|
| |
 まとめ まとめ
|
|
少しでも長く使って頂く為に、と思ったのですが、
不安を煽るような形になってしまったような気がします。
そのようなつもりはないので、ご了承下さい。
使用方法や注意事項さえ守れば、間違いなく長持ちします。
少し煩わしいかも知れませんが、
ぜひ試してみて下さい。
トップページへ戻る
|